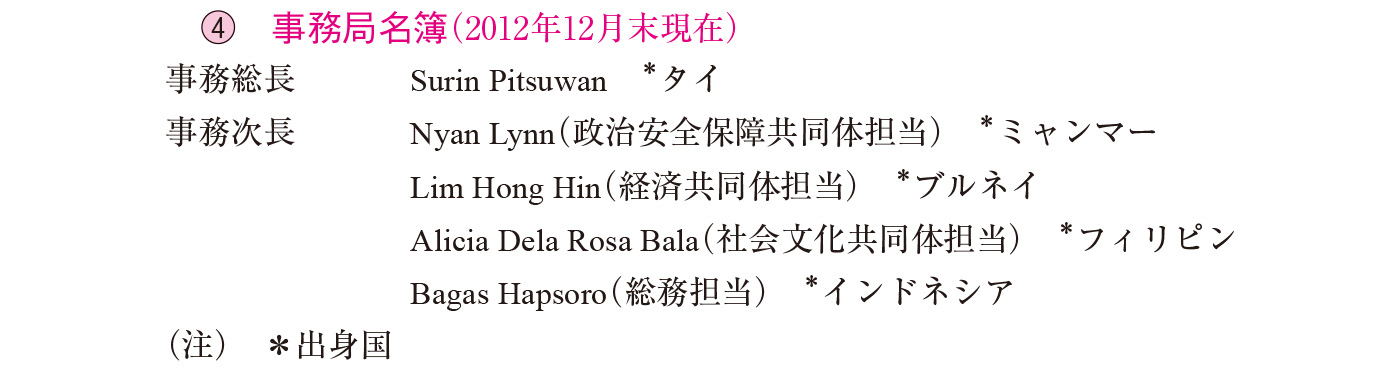2013 Volume 2013 Pages 183-196
2013 Volume 2013 Pages 183-196

2012年のASEANは米中という大国間の競合の下で地域機構としての姿勢をどのように示すのか,という点が焦点となった。
そのような構図が端的に現れたのが南シナ海問題である。法的拘束力のある紛争処理メカニズムである行動規範の策定をめぐりASEAN加盟国内において,アメリカの後押しを受ける対中強硬派と親中派の間で亀裂が表面化し,年次外相会議ではASEANの歴史上初めて共同声明を出すことができなかった。そのようなASEAN内の不和もあり,この1年を通して行動規範をめぐる中国との交渉はほとんど進展しなかった。他方,経済面における成果はASEAN主導の枠組みである地域包括的経済連携(RCEP)の交渉開始が宣言されたことである。
その他,政治面では「ASEAN人権宣言」の採択やミャンマーの民主化の進展に伴う変化がみられた。経済面では2015年1月までの経済共同体構築に向けてその遅延を挽回する努力がなされたが,11月のASEAN首脳会議においてASEAN共同体の構築を実質的に1年延期するという決定がなされた。
2012年のASEANに関する動向でもっとも注目を集めたのが,南シナ海問題への対応をめぐるASEAN加盟国間の折衝である。豊富な石油・天然ガス資源と優良な漁場を備える南シナ海においては島々の領有権や海域の管轄権をめぐり,中国,台湾,フィリピン,ベトナム,マレーシア,ブルネイの6つの国・地域が対立している。なかでも近年対立が激化しているのがほぼ全域の領有権を主張する中国とフィリピン,ベトナムの関係である。また,アメリカは公的には中立であるという立場をとりつつも,南シナ海における航行の自由を「国益」であると位置づけ,フィリピンやベトナムを事実上支援する姿勢をみせている。
2012年における南シナ海をめぐる地域機構としてのASEANの活動は,2002年に中国との間で合意に至った法的拘束力を伴わない「南シナ海における関係諸国行動宣言」(DOC)を格上げして,紛争処理のメカニズムを規定する法的拘束力のある「行動規範」(COC)を策定するための協議が中心となった。問題は,中国の姿勢があくまで南シナ海問題を国際問題化させるべきではなく二国間で処理すべきというものであり,したがってASEANという国際機構の関与やCOCの策定自体にも消極的であるという点である。中国がそのような意向を明示するなか,ASEANという地域機構の姿勢をめぐり加盟国内の対中強硬派と親中派の間で根深い亀裂が露わになった。
まず,4月の第20回ASEAN首脳会議においてはCOCの草案作成のプロセスについて立場の違いがみられた。フィリピンとベトナムは,まずはASEANのみで草案を作成した後に中国との交渉に臨むべきだとしたのに対し,議長国であるカンボジアを含む一部の加盟国からは,草案作りの段階から中国を参加させるべきだという意見が出された。ともあれ,同首脳会議において採択された「ASEAN共同体構築のためのプノンペン・アジェンダ」や議長声明においてCOC策定に向けて努力していくことが述べられた。
ASEAN内の亀裂が顕著にみられたのが7月の第45回外相会議である。この外相会議においてASEAN諸国はASEANの歴史上初めて共同声明を出すことができなかったが,その理由は南シナ海問題をめぐる衝突にあった。共同声明を作成するに際しフィリピンは「スカボロー礁」という固有名を,ベトナムは排他的経済水域と大陸棚の問題を,それぞれ盛り込むように主張した。それに対し,議長国カンボジアは,二国間問題は共同声明に盛り込まれるべきではないとして反発した。その後,インドネシアから当該部分の言い回しについて数多くの代替案が提示されるもカンボジアは取り上げず,結局共同声明自体が出されないことになった。予定されていた共同声明は132パラグラフで構成されていたというが,わずか4パラグラフにすぎない南シナ海問題のためにそれは水泡に帰した。共同声明を出せなかったことは,その後のサミットも含む諸会議の議題設定と青写真が提示できなかっただけではなく,域外にASEAN内の不和を印象づけることになった。
もっとも,この外相会議の直後にインドネシア外相がフィリピン,べトナム,タイ,カンボジア,シンガポールを相次いで訪問し,その結果として7月20日「南シナ海の6原則」の外相声明を発表することができた。具体的には,(1)DOCの実施,(2)実施のための指針の遵守,(3)COCの早期策定,(4)国連海洋法条約を含む国際法の尊重,(5)武力不行使,(6)紛争の平和的解決,である。これらは一般的な原則の域を脱するものではないが,インドネシアの外交的努力によりASEANは最低限の団結をアピールすることができたといえる。
その後,9月末の非公式外相会議においても協議がなされたが,結局11月の第21回ASEAN首脳会議においても進展はみられなかった。首脳会議後に発表された議長声明では,当初の案にあった「COC策定に向けた中国との建設的な取り組みを確認した」という箇所が削られ,結局DOCの重要性を再確認するにとどまり,COCは触れられること自体なかった。また,この首脳会議においては会議終了後の会見でカンボジアのカオ外務副大臣が「ASEAN諸国は南シナ海を国際問題化しないことで合意した」と発言し,フィリピンがそれに抗議する,という一幕もみられた。結局2012年を通してASEANは南シナ海問題について対外的なまとまりを発揮することはできなかった。なかでも、南シナ海に利害を持つフィリピン,ベトナム,マレーシア,ブルネイの4カ国の温度差が顕在化した。ASEANに強硬的な姿勢を求めたのはあくまでフィリピンとベトナムのみであった。
ASEAN内で激しく利害が衝突するのはこれが初めてではないが,これまでは少なくとも対外的には一体性を示してきた。2012年に南シナ海問題がここまで亀裂を露呈させてしまった重要な背景には,ASEANのなかでも中国との関係が深く経済的な依存度も高いカンボジアが議長国を務めていた,ということがある。議長国が落とし所を模索せずに自国の方針を一切曲げなかったことが2012年の南シナ海問題をめぐる分裂の重要な要因である。
ASEAN人権宣言の採択人権や民主主義といった加盟国の国内統治の問題は近年のASEANにおける最大の争点であり,政治安全保障共同体が経済,社会文化共同体に比べ加盟国間の対立を招くことが多かった理由でもある。人権を促進する手段について一般的には宣言,委員会,裁判所などがあげられるが,ASEANは政府間の人権委員会(AICHR)を加盟国間の激しい論争の末に2009年10月に設立している。そして2012年には「ASEAN人権宣言」が採択された。これはASEAN人権協力および共同体構築のための基本的な枠組みを提示するものである。その起草の作業はAICHRが担当した。AICHRはその権限があくまで教育や能力構築を通した人権の促進に限られており調査や人権保護活動を行うことができないため,その実効性がしばしば批判されてきたが,2012年は人権宣言の草案作成がその主たる活動となった。
人権宣言の草案作成プロセスが始まったのは2011年7月であるが,手順としてはAICHRによって設けられた起草グループがまず草案を作成し,それを2012年1月に行われた第1回の「ASEAN人権宣言に関するAICHR会合」に対して提出した。その後AICHRは会合を重ねていったが,4月にはASEAN外相会議において各国外相らと対話する機会を持ち,5月の第5回会合では「女性と子どもの人権促進および保護のためのASEAN委員会」(ACWC)と「移民労働者の権利促進および保護に関するASEAN宣言履行のためのASEAN委員会」というASEAN内の他のセクターと協議を行った。そして6月までに7回の会合を終えたうえで,7月の年次外相会議においてAICHRは外相らに対して草案を提出した。その際,各国外相らからは「市民社会と対話の機会を設けるように」という指示が与えられた。その後さらにAICHRは3回に及ぶ会合の機会を持ち,また,各国外相らも9月の非公式外相会議における協議により内容を調整し,11月のASEAN首脳会議で「ASEAN人権宣言」は最終的な採択を迎えることとなった。
このプロセスにおいてしばしば批判されたのが,人権団体などの市民社会組織が関与していないということである。市民との対話を欠き,あくまで各国の代表のみで決定されていることが非難の的となったのである。そのような非難を受けてAICHRは2012年6月と9月の会合では市民社会組織との協議の機会を持った。もっとも,たとえば6月の段階では草案を部分的にしか公開しないなど,必ずしも積極的に協力を求める姿勢ではなかったことには注意すべきである。
さて,このようなプロセスを経て採択された人権宣言であるが,内容はどのようなものになったのだろうか。宣言は前文および40項目からなり,それらは「基本原則」「市民的・政治的権利」「経済的・社会的・文化的権利」「発展の権利」「平和の権利」「人権促進および保護に関する協力」に分けられる。草案が公開された時点からしばしば指摘されてきたのは,世界人権宣言をはじめとする一般的な人権宣言と同等もしくは下回る内容であれば意味はない,ということである。それを踏まえ,まず前文では世界人権宣言や国連憲章,ウィーン宣言および行動計画などへの言及がある。そしてそれらとの差異という意味では「平和の権利」が特徴的である。そこでは「すべての人はASEANの枠組みによる安全保障と安定,中立性と自由の中で平和を享受する権利がある」とされている。他方,人権への制約も規定されている。具体的には,人権は「国家安全保障,公の秩序,公衆衛生,公安,公衆道徳」の必要性に応じて制限されるという規定や,「人権の実現は地域的および国家的な文脈の中で考慮されなければならない」のであり,多様な経済的,政治的,法的,社会的・文化的,宗教的要因を考慮せねばならないとされている。これらの点はASEAN内の保守的な勢力に配慮した結果であるとともに,NGOなどからは激しい批判を受けることとなった箇所でもある。
ミャンマー問題の進展人権保障制度とともにこれまでのASEANで意見の衝突がみられてきたのが,ミャンマー国内の人権と民主化への関与の是非をめぐる問題である。ただ,ミャンマーが近年民主化を進めてきたことから,この問題は大きな進展をみせつつある。すでにASEANは2011年11月の首脳会議においてミャンマーの2014年議長国就任を認めるという形で,民主化の進展に対して一種の褒賞を与えたが,2012年もそのような流れが継続してみられた。
ミャンマーでは4月1日に連邦議会補欠選挙が行われたが,ミャンマー政府からの要請を受けてASEANは選挙監視団を派遣した。近年,選挙監視を行う地域機構は増加しつつあるが,ASEANとしては初の試みである。
補選の直後に行われた第20回ASEAN首脳会議では,議長声明でミャンマーの補選を自由で公正なものだと評価するとともに,国際社会に対しミャンマーの民主的改革を支援し,すべての制裁を解除するように要請した。実際,この後に制裁は次々と解除されていくこととなった。
その後,ミャンマー西部のラカイン(ヤカイン)州で仏教徒と少数派のイスラーム教徒ロヒンギャ族の衝突が深刻化した。最初の大規模な衝突が5月末に発生しその後鎮静化したものの,10月に再燃し10万人を超える避難民を発生させるに至った。この問題に対し,ASEANは8月に「ミャンマー・ラカイン州における最近の情勢についてのASEAN外相声明」を出した。そこではまず前半部でミャンマーの民主化という政治的発展を好意的に評価したうえで,ミャンマー政府からの要請があれば人道的支援を行う用意があることを述べている。内容はあくまでミャンマー政府の意向を尊重するものであるといえる。11月の第21回ASEAN首脳会議の議長声明においてもこの外相声明の内容を繰り返すにとどまり,ミャンマーの国内問題に注文をつけたり憂慮したりする内容はみられなかった。
これまでミャンマーへの関与をめぐりASEAN加盟国間の意見の衝突が継続的にみられてきたが,ミャンマーの内発的な民主化への動きを契機に主要な争点からは退きつつあるのが現状である。
域外政治安全保障協力政治安全保障分野における域外関係もしくはASEANに関連する一連の広域的な会合においてもやはり南シナ海をめぐる問題が中心的な話題となった。
7月8日に行われたASEANと中国の高級事務レベル会合ではASEANがCOCの草案を提示したが,中国は拒否し,自らも参加する作業部会で一から作り直すことを主張した。その後行われたASEAN地域フォーラム(ARF)ではアメリカ国務長官のヒラリー・クリントンはCOCの策定を促すとともに,ASEANに対しては一体性を持つべきと要請した。また,多くの参加国からは国際法とDOCに則った解決を望む声が聞かれた。他方中国はCOCの早期策定に慎重であり,議長声明の原案には盛り込まれていたCOCの早期策定に関する記述も,最終的には削除されることとなった。また,同時期に開催されたASEAN・中国外相会議においても議論は進展しなかった。
9月13日にはASEAN・中国高級事務レベル会合が開催されたが,そこでも中国は南シナ海問題は二国間で解決されるべきであるとし,COCの早期策定にも慎重な姿勢をみせた。他方,同月21日から25日まで中国・ASEAN博覧会が広西チワン族自治区南寧市で開催され,中国の習近平国家副主席が出席し,南シナ海問題で関係が悪化したフィリピンのロハス内務・自治相と会談の機会を持った。
10月には2012年で第3回を迎えるASEAN海洋フォーラムとあわせて,初めてASEAN拡大海洋フォーラムが開かれた。そこでも南シナ海問題について議論されたが,共同声明ではDOCの尊重とCOCへの努力という2012年に何度も見られた文句が見られるにとどまった。さらに,10月29日にもASEAN・中国高級事務レベル会合の機会が持たれたが進展はなかった。
11月には東アジアサミットが開催されたが,基本的には7月のARFと同様の構図であった。アメリカのオバマ大統領は航行の自由と国際法に基づいた解決を求めるとともに,紛争防止のための新たなルール作りを訴えた。それに対し,中国の温家宝首相は南シナ海問題を国際化させることに反対した。また,ASEAN・中国首脳会議において,中国はASEAN側が提示した骨子案に対し,一から作り直すべきと主張し,一部のASEAN加盟国も賛成の意を示した。同会議で採択された「南シナ海における関係諸国行動宣言10周年を記念する第15回ASEAN・中国首脳会議共同声明」においても,COCについてはコンセンサスに基づいて今後も協議する旨が記されるにとどまった。このように結局2012年を通してCOCの策定に進展はみられなかった。
南シナ海問題以外では,朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の核・ミサイル開発問題もARFや東アジアサミットで議題となった。議長声明では関係各国の平和的な対話や6カ国協議の早期再開を希望する旨が盛り込まれている。
広域的な枠組みにおいて存在感を増しつつあるのがASEAN拡大国防大臣会議(ADMMプラス)である。ADMMプラスはASEANの10カ国とアメリカ,中国,日本,インド,韓国,オーストラリア,ニュージーランド,ロシアからなり,災害対策海洋安全保障,テロ対策などの分野における実践的な協力のプラットフォームとなっている。2012年5月に開催されたADMMではADMMプラスの開催頻度をこれまでの3年に1度から2年に1度に変更することが決定された。なお,次回は2013年6月にブルネイで予定されている。
また,ミャンマーの民主化進展により,ミャンマー国内の人権や民主主義の問題が域外諸国との関係の障害とはならなくなった。この問題がこれまでもっとも深刻であったのがEUとの関係であり,ASEAN・EUのFTA交渉が停止した主要な理由でもあったが,11月のアジア欧州会合(ASEM)首脳会議ではテインセイン大統領がミャンマー首脳として初出席した。
ASEAN諸国は2015年までに政治安全保障,経済,社会文化の3つの分野からなるASEAN共同体を構築することを目指している。このうち,ASEAN経済共同体(AEC)は,2007年11月に採択された「AECの青写真」において,「単一の市場と生産基地」「競争力のある経済地域」「公平な経済発展」「グローバルな経済への統合」の4本柱からなるとされており,具体的には17の行動分野と77の措置が規定されている。AEC達成のスケジュールは2008年から15年までを2年ごとに分けた4つのフェーズからなるが,第2フェーズを終えた段階では非関税障壁の撤廃やサービス貿易の自由化,ASEAN包括的投資協定の発効,規格の調整などが課題となっていた。予定された期日まで残り3年を切った2012年にはAEC構築の進捗度合いが問題となった。
4月の第20回ASEAN首脳会議では「ASEAN共同体構築のためのプノンペン・アジェンダ」が採択されたが,そこでは2015年のAEC構築に向けての努力を倍加させることが述べられている。また,統合への障害に対応するための優先的な活動や具体的な手段を選定する必要性が指摘されている。他方,成果としては3月にASEAN投資協定が発効を迎えたことなどが歓迎されている。
8月の第44回ASEAN経済大臣会議ではAEC構築の履行について中間的なレビューが行われ,その結果として進展の度合いに懸念が示された。ASEANではAEC工程表の進捗状況を「AECスコアカード」によって評価するという形をとっている。そして2012年から2013年の「フェーズⅢ」に入ってからの履行度合いは72%であることが示された。ちなみに,2008年から2011年までの4年間の達成度合いは67.5%であり,そのうち2008年から2009年の「フェーズⅠ」は86.7%,2010年から2011年の「フェーズⅡ」は55.8%であるため,近年のほうが進展の遅れが目立つことがわかる。「フェーズⅢ」に入ってから進展が加速する傾向にはあるものの依然として遅延の状態にあり,共同声明ではプノンペン・アジェンダに基づいて統合への努力を倍加させていく旨が記された。また,具体的な重要課題としては関税と輸送分野におけるAEC協定の批准を進めていくこと,国内法の施行能力を高め,地域的なイニシアティブに基づいた規制改革を実行していくこと,ナショナル・シングルウィンドウ(NSW)や自己証明制度などのAECプロジェクトを実行する能力を高めること,などがあげられている。ちなみに,このNSWとは通関手続きなどに関する窓口の一本化と電子化のためのASEANシングルウィンドウ(ASW)を構成するための各国レベルでの取り組みであり,自己証明制度とは特定の事業者に原産地規則に関する自己申告を認める制度である。
他方,この経済大臣会議にあわせて開催された第4回CLMV経済大臣会議では成長を持続するためにCLMV諸国をASEANに統合させることの重要性で一致した。CLMV諸国は名目GDPにおいてASEAN全体の8.9%,投資において9.7%と占める規模としては小さいものの,これら諸国がAEC青写真の工程を実現できるか否かは共同体実現を左右する要因のひとつである。2013年度版のCLMV行動計画に経済・貿易,人的資源開発,調整メカニズムなどの15の優先項目が含まれているとともに,公平な発展の重要性が指摘されている。
そして11月の第21回ASEAN首脳会議ではASEAN共同体の構築を2015年1月1日から同年12月31日へと,実質的に1年延期することが決定された。ASEAN共同体は3つの共同体から構成されるため延期の原因を一概にAECのみに帰すことはできないが,AECの達成状況は74.5%に上昇したものの依然として遅延のペースにある。とりわけ,批准後の各国内での実施が課題となっている。
ASEAN主導の地域包括的経済連携(RCEP),交渉開始を宣言2012年におけるASEAN経済協力の最大の成果ともいえるのが,地域包括的経済連携(RCEP)の交渉開始が宣言されたことである。RCEPはASEANに加え日本,中国,韓国,インド,オーストラリア,ニュージーランドの計16カ国で域内の貿易投資の自由化を進めるものである。ASEAN以外の6カ国はいずれもすでに「ASEAN+1」の形でASEANと自由貿易協定(FTA)協定を結んでいる国々であり,RCEPはそれらを統合し関税などのルールを一本化する意味合いがある。すでにASEANは2011年の首脳会議で「地域的な包括的経済連携に関するASEANフレームワーク」を発表し,ASEAN+1のFTAを基礎に広域FTAを形成することを強調していたが,その構想が2012年に交渉開始の実現を迎えたことになる。RCEPの特徴はあくまでもASEANがイニシアティブをとる点にある。
具体的には,11月のASEAN首脳会議ではRCEPの交渉開始が宣言されるとともに,「RCEP交渉のための基本指針および目的」が採択された。そこではまず総論部分においてRCEPの目的は近代的,包括的,高水準,互恵的である経済連携協定(EPA)を達成することとされている。ASEANの中心性も確認されている。
次いで,8つの原則が述べられている。具体的には,(1)WTOと整合的であること,(2)既存のASEAN+1よりも広く深いFTA,(3)貿易および投資の円滑化と透明性の向上,並びに参加国のグローバルおよび地域的なサプライチェーンへの関与の円滑化,(4)参加途上国への配慮,(5)参加国間の既存のFTAの存続,(6)オープンな新規参加,(7)参加途上国への技術支援および能力構築,(8)物品貿易・サービス貿易・投資および他の分野の交渉を並行して行うこと,の8項目である。
その後,8つの交渉分野についてそれぞれ基本的な方針が述べられている。具体的には,(1)物品貿易,(2)サービス貿易,(3)投資,(4)経済技術協力,(5)知的財産権,(6)競争,(7)紛争解決,(8)その他の分野,の8つである。「その他の分野」にはオーストラリアが「環境」と「労働」を加えるように主張してきたが,他の加盟国すべての合意は得られていない。また,AEC同様,政府調達は含まれていない。これら8項目のなかで中心となるのは(1)から(3)の3項目である。(1)の物品貿易については具体的な数値目標は設定されていないが,貿易量と品目数の双方において高いレベルの自由化を目指すとされている。(2)のサービス貿易についてはWTOと整合的な形で,すべての分野が自由化の対象となる。(3)の投資については促進,保護,円滑化,自由化の4つの柱を含むとされている。
交渉スケジュールについては,2013年の早期に開始し2015年末までには完了を目指すとされている。もっとも分野や品目の選定,自由化の程度などさまざまな面で交渉は難航すると思われる。ただ,2012年内にスムーズに交渉を宣言できたことを含め,RCEPを促進する要因として,環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)が存在することは重要である。アメリカ主導のTPPに対抗しようとする中国,RCEPをアメリカとのTPP交渉のテコにしようとする日本,TPPによる分裂を避ける,あるいは大国主導のFTAを避け中心性を発揮しようとするASEANなど思惑はそれぞれであるが,RCEP推進の背景にはTPPが存在している。
他方,これらと同時期に日中韓のFTAも交渉入りが宣言された。ASEANはこれに対してはRCEPに資するとの前提で支持してきた。また,ASEAN+3については5月の財務大臣・中央銀行総裁会議でチェンマイ・イニシアティブの資金基盤を倍増することが決定されるなど,各種協力が比較的順調に深化している。
最大の課題は対外的にASEANとしての一体性を発揮することである。具体的には,依然として緊張の続く南シナ海問題において如何に足並みをそろえるかが重要である。ASEAN内の亀裂の露呈による弊害としてASEAN当事者が何より懸念するのは,広域的な協力におけるASEANの中心性が損なわれることである。大国が参加する協力枠組みにおいて地域機構としてのASEANがイニシアティブを発揮するためにも,ASEAN諸国は団結することが重要である。
また,1年延期されたとはいえAECの構築も重要な課題である。とくに各国内で実施するための調整が困難な問題として存在している。他方,RCEPの交渉についても2015年末までに完了という期限は野心的なものであり,参加国の利害調整に積極的に取り組んでいかねばならない。
課題克服を占ううえで注目すべき点のひとつとして議長国があげられる。2012年は南シナ海問題でカンボジアが中国寄りの議事運営をみせたことが話題になった。2013年の議長国はブルネイである。南シナ海問題の当事国ではありながらフィリピンやベトナムに比べるとはるかに穏健な政策をとってきたブルネイの議事運営が注目される。
(日本学術振興会/カリフォルニア大学バークレー校)