巻号一覧
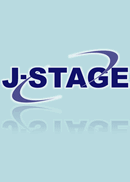
51 巻, 5 号
選択された号の論文の14件中1~14を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
松原 尚子, 稲光 まゆみ, 田中 俊一郎, 白土 秀樹, 平川 直也, 賀数 康弘, 小宗 静男2005 年 51 巻 5 号 p. 319-324
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー小児滲出性中耳炎130名246耳に全麻下に鼓膜チューブ留置術を施行し、チューブ抜去後の経過を判定した。チューブは長期留置型を使用した。チューブの挿入時期、留置期間、アデノイド切除、鼓膜穿孔について検討した。チューブ抜去後半年以上経過した時点で、170耳 (69.1%) は治癒、51耳 (20.7%) は滲出性中耳炎の再発を含む鼓膜緊張部陥凹を来した。平均挿入期間は18カ月であり、鼓膜チューブを18カ月以上留置した症例で治癒率が高かったため、18カ月以上の留置が有効と思われた。アデノイド切除術を行った症例は切除を行わなかった症例より治癒率は高かったものの、アデノイド切除が滲出性中耳炎の予後に有効であるとはいえなかった。平均挿入年齢は5歳であり、発症後早期に発見され治療されている耳は治癒率が高いと思われた。鼓膜永久穿孔は23耳 (9.4%) にみられ、チューブの留置期間や挿入回数にかかわらず生じていたことが明らかになった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10604K) -
安藤 瑞生, 松崎 真樹, 中崎 孝志, 牛嶋 達次郎, 室伏 利久2005 年 51 巻 5 号 p. 325-329
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー一側性に増殖した弁状のポリープ様病変によって呼吸困難を来した症例を報告し、発生機序として、初回の喉頭微細手術との関連を疑った。このような病変の再発を防止するためには、禁煙することは当然であるが、最小限で確実な手術操作を心がけねばならないと再認識させられた。本症例のような病変の増殖は緩徐であると考えられるが、急性炎症が加わることによって上気道閉塞を来し得るため、定期的な経過観察、場合によっては外科的切除による治療が必要となる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9633K) -
賀数 康弘, 中川 尚志, 柴田 修明, 白土 秀樹, 瓜生 英興, 小宗 静男2005 年 51 巻 5 号 p. 330-335
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー炎症性偽腫瘍 (inflammatory pseudotumor: IPT) は、腫瘍増殖を示す占拠性病変でありながら、病理組織学的には炎症性肉芽として診断され、新生物としての所見がみられないものを指す。肺や肝臓など全身での報告があり、頭頸部領域では眼窩、副鼻腔などでの報告はみられるものの、側頭骨のIPTは極めてまれである。今回われわれは中耳に限局したIPT症例を経験した。症例は27歳の男性。左鼓膜に透見された鼓室内赤色腫瘤の精査加療目的で当科受診となった。全身検索では炎症所見や異常所見は認められなかった。側頭骨CTで、鼓室洞に充満する軟部組織陰影が認められ、側頭骨MRではT1強調画像でやや高信号、T2強調画像で低信号、Gd造影で不均一に造影される腫瘍性病変が認められた。摘出術目的で経外耳道の鼓室開放と乳突洞経由のposterior tympanotomyを行った。鼓室洞に血管の乏しい白色被膜に覆われた腫瘍性病変が認められ、これを剥離操作で全摘した。病理では線維芽細胞の増生を伴った形質細胞やリンパ球などの炎症細胞浸潤が著明な炎症性肉芽との診断で、臨床上の所見とを考え合わせてIPTと診断した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10900K) -
望月 隆一, 牟田 弘, 川本 将浩, 山本 圭介, 林 伊吹2005 年 51 巻 5 号 p. 339-343
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー過去11年間に行われたmicrolaryngoscopy下の手術1, 510件/1,405例中、再手術を行った症例について検討した。声帯内自家脂肪注入術では手術後1年未満に再手術を行った症例が最も多かったのに対し、声帯ポリープ・声帯結節では、再手術までの期間は4-8年が多く、次が8年間以上と比較的長期間の症例が多くみられた。これは術後にはいったん治癒したprofessional voice userが、再度microlaryngoscopy下の手術を受けた例が多く認められたものと考えられた。この結果より、microlaryngoscopy下の手術をはじめとする音声外科の術後には、音声障害専門の言語聴覚士による術後音声治療を、長期にわたり続ける必要性が示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7497K) -
平野 滋, 山下 勝, 高北 晋一, 北村 守正2005 年 51 巻 5 号 p. 344-347
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー声帯の血管拡張性病変は、それ自体が声帯振動を障害することがあり、また出血性ポリープの原因にもなる。治療においては鉗除やCO2レーザーが使用されてきたが、より声帯粘膜組織の温存のためにKTPレ-ザーを用いた光凝固治療を試みた。6例に対し血管拡張性病変の光凝固をラリンゴマイクロサージャリー下に行ったところ、光凝固は容易に可能であり、粘膜上皮を温存したまま病変を凝固することができた。術後声帯振動に対する障害は認めず、全例音声機能が改善した。KTPレーザーによる光凝固治療は声帯血管拡張性病変の治療に容易かつ安全な治療法と考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6113K) -
馬場 均, 廣田 隆一, 豊田 健一郎, 大岡 正人, 小池 忍, 久 育男2005 年 51 巻 5 号 p. 348-352
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリーWe report a case of relapsing polychondritis successfully decannulated 7 years after the emergency tracheotomy. A 14-year-old girl was admitted to the hospital with a history of cough and dyspnea worsening for a month. Flexible laryngofiberscopic examination revealed severe subglottic stenosis. Tracheotomy was performed on the admission day. Histological findings from the cricoid cartilage were compatible to relapsing polychondritis. Systemic administration of corticosteroids was performed. The subglottic stenosis improved gradually. The decannulation and surgical closure of the tracheal stoma was performed 7 years after the tracheotomy. Though relapsing polychondritis causes recurrent inflammatory reactions in the cartilaginous structures, it is not impossible to close the tracheal stoma in patients of subglottic stenosis due to this disease.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9352K) -
田口 亜紀, 兵頭 政光, 影山 慎一, 山形 和彦, 森 敏裕2005 年 51 巻 5 号 p. 353-357
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー治療に難渋した外傷後の気管狭窄症例を経験した。症例は52歳、男性。仕事中の転落事故により頭部外傷を来し、同日気管内挿管を受けた。約1カ月後に抜管したところ呼吸困難を呈したため緊急気管切開を受けた。気管内の多発性肉芽による気管狭窄と診断され、治療を受けるも軽快しないため、2001年7月18日当科紹介入院した。長期挿管と局所感染による気管内肉芽に加えて胸骨裏面の骨増殖による気管圧迫、気管軟骨の気管内腔への突出が重複することによる気管狭窄であった。本症例に対しては抗生剤およびステロイドを併用した保存的治療とともに段階的手術を施行し、初診から3年後に気管切開孔を閉鎖することができた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8543K) -
目須田 康, 西澤 典子, 松村 道哉, 古田 康, 福田 諭2005 年 51 巻 5 号 p. 358-361
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー性同一性障害は過去8年の間に本邦にても診断・治療が施行されるようになったが、音声の変化を望む症例に対する治療、特にMTF (male to female) に対するピッチ上昇手術はこれまでガイドラインに明確な定義がされていなかったこともあり、本邦における報告は極めて少なく、手術を強く希望する場合海外の施設を訪れている例があると推測される。今回われわれは東南アジアの某国でピッチ上昇手術を受け、帰国後発声開始後に高度の気息性発声を呈した例を経験した。肉芽切除と各種保存的治療が施行されたが手術後約5カ月の時点で患者の満足は得られていない。今後本邦でも各地で性同一性障害で音声変更を望む例が出現すると予想されるため、ピッチ上昇手術の適応の検討、またこの問題における関係各科との連携の重要性について改めて認識することが必要であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8037K) -
小川 知幸, 益田 慎, 宮里 麻鈴, 福田 秀樹, 田中 裕之, 平川 勝洋2005 年 51 巻 5 号 p. 362-366
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリーわれわれは甲状軟骨形成術I型や披裂軟骨内転術を施行する際に、プロポフォールによるtarget controlled infusion (TCI) を用いた全身麻酔下に施行している。本麻酔法により疼痛が生じやすい部位、手技的に困難な部位を全身麻酔下に操作でき、その後速やかに覚醒させ発声、声門の観察が可能であった。よって本麻酔法により、患者の負担が軽減し、上級医による後進への指導が容易であった。麻酔による舌根沈下の可能性を考慮し、気道確保のために、ラリンジアルマスクと経鼻エアウェイを用いたが、ラリンジアルマスクは発声時に披裂を圧排し、声帯移動量を正確に評価できない可能性があった。これに対して経鼻エアウェイは気道確保に問題はなく、声帯の位置へ影響を与えず、声門の観察が容易であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8626K) -
山下 弘之, 時津 千恵2005 年 51 巻 5 号 p. 367-369
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリーElnell法による声帯外転術が無効であった2例を経験したので報告する。症例1: 74歳、女性、両側喉頭麻痺、甲状腺癌術後、心不全。1999年9月9日に当科を受診した。1989年に甲状腺全摘および気管切開を受けていた。10月26日に気切孔閉鎖を目的として全身麻酔下にEjnell法による声帯外転術を行った。術後に気管切開孔の閉鎖を試みたが呼吸困難のため閉鎖できなかった。症例2: 64歳、男性、両側喉頭麻痺、急性心筋梗塞、糖尿病。1999年2月10日に当科を受診した。呼吸困難に対し気管切開が行われていた。両側の喉頭麻痺を認めた。10月28日に全身麻酔下にEjnell法による声帯外転術を行った。術後にカニューレを抜去したが呼吸困難のため再挿入した。2003年8月29日に声門下の肉芽除去のためラリンゴマイクロサージャリーを行った。症例1は心肺機能の低下のため気管切開孔の閉鎖に至らなかった。症例2は糖尿病がベースにあり声門下に肉芽を形成した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5158K) -
田中 信三, 安里 亮, 山下 勝, 池田 晴人2005 年 51 巻 5 号 p. 370-373
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー一方の鼻腔から電子内視鏡を挿入して喉頭をモニターしつつ他方の鼻腔から可撓性チューブを挿入して病変を鉗除する経鼻的喉頭手術を、比較的大きな声門下肉芽腫例に行った。局麻下で坐位のまま、ピースバイピースに病変の大部分を鉗除した結果、呼吸困難は消失し嗄声も改善した。術後、残存病変は徐々に縮小し、4カ月後に消失した。本手術により気管切開が回避され、満足すべき結果が得られた。本症例は低侵襲手術として経鼻的喉頭手術の有用性を明示する臨床例の一つと考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6947K) -
讃岐 徹治, 一色 信彦2005 年 51 巻 5 号 p. 374-380
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー痙攣性発声障害は局所ジストニアとして定義されており、診断・治療ともに非常に難しいとされている。主訴は、あくまで本人の発声困難という訴えであり、その苦痛の程度は本人しか分からない。しかし診断を正しく行うことは、形態に変化が出る疾患ではなく診断は容易ではない。本稿では、当院を受診され内転型痙攣性発声障害と診断された患者所見などを用い、内転型痙攣性発声障害の診断の進め方、また検査所見の特徴や注意点についても検討した。その結果、診断するのは問診・発声所見・喉頭所見が基本であり、診断の進め方は、喉頭の器質的疾患やほかの機能的音声障害を除外していくことで内転型痙攣性発声障害にたどりつくことが可能であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (12776K) -
甲状軟骨形成術2型の手術手技を中心に讃岐 徹治, 一色 信彦2005 年 51 巻 5 号 p. 381-386
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー痙攣性発声障害は、まれな疾患で病態も全く不明といってよく、有効な治療もないと考えられてきた。現在、神経筋接合部に作用するボツリヌストキシンが痙攣性発声障害に応用され、外来で治療でき恒久的な障害も残さない利点があることから、世界的に普及している。しかし有効期間が3-6カ月であり再注射が必要という問題点もある。われわれは、内転型痙攣性発声障害患者に対して声門過閉鎖の防止を目的に喉頭枠組みを開大し、持続的で再発の可能性が少ない甲状軟骨形成術2型を1997年6月から行い、極めて良好な結果を得ている。そこで2004年10月までに得られた手術実績 (64症例、66件) をもとにそれらの症例をまとめ、その手術適応と手術のコツを中心に述べた。本手術の術式は決して難しくはないが、甲状軟骨の切開、剥離さらに開大幅の調節を慎重に正確に行うことが、手術成功に必要な条件であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10167K) -
2005 年 51 巻 5 号 p. 387-390
発行日: 2005/09/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (5569K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|