巻号一覧
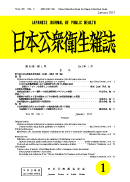
49 巻, 6 号
選択された号の論文の9件中1~9を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
原著
-
藺牟田 洋美, 安村 誠司, 阿彦 忠之, 深尾 彰2002 年 49 巻 6 号 p. 483-496
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 寝たきり予防を積極的に推進するため,在宅高齢者における自立度の 1 年後の変化と自立(ランク J)と準寝たきり(ランク A)の高齢者の自立度の改善・維持と悪化の予測因子の相違を初回調査の身体・心理・社会的側面から総合的に検討した。
方法 1997年に山形県内の65歳以上の高齢者に個別面接調査を実施した。1998年,同一の対象者に追跡調査を実施した。自立度の基準とした「障害老人のための自立度判定基準」(以下,判定基準)の自己評価と他者評価が一致した165人(ランク J:自立112人,ランク A:準寝たきり53人)を分析対象とした。調査項目は判定基準のほか,身体・心理・社会的項目20項目であった。なお,予測因子の分析では自立,準寝たきりともに改善・維持,悪化の 2 群に分類して検討した。
成績 1. 1997年の自立度別にみた 1 年後の転帰:死亡は自立が0.9%,準寝たきりが7.6%であった。女性,または75歳以上である場合,自立度が低下するほど,死亡者は多かった。
2. 自立度別にみた 1 年後の自立度の変化:自立高齢者の23.1%で自立度が悪化した。準寝たきりで自立度が改善した者は35.4%,悪化した者は14.6%であった。性・年齢階級による自立度変化への影響は認められなかった。
3. 自立高齢者の自立度変化の予測因子:身体的項目では,過去 1 年間の入院あり,心理的項目では自己効力感が低いこと,主観的健康感が悪いこと,社会的項目では老研式活動能力指標得点が低いことが自立度低下と関連していた。
4. 準寝たきりの自立度変化の予測因子:身体的項目では排尿が要介助であること,心理的項目では自己効力感の得点が低いことが自立度の悪化に関連していた。
結論 在宅高齢者では,自立度の悪化にともない,女性,または後期高齢者の場合,1 年後死亡になりやすいことが示された。また,1 年後の自立度変化では,準寝たきりで自立に改善した者が,寝たきりに悪化した者よりも多かった。在宅高齢者の 1 年後の自立度は可逆的であることが示された。
自立,準寝たきりともに自立度の悪化と心理的項目の自己効力感が結びついていることが明らかとなった。簡単な掃除など身の回りの行動に対して自信が持てないことを意味する自己効力感が低いことが,自立・準寝たきり高齢者の 1 年後の自立度を予測する上で極めて有効であることが明らかになった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1686K) -
前田 清, 太田 壽城, 芳賀 博, 石川 和子, 長田 久雄2002 年 49 巻 6 号 p. 497-506
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 高齢者の QOL に対する身体活動の意義や効果を明らかにすることを目的に,高齢者の身体活動や運動習慣の実態を把握し,これらの多寡やその変化が,QOL や身体症状に及ぼす影響について横断的および縦断的に検討した。
方法 名古屋市近郊の一地域に在住する63, 68, 73, 78, 83歳のすべての高齢者を対象とし,運動,身体活動習慣と QOL(6 分野)に関する自記式アンケート調査を行った。3 年後に同様の調査を行い,両年ともに回答の得られた958人を解析対象とした。
対象者の身体活動,運動習慣および QOL 各分野について 3 年間の変化を観察した。次いで初回の身体活動別に,同年および 3 年後の各 QOL を比較した。さらに身体活動習慣の変化が QOL に対する影響をみるため,前者の変化を説明変数の一つに用い,QOL 等の変化を目的変数としたロジスティック回帰分析を行った。
成績 対象者の日常身体活動は比較的よく保たれていたものの,3 年間でほとんどの習慣の実践割合は数~10%程度低下しており,低下の程度は高齢になるほど大きかった。しかし 3 年間で身体活動習慣の増加した高齢者も20~30%あった。横断的,縦断的いずれの検討においても,身体活動習慣の多い者ほど各 QOL は高かった。ロジスティック回帰分析の結果から,ほとんどの QOL 分野の変化に対して初年時の身体活動習慣は正の寄与を示した。また身体活動の変化も同様の寄与が認められた。
結論 高齢期においても日常身体活動はある程度維持されており,身体活動習慣の増加する者もあった。身体活動の多い者は QOL が高く維持されていた。身体活動を維持,増加させることは,高齢者の QOL の維持,向上に寄与することが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1107K) -
米山 京子, 池田 順子2002 年 49 巻 6 号 p. 507-515
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 妊娠,授乳により低下した骨密度の回復について再妊娠,再授乳の場合も含めて縦断的観察により検討する。
方法 妊娠初期に骨密度を測定した妊婦の中から第 1 子または第 2 子を出産した健康な産褥婦28人を対象として,超音波法による骨密度測定を出産後最長 5 年まで半年に 1 回の頻度で追跡し離乳後の骨密度の変化を授乳期間別,再妊娠の有無別に調べた。stiffness を骨密度指標とした。
結果 1. 骨密度は授乳期間が 0-1 か月(G1 群)では変化なしまたは出産後0.5-1 年,2-6 か月(G2 群)では出産後0.5-1.5年,8-12か月(G3 群)では 1 人以外出産後 1-4 年で妊娠初期値まで完全に回復した。平均的には G1-G3 群順に出産後0.5年,1 年,1.5年でそれぞれ妊娠初期値と有意差はみられなくなった。
2. 離乳後 1 年以上後に再出産した場合,再出産時の骨密度は前回出産時とほぼ同じあるいはそれ以上であり,再授乳後には妊娠初期値よりさらに高くなる場合もみられた。
3. 離乳後 1 年以内に再出産した場合,再出産時の骨密度は前回出産時まで回復せず,再授乳後にも授乳開始時までの回復はみられなかった。
結論 妊娠,授乳により低下した骨密度は授乳期間に応じて出産後0.5-4 年で妊娠初期値まで回復する。再妊娠,再授乳による骨密度回復への影響は,授乳期間ではなく離乳後次回出産までの間隔であることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (916K) -
平田 まり, 隈部 敬子, 井上 芳光2002 年 49 巻 6 号 p. 516-524
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 10歳代後半から20歳代前半の女性の多くが月経痛のために苦しみ,日常生活に支障を来たしている。それ故に月経痛と関連する日常生活要因を明らかにすることは,若い女性の Quality of Life(QOL)の向上に貢献する。本研究の目的は,やせている者の比率が最も高い青年期女性において食物摂取状況や身体活動度を反映する体格が,月経痛の頻度に関連するかを明らかにすることである。
対象と方法 18歳から21歳の女子大学生2,718人を対象にして2000年 4 月に,身長・体重測定と月経関連項目について自記式アンケート調査を行った。有効回答者2,288人の中,月経周期が 3 か月以上や過短月経の者を除いた2,282人を解析対象とした。月経痛の頻度と年齢,体格,運動,および月経関連項目(初経年齢・月経周期・月経期間・月経量)との関連をロジスティック回帰分析で検討した。
結果 2,282人の解析対象者の中,月経痛がいつもある者は34.1%,時々ある者は48.7%,ほとんどない者は17.2%であった。日本肥満学会の旧判定基準による分類では,やせ(BMI<19.8)群は34.8%,普通(19.8≦BMI<24.2)群は53.8%,過体重(BMI≧24.2)群は11.4%であった。体格の普通群を基準因子とした時,やせ群の「月経痛がいつもある」オッズ比は1.3 (95%信頼区間:1.1-1.6),過体重群のオッズ比は1.1 (95%信頼区間:0.8-1.5)であった。また月経痛がいつもある危険性は,初経年齢が若い者,および月経量が多い者は高く,月経周期が不規則な者は低かった。
結論 調査対象とした女子大学生において,月経痛の有訴率は82.8%と高かった。月経時にいつも痛みがある危険性は,体格が普通である者より BMI が19.8未満のやせた者に高いことが明らかになった。BMI が19.8未満の者は,日本の15歳から24歳の女性の半数近くを占めることを考慮すると,月経痛を緩和して QOL を高めるために,青年期女性のやせ志向性への対策が重要であることを本研究の結果は示唆するものである。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1046K)
公衆衛生活動報告
-
国柄 后子, 山津 幸司, 足達 淑子2002 年 49 巻 6 号 p. 525-534
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 身体活動量の増加,健康的な食生活,適切な飲酒,禁煙や減煙,口腔衛生,ストレス対処(休養)の 6 種類の生活習慣の改善を目的として,1 か月間の通信による最小限の行動変容技法を用いた介入を行い,6 か月後まで追跡することでその効果を検討した。
方法 募集は案内パンフレット(6 種類の習慣行動の案内,参加申込用紙,参加記念品の写真などで構成)の配布で行った。応募者435人(男性255人 平均年齢46.6歳,女性180人 平均年齢34.4歳)は,6 種類の習慣行動からひとつを自由に選び,習慣行動のセルフチェック,3 つ以内の習慣改善目標行動の設定をして申し込んだ。次ぎに記録シートと選んだ習慣行動の教育教材を受け取り,1 か月間毎日,目標行動の実行の有無を自己評価しセルフモニタリングした。指導者は 2 週間後に励ましの手紙を送り,終了時には,参加者が提出した記録シートに基づきコメントを添え,希望の記念品と一緒に送付した。
成績の評価指標としては,課題のコンプライアンスとして記録シートの提出率と目標行動の達成率を算出し,習慣行動の変化は同一質問紙で測定された,終了時と 6 か月後の行動変化を用いた。
結果 結果は,7.8%の応募率,80%の目標達成率という高いコンプライアンスが得られた。習慣行動の変化は,合計28項目中18項目の具体的な行動に有意な改善がみられた。たとえば,歩行,階段の利用,野菜の摂取,食べる速さ,飲酒頻度,外での飲酒頻度,1 日の喫煙本数,肺まで吸い込むこと,歯磨きの頻度,歯ぐきを磨く頻度,睡眠時間,ゆっくりした入浴頻度などが改善していた。さらに 6 か月後に,得られた272人(回収率62.5%)のデータで比較した結果,17項目の具体的な行動に改善がみられていた。
結語 最小限の介入であっても,準備性のある人にとっては行動変容のプロンプトとして有効で,費用効果の高い,公衆衛生領域に有用な習慣改善法であると思われた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1176K) -
中野 匡子, 金成 由美子, 角田 正史, 紺野 信弘, 福島 匡昭2002 年 49 巻 6 号 p. 535-543
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 医学教育の中で地域指向型教育の重要性が指摘されている。我々は,医学部 4 年生の公衆衛生学実習において,小人数グループでの地域指向型教育を 3 年間実施し,実習の教育的効果の評価を試み,今後の実習の方向性を検討した。
方法 1. 実習の概要:医学部 4 年生(70~80人)は小人数(2~3 人)グループに分かれ,福島市周辺の保健・医療・福祉・教育等関連施設で週 1 回(約 4 時間),計 3 回実習した。学生は施設の事業に参加し,体験実習の中から,解決すべき健康問題を把握し,施設の取り組みと今後の課題を検討した。施設実習後,学生は,報告会を行い,グループごとの報告書と,個別の自由記載の感想文を提出した。
2. 評価:平成11年度 4 年生73人(男42人,女31人,平均年齢23.6歳)について,実習の教育効果の評価を行った。1) 報告書の中で学生が挙げた「解決すべき健康問題」と,自由記載の個別の感想文を分類し,実習目的の理解度をみた。2) 社会意識の測定方法である ATSIM (Attitudes Toward Social Issues in Medicine)質問表を用い,実習前後の得点の変化を検討した。ATSIM 質問表は 7 群(社会因子,医療関係者間の協力,予防医学の役割,医師-患者関係,政府の役割,進歩対保守主義,社会への奉仕に対する意識)から構成され,得点が高いほど社会意識が高いと評価される。
結果および考察
1. 報告書の中で取り上げられた健康問題は,精神障害者の社会復帰のための環境整備,難病患者の在宅支援,学校での養護教諭と担任らの連携,知的障害児の地域生活のための環境整備などであった。また,個別の感想文においては「現場を体験・実感できた(73人中60人,82.1%)」,「医師として地域の人々や施設とどう関わるか考えることができた(26人,35.6%)」,「予防の必要性に気づいた(4 人,5.5%)」,「回数の増加を望む(5 人,6.8%)」等の意見がみられた。
2. ATSIM の得点は,7 つの群の各々および総計の平均点に,実習前後で有意な差はみられなかった。
まとめ 学生は施設での体験の中から地域の健康問題を把握した。個別の感想文では実習の意図を理解し実習に肯定的なものもみられた。ATSIM 質問表で測った社会意識には,実習の前後で有意な変化はみられなかった。今後,施設の選定,実習時間,学内での討論方法,評価法などに修正を加え,「公衆衛生の精神を体得した」医師養成のために,より有効な教育形態としていきたい。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1066K)
資料
-
藤田 啓子, 箆伊 久美子, 井上 和子, 〓 玉秀, 美ノ谷 新子, 福嶋 龍子, 松下 裕子, 拜原 優子, 宮本 郁子, 王 坤英, ...2002 年 49 巻 6 号 p. 544-553
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 1990年代から中国社会においても高齢化現象が急速に進んでいる。特に農村部から都市部への人口の大規模な移動は,従来の家族形態にも変化を来たし,高齢者の健康や生活に大きな影響を及ぼしている。このような状況下で,健康や医療に携わっている看護職者の高齢者に対する意識を知るために,看護職者が高齢者と考える年齢,高齢者が抱えていると看護職者が捉えている問題・健康管理方法・趣味・娯楽および老親の同居・世話について調査した。
方法 自作の質問紙を,中国衛生部が選定した遼寧省,山西省,貴州省,湖北省,吉林省,江蘇省,湖南省,寧夏回族自治区に勤務する看護職者に配布し,有効回答3,396を得た。
結果 1. 看護職者が高齢者と考えている年齢は,50歳以上~70歳以上に分布し,看護職者の87.5%は60歳以上を高齢者とみなしていた。遼寧省,山西省,吉林省,江蘇省では約30%の者が70歳以上と回答していたが,山西省を除いた 3 省は経済開発地区であり,高齢化率の高い地域である。
2. 高齢者が抱えていると考えられる問題は,健康問題81.1%,生活費の問題14.3%,家族との同居問題11.3%,住居の問題7.5%であった。
3. 健康管理方法では60%以上の高齢者が早寝早起き,約40%の者が栄養に注意,健康診断は約20%であった。
4. 高齢者の趣味娯楽については看護職者の62.4%がテレビの視聴をあげていた。家族の団欒34.8%,友人との会話が約36%であった。
5. 両親が高齢になった時の同居と世話については,約60%の者は「する」と回答していた。17~30歳群と31~60歳群の 2 群間では17~30歳群の方が有意に高く(P<0.01),地域別では寧夏自治区,山西省で差が認められた(P<0.01, P<0.05)。
考察 看護職者の約50%の者が65歳以上を高齢者と見なしており,わが国と同様の結果を示していた。高齢者の趣味・娯楽としては,テレビ視聴という回答が一番多かった。また,高齢者問題では健康問題とした者が80%以上を占め,わが国の健康問題より高かったが,これは高齢化が急速に進む一方で,社会保障制度が整備途上にあるためと考えられる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1331K) -
門田 新一郎2002 年 49 巻 6 号 p. 554-563
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 生活習慣病の予防は,学校健康教育の現代的課題としてその重要性が指摘されている。そこで,大学生の生活習慣病に関する意識,知識,行動について調査し,その実態を明らかにして,学校健康教育の在り方を検討する際の基礎資料にする。
方法 某国立大学の学生783人を対象に,質問紙法による無記名式で調査した。調査内容は,生活習慣病に関する予防態度,関心,不安,知識,健康行動・意識である。無回答の項目がある者を除いた736人(男子367人,女子369人)を分析対象とし,性別比較,および,予防態度と関心・不安,健康行動・意識との関連について検討した。
成績 生活習慣病の予防態度では,喫煙と飲酒では積極的態度をとっている者が70~85%みられたが,食生活と運動・スポーツでは少なかった。
生活習慣病の定義をよく知っている者は75%程度みられたが,学習意欲がある者や情報収集をしている者は少なく,生活習慣病への不安のある者も少なかった。
定期健康診断の受診意欲はほとんどの者が持っているが,当該年度に受診しなかった者が10.6%みられた。
主要死因,食塩の過剰摂取,肥満,糖尿病,高コレステロール血症,大腸がんに関する知識の正答率は21~97%と差が大きかった。
健康行動では朝食欠食や運動不足の者が30~60%とみられたが,喫煙しない者は90%と多くなっていた。健康意識では健康の自己評価の低い者や目覚めの良くない者が10~35%みられた。
性別比較では,予防態度,関心,受診状況,知識,健康行動・意識ともにかなり差がみられた。運動・スポーツで男子に実施している者が多かったが,それ以外の項目では女子に意識,関心が高く,知識の正答率も高くなっていた。また,女子に健康的な行動をとっている者が多くなっていた。
生活習慣病の予防態度と関心,受診状況,健康行動・意識には関連のみられるものが多かった。予防に積極的態度のみられる者は関心も高く,健康的な行動とっている者や健康意識の高い者が多くなっていた。
結論 大学生の生活習慣病に関する意識,知識,行動についてみると,予防態度はあまり積極的ではなく,関心も低かった。また,知識も不十分で,受診状況,健康行動・意識にも問題がみられた。これらのことから,大学での健康教育の推進は言うまでもなく,小,中,高等学校における健康教育の一層の充実が必要であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1177K) -
田中 毅, 高橋 央, 大山 卓昭, 岡部 信彦, 内田 幸憲2002 年 49 巻 6 号 p. 564-573
発行日: 2002年
公開日: 2015/12/07
ジャーナル フリー目的 経験豊富なドイツの現状を調査することで,日本におけるウイルス性出血熱輸入例対策の現状を評価した。
方法 ドイツではロベルトコッホ研究所のウイルス性出血熱対策担当者と面談し,ベルリン,ライプチッヒの高度隔離病床を視察した。日本では成田赤十字病院,りんくう総合医療センターを訪問し,両国間のウイルス性出血熱対策の相違を World Health Organization(WHO,世界保健機関)が1994年に提唱した「新興ウイルス感染症克服のための行動指針」に沿って比較した。
結果 ドイツでウイルス性出血熱の疑い患者が発生した場合,自治体指令センターの公衆衛生医が隔離を決定し,患者は国内に 5 施設ある隔離センターに専用車両で搬送される。ベルリンの病床はベッド全体がビニール製の隔壁で覆われた旧式で,高度医療は困難である。新型のライプチッヒのベッドは二重陰圧管理で,ベッド周囲が広く,高度医療が可能である。また出血熱患者がいない時には,耐性菌感染患者等を入院させて職員のトレーニングを行っている。
感染症サーベイランスの強化,国立試験検査機関の充実,実用化を前提とする感染症研究の推進という 3 つの目標については,両国とも最近改正された感染症に関する法律に則って,質の向上が継続されており,両国間に大きな差異はみられなかった。もう 1 つの目標である感染症を予防,制圧する戦略の策定では,相違点が複数認められた。第 1 にドイツではウイルス性出血熱対応の主体は自治体であり,有事には自治体中心に対策チームが速やかに編成されること,第 2 に日本の方針と異なり,ドイツの高度隔離病床は合計10床であること,第 3 に日本の隔離病床では飛沫感染対策が十分とはいえないこと,最後に,ドイツでは職員の訓練を兼ねて,耐性菌感染患者などを高度隔離病床に入床させていたのに対して,日本の高度隔離病床では空床利用されていないこと,であった。
結論 今後わが国では下記の諸点,1) 国立試験検査機関機能の更なる充実,2) ウイルス性出血熱患者対応に関する検疫所,自治体,国立試験検査機関の連携の必要性,3) 隔離病床数と設置地域の再検討,4) より実用的な隔離病床の構造,運用,利用法の確立,5) 高度耐性菌感染症患者による空床活用の是非,6) 医療従事者,その他関係者への新興再興感染症の教育実施,が重要であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2160K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|