巻号一覧
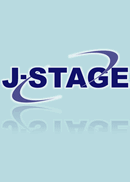
12 巻 (1961)
- 3-4 号 p. 183-
- 2 号 p. 89-
- 1 号 p. 1-
12 巻, 3-4 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
窪田 正八1961 年 12 巻 3-4 号 p. 183-198
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー3つないし6つのじよう乱だけから成りたつ順圧過度方程式は第1種および第3種の楕円函数を用いて解析的に解くことができる。これから,
1)順圧大気中の変動の週期は最低5日位までであるが,一般流とのやりとりからくる週期は短い。
2)週期はシステムの全エネルギーに逆比例するから,一般流の強さのえいきようは大きい。
3)代表的スケールが最中のスケールに近いほど週期は長く,しかも,その真中のじよう乱のスケールが両側のいずれかに片よつているとその程度は大きい。
4)運動エネルギーのやりとりは,小さいスケールが互に近いと,その間だけのやりとりが大きく,大きいスケールえのえいきようは小さい。
5)非線型項の時聞変動の週期は長い。
6)観測値を使つた積分では2万個ぐらいのinteractionの係数を使つたところで最高の相関係数を示す。小さいスケール同志の寄与が小さくむしろ実際の計算ではエラーの源になつていることを推測させる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1681K) -
窪田 正八, 広瀬 元孝, 菊池 幸雄一, 栗原 宜夫1961 年 12 巻 3-4 号 p. 199-215
発行日: 1961/03/24
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー球函数表示を用いると,格子点による方法に伴うような空間誤差は存在しないので,将来,長期予報に役立つと思う。もちろん,それはそれなりに厄介な問題もあるが,ここでは一応,北半球順圧予報方式の技術的説明,誤差分布からみて妥当と思われる波数の決定,2つの波が干渉して1つの波を作るとき用いられる Interaction Functionsの計算法および球函数への分解法を呈出し,あわせて1つの予報例に基づき,f∇2ψ=∇2Zの変換の問題などを見た。
なお,相関係数は0.73程度,全運動エネルギーの時間変動は0.18%に過ぎなかった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2101K) -
丸出 晴久1961 年 12 巻 3-4 号 p. 216-246
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー1・自然氷晶核の濃度が日々にまた季節的にどのように変化しているか,またその origin はどこにあるかなどを知るために1959年の11月から1960年の10月までの1年間,type Aの装置を用いて作用温度にたいする核数のスペクトルの観測を行つた.
自然氷晶核の濃度は作用温度が低くなると指数酌に増加することが明らかになつた。また-20°C核について9/l以下の濃度の観測される割合は50%(夏季)から70%(冬季)を占め,50/l以上の割合は10%(冬季)から20%(夏季)となり,100/l以上になると5%(冬季)から10%(夏季)と少くなることがわかつた。また主な流星雨の日から約28日目に氷晶核濃度の増大が観測されることもみいだされた.
流星雨との関係をさらに確めるためにその28日目の前後の期間に type B の装置を用いて-20°C核にいて5~10分おきの連続観測を行つた。1961年の5月までの主な6つの流星群についての結果,そつのいずれも28日目に核の増大が観測された。これが偶然の一致であるならばその確率は10-4となる。そしてその値は最高100~1000/lとなり普通の日の値の数十倍の増加を示した。しかしその増加は2~3時間ぐらい続き10時間以上続くことはまれである。またその前後の日にも約24時間の間隔で小さいピークがあらわれることもみいだされた。また,Leonids, Geminids, Ursidsなどの流星群に対応して2年とも同じ日付でピークが観測された。したがつてこれらの結果から,28日目に増加した氷晶核は流星群の軌道上に存在していた微細な流星塵であり,地球大気を通して地上まで運ばれてくるのに約28日を要すると結論してもその危険率は非常に小さいといえる.
2.Bowen(1953)の降水量の統計的研究をチエツクするために日本全国から約60年の観測年数を有し,相互に約200kmはなれている測候所を20ケ所えらび,月日別降水量の累年平均値を用いて統計的検定を行つた。その結果,大きな流星群の日から28~31日目の4日間の降水量はその前後に比し,平均として15%増加していることが,0.1%の危険率で有意となつた。そして個々の流星群にたいしては30%も増加していることがわかつた.
3.もし流星群からの微細な粒子が地上の氷晶核の濃度や降水量を増加させるとすれば,次のようなphysical processが推測される.
1) 氷晶核として観測された粒子の大きさは半径1μ前後と推定され,その粒子は成層圏内では自然落下により,対流圏では強い下降気流(数cm/sec)によつて地上まで運ばれたものと考察される.
2)対流圏に入つた流星塵は対流,大気拡散によつて約28日から数日の間全地球の,特に中緯度の大気中の氷晶核濃度を増加させ,各地において雲系に入つたものは氷晶の核として作用し,その結果として降水の増加をもたらすものと考えられる.
4.しかしながら,流星塵と氷晶核との関係は流星群と地上の氷晶核濃度との対応の統計的結果のみでは不充分である。流星塵が有効な氷晶核であることが直接的に証明され,また流星塵が宇宙空間(流星群の軌道上)に高濃度に存在していることの確認や,大気中に入つてから下層に到達する機構などが明らかにされなくてはならない。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5239K) -
測定および計算の方法について三崎 方郎1961 年 12 巻 3-4 号 p. 248-260
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー前報では,1959年に新たに設計製作した大気イオソの移動度スペクトロメーターの内部の気流分布に関する実験結果を述べたが,4~9l/secが適当な流量であることがわかつたので,これに基き,通気筒の一部を改造して,スペクトロメーター本来の機能をもたせて,測定を開始した。スペクトラム測定の方法は以前に筆者が考案した原理による。イオン・プローブは等長で,直径の異なる二本を用意したが,それぞれに適当な移動度範囲を受けもたせれば3~0.005m2/volt. secの範囲が走査できる。しかし当面の研究範囲は3~0.1cm2/volt. secとして,いわゆる小イオン群のスペクトラム微細構造を明らかにすることを目的とした、ここでは装麗および実験手順に関する詳細と,装置の特性(分解能等)について述べ,更に,清浄空気および汚濁空気中で行つた綜合検査の検討から,実験上の組織的誤差とその補正法について述べた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2848K) -
移動度スペクトラムと大気電気伝導率との関係三崎 方郎1961 年 12 巻 3-4 号 p. 261-276
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー小イオソ領域(移動度3.0~0.2cm2/volt.sec.)の移動度スペクトラムを筆者の方法によつて求めた。汚染大気中の状態と,清浄大気中のそれとを比較するために,測定は東京と長野県軽井沢とにおいて・全く同じ方式で行われた。
移動度スペクトラムと大気伝導率との関係について,両地点で得た資料を比較した結果,以下の結論を得た。
(1)東京(汚染大気)においては,小イオン数は電気伝導率から期待される値より可成り少い。この場合には大(又は中)イオンも電気伝導率に可成り寄与しているものと考えざるを得ない。一方,軽井沢(清浄大気)では電気伝導率は,事実上小イオンのみで充分に説明される。
(2)大気伝導率の変動が小イオン移動度の変化によることはない。電気伝導率が大きく変動しても,スペクトラムをとつてみると,小イオン群の移動度軸上における位麗は不動であることがわかる。
(3)小イオン・スペクトラムの尖頭値は,移動度1.0~0.7cm2/volt.sec.の範囲に見出される。ただし;伝導率にもつとも大きく寄与する領域は,それより稽大きく,1.3~1.0cm2/volt.sec.である。
(4)都市の空気のように,可成り汚染している大気中では,通常の小イオン数測牢法,つまり一定電圧を集電極に与えて測る方法は不適当である。こうした方法では,小イオンのみならず,相当量の大イオンも極に捕集されてしまうので,可成りの過大評価となるからである。
(5)大気の電気伝導率と,通常の測定法による小イオン数との比から,小イオンの平均移動度を算出することが屡々行われているが,これは上寵の事実を考え合せると,見掛けの値にすぎぬことがわかる。こうした見掛けの平均移動度は,伝導率の増減にしたがつて,やはり増減することが理解される。しかし,事実は(2)に述べた通り,平均移動度は不変である。
(6)正負のスペクトラムについては,本質的な差は見出されなかつた。日中と夜間では,平均移動度に影響を与える程ではないにしても,スペクトラムの形になにがしかの差が見出される。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2963K) -
矢野 直1961 年 12 巻 3-4 号 p. 277-293
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー大気中の自然放射性塵埃を測定するために自動連続記録装置を製作した。この装置はβ線と同時にα 線も測定することが可能であり,また採取時間は3時間以内で任意に決めることができる。
大気浮遊塵はサンプラーのアルミテープ上に取られ,集塵終了後5秒で検出器におくられ,計数および記録がおこなわれる。
大気中のラドン崩壊生成物の非平衡をしらべる目的でこのアルミテープ上の諸元素の蓄積の時間的変化を考察した。この装置は半減期の短い元素の減衰も計ることができるので,集塵終了後の84Po218および84Po210によるアルフア減衰曲線からこの非平衡を調べることができる。
この装置を使つて東京と軽井沢の野外観測をおこなった。東京では晴れた静夜には例外なく自然放射能の増大がみられた。この日変化は夜間,夜明けに向つて増加し,日中減少した。これに対して,軽井沢では日中が夜間に比べて増加する傾向を示した。気温や温度あるいは巨大空中塵はこの日変化を大きく支配する因子でないことが明らかになった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3364K) -
柳沢 善次1961 年 12 巻 3-4 号 p. 294-309
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー関東地方の西部及び東部地域で観測された停滞性の帯状エコーの特性やその発生について解析した。このような帯状エコーは小さい細胞状エコーの発達によって形成されたエコーであり,このエコーの発生は伊豆及び房総半島の地形やその付近の大気の状態に影響する。また,このような細胞状エコーが移動しつつ発達し帯状エコーになるための上層風の状態,湿潤空気層の厚さについても論じた。さらに,半島山岳地帯の細胞状エコー発生に対する効果を調べるために,この地域の地形上昇流の分布を計算した。
この解析の結果,このような停滞性の帯状エコーの発生,発達,消滅は地形の影響によって起ることが示された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3996K) -
三宅 泰雄, 川村 清, 桜井 澄子1961 年 12 巻 3-4 号 p. 310-317
発行日: 1961年
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー1959年と1960年の初秋,乗鞍岳の山腹(高さ1,450m)と山頂(高さ2,770m)で大気オゾンと亜硝酸(NO2)を測定した。その結果,日中時におけるオゾン濃度は気圧と密接な関係にあり,気圧が高いときはオゾン濃度も高いことがわかった。また,1959年における山頂と山腹のオゾンの日中時の平均値は58μg/m3および35μg/m3であつた。これはオゾソ濃度が観測地点の高さに大体比例して増加することを示している。1960年のオゾン濃度は,天候が悪かつたためか,1959年の場合よりも低かつた。山腹における測定から亜硝酸は日の出後(7~9時)と日没直後(18~20時)にそれぞれ極大値をもつような日変化のあることが見出された。しかしながら,山頂ではこのような日変化はなかつた。山腹における亜硝酸濃度の日中時の平均値は夜間時のそれと大体同一であり,1959年で2.8および3.1μg/m3,1960年では2.7および3.1μg/m3であった。山頂の亜硝酸濃度は低いけれども山腹におけると同じ関係があり,1960年における値はそれぞれ2.3および2.5μg/m3であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1351K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|