巻号一覧
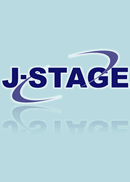
54 巻 (2008)
- 4 号 p. 432-
- 3 号 p. 282-
- 2 号 p. 110-
- 1 号 p. 2-
M33 巻 (1900)
- 336 号 p. 336_C1-
- 335 号 p. 335_C1-
- 334 号 p. 334_C1-
- 333 号 p. 333_C1-
- 332 号 p. 332_C1-
- 331 号 p. 331_C1-
- 330 号 p. 330_C1-
- 329 号 p. 329_C1-
- 328 号 p. 328_C1-
- 327 号 p. 327_C1-
- 326 号 p. 326_C1-
- 325 号 p. 325_C1-
- 324 号 p. 324_C1-
- 323 号 p. 323_C1-
- 322 号 p. 322_C1-
- 321 号 p. 321_C1-
- 320 号 p. 320_C1-
- 319 号 p. 297-
- 318 号 p. 249-
- 317 号 p. 201-
- 316 号 p. 155-
- 315 号 p. 105-
- 314 号 p. 57-
- 313 号 p. 1-
M32 巻 (1899)
- 312 号 p. 312_C1-
- 311 号 p. 311_C1-
- 310 号 p. 310_C1-
- 309 号 p. 309_C1-
- 308 号 p. 308_C1-
- 307 号 p. 307_C1-
- 306 号 p. 306_C1-
- 305 号 p. 305_C1-
- 304 号 p. 304_C1-
- 303 号 p. 303_C1-
- 302 号 p. 302_C1-
- 301 号 p. 301_C1-
- 300 号 p. 300_C1-
- 299 号 p. 299_C1-
- 298 号 p. 298_C1-
- 297 号 p. 297_C1-
- 296 号 p. 296_C1-
- 295 号 p. 295_C1-
- 294 号 p. 253-
- 293 号 p. 201-
- 292 号 p. 151-
- 291 号 p. 99-
- 290 号 p. 51-
- 289 号 p. 1-
M31 巻 (1898)
- 288 号 p. 288_C1-
- 287 号 p. 287_C1-
- 286 号 p. 286_C1-
- 285 号 p. 285_C1-
- 284 号 p. 284_C1-
- 283 号 p. 283_C1-
- 282 号 p. 282_C1-
- 281 号 p. 281_C1-
- 280 号 p. 280_C1-
- 279 号 p. 279_C1-
- 278 号 p. 278_C1-
- 277 号 p. 277_C1-
- 276 号 p. 276_C1-
- 275 号 p. 275_C1-
- 274 号 p. 274_C1-
- 273 号 p. 273_C1-
- 272 号 p. 272_C1-
- 271 号 p. 271_C1-
- 270 号 p. 267-
- 269 号 p. 211-
- 268 号 p. 161-
- 267 号 p. 107-
- 266 号 p. 53-
- 265 号 p. 1-
M30 巻 (1897)
- 264 号 p. 264_C1-
- 263 号 p. 263_C1-
- 262 号 p. 262_C1-
- 261 号 p. 261_C1-
- 260 号 p. 260_C1-
- 259 号 p. 259_C1-
- 258 号 p. 258_C1-
- 257 号 p. 257_C1-
- 256 号 p. 256_C1-
- 255 号 p. 255_C1-
- 254 号 p. 254_C1-
- 253 号 p. 253_C1-
- 252 号 p. 252_C1-
- 251 号 p. 251_C1-
- 250 号 p. 250_C1-
- 249 号 p. 249_C1-
- 248 号 p. 248_C1-
- 247 号 p. 247_C1-
- 246 号 p. 246_C1-
- 245 号 p. 201-
- 244 号 p. 165-
- 243 号 p. 109-
- 242 号 p. 61-
- 241 号 p. 1-
M29 巻 (1896)
- 240 号 p. 240_C1-
- 239 号 p. 239_C1-
- 238 号 p. 238_C1-
- 237 号 p. 237_C1-
- 236 号 p. 236_C1-
- 235 号 p. 235_C1-
- 234 号 p. 234_C1-
- 233 号 p. 233_C1-
- 232 号 p. 232_C1-
- 231 号 p. 231_C1-
- 230 号 p. 230_C1-
- 229 号 p. 229_C1-
- 228 号 p. 228_C1-
- 227 号 p. 227_C1-
- 226 号 p. 226_C1-
- 225 号 p. 225_C1-
- 224 号 p. 224_C1-
- 223 号 p. 223_C1-
- 222 号 p. 222_C1-
- 221 号 p. 211-
- 220 号 p. 157-
- 219 号 p. 109-
- 218 号 p. 59-
- 217 号 p. 1-
M28 巻 (1895)
- 216 号 p. 216_C1-
- 215 号 p. 215_C1-
- 214 号 p. 214_C1-
- 213 号 p. 213_C1-
- 212 号 p. 212_C1-
- 211 号 p. 211_C1-
- 210 号 p. 210_C1-
- 209 号 p. 209_C1-
- 208 号 p. 208_C1-
- 207 号 p. 207_C1-
- 206 号 p. 206_C1-
- 205 号 p. 205_C1-
- 204 号 p. 204_C1-
- 203 号 p. 203_C1-
- 202 号 p. 202_C1-
- 201 号 p. 201_C1-
- 200 号 p. 200_C1-
- 199 号 p. 199_C1-
- 198 号 p. 198_C1-
- 197 号 p. 197_C1-
- 196 号 p. 147-
- 195 号 p. 97-
- 194 号 p. 41-
- 193 号 p. 1-
M27 巻 (1894)
- 192 号 p. 192_C1-
- 191 号 p. 191_C1-
- 190 号 p. 190_C1-
- 189 号 p. 189_C1-
- 188 号 p. 188_C1-
- 187 号 p. 187_C1-
- 186 号 p. 186_C1-
- 185 号 p. 185_C1-
- 184 号 p. 184_C1-
- 183 号 p. 183_C1-
- 182 号 p. 182_C1-
- 181 号 p. 181_C1-
- 180 号 p. 180_C1-
- 179 号 p. 179_C1-
- 178 号 p. 178_C1-
- 177 号 p. 177_C1-
- 176 号 p. 176_C1-
- 175 号 p. 175_C1-
- 174 号 p. 174_C1-
- 173 号 p. 173_C1-
- 172 号 p. 155-
- 171 号 p. 105-
- 170 号 p. 53-
- 169 号 p. 1-
M26 巻 (1894)
- 168 号 p. 168_C1-
- 167 号 p. 167_C1-
- 166 号 p. 166_C1-
- 165 号 p. 165_C1-
- 164 号 p. 164_C1-
- 163 号 p. 163_C1-
- 162 号 p. 162_C1-
- 161 号 p. 161_C1-
- 160 号 p. 160_C1-
- 159 号 p. 159_C1-
- 158 号 p. 158_C1-
- 157 号 p. 157_C1-
- 156 号 p. 156_C1-
- 155 号 p. 155_C1-
- 154 号 p. 154_C1-
- 153 号 p. 153_C1-
- 152 号 p. 152_C1-
- 151 号 p. 151_C1-
- 150 号 p. 150_C1-
- 149 号 p. 149_C1-
- 148 号 p. 148_C1-
- 147 号 p. 103-
- 146 号 p. 51-
- 145 号 p. 1-
M25 巻 (1892)
- 144 号 p. 144_C1-
- 143 号 p. 143_C1-
- 142 号 p. 142_C1-
- 141 号 p. 1001-
- 140 号 p. 140_C1-
- 139 号 p. 139_C1-
- 138 号 p. 138_C1-
- 137 号 p. 137_C1-
- 136 号 p. 136_C1-
- 135 号 p. 135_C1-
- 134 号 p. 134_C1-
- 133 号 p. 133_C1-
- 132 号 p. 132_C1-
- 131 号 p. 131_C1-
- 130 号 p. 130_C1-
- 129 号 p. 129_C1-
- 128 号 p. 128_C1-
- 127 号 p. 127_C1-
- 126 号 p. 126_C1-
- 125 号 p. 125_C1-
- 124 号 p. 124_C1-
- 123 号 p. 101-
- 122 号 p. 51-
- 121 号 p. 1-
M24 巻 (1891)
- 120 号 p. 120_C1-
- 119 号 p. 119_C1-
- 118 号 p. 118_C1-
- 117 号 p. 117_C1-
- 116 号 p. 116_C1-
- 115 号 p. 115_C1-
- 114 号 p. 114_C1-
- 113 号 p. 113_C1-
- 112 号 p. 112_C1-
- 111 号 p. 111_C1-
- 110 号 p. 110_C1-
- 109 号 p. 109_C1-
- 108 号 p. 108_C1-
- 107 号 p. 107_C1-
- 106 号 p. 106_C1-
- 105 号 p. 105_C1-
- 104 号 p. 104_C1-
- 103 号 p. 103_C1-
- 102 号 p. 102_C1-
- 101 号 p. 101_C1-
- 100 号 p. 100_C1-
- 99 号 p. 89-
- 98 号 p. 47-
- 97 号 p. 2-
M23 巻 (1890)
- 96 号 p. 96_C1-
- 95 号 p. 95_C1-
- 94 号 p. 94_C1-
- 93 号 p. 93_C1-
- 92 号 p. 92_C1-
- 91 号 p. 91_C1-
- 90 号 p. 90_C1-
- 89 号 p. 89_C1-
- 88 号 p. 88_C1-
- 87 号 p. 87_C1-
- 86 号 p. 86_C1-
- 85 号 p. 85_C1-
- 84 号 p. 84_C1-
- 83 号 p. 83_C1-
- 82 号 p. 82_C1-
- 81 号 p. 81_C1-
- 80 号 p. 80_C1-
- 79 号 p. 79_C1-
- 78 号 p. 78_C1-
- 77 号 p. 77_C1-
- 76 号 p. 76_C1-
- 75 号 p. 75_C1-
- 74 号 p. 47-
- 73 号 p. 1-
M22 巻 (1889)
- 72 号 p. 72_C1-
- 71 号 p. 71_C1-
- 70 号 p. 70_C1-
- 69 号 p. 69_C1-
- 68 号 p. 68_C1-
- 67 号 p. 67_C1-
- 66 号 p. 66_C1-
- 65 号 p. 65_C1-
- 64 号 p. 64_C1-
- 63 号 p. 63_C1-
- 62 号 p. 62_C1-
- 61 号 p. 61_C1-
- 60 号 p. 60_C1-
- 59 号 p. 59_C1-
- 58 号 p. 58_C1-
- 57 号 p. 57_C1-
- 56 号 p. 56_C1-
- 55 号 p. 55_C1-
- 54 号 p. 54_C1-
- 53 号 p. 53_C1-
- 52 号 p. 52_C1-
- 51 号 p. 51_C1-
- 50 号 p. 49-
- 49 号 p. 1-
M21 巻 (1888)
- 48 号 p. 48_1-
- 47 号 p. 47_1-
- 46 号 p. 46_1-
- 45 号 p. 45_1-
- 44 号 p. 44_11-
- 43 号 p. 43_1-
- 42 号 p. 42_1-
- 41 号 p. 41_1-
- 40 号 p. 40_1-
- 39 号 p. 39_1-
- 38 号 p. 38_1-
- 37 号 p. 37_1-
- 36 号 p. 36_1-
- 35 号 p. 35_1-
- 34 号 p. 34_1-
- 33 号 p. 33_1-
- 32 号 p. 32_1-
- 31 号 p. 31_1-
- 30 号 p. 30_1-
- 29 号 p. 29_1-
- 28 号 p. 28_1-
- 27 号 p. 27_1-
- 26 号 p. 26_1-
- 25 号 p. 25_1-
M20 巻 (1887)
- 24 号 p. 24_1-
- 23 号 p. 23_1-
- 22 号 p. 22_1-
- 21 号 p. 21_1-
- 20 号 p. 20_1-
- 19 号 p. 19_1-
- 18 号 p. 18_1-
- 17 号 p. 17_1-
- 16 号 p. 16_1-
- 15 号 p. 15_1-
- 14 号 p. 14_1-
- 13 号 p. 13_1-
- 12 号 p. 12_2-
- 11 号 p. 11_13-
- 10 号 p. 10_12-
- 9 号 p. 9_11-
- 8 号 p. 8_11-
- 7 号 p. 7_11-
- 6 号 p. 6_10-
- 5 号 p. 5_11-
- 4 号 p. 4_10-
- 3 号 p. 3_10-
- 2 号 p. 2_10-
- 1 号 p. 1_15-
M19 巻 (1886)
- 39 号 p. 39_12-
- 38 号 p. 38_18-
- 37 号 p. 37_15-
- 36 号 p. 36_10-
- 35 号 p. 35_10-
- 34 号 p. 34_15-
- 33 号 p. 33_11-
- 32 号 p. 32_10-
- 31 号 p. 31_10-
- 30 号 p. 30_11-
- 29 号 p. 29_10-
- 28 号 p. 28_11-
- 27 号 p. 27_13-
- 26 号 p. 26_11-
- 25 号 p. 25_10-
- 24 号 p. 24_12-
- 23 号 p. 23_11-
- 22 号 p. 22_12-
- 21 号 p. 21_12-
- 20 号 p. 20_12-
- 19 号 p. 19_11-
- 18 号 p. 18_12-
54 巻, 3 号
選択された号の論文の24件中1~24を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
Contents
-
2008 年54 巻3 号 p. C5403_2
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (139K)
目次
-
2008 年54 巻3 号 p. C5403_1
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (138K)
特集 医学研究のUP-TO-DATE
-
--オートファジーのレビューに替えて--古谷 剛2008 年54 巻3 号 p. 282-286
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー人生の多くの部分は, 必要がなくなったものを捨てることに費やされる. 細胞も同様に, 合成と分解のバランスを保ちながら, 多様な外界の変化に柔軟に対応するために, 必要に応じて細胞内の自分自身の構成成分を『リサイクルする仕組み (システム) 』を持っている. このシステムを“オートファジー (自食作用) ”と呼び, 高等真核生物ではリソソームが, 酵母では液胞 (vacuole) が, 最終的なタンパク質分解の場となる. 近年, 様々な分野においてオートファジーの関与が報告されている. 私は, 2005年5月から2007年12月まで米国ハーバード医科大学細胞生物学教室Junying Yuan教授の所に留学した. 今回は, そのデータを簡単に紹介するとともにオートファジーの概説を試みたい.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1177K) -
後輩と自分自身のレベルアップを目指して大熊 泰之2008 年54 巻3 号 p. 287-293
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー平成12年に順天堂大学医学部附属静岡病院に赴任してからの約8年間において, 3-6ヵ月ごとにローテーションしてくる脳神経内科専門研修医30名に指導を行った成果を報告する. 具体的には, 30名全員が日本神経学会関東地方会に演題を発表し, それを確実に論文としてまとめてきた. 臨床研究の一環として症例報告を出し続けることは, 専門研修医と指導医双方に大きなメリットがあり, この地道な. 活動を長年繰り返していくことでStaff and Faculty Developmentが自然と成されていくと考える.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1440K) -
海老原 伸行2008 年54 巻3 号 p. 294-298
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーヒト角膜実質細胞の5-7%は骨髄由来で, 実質浅層に常在する. 骨髄由来実質細胞にはToll-Like受容体4 (TLR4) が発現しており, 上皮層を破壊し侵入してきた微生物に対する初期感染防御 (innate immunity) のfirst stepとして働く. 一方, 神経提由来実質細胞は角膜筋原線維芽細胞へ形質転換する事でTLR3・9を発現する. そして微生物刺激に対しIL-6, IL-8, GRO, ENA-78, RANTESなどのケモカイン産生や, 貧食能の亢進を示し, 初期感染防御のsecond stepとして働く. また, 骨髄由来実質細胞は角膜上皮細胞や神経提由来実質細胞の産生するMCP-1によって骨髄より角膜局所へ遊走し定着する. ヒト角膜実質細胞は角膜初期感染防御機構において重要な役割を演じている.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1434K) -
--内視鏡的治療による根治をめざして--長野 正裕, 結城 豊彦2008 年54 巻3 号 p. 299-307
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー2006年第3版『消化器内視鏡ガイドライン』 (日本消化器内視鏡学会監修) によれば, 食道癌の内視鏡的切除 (EMR) の絶対的適応病変は, 「深達度m1 (上皮内癌) ・m2 (粘膜固有層癌), 腫瘍径3cm未満」となっている. そこでEMR (Endoscopic Mucosal Resection), ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) の適応となるm1癌m2癌を拾い上げるため, 通常観察においての留意点, 積極的なヨード撒布 (ルゴール撒布) 施行, 生検での注意点などにつき言及した. 最近のトピックのひとつにNBI (Narrow Band Imaging) がある. これは, 内視鏡観察光の分光特性を変更することで, 粘膜表面の血管や粘膜微細模様の強調表示を行う光学的画像強調技術のことで, 粘膜表層の毛細血管像の強調表示や, 粘膜表面の微細模様 (いわゆるピットパターン) の強調表示が可能である. 食道観察においても有用であり, これを利用すればさらに小病変の拾い上げが可能であり, ヨード撒布, 生検病理診断を省略して治療に移行できる可能性がある. 早期食道癌さらには中・下咽頭表在癌の拾い上げに大いに期待できる検査法である.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (27420K)
原著
-
高血圧ラット心臓のニトロ化ストレスに及ぼす影響古川 覚, 木村 博子, 向田 政博, 山倉 文幸, 神野 宏司, 池田 啓一2008 年54 巻3 号 p. 308-317
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーKEIICHI IKEDA目的: 本研究は, 高血圧を発症した自然発症高血圧ラット (SHR) に10週間の持久的運動トレーニングを行わせ, 同週齢のSHRと心臓の3-ニトロチロシン (3-NT) 濃度, スーパーオキシドジスムターゼ (SOD) および一酸化窒素合成酵素 (NOS) の酵素量および活性を比較することにより, SHR心臓のニトロ化ストレスに及ぼす持久的運動トレーニングの効果を検討することを目的とした. 対象および方法: 15週齢のオスSHR20匹を, コントロール群 (25wk Cont群) および持久的運動トレーニング群 (25wk Ex群) に10匹ずつ分けた. 25wk Ex群には飼育ケージに取り付けられたカウンター付き回転ホイールにおける自発走トレーニングを10週間行わせた. 持久的運動トレーニング期間終了後, 両群のラットの心臓懸濁液を分画し3-NTの検出, Mn-SODおよびCu, Zn-SODの酵素量および活性の測定, さらに血管内皮型NOS (eNOS) 酵素量の測定を行った. また, 免疫組織染色により心組織の3-NT染色を行った. 結果: 持久的運動トレーニングはSHRの安静時収縮期血圧の上昇を抑制しなかった. しかしながら, 持久的運動トレーニングを行った25wk Ex群は25wk Cont群よりもミトコンドリア, 小胞体および原形質膜を含む顆粒画分の3-NT濃度が有意に低く持久的運動トレーニングが心臓のニトロ化を抑制していることを示していた. この変化は心臓の免疫組織染色においても確認することができた. また, 25wk Ex群のMn-SOD量は25wk Cont群よりも増加しており持久的運動トレーニングの効果が観察された. 結論: SHRの高血圧発症後の10週間の持久的運動トレーニングは心臓におけるMn-SODを増加させ, 心臓のニトロ化ストレスを軽減することが明らかになった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2142K) -
-日本透析医学会の統計調査との比較を中心に-船曳 和彦, 岡崎 圭子, 仲本 宙高, 有賀 誠記, 相澤 昌史, 金子 松五, 蒔田 雄一郎, 堀越 哲, 富野 康日己2008 年54 巻3 号 p. 318-323
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 順天堂東京江東高齢者医療センターは2002年6月1日に開院し, 質と安全度の高い先端的な高齢者医療を提供してきた. 開院後5年間における血液浄化室にて施行した血液透析患者について解析し, 今後の高齢者に対する透析療法に活かすため, わが国全体の慢性透析療法の現況と比較検討した. 対象・方法: 2002年6月より2007年5月までの5年間に, 当センター血液浄化室にて透析療法を施行された慢性維持血液透析入院患者および維持血液透析療法に導入された入院患者計431名 (男性265名, 女性166名) を対象とした. 対象患者を1年毎に性別, 平均年齢, 新規血液透析導入患者数を統計学的に評価するとともに, 新規血液透析導入患者の原疾患および入院中の死亡原因について調査し, 日本透析医学会の統計調査と比較検討を行った. 結果: 毎年透析患者数は増加傾向で開業時と比較して直近で約3倍となっていた. 5年間の平均年齢は, 70.8歳 (男性69.4歳, 女性73.4歳) であった. また, 5年間で計89名 (男性61名, 女性28名) が新規導入され, 平均年齢は71.6歳 (男性66.7歳, 女性76.4歳) であった. 患者の原疾患は, 糖尿病性腎症46名 (51.7%), 腎硬化症17名 (19.1%), 慢性糸球体腎炎7名 (7.9%) であった. 当センター入院中に46名が死亡し, 原因として感染症が最も多く (14名), 死亡患者全体の30.4%を占めていた. 悪液質/尿毒症により死亡した5名の入院時平均血清アルブミン値は, 2.4g/dlと低下していた. 結論: 当センター血液浄化室にて透析療法を施行された患者は増加傾向であり, 2006年6月からの1年間では平均年齢73.6歳と全国と比較して7.2歳高齢であった. 原疾患も糖尿病性腎症が半数以上を占め, 急速進行性糸球体腎炎の比率も高いことは高齢化に起因すると思われる. 死亡原因としては感染症が最も多く, 患者の高齢化や糖尿病患者の割合が多く免疫不全により誤嚥性肺炎や敗血症に罹患しやすいためと考えられた. 悪液質/尿毒症による死亡者は全例が高齢で長期透析患者であり, 低アルブミン血症を伴っていたことから当センター入院中の高齢長期透析患者に対する適切な栄養管理および透析効率の確保が一層必要と思われる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1095K) -
斎藤 淑子, 内藤 俊夫, 斎田 瑞恵, 池田 啓浩, 杉原 栄一郎, 福田 洋, 礒沼 弘, 林田 康男2008 年54 巻3 号 p. 324-327
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー背景: サイトメガロウィルス (CMV) はヒト免疫不全ウィルス (HIV) 感染者の日和見感染症の原因として重要視されている. しかし日本国内でのHIV感染者の抗CMV抗体陽性率を検討した報告は認められない. 対象と方法: HIV感染者72名の血清抗CMV-IgG抗体を測定し結果を比較検討した. 対象は全て日本人成人であり, 血友病患者やAcquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) 症例は含まれていない. 抗CMV-IgG抗体価の測定法は酵素抗体法 (ELISA) を用いた. 結果: HIV感染者の血清抗CMV-IgG抗体の陽性率は86.1%であり, コントロール群である非感染者の81.7%に対し高率であった. またHIV感染者間で比較すると, 陽性率は同性間性交渉経験のある若年男性で最も高い数価を示した. 結論: 性感染症罹患のリスクが高いと考えられる若年の同性間性交渉の嗜好を持つ男性は抗CMV抗体の陽性率が高かった. 同性愛および両性愛者の若年男性はHIVのみでなくCMV感染についても考慮する必要があると考えられる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (612K) -
網中 眞由美, 桑原 京子, 奥住 捷子, 佐藤 成大, 藤田 直久, 東出 正人, 平松 啓一2008 年54 巻3 号 p. 328-336
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 1999年および2005年-2006年に日本の臨床で分離されたメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) の薬剤感受性と, 近年世界中で注目されているバンコマイシンヘテロ耐性MRSA (hetero-VISA) について, それらの動向を調査した. 対象: 日本国内で分離されたMRSA, 1999年分離株138株および2005年-2006年分離株477株. 方法: 薬剤感受性測定はClinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 法に準じた寒天平板法で行った. hetero-VISAの検出は, バンコマイシンを4μg/ml含有したBrain Heart Infusion agarを使ったone-population analysisによってスクリーニングを行い, population analysisによって判定した. 結果: 10薬剤に対する薬剤感受性は1999年の調査時と変化を認めなかったが, アルベカシンに対する耐性率が有意に改善されていた (p=0.003). hetero-VISAは, 1999年分離株では5.1%の割合で検出されたが, 2005年-2006年分離株では0.6%で, 経年的に減少していることが明らかとなった. 結論: hetero-VISA検出数の経年的減少の要因として, 臨床における治療薬濃度モニタリング (TDM) を活用した症例ごとのバンコマイシン投与量および投与期間の適正化への取り組みが積極的に行われるようになっていることのほかに, 本邦における1991年以前のMRSA感染症治療で, β-ラクタム系薬が頻用されたことが関与した可能性が推測された. hetero-VISAの継続的なモニタリングは, MRSAのバンコマイシン耐性化を監視する指標として有用であるため, 今後はより簡易で精度の高い臨床検査室で実施可能な手法を開発していくことが課題である.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1303K) -
児玉 史子, 大澤 勲, 山路 研二, 稲見 裕子, 大井 洋之, 堀越 哲, 富野 康日己2008 年54 巻3 号 p. 337-343
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: IgA腎症例の血清IgA/C3比の時間経過による変化を検討する. 対象: 当院当科で実施した腎生検でIgA腎症と診断され, その後平均6.82年の経過を追えた81症例. 方法: 診断時およびその後の血清IgA/C3比の変動と臨床データ (尿所見, 組織所見, 血清Cr値, eGFR) およびステロイド使用の有無別での血清IgA/C3比の解析を行った. 結果: 血清IgA/C3比の平均値は, 診断時4.33±1.67から観察終了時3.32±0.97へと低下 (p<0.0001), 血清IgAは367.89±129.03mg/dlから328.69±100.36mg/d1へと低下し (p<0.0001), 血清C3は88.27±18.57mg/dlから100.14±16.69mg/dlへと上昇した (p<0.0001). 組織所見別, 尿所見別, ステロイド治療の有無別では, どの群においても時間経過後血清IgA/C3比は有意に低下したが, いずれも3.01以上を示した. 同時に, 血清IgAは有意に低下し血清C3は有意に上昇した. 但し, 経過中血清Cr値が30%以上上昇した腎機能悪化群では, 血清C3は上昇することなく, 腎機能不変群に比し低値を示した (p=0.0207). 結論: IgA腎症において, 発症初期の血清IgA産生亢進の状態は何らかの理由で時間の経過と共に低下すると考えられる. また, 腎機能が悪化する症例ではC3消費が強い可能性が示唆された. 血清IgA/C3比は, 年余の経過を経た時期でも3.01以上を示しており, 腎生検前診断に有効と考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1001K) -
-介護保険制度開始時と現在の比較-助友 裕子, 山路 義生, 池田 若葉, 黒沢 美智子, 稲葉 裕2008 年54 巻3 号 p. 344-351
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 介護保険制度導入開始時と現在におけるパーキンソン病患者の保健・医療・福祉サービスの利用状況とその変化を明らかにする. 方法: 2000年データは, 全国パーキンソン病友の会会員5513名を対象に行われた無記名の自記式質問紙調査より, 2007年データは, 同会の協力支部会員3500名を対象に行われた同調査より, 属性, 要介護度, サービス利用状況などの情報を収集した. 解析は, 男女ごとに2000年と2007年回答群の2群間比較 (t検定・χ2検定) を行った. 結果: 有効回答数は2000年が3459名 (62.7%), 2007年が1813名 (52.0%) であった. 要介護認定申請者は男女共に2007年回答群が有意に多い傾向が見られた. 利用サービスで有意な増加が認められたのは, 男女共にリハビリテーション, 加えて女性では訪問介護であり, 有意な減少が認められたのは, 男女共に訪問歯科診療, 入浴サービス, デイサービス, ショートステイであった. 一方, 利用中止サービスは, 男女共にリハビリテーションが有意に増加し, 有意な減少が見られたのは男女共に入浴サービス, 加えて男性では訪問診療, 訪問歯科診療, ショートステイであった. サービスに関する情報源は, 2000年と2007年男女共に主治医が中心であるが, 男女共友の会を通じた情報を入手する傾向にある. 介護保険導入開始時と比較して生活しやすくなったと回答した者は, 男性で2000年より2007年が有意に多かった. 結論: 介護保険の利用者は導入開始時より増加し, 男性は施設型, 女性は在宅型サービスを中心に利用する傾向がある. その中で, 事業体のサービス内容は利用者のニーズを満たしていないことが危惧される. 今後は, 多様な社会資源を通じてサービスの情報提供がなされるべきである.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1156K) -
--外来領域におけるトリアージプラン--伊藤 昭, 崎村 雄一, 森本 正一, 網中 眞由美, 堀 賢, 平松 啓一2008 年54 巻3 号 p. 352-357
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーインフルエンザから地球規模で瞬時に拡大するような未知の感染症に至るまで, 感染症に対する病院での万全を期した備えの必要性はますます高くなっている. 特に外来領域は, 病院に対して外部からの感染因子が持ち込まれる入口であることから, 感染症疑い患者に対する迅速なトリアージによる振り分け, 感染制御に配慮した環境作りが求められる. ここでは, 順天堂医院の医師, 看護師を対象にアンケート調査を行い, 外来領域の使用実態, 建築空間の感じ方, 感染制御に対する考え方, 環境・設備機能の改善点を抽出した. 診察室や処置室において感染対策上で問題を感じていること, 外来初診患者の適切な振り分けによる待ち時間の短縮を図ること, 感染症患者専用の診察待合や隔離スペースが必要との回答が得られた. また, 国内・海外の従来事例の比較検討においては, ある程度の隔離スペースを保持するものの, 動線の区分や感染症発生時期以外に有効に運用されているかどうかなどについて不明瞭なケースも多いことが分かった. このような結果から, 感染制御に配慮した外来領域の計画や建設, 環境整備が必要と考えて, 感染制御に最適なトリアージモデルプランを提案する. 通常時から感染症発生時, さらに大流行時といったフェーズ毎にフレキシブルに運用可能な診察ユニットを配置し, 清潔・汚染区域や人・物の動線分離を明確に設定, 感染制御に適した建築・設備面の仕様を示す. 本トリアージプランを実践することは, 機能性, フレキシビリティー, 省スペースといったデザイン上のコンセプトをかたちにするのみでなく, 病院建築において常時, 効率的な運用を図るという観点からも重要であると考えられる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1474K)
第21回都民公開講座《関節痛とつきあう》
-
鎌田 孝一2008 年54 巻3 号 p. 359-362
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (1226K) -
米澤 郁穂2008 年54 巻3 号 p. 363-366
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー腰痛の原因となる疾患は, ぎっくり腰, 椎間板ヘルニア, すべり症, 脊柱管狭窄症, 内臓疾患などいくつも存在する. そのため, 治療にあたっては, 正確な診断が不可欠である. 治療の中心は安静, 消炎鎮痛剤の内服, ブロック治療などの保存的治療であるが, 最近は運動療法の有効性も明らかになりつつある.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (767K) -
池田 浩2008 年54 巻3 号 p. 367-371
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー変形性膝関節症 (膝OA) のような運動器疾患では疼痛などによりADLが低下すると廃用性の萎縮が起こり, さらにADLが低下するという悪循環に陥るため, 治療においては疼痛に対するアプローチと伴にADLを向上させるためのアプローチが必要となる. 薬物療法や物理療法は受動的治療法であり直接的に廃用性の萎縮を改善させる効果はなく, ADLの向上という面からみると運動療法よりは劣る. したがって, ADLへの影響を踏まえて治療法を選択する場合, 運動療法を主たる治療法として捉えるべきである.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1029K) -
中村 洋2008 年54 巻3 号 p. 372-376
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー中高年にみられる関節痛のもっとも多い原因が変形性関節症osteoarthritis (OA) である. 保存的治療として, 安静, 保温, 運動療法に加えて, 薬物治療が行われる. アセトアミノフェンは容易に購入できる鎮痛薬で, 本邦では一日1.5gまで使われる. 痛みが強い場合は非ステロイド性消炎鎮痛薬nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) であるインドメタシン, ジクロフェナック, ロキソプロフェンといった薬を使用するが, 上部消化管障害などの副作用に注意が必要である. これらの薬剤はシクロオキシゲナーゼcyclooxigenase (COX) を抑えることによって, 痛みや炎症の原因となるプロスタグランディンE2 (PGE2) の産生を抑制して効果を発揮する. 近年, 胃腸障害を軽減するため, COX-2選択的阻害薬が使われるようになってきた. 関節内へ薬剤を直接注入する治療法も医療機関では行われている. ステロイド剤は即効性があり, 効果も劇的であるが, 副作用を避けるため頻回に用いないほうがよい. ヒアルロン酸はその物理的性質と抗炎症作用により, OAの症状を軽減するとされている. 副作用が少なく, 定期的に注入して効果をあげている. 現在販売されているサプリメントにはさまざまな種類があるが, グルコサミンはその作用が科学的に議論されている唯一の物質である. グルコサミンのOA治療への歴史は1960年代のドイツにさかのぼる. その後, 1990年代後半から北アメリカで大ブームを巻き起こし, いくつもの臨床治験が行われた. 有効性を示す研究結果があるが, 否定的な意見もある. 一方, グルコサミンの基礎的研究は盛んに行われており, 抗炎症作用, 軟骨分解酵素の抑制作用が明らかにされ, OAの症状を軽減するだけでなく, 進行を抑制する可能性が強く示唆されている.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (916K)
症例報告
-
斎田 瑞恵, 内藤 俊夫, 松元 直美, 大嶋 弘子, 礒沼 弘, 檀原 高, 薪田 も恵, 竹田 省, 久田 研2008 年54 巻3 号 p. 377-381
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー本邦では若年女性のヒト免疫不全ウイルスHuman Immunodeficiency Virus (HIV) 感染者が増加しており, HIV母子感染予防が大きな問題となっている. 順天堂医院が初めてHIV感染女性の母子感染予防に携わったので報告する. 症例: 40歳女性, 妊娠14週から抗HIV療法を開始し出産後2ヵ月まで継続した. 考察: 専門的知識と適切な対応でHIV母子感染の予防は可能である. HIV母子感染予防の症例は今後増えると予想されるため, 症例を重ね検討を加えていきたい.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (734K) -
正木 克由規, 島田 和典, 久米 淳美, 西谷 美帆, 深尾 宏祐, 高木 篤俊, 比企 誠, 鬼柳 尚, 大村 寛敏, 代田 浩之2008 年54 巻3 号 p. 382-386
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー今回, われわれは, 従来の保存的治療では改善が困難な重症慢性心不全に対し, 和温療法の併用により退院可能となった2症例を経験した. 和温療法は, 深部体温を1.0-1.2℃上昇させることで血管内皮機能を改善し, 慢性心不全の病態を改善させた. この和温療法は, 従来の治療と併用可能であり, 重症心不全に積極的に行う価値があると考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1341K)
抄録
-
2008 年54 巻3 号 p. 387-395
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (1947K) -
2008 年54 巻3 号 p. 396-419
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (5242K)
順天堂医学原著論文投稿ガイドライン
-
2008 年54 巻3 号 p. 429
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (243K)
順天堂医学投稿規程
-
2008 年54 巻3 号 p. 430
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (276K)
編集後記
-
黒田 博之2008 年54 巻3 号 p. 431
発行日: 2008/09/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (255K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|