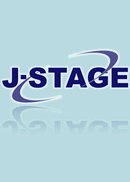統語に関する第二言語習得は, 少なくともその初期段階において, 母語のパラメター値を転移して行われると主張されてきた (Schwartz, 1998a & b;Schwartz & Sprouse, 1994, 1996;Tsimpli & Smith, 1991;Tsimpli & Roussou, 1991).母語転移のメカニズムに関して, Tsimpli & Roussouらは, 以下のように説明している : 母語転移とは、母語の素性を第二言語の形態音素にマッピングすること, すなわち第二言語のインプットを “誤って分析する” ことである.本研究は, 日本語話者による英語の義務的主語 (指示的名詞, 仮主語の
'it'と
'there') の習得を例にとって, 以上の仮説を考察し, “誤分析” 説にさらなる支持を与えることを目標とする.Chomsky (1995) が提案した理論枠組みによれば, 日英語の主語の違いは帰属する素性の特性によって説明づけられるということである.日本語の時制文では空主語が可能であるが, 英語ではそれが不可能である.これは機能範疇Tに帰属するD素性が原因となっている.英語のD素性は強く, 日本語のそれは弱い (Wakabayashi, 1997, 2002;cf. Yatsushiro 1999).しかし, このパラメターの違いは日本人英語学習者によって簡単に克服されるという報告がされている (Hirakawa, 2003;Wakabayashi, 1997, 2002;Wakabayashi & Negishi, 2003;Zob1, 1990).本研究は, 日英中間言語の中の動詞直前に位置する名詞句が, 英語でいう主語に当たるものなのかどうかを調査し, 以上の報告の正当性を吟味する.そして, 実験データを基に, 英語習熟度初・中級の学習者が英語の「主語-動詞」構造を「話題-空主語-動詞」と取り違える一方、述語の前には顕在的な句が必要であることを知っていることを示す (Kuribara, 2000, 2003).文法性判断テストを初級から中 (の上) 級に相当する学習者に実施した.このテストには, 2タイプの構文が含まれ, 1つは空主語が構造的に異なる環境に位置する文で, もう1つは「名詞話題句-主語」構造を持つ文である.データ分析の結果として, 学習者は, 動詞が主要部範疇の後に来る空主語節よりも名詞句のような句範疇の後に来る空主語節を著しく容認することが分かった.「名詞話題句-主語」構造については, 初・中級学習者の大多数が話題句が0標示されているか否か, 主語が顕在的か否かにかかわらず全ての構文を受け入れた.これらの結果は, 明らかに英語のD素性値を習得していないということを示す.学習者が習得したのは, むしろ, 英語は動詞の前に (日本語の意味での) 話題および/又は主語を生成し, それ (らのうちの一つ) はいつも形態音素を必要とする, ということの二点である (cf.Hawkins, 2001;Kuribara, 2000, 2003).
抄録全体を表示