巻号一覧
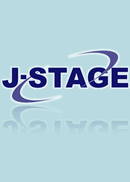
13 巻 (1999)
- 4 号 p. 301-
- 3 号 p. 139-
- 2 号 p. 81-
- 1 号 p. 21-
13 巻, 1 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
堀口 実, 岩渕 正之, 川端 啓介1999 年 13 巻 1 号 p. 21-31
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー症例は75歳女性で,肝機能異常を指摘されて入院.術前の直接胆道造影で上部胆管癌と診断され,1991年6月10日根治術を行った.切除標本の病理組織学的検討で胆嚢原発の高分化型扁平上皮癌と判明し,それが胆管に浸潤していた.胆嚢扁平上皮癌は稀なので,1970年以降の本邦での切除例28例を文献的およびアンケート調査を行って検討した.その結果,肝十二指腸靱帯を除く局所直接浸潤傾向が強く,腹膜播種や血行性転移が少ないことなどが特徴的であった.扁平上皮癌の予後は,他の胆嚢癌と比較した結果,仲々良好で,5生率46.2%を得,StageIVだけでも5生率31.3%を得た.また,StageIVaとIVbを比較するとIVaが有意に良好であり,治癒,非治癒切除別にみると非治癒切除例の5生率,12.5%に比し,治癒切除例の5生率,87.5%は有意に良好であった.さらに長期生存例も4例認めたことから,積極的切除および術後療法が望まれ,それによっては治療成積のさらなる向上も期待しうる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3032K) -
清水 潤三, 永野 浩昭, 左近 賢人, 堂野 恵三, 奥山 正樹, 武田 裕, 中森 正二, 梅下 浩司, 後藤 満一, 金 束石, 村上 ...1999 年 13 巻 1 号 p. 32-38
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリーExpandable metallic stent(EMS)を挿入した悪性胆道狭窄15例について,EMS挿入後の乳頭部開存の有無により2群にわけ(温存群8例,温存不能群7例),胆道感染,EMS挿入後の入院および在宅期間等について比較検討した.温存群ではEMS挿入後の胆管炎は全例に認めなかったが,温存不能群では7例中6例(85.7%)と高率に発症し,そのうち2例に肝膿瘍を合併した。胆汁細菌培養は温存群で1例(12.5%),温存不能群では全例(100%)陽性であった.入院期間にっいては両群問で差はなかったが,在宅期間は温存群の132.2日に比して,温存不能群で86.3日と短縮しており,特にEMS挿入後の在宅率は,温存不能群で有意に短縮していた。以上より,温存不能群では温存群に比べて,EMS挿入後高頻度に逆行性胆管炎を併発し,EMS挿入後のQuality of life(QOL)が低下していた.したがって,EMS挿入後に乳頭部が温存できなかった症例については,逆行性胆管炎に対する配慮の必要性が示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1909K) -
北川 雄一, 山口 晃弘, 磯谷 正敏, 堀 明洋, 金岡 祐次, 伊神 剛, 小田 高司1999 年 13 巻 1 号 p. 39-44
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー胆嚢摘出術施行例の胆嚢胆汁中総アミラーゼ値を測定し,アミラーゼ高値症例の臨床的特徴を検討した。最近11年間に題汁中アミラーゼ値を測定したのは1,983例で,うち総アミラーゼ値1,000IU/L以上の症例は158例であった.158例中73例は,胆管造影で胆管のみが描出された.残り85例中,総胆管結石35例と合流異常症8例,傍乳頭憩室3例は,高アミラーゼ胆汁の生じる可能性がある,病的総胆管と考えた.残り39例は,高アミラーゼ胆汁の存在に加え,胆管造影で膵管が描出されたため,潜在的に膵・胆管逆流が生じていると考えた.潜在的合流異常症例の胆嚢粘膜のmetaplasia,dysplasia,hyperplasiaは,それぞれ92.2%,14.6%,1.9%に認められた.胆嚢病理組織学的所見から,膵液逆流により胆嚢粘膜に変化が生じていると推察されたが,発癌との関係は明らかにできなかった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1958K) -
-当科の現況と問題点-川辺 昭浩, 桜町 俊二, 小林 利彦, 吉田 雅行, 竹内 豊, 木村 泰三1999 年 13 巻 1 号 p. 45-50
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー総胆管結石症に対する治療法は,開腹手術に加え腹腔鏡下手術,内視鏡治療(ESTやEPBD)などの普及により大きな変化がみられている。当科では,腹腔鏡下手術を第一選択とし,合併症を有する症例や全身状態不良例は,適宜開腹手術,内視鏡治療などを選択してきた.1992年1月より1998年8月までに経験した65症例を臨床学的に検討し,当科の現況と問題点について報告した.腹腔鏡下手術は48例で試みられ,43例(経胆嚢管法21例,、胆管切開法22例)で完遂し,重篤な術後合併症もなく良好な治療成績が得られた.腹腔鏡下手術は,乳頭機能を温存しつつ一期的に胆石総胆管結石を治療できる利点がある。特に経胆嚢管法は,適応は狭いが,手技的にも容易で理想的な手技と考えられた.しかし,合併症を有する症例やhigh risk症例に対しては,内視鏡治療や開腹手術を適宜選択するべきであると思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1353K) -
江川 直人, 屠 聿揚, 神澤 輝実, 鶴田 耕二, 岡本 篤武, 森山 佐知子, 小池 盛雄, 石垣 宏1999 年 13 巻 1 号 p. 51-54
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー高度胆管奇形と膵・胆管合流異常を合併した,きわめて稀な1例を経験したので報告した.症例は41歳男性.上腹部痛を契機にERCPにて胆管,膵管系の異常が発見された.総胆管は左右の肝管に至る前に2分岐し,太い一方に胆嚢管が合流し,胆嚢管の近傍に短く筆尖状に途絶する管状構造が認められた.また,木村分類I型(膵管合流型)の膵・胆管合流異常も合併しており,胆摘術,肝外胆管切除術,胆管空腸吻合術が行われた.術中所見より,筆尖状の管状構造は未発達の左副肝管と判明した.ERCPを参照すると,副肝管は胆嚢管とあたかも太い共通管を形成し,下方までのびており,久次の副肝管走向異常分類0型の鏡面対称型を成すものと考えられ,きわめて頻度の低いものである.一方,膵・胆管合流異常とは,発生学的にみて相互に関連性のない事象と考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1413K) -
坂東 正, 霜田 光義, 長田 拓哉, 塚田 一博1999 年 13 巻 1 号 p. 55-59
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー症例は33歳,女性.上腹部痛を主訴に受診した近医にて施行された腹部USで,嚢ポリープを指摘され,精査加療目的にて当科紹介入院となった.ERCPで胆は,胆管の拡張を伴わない膵管合流型の膵・胆管合流異常が認められた.腹部US,ERCP,CT,EUSにて,多発性胆嚢ポリープと診断し,胆嚢摘出術を施行した.切除標本の肉眼所見では,全体的にcholesterosisの所見で,最大径15mmのポリープが多数認められた、病理所見では,胆嚢粘膜は肥厚し,一層の円柱上皮に覆われて乳頭状に発育し,その内部には脂質を含んだ泡沫細胞が集簇していた.以上より,胆嚢papillomatous cholesterosisと診断した.胆嚢papillomatous cholesterosisの報告例は少なく,胆管非拡張型の膵・胆管合流異常に合併したものは極めて稀であり,示唆に富む症例と考え報告した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2395K) -
坂東 正, 霜田 光義, 長田 拓哉, 塚田 一博, 山岸 文範1999 年 13 巻 1 号 p. 60-64
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー腹腔鏡下胆嚢摘出術の術中胆道肝動脈同時損傷に対する,膠道再建術後吻合部狭窄の1例を経験した.症例は65歳,女性.某病院で,胆嚢結石症の診断で,腹腔鏡下胆嚢摘出術が行われたが,術中胆道損傷を来し,総肝管空腸吻合による胆道再建術が施行された.術後約1年胆管炎を繰り返し,当院入院となった.胆道造影にて吻合部狭窄が認められ,PTCDを用いた内瘻化および狭窄部の拡張を約4カ月行ったが狭窄は改善せず,再手術を施行した.血管造影で,右肝動脈の離断所見が認められた.吻合部胆管壁は硬化肥厚していたため,狭窄部切除と再吻合を施行した.術後1年半経過したが,経過は良好である.腹腔鏡下胆嚢摘出術時の偶発症に対する処置は,重複する合併症に注意し,血管損傷合併時には,術後狭窄が発生する可能性があり,残存肝管をできるだけ短くし,できるだけ大きめの吻合口での胆道再建が必要であると思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2010K) -
久保田 香, 遠藤 格, 瀧本 篤, 森脇 義弘, 藤井 義郎, 渡会 伸治, 嶋田 紘, 國広 理, 稲山 嘉明, 加藤 弘1999 年 13 巻 1 号 p. 65-70
発行日: 1999/02/25
公開日: 2012/11/13
ジャーナル フリー症例は66歳女性.褐色尿と黄疸を主訴に近医を受診したところ,肝門部腫瘤指摘され,精査目的で当科入院となった.ERCPでは,総肝管に腹側からの圧排像を認めた.CTおよびEUSでは,総肝管に接して長径1.5cmの腫瘤を認め,悪性疾患の12cリンパ節転移または悪性リンパ腫と診断した.腫瘍マーカーの上昇がみられ,閉塞性黄疸を来したことから,開腹術を施行した.術中所見では,胆嚢管と総肝管の間に直径2cmの弾性硬の腫瘤を認めたため,胆嚢とともに摘除した.組織学的にはリンパ球を主体とする炎症性細胞の著明な浸潤を認めたが,明らかなリンパ濾胞の形成はなく,inflammatory pseudotumorと診断された.黄疸を来したinflammatory pseudoturmorの報告例は,本例が6例目であった。閉塞性黄疸を来す肝門部腫瘤の鑑別診断として,本疾患を念頭におくべきと思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2850K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|