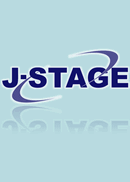-
浮田 雄生, 多田 知子, 池田 真幸, 新後閑 弘章, 遠藤 琢朗, 大牟田 繁文, 前谷 容
2007 年 21 巻 5 号 p.
617-622
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
ERCP後膵炎の危険因子について従来欧米で報告されている因子にERCP施行時間,深部挿管までの時間を加えて検討した.
対象は2003年8月から2006年5月までにERCPを施行したうち,いわゆる新鮮乳頭の629例,平均年齢65.5歳,男女比1.4:1.0,全体での発症率は4.1%であった.これを,膵炎を発症した群(発症群)と発症しなかった群(非発症群)に分けて検討した.
年齢,男女比,総胆管径,主膵管径には差がなかった.施行時間は47.5分,29.4分と発症群で有意に長かった.深部挿管するまでの時間は17.4分,8.7分と発症群で長かったが有意差はなかった.膵管造影率は85.2%,36.5%と発症群で有意に高かった.
施行時間と膵管造影の有無がERCP後膵炎の危険因子として示された.
抄録全体を表示
-
岡野 直樹, 五十嵐 良典, 三浦 富宏, 三木 一正
2007 年 21 巻 5 号 p.
623-629
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
背景: 十二指腸乳頭部腫瘍に対し完全生検や治療目的で内視鏡的乳頭切除術が行われているが,まだ胃や大腸のように確立した手技とはなっていない.今回我々の施設で施行した内視鏡的乳頭切除術症例の早期合併症を検討し,安全性について評価した.
方法:対象は2002年10月から2007年4月までに内視鏡的乳頭切除術を施行した20例で男女比は11:9,平均年齢は68.9±11.8歳(34~89歳)である.術後に可能な限り胆管および膵管へのドレナージ術を施行した.
結果:全例一括切除可能で,早期合併症としては6例に出血を認めたが内視鏡的に止血可能だった. 輸血を必要とする例はなかった. 3 例に膵炎, 1 例に胆管炎の合併を認めたがいずれも保存的に軽快した. 穿孔はなく致死的な合併症もなかった.
結論:内視鏡的乳頭切除術は,診断および術前後の管理を十分に行えば安全に施行することが可能である.
抄録全体を表示
-
信岡 隆幸, 木村 康利, 大野 敬祐, 西舘 敏彦, 秋月 恵美, 水口 徹, 向谷 充宏, 平田 公一
2007 年 21 巻 5 号 p.
630-636
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
教室で経験した漿膜下層(ss)浸潤胆嚢癌(以下ss胆嚢癌)44症例について解析し,術式の在り方について検討した. 5生率は50. 2%であった. 肝切除付加群で有意に予後が良好であったが,肝切除範囲の多少では有意差を認めなかった.膵頭十二指腸切除術(以下PD)群の3生率は83.3%と良好であったが,胆管切除群との間に有意差は無かった.郭清度D1以下群に比しD2以上群で予後は有意に良好で,とくに頸部,胆嚢管癌でその意義が伺われる傾向にあった.
予防的系統的肝切除, 予防的リンパ節郭清としての胆管切除・PD付加の意義は不明瞭であった.D2以上のリンパ節郭清と肝切除を伴う根治的手術がss胆嚢癌の至適術式と考えられた.
抄録全体を表示
-
三上 繁, 鈴木 功一, 清水 史郎, 秋本 政秀
2007 年 21 巻 5 号 p.
637-641
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
内視鏡的乳頭バルーン拡張術による総胆管結石治療後5年以上経過した症例の長期予後について検討した.対象101例の観察期間は87.3±26.5カ月(平均7.3年)で,早期の合併症としては膵炎が2例(2.0%)認められたのみであった.後期の合併症としては,胆管結石の再発を5例(5.0%)に認め,再発までの期間は3~28カ月であった.また,5例中4例が胆嚢からの落下結石と考えられた.胆嚢炎の発症は認められなかった.画像検査において胆管気腫像が認められた症例もなかった.死亡例は4例で,死因は膵癌,肝内胆管癌,肝不全,心筋梗塞で,死亡までの期間は25~34カ月であった.有石胆嚢を温存した場合は胆嚢結石の再落下が問題となるため,可能ならEPBD後に胆嚢摘出術を施行すべきであるが,一方EPBD後は胆嚢炎の発症頻度が少なく,胆嚢摘出術のハイリスク症例における総胆管結石治療の第一選択と考えられた.
抄録全体を表示
-
滝川 一
2007 年 21 巻 5 号 p.
642-646
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
原発性硬化性胆管炎(primary sclerosing cholangitis; PSC)は肝内外の胆管の線維性狭窄を生じる進行性の慢性炎症疾患であり,自己免疫の関与が示唆されているが詳細は不明である.これまでの全国調査で,わが国のPSC患者の年齢分布には2つのピークが存在し,若年者には炎症性腸疾患(inflammatory bowel disease; IBD)を合併した典型例が多いのに対し,高齢者のピークには自己免疫性膵炎(autoimmune pancreatitis; AIP)に伴う硬化性胆管炎が含まれていた.AIPに伴う硬化性胆管炎は規在ではPSCとは区別されている.近年,AIPに類似した膵病変を伴わない硬化性胆管炎の存在が知られるようになった.今後IgG4関連硬化性胆管炎とも呼ばれ,AIPと同じ範疇に含まれると考えられる疾患の実態を明らかにする必要がある.
抄録全体を表示
-
鎌田 英紀, 内田 尚仁, 小野 昌弘, 有友 雄一, 筒井 邦彦
2007 年 21 巻 5 号 p.
647-651
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
ダブルバルーン内視鏡(double balloon endoscopy; DBE)を用いて電気水圧衝撃波結石破砕術(Electrohydraulic lithotripsy; EHL)で治療し得た胆石イレウスを経験したので報告する.症例は70歳,女性.嘔吐を主訴に近医を受診し,上部消化管内視鏡検査にて十二指腸下行脚に直径約4cmの胆石の嵌頓が確認され,胆石イレウスと診断された.精査加療目的で当科紹介入院となった.腹部CT検査では,十二指腸水平脚に直径4cmほどの石灰化した胆石を認めた.内視鏡を用いたEHLによる砕石を試みた.初回は2チャンネルスコープを用いたが,治療後に胆石が空腸に移動したため,2回目以降はDBEを用いて治療を行った.計3回のEHLにより砕石でき1週間後の腹部CT検査でも胆石の残存はなかった.胆石イレウスに対しては外科的治療が行われることが多かったが,DBEを用いたEHLによる砕石術は有用な治療法と思われた.
抄録全体を表示
-
國枝 良行, 千々岩 一男, 近藤 千博, 内山 周一郎, 甲斐 真弘, 大内田 次郎, 旭吉 雅秀, 永野 元章, 片岡 寛章
2007 年 21 巻 5 号 p.
652-658
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
肝内胆管の限局性拡張を契機に根治切除した微小肝内胆管癌の1 例を経験したので報告する.症例は84歳女性.主訴なし.検診での腹部超音波検査で外側区域肝内胆管の限局性拡張を認め精査目的で当科を紹介された.血液生化学検査では異常なし.腹部CTでは肝内胆管B2の拡張を認め,その起始部は狭窄していたが腫瘤影は認めなかった.ERCPでB2根部狭窄部胆管の擦過細胞診を施行したがClass IIであった.腹部血管造影では肝動脈A2起始部に軽度のencasementを,CTAPでP2起始部の壁不整を認めた.術前検査では明らかな癌の存在は認めなかったが,肝内胆管癌の可能性が高いと診断し肝左葉切除術を施行した.病理組織診断では肝内胆管癌であり癌浸潤は胆管周囲グリソン鞘内に留まっていた.画像検査で限局した肝内胆管拡張を認める場合には肝内胆管癌の存在を念頭に置いて精査する必要性が示唆された.
抄録全体を表示
-
酒井 丈典, 古川 哲, 赤須 玄, 大塚 隆彦, 御鍵 和弘, 丸山 祐一郎, 川原 隆一, 酒井 久宗, 内田 信治, 堀内 彦之, 木 ...
2007 年 21 巻 5 号 p.
659-664
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
胆道系の分岐には様々な形態異常が知られており,副交通胆管枝もその1形態である.今回は布側肝管と胆嚢管を交通する副交通胆管枝の2例を経験したので報告する,症例1は68歳, 女性. 症例2は63歳, 男性. 両症例とも閉塞性黄疸にて紹介入院となった. PTBDの精査造影の際に,右肝管と胆嚢管を交通する副交通胆管枝の存在が判明した.症例1は進行胆管癌,症例2は膵頭部癌の診断で膵頭十二指腸切除術が施行された.両症例とも,副交通胆管枝は肝に単独の支配領域を有さず,右肝管に胆汁流出の障害となるような狭窄などが認められないことから,副交通胆管枝の処理は結紮切離のみで対応した.今回の副交通胆管枝は直接造影で発見されたが, MRCPやDIC-CTによる発見の報告も増加しており, 今後同検査の普及, 発展により,直接胆道造影を用いずとも胆道走行異常の詳細な検討が非侵襲的に行えるようになる可能性があると考えられる.
抄録全体を表示
-
筒井 邦彦, 内田 尚仁, 有友 雄一, 小野 昌弘, 鎌田 英紀
2007 年 21 巻 5 号 p.
665-669
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
重症急性膵炎にcholedochoceleを合併した症例を経験したので報告する.症例は70歳男性で,今まで特発性急性膵炎による入院歴が2回あった.今回も腹痛を主訴に近医受診し,急性膵炎の診断のもと当科紹介となった. 血液検査, 腹部C T 検査で厚生労働省急性膵炎重症度スコア9点の重症急性膵炎と診断した.一部に膵壊死の所見を認め,蛋白分解酵素阻害剤と抗生剤による持続動注療法を開始するとともに,ICU全身管理下に加療したところ順調に急性膵炎は改善した.明らかな胆石や高脂血症もなく,また,大酒家でもないため,原因検索の目的でERCPを施行した.Choledochoceleを認め,急性膵炎の原因と考えられ,内視鏡的乳頭括約筋切開術を施行した. その後約4 年問経過を追っているが, 急性膵炎の再発は認めていない. 原因不明の重症急性膵炎の場合,その原因として本症も念頭に置く必要があると思われた.
抄録全体を表示
-
堤 康一郎, 河本 博文, 原田 亮, 藤井 雅邦, 中西 崇, 水野 修, 石田 悦嗣, 小川 恒由, 深津 裕寿, 坂口 孝作
2007 年 21 巻 5 号 p.
670-676
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
69歳男性.心窩部痛にて近医を受診し,急性膵炎と診断され,保存的加療にて速やかに改善した.腹部CT,MRCPにて主膵管拡張を認め,ERCPを試みるも深部挿管不能なため,当科入院となった.ERCP上,総胆管末端は7mm大に嚢状拡張し,Oddi括約筋を介した後に拡張膵管と総胆管が造影され,共通管に発生したcholedochoceleと診断した.総胆管結石も認めたため,Needle knifeによる切開にて嚢腫内腔を露出後,深部挿管可能となり,ESTおよびバルーン採石術を行った.術後1カ月の主乳頭には胆管口と膵管口の分離を確認した.また初回ERCP時の胆汁中アミラーゼ13930IU/
l高値で,膵液の胆管内逆流が示唆され,術後604IU/
lと低下した.後日腹腔鏡下胆嚢摘出術を行い,悪性所見なく経過良好である.Choledochoceleによる膵液および胆汁の相互逆流が急性膵炎, 胆石症の一因となったことが示唆された.
抄録全体を表示
-
牧野 勇, 谷 卓, 高村 博之, 中川原 寿俊, 田島 秀浩, 大西 一朗, 北川 裕久, 伏田 幸夫, 藤村 隆, 西村 元一, 萱原 ...
2007 年 21 巻 5 号 p.
677-684
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
症例は52歳の女性,褐色尿を主訴として来院した,画像診断にて肝門部に2つの嚢胞性病変を認め,一方は主に肝内側区域に存在し肝門部で左右のグリソン鞘を圧排する単房性嚢胞性病変で,他方はこの病変と接して肝外に突出し内部に壁在結節を伴う多房性嚢胞性病変であった.後者の病変は肝外胆管に接し,これを圧排しており,肝外胆管が狭窄を呈していた.拡大肝左葉切除,肝外胆管切除にて切除しえた.切除標本では肝内側区域に存在する単房性嚢胞性腫瘍と,これと連続して肝外に突出し総肝管を圧排する多房性嚢胞性腫瘍を認め,後者の嚢胞壁には乳頭状腫瘍が存在した.病理組織所見では2つの嚢胞性病変は一連の腫瘍と考えられ,現行の規約に従い胆管嚢胞腺癌と診断した.一方で,この嚢胞性腫瘍は標本造影で胆管との交通が証明され,組織学的に卵巣様間質を認めないことから,近年提唱されている胆管内乳頭状腫瘍に分類できると考えられた.
抄録全体を表示
-
伊佐山 浩通, 佐々木 隆, 中井 陽介, 外川 修, 川邊 隆夫, 戸田 信夫, 小俣 政男
2007 年 21 巻 5 号 p.
685-691
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
肝門部胆管癌に対する治療の基本は切除であり,本当に切除不能であるかどうかを真摯に検討することが重要である.現在の技術では根治の望める抗腫瘍療法は存在しないからである.非切除例に対する治療は胆道ドレナージと抗腫瘍療法の二本立てである.胆道ドレナージとしてはMetallic stentを片葉に留置した成績が良好で第一選択と考えられる.しかし,高いエビデンスではないので,今後も検討が必要である.抗腫瘍療法として局所進行例に対してはPDTの有効性が示されているが,放射線照射に関しては明確ではない.全身化学療法では標準治療が決まっていない.しかし,最近保険適応となったGEM,S-1の2剤の成績が良好あり,今後これらの薬剤を使用したレジメンから標準治療が決まってくるものと考えている.化学療法を安全かつ効果的に継続していくためにも,胆道合併症のマネージメントは非常に重要であることを再度強調したい.
抄録全体を表示
-
齋藤 博哉, 鉾立 博文, 武内 周平, 高邑 明夫
2007 年 21 巻 5 号 p.
692-701
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
肝門部胆管癌に対する非手術的治療として, 胆道ドレナージ術と抗腫瘍療法について概説した.内瘻術では,メタリックステント(MS)が開存率に優れ,さらにチューブステント(TS)では内瘻化が困難であった肝門部・肝内胆管閉塞にも応用され,患者のQOLの向上に大きく貢献してきた.MSの開存期間は抗腫瘍療法を施行することで延長されるため,内腔の局所制御を目的に放射線治療をはじめとした抗腫瘍療法が多くの施設で併用されるようになった.しかし,抗腫瘍療法により長期生存例が経験されるようになると,今度はMSによる後期合併症が問題となってきており,その適応に変化が見られるようになった.さらに併用療法の内容は化学療法の発達などにより変遷してきている.今後,抗腫瘍療法,ドレナージ法個々の確立と同時に,抗腫瘍療法に応じた最適な胆道ステンティングの組み合わせを検討する必要がある.
抄録全体を表示
-
二村 雄次
2007 年 21 巻 5 号 p.
702-708
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー
肝門部胆管を含めた肝の区域・亜区域の局所解剖の研究は1950年代に欧米で始まったが,その臨床的外科的局所解剖の研究の発展は日本の臨床家に負うところが大きい.肝門部胆管癌の診断体系はMDCTの登場により大きく変貌した.ステージングおよび手術法の立案はMDCTだけでも十分可能であるといっても過言ではない. 肝外胆管切除, 尾状葉切除を伴う肝切除が標準的な手術法になりつつあるが,黄疸肝の手術前治療のうちでは内視鏡的ドレナージか経皮経肝的ドレナージかの選択,減黄後の肝切除の時期,門脈塞栓術後の手術時期など,今後も明らかにしなければならない問題も多い.手術適応に関しても施設毎に基準が異なっていることも事実である.外科的切除が唯一の根治療法であることは周知の事実であるので,容易に非手術療法を選択するのではなく,あくまで切除の可能性を追求した後に切除不能の要因を明らかにし, セカンドオピニオンも十分に聞いた上で非切除療法の適応を再検討する必要があろう.外科的切除に伴う補助療法の有効性については未だ十分な臨床研究がされていないので,今後エビデンスレベルの高い研究成果を創出することが期待される.
抄録全体を表示
-
五十嵐 良典, 岡野 直樹, 三浦 富宏, 大久保 洋一郎, 渋谷 和俊
2007 年 21 巻 5 号 p.
709-712
発行日: 2007/12/31
公開日: 2012/11/13
ジャーナル
フリー