2023 Volume 1 Pages 87-90
2023 Volume 1 Pages 87-90
本年表(増補改訂版)を最初に手に取った時、驚いた。1,104頁もある総合大年表ではないか。本年表は、「ボランティア・NPO・市民活動」(以下、「市民活動」と記す)の歴史がわかる巻頭写真、16分野・約1万3,800項目、164本のコラムなどで構成されている。監修は、社会福祉法人大阪ボランティア協会ボランタリズム研究所である。本年表によると、同協会は1965年設立の、現存する中では日本で一番古い民設民営のボランティア中間支援団体である。主な活動は、ボランティアへの学習・活動支援、コーディネーション、情報提供、研究・出版活動など、ボランティア・センターのモデル化を追求し、今日ではボランティアだけでなく、NPO活動や企業の社会貢献活動への支援も積極的に実施している。同研究所は2009年10月に協会内に設立された、ボランティアベースの研究所である(同書 2頁、1,098頁 2021年)。
評者は、国際協力NGOの研究者として過去に『NGOの発展の軌跡』(明石書店、2005年)、『激動するグローバル市民社会』(明石書店、2017年)などを出版してきたが、本年表を見てもっと参考にさせてもらえば良かったと後悔もしている。それは、本年表が日本の市民活動の熱い苦闘の歴史を分かりやすく紹介しているからである。
本稿では、本年表の書評として最初に目次を紹介し、次に筆者なりのコメントを述べ、最後に今後の課題に関する考えを述べていく。
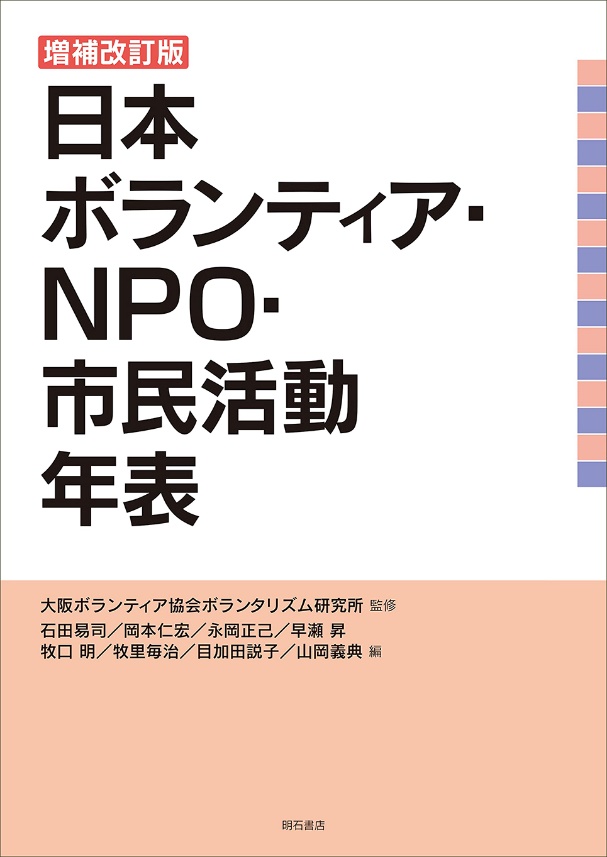
本年表の目次
増補改訂版の刊行にあたって
初版刊行にあたって
概観(増補改訂版)
概観(初版)
増補改訂版の構成
1 人権(分野責任者:加藤昌彦)
2 社会福祉(分野責任者:永岡正己)
3 医療・保健・衛生(分野責任者:黒田研二)
4 教育・健全育成(分野責任者:佐藤一子)
5 文化(分野責任者:伊木稔)
6 スポーツ・レクリエーション(分野責任者:石田易司)
7 ジェンダー・フェミニズム(分野責任者:岡野八代)
8 まちづくり・地域づくり(分野責任者:小林郁雄)
9 防災・災害救援・復興支援(分野責任者:室崎益輝)
10 国際協力・国際交流・多文化共生(分野責任者:大橋正明)
11 反戦・平和(分野責任者:目加田説子)
12 環境・自然保護(分野責任者:星野智子)
13 消費者保護(分野責任者:小林真一郎)
14 支援組織(分野責任者:吉田忠彦)
15 支援行政(分野責任者:山岡義典)
16 企業の社会貢献(分野責任者:山岡義典)
市民活動史年表作成のための資料
索引
コラム はじまりのミッション(128コラム)
コラム 視点 テーマで学ぶ(36コラム)
次に、本年表にコメントについて考えてみたい。
第1に、本年表は、16分野の生きた市民活動年表であることである。本年表は、2014年の初版の14分野を、上記の各分野の責任者と、充実した執筆陣により、16分野に拡大している。初版14分野「8 まちづくり・災害復興支援」と「13 支援組織・支援行政」は、本年表では16分野「8 まちづくり・地域づくり」、「14 支援組織」および「15 支援行政」に分かれた。また、表や概要が充実し、項目は1万3,773項目に増え、コラム数も164にのぼるなど興味が尽きない。特にコラムは、多くの研究者・専門家が執筆しており十分な価値がある。
年表は明治維新前後から2020年までの活動の歴史を創生期、成長期、発展期に分けて記録している。また、2011年以降の3.11東日本大震災から新型コロナ感染拡大の最新情報がアップデートされている。東日本大震災は津波被害、原発事故や最近の新型コロナ感染禍などにおける多くの市民支援活動の実態がはっきりと記録されており、その活動と記録が将来の世代に引き継がれていくことが肝心だと改めて思わせる。
第2に、本年表が、日本の市民活動の歴史書であることである。
明治時代初期の市民活動は、明治政府の意向で恩賜財団など一部の限られた団体しかできなかった。昭和初期、戦時国家体制の「臣民」の時代は、国家権力に従わなければ弾圧や規制を受けた。本年表には、数多くの困難を乗り越え、権利を獲得してきた人々や団体の苦闘の歴史が描かれている。それは、日本に市民社会が根付いてきた事実を明らかにしている「証し」でもある。特に、巻頭の「写真で見るボランティア・NPO・市民活動の歴史」は、その写真一枚一枚に市民活動の情熱と息遣いが聞こえてくるようだ。その意味では、本年表は単なる年表ではなく、日本の市民活動の「歴史書」としても読むことができる。「始まりのミッション」を大切に確認しつつ、「最後まであきらめない」「粘り強く行っていくこと」の大切さを教えてくれる。本年表の16分野は、どの分野も市民活動に関心のある人は一読する価値がある。
第3に、本年表は、日本の「市民社会スペース」の手引書になるということである。
本年表は、JANIC/THINK Lobbyの活動の柱の一つでもある縮小している日本の「市民社会スペース」を考える上での「手引き書」になる。これらの記録から、過去に日本の市民活動や市民団体の先人たちがどのように活動し、権利を獲得してきたのか、団体の活動を行ってきたかを確認することができる。特に、「はじまりのミッション」と題したコラムでは、現代に通じる活動や団体の創設、転機などを書いており、それぞれの時代において、市民社会と政府や企業との位置関係がどのようになっていたのか、どのように市民活動が自分たちの空間としての市民社会スペースを確保・維持してきたか、その一端を把握することができる。「市民活動(ボランティア)は市民社会の成熟と関係しており、自由で、自立的な市民の存在を抜きにして活発化しえない」と述べ、「独裁権力が絶対的な支配力を行使している社会においては市民(ボランティア)活動やNPOの活動は窒息してしまう」(本書、21頁)と指摘する。日本において権威主義的な体制を作らないためにも、「市民社会スペース」の維持が必要であると認識させられる。
第4に、本年表は、国際協力NGO関係者に有益な市民活動の記録を提供している。
国際協力NGO(以下にNGOという)関係者は、「10 国際協力・国際交流・多文化共生」に関心があるのではないだろうか。この分野は他の分野に比べ新しいが、他の分野にも関心を広げることで、明治時代以後、先人たちが様々な困難を乗り越えて市民活動を継続してきたことを知ることができるだろう。また国際協力活動に関しては、1990年以後に動き出した、国際協力活動における政府のNGO支援や両者のパートナーシップの歩みは、まだ歴史が浅いとはいえ、その流れと事実を改めて確認しておく必要がある。その背景には、1980年代の10年間、国際的にはインドシナ難民支援活動を契機とする国際協力活動が盛り上がったにも関わらず、日本のNGOは、なかなか政府からの支援を受けられなかったという記憶がある。同じDAC加盟国である欧米諸国はNGOを手厚く支援していたが、当時ODA大国であった日本政府は、NGO支援をほとんど実施していなかったという事実がある。現在でも、日本政府によるNGO支援はODA総額の約2%であり、DAC諸国平均の約10%に比べて高いとはいえない。日本のODA大綱が、経済安全保障重視へと変質していく中で、日本のNGOは、人間の安全保障や国連の持続可能な開発目標(以下SDGsという)を基本とするNGO支援の量的・質的な充実を日本政府に対し、求めていくべきである。
日本という社会では、市民活動は常に主流ではなかった。日本では、政治家・官僚・企業の力が強く、ボランティア・NPO・市民活動に対する一般市民の関心も特に強いわけではない。しかし本年表を読むと、市民活動が明治、昭和、平成、令和の時代をしぶとく生き抜いてきたことがわかる。今後、市民活動はどのように未来に向けて持続的な活動を行い、どのようにそのミッションを果たしていけばよいのだろうか。市民活動を継続するための今後の課題として、以下に気づいたことを挙げておく。
第1に、SDGsについてどのように取り上げるかである。この原稿を執筆している現在(2023年1月)、政府、企業、マスコミは社会貢献活動の掛け声としてSDGsに光を当てており、NPO・NGOの活動が時々、埋没してしまいそうに思うことがある。しかし、SDGsが国連で採択された2015年からまだ8年ほどしか経過していない中で、最新の活動を詳細に記載することは難しい。
国連が2001年に掲げたミレニアム開発目標(MDGs)は、2001年から2015年までの14年間、発展途上国を対象とした開発目標であり、日本国内を対象としていかなかったので日本国内では盛り上がらなかったといわれる。それでも、2005年の「ほっとけない世界まずしさキャンペーン(ホワイトバンドキャンペーン)」では、日本全国で約400万本のホワイトバンドが販売されており、関心の高さを示した。地球的な課題を扱うMDGsやSDGsの広がりは、国連や各国政府だけでなく、NGOによる開発教育、キャンペーン、政策提言の延長上に存在していると私は確信している。
本書では「10 国際協力・国際交流・多文化共生」、「12 環境・自然保護」などの分野を中心にSDGsに関する記録が掲載されているが、SDGs関連のコラムは教育分野の「持続可能な社会づくりの担い手を育てる―ESDとSDGs」だけなのはさびしく、もう少しあってもよかったのではないか、と考える。今後SDGsが一時の流行で終わってしまうのか、2030年以後のポストSDGsに続いていくのか、後世でどのように語られるのか分からないが、「SDGsウオッシュ」といわれる、見せかけのSDGs活動を行う企業も出てくる中で、長い苦闘の歴史を歩んできた市民活動は、「SDGsを実現する本物の活動」の主体である、と改めて理解できる。
第2に、新型コロナウィルス感染症(COVID-19、以下コロナ感染症)の拡大に関する記録について、である。2020年からのコロナ感染症の拡大の中で、日本を含む世界は未曽有の危機に陥った。今回のコロナ感染症は、20世紀初頭のスペイン風邪流行と並ぶ世界的なパンデミックであり、21世紀に入ってから最大規模のグローバル感染症だといえる。本原稿を書いている2023年1月現在でも、コロナ感染症は一向に収まる気配はない。もちろん、本年表においても、対コロナ感染症に対する支援・提言活動が記録されている。2020年に感染拡大が始まったコロナ感染症なので、本年表に記載される内容は少なく、今後の年表に記載されることになるだろう。だがこのグローバル感染症に対する市民活動に関しては、後世の記録に残す必要があり、本年表においてもコラムなどでもっと取り上げても良かったのではないか、と考える。
第3に、市民活動は、デジタル・情報技術(IT)時代にどう向き合い、対応していくかについて、である。本年表では、「展開期となる現在は、情報・通信革命が本格的な社会変容をもたらしつつある時期と重なっている」(同書、20頁、2021年)と指摘し、「13 消費者保護」の中でも、消費者庁によるデジタル化への対応が記録されている。しかし今後、日本が、デジタル・IT・人工知能(AI)社会とどう向き合うのか、IT・AIをどう活用するのか、人間の労働の喪失と分配や、管理・監視社会とどのように向き合っていくのか、その中で市民活動はどのような提言や支援を行っていくのか、といったテーマを、どこかでもっと取り上げても良かったのではないかと考える。
本稿では、『日本ボランティア・NPO・市民活動年表』の書評として、最初に本年表の目次を紹介し、次にコメントを行い、さらに今後の課題について触れた。
最初にも述べたが、本年表は全部で1,104頁と実に重たい大著である。このような大年表をまとめた、編者、分野責任者、執筆者の方々のご苦労に改めて敬意を表したい。多くは実際に市民活動に関わり、市民活動に対して深い理解と情熱を持たれている方々であると確信する。そうでなければ、とても本年表は完成できなかっただろう。
また、国際協力NGOに関心ある方は、本年表「10 国際協力・国際交流・多文化共生」の分野の市民活動とJANICの『NGOデータブック2021』(外務省/国際協力NGOセンター、外務省、2022年)を見比べて調べることをお薦めしたい。そうすれば、読者は国際協力NGOの歩みを一層深く理解できるだろう。
日本政府は2022年度末、防衛・原発・ODAの政策を、十分な議論なく大きく転換しようとした。このような社会の大きな分岐点において、本年表が取り上げた16分野の課題を解決するために、市民活動が果たす役割は益々重要になってくる。私たち日本人は、このような市民活動の歩みを理解し、深い情熱を注いで守り育てなければならない。そのためにも、本年表のような、事実に基づく記録を残していくことが求められる。