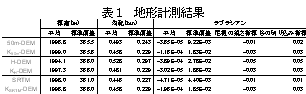抄録
1.はじめに地形特性は,標高・勾配・方位・ラプラシアン(凸型斜面の程度・凹型斜面の程度)などDEMから計算される特徴量で示すことができる.1990年代に国土地理院によって日本全国を網羅する50m-DEMが整備され,地形計測に用いられるようになった.日本の細かい地形のきめ(テクスチャ)を表す空間解像度としては2.5万分の1の地形図から作成される限り,50m-DEMがほぼ限界である.北海道地図KKの10m-DEMは、格子間隔はより細密であるが,当然のことながら元データである等高線地形表現力を越えるものでは無い.DEM取得法として,等高線地図から作成する方法以外に,パララックスのある空中写真・衛星画像からの作成,レーザスキャン測距とレーダの位相信号による直接作成などがある.最近では,NASAがスペースシャトル・ミッションとしてレーダを用いて作成したSRTMが注目される.SRTMは,陸域の80%を解像度3秒メッシュ(アメリカでは解像度1秒メッシュが公開)で作成されている.従来は等高線地図から作成した1km-DEMが存在したが,精度が非常に劣る地域があった.同一精度で地球をカバーするSRTMが登場したことで,地形計測による大陸規模の比較研究が可能になるなど期待は大きい.本研究では,飛騨山脈の南端に位置する乗鞍岳(北西端36°10′N・137°28′E,南東端36°04′N・137°37′E)を検討対象地域として,異なる作成法のDEMを用いて,地形特徴量(勾配とラプラシアン)を計算し,集計処理を行い,それぞれのDEMについて特性の比較検討を行う.なお,元データや作成アルゴリズムから比較検討することも可能であるが,ここでは利用者の立場から,それぞれのDEMの特性について報告する.2.使用データと処理方法使用したデータは,等高線地図から作成されたDEMとして国土地理院作成の50m-DEM・北海道地図KK作成の10m-DEM(以下H-DEMと記す),森田・野上(2004)がデジタル写真測量で作成した10m-DEM(以下K-DEMと記す),SRTMの4種類のDEMである.50m-DEMとH-DEM,SRTMは,緯度経度座標系を採用しており,南北方向と東西方向の格子間隔が異なるので,それを補正して勾配・ラプラシアンのような微分計算を行う必要がある.微分計算の結果について座標系を例えばUTMに変換するのと,座標系をUTMに変換してから,微分計算を行うのでは当然結果が異なる.既存のGISソフトではしかも補間法がブラックボックス化されており,その補間法が微分値を大きく変える可能性があるので,異種DEMの比較では当然前者の方法を用いる必要がある.いっぽうK-DEMは,UTM座標で作成したものであるので,微分値の計算にそのような補正は必要ない.そこで,本研究では既存3種の緯度経度法DEM( 50m-DEM・H-DEM・SRTM)の格子点に合わせて,最も細密なK-DEM(UTM座標、10m格子間隔)からリサンプリングして共通の格子間隔の新しいDEMを作成し,それぞれについて,この新しいDEMを基準にして勾配・ラプラシアンについて,相互に比較することにした.3.結果 それぞれのDEMとK-DEMの標高・勾配・ラプラシアンの計算結果を表1に示す.また,ラプラシアンの小さい値の方から5%値を尾根の鋭さの指標,大きい値の方から5%を谷の切り込み指標とした.1)勾配: 50m-DEMとH-DEMは,K-DEMからみて,より急勾配の斜面を表現している. 2)ラプラシアン: H-DEMは,K-DEMからみてラプラシアンの標準偏差が最も大きい値を示した.つまり,地形の煩雑さを誇張するような表現をしていることがわかった.以上2点の特徴は等高線データからDEMを作成するそれぞれのアルゴリズムの影響と考えられる.また,SRTMは等高線データを経由しない直接取得のDEMであり,格子間隔は異なるが空中写真のパララックスから直接得られたK-DEMに近い特性を示した.参考文献森田 圭・野上道男 2004.デジタル写真測量による10m-DEMの作成と乗鞍岳における植生分布の地形的立地条件解析.日本地理学会発表要旨集 65:74