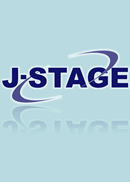-
沖田 極
1997 年3 巻3 号 p.
195-196
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
-
Samuel S Lee
1997 年3 巻3 号 p.
197-199
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
In cirrhosis, the circulation becomes hyperdynamic, characterized as increased baseline cardiac output with decreased arterial pressure and peripheral vascular resistance. Despite the increased basal cardiac output, the heart reacts subnormally when subjected to physiological or pharmacological stress such as exercise, drugs or surgery. This blunted responsiveness of ventricular contractility has been termed “cirrhotic cardiomyopathy, ” but its pathogenesis remains unclear. We aimed to clarify the pathogenic factors underlying this condition, in particular the role of membrane changes in autonomic receptors or their signal transduction pathway, in different rat models of chronic liver disease. The majority of studies were performed in the chronic (4-week) bile duct ligated cirrhotic rat (BDL), a model of biliary cirrhosis with deep jaundice. Other studies were also performed in 3 other models of portal hypertension / cirrhosis were studied : portal vein-stenosed rats with infrahepatic portal hypertension but no parenchymal liver disease (PVS); thioacetamide-induced cirrhotic rats (TA), bile duct ligated cirrhotic rats then subjected to choledochojejunostomy to reanastomose the bile flow and relieve biliary obstruction (BDR) Controls had sham operation. Isolated left ventricular papillary muscles from these groups were tested for β-adrenergic responsiveness by electrical stimulation at 1Hz, voltage 1.3 × threshold, with graded doses of the β-adrenergic agonist isoproterenol. Compared to the sham-controls, muscles from all 3 cirrhotic groups showed blunted isoproterenol responsiveness, while PVS was not different from shams. Cardiac sarcolemmal plasma membranes were prepared from the ventricles of BDL or control rats by sucrose gradient centrifugation. Static and dynamic components of membrane fluidity were assessed by using diphenylhexatriene and stearic acid labelled with a series of 9-anthroyloxy probes, respectively.
3H-dihydroalprenolol and
3H-methyl scopalamine were used as radioligands to respectively characterize the stimulatory β-adrenergic and inhibitory muscarinic (m2) receptors. G-proteins were assessed by fluoride stimulation and SDS-PAGE with western blots using rabbit antibodies to G-protein subtypes. Adenylyl cyclase activity measured by cAMP generation was measured at baseline and following stimulation with 3 compounds : isoproterenol to activate the receptor, NaF to stimulate Gs-protein directly, and forskolin which stimulates adenylyl cyclase independent of receptor activation. BDL and TA rats showed decreased cAMP generation with all 3 drugs, whereas the BDR rats only showed decreases with isoproterenol and NaF, but intact forskolin responses. Compared to controls, the BDL rats had a 15% decrease in the β-adrenoceptor density without any change in the binding affinity. The receptor density and binding affinity of the m2 receptors were unchanged from controls. Despite the unchanged m2 receptor characteristics, isolated left ventricular papillary muscles from BDL rats showed blunted carbacho-induced attenuation of isoproterenol-stimulated contractility, indicating blunting of muscarinic function. Moreover we found a 40% decrease in isoproterenol-stimulated AC activity, suggesting that postreceptor factors in the signal transduction pathway for the β-adrenoceptor are also involved. This was confirmed by the fluoride and forskolin studies which showed attenuated responses, indicating defective Gs and AC enzyme activity in BDL rats. The BDL menbrane content of Gas and Gia as determined by western blotting were decreased by 20% and 47%, while the G
commob B level was unchanged. Both static and dynamic membrane fluidity significantly decreased, and the membrane cholesterol content was increased in the BDL rats, with consequent increased cholesterol : phospholipid ratio.
抄録全体を表示
-
山本 一仁, 恩田 昌彦, 田尻 孝, 鳥羽 昌仁, 梅原 松臣, 吉田 寛, 真々田 裕宏, 谷合 信彦, 西久保 秀紀, 松本 智司, ...
1997 年3 巻3 号 p.
201-207
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
食道静脈瘤患者6例に対して内視鏡的硬化・結紮術 (ESL) を行い, その施行前後の血行動態を血管造影にて検討した.治療前は, 静脈瘤への供血路として左胃動脈は全例, 左胃静脈は5例で関与していた.左胃静脈の血流方向は遠肝性4例, to-and-fro性2例であった.治療後, 静脈瘤が完全消失した5例では左胃静脈の血流方向が変化し, 2例が遠肝性から求肝性, 2例が遠肝性からto-and-fro性, 1例がto-and-fro性から左胃静脈描出不能へとそれぞれ変化した.また, 左胃静脈が描出された4例中3例に左胃静脈径の狭小化を認めた.一方, 遺残した症例は静脈瘤供血路が左胃動脈のみであり治療前後でto-and-fro性のまま変化を認めず, 血管径の変化もみられなかった.ESLは, 左胃静脈が静脈瘤に供血する症例に対しては左胃静脈の完全あるいは高度な血栓化により血行動態の変化が生じたと考えられた.
抄録全体を表示
-
関山 達也, 長戸 孝道, 吉田 明弘, 古明地 弘和, 長野 具雄, 大須賀 勝, 寺田 秀人, 勝田 悌実, 里村 克章, 荒牧 琢己
1997 年3 巻3 号 p.
209-213
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
門脈圧亢進症においては肺合併症がしばしば認められるが, 肺循環動態に関する報告は少ない.われわれは慢性肝炎41例 (50.3±11.6歳, 男性/女性=26/15), 肝硬変41例 (50.1±8.9歳, 男性/女性=26/15) を対象として, 肝静脈カテーテル検査, 右心カテーテル検査を施行し比較検討した.肝硬変では慢性肝炎に比し肝静脈楔入圧, 肝静脈圧較差, 心係数が有意に上昇, 肺血管抵抗、総末梢血管抵抗は有意に低値であった.肝硬変において肺血管抵抗と総末梢血管抵抗の間に有意の正の相関, 肺血管抵抗と肝静脈圧較差の間に有意の負の相関関係が認められた.肺血管抵抗は総ビリルビン値と有意の負の相関, コリンエステラーゼ値とは有意の正の相関関係を示した.これらの結果は, 肝障害の進展に伴い, また全身血行動態の循環亢進状態の一部として肺血管抵抗の減弱が生じることを示唆する.
抄録全体を表示
-
とくに食道壁貫通枝の役割について
日野 昌力, 角谷 宏, 千葉井 基泰, 増田 勝紀, 鈴木 博昭
1997 年3 巻3 号 p.
215-219
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
食道静脈瘤17例に対し内視鏡治療前後で内視鏡的超音波カラードプラ法を行った.治療前には, 全例で壁内血流が検出されたが治療後は4例に残存していた.食道壁貫通枝 (EPV) が認められたのは9例 (52.9%) で, 血管径は1.9~6.2mm (平均3.3±1.5mm), 血流方向はtoward7例, away2例であった.治療終了時EPVは全例で消失した.早期再発率からみると, 壁内血流が残存した群としない群で差は認められなかった.towardのEPV7例中3例で早期再発が認められたのに対し, EPV (-) 症例では8例中1例であった.awayのEPV2例には早期再発は認められなかった.towardのEPVの血管径は, 早期再発例で5.3±0.8mmで, 長期非再発例の2.3±0.3mmと比較し有意に拡張していた.また, 早期再発例では再発時にEPVの血流が回復している様子も観察できた.食道静脈瘤の早期再発の要因として著しく拡張したtowardのEPVが重要な役割を果たしていると考えられる
抄録全体を表示
-
藤田 順子, 蓮見 昭武, 吉田 昌, 森田 美和, 杉岡 篤, 島津 元秀, 北島 政樹, 青木 春夫
1997 年3 巻3 号 p.
221-225
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
門脈圧亢進症における消化管壁内粘膜下A-Vanastomosis (A-VA) 開大増加に伴う循環亢進状態に関しては, 食道胃静脈瘤・門脈圧亢進症性胃症の発症に直接関連する病態として, 多くの検討がなされてきている.しかし従来の検討方法は, 生理学的手法による循環亢進状態の証明ないしは組織学的なA-VA血管の証明などで, 生理的条件下におけるA-VA開大の病態の直接的証明ではなかった.そこで, Wistar系ラットに四塩化炭素を投与して肝硬変症を作成し, 生体内顕微鏡下にMonastral Blue B (MBB) 色素を投与した時の胃壁粘膜下層における細動・静脈内のMBBの流れを生体内で観察した.その結果, 正常対照群ではA-VA血管を認めなかったが, 肝硬変群では随所で細動脈と細静脈とを直接吻合するA-VA血管を観察し得, 門脈圧亢進症におけるA-VA開大増加の病態を, はじめて生体内で動的に直接証明することができた.
抄録全体を表示
-
月岡 佳久, 真田 淳, 武井 和夫, 武田 一弥, 清水 直樹, 篠原 靖, 堀部 俊哉, 角谷 宏, 白鳥 泰正, 宮岡 正明, 斉藤 ...
1997 年3 巻3 号 p.
227-231
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
1989年1月から1996年7月までに大腸内視鏡検査を受けた肝硬変症について, 出血しやすい血管拡張の臨床像を明らかにするために, 出血群と非出血群に分け比較検討を行った.大腸内視鏡検査を受けた肝硬変患者の31例26.5%に血管拡張を認めた.出血群は7例, 非出血群は24例であった.年齢, 男女比, 肝癌合併率, 食道胃静脈瘤合併率には出血群, 非出血群で差は認められなかった.発赤斑とクモ状血管拡張の血管拡張に分類でき, 出血群, 非出血群ともにクモ状血管拡張の方が多かった.血管拡張は右側結腸に比べ左側結腸に多く, 出血群, 非出血群に差は認められなかった.肝予備能の悪化した症例に出血しやすい傾向が認められた.肝予備能の悪化例に消化管出血を認めた場合, 本症も念頭に出血源の検索にあたることが重要と思われた.
抄録全体を表示
-
MIB-1抗体を用いた免疫組織化学的染色による検討
岩田 豊仁, 吉本 次郎, 児島 邦明, 深澤 正樹, 別府 倫兄, 二川 俊二
1997 年3 巻3 号 p.
233-239
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
肝硬変症を基礎疾患とした静脈瘤直達手術360例中, 術後に肝癌発生を認めた82例を対象とした.静脈瘤手術時の臨床的背景因子と肝生検組織を用いたMIB-1抗体による免疫組織化学的染色にて測定したKi-67の標識率 (L.I.) から, 肝硬変症における肝癌発生の危険因子を検討した.直達手術時45歳以上の症例およびAFP値21ng/m
l以上の症例で累積肝癌発生率が有意 (p<0.01) に高率であった.肝癌発生例のKi-67L.I.は0.16±0.10%と非発生例の0.07±0.06%に比較し有意 (p<0.01) に高値であった.Ki-67L.I.が0.10%以下群に比較し0.11-0.21%群および0.21%以上群の累積肝癌発生率は有意 (p<0.01) に高率であり, 肝細胞増殖能の元進している肝硬変症において肝癌発生の危険性の高いことが示唆された.以上よりKi-67L.I.による肝細胞増殖活性の測定は肝癌発生の予知因子として有用と考えられた.
抄録全体を表示
-
大舘 敬一, 重田 博, 千佐 俊博, 山崎 聖二, 中川 一郎, 伊藤 まゆ, 榎本 武治, 遠藤 徹, 田添 貴史, 草刈 幸次, 稲葉 ...
1997 年3 巻3 号 p.
241-244
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
当科では食道・胃静脈瘤治療に対して, 1982年以来, 内視鏡的治療を第一選択としてきた.1996年まで, 223例の食道・胃静脈瘤例に対し内視鏡的治療が行われ, 内視鏡的治療後に何らかの手術を要した症例は11例 (4.9%) であった.静脈瘤関連では4例 (1.8%) に手術が付加され, 1例の食道離断術の他に, 局所性門脈圧亢進症1例を含む胃静脈瘤出血3例は内視鏡的治療が無効で, Hassab手術を要した.食道・胃静脈瘤はほとんどの症例で, 内視鏡的治療で制御可能であった.しかし, 少数例ながら, 硬化療法では難治の胃静脈瘤に対して早期に手術療法を選択すべきであり, また内視鏡的治療が本来適応外である局所性門脈圧亢進症の存在を考慮すべきである.
抄録全体を表示
-
-とくに高濃度ブドウ糖液を用いた手技の有効性について-
谷口 英明, 武南 達郎, 河合 公三
1997 年3 巻3 号 p.
245-249
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
当院でB-RTOを行った孤立性胃静脈瘤11症例について検討した.11例中10例は大きな合併症はみられず, 胃静脈瘤を消失させることができた.胃腎短絡路をバルーンで閉塞させた後, 逆行性に造影し, 胃静脈瘤の流入路および流出路を確認した.流入路は, 短胃静脈, 後胃静脈が主体であるものが8例, 左胃静脈が主体であるものが3例であった.また, 流出路は胃腎短絡路以外の副流出路が全例に認められた.当院では副流出路に対し, バルーン閉塞下に50%もしくは70%ブドウ糖液を注入することで副流出路をできるだけ遮断させるようにしている.50%もしくは70%ブドウ糖液は安全性が高く, また細い副流出路であれば容易に血流を遮断することが可能であり, 前処置として有効な手段の一つと考えられた.
抄録全体を表示
-
福田 保, 岡村 誠介, 岡久 稔也, 柴田 啓志, 伊東 進
1997 年3 巻3 号 p.
251-256
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
食道上中部に存在する孤立性静脈瘤 (SoV) および散在性静脈瘤 (ScV) の成因や臨床的意義について十分な検討はなされていない.今回われわれは, 上部消化管内視鏡検査を施行した6660例中, SoVおよびScVを認めた54例85病変について検討した.SoVは36例36病変, ScVは18例49病変, ドーム型は36例53病変, カマボコ型は19例32病変, 青色調は32例54病変, 白色調は25例31病変認めた.病変は25~34cmの後壁に最も多く, 内視鏡的併存病変では慢性胃炎が最も多く, 上部消化管内視鏡全例との比較では通常の食道静脈瘤が有意に少なかった.ドーム型はカマボコ型および上部内視鏡検査全例に比して有意に高齢者に多く認められた.基礎疾患では, 通常の食道静脈瘤を来す疾患は24.1%と少なかった.SoVやScVの原因としては, 通常の食道静脈瘤と同じ成因は少なく, ドーム型は加齢による粘膜下静脈の局所的な脆弱性が原因と考えられた.
抄録全体を表示
-
梅澤 正, 富永 静男, 大久保 賢治, 北村 玲子, 小金井 裕之, 斉藤 聡, 山内 裕代, 永瀬 肇, 沼田 和司, 斉藤 紀文, 田 ...
1997 年3 巻3 号 p.
257-261
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
食道静脈瘤に対し, 経頚静脈的肝内門脈大循環短絡術 (TIPS) および内視鏡的食道静脈瘤硬化療法 (EIS) はそれぞれ有効な治療法として確立されているが, 治療効果や長期予後に関して, 一部問題点も残されている.TIPS単独ではステントの閉塞による静脈瘤の再形成, 出血が危惧され, EIS単独では消失効果不良な場合や, 新たな静脈瘤, 門脈圧亢進性胃症の形成が問題となる.今回われわれはEIS単独では形態の改善を認めず, TIPS単独療法後も再出血を来した巨木型静脈瘤の1例と, 初回治療の巨木型静脈瘤の1例に対し, TIPS後EISを併用し良好な成績を得ているので報告する.この併用療法では減圧により少量の硬化剤で静脈瘤の消失が得やすく, シャント機能低下時でも消失効果の持続が期待できる.また, TIPS後の肝への門脈血行動態を変化させる可能性もあり, 難治あるいは大シャントとなっている巨木型静脈瘤に対して有用な方法と考えられる.
抄録全体を表示
-
斎藤 文子, 小原 勝敏, 入澤 篤志, 滝口 藤夫, 東條 淳, 伊藤 昌幸, 宍戸 英夫, 坂本 弘明, 粕川 禮司
1997 年3 巻3 号 p.
263-268
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
食道壁外シャントを有する食道静脈瘤症例においては, 内視鏡的硬化療法施行時に, 注入した硬化剤が食道壁外シャントを介して大循環へ流出することがある.とくにシャント血管径の大きな場合には, 硬化剤単独での食道壁外シャントの閉塞は困難である.そこで, 巨大な食道壁外シャントを有する症例3例において, シャントを閉塞する目的で, 超音波内視鏡 (EUS) により同定した食道壁外シャント部の局所にのみEVLを行う選択的内視鏡的静脈瘤結紮 (selectiveEVL;s-EVL) を併用した内視鏡的硬化療法 (EIS) を行った.s-EVLによって食道壁外シャントが閉塞されると, 結紮部位肛門側静脈瘤の穿刺では硬化剤が壁外へ流出しなくなるので, 供血路までの十分な硬化剤の注入が可能となった.s-EVL併用EISは巨大な壁外シャントを有する食道静脈瘤症例に対して安全かつ効果的な治療法と考えられた.
抄録全体を表示
-
村上 匡人, 國分 茂博, 日高 央, 浅野 朗, 高田 雅博, 中沢 貴秀, 西元寺 克禮
1997 年3 巻3 号 p.
269-273
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
症例は62歳女性.C型肝炎 (+) の肝硬変症.予防的硬化療法目的にて入院.硬化療法前の左胃動脈造影静脈相で胃上部の血流方向は遠肝性であった.初回硬化療法にて35cm, 12時よりの穿刺時, 静脈瘤から直接血液を採取.ガス分析において酸素分圧 (PO
2) は41.3mmHg, 同時に測定した動脈血酸素分圧PaO
285.6mmHgとの比 (PO
2, /PaO
2) は0.482であった.同部に5%EOIを13.5ml注入し静脈瘤造影では左胃静脈まで造影された.2回目の硬化療法時における静脈瘤血の採取では, PO
2, は74.5mmHgと上昇し, PO
2/PaO
2も0.948と著明に上昇していた.硬化療法はその後2回追加し, 静脈瘤は消失し, 左胃動脈造影でも血流方向の改善を認めた.静脈瘤酸素分圧の上昇の一因は, 硬化療法時の供血路遮断による静脈瘤への動脈血流入の相対的増加にあると考えられ, 血行動態の変化との密接な関連性が示唆され静脈瘤の病態を考える上で重要と思われ報告した.
抄録全体を表示
-
保刈 岳雄, 高野 靖悟, 大塚 善久, 東風 貢, 中田 泰彦, 河野 悟, 山崎 猛, 川上 新仁郎, 小池 拓也, 岩井 重富
1997 年3 巻3 号 p.
275-279
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
56歳の女性.主訴は上腹部痛と背部痛で来院.入院時検査にて白血球, CRP, 血清アミラーゼの高値, 低カルシウム血症, 代謝性アシドーシスと高度の肝機能障害と軽度の腎機能障害を認め, 腹部CTでは膵の腫大, 膵全体の実質内部不均一, 膵周辺への炎症の波及を認めるとともに肝右葉の虚血・壊死像を認めた.腹部血管造影では, 脾静脈と上腸間膜静脈の閉塞とそれに伴う側副血行路の発達, cavernomatous transformationの形成, さらに固有肝動脈, 左右肝動脈の狭窄を認めた.重症急性膵炎の診断で人工呼吸器による呼吸補助, 腹膜透析, 腹腔動脈からの膵酵素阻害薬の持続注入を施行.全身状態の改善を待って入院後3カ月目に認めた仮性膵嚢胞に対して嚢胞摘出, 膵嚢胞空腸吻合術を施行し, その1カ月後軽快退院した.高度の肝血流障害と門脈血行異常を来した重症急性膵炎の1治験例を報告した.
抄録全体を表示
-
池田 秀博, 芦田 寛, 上田 さつき, 楠 徳郎, 森 啄磨, 坂上 庸一郎, 島田 隆男, 谷口 由紀子
1997 年3 巻3 号 p.
281-285
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー
症例は56歳男性で, 前医にて嫌気性菌 (
Fusobacterium necrophorumと
Bacteroides furagilis) による化膿性門脈炎および門脈血栓症と診断され入院治療を受けた.腹部血管造影で前区域枝以外の肝内門脈枝と上腸間膜静脈に閉塞を認めた.約1年後に著明な食道胃静脈瘤を認め, 治療目的にて入院となった.腹部血管造影では肝内門脈枝と上腸間膜静脈の閉塞状態は同様であったが, 1年前にはほとんどなかった求肝性側副血行路 (cavernous transformation) が発達していた.ただ, 肝内門脈枝の発達は不十分で, 静脈瘤を形成する遠肝性側副血行路を認めた.門脈系の血行動態を考慮し, 遠位脾腎静脈吻合術を施行し静脈瘤は消失した.以上, 化膿性門脈炎後約1年で食道胃静脈瘤を認め, 経時的に門脈血行動態を観察しえた肝内門脈・上腸間膜静脈血栓症の1例を報告する.
抄録全体を表示
-
豊永 純
1997 年3 巻3 号 p.
287
発行日: 1997/12/10
公開日: 2012/09/24
ジャーナル
フリー