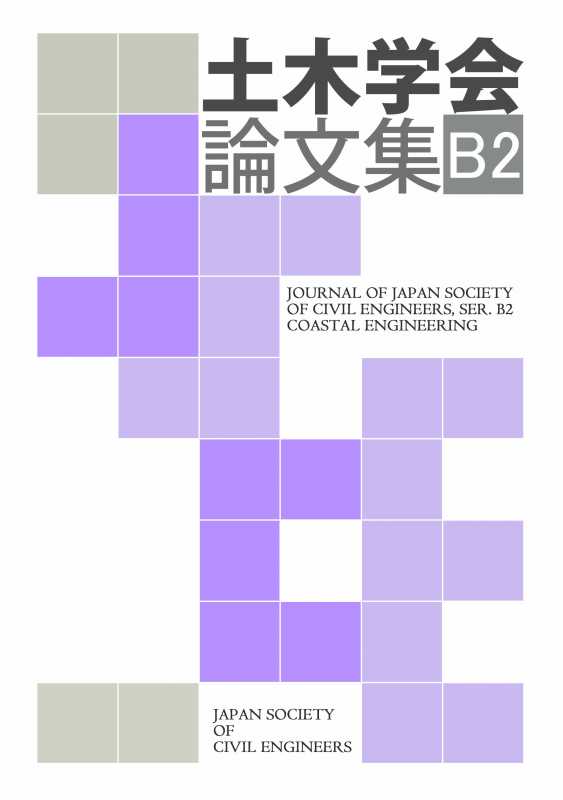-
郡司 滉大, 有川 太郎
2022 年78 巻2 号 p.
I_301-I_306
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
本検討では南海トラフ地震を対象として,地震発生直後の水位データから三重県A町に到達する津波到達時間を機械学習を用いて瞬時に予測した.予測誤差比較を地震の規模ごとのモデルと用いたすべての地震の規模のデータを用いたモデルで行った.地震の規模ごとに差があるものの,教師データ数を増やすごとに誤差の減少傾向がみられたことから,地震の規模ごとに最も誤差が小さかったモデルを用いて津波到達時間予測誤差比較を行った.本検討で用いた初期水位と津波到達時間の場合,多くの地点において5分以上予測値が過大評価となっていたMw9.0に比べ,教師データが増されたMw8.6における予測は過大評価が改善された.また,教師データを異なる規模の地震シナリオとした時の予測精度について評価した.
抄録全体を表示
-
Karina A. SUJATMIKO, Yoshihiro OKUMURA, Jo OHTANI
2022 年78 巻2 号 p.
I_307-I_312
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
When tsunamis occur, rapid self-evacuation is encouraged to evade the danger. People are expected to immediately decide without prompting from authorities. Past tsunami events have demonstrated that residents intuitively start an evacuation because of a “must escape” atmosphere. This study refers to this situation as a reality-of-evacuation-start (RES). Information regarding natural and social cues that initiate the evacuation (namely RES sources) are valuable for establishing a disaster risk reduction strategy. This paper proposes a method for estimating the impact of various RES sources through a combination of questionnaires, video analysis, and numerical simulation. The analysis from a case study of the 2018 Palu tsunami reveals that 28% of residents immediately evacuated after feeling ground motion. Before tsunami arrive to their location, 67% of resident already start to evacuate. Analysis from video at Palu commercial building shows 37% people exposed by shouting people and 16% hearing clear instruction to evacuate. The impact of social cues in Indonesia differed from that in the 2011 tsunami in Ishinomaki, Japan. Specifically, in Palu, seeing other people evacuate had more impact in urging people to start evacuating than hearing people calling for an evacuation. This indicates that the disaster risk reduction strategy should not be generic among countries. Instead, educational material for tsunami training and drills must be attentive to adapt to the local characteristics.
抄録全体を表示
-
犬飼 直之, 小保方 快
2022 年78 巻2 号 p.
I_313-I_318
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
日本海沿岸域ではたびたび地震津波が発生している.このうち2019年に発生した山形県沖地震では,地震発生後5分で陸地に到達した.発生後の避難時間が短い津波の場合,迅速な情報提供と避難行動の開始が必要である.ここでは,新潟市周辺の県市省庁を対象に,津波情報の伝達状況などについてWeb検索や電話,対面取材をおこない資料提供などもしていただいた.これにより,津波発生時の行政の情報伝達状況を把握するとともに,課題などを考察した.次に,津波伝播状況を把握するために数値シミュレーションを実施した.結果は観測値とよく一致することを確認した.最後に,新潟市を中心とした新潟県内で住民へのアンケートを実施し,地震発生時にいた場所や,地震や津波情報の入手方法などを把握した.
抄録全体を表示
-
大石 裕介, 広上 新, 新出 孝政, 高野 和哉, 松本 大輔, 大岡 稜, 古村 孝志, 今村 文彦
2022 年78 巻2 号 p.
I_319-I_324
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
リアルタイム交通量観測データとリアルタイム交通シミュレーションに基づき,地域の交通流を数値データとして再現するデジタルツインを用いて,津波避難時の交通制御を最適化するシステムの有効性を検討した.深層学習による交通量調査を名古屋市臨海部を対象に実施し,取得した交通量データから地域の交通シミュレーションモデルを構築した.本モデルを用いて,15分の観測データから近未来の15分の交通量を予測したところ,平均19.9%の誤差で観測データを再現することを確認した.構築した交通シミュレーションモデルを用いて,南海トラフ巨大地震発生時に早期の津波浸水が予測される庄内川の東側への西側からの自動車の侵入を禁止する交通制御の効果を検討したところ,津波曝露台数が約71%軽減する効果が確認された.
抄録全体を表示
-
佐藤 翔輔, 藤田 崇宏, 遠藤 匡範, 岩崎 雅宏, 皆川 満洋, 高橋 里佳, 南城 真佐英, 渡邉 勇, 今村 文彦
2022 年78 巻2 号 p.
I_325-I_330
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
地震発生時間の違いに着目して,同一地域における津波避難行動の差異を明らかにすることを目的とし,2016年11月22日の早朝に発生した福島県沖地震と,2021年3月20日の夕刻に発生した宮城県沖地震における住民の避難行動に関する質問紙調査のデータを分析した.その結果,1)夕刻の地震の方が,暗い中でのとっさの行動をためらい,事態推移の把握に注力したために,早朝の地震よりも避難した割合がやや低かったこと,2)夕刻の道路上の車交通量が多いことが原因となり,早朝の地震よりも多くの渋滞が発生したこと,3)発生時間に関わらず,訓練の参加経験が避難の実施に関連し,夕刻の地震では性別(男性であること)が,早朝の地震では勤務形態(パート・アルバイトであること)が避難の有無と関連していたこと,などが確認された.
抄録全体を表示
-
安田 誠宏, 下村 凌雅, 森 信人
2022 年78 巻2 号 p.
I_331-I_336
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
津波防災においてソフト対策を有効に機能させ,被害を軽減するためには,住民が防災について正しい知識を持ち,発災時に正しく行動する必要がある.そのためには,防災対策を立案する行政が,住民の意識を正しく把握し,的確な防災情報や知識を提供することが望ましい.本研究では,2006年と2011年に実施されたアンケート調査結果に加えて,東日本大震災から10年が経過した2021年に追跡調査を行い,行政と住民の津波防災に関する意識のずれと経年変化を分析した.ハード対策については意識のずれがあり,行政が考えている以上に住民はソフト対策の充実を望んでいるが,この10年間でソフト対策についての意識のずれは減少し,解消傾向にあることがわかった.
抄録全体を表示
-
大江 崇, 富田 孝史
2022 年78 巻2 号 p.
I_337-I_342
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
津波火災は津波避難ビルを危険にさらし,災害直後の救助・救援や復旧活動に影響を与える可能性がある.そのため津波災害リスク軽減のための事前対策の検討において津波火災の延焼発生リスクを評価することは重要である.既往研究では,評価対象区画内におけるデータを使用して津波火災のリスク評価が行われている.しかし,津波はその周辺地域から瓦礫を流入させる可能性があるため,本研究では,評価対象区画内だけでなく,その周辺の建物被災状況を考慮した延焼発生リスクを評価する統計モデルを構築した.回帰分析の結果,評価対象区画の海側領域の建物被災状況を考慮することの重要性が示された.また,構築したモデルを用いた場合では,延焼発生期待値0.01以上の区画において実際に津波火災延焼が発生していた.
抄録全体を表示
-
高井 環, 奥村 与志弘, Karina A. SUJATMIKO
2022 年78 巻2 号 p.
I_343-I_348
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
津波などの危険が迫っている場合,直感的に行動する者の避難行動の成否は地域に醸成される切迫感の高低に左右される.この切迫感を高める対策の重要性はこれまでにも指摘されているが,いずれも行政や住民による呼びかけなど,それ自体が情報を発するソース(情報発信源)に注目したものに限られていた.しかしながら,地震発生からの時間経過などの住民を取り巻く状況の変化も地域に醸成される切迫感に大きな影響を与えると考えられる.本研究では,過去5年分の津波避難訓練の行動データを状況の変化に注目して分析した.その結果,時計を用いた厳密な時間管理が行われていないにも関わらず4割から9割が決まった時間に避難を開始していること,住民の参集状況に関する発言が多数観察され,避難開始のタイミングに強く影響していることが確認された.
抄録全体を表示
-
鎌田 紘一, 門廻 充侍, Anawat SUPPASRI , 今村 文彦
2022 年78 巻2 号 p.
I_349-I_354
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
2011年3月11日に発生した東日本大震災により我が国は甚大な被害を受け,これまで様々な被害実態と低減の先行研究が行われてきた.従来の津波災害において,身体損傷による外傷死(損傷死)は注目されていなかった.本研究では,同災害の損傷死の被害実態を検討するため,犠牲者情報を用いて宮城県の郵便番号地区を対象に,遺体発見場所に基づいた損傷死を検討した.個人属性から,損傷死とその他の死因間で性別比および高齢者率の差はみられなかった.位置情報および特化係数から,損傷死が特徴的な地域を示し,津波瓦礫が損傷死に影響した可能性が示された.損傷死率と最大浸水深の関係から,損傷死と津波外力に有意な正の相関が示され,津波外力が損傷死に影響していることを示した.これらの結果は被害実態を踏まえた具体的な防災対策に貢献している.
抄録全体を表示
-
信田 晃成, 門廻 充侍, Anawat SUPPASRI , 今村 文彦
2022 年78 巻2 号 p.
I_355-I_360
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
東日本大震災発災時,瓦礫が妨げになり,救助活動の遅延が発生した.我が国では,巨大な地震津波の発生が想定されており,人的被害軽減のため被害者の早期発見は必要不可欠である.本研究では,東日本大震災における津波瓦礫に焦点を当て,宮城県内で瓦礫から発見された犠牲者の自治体ごとの傾向を明らかにし,瓦礫内発見率と建物被害および最大浸水深の関係を検討することを目的とした.宮城県の沿岸自治体の瓦礫内発見率を分析した結果,名取市および気仙沼市において瓦礫内発見率が高かった.また,同市における,瓦礫内発見率と建物全壊率の関係を検討した結果,残存建物および木造率が瓦礫内発見率に影響を与えることが示唆された.さらに,同市の瓦礫内発見率と浸水深の関係を検討した結果,郵便番号地区を超えた瓦礫の移流に関する知見が得られた.
抄録全体を表示
-
成田 峻之輔, 佐藤 翔輔, 渡邉 勇, 新家 杏奈, 今村 文彦
2022 年78 巻2 号 p.
I_361-I_366
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
本研究では,2011年3月11日に発生した東日本大震災発災後の人々の移動が危険方向であったか否かを評価し,危険方向移動者の割合やその特性を明らかにするため,岩手県・宮城県・福島県の3県を対象に発災後の移動行動を分析した.得られた結果は,主に次の通りである.1)分析対象者の3割以上が,発災後に一度でも危険方向へ移動していた.2)人に乗せてもらって移動した人は危険方向へ移動しない傾向があった.3)公務員・団体職員は発災後最初のトリップで危険方向へ移動する傾向があった.4)発災時に外出中であった人は危険方向へ移動する傾向があった.5)発災前の備えや事前に得ていた情報の中でも過去の浸水域や避難方向を示す標識を見たことがあることは危険方向移動を抑制する可能性が示唆された.
抄録全体を表示
-
田下 健人, 中山 恵介, 新谷 哲也
2022 年78 巻2 号 p.
I_367-I_372
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
内部波が斜面上で砕波することで,底層物質の巻き上げや水平方向の長期輸送および鉛直拡散を引き起こし,沿岸域における生態系や水質に大きな影響を及ぼす可能性がある.特にエネルギーの高いbreatherは3成層で発生するため,上記の影響も著しくなると考えられる.過去の研究により,breatherの斜面上での砕波では,それぞれ物質輸送の異なる4種類の砕波形態が確認され分類可能であることが示された.しかし,3成層状態において発生するbreatherが地形と干渉して生み出す流動場に関して十分な研究は行われていない.本研究ではbreatherがどの程度の地形変化に対応して存在可能なのか,波形やエネルギーがどのような影響を受けるのかについて3次元環境流体モデルFantomを用いて解析を行った.その結果,急激な地形変化に伴ってエネルギー減衰が顕著に確認され,特に比較的波長が長い場合にはエネルギーの減少割合が大きく,地形変化に対する安定性が低下することが示された.
抄録全体を表示
-
三木 脩平, 黒岩 正光, 梶川 勇樹
2022 年78 巻2 号 p.
I_373-I_378
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
近年,人工リーフ開口部における洗掘や背後の水位上昇に伴う強い流れの発生による砂浜の決壊などの問題が発生しており,人工リーフ天端上における砕波などにより,波浪・海浜流が非常に複雑化しているため,流れの分布に影響を与える渦動粘性係数を3次元的に求める乱流モデルの導入が必要である.本研究では3次元海浜変形予測モデルの精度向上のため,海浜流場計算に3次元1方程式乱流モデルの導入を行い,既往の乱流モデルとの比較・検討および海浜流モデルの適用性を検討した.その結果,3次元1方程式乱流モデルを導入することによって,人工リーフ周辺における海浜流場への影響を確認することができた.また,実験との比較から,3次元1方程式乱流モデルを用いた計算結果が,最も実験結果に近い結果が得られた.
抄録全体を表示
-
到津 春樹, 増永 英治
2022 年78 巻2 号 p.
I_379-I_384
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
本研究では東京湾湾奥部における混合現象を定量的に評価することを目的とし,湾央から湾奥にかけて長期観測されている5箇所の観測データ1年分を用いて解析を行なった.風,潮流および浮力の水平勾配から推定される水平リチャードソン数(𝑅ix)は鉛直方向の成層状態と有意な相関関係があり,𝑅ixを用いることで東京湾の湾央部から湾奥部にかけての広い範囲における鉛直方向の混合状態を説明可能であることが明らかとなった.浦安沖以外では𝑅ixに対する潮汐の影響は小さかった.また,10日間スケールで平均した河川流量は水平密度勾配と有意な相関性が見られただけでなく,河川流量から推定した水平密度勾配から推定した𝑅ixRと観測値から算出した𝑅ixの間に有意な相関関係が見られた.以上から東京湾の湾央から湾奥にかけての鉛直混合状態は主に風と河川流量から説明可能であることが明らかとなった.
抄録全体を表示
-
片岡 貴, 竹安 希実香, 内山 雄介, 御手洗 哲司
2022 年78 巻2 号 p.
I_385-I_390
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
海洋環境問題に広範に用いられる数値Lagrange粒子追跡モデリングにおいて,波浪の効果は単にStokesdriftと背景Euler流速の線形和としてad hocに表現されてきた.本研究は,波浪作用下におけるLagrange粒子追跡の適切な解析方法を示すことを目的に,Lagrange運動方程式に関する理論的な整理と考察を行い,さらにサンゴ浮遊幼生の沿岸分散を例にvortex force型波平均3次元Euler流動モデル(ROMS-WEC)を用いたLagrange粒子追跡比較実験を通じて,波浪効果の具体的な導入方法やその効果を検討した.海浜流は初期分散過程に強く関与するとともに,その影響はその後の分散過程に対しても継続的に波及するため,波浪を考慮しない流動計算結果にStokes driftを加算する従来の方法では波浪の影響を大幅に過小評価する可能性が高く,モデルによる海洋物質分散解析のあるべき方向性を実例とともに具体的に示した.
抄録全体を表示
-
石川 仁憲, 島田 良, Mika Viljam KONTTO , 小峯 力
2022 年78 巻2 号 p.
I_391-I_396
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
海水浴場における水難事故の主要因は離岸流である.本研究では,オープンエリアで突発的,断続的に発生する離岸流と,突堤に沿って連続的に発生する離岸流を対象に,特性の異なる2種類の離岸流を検知できる単一のAIモデルの構築を試みた.最終的に,離岸流の検知精度がAccuracy = 87%,Precision = 48%, Recall = 100%のAIモデルを構築した.構築したAIモデルを現地海岸に適用した結果,オープンエリアと突堤に沿って発生する離岸流を検知することができ,AIによる離岸流検知エリアは実際の離岸流発生箇所と概ね一致し,単一のAIモデルが特徴の異なる離岸流を検知可能であることを確認した.一方,オープンエリアでの断続的な離岸流の発生については適切に検知できていたが,突堤に沿った連続的な離岸流については見落としが多くあったと考えられた.
抄録全体を表示
-
志村 智也, 西村 柚希乃, 森 信人, 宮下 卓也, 馬場 康之, 島村 翔, 安田 誠宏
2022 年78 巻2 号 p.
I_397-I_402
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
台風による高波の外洋での観測はこれまで非常に限られていた.本研究では2021年の夏季台風シーズンを対象として,最新の小型GPS波浪ブイの複数台の展開および波浪観測衛星データの活用により,ほとんど行われてこなかった外洋でのスペクトル情報を含む台風高波観測を実施した.外洋で10mを超える有義波高の台風高波を複数地点で観測できており,台風高波の物理過程の理解にとって非常に有用なデータとなる.観測値と波浪モデル推算値を比較した結果,推算値では高波浪の再現精度が悪く,波高および周期を過少評価,周波数分散を過大評価することがわかった.また,推算値はブイより衛星観測値との相関が高く,ブイで捉えられるような局所的な波浪変動を表現するには課題があることがわかった.
抄録全体を表示
-
春山 和輝, 豊田 将也, 加藤 茂
2022 年78 巻2 号 p.
I_403-I_408
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
勢力の強い台風襲来時の中小河川では,洪水流が短時間のうちに河口に到達するため,高潮と洪水のピークが重なりやすく複合氾濫に対するリスクが高い.これまでに複合氾濫に対する検討は主に一級河川を対象としており,中小河川での影響を定量的に評価した研究はほとんど行われていない.本研究では,流域全体と河口域の高解像度計算を組み合わせ,2018年台風24号を対象に愛知県東三河地方の二級河川(柳生川,梅田川)における水位に関する計算を実施した.再現計算とピーク時刻に関する感度実験の結果,柳生川および梅田川では高潮・洪水のピーク時刻が重複し,高潮・洪水が単一で発生する場合に比べて柳生川で14.3%,梅田川では5.0%の水位上昇効果が明らかとなった.さらに,複合氾濫発生を想定した氾濫実験では橋梁付近の河川狭窄部が複合氾濫に脆弱な地点であることも明らかとなった.
抄録全体を表示
-
川崎 浩司, 二村 昌樹, 山本 剛士, 村上 智一, 下川 信也
2022 年78 巻2 号 p.
I_409-I_414
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
本研究では,海域で国内唯一の自然環境保全地域に指定されている沖縄県西表島の網取湾で,20m/s以上の風速を観測した台風1513号を対象に3次元流動解析を行った.現地で観測された流速との比較を通して,台風モデルで使用される海面抵抗係数とスマゴリンスキー係数が解析結果に与える影響を評価した.解析結果から,網取湾の3次元流動特性を検討した.海面抵抗係数について,従来使用されてきた風速に対して単調増加する式を使用すると流速を過大評価する結果になり,ある風速下で海面抵抗係数の増加を制限することが望ましいことが示された.また,網取湾ではリーフ地形が広がる特異な地形条件であることが,流動場に大きく影響していることが明らかとなった.本研究より,台風時の複雑な流動場がサンゴ等の生息環境に影響を及ぼしていることが示唆された.
抄録全体を表示
-
佐々木 達生, 西田 渉, 本橋 英樹
2022 年78 巻2 号 p.
I_415-I_420
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
平成30年台風21号では,錨泊中の油タンカーが走錨,漂流に至り,関西空港連絡橋に衝突し,連絡橋としての機能を喪失する被害が生じた.本研究は,錨泊中の船舶が走錨,漂流で重要なインフラ施設へ被害を及ぼす可能性を踏まえ,漂流物の移動予測に資する知見を得ることを目的とする.台風によって発生する高潮と波浪により,漂流物がインフラ施設に衝突するプロセスの再現を試みた上で,3次元流体解析による外力推算に基づいて,漂流経路の簡易予測手法の検討を行った.境界条件を固定とした船舶の3次元モデルにより船舶が受ける主要な外力として波漂流力と風圧力から数値積分した移動方向と移動距離は,見かけ上は実態を概ね再現するものの,十分な精度とはいい難い.これは評価していない他のパラメータ設定が不十分であり,検証の継続が必要である.
抄録全体を表示
-
白井 知輝, 盛田 理子, 榎本 容太, 有川 太郎
2022 年78 巻2 号 p.
I_421-I_426
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
津波来襲時の漂流物の挙動には大きな不確実性が伴う.現状では,漂流物の形状や比重の違いによって,漂流挙動のばらつき度合いがどの程度変わるのかという点に関して知見が不足しており,数値計算におけるばらつきの評価についても改善の余地がある.そこで本研究ではまず,漂流物の形状と比重を変えた場合の漂流挙動への影響を,水理模型実験を行い評価した.次に,本研究の実験結果を元に,ランダム移動モデルにおいて漂流挙動の不確実性の大きさを表現する係数αの値を見積もり,数値計算に適用した.結果,漂流挙動の不確実性を定性的に再現するためには,既往研究で用いられることが多いαの,10倍程度の値を用いる必要があることがわかった.今後,特に漂着直前の漂流挙動の再現精度向上に向けて,喫水の影響を考慮したαの検討が必要となる.
抄録全体を表示
-
宇多 高明, 内藤 慎也, 住田 哲章, 五十嵐 竜行, 芹沢 真澄
2022 年78 巻2 号 p.
I_427-I_432
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
清水海岸における堤防前面での養浜盛り土後の地形変化を予測するために,堤防前面での土砂投入を正確に表現可能な土砂の湧き出し方式を考案し,これをBGモデルに組み込んだ.その上でこのモデルを清水海岸での新型2号堤建設時の地形変化予測に適用した.この結果,景観改良のために行う予定の既設2号堤の段階的撤去とともに,長さ80mの新型2号堤(北)(南)を配置し,年間8万m3の養浜を行えば,清水海岸の目標浜幅80mの達成が可能なことが明らかになった.
抄録全体を表示
-
田﨑 拓海, 原田 英治, 後藤 仁志
2022 年78 巻2 号 p.
I_433-I_438
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
前浜では往来する遡上波により活発な漂砂が生じ,透水性斜面における流体の浸透・滲出が底質の輸送に影響する.複雑に変化する自由水面下の漂砂過程の計算は,波動場の解析に高精度MPS法を採用し移動床を構成する個々の底質を個別要素法で追跡するDEM-MPS法により実施されてきたが,干出部への流入時の液相体積保存を考慮した漂砂過程の解析は実施されていない.本研究では,体積保存型のDEM-MPS法による遡上波解析を実施し,水面形状や遡上距離の解析における従来型DEM-MPS法に対する優位性を示す.また,斜面への浸透・滲出流や底質へ作用する流体力の分布から,遡上波下の浸透・滲出による流体力が斜面方向と比較して,無視し得ない程度の効果を持つことを示唆する.移動床表層の応力鎖から,引き波時の移動床骨格構造の締固まりによる底質の移動抵抗の増加と,それに伴う漂砂の抑制を示す.
抄録全体を表示
-
加藤 佑典, 越智 聖志, 宮武 誠, 佐々 真志, 坪川 良太, 牛渡 裕二, 飯田 泰成, 阿部 翔太
2022 年78 巻2 号 p.
I_439-I_444
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
北海道内の沿岸道路における非越波条件下の高波浪時に護岸擁壁背後法面で発生する陥没型被災に関して,移動床水理模型実験を実施し,浸透流動の逆推定解析を行った.実験は,まず後浜から地下水位のみを与え,水圧計を用いて法面砂層内の地下水位を確認した.その後,当該海域における1年確率波を作用させた場合と波浪作用無しの2つのケースにおいて,蛍光塗料を注入し,その流動を追跡することで,逆推定解析を実施した.解析の結果,後浜地下水位のみを与えた場合は岸沖方向に卓越していた浸透流向が,波浪を作用させた場合には,擁壁背後で大きく下向きに転じ,既往研究で明らかにした陥没型被災の崩壊方向角度と概ね一致することより,陥没型被災と浸透流動の関係性が示唆された.
抄録全体を表示
-
辻本 剛三, 金 洙列
2022 年78 巻2 号 p.
I_445-I_450
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
自然界の流動系の配置は流動抵抗を低減するように進化しなければならないとするコンストラクタル法則に基づいて,底質粒径と前浜勾配の動的な関係を波形勾配と逸散型,中間型,反射型の海浜タイプで再整理し,既存の観測データが曲線内に分布していることを確認した.底質粒径と前浜勾配の動的な関係から汀線での前浜勾配を定義し,BruunやKriebelによる平衡断面形状の評価式に取り込み,波浪の変化による陸域から沖合までの断面の変動を示すことが可能となった.
鳥取砂丘海岸の1973年から1984年の深浅測量結果を平衡断面として,観測期間内の平均波浪と最大波浪の変化による底質粒径と前浜勾配の動的関係からBruunやKriebelによる平衡断面形状を比較した.側線によっては平均波浪下での水深7m付近までの断面形状が再現されている.
抄録全体を表示
-
乳原 材, 内山 雄介, 小硲 大地
2022 年78 巻2 号 p.
I_451-I_456
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
内湾における海底地形の形態変化および形成機構を定量的に評価するために,高解像度領域海洋循環モデルROMSによる流動シミュレーション結果を用いたオフライン計算による,多粒径土砂に対応した水深積分型の浮遊土砂輸送モデルと,掃流輸送・地形変動を事後的に算定する地形変動モデルを開発し,明石海峡周辺海域へ適用した.浮遊砂輸送モデルは土砂の平面的な移流分散特性を現実的に表現し,大規模地形の形態変化を評価する上で十分な再現性を有することを確認した.明石海峡周辺における流動構造は現況の海底地形の継続的な形成を促進するとともに,大規模な形態変化を引き起こしている可能性が高いことや,大規模砂堆は鹿ノ瀬と沖ノ瀬では底層流と土砂フラックスの収束特性や掃流輸送の寄与などの土砂輸送形態が異なり,大潮期強流イベント時に土砂輸送が強化されるなどの幾つかの重要な知見を得た.
抄録全体を表示
-
横田 拓也, 小林 昭男, 宇多 高明, 野志 保仁
2022 年78 巻2 号 p.
I_457-I_462
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
千葉県君ヶ浜では,人工リーフの建設後その背後に舌状砂州が形成されたが,その後風の作用により舌状砂州から内陸への飛砂が活発化した.そこでBGモデルとセルオートマトン法を組み合わせることにより波による漂砂と飛砂を同時に考慮可能な海浜変形予測モデルを用いて海浜変形予測を行った.現地実測データを基に現象の再現計算を行った上で,人工リーフを撤去した場合の地形変化予測と,海浜砂と同じ粒径の細砂を用いた養浜を行った場合の地形変化予測計算を行った.細砂海岸に人工リーフなどの消波構造物を設置すると,飛砂による内陸への砂移動が助長されることが示された.
抄録全体を表示
-
高橋 紘一朗, 宇多 高明, 小林 昭男, 星上 幸良, 野志 保仁
2022 年78 巻2 号 p.
I_463-I_468
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
環境指標の一つである海浜植生は,砂丘安定化や飛砂抑制の効果を有しており,今後の海岸づくりを進めていく上で考慮すべき項目の一つである.このことから,沿岸に各種施設が造られて波浪場が変化する場合も含め,海浜地形と植生帯前縁線の位置を予測するモデルを開発した.5海岸において海浜植生帯の繁茂状況を調べた上で,波浪データに基づいて多年草からなる植生帯の前縁線標高と平均遡上高の関係を調べ,これとBGモデルによる地形変化計算とを組み合わせ,海浜変形に伴う多年草繁茂域の前縁線位置の予測モデルを構築した.モデルは検見川浜を対象として妥当性を検証した.
抄録全体を表示
-
Mustarakh GELFI, Takayuki SUZUKI, Ravindra JAYARATNE
2022 年78 巻2 号 p.
I_469-I_474
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
The existing predictive landward structure scour depth equation of Jayaratne et al. (2016) is able to foresee the scour depth induced by overflowing tsunami wave. The equation comprises several measurable parameters in the field such as dike height (Hd), inundation depth (h), and landward structural slope (𝜃). However, implementing the predictive depth equation urges careful attention due to simplification of the fitted coefficient (𝜆). This study explores the sediment size effect to the landward scour depth equation through laboratory investigation. Three different sediment sizes were tested and repeated three times during experiments to make total of nine test runs. Main scour feature of scour depth (Ds) is scrutinized to get an in-depth understanding of landward toe scour behavior in relation to median sediment size (D50). In addition, we also show that in analyzing scour extent (length, Ls), sediment size effect cannot be easily omitted. This study found that in the range of non-cohesive sand samples in the range of D50 = 0.30- 2.56 mm, Ds and Ls tend to be inversely proportional to the grain size. Therefore, we propose to revise the fitted coefficient (𝜆s) to be a function of D50 in applying existing scour depth predictive equation of Jayaratne et al. (2016). Regarding Ls, further work is required to explore the effect of sediment size on Ls.
抄録全体を表示
-
青木 健太, 谷上 可野, 片山 裕之, 三浦 成久, 鈴木 崇之
2022 年78 巻2 号 p.
I_475-I_480
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
水深20m超となる大水深での着床式洋上風力モノパイル基礎は,長期安定性の観点から洗掘対策が要求されている.著者らは,波のみを外力とした移動床模型実験によりモノパイル基部の局所洗掘と袋型根固材を用いた洗掘対策工敷設範囲の検討を行った.しかし,洋上風力推進海域の海流は表層において約1.0m/sあることが確認され,また既往の研究により波と流れの同時作用の場合には,波だけの場合より局所洗掘深が増加する報告もなされている.このように安定性の検討には波のみならず流れの影響も考慮することが必須である.そこで本研究では,波と流れによるモノパイル基部局所洗掘および袋型根固材を用いた洗掘対策工効果検証を目的とした移動床模型実験を実施し,袋型根固材による洗掘対策工が波と流れに対しても効果があることを確認した.
抄録全体を表示
-
宇多 高明, 小嶋 崇央, 大木 康弘, 村田 昌樹
2022 年78 巻2 号 p.
I_481-I_486
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
大津漁港~高戸鼻間の長さ13.5kmの弓状に延びた砂浜海岸では,北端に位置する大津漁港近傍で堆砂が進み,対照的に大津漁港の南側海岸では侵食が進んできている.この地形変化の機構を明らかにするために,大津漁港~高戸鼻間を対象に粒径を考慮した等深線変化モデルを用いた計算を行った.既往地形変化の再現を行うとともに海浜形状の将来予測計算を行った.解析の結果,大津漁港のつくる波の遮蔽域へと向かう北向きの沿岸漂砂が今後も続くために,天妃山(岩礁)の北側隣接部にある磯原海岸や,天妃山以南の海岸で侵食が激化することが分かった.
抄録全体を表示
-
内藤 慎也, 住田 哲章, 宇多 高明, 三波 俊郎
2022 年78 巻2 号 p.
I_487-I_492
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
清水海岸では,2019年11月~2021年7月に三保松原砂嘴先端部からサンドリサイクルにより調達した土砂10.1万m3と,安倍川河道の採取土砂3.3万m3,合わせて13.4万m3の土砂による養浜が行われた.養浜は,トラック輸送された土砂を堤防前面で盛り土する方式で行われた.本研究では,空中写真や深浅測量データを用いて,まず清水海岸の長期的な地形変化について調べた上で,この間新設された新型突堤の背後域で行われた集中的盛り土養浜の効果について調べるとともに,残された課題について考察した.
抄録全体を表示
-
宇多 高明, 居波 智也, 櫻田 哲生, 五十嵐 竜行
2022 年78 巻2 号 p.
I_493-I_498
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
沼川第二放水路にある3本の水路のうち東端を流れる1号水路では,函体内堆砂が少ない条件では,吐口前面の地盤高を函体の天端高より約0.5m下げればフラッシュ放流が可能である.一方,放水路の西端を流れる3号水路では,放水路による沿岸漂砂阻止による堆砂があるため,1号水路と同様な方式でのフラッシュ放流はできない.そこで3号水路について移動床水理模型実験を行い,掘削深や吐口形状を変えたフラッシュ放流実験を行った.この結果,3号水路では吐口から放水路上に斜め下流へと向いた溝を掘り,これに沿って流水を流せばフラッシュ放流が可能なことが分かった.
抄録全体を表示
-
佐藤 愼司
2022 年78 巻2 号 p.
I_499-I_504
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
地形と底質の変化が激しい離岸堤背後の砂礫海岸において,UAVによる高頻度現地観測を実施した.砂礫は標高に応じて帯状に分布し,標高の高い領域と汀線近傍では砂,その間の領域では礫が卓越していた.地形変化は汀線近傍ほど大きく,来襲波の遡上標高や波向きに強く影響を受けるのに対し,砂礫の変化は,標高の高い領域でも大きく,潮汐などの常時外力の影響を強く受ける.また,堆積が生じる場合には,底質が砂から礫に変わることが多く,礫から砂になる場合には侵食している場合が多い.これらにより,混合砂礫海浜の分級過程には,地形変化と表層砂礫の間により直接的な機構が介在していることが示唆された.
抄録全体を表示
-
武若 聡, 内堀 圭一郎
2022 年78 巻2 号 p.
I_505-I_510
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
2006年から2016年の間に収集された衛星シーンから延長約16kmの鹿島灘南部砂浜の汀線位置を読み取った.汀線位置の読み取りには,2006年-2011年はSAR衛星(ALOS,22シーン),2011年-2016年は可視衛星(Landsat,79シーン)とSAR衛星(ALOS-2,10シーン)の111シーンを使用した.砂浜の南部に設置されている5基のヘッドランド間の汀線変動の特徴を調べた.ヘッドランド間の汀線分布の平均位置と傾きを求めたところ,それぞれに季節的な変動が,また,両者の間に高い相関が見られた.観測域では夏季に南方から相対的に小さい波の入射が,冬季に北方から相対的に大きい波入射波が多く,これに呼応する形で汀線の平均位置,傾きが変動していた.前者が岸沖方向の,後者が沿岸方向の漂砂によると仮定した分析を行った.
抄録全体を表示
-
鈴木 崇之, 安田 永遠, Mohammad TABASI , 比嘉 紘士
2022 年78 巻2 号 p.
I_511-I_516
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
砂浜海岸では,汀線近傍において沿岸方向に凹凸状のリズミックな地形が形成される.このうち,波長が100mオーダーのメガカスプの形状の変化の解析を目的とし,茨城県の波崎海岸にて測量された約30年間の地盤高データからカスプ波高(凸部から凹部までの長さ)を算出し,波浪データとの関係性を検討した.その結果,高波浪イベント後,カスプ波高は増加,減少,変化しないの3パターンに分類ができた.また,これらのパターンは高波浪イベント直後のカスプ波高に依存しており,15m未満では増加傾向,それ以上の値では減少傾向となっていることが分かった.イベントの波浪エネルギーフラックスとの関連性を検討したところ,カスプ波高増加のパターンでは,そうでない場合に比べエネルギーフラックスの沿岸方向成分が占める割合が大きいことが分かった.
抄録全体を表示
-
石川 仁憲, 宇多 高明, 田村 貴久, 中野 優, 長谷川 準三, 芹沢 真澄
2022 年78 巻2 号 p.
I_517-I_522
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
茅ヶ崎海岸では,後浜において盛り土養浜が行われている.既往の地形変化予測モデルでは,波の作用により盛り土が削り取られて汀線へと供給される現象を,水面下での砂の湧き出し方式で表現しているが,実際には浜崖後退に伴って土砂が供給がされることから,両者に物理的な相違があった.本研究では,土砂の湧き出し範囲で盛り土の限界高さを超えて堆積する土砂を沖側の計算点に移す方式をBGモデルに組み込んでモデル化し,茅ヶ崎海岸の沿岸方向6km,岸沖方向2.6kmの区域にこのモデルを適用した.また,2019年10月12日に襲来した台風19号に伴う高波浪による急激な沖向き漂砂による地形変化を,平衡勾配の変化としてモデル化し,計算を行った.計算結果は,実測地形変化とよい一致をみた.
抄録全体を表示
-
辛 翔, 青木 伸一, 岡辺 拓巳
2022 年78 巻2 号 p.
I_523-I_528
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
本研究では,海食崖前面で発達する砂丘の形成メカニズムを明らかにするために,渥美半島表浜海岸に位置する伊古部砂丘を対象として,砂丘形成の必要条件である砂浜幅と風外力に着目して検討を行った.砂浜幅については,その経年変化と砂丘の消長に明確な対応関係があり,近年の砂丘の再形成は海岸保全事業による砂浜の回復に起因していることがわかった.風外力については,砂丘周辺で種々の風観測を実施するとともにCFDを用いて検討した.その結果,砂丘前面の砂浜で観測される風は,北西の季節風が卓越する冬季であっても,高さ20m程度までは南西方向から崖に向かって強い風が吹いており,これが砂丘を形成する外力となっていることがわかった.この風は,崖地形による後流渦の形成に伴う逆流として生じていることを数値計算により確認した.
抄録全体を表示
-
宇多 高明, 星上 幸良, 和知 久仁彦, 大木 康弘, 押見 青幹
2022 年78 巻2 号 p.
I_529-I_534
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
阿字ヶ浦海岸では2021年夏季にサンドリサイクルが行われた.その際,養浜盛り土後の海浜変形と掘削域での再堆砂状況をUAV測量により調べた.UAV測量は養浜直後の2021年7月16日を初回とし,養浜から3,6か月経過後の2021年10月15日と2022年1月17日に行った.投入土砂は養浜から3か月後には北向き漂砂によりその大半が運び去られ,さらに6か月後には海浜はほぼ土砂投入前の姿に戻った.これより現行方式でのサンドリサイクルの継続実施は疑問であり,適切な漂砂制御施設を配置し,養浜砂が投入箇所に安定的に留まることが可能な方式へと改善することが必要なことが分かった.
抄録全体を表示
-
中道 誠, 佐藤 愼司, 多田 直人, 髙山 靖史, 山本 隼也, 松本 知晃
2022 年78 巻2 号 p.
I_535-I_540
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
高知海岸では,河川からの供給土砂が減少したことで,海岸侵食が問題となっている.さらに,気候変動による海面上昇や波向の変化等に伴って海岸侵食の進行が懸念されている.本研究では,物部川流砂系海岸を対象に,気候変動が海浜変形に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし,これまでの汀線変化状況の実態分析と等深線変化モデルを用いた現状の漂砂移動特性の検証を行うとともに,観測データに基づく潮位・波浪の変化特性に関する分析を実施した.これより,現状でも潮位に加え波浪も気候変動の影響が顕在化し始めていること,近年の波向は僅かに東方向(反時計周り)へ変化し西向きの漂砂量が増大傾向にあることがわかった.また,河口の両岸で西向きの漂砂が卓越しており,反時計周りの波向変化は東側の海岸侵食を深刻化させることが確認された.
抄録全体を表示
-
宇多 高明, 内藤 慎也, 岩辺 路由, 大石 昌仙, 竹内 由衣, 石橋 さくら
2022 年78 巻2 号 p.
I_541-I_546
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
御前崎港の東側に造られたマリンパーク御前崎では,御前崎の白羽地区方面からの沿岸漂砂による大量の堆砂が課題となる一方,白羽地区では侵食が進んでいる.そこで過剰な堆砂と侵食を解決する一手段として,マリンパーク御前崎から白羽地区へのサンドリサイクルが行われてきた.しかしながら投入砂は直ちに流出し,必ずしも期待する効果が得られていない.本研究では,空中写真や深浅測量データを用いてマリンパーク御前崎と白羽地区の海浜地形変化を解析し,現況のサンドリサイクルの効果と課題を整理し,今後の侵食対策方法について考察した.
抄録全体を表示
-
片野 明良, 清水 利浩, 千田 奈津子, 眞井 里菜, 有川 太郎
2022 年78 巻2 号 p.
I_547-I_552
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
海浜上を斜めに移動する飛砂を遮断し,ある領域内に閉じ込めるという発想に基づき,汀線に平行な堆砂垣と堆砂垣からある一定の距離(離垣距離)を隔て,岸沖方向に設置する縦堆砂垣群の配置を考案した.離垣距離は隅角部に集中する飛砂の一部を風下側に流出させ,かつ垣設置時,維持管理作業用に利用する.配置の特徴は,縦堆砂垣の長さと縦堆砂垣間の距離を調整することにより飛砂の捕捉範囲を任意に決めることができることに有る.現地実験は以下の結果を示した.縦堆砂垣群配置は意図したように飛砂制御をしている.汀線に平行に設置される堆砂垣と直交する縦堆砂垣周辺の堆積量から飛砂量が算定できた.汀線に平行に設置される堆砂垣と縦堆砂垣の飛砂通過断面の中央点を通り卓越風向に平行な汀線から堆砂垣までの距離(飛砂発生可能砂面長)は飛砂発生域の特性を示す指標になり得る可能性がある.離垣距離5mは適切に機能する.
抄録全体を表示
-
清水 利浩, 千田 奈津子, 眞井 里菜, 片野 明良, 小川 秀成
2022 年78 巻2 号 p.
I_553-I_558
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
侵食対策として養浜した砂浜は,防護面だけでなく利用や環境性に優れている.この砂浜を長期的に適切に維持するためには,海岸特性を把握した上で,管理指標を明確にし,日々の点検を適切に実施する必要がある.砂浜を海岸保全施設として管理するためには,施設としての健全度を事前に定めておくことが重要となる.しかし,砂浜はコンクリート構造物とは違い常に変形するため,管理指標を一律に規定することが困難であり,健全度を定める手法は確立されていない.そこで,沿岸漂砂の収支による地形変化がほとんどない新潟港海岸をケーススタディとして,砂浜の健全度指標を検討し定義した.砂浜の健全度は他の海岸構造物と同様にランク分けし,供用期間に応じて監視すべき浜幅を変動させる考え方を導入した.本研究は,海岸特性が十分に観測できている海岸で適用できるものである.
抄録全体を表示
-
山邊 凜, 佐々木 勇弥
2022 年78 巻2 号 p.
I_559-I_564
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
天竜川河口部において2018年10月洪水後の約2か月半の間に河口砂州がおよそ600m回復,伸長した.この急激な河口砂州回復過程を明らかにすることを目的に,河口部に設置した定点観測カメラ画像の解析を行った.その結果,この急激な河口砂州の回復は,河口砂州付け根側からの沿岸漂砂によってではなく,河口開口部周辺に堆積していた土砂の河口砂州先端部への移動と河口砂州とは独立して河口部に出現,発達した島の河口砂州への結合によって引き起こされたことが分かった.また,河口砂州先端部に集まるように波の屈折が生じていたことが堆積土砂の河口砂州への帰着に寄与し,発達した島の水際線と波向きの関係が島から河口砂州に向かう沿岸漂砂を生じさせ,島の河口砂州への結合に寄与したと考えられた.
抄録全体を表示
-
蜜澤 岳, 百瀬 年彦, 勝見 尚也, 鴈澤 好博
2022 年78 巻2 号 p.
I_565-I_570
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
手取川流砂系における沿岸漂砂の移動方向を推定するため,手取川中流域-手取川河口-能登方面の約95kmの範囲における河川砂および海岸砂の色をL*a*b*空間で数値化し,a*値(赤成分の強さ)とb*値(黄成分の強さ)を分析した.河川砂のa*値とb*値は河口付近で急激に増加し,河口から能登方面にかけて,a*値とb*値は順次増加することが示され,能登方面の海岸砂は,手取川河口周辺と比べて,赤黄色化が進行していることが明らかとなった.砂の赤黄色化は,無色鉱物が鉄さびに被覆されることによって生じることも示された.鉄さびが,塩水や空気と接する環境下で時間とともに生成されることを踏まえると,手取川流砂系における沿岸漂砂は北向き(手取川河口から能登方面)に移動すると考えられた.
抄録全体を表示
-
渡邊 国広, 加藤 史訓, 諏訪 義雄, 山田 浩次
2022 年78 巻2 号 p.
I_571-I_576
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
日本における砂礫浜の全国的な変化傾向を把握する目的で4時期の地形図から砂礫浜の汀線及び陸側境界を判読して比較した結果,1992年から2006年にかけて砂礫浜の面積は115×104m2/年の速度で減少しており,延長では250kmの砂礫浜が消失したことがわかった.陸側境界の変化による面積減少は143×104m2/年と算定され,汀線後退による減少量と比較して無視できないばかりか1978年~1992年よりも面積減少が加速していた.1978年~1992年に汀線が前進傾向にあった箇所のうち約53%において後退に転じており,侵食域を移しながらも後退箇所が存続していることが確認された.汀線変化の傾向は海中を含む土砂量変化の傾向と概ね整合していたものの,汀線が後退していなくとも土砂量が減少した海岸もあり,海中における土砂消失の進行にも留意する必要があることが示唆された.
抄録全体を表示
-
鈴木 崇之, 胡 佳一, 吉村 那月, 比嘉 紘士
2022 年78 巻2 号 p.
I_577-I_582
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
養浜事業は海岸構造物の有無にかかわらず海岸侵食対策として多くの地域で実施されている.陸上養浜では遡上波による侵食作用により底質は徐々に海浜部に流出するが,養浜部の底質粒径や締固め度合いの違いによる流出量への寄与に関する検討はまだ十分とは言えない.そこで,本研究では異なる2種類の中央粒径を使用すると共に初期締固め度合いも変化させ,両者が養浜部の地形変化(侵食)に与える影響を明らかにすることを目的とした室内実験を実施した.解析では中央粒径0.32mmの結果も加えて検討を行った.その結果,波が養浜部を超えない場合,中央粒径0.32,0.70mmでの侵食量はほぼ同等であったが,0.08mmはそれらの約2倍であった.また,波が養浜部を越える場合,中央粒径が小さくなるにつれて侵食量は大きくなり,底質の影響が大きく表れることがわかった.
抄録全体を表示
-
楳田 真也, 有田 守, Tussanun THUNYAPHUN , DO Quynh Nhu , 由比 政年
2022 年78 巻2 号 p.
I_583-I_588
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
石川海岸の砕波帯から沖合における底質粒径の岸沖・沿岸方向変化および手取川の土砂管理が現在に近い状態が続いている最近20年余りの沖合海底地形の変動状況を明らかにするため,底質調査と地形解析を行った.砕波帯沖の粒度組成の沿岸方向変化は,海岸流により底質が分級し,漂砂下手側で細粒化する傾向を示した.岸沖方向の粒度組成の変化は砕波点から沖向きに細粒化する傾向を示したが,水深15~18m付近を境に沖側で粗粒化した.砕波帯沖で粗粒径成分が多く含まれる地点は侵食傾向にある領域に位置していた.松任地区沖合では,沖合侵食によって海水準が現在より低い時代の陸上堆積物が海底表層に近年露出するなどしたため,表層底質の粗粒分の割合が増加した可能性がある.
抄録全体を表示
-
渡部 正一, 村野 幸宏, 服部 博, 浅野 剛, 後藤 英生
2022 年78 巻2 号 p.
I_589-I_594
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
駿河湾奥に位置し,海底谷が海岸付近まで迫る富士海岸吉原工区では,侵食対策として動的養浜が実施されているが,土砂の沖流出などもありそのコスト縮減が課題であったことから「土砂流出防止工」が検討され,2013年から2018年にかけて設置された.
本研究では,この海底谷の急勾配斜面上辺付近に設置された土砂流出防止工について現地調査を行い,土砂流出防止工設置前後の地形変化および底質変化から土砂流出防止工周辺の土砂動態を把握し,その効果検証を行った.その結果,土砂流出防止工設置以前は,高波浪によると思われる海底谷への土砂流出が生じていたが,土砂流出防止工の整備により沖流出が軽減され,土砂流出防止工の効果が発現しつつあることが明らかとなった.
抄録全体を表示
-
川崎 浩司, 山本 剛士, 松下 紘資, 平石 哲也, 間瀬 肇
2022 年78 巻2 号 p.
I_595-I_600
発行日: 2022年
公開日: 2022/11/01
ジャーナル
フリー
海上空港施設では,建物の高さ制限により護岸の嵩上げが難しいことから,護岸前面に消波工を設置することが多い.また,海上から空港施設内への侵入防止の観点から消波工と護岸の間に切り欠きを設けることがある.本研究は,切欠きを有する消波工を対象に数値解析を行い,消波護岸の被覆形式の違いによる越波流量を評価した.全断面被覆形式の切欠きの有無による越波流量を比較すると,切欠きを有した方が越波流量が大きくなること,全断面被覆形式と二層被覆形式の比較より,既往の実験結果と同様,全断面被覆形式の方が越波流量が大きくなることが確認された.さらに,計算解像度,評価時間の観点から,数値解析により越波流量を評価する際の留意事項について整理した.
抄録全体を表示