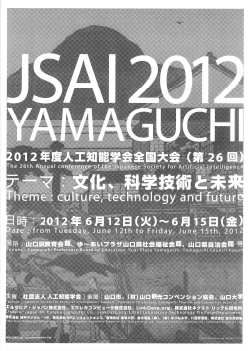-
山川 宏
セッションID: 3N1-OS-21-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
フレームを自動生成する機能は,推論の柔軟性向上に役立つが,計算機で未実現である一方,動物の脳では実現している.課題である,膨大なフレーム探索範囲の削減には変数間関係の同一性を用いるのが有効である.本稿では,脳における記憶整理機能の特徴を参考とし,高次元二値分布における関係の同一性として反転分布について対称性を仮定すると得られる縮約表現が候補となりうることを議論し,その基礎的な性質について述べる.
抄録全体を表示
-
杉浦 元亮
セッションID: 3N1-OS-21-10
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
脳機能計測、特に機能的MRIをAI研究に応用する際に重要な実験デザイン上の考え方を2点提案する。まず1点は適切な統制条件の重要さである。ここでは人間の認知過程の奥深さと解析・解釈の見通しを十分に配慮する必要がある。もう1点は“脳機能も計測してみる”という「追加」的な発想を避けることである。脳機能計測を上手に使う研究コンセプトは3つある。脳機能計測の応用研究は脳機能計測のプロとの恊働が得策である。
抄録全体を表示
-
松浦 弘幸, 和崎 克己
セッションID: 3N1-OS-21-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
神経細胞の軸索伝導の活動,つまり,脱分極,再分極課程の神経活動インパルスの波形を,分極ベクトルの回転を考える事により,そして,軸索上をその分極ベクトルが回転して伝搬するというモデルを作成した.神経軸索の膜上を伝搬する分極ベクトルは,水分子による水和を考慮すると高々,電子の質量の10倍程度の水和イオン粒子(qusai-particle),つまり準粒子(ポラリトン)と見せる.
抄録全体を表示
-
小島 昇, 下園 惇平, 江上 心太, 秋山 英久, 三島 健司, 荒牧 重登
セッションID: 3N1-OS-21-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究では、脳血流測定を用いた人間による意思決定の識別を目的とする。タスクとして左右判別を設定し、人間が左右を決定した際の脳血流の特徴をより効果的に測定するための条件設定について調査する。実験では、近赤外光脳機能イメージング装置(fNIRS)を用いて識別精度の向上を目指す。
抄録全体を表示
-
光田 友里恵, 後藤 かをり, 参沢 匡将, 下川 哲矢, 広林 茂樹
セッションID: 3N1-OS-21-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
近年では脳機能計測機器の利用が医療・福祉分野だけではなく,経営・経済分野にまで広がっている.その背景には消費者の購買行動が必ずしも合理的ではないところに着目し,購買行動中の脳活動から消費者の心理を探り,マーケティングに活かそうという狙いがある.本研究では購買意思決定要因の一つである価格に焦点を当て,将来的な価格評価システム構築のためにNIRS(近赤外線分光法)を用いた価格評価の基礎研究を行った.
抄録全体を表示
-
三野 哲志, 参沢 匡将, 広林 茂樹
セッションID: 3N1-OS-21-5
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
近年,脳情報を入力としてユーザの意図を反映するBrain Computer Interface(BCI)の研究が盛んに行われており,麻痺患者等のコミュニケーション支援システムとして期待されている.本研究では,近赤外分光法(NIRS)を用いて前頭前野の脳活動を計測し,得られた脳情報によってカーソルコントロールを行うBCIを作成し,その有効性について検証を行った.
抄録全体を表示
-
後藤 かをり, 参沢 匡将, 広林 茂樹
セッションID: 3N1-OS-21-6
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
近年Brain-Computer Interface(BCI)の開発が盛んに行われている.近赤外分光法(NIRS)を用いたBCIの開発にあたり,NIRSで計測可能な血流変化に対応する脳活動は脳波計(EEG)に比べ反応に時間が掛かることから,本研究では短い時間でより情報量を反映させる手法として複数の認知タスクを用いることによる2択以上の判別可能性およびその精度向上について検討を行った.
抄録全体を表示
-
石井 孝洋, 金 天海, 仁科 繁明, 菅野 重樹
セッションID: 3N1-OS-21-7
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
視触覚刺激による身体イメージ転移錯覚の一つとしてラバーハンドイリュージョンが知られている.この種の錯覚下では転移先の身体が受ける感覚を自分の身体で感じるかのような反応が起こることが知られており,錯覚の生起を操作できれば新しい情報呈示方法等への応用が考えられる.本研究では杭型の物体が仮想の手に刺さる映像と振動モーターを用いて,視触覚刺激の時間的同期性が身体イメージ転移錯覚に与える影響を考察した.
抄録全体を表示
-
山野 悠, Inventado Paul, Cabredo Rafael, Legaspi Roberto, 福井 健一, 森山 甲一, 栗 ...
セッションID: 3N1-OS-21-8
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
近年、人間の感性を扱う分野に関する研究が盛んに行われている。感性情報を取得するうえで脳波解析による手法は有力であり、それに関する様々な研究が行われている。しかし、脳波と感性の対応関係は未知の部分が大きい。本研究では未知である部分を解明すべく、楽曲を聴いている間の脳波と感性を対応させ、機械学習により脳波データからの感性推定器を構築した。これにより、感性をより適切に反映させた自動作曲が期待できる。
抄録全体を表示
-
森川 幸治, 足立 信夫, 入戸野 宏
セッションID: 3N1-OS-21-9
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究はテレビ画像に対する事象関連電位の分析によりユーザの 認知状態の推定を目指している。対象とした認知状態は、期待していた番組と 実際に呈示されたテレビ画像との不一致に起因する期待はずれの状態と、 見出し情報に対する関心度についてである。脳波計測は学生の実 験参加者に対して実施し、いずれもテレビ画像の呈示を起点とする 数百ms以内に認知状態と有意に相関のある電位成分を見出した。
抄録全体を表示
-
吉井 伸一郎
セッションID: 3N2-OS-7-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
多次元のデータを解析する手法として、グラフ理論を用いて情報の相関関係を解析するシステムを考案した。コミュニティ分割の手法により、各ノード間の情報類似性を分析する。これをレコメンデーションサービスと言う実業に適用した事例を紹介する。実サービスを通じて得られる、限定合理的なユーザのクリックを、当システムの教師信号として扱うことにより、自動学習型のCrowd Computingが実現できることを示す。
抄録全体を表示
-
鈴木 健
セッションID: 3N2-OS-7-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
システム自体が一種のセンサーモーター系をもつようなウェブシステムを構想し、そのシステムが集合知を実現する可能性を検討する。具体的にはソーシャルネットワークを使った民意集約システムについて考える。
抄録全体を表示
-
廣瀬 通孝
セッションID: 3N2-OS-7-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
Based on the rapid progress of digital technology, life-log technology has become popular and realistic. Currently, huge amount of data can be captured, stored and reutilized in the digital media. In this paper, experimental future estimation system as one of the most promising applications of the life-log technology is introduced. This application will be extended into the latest system called “diary of the future”.
抄録全体を表示
-
岡 瑞起, 池上 高志
セッションID: 3N2-OS-7-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
2011年の人工知能学会全国大会でも、同テーマのオーガナイズドセッションを開催しました。そこでは、Massive Data Flow (MDF) の時代に理論に何ができるか?ということをテーマにMDFを生成する立場と、MDFを解析する立場に分かれていろいろと議論を行いました。今回は、そこから一歩進んで、生成と解析という対立軸ではなく、現在、手持ちのアイディアと方法論を武器に新しい提案を行ないます。
抄録全体を表示
-
清田 陽司
セッションID: 3N2-OS-7-5
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
HTML5規格の浸透やスマートフォンなどの新たなデバイスの普及は、Web情報サービスにおけるアクセスログ解析のあり方にも大きな影響を与えている。現在はページ閲覧ログが主な解析対象であるが、より細かなユーザインタフェース上の操作に関するログデータも取得できるようになってきている。本発表では、このようなきめ細かなログデータをどのように活用すべきかについて論じる。
抄録全体を表示
-
増田 直紀
セッションID: 3N2-OS-7-6
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
近年,計測技術の向上などを背景として,人と人がいつ,どのくらいの長さだけ相互作用するか,という「テンポラル・ネットワーク」のデータが急速に蓄積されつつある.また,類似のデータは人の社会行動以外の文脈でも記録されるようになってきている.しかしながら,その解析手法の開発はまだ十分でない.本発表では,テンポラル・ネットワークとそのいくつかの解析手法を紹介し,課題,今後の展望などについて述べる.
抄録全体を表示
-
和泉 潔
セッションID: 3N2-OS-7-7
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
様々な社会的場面での大規模な行動データから、人間行動の基本パターンを抽出する。複数のパターンが集まったシミュレーションから、集団や社会の起こりうるリスクを事前に見せる。この目標のために、実世界とシミュレーションの統合に関する研究が世界中で進んできている。本分野の最新動向を紹介しながら、可能性と課題について議論する。
抄録全体を表示
-
竹内 勇剛
セッションID: 3O1-OS-3a-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究では,実世界と仮想世界という2つの作業環境において,エージェントの身体が存在する環境の違いと情報の提示内容の違いが,エージェントが行なう指示に対する人の受容頻度及び印象に与える影響を実験によって調査した.その結果,エージェントと身体を介して環境を共有することと,視界環境に直接対応した情報提示方法が,エージェントが提供する情報の信頼性を高める可能性が示唆された.
抄録全体を表示
-
西村 貴章, 明石 直也, 半田 守, 神田 智子
セッションID: 3O1-OS-3a-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
メタバース上のアバタに対しても,人間が身体性を持ち続けており,アバタとの適切な個体距離を保つための適応行動をとることを,アバタと人間間の1人称視点の相互接近実験を通して検証した.その結果,自分と異なる個体距離をとるアバタとの間に,近接相の変化,移動距離や移動回数の増加などの適応行動が見られた.また,自分と同じ個体距離をもつアバタに対しては,対人認知の主観的評価が最も高いことが示された.
抄録全体を表示
-
古谷 純, 大本 義正, 西田 豊明
セッションID: 3O1-OS-3a-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
現時点のエージェントに対するインタラクションは、強いモチベーションがなければ受動的になってしまう。この問題を解決すべく、本研究では、エージェントの行動によって、人間の能動性を引き出すことを目指した。実験でエージェントの提示する情報の内容の抽象度に変化を付け、暗黙的にエージェントの扱える情報の抽象度を人間に伝えることで人間の能動性を引き出せることが分かった。
抄録全体を表示
-
谷 尭尚, 山田 誠二
セッションID: 3O1-OS-3a-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
デスクワーク中のユーザに対する円滑な情報提示を実現するため,机上にかかる圧力を用いてユーザの繁閑を推定し,情報提示タイミングを決定する方法を提案する.机上に圧力センサシートを敷き,圧力を測定する.この圧力は,ユーザに負荷をかけずに測定でき,かつ状態推定に有用な情報が含まれている.そこからキーや腕の押圧等の特徴量を抽出し,分類学習によりユーザの状態を推定する.実験の結果,約80%の精度で推定できた.
抄録全体を表示
-
小川 貴弘, 藤原 菜々美, 尾関 基行, 岡 夏樹
セッションID: 3O1-OS-3a-5
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
我々は,エージェントの内部状態を心象を擬した映像(心象映像)によって相手に表出する“シースルーワーキングメモリ”のコンセプトを提案してきた.本研究では,エージェントの内部状態として視覚記憶の探索・回想を扱い,連想によって視覚情報をワーキングメモリに呼び出してくる手法について述べる.また,単純な連想による情報選択が,膨大な記憶に対する有効なフィルタリングとしても働く可能性について議論する.
抄録全体を表示
-
奥内 啓太, 角所 考, 小島 隆次, 片上 大輔
セッションID: 3O1-OS-3a-6
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究では擬人化エージェント間の対話において対話者間の役割関係や会話状況等の対話シーンに依存した定量的な表出傾向の違いを反映可能なノンバーバル表現の表出モデルについて検討する。具体的には人間同士の会話に見られるノンバーバル表現の表出傾向に関する社会科学の知見と実際のTV番組の会話映像を基に役割関係や会話状況による定量的な表出傾向の違いをパラメータによって制御可能な数理モデルを構築する。
抄録全体を表示
-
高橋 英之, 大森 隆司
セッションID: 3O1-OS-3a-7
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
ロボットへの擬人化処理は,ロボットへの親和性を高め,人間とロボットとの関係性を円滑にすると考えられる.しかし近年の研究で,このような擬人化処理は単一の処理ではなく,意識・無意識の処理過程が混在した多次元的なものであると考えられている.本発表では擬人化処理の多次元性について実際の人間(成人・幼児)とロボットとの実験の事例から考察したい.
抄録全体を表示
-
齋藤 千夏, 高橋 英之, 岡田 浩之, 金岡 利知, 渡辺 一郎
セッションID: 3O1-OS-3a-8
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
ヒトは無意識に動きを同調された相手に対して親和性が高まると言われている.しかし,動きの同調に対して意識的になると逆に親和性は減少することも報告されている.本研究では,富士通研究所が開発している子ぐま型ソーシャルロボットを用い,子ぐま型の自律ロボットがヒトの動きに対してアイコンタクトなどにより無意識的に同調した際に,ロボットに対する親和性が増大するのかを複数の指標から検討した.
抄録全体を表示
-
金岡 利知, 今井 岳, 立田 隼人, 渡辺 一郎, 安川 裕介
セッションID: 3O1-OS-3a-9
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
人であればさりげなく相手の興味を引くサインを出しつつ話し掛けるタイミングを伺うように、端末はユーザに対して情報の重要性・緊急性を考慮して、ユーザに迷惑・邪魔といった心理を与えないようにふるまう必要がある。今回、自然な生き物感と擬人化を特徴とする子ぐま型ソーシャルロボットを用いて、人の社会的ふるまいに基づく人に優しい情報提供技術を開発し、効果検証を行った。
抄録全体を表示
-
今井 倫太
セッションID: 3O2-OS-3b-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
制約モデルを用いて、人とエージェントのインタラクションで起きた現象のモデル化を行ない、その可能性について検討する。言語により導入される制約、非言語表現に導入される制約、環境によって導入される制約によって、人とエージェント間である発話やジェスチャがなぜ生じたのかという理由を考察する。
抄録全体を表示
-
奥野 敬丞, 稲邑 哲也
セッションID: 3O2-OS-3b-10
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
身体運動と言語表現の統合を目標とした研究の第一段階として,コーチングに用いられる動作と言語表現の統合法のモデル化を目指す.テニススイングのコーチを題材として,手本動作,学習者が行った動作,コーチが強調した手本動作およびコーチが用いた言語表現を観察・分析した.各動作間の類似性と使用された言語表現の関係性を,位相空間上でモデル化し,効率の良いコーチングを実現するための応用について議論する.
抄録全体を表示
-
上野 未貴, 森 直樹, 松本 啓之亮
セッションID: 3O2-OS-3b-11
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
テキスト情報のみによる対話システムの実現の難しさを解決することを目的として, 筆者らの共通の絵を題材にユーザとシステム間で対話するシステム Pictgent では使用する絵は事前に準備しておく必要があるが, 逆にユーザ入力から絵自体を生成したいという要求も高い. そこで,本研究では Pictgent に対話から絵を生成する機能を導入する手法を提案する.
抄録全体を表示
-
村川 賀彦
セッションID: 3O2-OS-3b-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
これまでの人とエージェントのインタラクションは,その場での行き当りばったりで検討されていて,その場面では確かにそうだが,ちょっと違った場面ではあてはまらないのではないかという疑念をいだかさせるものだった.そこに理論を持ちこんでインタラクションを汎化してモデル化できれば,そのようなことがなくなり,また,事前に検証が可能となるものと考える.はたして,モデル化が可能なものなのかを議論したい.
抄録全体を表示
-
森 直樹, 小林 一樹, 山田 誠二
セッションID: 3O2-OS-3b-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
メール着信等のPC上での情報通知は一般的にユーザ状態を考慮せず割り込んでくるため,大量の情報が通知されると,主となるタスクが阻害される問題が生じる.この問題に対し,本研究では,集中時に中心視野領域が縮小するVisual Field Narrowing現象を利用し,ユーザ状態推定不要かつ,タスクを阻害しないタイミングで情報通知を行うペリフェラルエージェントを提案する.
抄録全体を表示
-
小林 一樹, 山田 誠二
セッションID: 3O2-OS-3b-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究では注意を大きく奪わずに周辺的な認知によってユーザとのインタラクションを実現するPeripheral Cognition Technology(PCT)を提案する.ここでは,携帯情報端末の姿勢を変化させるデバイスを開発し,ユーザの作業に割り込まずに情報通知を伝達する手法について検討する.
抄録全体を表示
-
今吉 晃, 児玉 渉, 棟方 渚, 小野 哲雄
セッションID: 3O2-OS-3b-5
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究では対話者が作る社会空間を情報的に拡張するAugmented Social Space (ASS)を提案する.この空間は,対話者の属性,身体動作,距離,音声を要素とする制約の動的な振る舞いによりエネルギー場を構築し,その強度によりASS間の情報の送受信を制御する.これにより,ロボットの空気を読む機能が実現可能となる.さらにASS間のインタラクションにより対話者自身の行動も変化することを示す.
抄録全体を表示
-
尾形 正泰, 杉浦 裕太, 大澤 博隆, 今井 倫太
セッションID: 3O2-OS-3b-6
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
指に装着する指輪型のエージェントロボットを提案する.手が影絵に使われるように擬人性がある点を利用して,手にロボットデバイスを装着してエージェントの存在感を演出する.手に載せることで人間とのコミュニケーションで自然な距離を保ち,生活の中で人間の手を使う作業についてサポートをすることができる.買い物タスクに注目してユーザの行動と商品の探索を補助するシステムを設計してユーザスタディを行った.
抄録全体を表示
-
外山 紀子
セッションID: 3O2-OS-3b-7
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
前言語期の乳児と母親のコミュニケーションは,泣きや身体動作等による手がかりの発信とその読み取りによって成立する。離乳食開始当日から1年間の観察(母子3組各16回)に基づき,手がかりの意図性が母親による調律を経て明確化していく過程を報告する。離乳期の母子同様,人とエージェントの間でも現状では言語的コミュニケーションが成立する可能性は低い。この問題を解決する糸口を,離乳食場面の母子のやりとりに探る。
抄録全体を表示
-
寺田 和憲, 伊藤 昭
セッションID: 3O2-OS-3b-8
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本発表では、人間とロボットの違いの本質を定型性と逸脱性に基づいて議論する。人間は機械の振舞いに対しては定型性を期待し、人間の振舞いに対しては逸脱性を期待する。我々は、定型性に対する逸脱性こそが機械と人間をカテゴリー分類する上での決定的要因だと考える。実験結果を交えてこの論理を展開する。
抄録全体を表示
-
稲葉 通将, 平井 尚樹, 鳥海 不二夫, 石井 健一郎
セッションID: 3O2-OS-3b-9
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本論文では,人間と雑談を行うコンピュータ(非タスク指向型対話エージェント)を設計し、被験者実験を含む評価実験を行う。本研究で設計するエージェントは統計的応答手法と話題別学習という2つの特徴を持つ。統計的応答手法は、ランキング学習を用いて応答を行う手法である。また、話題別学習は、各話題に特化して学習したエージェントを複数用意し、応答するエージェントを文脈に応じて変えながら対話を進める手法である。
抄録全体を表示
-
YOUNES EL HAMDI, Takumi Okamoto, Nak Young CHONG, Il HONG SUH
セッションID: 3P1-IOS-2a-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
In this paper, we study the problem of creating an inference mechanism to recognize and respond to human behavior. We provide probabilistic methods to build a new Bayesian framework to deal with human tracking problem. Specifically, we present a set of efficient algorithms that encompass the learning solutions for practical applications which cope with unreliable and noisy measurements. Unlike almost all of related works, we propose an efficient algorithm for sensing systems that presents an alternative to sensors that are sometimes perceived as invasive, where notably we do not use vision-based learning. Preliminary results show that the proposed system can be deployed in different environments and significantly outperforms existing methods in a very reliable manner.
抄録全体を表示
-
Eleanor Clark, KENJI ARAKI
セッションID: 3P1-IOS-2a-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
We present a system for generating casual English short sentences from regular English input using a phonetic rule-based approach. This is addressed as an AI task, with the potential application of generating Twitter-style sentences for marketing or other communication purposes. Our aim was to automatically produce sentences that would appear to a human reader to be indistinguishable to sentences which are the result of human creativity. To evaluate the performance of the system, we conducted Turing-type tests with human readers, to consider firstly "human-likeness", and also "legibility" of the sentences. In this paper, we discuss the overall design of the system, the custom-made phoneme database, and the process and results of our evaluation experiment.
抄録全体を表示
-
Kristianto Giovanni Yoko, Minh-Quoc Nghiem, Yuichiroh Matsubayashi, Ak ...
セッションID: 3P1-IOS-2a-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
Natural language definitions of mathematical expressions often play an essential role to understand mathematical content of scientific papers. However, there exists no available annotated data that contains relations between mathematical expressions and their definitions. Such annotated data enables us to apply and compare different approaches for this relation extraction task. In this paper, we first introduce our guideline for annotating definitions of mathematical expressions in scientific papers. This guideline describes specific types of mathematical expression description that should be annotated as definitions and how to annotate them. Based on the guideline, we manually annotated 14 papers from International Journal on Document Analysis and Recognition (IJDAR) from Springer. We also developed and investigated the performance of pattern matching and machine learning based methods in comparison with an existing naive practice that is based on the head noun of preceding text.
抄録全体を表示
-
Svetoslav Dankov, Rafal Rzepka, KENJI ARAKI
セッションID: 3P1-IOS-2a-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
Augmented Reality applications are becoming more popular with the continued miniaturization of technology. With the increasing use of smart phones, which often provide increased processing power, enhanced and open software platforms, Augmented Reality has become instrumental in the way we perceive our surroundings and the information that it carries. It is now possible to implement an Augmented Reality system without carrying bulky and expensive equipment. Currently, there are many systems that implement some form of Augmented Reality to provide a specialized interaction to users. However, those systems usually employ expensive, immobile components with highly specialized interfaces. In this paper we present a novel approach for building interactive interfaces using Augmented Reality. UIAR (User Interface through Augmented Reality) is an augmented reality framework that allows for the ubiquitous creation and dissemination of interactive user interfaces. Here we present the novel interaction schemes of UIAR alongside with an evaluation of their efficacy, usability and performance.
抄録全体を表示
-
Pawel Dybala, Michal Ptaszynski, Rafal Rzepka, KENJI ARAKI, Kohichi Sa ...
セッションID: 3P1-IOS-2a-5
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
Although we are still quite far from constructing a human-like conversational system, researchers all over the world keep investigating numerous factors that make conversations between humans. In this work we focus on two such factors: humor and metaphors.Numerous research projects exist in the area of metaphor understanding and generation. We propose a unique approach to this subject, based on an observation that humans can not only properly understand and generate metaphors, but also make fun of their misunderstandings. For instance, an utterance "you have legs like a deer" can be understood as a compliment ("long and graceful"), as well as an insult ("very hairy"). If used properly, such misunderstanding can serve as source of humor in human-computer conversations.Currently we are working on constructing a large scale metaphor conceptual network, in which links between concepts are calculated accordingly to their roles in metaphor understanding. When finished, the network should make it possible for the computer to understand and generate metaphors, and, consequently, also misunderstand (or act as if it misunderstood) them. In this paper we propose a design of a conversational system utilizing these mechanisms. We also consider using emotion-from-text detector to improve aptness of generated misunderstandings.
抄録全体を表示
-
Gluckstad Fumiko Kano
セッションID: 3P1-IOS-2a-6
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
The internet revolution has brought about fundamentally new possibilities for people located at opposite sides of the globe to real-time dynamically communicate with each other. Although people most often use English as a common communication code, misunderstandings are almost unavoidable in cross-cultural communications.When focusing on problems at the lexical level, two questions might immediately arise: How can one improve the transfer of original conceptual meanings of source concepts to a target audience when there are no 100% equivalent concepts existing between the two cultures in consideration? And how does cultural prior-knowledge influence in such a communication scenario? The answers might be identified in Sperber & Wilson's Relevance Theory of Communication (1986) and the Knowledge Model involved in category-based inductions (Murphy, 2004). These cognitive theories imply that an audience's prior-knowledge is used for his/her inferential process of learning new information and such prior-knowledge is organized in a taxonomic hierarchy in his/her memory. Supported by these ground theories, a framework of bridging culturally-dependent ontologies by applying the Bayesian Model of Generalization (Tenenbaum & Griffiths 2001) is proposed. This approach enables one to estimate probabilities of how an information receiver generalizes a source concept from a given stimulus in a cross-lingual context.
抄録全体を表示
-
Michal MAZUR, Rafal RZEPKA, Kenji ARAKI
セッションID: 3P2-IOS-2b-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
In this paper we would like to present the idea of an English tutoring system aimed to bring a new standard in language teaching. The Co-Mix project concentrates on second language vocabulary acquisition that is central to language itself and of high importance to the typical language learner. We compare some existing methods of teaching vocabulary and present the usefulness of our sentential context-learning method based on the phenomenon of code-mixing. Since such a method has not yet been fully explored, we would like to progress with the research in the fields of natural language processing and artificial tutor systems. We also perform a preliminary experiment to check our hypothesis on sentences with certain emotional loads. We investigate the effect of emotion on the learner's performance in studying and propose how this method can be applied in a casual conversation system with the purpose of teaching English as a second language.
抄録全体を表示
-
Daniel Berrar, Akihiko Konagaya, Alfons Schuster
セッションID: 3P2-IOS-2b-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
Alan Turing's question "Can machines think?" motivated his famous imitation game, which became widely known as the Turing test. Constructing a machine that can pass the test was seen by many as the "holy grail" of artificial intelligence (AI) research because such a machine must be assumed to have intelligence. The test had a tremendous impact on computer science and stirred many philosophical debates over the last decades. Today, however, the test has nearly vanished from research agendas in AI. Here, we argue that the Turing test is still inspirational. Modern computing machinery is now an integral part in myriads of problem-solving processes and has revolutionized how science is done. Machines can make us think, that is, help us refine or develop new theories about the natural world.
抄録全体を表示
-
竹内 孔一, Koichi Satoh, Suguru Tsuchiyama, Masato Moriya, Yuuki Moriyasu
セッションID: 3P2-IOS-2b-3
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
In this research we construct a predicate argument structure annotator that can disambiguate predicate's semantic concept and semantic role types of its arguments in a running texts. The semantic concepts are manually constructed and systematically organized by event type of predicates according to linguistically-motivated lexical semantic structure. For example the following predicates ``get'', ``take'', ``buy'', ``obtain'', ``take'', ``rob'' and ``rent'' must contain a shared meaning of 'Getting from something'; and the difference of ``get'' and ``rent'' must be with/without ownership of the obtained object. We describe this semantic shared/different meaning with abstracted LCS-base structure in our Thesaurus, e.g., The semantic structure of ``get'' might be ([Agent] CAUSE BECOME [Theme] BE AT [Goal=person]), and ``rent'' might be more detailed structure as [Agent] CAUSE (BY MEANS OF [Agent] renting [Theme]) BECOME [Theme] BE AT Goal=person]). This thesaurus is continuously constructed taking into account what are the base semantic structure among all Japanese predicates. Thus by making predicate argument structure annotator (we call ASA) based on thesaurus, we can see how the thesaurus's concepts can catch the same expressions of natural language. For this purpose, ASA can recognized idiom and equivalent expressions of predicates e.g., ``X ga Y ni hone-wo oru (X gives oneself trouble about Y)'' and ``X ga Y ni kurou-suru (X has difficulty with Y)'' with disambiguating verb senses ``hone-wo oru (gives oneself trouble about/break one's back)''. By constructing predicate argument structure with systematic thesaurus, we try to convert running texts into more semantically controllable descriptions.
抄録全体を表示
-
松浦 弘幸, Katsumi Wasaki
セッションID: 3P2-IOS-2b-4
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
I proposed the positive hypotheses of neuo-interferences, ephapse as engineering models. The nero-interferences and synaptic ones as ephapse are propagated by polaritons which are a kind of quasi particles, i.e. quantized polarization waves. Polaritons, which has spin 1, are massive vector particles and massive photon. polaritons are connecting between many ionic current, Na+, K+, Cl- etc when neurons, fibers (axons) are conducting their excitations. The Na+ currents, into insides of membranes of axons, cause the K+ currents to outside of axons through charged or non-charged quantized polarization wave, i.e. polaritons. Various interferences, ephapse, synaptic and the other interferences are intermediated by polaritons. Those quantum interferences are commonly adjusting our neural and brain's conditions by interacting with each neurone. One of my purposes is to study effect of quantum neuro-interferences, and propose new concepts of neural network accompanied with quantum interferences. . And I would like to show the application for Quantum Neural Networks, Quamtum Bayes' theory that they have quantum interferences and can considered as quantum version of Bayes theory and neural Network.
抄録全体を表示
-
安部 敏樹
セッションID: 4A2-NFC-1-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本研究は協働における諸条件の検討を目的に、質・量ともに同程度のプロジェクト20個を、異なる条件のもとで参加者に課した。プロジェクトのメンバーは4~6人、期間を約3ヶ月間と限定した上で、「コミュニケーション量」「コミュニケーション形態」「チーム内でのルールの共有」の3つの側面からより創造的で効率的な協働への最適な諸条件を提言する。協働に関わる分野でのチームビルディングや組織論への貢献が期待される。
抄録全体を表示
-
鳥海 不二夫, 篠田 孝祐, 榊 剛史, 栗原 聡, 風間 一洋, 野田 五十樹
セッションID: 4A2-NFC-1-2
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
本チャレンジでは,今後も日本で発生するであろう様々な災害において災害救助支援を実現するための基盤技術を構築することを目指す.
抄録全体を表示
-
原 聡, 鷲尾 隆
セッションID: 4B1-R-2-1
発行日: 2012年
公開日: 2018/07/30
会議録・要旨集
フリー
スパース共分散選択(SICS)は確率変数間の従属性を推定する問題である.本発表ではDALとADMMという2つの手法を組み合わせた新たなSICSアルゴリズムを提案する.DAL-ADMMは従来のADMMと同様に各更新ステップが解析的に計算可能であり,その実装が容易であるという利点を有している.最後に従来のADMMアルゴリムとの理論的及び実験的比較についても述べる.
抄録全体を表示