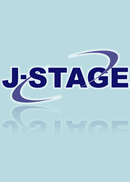日本語は空主語ならびに空目的語を許すが, 英語はどちらも許さない.この違いから, 日本人英語学習者にとっては, 目的語を義務的に使用することを習得することと主語を義務的に使用することが, 同程度に困難であることが予測される.この予測に反して, 本研究のデータによると, 目的語を義務的に使用することは主語を義務的に使用することよりも, 日本人英語学習者にとってはるかに難しい.Yhan (1997) は中国人英語学習者について本研究と同様のデータを用い, この非対称性は入力において引き金となるデータが入手可能かどうかに原因があると論じている.すなわちYUanの説明では, 主語の義務的使用の習得については主語と動詞の一致を示す形態的証拠によって明示的な引き金が与えられ, それによって習得が起こるが, 目的語の義務的使用についてはそのような形態的証拠が存在せず, そのため習得が起こらない.YUanは, 表層的な形態素使用は, その規定にある文法能力を必ずしも反映しないとしているため, この議論を反証することは極めて難しい.しかし同時に, この議論は実験的データによって支持されるものではない.例えばDavies (1996) は, 主語と動詞の一致と主語の義務的な使用に相関関係が見られないことを明らかにしている.本研究ではYhanの立場を取らず, 主語と目的語に見られる非対称性は入力における一貫性の問題であるという説明を試みる.主語名詞句は英語の全ての文において一貫して音形を持つが, 目的語は必ずしも全ての文で音形を持つわけではない.この種の入力を受けて, 日本人英語学習者は, 英語では主語は義務的に使用する必要があるが目的語は母語と同様に省略しても良いと誤解してしまう可能性がある.また英語の動詞には自動詞および他動詞両方の用法があるものがあり, それらが目標言語の文法とは異なる中間文法を作り出す原因となっている可能性もある.さらに英語動詞の自他性についての形態的指標の欠如が, 日本人英語学習者による動詞の統語的特質の習得を困難にしているとも考えられる.
抄録全体を表示