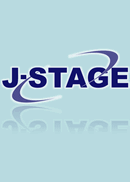-
Minju Kim, Kazunari Morimoto, Noriaki Kuwahara
2015 年4 巻1 号 p.
13-20
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
Cardinal directions are presented as visual information for guidance and leading. The purpose of this study is to clarify the elements of design for an intuitive better understanding of cardinal directions. First, current cardinal directions were collected from the literature and field studies, and components of design that should be considered when drawing cardinal directions were extracted. Then, using the four types of cardinal directions based on design components as the stimulus, the perspicuity of each diagram was analyzed through paired comparison method. As a result of the integrated evaluation of four types of cardinal directions, the use of the letter N meaning the north direction in any of the types was proved to lead to better understanding. However, depending on the type of cardinal directions, the appropriate state of design element that could help the audience to understand differed. Specifically, if the pointer only indicated north, it was answered that it would be better to understand to display only the letter N, but if there were four pointers indicating four directions, it would be better to display all the four directions. In other words, it will be optimal if the design elements and displayed characters combine appropriately depending on the respective direction number. In addition, since excessive simplification comes to reduce the perspicuity instead, it is required to denote the necessary character information for orientation.
抄録全体を表示
-
藤 和久, 小川 淳一, 松田 祐之, 小林 めぐみ, 森脇 健二, 平本 健治, 金 成彦, 山田 浩明, 王 存涛, 濱田 泰以
2015 年4 巻1 号 p.
21-26
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
繊維強化複合材料を用いた射出成形品は、成形品中の繊維の長さが、成形品物性に大きく影響することが知られている。そこで本研究では、射出成形用の炭素長繊維強化ポリプロピレンを用いて、材料の溶融粘度や成形機の混練スクリューの圧縮比及び背圧が、成形品中の残存繊維長に及ぼす影響について明らかにした。供試材料として、4つの溶融粘度の異なるポリプロピレンを用いて炭素繊維を30 wt%含む長さ7 mmの炭素長繊維強化ポリプロピレンペレットを調製し、圧縮比の異なる混練スクリューにて背圧を変えて射出成形を行い、成形品中の残存繊維長、及び引張特性と衝撃強度を評価した。その結果、高溶融粘度の材料と圧縮比1.8の低せん断スクリューを用いて、低い背圧で成形することで、成形品中に1 mm以上の炭素繊維を残すことが可能であり、それに伴いより高い物性を発現させることが可能であることを見出した。
抄録全体を表示
-
田茂井 勇人, 迫田 健太郎, 魚住 忠司, 大谷 章夫, 仲井 朝美
2015 年4 巻1 号 p.
27-30
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
繊維強化プラスチック(FRP)は強化繊維、樹脂、界面の要素より構成されているが、単一の繊維および樹脂からなる複合材料では発現し得ない物性を材料に付与するため、特にハイブリッド複合材料に関して多くの研究がなされている。繊維ハイブリッド複合材料は、一般には2種類以上の繊維を組み合わせた材料のことを示している。同じ繊維材料を使用しているが、繊度や撚糸状態等、構造が異なる繊維材料を1つの強化形態内で併用するハイブリッド構造を、本研究では“繊維ハイブリッド”の一種と考えた。テキスタイル技術には撚糸と無撚糸を組み合わせた「ちりめん」がある。この「ちりめん」を強化基材に用いることで、繊維構造ハイブリッドによる新たな特性や機能が期待できる。本研究では、ちりめんの構造を適用した炭素繊維織物複合材料のたて糸方向に対する引張方向および撚り数が、初期破壊発生応力に及ぼす影響を検討し明らかにした。次に、上記複合材料の強化形態のよこ糸を変更し、よこ糸に撚糸と無撚糸の交互配置とした場合、さらに、ガラス繊維を用いた場合の2種類の繊維ハイブリッド複合材料において、撚り数の初期破壊発生応力に及ぼす影響を明らかにした。また、初期破壊発生時のよこ糸撚糸の見かけの繊維束内界面強度を算出し、よこ糸撚糸の撚り数との関係を明らかにした。
抄録全体を表示
-
鈴木 直弥, 西野 智也, 金田 啓彰
2015 年4 巻1 号 p.
31-34
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
海上風は、大気・海洋間の運動量・熱・CO2乱流輸送における促進力として重要なパラメータである。したがって、海上風速を全球規模で精度良く観測することは重要である。そこで全球規模で海上風速を観測している人工衛星データが有用となる。人工衛星による海上風観測は、マイクロ波散乱計・放射計が用いられる。現在の最新では、MetOp-B/ASCAT(The Meteorological Operational satellite program-B/Advanced Scatterometer)がマイクロ波散乱計における全球の約8割を1日で観測している人工衛星である。しかし人工衛星マイクロ波散乱計による海上風観測は推定値であるため、常に精度検証をすることが重要である。そこで本研究では、人工衛星マイクロ波散乱計MetOp-B/ASCATの風速Level 2データをブイデータと比較することで精度検証を行った。精度比較に用いたブイデータは、TAO(Tropical Atmosphere Ocean) /TRITON(Triangle Trans-Ocean Buoy Network)ブイ(13点)、PIRATA(Prediction Research Moored Array in the Tropical Atlantic)ブイ(8点)、RAMA(Research Moored Array for African-Asian-Australian Monsoon Analysis and Prediction)ブイ(5点)、NDBC(National Data Buoy Center)ブイ(14点)である。データ使用期間は2013年の一年間とした。全球規模におけるブイ風速に対するMetOp-B/ASCAT風速のRMS差を算出した結果、1.02 m/sとなり公証測定精度2.0 m/s以内で精度が良いことが示された。5つ海域毎に分けてRMS差を算出した結果においても全ての海域で精度が良かった。また、全体的な傾向としてMetOp-B/ASCAT風速がブイ風速より大きく見積もる傾向も示された。
抄録全体を表示
-
柿田 恭良, 森 雅斗, 大谷 章夫, 仲井 朝美
2015 年4 巻1 号 p.
35-40
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
本研究では組物複合材料のエネルギー吸収特性について検討した。強化繊維に炭素繊維、母材樹脂にナイロン66樹脂を用いた熱可塑性樹脂複合材料円筒(CF/PA66)を作製し、樹脂、強化繊維の異なる複合材料円筒とエネルギー吸収特性を比較した。エポキシ樹脂を用いた熱硬化性樹脂複合材料パイプ(CF/Epoxy)はCF/PA66に比べて、エネルギー吸収量が小さくなった。断面写真より長手方向のクラックが発生し、外側の層の曲率が大きくなっていることから、長手方向クラックが発生することで、外側の層が曲がりやすくなり、繊維の破壊に必要なエネルギーが減少したためだと考えられる。強化繊維にガラス繊維を用いた熱可塑性樹脂複合材料パイプ(GF/PA66)はCF/PA66と同様の破壊様相を示したが、エネルギー吸収量は低い値を示した。これは強化繊維の引張強度が影響していると考えられる。エネルギー吸収量の速度依存性に関して破壊じん性が影響し、破壊じん性の速度依存性が小さいほど圧縮速度によるエネルギー吸収量の差が小さいことが分かった。
抄録全体を表示
-
田茂井 勇人, 小林 彩香, 仲井 朝美, 鋤柄 佐千子
2015 年4 巻1 号 p.
41-46
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
本研究では、繊維の配向、繊維の種類、織組織を変化させた織物を使用し、撚り構造が炭素繊維織物の力学的特性に及ぼす影響について実験的に検討した。評価方法としてはKES法の標準測定試験条件を元に、圧縮試験、曲げ試験を用いた。圧縮特性については、各試料において撚り数10、30 T/mでは圧縮仕事量は増加し、その後減少した。偏平である繊維束に撚りを少し施すことで繊維束の形状が楕円から円に近づき、厚みを生じる。厚みが増加することにより、圧縮仕事量は増加する。一方、撚りが多くなるにつれて繊維束の締め付け力が大きくなり、硬くなる傾向にある。すなわち、圧縮仕事量は減少する。この繊維の性質が結果に表れたと考えられる。曲げ特性については、すべての織物において曲げ剛性は撚り数の増加とともに増加し、撚り数が100 T/m以上になると減少した。繊維束に撚りを施すことで繊維束の締め付け力が大きくなり硬くなる傾向にあるが、撚り数がある一定値を超えると織物が平面を保てなくなり、面外に変形した。以上のように、繊維構造ハイブリッドの概念を炭素繊維織物に適用することにより、強化形態である織物の力学的特性を変化させることが可能であることがわかった。
抄録全体を表示
-
西尾 友志, 岩本 恵和, 勝又 英之, 鈴木 透, 金子 聡
2015 年4 巻1 号 p.
47-52
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
pH応答ガラス電極は、Liを多く含む特殊なガラスからなり、一般の硬質ガラスに比べて化学的耐久性に劣る。近年、pH応答ガラス電極は、高アルカリ条件下で用いられることが多々あり、そのような条件下で使用した場合の寿命は、極めて短い。本研究では、高アルカリ溶液などの過酷な使用条件でも、長寿命で安定して測定できるpH応答ガラス電極の開発を試みた。我々は希土類元素がガラスの耐久性を向上させることを報告しており、これまでの知見をもとにランタノイド希土類元素を添加したpH応答ガラスを作製した。そして、pH応答ガラスと鉛フリーガラス支持管との接合性、pH応答性、およびアルカリ溶液における耐久性の評価を行った。その結果、pH応答ガラスに添加するランタノイド希土類元素のイオン半径が小さくなるにつれて、膨張係数が小さくなる傾向が得られ、鉛フリーガラスとの接合が容易になった。また、これらを用いた電極の感度や不斉電位などは、JIS規格を満足することが確認できた。ガラス試験片によるアルカリ耐久性を評価した結果、各元素の溶出量が従来の1/2以下という結果が得られた。さらに、電極形状にて21日間のアルカリ浸漬試験を行った結果、感度97 %以上、アルカリ誤差35 mV以内を維持した。以上の結果より、今回開発したガラスは、アルカリ用pH電極用として実用的であることが明らかになった。
抄録全体を表示
-
鈴木 直弥, 三浦 洋貴, 高垣 直尚, 小森 悟
2015 年4 巻1 号 p.
53-58
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
地球温暖化等の気候変動予測において大気・海洋間の運動量・熱・CO2輸送を正確に評価することは重要である。また、その中でも、大気・海洋間運動量輸送は大規模な海流、風波、高潮など様々な海水運動の駆動源となっている。大気・海洋間運動量フラックスに用いられる主なパラメータは風速データである。しかし、全球規模の風速データとしては、再解析データや人工衛星データなど時空間解像度の異なった様々なデータが多く提供されている。したがって使用する風速データの相違によって大気・海洋間運動量フラックスにどのような相違が生じるか影響を検討する必要がある。本研究では、大気・海洋間運動量フラックスを全球規模で推定し、相互比較を行うことで、どのような影響があるか検討を行った。使用した風速データは、NCEP-R1(National Center for Environmental Prediction-Reanalysis)/6時間毎、NCEP-R2/6時間毎、ECMWF-ERA40(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts- ECMWF Reanalysis 40-years)/6時間毎、JRA-55(Japanese 55-years Reanalysis project)/3時間毎と6時間毎の再解析データ、そしてCCMP (Cross-Calibrated Multi-Platform)/6時間毎の複数人工衛星データである。データ使用期間は2001年の一年間とした。全球規模での大気・海洋間運動量フラックスの年平均を算出した。その結果、NCEP-R1、NCEP-R2、ECMWF-ERA40、JRA-55/3時間毎、JRA-55/6時間毎、CCMPはそれぞれ0.116、0.179、0.119、0.135、0.135、0.129 N/m2であり、最大で差が約54 %であった。また緯度毎に比較した結果、高緯度で大きな差を示した。時間解像度による違いは見られなかった。したがって、高風速域の高緯度で空間解像度の影響が大きいと考えられる。
抄録全体を表示
-
鈴木 直弥, 塚本 誠二
2015 年4 巻1 号 p.
59-64
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
大気・海洋間の運動量・熱・CO2乱流輸送における促進力として海上風速は重要なパラメータである。したがって、全球規模で海上風速を観測可能な人工衛星データが有用である。人工衛星による海上風観測は、マイクロ波散乱計・放射計が用いられる。海上風速・風向のみであれば、マイクロ波散乱計が高解像度で全球観測に優れているが、軽量であり関連した他の観測パラメータを同時に観測できるという利点からマイクロ波放射計を搭載した人工衛星も多い。現在の最新では、SAC-D/Aquarius(Saterlite de Aplicaciones Cientificas-D/Aquarius)が海表面塩分濃度の観測目的で海上風速もマイクロ波放射計で観測している。また、最近グリッド化されたLevel 3データの配布が開始されたため、精度検証をすることが重要である。本研究では、SAC-D/Aquariusの風速Level 3データをブイデータと比較することで精度検証を行った。ブイデータは、TAO(Tropical Atmosphere Ocean)/TRITON(Triangle Trans-Ocean Buoy Network)ブイ(26点)、PIRATA(Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic)ブイ(16点)、RAMA(Research Moored Array for African-Australian Monsoon Analysis and Prediction)ブイ(20点)、NDBC(National Data Buoy Center)ブイ(19点)である。データ使用期間は2012年の一年間とした。全球規模におけるブイ風速に対するSAC-D/Aquarius風速のRMS差を算出した結果、1.76 m/sとなり公証測定精度1.5 m/sより高く、精度が悪いことが示された。また海域毎に分けてRMS差では、インド洋、北大西洋、北太平洋が、それぞれ1.73、2.15、2.49 m/sと精度が悪く、赤道太平洋、赤道大西洋は、それぞれ1.46、1.30 m/sで精度が良かった。全体的な傾向としてSAC-D/Aquarius風速がブイ風速より大きく見積もる傾向も示された。
抄録全体を表示
-
大薮 多可志, 梶原 祐輔, 河内 雅典, 木村 春彦
2015 年4 巻1 号 p.
65-70
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
植物生体電位は植物から発信される有力な情報といえる。この生体電位と環境要因や成長率などとの関係が明らかになれば応用範囲が広く人間社会に大きな貢献となる。特に野菜工場へ応用することができれば生産管理にも応用でき、高効率で安全・安心な野菜生産が可能となる。本研究においては、野菜工場における主環境要因の一つである照射光周波数と生体電位との関係を調べた。養分としてガス状エチルアルコールを採用し、その雰囲気に対する浄化能力について調べた。被験植物は代表的な果菜類であるナスを採用した。結果として、様々な周波数の混合光である白色光下における生体電位が大きく浄化能力も高いことが明らかとなった。本実験の浄化能力は、ナスの当該ガスの摂取・分解能と考えられる。酸化スズ系ガスセンサを用いて実験容器内の濃度変化を調べることにより被験植物の浄化能力特性を導出した。ガスセンサ出力が、ナスのエチルアルコール吸収・分解ととともに濃度が減少する。その特性のピーク値を半値幅で除することにより浄化能力を導出した。
抄録全体を表示
-
Nobuo Obara, Nozomi Oki, Masahiko Okai, Masami Ishida, Naoto Urano
2015 年4 巻1 号 p.
71-76
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
In this study, the development of a simple isolation method for obtaining yeast Saccharomyces cerevisiae with high fermentative activities from coastal waters was examined. 824 isolates were obtained on YPD2 (glucose 2 %) solid medium from coastal waters of both Tokyo Bay and Sagami Bay in Japan. In the first screening from the isolates, 221 of the 824 yeasts had fermentative activities in YPD2 liquid medium by a Durham pipe test. In the second one, 55 of the 221 yeasts had fermentative activities in YPD30 (glucose 30 %) liquid medium by the same test. In the third one, exact amounts of gas produced by the 55 strains were rapidly measured by a syringe test and the gas productivities of the 29 strains were higher than that of a marine-derived Saccharomyces cerevisiae C19 which was isolated and used for bioethanol production in previous studies (Takagi et al., 2015; Obara et al., 2015; Obara et al., 2012). Above all, the best 4 strains with the highest gas producing activities among the 29 ones were also identified as Saccharomyces cerevisiae. Thus, the yeast species S. cerevisiae was found to be simply isolated from coastal waters by the method as above. In addition, ethanol productivities of 10 strains randomly selected from the 29 ones were measured. There was an almost linear relationship between ethanol and gas productivities in the 10 strains. Therefore, bioethanol productivities of the yeast isolates from coastal waters could be speculated by measuring amounts of gas produced by the syringe test.
抄録全体を表示
-
羽鳥 剛史, 二神 透
2015 年4 巻1 号 p.
77-82
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
本研究では、自然災害に関わる想定の限界についての認識不足を「メタ無知」と呼称し、地震災害を対象として、人々がどのような想定意識を有し、その想定をどのように評価しているかを明らかにし、メタ無知の傾向を実証的に把握する。この目的の下、南海地震に関連する事柄・事象として①地震震度、②津波高さ、③建物倒壊、④建物焼失、⑤人的損失、⑥土木施設損壊、⑦ライフライン施設損壊を取り上げ、愛媛県八幡浜市の住民324名を対象に、これらの災害事象に関する想定意識とその想定を超える事態に対する意識について調査を実施した。その結果、地震災害の規模やそれによって生じる諸事態の可能性を過小に想定している人ほど、その想定の限界を認識していない傾向が確認された。以上の結果は、認知心理学におけるDunning=Kruger効果と整合的であり、地震災害に関わる想定意識の低い人は、それにも関わらず、自分の想定の低さを感知していないという意味において、メタ無知に陥っている可能性を示唆している。最後に、自然災害による被害を軽減する上で、本研究の結果が示唆する点について考察した。
抄録全体を表示
-
Hiroshi Oguma, Atsushi Koizumi, Keita Norishima, Junpei Kuboniwa, Yuji ...
2015 年4 巻1 号 p.
83-90
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
Heterogeneous wireless systems, such as a combination of mobile broadband wireless access (MBWA) and wireless local area network (WLAN), are candidates to achieve large capacity in next generation mobile communication systems. For capacity expansion, small cells of multiple wireless networks are deployed densely in these systems. Many cells overlap. Therefore, users must discover many cells at once for cell selection. Consequently, radio resources are used intensively for cell selection. Cell selection errors occur in dense small cell environments. As described herein, a channel quality map construction scheme using multi-Global Navigation Satellite System (GNSS) signals for heterogeneous wireless networks is proposed. The scheme uses positioning information and the average of signal strength for cell selection. Using positioning information, users can select cells which have a better channel quality quickly and easily. The proposed scheme is considered to be useful to optimize data traffic offloading in the heterogeneous wireless network. The 50 % user throughput and system throughput of the proposed scheme by comparison with the conventional scheme which uses measured instantaneous signal strength was studied. Computer simulation results show that the proposed scheme can improve the 50 % user throughput by 68 % in comparison with the conventional scheme. In addition, the system throughput is enhanced by 10 % compared with the conventional scheme. Furthermore, based on measured data, the positioning accuracy with multi-GNSS signals is a realizable level for the channel quality map construction scheme. This report describes the developed channel quality map construction scheme prototype system.
抄録全体を表示
-
Hiroyuki Noda, Yoko Miyamoto
2015 年4 巻1 号 p.
91-94
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
In this paper, the mechanism for the antibacterial activity of a mixture of 3,4,5-trihydroxy benzoic acid (GA) and magnesium oxide (MgO) for Escherichia coli (JCM1649, E coli) is investigated. Antibacterial activity was assayed by the liquid dilution method against E coli. E coli in the logarithmic phase and the culture medium with pepton, yeast extract, NaCl, glucose, and MgSO4 7H2O were used in all experiments. The logarithmic phase culture of E coli (1x105 CFU cm-3) was added to the culture medium with GA and/or MgO. A Clark-type oxygen electrode with 1.1 cm-3 volume cell was used for the measurements of the oxygen consumption profile of a mixture of GA and MgO. The concentration of hydrogen peroxide (H2O2) in the mixture was estimated by using porphyrinato-titanium complex. Efficient antibacterial activity was observed on a mixture of 2 mg cm-3 GA and 2 mg cm-3 MgO. The addition of 110 units cm-3 catalase, which is an enzyme of H2O2 decomposition, in a mixture of 2 mg cm-3 GA and 2 mg cm-3 MgO led to the decrease of the antibacterial activity as same as the case of 2 mg cm-3 MgO. Moreover, the production of H2O2 in the mixture was confirmed by the oxygen consumption profile under the addition of 500 units cm-3 catalase. The accumulation of 3-4 mmol dm-3 H2O2 was confirmed in a mixture of 2 mg cm-3 GA and 2 mg cm-3 MgO. The increase in the concentration of H2O2 from 3 mmol dm-3 to 4 mmol dm-3 led to a drastic increase in the antibacterial activity. Based on the results of this study, a possible mechanism for the antibacterial activity of a mixture of GA and MgO is discussed, concerning a synergy effect on the antibacterial action of MgO and that of H2O2.
抄録全体を表示
-
宮下 知也, 横田 正, 木戸 康嗣, 岡村 拓哉, 飯島 陽子, 鈴木 英之, 柴田 大輔, 衛藤 英男
2015 年4 巻1 号 p.
95-100
発行日: 2015年
公開日: 2015/06/30
ジャーナル
フリー
我々は緑茶を亜臨界水抽出130℃で処理することで高濃度カテキン含有でありながら苦渋味を抑制した緑茶飲料になることを報告した。本報ではこの緑茶抽出物の有用成分や香気成分および水色について検証を行った。その結果、従来の熱水抽出よりも有用成分(アスコルビン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、ケルセチン、サポニン、水溶性食物繊維)が高濃度で抽出され、機能性を有する緑茶飲料であることが分かった。また、テアニンから生成される(S)-3-アミノ-1-エチルグルタルイミド(環状テアニン)はACE阻害活性があり、緑茶の中でも玉露や碾茶に多いことも明らかにした。さらに、緑茶特有の香気成分および水色に関連するクロロフィルの増加も確認した。従って、亜臨界水抽出は従来よりも優れた香気と水色を示し、苦渋味抑制だけでなく新たな機能性を有する緑茶飲料の製造方法としての可能性を示唆した。
抄録全体を表示