巻号一覧
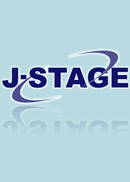
20 巻 (1991)
- 4 号 p. 177-
- 3 号 p. 117-
- 2 号 p. 51-
- 1 号 p. 1-
前身誌
20 巻, 2 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
, ,1991 年20 巻2 号 p. 51-58
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリーIn blood coagulation, fibrinogen-bound sialic acid has played an important role in the fibrinogen-fibrin conversion through the action of thrombin. The use of high performance liquid chromatography (HPLC) for determining sialic acid was attempted. Namely, a fibrinogen specimen was thoroughly dialyzed against sodium chloride orphosphate buffer solution, and then hydrolyzed in mild acid or by incubation with neuraminidase. After ultrafiltration to remove high molecular substances, the sialic acid in the filtrate was determined by HPLC, eluted by an isocratic procedure from a strong cation exchange resin column with a 1% phosphoric acid solution as a mobile phase. This analysis showed that each molecule of fibrinogen has 6.46 residues of sialic acid on average. This HPLC method can be directly used for quantitative determination of sialic acid released from fibrinogen without any conversion into derivatives and thus with fewer errors than conventional methods. In addition, the measurement was highly reproducible. Samples containing more than about 0.05 nmol of sialic acid or more than about 3.4μg (0.01 nmol) of fibrinogen can be determined by this method. The HPLC analysis required less than 9 minutes for the elution of the sialic acid. The results of this HPLC analysis suggest that fibrinogen molecules having different numbers of sialic acid residues are present in the blood. And it seems possible to determine sialic acid in other sialo-compounds of high molecular weights.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (990K) -
杉田 収, 和田 玲子, 松井 朝子, 橋本 尚士, 広川 恵子, 屋形 稔, 岡田 正彦1991 年20 巻2 号 p. 59-66
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー病院の外来で受診した20歳以下の新患患者の約1400名から, 血清酵素活性9項目の基準値 (正常値) を作成した。基準値作成用試料として患者血清を用いることの危険性を考慮し, 別に小児科患者から健常者らしき者224名を選択して両者のデータを比較した。同様に健常小中学生の338名から作成した基準値とも比較した。
その結果, 新患患者からの基準値はクレアチンキナーゼ以外はほぼ健常小児のそれに近似し, 実際の診療に利用しうるものと考えられた。したがって, 求めようとする検査項目の基準値に大きく影響を与える疾病が少なければ, 次善の策として, 外来新患患者集団であっても, その血清は基準値作成用試料として利用しうるものと考えられた。また10歳前後からGPT, LDH, γ-GTPに危険率1%で有意な性差の認められた点が注目された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1081K) -
宮沢 正, 西口 嘉乃, 渡邊 富久子1991 年20 巻2 号 p. 67-71
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー酵素免疫測定法によりジアセチルモルヒネ (通称「ヘロイン」) 乱用者の尿中モルヒネのスクリーニングテスト法を開発した。
抗モルヒネ抗体は抗モルヒネ-3-BSA抗血清, 第二抗体は抗ウサギγ-グロブリンヤギまたはブタ抗血清結合ガラスビーズを用いた。酵素標識モルヒネは, モルヒネ-6-ヘミサクシネートにアルカリホスファターゼをカルボジイミド法にて結合させたものを用いた。
本法の最小検出感度は25pg/tube, 検量線の測定可能範囲は25pg-1ng/tubeであった。
実際の容疑者尿36検体について, 本法による測定結果 (1000倍希釈試料) とGC-MSによる同定結果を比較したところ, 両者はよく一致し, 尿中モルヒネのスクリーニングテスト法として犯罪鑑識および臨床検査業務に有用と考える。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (483K) -
久保野 勝男, 高口 聖民代, 坂本 和夫, 米沢 真佐子, 塚田 裕1991 年20 巻2 号 p. 72-77
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー健常人における血中アデノシン濃度をradioimmunoassayにより測定した。
血中アデノシン濃度測定においてはサンプルの採取条件がひとつの重要なポイントとなり, EDTA, deoxycoformycin, dipyridamoleの混合液をインヒビタ-として用いることにより, 安定した結果が得られた。
男性52名, 女性47名, 合計99名の健常成人における血漿中アデノシン濃度は12.0-49.9pmol/ml であり, 20歳代, 30歳代においては性差・年齢差は認められなかった。
12名の健常成人において, 血漿中アデノシンと血球中アデノシンを比較した結果, 血漿中アデノシンに比べて血球中濃度は約10倍の高値を示した。
血漿中, 血球中アデノシンについて, 両者の間には有意な相関関係が見られなかったが, 何らかのかたちで生体内の各調節機能に関与しているものと考えられる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (559K) -
石毛 雅夫, 石毛 英幸, 加藤 裕久, 茅野 真一, 杉 正人, 藤本 正雄, 永井 良三, 磯部 光章, 矢崎 義雄1991 年20 巻2 号 p. 78-83
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー心筋障害の新しい生化学的検査法としてヒト心筋ミオシン軽鎖I (light chain 1: LC1) に対する, 酵素免疫測定法 (enzyme linkid immunosorbent assay: ELISA) を開発した。本測定法は高感度であり1-100ng/mlの血清中のLC1が測定可能であった。測定内および測定間の再現性, 血清に添加した精製LC1の回収率も良好であった。患者血清の希釈曲線は原点を通る直線となった。このELISAは, 2時間以内に測定が終了するため心筋梗塞の迅速な診断に役立つことが期待される。
ラジオイムノアッセイとの間の相関係数は0.98, 回帰直線はIRMA=0.99×ELISA-1.6であった。本測定に用いた試薬はすべて4℃で6カ月以上安定であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (519K) -
鈴木 聡, 山内 忠一, 佐藤 浩, 金森 利至, 延原 正弘, 深谷 孝夫, 星合 昊1991 年20 巻2 号 p. 84-90
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー血中17β-エストラジオール (E2) 値を迅速に測定するため競合法に基づく酵素免疫測定法を作製した。
本法では抗E2-6CMO-チログロブリン抗体, およびE2-3CME標識ペルオキシダ-ゼを用いることにより血清検体の直接測定が可能であり, さらに半自動免疫測定機器 (イムラボットSA-101) を使用した傾斜回転法により反応時間を30分と迅速化することができた。
本法のE2測定範囲は300pg/ml-10ng/mlであり, この範囲での測定値変動係数は同時再現性で 4.7-14%, 日差再現性では20%以下であった。一方, 種々ステロイドのうちエストロン, E2-3-(β-D-グルクロナイド) で各26%, 29%の交差率を認めたが, 排卵誘発時血中E2濃度を測定した結果, ラジオイムノアッセイとの相関はYEIA=1.66×RIA-0.01 (n=90), 相関係数r=0.95と良好であり, 体外受精などにおける血中E2値の迅速測定に応用可能であることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (749K) -
松下 誠, 入野 勤, 村本 良三, 櫛下町 醇1991 年20 巻2 号 p. 91-96
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー筆者らは, コバルトを用いるCo-ビウレット反応を組み立て, その反応特異性, 吸収スペクトルおよび反応の蛋白質問差などの基礎的性状を調べ, 同じ第一遷移金属である銅やニッケルを用いるビウレット反応との比較検討を行った。その結果, Co-ビウレット反応はCuあるいはNi-ビウレット反応とも異なった反応特性を示した。また, これらの3種のビウレット反応の中では, 蛋白質の定量法としてはCuおよびNi-ビウレット反応がCo-ビウレット反応に比べ有用であることが確認された。
さらに, 以上の検討結果から, ビウレット反応と用いられる遷移金属に関する解析を行ったところ, 平面四角形状錯体 (dsp2混成軌道) を形成しやすい遷移金属がビウレット反応を引き起こすことを明らかにした。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (646K) -
界面活性剤によるプロゾーン現象の改善大竹 皓子, 野口 昌代, 加野 象次郎, 入 久巳1991 年20 巻2 号 p. 97-107
発行日: 1991/06/30
公開日: 2012/11/27
ジャーナル フリー免疫比ろう (朧) 法による免疫グロブリン測定において, モノクローナル蛋白ではポリクローナルのものよりも低濃度でプロゾーン現象が出現する。これを改善するために, 高濃度域での沈降物の安定化を目的とした界面活性剤の選択とその使用濃度について検討した。
66mmol/lリン酸緩衝液, pH7.0に0.2mol/lKCl, 4%PEG6000, 0.5%Brij-35を含む反応緩衝液に, さらに, 非イオン系界面活性剤のユニルーブHSN-1118またはプルロニックF-68を1%濃度に添加した結果, プロゾーン現象の改善に著しい効果が認められた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (983K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|