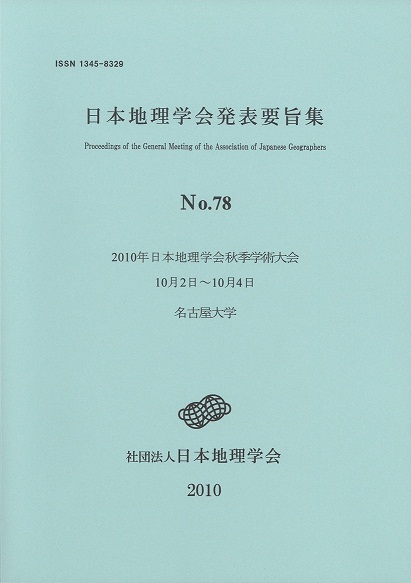-
遠藤 尚, 白川 博章, 乃田 啓吾, 沖 一雄
セッションID: 511
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに
インドネシアでは、1997年の経済危機による一時的な停滞はあるものの、1980年代の輸出志向型工業への転換以降、経済成長が継続してきた。これに伴い、15歳以上労働人口に占める農林漁業従事者の割合は、1980年の55.9%から2011年には35.9 %まで大きく減少している(BPS 2012)。農林漁業従事者数については、人口増加を背景として2000年まで増加傾向にあったが(加納 2004)、2000年から2011年にかけては減少に転じている(BPS 2012)。
しかし、このような就業構造の変化に伴う農村住民による自然資源利用状況や世帯生計の変化については、報告者による2001年時点の西ジャワ農村の事例以降(遠藤2006)、ほとんど報告がみられない。このため、2001年時点で既に確かめられていた、1990年代以降の新規就業層を中心とした都市就業の拡大傾向とそれに伴う生計構成の変化についても、その後の動向が明らかとなっていない。また、報告者によるこれまでの分析では、薪炭利用等、収入源ではない自然資源利用についてはほとんど言及してこなかった。したがって、本報告では、2013年9月に実施した農村世帯調査を基に、西ジャワ農村における世帯生計と自然資源利用の現状を明らかにし、2001年以降のその変化について検討することを目的とする。
2.対象地域の概要と研究方法
本研究の調査対象地域は、西ジャワ州チアンジュール県、シンダンジャヤ村である。シンダンジャヤ村は、県庁所在地であるチアンジュールの東約10km、バンドゥン—チアンジュール—ジャカルタを結ぶ主要道路の北4km、チラタ湖南岸に位置している。2012年12月時点の人口は、6,484人、人口密度は1平方キロメートル当たり1,706人に上る。シンダンジャヤ村が隣接するチラタ湖は、チタルム川中流域に位置する面積約65km
2のダム湖であり、コイやナイル・ティアピアの養殖が盛んに行われている。また、シンダンジャヤ村を含むチアンジュール県は、インドネシアにおけるブランド米の生産地域として知られている。このように、対象地域周辺では、チタルム川、およびその支流の水資源を利用した農業、水産業が重要な産業となっている。一方で、チタルム川の水質および水量の管理については、流域レベルを超えた重要な課題である。その背景には、チタルム川が首都ジャカルタの上水供給の8割を占める重要な水源であると同時に、世界でも有数の深刻な水質汚濁を抱える河川であることがある(針谷ほか 2011)。
2013年9月13日から16日の4日間、シンダンジャヤ村の1集落、RW8において調査票を用いた聞き取り調査を実施した。調査対象世帯は、RW8の隣組RT1、RT2の全世帯、およびRT3の一部世帯、全111世帯である。RW8は、村内で最も北に位置し、湖に隣接する集落であり、集落の全世帯数は265世帯であった(2013年8月時点)。調査項目は、世帯構成員の属性、世帯構成員の就業状況、世帯の動産・不動産所有状況、農地・養殖いかだの経営状況、薪炭利用の状況等である。
3.シンダンジャヤ村における世帯生計と自然資源利用
調査結果から、調査村周辺で行われている水稲耕作、および養殖業の多くは、大都市居住の経営者等、調査村住民以外によるものであることが明らかとなった。調査対象世帯の中で、水田経営世帯は6世帯、養殖いかだ経営世帯は12世帯に限られていた。一方で、調査対象世帯の就業者の40%以上が、農業、養殖業および非農業部門の賃金労働者であった。ただし、自給用の釣りや集落周辺での薪の採取、利用等については、広く行われていることが確認された。このように、この地域では、農村住民の多くが、周辺の自然資源を主要な生産財として利用するためのアクセスを持たず、自給用の消費材入手先として利用するに留まっていること、そして、主な収入は不安定な雇用労働に依存していることが明らかとなった。
(参考文献)
遠藤 尚 2006.西ジャワ農村における住民の階層構造と親族関係―ボゴール県スカジャディ村の事例―.アジア経済 47(9): 2-21.
加納啓良 2004.『現代インドネシア経済史論』東京大学出版会.
針谷龍之介・吉田貢士・加藤亮・黒田久雄・乃田啓吾 2011.インドネシア国チタルム川流域における利用可能水資源量の時空間分布.H23 農業農村工学会大会講演会講演要旨集: 266-267.
BPS 2012.
Statistik Indonesia 2012. (『インドネシア統計年鑑 2012』)BPS.
抄録全体を表示
-
内山 庄一郎, 鈴木 比奈子, 臼田 裕一郎
セッションID: 117
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
日本全国の過去の自然災害について網羅的なデータベースを構築し、そのAPI配信を行う。
抄録全体を表示
-
羽田 麻美, 乙幡 康之
セッションID: P020
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ 研究目的 秋吉台のカルスト台地上では,年に一度おこなわれる山焼きにより草原が維持され,石灰岩が露出したカレンフェルト地形が広がる。しかし近年,採草地としての需要低下や山焼き時の人手不足等により,草地面積は縮小傾向にある。放置された草原は,スギやヒノキの植林地や,落葉広葉樹や常緑樹の混交林へと変化している。そこで本研究では,この台地上において草地から森林に変化した地域を選び,森林環境下になったことで石灰岩表面に進入した蘚苔類の分布を調べるとともに,蘚苔類がその下部の溶食形態に及ぼす影響を明らかにすることを目的とし,調査をおこなった。
Ⅱ 地域概要および調査方法
1.調査地における植生の変化
調査地域は,秋吉台の真名ヶ岳(標高約350m)の東斜面にあるドリーネを選定した(図1)。この地域は1948年に米軍により撮影された空中写真では草地で,1968年撮影の空中写真では少なくとも森林に変化している。なお,このドリーネでは2013年7月にスギの伐採がおこなわれており,切り株の樹齢から約50年経過した植林地であることがわかり,空中写真の結果とも調和的であった。さらに,石灰岩の表面には直接降雨が流れることによりリレンカレンという溝状の溶食凹地形が形成されるが,本調査地域では,台地上の草地ではみられない蘚苔類に厚く覆われたリレンカレンが存在する。森林下でのリレンカレンの存在は,この地域が長く草地であったことの指標として捉え,その形状(幅と深さ)を計測した。
2.ピナクル表面に付着した蘚苔類
調査では,簡易測量にてドリーネの南北断面を計測し,南向き斜面と北向き斜面において,ドリーネ底からの比高によりそれぞれドリーネ上部・中部・下部に分類した。各地点において,高さ1m以上の最も蘚苔類が繁茂しているピナクルを選び,蘚苔類の植被率と腐植土の有無を調べた。
Ⅲ 調査結果および考察
1.ドリーネ斜面における蘚苔類の分布と腐植土
ドリーネ内のピナクル上では,約17種の蘚苔類が確認されたが,斜面方位によって蘚苔類の植被率に違いが見られた。すなわち,北向き斜面に露出するピナクルの方が,南向き斜面よりも植被率が高い。また,各ピナクルにおける植被率は,ドリーネ上部に面した側よりも,ドリーネ底に面した側の方が高い傾向にあった。これは蘚苔類の分布がドリーネ地形の環境に既定されているものと考えられる。腐植土の生成については蘚苔類の種によって違いが見られ,南向き斜面のドリーネ上部で優占するアツブサゴケ(
Homalothecium laevisetum)群落で最も発達していた。
2.蘚苔類の被覆下にあるリレンカレンの形状
蘚苔類に覆われたリレンカレンの形状を計測した結果,幅2.8~5.3cm,深さ0.5~1.4cmであり,羽田(2007)で計測した草地上での形状とほぼ同じ分布範囲を示すことがわかった。付着した蘚苔類を剥がすと蘚苔類の根は微細な石灰岩片を抱え込んでおり,物理的風化の促進が考えられたが形状値には明瞭な差はない。すなわち,植林後50年程度で生じた蘚苔類の根(仮根)では,元々のカレンの形状を変える程の物理的風化は生じていない。今後は,蘚苔類下に生成された腐植土の影響等も考慮し,環境変化に伴う生物風化作用について明らかにすることが課題である。
抄録全体を表示
-
小島 千鶴
セッションID: 533
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
第二次世界大戦後、高品質の化学肥料が生産可能となり、日本では1960年代以降に化学肥料の施肥量が急激に増加した。しかし1970年代に入ると、全国の地下水から高濃度硝酸態窒素が検出されるようになり、化学肥料に含まれる窒素が起因していると考えられた。近年に入り、環境基準法、水質基準項目に硝酸・亜硝酸態窒素が加わり、野菜の硝酸イオン低減化マニュアル(農林水産省)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル水質汚染マニュアル(環境省)等の対策も取られているが、基準値を上回る地域も依然として存在する。 大間々扇状地が位置する赤城山南麓一帯は県内最大の農業生産額を誇る地域であり、過去の井戸調査結果からは高濃度の硝酸態窒素が確認されている。これを踏まえ、本研究では大間々扇状地における地下水の水質の現状を調査し、地域特性を明らかにすることを目的とする。 分析結果から大間々扇状地の地下水のNO3-Nは環境基準値である10mg/Lを超過する値が広範囲で確認され、一番高い値は63.4mg/Lであった。又、濃度は地域差があり、農用地が多い地域は高く、農用地が少ない地域、及び沖積低地では殆ど検出されなかった。このことから沖積低地では脱窒が起こっている可能性が示唆された。濃度には季節変動があり、9月10月と2月3月以降に値が高くなり、11月~1月間は低下する傾向がある。一方、地下水位は9月・10月に高く、11月以降から約3月まで下がり続ける地点が多い。桐生・伊勢崎観測所の結果から、9月10月は、70mm以上の降水量があり、NO3-Nと地下水位が高い値を示したのは、降雨により硝酸イオンが地下水に多く流入した為と考えられる。しかし春先のNO3-Nの上昇背景は解明することが出来ず、今後の課題としたい。
抄録全体を表示
-
企業や協同組合による非木材林産物利用と地域住民
藤岡 悠一郎
セッションID: P056
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1. はじめに
経済のグローバリゼーションやマクロな社会経済変容のなかで、アフリカ農村における生業形態は急速に変容している。植物の果実や油脂などの非木材林産物は、アフリカの多くの農村において、自給用に採集、消費されてきたが、近年では国際機関やNGOなどが現金稼得源としての利用に注目し、各国で積極的に利用されるようになっている。そうしたなか、企業による加工品販売に住民が強く関わる事例や住民が協同組合を立ち上げる事例などが、アフリカの農村でみられるようになっている。本研究では、南部アフリカの半乾燥地域に広く分布する、ウルシ科の落葉高木であるマルーラ(
Sclerocarya birrea)の果実利用について、経済成長の著しい南アフリカに注目して検討した。マルーラの果実は、南部アフリカの各地で酒や油の原料として広く利用されていることが知られている。南アフリカでは、酒造会社のDistell社が1983年にマルーラの蒸留酒を開発し、現在では南アフリカの主要なお土産となり、海外にも輸出するようになった。こうした企業による商品流通や協同組合の立ち上げなどにより、住民によるマルーラ利用がいかに変化しているのかを検討した。
2. 方法
2010年10月、2012年2月に南アフリカ北東部のファラボルワとその周辺のタウンシップ、農村において現地調査を実施した。ファラボルワには、アマルーラという蒸留酒をつくる工場があり、そこの担当者にインタビューを行った。また、周辺のタウンシップに立ち上げられた協同組合を訪れ、組合員に聞き取りを実施した。さらに、街中やタウンシップでマルーラの果実を採集している人に聞き取りを行い、果実の利用方法などに関する情報を取得した。
3. 結果と考察
(1)ファラボルワ周辺のマルーラの分布:南アフリカ北東部に位置する町ファラボルワは、市街地の周辺に複数のタウンシップが存在し、その周辺に農村が立地している。この地域はマルーラが分布する地域であり、市街地のなかやタウンシップ、農村に多数のマルーラの木が分布していた。これらの木は人が意図的に植えたものではなく、自然に生えてきたものであると住民は説明していた。
(2) マルーラの多様な利用形態:Distell社は、マルーラの果汁を原料にした蒸留酒アマルーラを1994年から国際市場に販売し、現在では100か国以上に輸出している。その原料となるマルーラの果汁の80%以上をファラボルワ周辺20km圏内で入手していた。工場ではマルーラを栽培してはおらず、原料のすべてを地域の住民から工場が買い取っていた。住民が果実を集めると携帯電話で工場に連絡をし、担当者が車で回収し、工場でお金を支払うという仕組みになっている。他方、2000年以降、ファラボルワ周辺のタウンシップにおいて、マルーラ酒や油の原料となる種子の仁を販売する共同組合が複数設立されていた。
(3)住民によるマルーラ利用:かつて、本地域の人々はマルーラの果汁を発酵させた醸造酒を、主に自家消費用に利用してきたが、企業によるマルーラの買い取りが行われるなか、協同組合の設立やインフォーマルセクターでの個人的な酒の販売など、現金稼得源としての利用が多様化する傾向がみられた。それは、企業や行政によって主導される側面もあるが、タウンシップや農村に暮らす人々の自律的な生計戦略の結果として現れていた。
付記 本研究は、平成21-23年度文部科学省科学研究費補助金(特別研究員奨励)「西南部アフリカ・半乾燥地域における気候変動とモパネ植生の動態、地域社会の脆弱性」の一環として行われた。
抄録全体を表示
-
西表島仲間川下流域のマングローブ林の事例
内山 庄一郎, 宮城 豊彦
セッションID: P038
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
SfM (Structure from motion)による簡単で正確なDSM、オルソ画像の作成が実現した。デジタルカメラ画像や空中写真画像からDSM、オルソフォトを作成できる。本稿では、複数時期の空中写真画像からDSM、オルソ画像を作成し、それらを比較し、変化を抽出することを目的として試行的に実施した。対象地域は、沖縄県の西表島仲間川下流域にあるガリー沿いにマングローブ林の破壊が観察された地域とした。結果として、SfMで空中写真からDSM・オルソを生成することで、既存の10mメッシュデータよりはるかに精密なDSMが得られた。ただし、DEMではない。また、高精度のオルソフォトが得られた。今回の例では、地上解像度0.3mである。多時期の空中写真を用いることで、横方向の変化、つまりマングローブ林の拡大のみならず、縦方向、バイオマスの変化についても調査可能である。
抄録全体を表示
-
池田 真利子
セッションID: 323
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
都市ベルリンは,分断都市としての歴史を背景とし東西で異なる変化を遂げてきた.とくに政治転換期以降,ベルリンの旧東西境界域では,その場所の開発を巡り,都市の在り方と併せ議論が成されてきた.本研究は,2000年代初頭から計画されていたシュプレー川沿岸域におけるメディアシュプレー計画と,それに対抗する文化施設および市民団体の反対運動に着目することにより,都市空間において文化が担う意味を多面的に分析する. 東西統一以降,旧東ベルリン地区では芸術や音楽に関連する文化的利用が発現した.なぜなら,東西分断期にて急進的に近代化・都市化が進められた旧西独地区に比較して,旧東独地区には,放置・老朽化した空き家や未利用地が未修復・未解体の状態で残されていたためである.また,こうした空き家や未利用地の一部は,旧ドイツ民主共和国(以下,DDR)に位置したため,その所有権の所在において不明確なものも多かった.こうした所有権の不明な土地・建物において,東西統一前後から,アーティストや市民団体による文化的利用が積極的になされた.シュプレー計画とは,シュプレー川沿岸域において計5地区にわたり計画された事業であり,事業面積は約180haにも及ぶ.事業主は,2001年に土地所有者である市議会・地区議会・商工会議所(IHK)の代表者により期間限定的に設立されたメディアシュプレー有限会社(Mediaspree GmbH)である.同有限会社は,2001年から,「コミュニケーション及びメディア関連産業」を中心とするオフィス・商業施設の誘致を開始した.2006年にメディアシュプレー計画に対して,最初の反対運動が発生した.運動主体は文化施設運営者や市民イニシアチヴから成る市民イニシアチヴ連合(以下,市民連合)であった.この市民連合は,公共緑地の不足と,シュプレー川沿岸域の文化施設の立ち退きに対する反対を主張した.特にメディアシュプレー計画が多く位置するフリードリヒスハイン=クロイツベルク地区では,反対運動への賛同者が多く,デモンストレーションや署名活動の結果,16,000人分の有効署名を基に地区選挙が開催された.地区選挙の結果,①新規建設に際し,河岸より50m以上の距離を保持,②地上から軒下までが22m以上の高層建築の禁止,③橋梁建設の禁止という案が87%採択された.しかし,投票結果はその後,市政に反映されず,現在では個々の文化施設が移動する際に反対運動が発生する程度にとどまっている.旧東西境界に近接する場所は,東西分断時には国家の縁辺部として衰退していたが,統一後に地理的中心性を回復した.こうした衰退地域において,アーティストや市民が文化的利用を行った結果,クリエイティヴな場所のイメージが創出され,こうした都市イメージを利用した都市開発メディアシュプレー計画が考案された.こうした文化的価値が経済的価値へと置換されていく過程は,新たなジェントリフィケーションとして理解することができるのではないであろうか.また,こうした変容過程において,市民運動の主体は観光資産としての重要性において自らの存続を主張する.こうした市民運動そのものが,新自由主義経済下において変容を遂げつつあると解釈できる.
抄録全体を表示
-
横山 俊一, 長谷川 直子, 谷口 智雅, 宮岡 邦任, 戸田 真夏, 大八木 英夫, 元木 理寿, 山下 琢巳, 早川 裕弌
セッションID: P066
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本研究は水と人の地誌研究グループで目指している地理学的視点を取り入れたガイドブックの作成のため関連分野の書籍の出版状況の地域的特徴の一端を考察することを目的としている。ガイドブック作成の際には一般読者の求める地域のニーズが重要となってくる。そこで本研究では『出版年鑑』の書籍目録を用いてガイドブックで取り上げている地域について考察をおこなった。
抄録全体を表示
-
宮城県岩沼市を対象に
泉 岳樹, 山本 遼介, 大澤 啓志
セッションID: 905
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1 はじめに
2011年3月の東北地方太平洋沖地震による津波により東北地方から関東地方にかけての海岸林は甚大な被害を受けたが,津波の高さや微地形の影響などにより残存した海岸林もある.残存海岸林では,被災後1年以上経ってから枯死する樹木もみられるため,その動態を捉えることは,海岸林の再生を計画する上でも重要である.本研究では,近年,技術革新が進むUAV (無人航空機)を用いて地上解像度約3cmという超高解像度の画像を取得することにより残存海岸林の実態把握とオブジェクトベース画像解析による樹種判別を試みる.
2 現地調査の概要
対象地域は宮城県岩沼市沿岸域の長谷釜地区とした.この地区は,石川・大澤(2013)の現況調査により仙南地域で最も多くの残存海岸林が確認されている.使用するUAVは,(株)情報科学テクノシステムのRobinというシングルローターの無人ヘリコプターで,2013年6月30日,7月1日の早朝に高度約150mから撮影を行った.オーバーラップ率約80%,サイドラップ率約50%のステレオ画像を約1600枚取得した.また,2013年8月に植生調査を行った際に,樹種判別のグランドトゥルースデータとしてクロマツ,アカマツの位置を計33本分取得した.
3 取得データの概要
取得したステレオ画像を写真測量ソフトで処理し,オルソモザイク画像(図1 左)とDSM(数値表層モデル)を作成した.オルソモザイク画像を目視すると,枝葉を細かく確認することはできないが,樹冠の形態的特徴ははっきりと読み取れ,色彩情報と合わせることで,単木単位での樹種判別ができる可能性があることが分かった.次に,DSMは楕円体高となっているので,ジオイド高を減じてDSM (標高)を求めた.DSM (標高)から基盤地図情報の5mメッシュDEMを減じることにより,残存海岸林の樹高を推定した(図1 右).単木単位の樹冠形状を捉えることはできなかったが,海岸林の残存状況を定量的に把握できることが明らかとなった.
4 オブジェクトベース画像解析による樹種判別
残存海岸林の一部を対象(図2 上)にオルソモザイク画像とDSMを入力データとしたオブジェクトベース画像解析による樹種の自動判別を試みた(図2 下).クロマツとアカマツのみを対象として検証を行ったところ,判定精度は84.2%であった.その他の樹木や陰影が大きな誤差要因となるため,現状では,樹種の自動判別による単木単位での分布図作成は困難であることがわかった.可視域の色彩情報のみでの解析には限界があるため,自動判別の精度向上のためには近赤外域のデータや樹冠形状を単木単位で捉えたDSMなどの新たな情報の追加が必要と考えられる.
参考文献 石川幹子・大澤啓志(2013): 仙南平野海岸林調査報告書, pp149.
抄録全体を表示
-
馮 雷
セッションID: 806
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1. はじめに 1949年新中国建国から70年代末まで、保守な社会主義計画経済体制、「上山下郷」などの政治運動の影響を受け、閉鎖的な環境下、中国都市の発展はほぼ停滞した。1978年改革開放以来、対外開放政策を実施する同時に、対内改革の試みも取り組んできた。その結果、大都市への人口集中、また都市間の人口移動も活発するようになった。更に、1992年以降、社会主義市場経済へ移行する過程で、中国の都市において、急激な人口増加を成り遂げ、2014年現在、人口1000万人を超える大都市が幾つ登場してきた。近年、中国における都市化の進行や、住宅市場の自由化によって、大都市に限らず、地方中小都市への人口集中も目立つようになった。多くの流入人口の受け皿とした都市住宅の需要が高まり、旧市街地の再開発や、周辺部の農村を編入による市街地の外延的拡大という一般的な開発パターン以外には、既存の市街地のすぐ横に、新しいまちを開発するまでになって、いわゆる「造城運動」が盛るとなった。但し、これらの新たな作ったまちは住宅ビルが林立しているにもかかわらず、住民の影が見当たらない「空城」となった。これら「空城」の出現は学術界における議論がまだされていないが、中国の都市化を理解する際に、十分に研究する必要があると考えられる。 2. 研究目的 本研究は、「空城」発生のメカニズムと形成の経緯によって、類型化することを図りたい。筆者はこの「空城」を形成することを発展を先行する開発と呼ばれる「分裂型都市化」という論説との関連性を検討しつつ、さらに「空城」が形成する制度的な要因に導きたい。本来「分裂型都市化」は成功事例として挙げたことにした。いわば、国家戦略である上海浦東新区の開発によって、都市の国際地位の飛躍的な上昇に伴いヒト、富、情報は上海に集まるようになった。 3. 結論 「空城」形成の理由として以下の三点が考えられる: ①「城郷二元化」の国土構造による農村人口が都市への自由流動を障害し、また都市に流入した農村人口の収入や待遇などは都市人口との格差が大きく、都市での住宅を負担する経済力がない;②1978年から住宅制度改革を提起したから1998年7月に至って、福利住宅分配制度が終結され、住宅分配貨幣化への移行を果たした。その結果、不動産市場の自由化により、利益を追求した開発行為により過剰的な開発が発生した;③1994年分税制改革以来、地方政府は財政を確保する手段として、土地資源を手放し、「商品房」(自由売買できる住宅)の開発を通して、地方政府収入の重要な財源となった。住宅需要と供給の不均衡は、中国の都市における潜在化している問題となり、結果として「空城」という形で現れた。以上の考察を通して、近年の中小都市における「造城運動」が意図的に、質的には都市化の本来の姿と異なり、地方政府が主導する投資的な開発行為となる成分少なくはない。 本研究を通して、過去30年中国都市住民の居住空間の変容と再編を踏まえながら、社会主義体制下土地国有化を前提とした中国の都市構造の形成を解明することにあたって、重要な意義があると考えられる。
抄録全体を表示
-
ラナウィーラゲ エランガー
セッションID: 301
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
保護区域における 観光は、収入と雇用の増加を通じて、自然を保護しながら維持管理のための資金調達をするといった経済発展を促す可能性を提供している。保護地域は重要な環境価値を有しており、それらしばしば敏感な環境に置かれている。そのため、これらの地域の観光は持続可能なものであるということが重要になってくる。
持続可能な観光を確立させるには、観光客による環境に対する有害な影響を抑制し、地域コミュニティーを守り、そして訪問者の満足度に対しての管理が必要となります。特に発展途上国では、観光からの短期間のうちに経済利益を得るための政治的圧力により実行不可能な慣行がしばしば推奨され、結果として観光影響観光の経済的利潤の遅延を招くことがある。本研究で取り上げるスリランカは観光客を誘致する多くの自然の魅力をもつ発展途上国である。
本研究はウダワラウェ国立公園と呼ばれるスリランカの有名な保護区域を事例にスリランカの保護地域での観光に関連する特色と問題点を、スリランカの保護地域の運営に関する資料の分析、および国立公園内やその他の保護地域での観光の管理や政策を担当する当局のさまざまなメンバーへのインタビュー、そして 、公園にて観光客へのアンケート調査や観光客の行動や観光活動を直接観察することによって検討したものである。
現在の公園管理システム、観光客の特性や行動の分析によると、観光活動による動物への攪乱 、過密化、ガイドや通訳システムの乏しさが公園内の観光の主な課題であることが明らかになった。
抄録全体を表示
-
原発事故後の「福島」の地理的スケール
水野 勲
セッションID: 321
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
福島第一原発という名前が、もしも別の名前(たとえば、双葉大熊原発)であったなら、福島県の農産物の風評被害を避けられたのに、というコメントを、発表者は福島県での調査の際に何度か聞いた。そもそも風評被害とは何であり、それは地名とどのように関わるのだろうか。 地名は単に、特定の土地に付けた名前であるだけではなく、集合や関係についての論理階型(logical type)の問題を含む。そこで発表者は、集合論のアプローチにより、原発事故後に「福島」という地名が、さまざまな地理的スケールで、どのような区別と「空間の政治」を含んでいたかを考察したい。
2011年3月の福島第一原発事故の前には、「福島」は福島県か福島市としか関係がなかった。しかし、原発事故後、県と市と事故原発が同じ名前をもった、自己言及性の集合関係におかれた。このため、「I love you & I need you ふくしま」という応援ソングが、原発事故から1ヵ月後に猪苗代湖ズ(福島県出身のミュージシャンの即席グループ)によって歌われたのである。ここで福島県という行政領域が、原発事故をめぐる言説の特権的な地理的スケールになったことに注目したい。福島ナンバーの自動車、福島県産の農産物、福島県出身者が、何のコミュニケーションもなく区別されたからである。これは、放射能汚染地=福島県という単純化(区別)を行うことにより、さまざまな空間政治的な効果をもった。東京オリンピックの招致では、福島は東京から遠いという言説が用いられたのは、その区別の一例であろう。 しかし、別の地理的スケールによって、問題の地平を提示することができる。福島県内のスケールでは、福島第一原発の事故によって避難を余儀なくされている「警戒区域(後に避難準備区域)」、あるいは原発事故によって避難している住民および役場の場所を、「福島」と呼ぶこともできる。また広域ブロックのスケールでは、放射線管理区域の指標である年間1mシーベルトの空間放射線量の地域(東北、関東の一部)あるいは福島第一原発から電力を供給されていた関東地方を、「福島」と呼ぶことができる。そして、国家スケールでは、福島から自主避難している住民の居住地(全国都道府県に分散)あるいは全国の原発施設のある地域を、「福島」と呼んでもいいのではないか。さらに、グローバルスケールでは、諸外国が日本からの農産物輸入を禁じている都道府県(東日本に広がる)あるいは原発事故の放射性物質が大量に撒き散らされた太平洋地域を、「福島」と呼ぶべきではないか。「福島」という地名を、県という地理的スケールに閉じ込めて議論することは、きわめて恣意的な「空間の政治」であると考える。
抄録全体を表示
-
2012年調査・自由回答記述の構造分析
坪井 塑太郎
セッションID: 104
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ.問題所在と研究目的
アンケート調査においては,あらかじめ設定された尺度(選択肢回答法)において回答を求め,これをもとにデータ解析が行われる場合が多く,これまで「自由回答」は,そのデータ解釈を補完するものとして位置付けられてきた.しかし,近年では,企業ソリューションの現場等において,アンケートの自由回答記述やWebサイトに寄せられるユーザーからの書き込み,twitter,Facebook等のSNSへの投稿テキストをもとに,顧客や市場のニーズを抽出し,製品やサービスへの不満点等を分析する「テキストマイニング」手法が着目されつつある.本研究では,同手法により,東日本大震災における被災者の高齢者支援に関する自由回答を対象とし,要望の構造を明らかにすることを目的とする.
Ⅱ.研究方法
本調査は,東日本大震災における被災3地域(岩手県大船渡市・宮城県気仙沼市・福島県新地町)において,発災から1年後の2012年3月に行ったアンケート調査に基づき分析を行った.分析にあたっては,出現用語における表記の統一(「買物」「買い物」「買いもの」,「仮設」「仮設住居」「仮設住宅」等)を行った後,文法による形態素の分類と採用品詞による選択を経て出現頻度による集約解析を実施した。本研究では,自由回答のもつ意味空間と属性との関係を検討するために,「調査地域」「被災状況」「復興感」「年齢」「性別」を外部変数として設定し,データ欠損値を除く936件を分析対象とした.
Ⅲ.分析結果
出現用語の係り受けを考慮してその出現数の傾向をみると,3調査地に共通して「病院」や「買物」への「交通」の「便」の改善に関する支援要望が多く見られた.また被災状況と復興感を外部変数とする多重対応分析を行った結果,「全壊」の被災者は,復興感が「0~20%」と低く,仮設住宅での生活全般にかかわる支援要望が見られた反面,「一部損壊」や「無被害」の被災者は,比較的高い復興感をもち,その要望は「介護」や「デイサービス」などより高度な要望になっていることが明らかになった. 本調査は同一地域を対象とした3年間の継続調査で実施されており,今後は被災者の支援要望の変化や要因等についても併せて検討していくことが課題である.
抄録全体を表示
-
岩船 昌起
セッションID: 101
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
【はじめに】東日本大震災では、岩手県宮古市でも津波襲来直前まで防潮堤門扉の閉鎖や警戒活動等に携わっていた消防団員16名が殉職された。現在、被災地だけでなく日本各地で地域防災計画の見直しが行われており、命を優先した避難体制の強化が求められている。 本発表では、2012年12月7日に三陸沖で発生したマグニチュード7.3の地震に対応した消防団員の行動を考察し、岩手県宮古市で現在進められている「津波避難計画」の中の「緊急避難(レベル)」を紹介する。また、命を優先した避難体制との係りから防潮堤の門扉や乗り越し道路等のハード面についても若干の考察を加えたい。
【被災地区消防団員の津波警戒時の対応行動】2012年12月7日17時18分頃に三陸沖(牡鹿半島の東、約240km付近)でマグニチュード7.3(速報値)の地震が発生し、盛岡市と滝沢村で震度5弱、また久慈市、宮古市、陸前高田市等で震度4が観測された。この地震による強い揺れを受けて、宮古市では17時18分に災害警戒本部が設置された。一方、気象庁では17時22分に青森県太平洋沿岸、岩手県、福島県、茨城県に津波注意報が発表され、宮古市での津波到達予想時刻が17時50分とされた。消防団員は、地震による揺れを感じた場合には、取り決めとして、防潮堤の門扉の閉鎖や地域住民の避難誘導等に当たるために、災害本部等からの指示を待たずにまずはそれぞれ屯所に向かう。例えば、東日本大震災の津波被災地区の宮古市新川町に立地する第一分団の分団員Aは、地震発生時17時18分に屯所と同じに町内の職場におり、道のり約130mを歩いて17時21分に屯所に到着し、屯所から道のり約50mにある「第三水門」を「1分で閉めた」という。しかし、非被災地区の仮設住宅に住んでいる分団員Bは、地震発生時17時18分に仮設住宅で夕食の準備をしており、多少片付けてから道のり約1.5㎞を歩いて22分かかり17時40分に「既に閉じられていた第三水門」に到着した。そして、屯所から道のり約290mの中央公民館まで歩いて到着し、津波到達予想時刻の17時50分に「高台避難」を完了させた。このように津波被災地区では、東日本大震災以降、被災者である消防団員の多くが非被災地区の仮設住宅等に移り住んだために、地震発生直後数分で津波警戒行動に従事できる「被災地区で生活する分団員」の人数が極めて少なくなり、被災地区に立地する消防分団の緊急時の活動が極限られた分団員で何とか維持されている。これは、消防団員の高齢化と共に看過できない問題である。
【宮古市津波避難計画における緊急避難】宮古市では、地域防災計画で「消防団員は津波到達予測時刻10分前には高台に避難していなければならない」という「10分ルール」を定めた。そして、これを完了させるために20分前には防災行政無線で消防団員の避難を呼びかけることとしている。従って、宮古市では津波到達予想時刻の20分前からは浸水の恐れがある地区での消防団等による公助が基本的一時的に終了し、それ以降から津波到達予想時刻までは共助と自助で住民個々の避難が行われなければならないこととなる。2014年1月現在策定中の宮古市各地区での「津波避難計画」では、消防団の「10分ルール」に呼応する形で、地域住民の避難行動も津波到達予想時刻の20分前から「緊急避難(レベル)」に移行することが提示されている。「緊急避難」とは「津波到達予想時刻の20分前になった時点で初動避難の目標の避難場所に到達していない場合の避難行動の様式」である。約20分後に津波が到達することと、自分の体力との関係を考慮した上で、現在位置から「目標の避難場所」に到達できるかできないかを判断して、できると考えた場合にはそのままの徒歩等を続けて、できないと考えた場合には現在位置から一番近い避難ビル等の高所に逃げ込む。これは、堤防を越えた津波の動きの解析と人びとの体力に応じた避難行動の様式に基づいている(岩船 2012)。
【防潮堤門扉の手動閉鎖の問題】宮古市の消防団の「10分ルール」および「緊急避難」の実施を考えた場合、漁港等と市街地との間に設置された防潮堤門扉の閉鎖はそれらを妨げる可能性が高い。例えば、津波襲来前に「船出し」を行うために港に急行したい漁業関係の「懇願」等によって、ギリギリまで門扉を閉鎖できないからだ。安全性を考慮して遠隔操作できる門扉等が開発されているが、津波襲来直前まで堤外にいる人々の「自助」での避難行動を阻害しないためにも「乗り越し道路」が少なくとも要所に一つは必要であろう。地面との比高が大きい堤防であるほど、設置に必要な用地も広くなるが、生死が懸かった究極の場面でのトラブルを未然に防ぐためにも、各自の判断で避難行動が自由に選択できる施設環境が整備されることが望ましいだろう。
抄録全体を表示
-
柴田 陽一
セッションID: 809
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ.はじめに
昨年,2012年に実施した長春近郊農村調査の内容と,中国を対象とする教育地理学的研究の課題について,拙論(2013)をまとめた。その中でも言及したことであるが,「改革開放」後,中国は義務教育法(1986年)を制定し,義務教育(小学校6年と初級中学3年)の普及を進めてきた。1980年に93%だった小学校入学率は,2010年現在,99.7%に達している。しかし,中国の義務教育は,①地区間および都市-農村部間の学校における教育格差,②学校統廃合(分布調整)による通学困難児童の出現,③都市部における農民工子弟の教育など,いまもなお多くの問題を抱えている。本報告では,吉林省中西部に位置する松原市中心部を事例として,新しい地級市の誕生(1992年)による行政区域の再編やそれと並行する都市化の進展と関連づけながら,約30年間の小学校通学区域の変化を明らかにし,上記の諸問題の一端について考察しようとするものである。
Ⅱ.行政区域の再編と都市化の進展
人口約290万人の松原市は,寧江区(市轄区),扶余市(県級市),乾安県・長嶺県,前郭爾羅斯蒙古族自治県(以下,前郭県)を管轄する。その中心部は松花江を挟んだ2つの地区から成る。かつて江北地区は扶余市(現在の扶余市とは異なる),江南地区は前郭県に属していたが,1992年の松原市誕生にともない,江南地区の大部分も扶余区(後の寧江区)に編入された。また,1992年以後,江北・江南地区ともに都市化の進展が著しい。『吉林省地図集』の「城市建設用地拡展」を見ると,かつて市街地とは独立した集落であった郊外村のすぐそば,もしくは中に新しい直線道路が整備された様子が理解できる。こうした行政区域の再編および都市化の進展が,小学校通学区域にも影響を与えていると想定される。
Ⅲ.フィールド調査
2013年8月17日~26日に,斉斉哈爾大学の王治良氏と共に実施した。現地で調達した市街地図やネットの情報を頼りに,中心部にあるはずの小学校を一つひとつ訪問し,現在地を確認した。そして学校関係者(校長,一般教員,用務員)および周辺住民に,学校の規模(児童数・学級数),通学区域,位置・名称の変化,スクールバスの有無などを尋ねて回った。また,学校周辺の様子も観察した。その結果,中心部には約30校の小学校が存在し,4つの管理主体の下に置かれていることが判明した。すなわち,松原市教育局,寧江区教育局,前郭県教育局,油区教育処である。なお,カウンターパートの中国人研究者を通じて教育局(処)への訪問を何度も試みたが,最後まで実現しなかった。
Ⅳ.小学校通学区域の変化
一部の小学校では,校門等の掲示から通学区域が判明したし,聞き取りやネットの掲示板によって何々路の北,何々街の東といった大まかな範囲を知ることができた例もあった。しかし全体としては,日本と同じレベルで通学区域を知ることは困難であった。ある小学校教員によると,教育局(処)には通学区域を示した「学区地図」があるらしいのだが,それを入手することはできなかった。そこで,中心部の小学校数と位置の変化から,この問題を考えてみたい。約30年間に新設された学校数は多くない。おそらくは1992年以後に開発された地区に置かれた1校のみ(市直轄校)であろう。逆に,統廃合された学校は4校あり,いずれも1992年以前の市街地とは独立した郊外村にあったものである。統合先は市街地と郊外の境に位置する学校(通学区域が広く,そのためスクールバスを所有)である。そのうち2校は1992年以前の市街地から移転してきたものである。このように,松原市中心部の教育空間は,市街地の学校(スクールバスなし,通学区域が狭い),市街地と郊外の境に位置する学校(スクールバスあり,通学区域が広い,郊外の学校の一部を分校として統括する拠点の役割を担う),郊外の学校という三層構造になっており,それに応じた通学区域が設定されていることが理解できる。ただ,中国の通学区域の問題はそう簡単ではない。この点については報告時に議論したい。
拙論2013.中国を対象とする教育地理学的研究に向けて―長春近郊農村調査を起点として.小島泰雄編『中国東北における地域構造変化の地理学的研究―長春調査報告』京都大学人間・環境学研究科地域空間論分野,56-67.
本研究には,科学研究費補助金(基盤研究(B)海外学術調査,課題番号24401035,代表者小島泰雄)の一部を使用した。
抄録全体を表示
-
島津 弘
セッションID: 116
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに 仙台平野は2011年東北地方太平洋沖地震による津波被害を受けた.名取川に沿って津波はおよそ6km遡上した.名取川下流堤外地は伝統的土地利用慣行が残り,高水敷は現在でも民地として耕作が行われ,これらの農地は津波遡上の被害を受けた.地震津波災害以降,名取川では複数回の洪水が発生し,高水敷にも氾濫した.このとき津波堆積物や塩分が流されるとともに,一部の農地は再び被害を受けた.津波災害後,放棄されたままの農地もあったが,多くは再耕起された.しかし,その後放棄される農地が拡大してきた.本発表では津波遡上およびその後の洪水時の水の流れと高水敷への影響を河川の微地形との関係から明らかにし,耕作放棄およびその拡大との関わりを検討した.現地調査は2011年5月(被害状況,表層堆積物),8月(農地の復興状況,津波被害聞き取り),2012年11月(地形断面測量,その後の洪水による影響,耕作放棄の状況),2013年11月(耕作放棄の状況)に行った.また,耕作放棄状況の把握には空中写真およびGoogle Earthの画像も用いた.
2.名取川堤外地の微地形と津波遡上プロセス
名取川堤外地の微地形と津波遡上の概要についてはすでに報告した(島津,2012,日本地理学会発表要旨集82).堤外地部分は流路となっている低水敷と平水時の水面とは2m程度の比高がある氾濫原である高水敷に分けられる.高水敷は2段の地形面に分けられる.地形面上には流路跡と考えられる縦断方向に延びる浅い凹地が見られる. 河口からの距離に応じて遡上した津波の強さと卓越するプロセス,微地形との関係が異なる.河口~2.5kmでは高水敷における水深が4m程度に達し,遡上および引き波による強い侵食が生じた.2.5km~4kmでは高水敷における水深は3m程度で堆積プロセスが卓越した.4km~5kmでは津波の深さが急に浅くなった.微地形の高まり部分は水没しなかったが,そのほかの部分では水流があり,堆積が生じた.5km~6kmでは微地形の低まりの部分を津波が遡上した.津波が遡上した部分ではわずかに堆積が生じた.
3.津波災害後の河川洪水による高水敷への影響
津波災害後の2011年9月,2012年5月,6月に流域で豪雨が発生した.調査地域の上流端の名取橋におけるこれらの出水時の最高水位は平水時の+4~4.5mであった.聞き取りによると高水敷上に氾濫し,河口から4km地点より上流側における影響が大きかった.微地形の低まりの部分では湛水したこともあり,作付けされていた作物が大きな被害を受けた.一方,高まり部分も影響を受けたが,被害の程度は小さかった.氾濫水が低まりの部分を集中的に流下したことが推定できる.2012年11月の観察では,堤防沿いの微地形の低まりの部分では,観察直前の雨で湛水していた.このような部分で耕作を行っている人もいたが,降雨後にしばしば湛水するようになったとのことである.
4.津波災害後の耕作放棄地の拡大と微地形の関係
津波災害後の5月上旬に現地に入ったときには,盛んに再耕起が行われていた.一方,そのままで放置された農地も多く存在していた.そのような農地は2.5kmより河口寄りに多く,津波による被害程度が大きかっただけでなく,閖上地区では耕作者の死亡,移転により放棄されたところもある. 一度,上流寄りでも再耕起されない場所や,再耕起されたところでもその後放棄された場所も見られた.それらは微地形の低まりの部分に集中し,帯状に分布している.以上のことから,高水敷の微地形が津波遡上とその際の地形プロセスに影響しただけでなく,その後の河川洪水の際も大きく影響した.排水不良地を形成し,その結果そのような場所が耕作放棄につながったと考えられる.
抄録全体を表示
-
つくば市N小学校区の事例
王尾 和寿, 村山 祐司, 温井 達也, 相澤 道代
セッションID: 701
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
近年、通学途中の児童と自動車の接触事故、震災や竜巻被害の発生などを契機として、通学路における児童の安全確保は喫緊の課題となっている。本研究では通学路の不安箇所を把握し改善につなげるため、地域に居住し地域を熟知している保護者の視点で不安箇所を抽出し、その属性を用いて空間的特性を明らかにした。データ取得については、地域の危険箇所や不安箇所に関するデータ収集を行うため、2012年10月および2013年12月に、茨城県つくば市内のN小学校区において、児童と保護者による通学路点検を実施した。集団登校に保護者が同行し、通学路の不安箇所を、交通、犯罪、災害の視点でチェックし、GISデータベースを作成した。次にカーネル密度推定により、不安箇所の分布特性を把握し、属性情報と共に分析を行った。 結果として2012年では108枚の不安箇所マップを回収し、393地点の不安箇所(交通不安244、犯罪不安86、災害不安63)を取得した。また2013年では111枚で382地点(交通不安226、犯罪不安101、災害不安55)の不安箇所を取得し、両年次共、交通不安の箇所数が最も多かった。2013年データに対してカーネル密度推定を適用した結果、交通不安、犯罪不安、災害不安、それぞれに不安地点密度の高い場所が異なっていた。交通不安は箇所数が最も多く、学校区全体に分布しているが、特に交通量の多い幹線道路を横断する地点で、密度の高まりが見られた。犯罪不安については、民家や人気が無い農道での不安感が高かった。災害不安については、周辺に民家が無く、災害発生時に避難する場所も無い地域での密度が高く、2012年調査と比較して不安感の高まりが見られた。また、道幅が狭く家屋が密集する地域での不安感も高く、塀や壁が崩れる恐れを指摘する声が多かった。さらに、児童の性別と保護者の不安感の関係を探るため、交通、犯罪、災害、それぞれの不安箇所について、男児のみが通学、女児のみが通学、男女が通学、の3タイプの割合を計算した結果、犯罪不安では女児のみが通学している保護者の割合が高く、災害不安では男児のみが通学している保護者の割合が高い傾向がみられた。
抄録全体を表示
-
赤坂 郁美, 王 露莎, 高橋 日出男
セッションID: P028
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1. はじめに 内モンゴルにおける年降水量は100~500mmほどで,その約6~8割が夏季(6~8月)に集中するため,夏季降水量の年々変動が水資源に与える影響は大きい。そのため,これまでの先行研究により,内モンゴルの各地域における降水の長期変動傾向が調査されている(e.g. 蘇ほか,2010).しかしながら,内モンゴル全域を対象として降水変動とその地域特性を詳細に明らかにした研究はほとんどみられない。そこで本研究では,内モンゴル全域における夏季降水量の年々変動とその地域特性を明らかにすることを目的とする。また夏季降水量変動の要因についても考察する。
2. 使用データ及び解析方法
夏季降水量データとして,内モンゴル気象局によって観測された1961~2007年の7月の月降水量データを使用した。解析に使用した観測地点は23地点で,解析対象期間中に欠測は含まない。また降水の年々変動と大気循環場との関連を解析するために,NCEP/NCAR (National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research)の2.5ºグリッドの再解析データ(Kalnay
et al. 1996)から850hPa面高度,風系,比湿の月別データを使用した。解析対象期間は降水量データと同じ期間とした。 まず夏季降水量の年々変動パターンの類似性に基づく地域分類を行うために,規準化した23地点の月降水量偏差データにクラスター分析(ユークリッド距離,Ward法)を行った。クラスター分析の結果に基づき,クラスターごとに降水量偏差の平均を求めた。降水量の年々変動に関する解析を行うために,平均降水偏差が0.5以上の年を降水が多い年,-0.5以下の年を降水が少ない年として,それぞれの場合の降水分布,大気循環場の特徴と関連を考察した。
3. 結果と考察 夏季降水量の年々変動パターンは大きく3つに分類され,各クラスターに属する地点は内モンゴル北東部(クラスター1:C1),中央部(クラスター2:C2),西部(クラスター3:C3)にまとまって分布する結果となった。降水が多い年,少ない年の降水量分布をみると,いずれの年もC1地域とC2地域を中心に降水量が多い。降水が多い年の850hP面の大気循環場をみると,C1およびC2地域周辺に低気圧性の循環がみられた。また太平洋高気圧西縁部が中国南部に向けて張り出していた。つまり,対流圏下層の低気圧性循環の位置と太平洋高気圧西縁部の中国南部への張り出しの強さにより,中国南部から内モンゴルにかけての水蒸気輸送量とその経路が異なり,C1およびC2地域の夏季降水量が変動すると考えられる(図1)。またC3地域では,内モンゴル北東部と中央部とは異なり,梅雨前線の北上が夏季降水量の年々変動に関連していることが分かった(図略)。
引用文献
Kalnay, E.
et al. 1996. The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project.
Bull. Amer. Meteor. Soc.77: 437-471.
蘇立娟・鄧曉東・達布希拉図・闫宾・毕力格 2010.内蒙古東部近40年気温降水変化分析.
Journal of Anhui Agriculture Science.
38(21):1214-1215.
謝辞:本研究の一部は文部科学省GRENE事業、日本学術振興会科学研究費補助金(20240075及び24501297)の支援により実施した。
抄録全体を表示
-
久保 倫子, 由井 義通, 益田 理広, 石坂 愛, 神 文也, 川村 一希, 羽田 司, 矢ヶ﨑 太洋, 阪上 弘彬
セッションID: 813
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.研究の目的と方法
1960年代以降,大都市圏郊外地域では,短期間に大量の住宅が供給され郊外化が急激に進展した。開発から30~40年を経過したこの種の住宅団地では,世帯主が一斉に高齢化するとともに,その子らも独立,転居してしまい,高齢者のみで構成される世帯が急増し,その後空き家化を免れぬ状況が生じている。空き家が増えると,地域社会の衰退や治安の悪化などの問題が発生する。空き家の発生には地形的条件,地域の社会経済的条件,土地・住宅の特性,世代交代の進捗具合などが複雑にからみあって影響している。そこで,本研究では茨城県牛久市を事例として,空き家問題を地誌学的手法により検討する。つまり,空き家増加に関係する住宅市場や制度の問題,牛久市や住宅地の地理的特性,住民の社会経済的特性,住宅個別の条件のほか,空き家問題に対する住民の意識や地域と住民の関わり方などを総合的に分析する。人口約4万人を擁する牛久市は,JR常磐線により東京都内への通勤が可能であることから,1970年頃から住宅団地の開発が盛んに行われた。市内の住宅地においては空き家の増加が顕著であり,空き家等の適正管理に関する条例を制定している。
2.調査の手順
本研究の目的を達成するため,牛久市内の4つの住宅地において現地調査を実施した。最もJR牛久駅に近接したA地区は全1,606戸のうち68件の空き家がある。B地区は全925戸に対し76件,C地区は全360戸に対し33件の空き家がある。駅に近接しているものの駅へ向かう過程で急勾配の坂を経由するD地区では,全475戸に対し32件の空き家が確認されている。調査内容は,①空き家実態調査:空き家の周辺に居住する住民に対してインタビュー調査を行い,空き家になった時期,理由,空き家化する前の居住者の特性などを明らかにした。②住民へのアンケートおよびインタビュー調査:自治会の協力を得て,4地区の全戸を対象にアンケート調査を実施した。居住経歴,将来的な家の管理や空き家に対する考え方,子の居住地,地域との関わり方などを問うた。各地区のアンケート回答数と回収率は(2014年1月14日現在),A地区391(24.4%),B地区172(18.6%),C地区61(16.9%),D地区196(41.3%)であった。さらに,自治会役員に加え、約20名の住民に対してインタビュー調査を行い牛久市での空き家増加の要因を検討した。
3.空き家化の要因
空き家化する要因を検討すると,居住者の高齢化と世代交代に関するもの,経済的要因,制度上の問題,個別の事情などが挙げられる。また,大都市圏の居住地域構造が郊外化から都心回帰に向かう中で,若年層の就業状況や居住選好,住宅市場が大きく変容し,大都市圏における牛久市の立ち位置や機能が変化してきたことの影響も大きい。
【付記】本研究では,公益財団法人国土地理協会助成金(「郊外住宅地における空き家発生の実態とその対策に関する基礎的研究」研究代表者:久保倫子)を使用した。
抄録全体を表示
-
岩手県陸前高田市の事例
矢ケ﨑 太洋, 吉次 翼
セッションID: P045
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本研究は東日本大震災の被災地における住民の自主再建住宅の分布を速報的にまとめるとともに、分布の形態とその立地に関する分析と考察することを目的とする。 2011年3月11日に発生した東日本大震災によって三陸沿岸地域は大きな被害を受けた。こうした被害によって被災した三陸沿岸地域の平野部に居住していた住民の仮設住宅への入居や地域外への流出、同地域内の非浸水地への自主再建が促進される一因となった。自主再建は住民が自前で土地と住宅を調達し、自主的に再建を行う復興形態であるが、仮設住宅と比べると景観や土地利用に基づいて把握することが容易でないため、調査・研究が進んでいない。地域住民の自主再建は被災地の復興計画および復興後の地域構造に影響を与えるため、自主再建の現状把握と分析は今後の復興において重要な意味を有する。
抄録全体を表示
-
吉田 圭一郎, 廣田 充, 水野 一晴
セッションID: 902
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
I はじめに
近年,地球温暖化の影響が様々な生態系において顕在化している.熱帯の高山植生も例外ではなく,気温上昇やそれに伴う氷河の後退,消滅により,深刻な影響が生じつつある.そのため,熱帯における高山植生の成立過程を明らかにし,現在進行中の気候変化による影響を予測することが急務である(Herzog et al. 2011).こうしたことから,発表者らは2012年より熱帯高山における気候変化による生態系への影響を明らかにする目的で,熱帯アンデスの氷河後退域において調査を行ってきた.
一般に植生発達過程や遷移系列を明らかにするためには,当該地域への植物の侵入定着プロセスを考慮する必要がある.特に,高山植物は厳しい寒さなどの環境に適応するため,特有の生活型や生育形をもっており(Nagy & Grabherr 2009),氷河後退域への侵入定着プロセスは種毎に異なることが予想される.
そこで,本研究では,熱帯アンデスの氷河後退域における高山植物の分布やその種多様性のパターンについて明らかにするとともに,出現種の生活型や生育形を考慮した植生発達について検討した.
II 調査地と方法
本研究の調査対象地はボリビア・アンデス,チャルキニ峰(5329m)西カールである.このカールの氷河後退域における植生発達を明らかにするため,標高4800mから5000mで成立年代の異なるモレーン上に計140カ所の調査プロット(2×2m)を設け,植生調査を行った.ターミナル・モレーンでは,40mのラインに沿って,2m間隔で調査プロットを設置し,ラテラル・モレーンでは標高10m毎に調査プロットを設置した.調査プロットでは,植被率,出現種,裸地の比率,最大礫のサイズなどを記載した.なお,植物の同定はHerbario Nacional de BoliviaのMeneses教授に依頼した.
III 結果と考察
チャルキニ峰西カール氷河後退域のモレーン上には,主にイネ科とキク科からなる35種が出現した.イネ科の
Deyeuxia nitidulaが優占しており,木本種の
Senecio rufescens,
Baccharis alpinaや草本種の
Belloa conoidea,
Perezia multifloraが高い頻度で出現した.
一般化線形モデルによる解析の結果,植被率とは異なり種多様性はモレーン年代との対応は不明瞭であった一方で,標高傾度と良い対応関係が認めら,成立年代が同じでも標高が高いほど種多様性が低くなっていた.出現種の生活型組成は,ラウンケアの区分のうち地表植物(Ch)と半地表植物(H)で主に構成されていたが,高標高域では地表植物(Ch)やイネ科を除いた半地表植物(H)の出現頻度が減少した.また,生育形についてみると,低木型や叢生型の種群は標高が上昇しても出現頻度はほとんど変わらなかったが,クッション型やロゼット型の種群の出現頻度は,4800-4850mでは両者ともほぼ全てのプロットで出現したのに対し,4900m以上ではそれぞれ26%と40%と,標高の上昇にともない急激に低下した(表1).このことは,山岳氷河の後退域において,新たな種の侵入や定着には標高傾度に沿った環境条件の差異が影響しており,その結果として種多様性と標高との対応関係が表れたと考えられた.
本研究から,熱帯高山の氷河後退域における植生発達にはその成立年代だけでなく,標高に沿った環境条件に影響を受けた植物種の侵入定着プロセス関与することが明らかとなった.今後,地球温暖化による熱帯の高山植生への影響を理解するために,こうした植物群集の形成に影響する要因についてさらに考慮していく必要があると考える.
本研究は、平成25年度科学研究費補助金基盤研究(A)「地球温暖化による熱帯高山の氷河縮小が生態系や地域住民に及ぼす影響の解明」(研究代表者:水野一晴)による研究成果の一部である.
抄録全体を表示
-
VFXスーパーバイザーの年間コンタクトアナリシス
原 真志
セッションID: 421
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
映画,アニメなどに代表されるコンテンツ産業が経済の牽引力として注目されて久しい(Scott, 2000;2011). また,知識ベース集積論が,イノベーションに重要な暗黙知の共有のため対面接触に有利な近接立地が促進されることを論じたが(Maskel and Malmberg, 1999),間接実証のみで対面接触の直接実証が不足していた(Malmberg and Power, 2005).映画産業ではハリウッドがクラスターとして依然として競争優位を維持しつつ,映画プロジェクトはグローバル化しているという二面性があり(原,2009),さらにプロジェクトベースで時限組織がつくられ多数の主体が相互作用して離合集散するプロジェクトエコロジーの特徴を有する(Grabher, 2002).本研究は,ハリウッド映画産業において,時限組織のプロジェクトリーダーによるどんな立地のいかなるコミュニケーションによって,ローカル&グローバルの空間関係を含むプロジェクトが開発され,実行されるのかのダイナミズムを,コミュニケーション手段の選択を含む分析から明らかにすることを目的とする.
抄録全体を表示
-
南三陸海岸ジオパーク構想の実現に向けて
宮原 育子, 谷口 宏充, 永広 昌之, 久利 美和, 南三陸海岸ジオパーク 準備委員会
セッションID: 108
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
日本におけるジオパークの特徴のひとつとして、自然災害による被災遺構がジオパークの要素として組み込まれていることが挙げられる。北海道の洞爺湖有珠山ジオパークや、長崎県の島原半島ジオパークは、火山噴火による被災遺構をジオサイトの目玉として観光客を引きつけている。
東日本大震災においても被災した沿岸部でジオパークを立ち上げ、ジオツーリズムを進めていくことは、被災地の経済復興に資するとともに、より効果的に子供たちから大人まで、防災教育や自然教育を進めることにつながる。
岩手県は、震災前に進めていたジオパークの整備を震災後直ちに進め、2012年に「いわて三陸ジオパーク」を設置して、沿岸部でのジオツアーを始めている。
宮城県では、震災直後から、県内の地質学や地理学の研究者が中心となって、「南三陸海岸ジオパーク準備委員会」を組織し、宮城県北部の南三陸町から南部の山元町までジオパークの設置を構想している。2012年には松島町において東北地理学会主催のジオパークのシンポジウムを開催し、松島町の町民にも関心を持たれた。その後、宮城県や被災した7市7町の自治体の首長や震災復興担当課へジオパーク構想の説明を行っているが、各自治体では生活再建が優先事項であり、ジオパークへの関心は薄い。
宮城県には、気仙沼から牡鹿半島までの、古生代~中生代の地質が典型的なリアス海岸をつくる地域と、石巻平野や仙台平野のように、新生代第四紀の新しい地層が直線的な海岸をなす地域、多島海からなる松島地域など、変化に富んだ自然が見られ、そこには学術的にも景観の上でも重要な、高い評価を受けている多くの自然遺産が存在している。また、震災後には過去の津波堆積物の地層が見つかり、将来の津波再来への大きな手がかりとなる可能性がある。また、海苔やカキなどの沿岸漁業やいちごを中心とする農業、野蒜築港跡地や貞山運河などの土木遺産、津波で残った小学校や倒壊したビルなどの被災遺構が存在する。
今回の震災では、宮城県では津波による子供の犠牲が岩手県に比べて多かったといわれる。これは、日頃の教育の在り方の違いと考えられている。仙台平野での津波の発生周期は約200年といわれているが、地震津波の発生のメカニズムと被害の可能性を、地域の住民が次世代に伝承していくためには、ジオパークの設置とジオサイトを学ぶジオツーリズムを地域主体で進めていくことが必要であり、南三陸海岸ジオパーク準備委員会としても、地域の再生と防災を目指して、今後も宮城県沿岸部のジオサイトの調査とジオツアーの実施を通じて、地元自治体に働きかけを続けていく予定である。
抄録全体を表示
-
北海道十勝管内の有機農家ネットワークの事例から
鷹取 泰子
セッションID: 415
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
■研究の背景・目的
農林水産省の農産物地産地消等実態調査によれば、2010年世界農林業センサスで把握された全国16,816の産地直売所の92.9%が常設施設利用型であり、朝市等の常設施設非利用型は7.1%に過ぎない。後者の場合、初期投資が少ない等の利点があるほか、近年では軽トラックを活用した市場(軽トラ市)などの直売形態が全国各地で認められる。また同調査では地場農産物販売にあたり「高付加価値品(有機・特別栽培品)の販売」への取組状況が相対的に低いと報告されている一方、大西(2012)のような、有機・特別栽培品を中心に取り扱う直売活動の事例は全国各地で観察・注目される。そこで本研究では常設施設非利用型の直売所、および高付加価値品を取り扱う直売所の活動について、その存在意義を明らかにしながら、直売所がローカル・フードシステムに果たす役割や展開について明らかにすることを目的とする。
■事例地域概観
本研究では北海道十勝(総合振興局)管内の屋外型の有機直売市場を事例として取り上げる。同管内は日本で有数の大規模農業経営が展開され、食料供給の重要な拠点として機能している。北海道の大規模畑作農業地域は、井形ほか(2004)が指摘するように加工原料などを主たる生産物とする産地形成の中で、直売や契約栽培などによる環境保全型農業の推進が難しい地域の一つでもある。
■帯広市の直売市場(マルシェ)の概要
今回事例としてとりあげる直売市場(マルシェ)は商業施設(パン販売店)の店舗入口付近に設置される屋外型市場である。5月から10月までの約半年間、毎日2時間限定の営業である。創業60年以上のパン販売店は新しく旗艦となる店舗の開店に合わせ、有機農産物等を販売する直売市場の設置を模索し、帯広市内の有機農家Y氏に相談を持ちかける形で始まった。2013年に4シーズン目を迎えた市場は、有機農業や自然農法で生産された農産物やその加工品を販売する14軒の農家・農場からなる産直会によって運営され、シーズン中毎日2-4軒の農家が当番制で生産物の販売をおこなっている。
■常設施設非利用型の有機直売市場の存在意義
十勝管内の直売所は2012年時点で45個所が確認されている中にあって、分散する有機農家が本市場に参集し、有機や特別栽培品を志向する消費者の来店を促し、両者の出会いや交流の場としての役割を果たしている。またとくに本事例の場合、パン販売店の強力なバックアップと協力体制が直売市場を支える大きな基盤である。限られた季節・短時間の営業、当番制の販売形態では各農家の販売金額に占める割合はさほど大きいものではない。しかし既存の商業施設との協力しながら常設施設を利用しないことによる経済的負担の軽減等の効果は大きく、農産物の量り売り販売等とあわせコスト削減が実現できている。結果として慣行品よりは割高な値段設定をした場合でも、他所で販売される高付加価値品(有機・特別栽培品)に比較した場合の低価格を実現できている。これらが一部の購買層に評価され、少量多品目で珍しい品目の販売も生かしつつ直売市場の魅力や強みを生んでいた。
■今後のローカル・フードシステムの展開の可能性
地産地消をめざし地元農家と協力しながら地場産農産物の積極的な活用を実現してきたパン販売店と有機農家のネットワークにより支えられる直売市場の存在は、国の農業政策の中に位置づけられる十勝管内にあって、経済的な意義は大きいものではない。しかしながら近年、直売所の競合や需要の飽和状態という課題が諸分野から指摘されている状況で、例えば直売所の差別化を探る方策の一つとして、あるいは2011年の東日本大震災の発生に際し、直売所によって支えられるローカル・フードシステムが非常時の食料供給に重要な役割を果たしてきたという報告(大浦ほか(2012))なども踏まえながら、ローカル・フードシステムの中に積極的に位置づけること等でさらなる展開の可能性が見込まれるだろう。
■文献
井形雅代・新沼勝利 2004. 北海道大規模畑作地帯における環境保全型農業の展開--津別町の有機,減農薬・減化学肥料タマネギ生産を事例として.農村研究 99: 82-90.大浦裕二・中嶋晋作・佐藤和憲・唐崎卓也・山本淳子 2012. 災害時における農産物直売所の機能―東日本大震災被災地のH市直売所を事例として―. 農業経営研究 50(2): 72-77.大西暢夫 2012. この地で生きる(6)にぎわいを創り出す支え合いの朝市: オアシス21オーガニックファーマーズ朝市村(名古屋市・栄).ガバナンス 137: 1-4.
抄録全体を表示
-
三原 昌巳
セッションID: 113
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
東日本大震災発生日から約3年が経過し,緊急を要する問題解決としての,いわば火事場の臨機応変な対応が求められる時期を脱し,主要な関心は地域の地場産業や生活基盤の復旧・維持などへと移っている。しかし一方で,福島県は原発の影響により,他の地域に比べて,その速度が緩やかであることは否めない。したがって,地域の再生・復活という観点から,その復旧プロセスを注視する必要があるが,震災後,他の被災地域に比べて福島県を対象とした研究は,さほど多くないと思われる。そこで本報告では,地場産業として観光産業に着目し,震災後における観光地の復旧プロセスを明らかにしながら,観光地として淘汰されにくい,持続的な地域基盤づくりを考える。対象事例は,福島県二本松市岳温泉地区とした。福島県は,温泉地の数が130を超え,都道府県別にみても上位に入る主要県である。そのため,福島県において,温泉地とそれに関わる観光産業は,重要な地場産業といえる。対象事例の概略は以下のとおりである。岳温泉地区は,福島市と郡山市に南北を挟まれる二本松市の西部に位置する。観光資源としては,安達太良山山麓の豊かな自然と良質の温泉を有しており,県内有数の観光地の一つに数えられる。1980年代の「ニコニコ共和国」のイベントでは全国的な誘客効果がみられたが,90年代に入ってから観光産業の慢性的な営業不振に陥っている。近年は,自然環境を活かしたウォーキングコースの整備や保養リゾート地をテーマにした集客活動などが進められてきた。2011年3月の震災では,一部損壊の建物被害が多くみられたほか,一次避難として地区内体育館,二次避難として宿泊施設を,主に浪江町からの原発避難者へ提供した。浪江町は,二本松市の隣接自治体にあたる。調査方法は,主に聞取り調査と資料収集による。復旧という視点からは,現況と震災以前の状況との比較が重要であると考え,震災以前の様子について,2010年夏に,現地調査した際に収集したものを使用する。 主な調査結果は,次のようにまとめられる。第一に,観光産業における人材不足が指摘できる。震災を受けて,少なからぬ従業員が退職しているため,大規模宿泊施設では,ハローワークをとおして求人を行っている。しかし,従業員確保の厳しい状況は通年にわたり続いている。建物の修繕を終えて,収容人数の点では震災前の数に回復したが,従業員の人手不足により,宿泊客の受入れが出来ないままの宿泊施設もみられる。 二つ目に,浜通りからの避難者の受入れによって,地域に様々な変化が起きている。震災直後からの数ヶ月間に岳温泉地区に避難していた浪江町の住民は,その多くが二本松市内各地の仮設住宅へと移った。そのなかには仮設住宅入居後も現在に至るまで,岳温泉地区の日帰り入浴を利用し続ける者もおり,その理由としては,最初の長期避難場所であったため,岳温泉が住民同士のコミュニケーションの場となっている,仮設住宅が手狭なために広い浴場での入浴を求めている,などが考えられる。一方,岳温泉地区で避難場所を提供した宿泊施設では,現在もなお,観光客の受入れが激減している。 三つ目に,地域に根付いた活動については,参加者の落ち込みがさほどみられない。例えば,ウォーキングなど,保養リゾートづくりの一環として推進されたイベントがある。イベントの参加者は,当初,首都圏も含めた広域からの誘客を意図していたが,実際には福島県の県北地域を中心とする地元からの参加者が多い。さらに,震災による避難者がこれに参加し始めており,活動の定着化が進んだ。
抄録全体を表示
-
諫早市中心市街地を事例に
箸本 健二
セッションID: 819
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
2000年代前後より、地方都市の中心市街地における大型店撤退が増加し、その跡地利用の停滞が「まちづくり」の阻害要因となっている。一方、少子高齢化社会が進行する中で小売販売額の縮小は不可避といえる。また郊外の大型商業施設も地方都市の消費需要を支える核であり続けよう。この状況下において、中心市街地の商業空間を高度経済成長期の規模で維持していくことは困難であり、規模縮小を前提としたまちづくりが求められる。本報告は、諫早市中心市街地における「諫早サティ」跡地の再開発を事例に、当事者間の合意形成、消費者ニーズの反映、行政の協力体制などを検討し、地方都市におけるダウンサイジング型再開発の方策について考察する。<BR>諫早市は、長崎県のほぼ中央部に位置し、江戸時代から交通の要衝として発展した。2005年3月には1市5町による合併を経て、14万人(2010年国勢調査)を超える人口規模を擁している。他方、売場面積1,000㎡以上の大型店は市内全域で32店舗(2013年4月)に達し、大部分が郊外立地であるため、中心市街地の空洞化は著しい。中心市街地には協同組合連合会に組織化された3商店街のほか、ダイエー、サティ(旧ニチイ)の大型店が立地していたが、前者が1998年、後者は2005年にいずれも閉鎖された。 諫早サティの閉鎖による中心市街地への悪影響を懸念した連合会と市は、当初、商店街が建物を借り受ける形での利活用を模索した。しかし、建物の老朽化(1972年竣工)と広い売場面積(4階建て、4,448㎡)から再利用の採算性は低いと判断し、連合会を事業主体とするダウンサイジング型の建て替えに方針転換した。市は、国の中心市街地活性化戦略的補助金(1/2補助)の獲得に動き、同時並行で地権者の対応にあたった。これらが奏功して、サティ撤退の1年3カ月後、売場面積を1,949㎡に縮小し、地 元の消費者の要望を踏まえた食品スーパー、雑貨品店をテナントに含む「アエル諫早」として再開した。。<BR>アエル諫早開発の第1の特徴は、事業継続の根本となる事業採算性を重視し、あえて売場面積の縮小をともなう「建て替え」に踏み切った点である。短期的には負担増となる意思決定であるが、建物の解体費用は市が負担し、再建費用(総額5,6億円)のうち2億を国の戦略的補助金、1億を市、残る2.56億円を商店街が自己負担する按分を行った結果、20年間での償却を可能にした。第2の特徴は、消費者の要請に基づくテナントミックスを実施した点である。核店舗である食品スーパーやファンシー雑貨店は、消費者調査に沿ったテナントミックスである。第3の特徴は、地権者調整の早期進行である。諫早サティの撤退は2004年9月に発表されたが、同月30日には地権者交渉を始め、このことが奏功して2005年2月のサティ撤退時にはダウンサイジングを前提とする再開発への合意をほぼ取り付けている。そして第4の特徴は、アエル諫早を中心市街地全体の集客装置と位置づけたことである。具体的には駐車場を90分無料とし、商店街への買い回り時間を確保した。当初は回転率の低下も懸念されたが、1日平均で8回転~9回転を確保している。。<BR>2006年5月に開業したアエル諫早は、2013年現在順調に経営を継続し、他の中心市街地商業施設への来街者も増えている。こうした中、1998年に閉鎖されたダイエー諫早店の撤退跡地の再開発事業が立ち上がるなど、アエル諫早の波及効果は大きい。本報告ではアエル諫早の成功要因について、①官民の役割分担、②地権者交渉、③ダウンサイジング、④意思決定スピードの重要性などの視点から考察を行う。
抄録全体を表示
-
―奈良県天理市を事例に―
石坂 愛
セッションID: 825
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ.序論
2000年代に入ると,主体間関係の重要性が見直され,より詳細な都市計画遂行過程を追う研究が見られるようになった.しかし,自治体や民間組織の他に都市機能に影響する絶対的要素をもつ主体が都市形成に関与する事例があり,宗教都市はそのひとつである.日本の宗教都市研究は,①近世以前成立都市のものに偏向しがちであり,ゆえに資料が限定され詳細な形成過程やそれに伴う課題が把握しづらい②台頭してきた建築学の分野の特性上,景観形成に着目したものが多いことから,主体間関係への着目が欠如しているという課題が残された.本研究では宗教都市構想を実現する上での課題を明らかにし,その改善策を提示することを目的とする.その方法として奈良県天理市の宗教都市構想の基盤となる「八町四方構想」について,天理教教会本部の計画遂行過程を明らかにし,天理市や地域住民の見解と関わり方をみる.
Ⅱ.研究内容
天理教教会本部の所在する奈良県丹波市町を中心とした周辺六ヶ村が合併し,1954年に天理市が発足した.市制発足に際し①天理教が名称の由来となった事実の風化を防ぐ②「理想的な宗教都市」の実現といった目的のもと,天理教二代真柱によって提唱された都市構想が「八町四方構想」である.これは,教会本部の神殿周辺に病院や学習施設の入った一辺約870メートルの「おやさとやかた」とよばれる城郭建築を巡らせる計画である.1955年の八町四方構想の発表から2013年までにおやさとやかたの約38%が完成しているが,2005年以降の竣工および完成棟はなく,計画の進行は緩やかになっている.その理由として,①教会本部の財政問題②八町四方内部の土地を確保する上での問題が挙げられる.現在の八町四方内における約17%の土地は国や地方自治体,もしくは個人の所有であり,土地売買に際し,協力・競合のもと都市構想は進められている.今回の発表では,教会本部のみで遂行されている状態になっている都市構想の現状を明らかにするほか,地域住民の見解として,天理市における交通整備の発達以降門前町としての機能を持つようになったものの,八町四方内に位置するために立ち退きを強いられる三島アーケード街の店舗と教会本部との競合事例を提示する.これらを踏まえ,天理市における八町四方構想遂行における課題として,①天理教の宗教的世界観を実現のため,神殿内部にぢばを固定し,四方正面の構造を重視する等間隔・遠心的な聖地拡大に基づく都市構想が計画され,交通整備による土地利用変化に対応しづらい②「八町四方内部は聖域であり,俗物は排除されるべき」という元来の見解に対し,「陽気ぐらしの概念に反している」という疑問が挙がるなど,地域住民の本部に対する不信感の鬱積などが挙げられる.また,天理市の発達過程,宗教に関する国内の動向についてまとめると,政教分離の概念が「信教の自由」から「宗教団体による政治的圧力を防止すること」に比重を置かれるようになった1960~1970年代は,天理市が宗教文化都市をうたい,市と教団が一体となって「宗教都市」を創りあげていこうとした矢先であることから,③政教分離の風潮による地方自治体からの援助制限も考えられる.
Ⅲ.結論
宗教の「聖」と都市の「俗」が強調した宗教都市づくりは,市制施行時から低迷しつつある.改善策として,天理市一体となった教祖の言説「神のやしろ(聖域)」についての再検討や都市構想の重要性の再認識が必要である.また政教分離の意義を問い直し,都市構想の周知拡大など,憲法に触れない教会本部への協力が可能であると考えられる.
抄録全体を表示
-
大上 隆史
セッションID: 632
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
三陸海岸北部の河川群の概略と研究目的三陸海岸北部には中期更新世以降の継続的な隆起を示す海成段丘群が認められ,これらを下刻して発達する河川群の中には顕著な遷急点を有する河川が存在する.遷急点を有する河川は,隆起に伴って新しい河床縦断形に移行する途上のステージにあることが予想される.一方で,こうした遷急点はすべての河川に発達しているわけではない.遷急点が認められない河川では遷急点が既に消失したステージにある可能性も考えられる.本発表では三陸海岸北部の河川群の発達段階を具体的に検討するため,実際の河床縦断形と定常状態を仮定した河川縦断形を比較した.
ストリームパワー侵食モデルにもとづく平衡河川の河床勾配 河川流量と河床勾配の積として求められるストリームパワーは河川水が流下する際の仕事率であり,一般に河床の侵食速度はストリームパワーの冪関数として表現できると考えられている.河川流量の代替指標として各地点の上流の流域面積
Aを用いると,侵食速度
E は
E=KAnSm,と表現できる(
Aは河床勾配,
Kは係数).このモデルを用いると,隆起速度
Uで隆起している地域の岩盤河川について,平衡状態に達しているときには
S=(U/K)1/nA-(m/n)という関係式を導くことができる(たとえばWhipple et al, 2000).すなわち,平衡状態にあるならば
log(S)=-θ×log(A)+log(ks) となり
,log(S)は
log(A)の一次関数として表現できることを意味する(ただし,
θ=m/n,
ks=(U/K)1/n).
河床縦断形とS−Aプロットの作成方法 河床縦断形の作成にあたって,国土地理院が公開している数値標高モデル(10 mメッシュ)を使用した.計算にはUTM54座標系において20 m間隔で再サンプリング処理した数値標高モデルを用いた.流域解析を行い,流路となる各セルのXYZ座標と各地点の上流側の流域面積を算出した. また,流路長500 m毎に最近傍のセルを抽出し,各区間の平均勾配を計算した.上記のデータを用いて河床縦断形とS−Aプロット(横軸に ,縦軸に をとったもの)を作成した.
結果:遷急点を有する河川のS−Aプロット 有家川のS−Aプロットを見ると,上流から下流にかけてA~Cの3区間(A:概ね直線で回帰できる区間(緩勾配),B:漸移的な区間,C:急勾配の区間)に区分できる(図).区間Bと区間Cの境界が顕著な遷急点となっている.松沢川のS−Aプロットは区間Aと区間Cから構成され,区間Bが欠如,または認定が困難となっている.
結果:遷急点を認定できない河川のS−Aプロット 玉川のS−Aプロットをみると全体に上に凸状の曲線的な分布を示しており,遷急点が見られる河川のような区分は難しい.
三陸海岸北部と河床縦断形の解釈,考察
遷急点を有する河川の区間Aについて,S−Aプロットが概ね直線に回帰できることは平衡河川に近い状態にあることを示唆している.ただし,河床縦断形全体を見ると,区間Aは現在の隆起速度に適合したものではなく遷急点が形成される前の条件下で発達したものが残存・維持されていると見なすのが適当であり,遷急点および区間Cの上流側への移動に伴って河床縦断形が更新されていくことが予想される.区間Bの存在は,河床縦断形の更新は遷急点の移動のみによるわけではなく,遷急点付近の曲率が減少するような河床の侵食が同時に進行していることを示す.
河床高度が上昇中の河川ではS−Aプロットは上に凸になると考えられており(たとえばChen et al., 2006),遷急点がみられない玉川の河床縦断形もこの特徴を有している.
これらの河川の河床縦断形は三陸海岸北部の地殻変動,特に隆起速度の変化に伴って形成されてきたものである可能性が高い.また,河川毎の縦断形の特徴の違いは基盤岩の地質・物性によると考えられる.さらに流域間でのS−Aプロットの比較を進める予定である.
(引用文献:Whipple et al., 2000,
Geol Soc Am Bull,
112, 490―503.Chen et al.,
Chi. Sci. Bull,
51, 2789―2794. )
抄録全体を表示
-
土`谷 敏治, 井上 学, 今井 理雄, 山田 淳一
セッションID: S0801
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
運輸部門の規制緩和から10年以上が経過し,地域社会におけるモビリティ確保に向けた取り組みは,その枠組みを変容させようとしている.かつて,日本における地域公共交通を維持するスキームは,国による許認可のもと,新規参入を制限し,既存事業者を過度な競争から守る体制とする一方,サービス提供からの退出(休廃止)のハードルを高くしており,公共交通ネットワークの大幅な縮小が進行しないよう,配慮されていた.規制緩和により,地域公共交通の分野においても,基本的に競争原理に基づく参入および退出が可能となり,その枠組みは大きく変容した.しかし,実質的に競争が進行した分野は,都市間高速バスや大都市周辺部の大規模住宅地などに限られた.鉄道や乗合バスの事業の大部分は,少子高齢化による通勤通学者の減少,マイカー依存による利用減少などの影響を受けており,既存サービスの撤退が相次ぐ結果となった.
その結果,公共交通を取り巻くステークホルダー,すなわち,市民・行政・事業者の相互関係は,近年,大きく変わろうとしている.従来,独立採算の営利事業としてサービスを提供していた事業者,利用者(消費者)としての市民,また公共交通サービスの一応のバックアップを担っていた行政と,相互に依存する関係にあったといえる.規制緩和後,サービスからの退出の自由度が増した事業者と,地域の公共交通ネットワークを維持する責任を従前以上に担う行政,そして,利用者あるいは消費者としての立場のみならず,市民として自ら“まちづくり”を意識し,将来の公共交通サービスの確保に考える市民と,いわば,三者による協働が求められるようになってきている.
公共交通の分野は,上記三者のステークホルダーのみならず,土木・工学,経済学などの研究分野,さらに建設業者やコンサルタントなど,さらに複雑な利害関係によって形成されている.そのなかで地理学,とくに近年の交通地理学の研究は,実体的かつ現在進行的な交通現象の分析を進めており,より社会に向けて,活用され得るメッセージを発信することが求められている.
超高齢社会,フードデザートの解消,環境問題,さらに中心市街地の空洞化など,様々な要因から,公共交通のネットワークを維持する必要性が高いことは,論を俟たない.しかし,その対策は,どの分野からも抜本的な解決策は提示されておらず,未だ模索の続く状態である.そのなかで,地理学が得意とする,地域の実情を的確に捉え,地域社会のモビリティ確保のための,適切な分析と示唆が求められる.本シンポジウムでは,広く社会的な関心との協調を図りつつ,地理学の研究アプローチに立脚しながら,この課題に対峙したい.
抄録全体を表示
-
磯野 巧
セッションID: 315
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本発表では,カナウィンカ地域におけるジオパーク運動がどのように展開してきたのかを,ジオパークや大地の遺産をめぐるオーストラリアの全国的動向や,カナウィンカ地域内のローカルアクターによる活動実態の分析を通して明らかにする。オーストラリアにおけるジオパーク運動は,その主たる観光資源となる大地の遺産Geoheritageの保全・評価制度の導入によりはじまった。1975年,連邦政府環境遺産省の中にあるオーストラリア遺産委員会(AHC)は,国家遺産リスト(RNE)制度の受け皿となった。RNEの中で,地質・地形学的な資源に関しては,オーストラリア地学協会(GSA)の協力のもと,連邦政府が掲げるクライテリアに即して評価し,資源に対する重要性Significanceが明記された(International,National,State,Regionalレベル)。2008年までに691の資源が大地の遺産として認定されている。
1989年,カナウィンカ地域東部に位置するコランガマイト・サザングランピアンズ両自治区において,スコリア丘やマールなどを当該自治区の「観光のアイコン」に位置づけ,火山景観を活用した観光振興を図るために,Volcano Discovery Trail Committee(VDTC)が組織された。主たる組織構成員は両自治区の住民であり,彼らはボランティアで活動に取り組んでいた。当該自治区ではナショナルトラスト運動も隆盛しており,たとえばコランガマイト自治区のデリラナム町では,町内に存在する大地の遺産を住民自らが管理・観光活用している。 1998年,カナウィンカ地域全域に分布する火山景観をひとつのまとまりとして捉え,当該地域における火山活動の軌跡にストーリー性を付加し,それを観光資源とする動きがはじまった。火山景観を活かした広域観光はVDTCが発足したカナウィンカ地域東部から進展したが,広域観光の推進に際し,カナウィンカ地域へお交通および観光の結節点にゲートウェイを設置した。 こうした状況下,当時の連邦政府環境遺産省のUNESCO担当者がカナウィンカ地域における取り組みに興味を示し,2004年にVDTCを主軸としたジオパーク構想の推進が決定した。世界ジオパークネットワーク(GGN)への申請に先立ち,2007年にVDTCや国内研究機関を中心として国内版ジオパークネットワーク(AGN)を立ち上げ,カナウィンカ地域を含む10地域が名を連ねた。2008年にGGNに加盟し,以降は姉妹ジオパーク(中国,ドイツ)との国際交流および連携事業,国際会議参加にも積極的となった。しかし,2013年の再審査時,連邦政府環境遺産省・環境保護委員会の判断によりカナウィンカ地域はGGNから外れ,国内版ジオパークとして再編された。
カナウィンカ地域におけるジオパーク運動の展開について,本研究で得られた知見を整理すると,次の通りとなる。カナウィンカ地域での取り組みは,オーストラリアにおけるジオパーク運動を牽引したパイオニア的存在であった。カナウィンカ地域におけるジオパーク運動は当該地域東部より展開し,その活動領域を徐々に西部へと拡大した。現在は国内版ジオパークとして活動しているが,GGNから外れたことを契機として,対ローカルなか活動を重視する傾向へと回帰したと言える。
抄録全体を表示
-
国際化するドイツ地理学からの検討
加賀美 雅弘
セッションID: S0304
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
日本の地理学の国際化を考えるために,ドイツの地理学に目を向け,そこで国際化に向けた活動がいかに進められているかを,近年実施されているいくつかの試みを踏まえて紹介する。ドイツ地理学は,特に1990年代以降,ドイツ語圏,ヨーロッパもしくはEU域内,グローバルスケールという3つの空間レベルで学術交流や学生交流などの国際化を進めており,日本地理学にとって参考になる。
抄録全体を表示
-
竹田 智道
セッションID: 826
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本研究では,大雄山最乗寺(神奈川県南足柄市)への参詣団体の属性を分類し,その分布と参詣行動を雑誌「大雄」より分析し,信仰圏モデルによる地域区分を行った.また,従来の信仰圏研究において取り上げられることの少なかった参詣団体を併せて取り上げ,信仰圏を構成する団体の拡張を試みた.分布の指標は「宗教行為―現世利益志向型」「宗教行為―安心志向型」「非宗教行為型」の3点を用いた.
「宗教行為―現世利益志向型」は地理学における従来の山岳宗教研究において主に扱われてきたグループであり,参詣中心の講,信仰中心の講,参詣中心の企業が該当する.祈祷または御供式を伴う参詣行動をとることが特徴である.最乗寺を祈祷寺院として利用しており,宗教的マスである民衆にあたる.参詣中心の企業は大雄山に比較的近接し,参詣中心および信仰中心の講は東京都と神奈川県に分布する傾向がある.「宗教行為―安心志向型」は地理学における従来の山岳宗教研究においてはあまり扱われてこなかったグループであり,修行中心の企業,修行中心の学校が該当する.座禅や研修を伴う参詣行動をとることが特徴である.修行中心の企業は東京都と神奈川県の中核都市に多く分布し,修行中心の学校は神奈川県内に散在している.従来は安心志向が宗教的エリートの信仰をそれぞれ集めてきたが,このグループには僧侶もしくは僧侶を目指す学生のみでなく宗教的マスも含まれ,近年は修行体験の形でマスレベルへの展開をみせている.「非宗教行為型」は宗教行為を行わないため信仰圏構造に含まれない.
これらを用いて信仰圏を区分した結果,大雄山からの距離によって信仰圏を3区分でき,大雄山の東部から北東部へ広がるセクター性を顕著に有することが明らかになった.また,大雄山信仰圏は単一の同心円からなるものではなく,第1次信仰圏と第2次信仰圏が中心を異にする円として複合的に存在する構造を示した.これは,祈祷が行われる場が大雄山最乗寺のみではなく,祈祷者が大雄山最乗寺の僧侶と主に東京都在住の先達の2者によって構成されているという宗教的事由に起因するものと考えられる.
第1次信仰圏は大雄山を中心として40km圏内であり,参詣・信仰中心の集団のうち,企業のように道了尊信仰を軸としない共同体が多く分布する.主に神奈川県南足柄市や小田原市が該当する.僧侶の活動拠点がこの地域にあたり,信仰の中核をなしている.第2次信仰圏は大雄山を中心として40~100km圏であり,参詣・信仰中心の集団のうち,講のように参詣目的で組織された共同体が密に分布する.主に神奈川県横浜市や東京都特別区をセクターとし,この地域を境として分布が疎になっている.講が参詣とレクリエーションを同時に行う点は,従来の研究における第2次信仰圏と同様である.祈祷寺院としての最乗寺の布教はここが中心であり,先達の布教拠点を核とする同心円を構築している.第3次信仰圏は大雄山を中心として100km以遠であり,参詣中心の集団が飛び地的に分布する.特に信仰中心の集団は参詣中心のものよりも距離の影響を強く受けている.最外縁は300~350km圏である.学校については同心円状の距離ではなく,都道府県の境界によって明確に区分されるが,これは神奈川県内の地域学習という教育的理由によると考えられる.よって,大雄山信仰圏においては同心円構造がおおむね成立するが,先達の拠点や都道府県界のような社会的要因によって形が歪められて存在しているといえる.
抄録全体を表示
-
―埼玉県鶴ヶ島市周辺を事例に―
水谷 千亜紀, 東 博紀
セッションID: P049
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
土地利用は,都市計画はもとより温室効果ガスや面源由来の汚濁負荷の算定などに用いられ,環境負荷の削減にむけた将来シナリオを考える上で重要な要素である.本研究では,土地利用変化予測モデルのひとつである遷移確率モデルのDinamica EGOを用いて過去の土地利用変化の再現精度を調べた.結果として,市街地の増加という傾向は再現できたものの,市街地を過剰に発生させてしまった.今後は開発抑制地域など規制に関する要素をモデルに組込むことが課題である.
抄録全体を表示
-
田中 圭
セッションID: P035
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに 従来,対象地域のベースマップとして空中写真を用いる場合は,国土地理院や航測会社が撮影した写真を購入するか,カイトまたはバルーンにカメラを取り付けて撮影する方法等が挙げられる.前者は,広い範囲を一度に撮影することができるが,山間地域等では10年間隔での撮影スケジュールとなっているため,時間的制約が大きい.一方,後者は必要な時に撮影することができるため撮影頻度は高いが,撮影時は風が安定していることが条件なため,気象状況の影響を非常に受けやすい.
一方,近年ではGPS,ジャイロ・加速度センサといったMEMSデバイスが飛躍的に発達し,小型化および低価格化したことで,UAVに搭載する機体が多く登場した.機体はこれらのセンサを用いてリアルタイムに飛行姿勢を修正することで,多少風が強い状態においても,常に安定した状態を保ちながら飛行することができる.その結果,非熟練者でも高解像の空中写真(斜め・垂直写真)を容易に取得することが可能となった.また,UAVには,あらかじめ飛行コースを設定することにより,自律飛行できる機体も存在する.自律飛行は操縦者の負担を軽減し,対象地域を効率的に撮影できる.さらに,定期的に飛行することで,時系列的な変化も追うことができる.
本発表では,UAV(複数のプロペラで飛行するマルチコプター)を用いて取得した地理空間情報の事例について紹介し,その可能性について検討する.
2.事例 1)写真計測(オルソ画像・DSM)
機体にカメラ(GoPro)を取り付け,対地高度30m程度の高さから2秒間隔で垂直方向に撮影した.これらの画像をSfM ソフト(PhotoScan)を用いて,作成したオルソ画像・DSMを図1に示す.乾田,畑,家屋が混在する土地利用でも高精度な写真計測が可能である.
2)植生指標
ここでは,高価な近赤外線カメラは用いず,小型かつ軽量なカメラ(GoPro)を2台用意した.1台は通常に撮影を行うが,もう一方のカメラには,レンズの前に赤外フィルターを装着し,撮影することで,フォルスカラーおよび植生指標を取得できる.
3)気温観測
機体に温度データロガーを装着し,逆転層の観測を行った.対地高度110m程度まで上昇させる間,1秒間隔で気温を記録し,逆転層が形成されていることを確認した.また,約2m程度の高さで周囲を飛行と同時に観測を行うことで,鉛直方向・水平方向の気温分布データを取得できた.
このように,様々な地理空間情報を取得することができるUAVは,地域調査のツールとして今後活用されることが大いに期待できる.しかし,空を飛行する以上,墜落事故を想定した運用が必要である.そのためには,電波法・航空法の順守や賠償責任保険の加入等,安全への配慮はしなければならない.
抄録全体を表示
-
香川 仁
セッションID: 320
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
-
山田 育穂, 岡部 篤行
セッションID: P050
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Moranの
I統計量(Moran 1948)は、地区データの空間自己相関の検定手法として最も広く用いられているものの一つである。対象地域内の地区数が十分に大きく、解析対象とする変数が特定の仮定を満たす場合、
I統計量の確率分布は漸近的に正規分布に従うとされ、それに基づいて検定が行われる。しかしながら、検定において特に重要となる分布の裾野では、
I統計量の正規分布からの乖離が指摘されており(Tiefelsdorf and Boots 1995)、また検定の際に
I統計量の正規性確保に必要な条件が精査されていることはごく稀である。山田・岡部(2013)は、Cliff and Ord(1971)の研究をシミュレーションによって拡張し、地区数を2,500まで増加させても、解析対象変数が
I統計量の正規性に必要な条件を満たす場合であっても、実際には
I統計量が正規分布に従わないことが少なくないことを示した。本研究は、シミュレーションを更に拡大して、
I統計量の裾野分布の特徴について検証を進めた。その結果、1セット10万回のMonte Carloシミュレーションを1000回繰り返した平均値でも、シミュレーションにより得られる棄却限界値はその理論値から無視できない乖離があること、一方でシミュレーションにより得られる
I統計量の推定分布は、地区数と繰り返し数が大きい場合には非常に安定していることが分かった。以上のことから、
I統計量を用いた検定では順列空間ランダムのシミュレーションによる方法が
I分布に正規性を仮定する方法より優れているという知見が再確認された。さらに、
I統計量の推定分布の安定性から、予め大規模なシミュレーションにより解析対象変数の分布形と地区数に応じて算出した棄却限界値を、実データの検定に利用できる可能性が示され、過去の研究事例の再検証などにも活用が期待できる。
抄録全体を表示
-
ペイン シャーロット
セッションID: S0703
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
東南アジアではスズメバチ類が食用されているが,巣箱を用いて飼育している国は日本のみである。 この発表では、歴史の通観と近年の状況から、クロスズベバチ飼育の現状を明らかにすることを目的とする。データには2013年に岐阜県で実施したアンケート調査の結果と文献・二次資料を用いる。 クロスズメバチ用の巣箱が記録されたのは19196年に遡る。春のはじめに野生の巣を採集して巣箱に入れた後、収穫する秋まで人間が6ヶ月間管理するこうした手のかけ方に地域文化の中にクロスズメバチの重要性を見出すことができる。1994年に,クロスズメバチ飼育に熱心な人が女王バチを越冬させる方法を確立し、それが普及したことにより、人間がクロスズメバチと関わりをもつ時間がより長くなり,11ヶ月間ほど飼育するようになった。この方法は、少なくとも3つ全国テレビ番組、3つの国際テレビ番組で放映されさらに5つの愛好会に広がり、飼育した巣を持ち寄る「地蜂サミット」が行わるようになった。このことがさらに周辺のクロスズメバチ飼育を行ってきた地域に大きな影響を与え、クロスズメバチ飼育愛好団体が中部地方の各地に作られた。現在、22の愛好会が存続し、クロスズメバチ飼育は活発になされている。 しかし、2013年のデータを見ると,飼育する人々の平均年齢は64.7歳で,若い世代には飼育の経験が非常に少ない。この年齢層の人々がクロスズメバチ飼育に無関心になったことにより、後継者が減少し、その将来が危惧される傾向にある。 これまでもクロスズメバチ飼育の伝統にはいくつもの変化がみられたが、現在は重要な一転機となっている。これは、人々が自然と離れていく大きな文化的な傾向の兆候のの一つで、社会全体について影響を及ぼすことかもしれない。
抄録全体を表示
-
~錫林浩特市の「風干肉」販売を事例として~
関根 良平, 庄子 元, 佐々木 達, 蘇徳 斯琴, 小金澤 孝昭
セッションID: P058
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本報告は、上述した対象地域のうち、牧畜を主たる生業としてきた錫林郭勒盟における、農民専業合作社形式で成立した牛の干肉販売を中心とする地域的な取り組みである。農民専業合作社は、これも前述した伊利や蒙牛などの酪農巨大企業、すなわち「龍頭企業」とともに地域経済の牽引役として2007年から制度化された新たな協同組合である。前者は、農牧民を垂直的に統合しつつ地域経済をリードし、後者は農牧民の共同により生産から流通までを合理化し、農牧民の利益拡大をはかる役割を担うものである(李・大島2010)。本報告で取り上げる、ボルガンソムバインデルゲルガチャの牧民25世帯によって運営されている合作社は、2009年に30万元の補助を政府より獲得し設立された。この地域の秋冬にかけての名産品であり、空港などでの土産物としても需要の多い牛の干し肉を自ら生産し、それを地域の中心都市である錫林浩特市に設けた店舗で販売するのがこの合作社の設立目的である。合作社の経営陣はじめ店舗の従業員も当該ガチャの出身者からなり、この合作社が食品の加工・販売免許および商標を申請登録しており、毎年の利益の90%は出資した世帯に均等配分するとともに10%は合作社の資本に組み入れるというのが基本的な事業スキームとなっている。
抄録全体を表示
-
北島 晴美
セッションID: 801
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに<BR>
高齢化が進行し高齢者の死亡比率は経年的に上昇している。2010年の65歳以上死亡は全死亡数の85%,75歳以上死亡は69%となり,高齢者の死亡状況が全死亡の状況を左右するといっても過言ではない。死亡率の季節変化は,1950年代以降夏季のピークが消失し,冬季に高く夏季に低い傾向が見られる。4大死因のうち悪性新生物以外は,冬季に死亡数が増加し,低温が死亡に影響している。<BR>
一方,1990年代以降,顕著な高温年が出現しているが, 2010年夏季は特に高温となった(8月の日本の月平均気温偏差1.97℃,正偏差第1位,気象庁)。地球温暖化が進行すれば今後も夏季の異常高温が頻出する可能性があり,人間の健康への影響が懸念される。<BR>
本研究では,夏季の気温と死亡率について,最近の変動傾向を調べ,気候が死亡にどの程度関連するのか明らかにすることを目的とする。<BR>
発表者らは,2010年夏季と2009年夏季の60歳以上死亡率の差から都道府県別の特徴を検討した(北島・太田,2011)。60歳以上一括死亡率は人口構成の影響を受けるため,今回は,高齢者の年齢階級別夏季死亡率について,気温との相関関係を分析した。<BR>
<BR>
2.研究方法<BR>
使用した死亡数データは,平成21年(2009),22年(2010),人口動態統計(確定数)(厚生労働省)である。北島・太田(2011)と同様に,各月死亡率は,1日当り,人口10万人対として算出した。死亡数が多く死亡率が安定する75~84歳,85~94歳年齢階級を対象とした。人口は2010年国勢調査人口(日本人人口)(総務省統計局)を使用した。<BR>
都道府県庁所在地の気象観測地点における月平均気温を,各都道府県の気温として使用した(気象庁ホームページからダウンロード)。<BR>
<BR>
3.都道府県別2009年・2010年8月気温<BR>
都道府県毎の8月気温平年値と2009年8月・2010年8月の月平均気温との散布図を図1に示す。2009年8月の日本の月平均気温偏差は-0.77℃であり,平年より低温な月であった。高知県,福岡県以外の九州,沖縄県のみが平年値よりも高温であった。一方,2010年8月は,全都道府県で平年値よりも高温となった。<BR>
<BR>
4.都道府県別気温と高齢者死亡率<BR>
図2に2009年8月と2010年8月の都道府県別気温と85~94歳死亡率との散布図を示す。85~94歳死亡率と気温との相関係数は,2009年8月 r=-0.170 p=0.253,2010年8月r=-0.505 p=0.000,同様に75~84歳死亡率と気温との相関係数は,2009年8月 r=0.001 p=0.996,2010年8月r=-0.327 p=0.025である。低温傾向であった2009年8月の死亡率と気温には相関関係がないが,高温となった2010年8月の85~94歳死亡率,75~84歳死亡率は,いずれも気温と有意な(有意水準0.1%,5%)負相関がある。<BR>
相対的に低温な地域で,2010年8月気温の平年差が大きい傾向があり(図1),高齢者死亡率も顕著に上昇した(図2)。<BR>
<BR>
抄録全体を表示
-
上村 早江子, 梶原 英彦, 野中 健一
セッションID: S0704
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに−都市養蜂の取り組み
近年の日本では、都市内におけるミツバチ養蜂(都市養蜂)が広がっている。企業や商店街などが主体となって飼育管理を行うことが多く、全国各地に広がりつつある。都市の街路樹や園芸植物には蜜源植物が多く、養蜂に都合が良い。いっぽう、住民にとっては、ハチ刺害の不安も生じる。また、ミツバチの飼育は法令により適正な飼育管理が求められる。ハチミツなどの生産物はその土地のものとして付加価値がつき、さまざまな商品原料として用いることにより、新しい地産商品展開が可能となる。
本研究は、都市養蜂が環境や地域住民との関係などさまざまな制約を受けると考えられるなかで、事業がどのように成立しているのか、また、それをどのように有利に活用しているのかを、高校での実践事例をもとに明らかにすることを目的とする。 対象は、名古屋市内の高校屋上での都市養蜂と採取されたハチミツの商品化を事例とした。授業・クラブ活動として養蜂を行い、商品開発へと展開し、地域住民やそれを超えたさまざまなつながりができているのが特徴的である。調査では、きっかけと実現するための地域での了解過程、飼育管理、生産物利用、商品開発と販売を調べた。
2.高校授業における養蜂
導入とプロジェクト展開 愛知県立愛知商業高等学校では、2011年度より屋上での養蜂が始められた。これは、3年次総合学習として展開される課題研究のひとつ「マーケティング研究」講座で「文化のみちのまちづくりへの貢献」を題して、まちづくりを学ぶテーマが設定された。これを選択した受講生が名古屋学院大学経済学部地域活性化研究室(水野晶夫教授)に協力を求め、講義を受ける中で、同教授が前年度より始めていた大学内の屋上養蜂に関心をもった生徒の発案により取り組むことになった
。 担当教員(梶原)による職員会議での説明と承認後、生徒が周辺地域への説明に回り了解を得た。そして同年6月より校舎屋上で飼育を開始し、採蜜を行うようになった。
2012年度からは、この活動は新たに創設されたマーケティングクラブに引き継がれ、現在に至っている。
3.養蜂とハチミツの活用
授業は、同校の立地する名古屋市東区徳川周辺の理解とその歴史文化を生かしたマーケティングと養蜂を通じた生態系向上やハチミツを使った商品開発などで地域活性化を目的とした。同校近くには徳川園庭園がありそれを蜜源として得られるハチミツは地域資源となり得ると期待され「徳川はちみつ」と名付けられた。そして、ハチミツそのものの販売ではなく、それを材料とした商品化によりさらなる地元産品の開発がめざされた。
初年度には東区内で、レストランでの利用や洋菓子店での製品化が実現した。2年目には、アイスクリーム商品開発を手がけ、陸前高田の米崎りんごを用いた「希望のはちみつりんご」アイスクリームとして販売されるようになった。3年目には、名古屋の伝統的和菓子ういろうへの使用が実現した。レストランでの利用、アイスクリーム、ういろうは、イベント商品ではなく、定番商品となっている。使用業者からは地元素材を用いたことによる新規顧客獲得やコミュニケーション向上につながったことなど評価されている。
4.地域・社会への発信
理解を得ることのできた地域には、保育園児や小学生を対象としたミツバチ観察会・採蜜体験、公開イベントへの参加などを行っている。そして養蜂から理解できる生態系や環境保全の説明も行っている。また、陸前高田産りんごを用いたことにより東北大震災復興への協力も行い、販売売り上げの一部寄付、現地給食での活用、交流等が行われている。
5.まとめ
実践的な活動により、生徒の主体性を増す教育効果が得られたが、ミツバチの管理、周辺の蜜源から得られたハチミツの味の季節差など生き物の特質により地域の自然環境への関心が高まり、また養蜂を受け入れてもらうための説明や商品化により、地域住民・社会・さらに広い人々とのコミュニケーションが広がった。商品開発・製造・販売においては、メンバーが全員女子であり、そのセンスが発揮された。養蜂とハチミツが軸となって、地域から周辺へさらに遠くとの場所的つながり、世代や属性を超えた人的つながりができた。
抄録全体を表示
-
第2回農産物購買行動アンケート
関根 良平, 佐々木 達, 小田 隆史, 増田 聡
セッションID: 111
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
報告者らは2013年1~2月に本報告と同じ福島県いわき市の市民を対象に食料品の購買行動と意識に関して調査を実施し、2013年日本地理学会秋季福島大会において佐々木(2013)として報告している。そこでは①野菜の購入先は食品スーパーが主流である。震災前後で購入先に大きな変化は見られない。②野菜を購入する際に重視されているのは産地、鮮度、価格の3要素である。風評と関連する放射性物質の検査はこれに続く結果となっており、原発事故以降に新たな判断材料として加わった。③購入産地は県外産にシフトしている。ただし、産地表示や検査結果を気にする反面、判断に用いる情報ソースは二次情報、三次情報である可能性も否定できない。④購買行動において国の基準値や検査結果に対して認知されているが,信頼度という点においては低い。野菜の購買基準は,「放射性物質の検査」と答える人も多いが,風評とは関連性のない「価格」を挙げる人が多い。しかし、「価格」要因は消費者サイドに起因するのではなく現在の小売主導の流通構システムから発生している可能性がある。といった諸点を指摘した。本報告は、こうした風評被害の特性と構造の変化、もしくはその「変容しにくさ」が働くメカニズムを解明したい。これは、事故より3年を経てもなお、汚染水や除染廃棄物問題が復興の足かせとなっている福島県では、調査研究においても一過性ではない継続的な視点が不可欠と考えるからである。
抄録全体を表示
-
河本 大地
セッションID: 414
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ はじめに 本報告は、日本における有機農産物産地の地理的分布とその規定要因を明らかにすることを目的とする。各種統計から有機農業が盛んにおこなわれている地域を見いだし、その類型化を立地と主要作物によって行い、その結果に有機認証の取得および有機農産物流通の状況を関連づけて分析・考察する。 使用した統計は、2000年の世界農林業センサスで調査された「環境保全型農業取組み農家」項目(無農薬・減農薬・無化学肥料・減化学肥料・堆肥使用)、農林水産省が公表している2005年および2013年の有機JAS認定事業者一覧である。2000年時の市区町村単位で各地域の特徴を分析した。 なお、本研究は日本地理学会2007年春季学術大会で発表した内容に、その後の変化等を加えて更新したものである。 Ⅱ 日本における有機農業の展開経緯 日本では、1970年代初頭から、フードシステムのグローバル化・産業化や農業における生産主義を背景に、それらのひずみである、食物の安全性低下や環境問題の深刻化、農村地域の疲弊などに問題意識を抱いた一部の農業者・消費者・学者等が、社会運動としての有機農業と関連活動をおこなってきた。特に、日本有機農業研究会を中心に、生産者と消費者との間の信頼関係を重視する「産消提携」を軸とした有機農業運動が展開され、それを「原型」として徐々に有機農産物の専門流通事業体、生協等を経由する流通体系が発展してきた。また、農村地域の構造的問題を背景に、農協や地方自治体が地域振興策の一環として有機農業を推進する事例も、同じ時期から増えてきた。 一方、農林水産省は、1992年に減農薬・減化学肥料などの技術を中心とする環境保全型農業の推進を開始した。また、「有機」食品表示の氾濫や国際的な表示・規制の動きの影響を受けて、有機農産物等の基準・認証制度の導入を急ぎ、2001年には有機JAS検査認証制度を発足させた。結果として、有機農業を実施する農家に対する政策は表示規制に偏向し、他方で経営重視の事業体による有機農業の導入や「有機ビジネス」が成長している。2001年以降は、有機食品の輸入増加も顕著である。 その後、2006年に制定された「有機農業の推進に関する法律」に基づく農林水産省の推進計画により、自治体が有機農業推進の責務を有するようになったり、国の事業仕分けの影響を受けたりと、有機農業をめぐる状況は大きく変化している。 Ⅲ 日本における有機農産物産地の分布と類型 有機農業をめぐる状況は、時間的に大きく変化してきたが、空間的な違いも大きいと考えられる。 本研究の結果、環境保全型農業一般の実施が盛んな地域と、有機農業の盛んな地域とでは、地理的分布が大きく異なっていることが明らかになった。また、有機農産物産地の地理的分布は、有機JAS認証の取得が多いか(認証型)少ないか(非認証型)で様式が異なることも判明した。これらの地域は、立地および主要な有機栽培作目の2点により、都市の野菜産地、平地の野菜・果実産地、平地の米産地、中山間の野菜・果実産地、中山間の米産地、茶産地、島嶼・沿海の果実等産地の7つに類型化された。 さらに、各産地の主要な有機農産物出荷先を調査し、有機農産物流通の空間的パターンの概況を明らかにした。 以上の詳細は当日報告する。 Ⅳ まとめ 以下の点が、主な特徴として見いだされた。 *有機農業は、所与の地域的条件に適合する形で展開してきた。多くの有機農産物産地において、農業産出額1位作目と主な有機農産物が同一である。 *有機農業の展開を強く規定してきたのは、①産消提携を中心とした有機農業運動、②地域振興策としての推進、③有機JAS検査認証制度のビジネス活用の3つである。 *流通については、東日本の産地からは東京圏へ、西日本の産地からは県都や近隣都市への傾向が顕著である。 *有機JAS認証制度等によって市場主義的色彩が濃くなり分布が変化している。第一に、新たな産地形成が、特に南九州(かごしま有機生産組合による普及)と、東京圏への出荷を志向する東・北日本の平地農業地域で顕著である。これは、個別経営の大規模化・企業化を伴っている。第二に、西日本の中山間地域を中心に、上記の①②が産地形成に大きく寄与してきたが、そこでは認証型産地は2005から2013年にかけて激減している。これには、高齢化した家族農業経営と生産者グループが有機認証から、あるいは農業経営そのものからリタイアしていることや、バイヤー側が安定的な取引を求めていることなどが、大きく関係していると考えられる。
抄録全体を表示
-
鈴木 比奈子, 内山 庄一郎, 井上 公
セッションID: P039
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに 防災科学技術研究所 自然災害情報室では1964年より自然災害に関する資料の収集・整理・保管・発信を行っている.所蔵資料の中には,50年前に撮影された新潟地震の災害空中写真およびロールフィルムが複数含まれており,液状化被害等,発災当時の上空からの様子を把握することが可能である.ただし,保存状態が良くないため,フィルムに歪みや膜面の剥がれなどの劣化が生じている.SfM(Structure from motion)などの画像処理をベースとした三次元形状復元技術や撮影位置推定技術を用いて,デスクトップPCでも写真から三次元モデルを生成することができるようになった(内山ほか,2014).本稿では,こうした古い空中写真のスキャニング画像にSfMを適用することで,当時の地形,被害状況の調査への活用可能性を探った. 2.空中写真の処理 使用した空中写真は,以下のとおりである. ・1964年7月21日カラー撮影 ・カメラ:RC5a,No.213 ・焦点距離152.12mm ・基準面:0m ・高度:1520m,750m ・縮尺:1:10000,1:5000 ・SfM使用枚数:3コース19枚 空中写真は20μメートル(1,270dpi)でデジタルスキャンを行い,四隅の点を用いて,角度補正を行い,一定サイズに切り出した.切り出した空中写真は,SfMソフトウェアにはAgisoft PhotoScan 1.0.0を用いた. 3.結果と今後の展開 この結果,地上解像度0.2mのオルソフォトを得ることができた(図1).液状化によって川岸町アパートが転倒した様子や,周囲の地盤に多数の噴砂痕が観察される. 今後は,この情報にGCPを付与し,新潟地震地盤災害図(西田ほか,1964)とオーバーレイし,詳細な調査を実施する.
抄録全体を表示
-
―石碑文字列の判読と震災遺構アーカイブの 試み―
鈴木 比奈子, 内山 庄一郎, 井上 公
セッションID: 118
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに SfM(Structure from motion)などの画像処理をベースとした三次元形状復元技術や撮影位置推定技術を用いて、デスクトップPCでも写真から三次元モデルを生成することができるようになった(内山ほか、2014)。地域の過去の自然災害を知るうえで、歴史災害資料の活用は欠かせない。しかし、屋外の災害記念碑や災害遺構は日々風化が進み、時に失われる。これらについてデジタルカメラで撮影しSfMで三次元モデルを作成することによって、効率的な歴史災害資料の解析やアーカイブへ活用できる可能性がある。本稿では、石碑や複雑な立体物の三次元モデル化とその活用可能性について検討する。 2.歴史災害資料のSfM処理とその結果 対象物に対し、視差を与えながら撮影を行い、SfM技術を用いて三次元モデリングを生成した。本稿では、汚れや風化によって判読が難しい状態にある古い石碑に刻まれた文字、および複雑な立体形状の石像について実施した。 2.1 碑文の再現 災害記念碑は地域が過去に経験した災害の実績を後世に伝える、重要な災害資料のひとつである。従来は写真撮影や拓本により災害記念碑に刻まれた情報をアーカイブしていたが、写真では表面情報を明瞭に読み取ることが難しく、拓本では接触型のアーカイブ方法であるため対象物を劣化させる恐れがある。 対象物は1927年に建立された千葉県野島埼厳島神社の境内にある関東大震災の災害記念碑である。図1の上部は対象とした石碑とその周辺の様子である。表面に刻まれた文字列は深さ5mm程度で、苔の繁茂や風化作用によって読み取りが難しくなりつつある。碑文を再現するために石碑表面から60cm程度離した状態でカメラを保持し、石碑表面に対して平行移動しながら158枚の写真を撮影した。 図1の下部左は撮影した写真から生成した石碑のオルソフォト、中央が石碑表面に対し陰影処理を行った状態、右は陰影処理後に判読した文字列である。三次元モデル化によって、表面の汚れの影響を大幅に軽減することが可能となった。また陰影処理によって、非常に明瞭に文字列が判読できる状態になった。 2.2 立体物の三次元モデリング 図2上部の石像は、前項の石碑が立つ厳島神社の拝殿前、右手にある吽(うん)型の狛犬である。設置時代は不詳であるが、江戸時代中期の作と推定される。狛犬のサイズは鎮座する足元から頭部までの高さが約70cmである。この石像にカメラを向け70cm程の距離を保ちながら、螺旋を描くように頭部から足元にかけて133枚の写真を撮影した。モデリングした結果を図2下部に示す。ほぼ実物に近い立体物に見え、穴のある立体物や複雑な表面形状であっても、非常にリアルに再現できることが示された。粘土で造形したような石像表面の複雑な凹凸も再現している。 この石像の例によって、穴の開いた複雑な立体物の三次元モデリングが可能であることが示された。これを自然災害により被災した構造物などへ適用し、震災遺構の三次元モデルをアーカイブできる可能性がある。 3.今後の展望 災害記念碑をはじめとした歴史災害資料や震災遺構は、日々風化が進み、情報が失われている。そういった貴重な災害情報の収集や、震災遺構のアーカイブなどにSfMを適用し、災害資料の収集に活用したい。
抄録全体を表示
-
宮城県仙台市における事例
山本 遼介, 泉 岳樹
セッションID: P041
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1 はじめに
東日本大震災の復興過程のアーカイブについては,NHKの「東日本大震災アーカイブス」の中での復興の軌跡や(独)防災科学技術研究所を事務局とする「東日本大震災・災害復興まるごとデジタルアーカイブス」(略称:311まるごとアーカイブス)をはじめとして,様々な取組がなされてきた.それらの中でも,Google社の日本法人が行っている「未来へのキオク プロジェクト」では,写真や動画の投稿プラットフォームとして既に6万1千件以上のデータがアーカイブされているだけでなく,ストリートビューという360度画像の閲覧サービスのデータを震災直後と震災後2年の2時点で取得し公開している(一部地域については震災前のデータ有).360度画像は,人の目線に近い視点から空間全体を記録しているので,臨場感があるだけでなく,町並みや景観の記録としての価値も高く,このデータを元に建物の3次元モデルを作成し町並みを復元する試みもなされている.
本研究では,このように利用価値の高い360度画像を取得できるMMSを用いて独自にデータ取得を行い,復興過程のアーカイブを試みる.その際,写真測量技術により複数の360度画像から画像内の地物の位置や高さなどを計測する機能の有効性についての検討を行う.
2 研究手法
MMSによるデータ取得は,(株)トプコン製のIP-S2 Liteを用いた.このシステムでは,車両のキャリア上に6つのカメラ,GPS,IMUを備えたメインユニットを搭載し,車内に接続されたPCで動画撮影の制御とデータの保存を行う.このMMSはレーザースキャナを搭載していないが,撮影データの後処理により,動画内の地物の位置や高さを測定することができる.
対象地域は,被災地で最も早く防災集団移転事業が進んでいる宮城県岩沼市とした.
現地調査は,2012年8月4日~7日と2013年11月18日~19日に行い,津波の被害を受けた岩沼市沿岸部(仙台東部道路の東側)をMMSにより撮影した.
3 結果
2012年と2013年のデータを比較すると,以下の変化を見ることができた.(1)防災集団移転地において造成工事が本格化し,用水路の整備や地面のかさ上げ等が開始された.(2)「震災遺構」にもなり得た相の釜地区の水防倉庫が解体された.(3)「千年希望の丘」の造成工事が開始された.(4)海岸部にあった瓦礫等が撤去され,防潮堤の工事が本格化した.また,画像内の計測機能については,特徴点が抽出できるところでは概ね1m以内の精度で測定できることが分かった.
今後は,現地調査を継続的に行うとともに,変化の大きい場所について,位置や高さの測定など定量的な解析を行う予定である.
抄録全体を表示
-
堀 和明, 清水 啓亮, 谷口 知慎, 野木 一輝
セッションID: P007
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
石狩川下流域には蛇行流路の自然短絡によって形成された三日月湖(河跡湖)が多数みられる.これらの面積は把握されているものの,湖盆形態について十分な調査がなされているとはいえない.また,細粒な土砂による埋積や人工改変が進んだ場合,近い将来に消失する可能性があるため,現在の湖盆形態を把握しておく必要がある.三日月湖の規模や水深は小さいため,本研究では安価で容易な方法を用いた湖盆図作成を試みた.具体的には,ゴムボートにエレキモータを取り付けて湖沼内を走行し,GPS機能搭載の魚群探知機で水深測定をおこなった.また,底質を把握するための採泥調査もおこなった.
現地調査は美唄市および樺戸郡浦臼町に分布する伊藤沼,菱沼,月沼,トイ沼,ピラ沼において2010年8月~9月にかけて実施した.これらの湖沼の面積は0.018~0.145 km
2である(草ほか,2001).エレキモータとGPS付魚群探知機(Lowrance HDS-5)を取り付けたゴムボートで湖沼内を走行しながら測深をおこなった.水深の小さい場所では水生植物(とくにヒシ)が繁茂していたり,モータの先端部が湖底に触れたりするため,ボートで進入することが困難であり,そこでの測深はおこなえなかった.水面の標高は測量および湖沼に設置されている各種施設の高さから求めた.また,湖岸線の緯度経度は,Google Earthの画像(2012年6月撮影)をトレースして決定した.この湖岸線を水深0 mとみなした.測深データおよび湖岸線のデータについて解析ソフト(Surfer)を用いて補間をおこない,等深線を描いた.補間法にはKrigingを用いた. 湖底表面の堆積物はエクマン・バージ採泥器を用いて採取した.また,各湖沼において水深の大きな1地点において,佐竹式コアーサンプラーにより長さ30~40 cm程度の柱状試料を採取した.試料については過酸化水素水を用いて有機物を分解させた後,レーザー回折式粒度分布測定装置により粒度を測定した.柱状試料については1 cm間隔で分析をおこなった.
各三日月湖では,面積の非常に小さい月沼を除き,屈曲部の外側(流路だったときの攻撃斜面側)で水深が大きくなっていることから,ほとんどの三日月湖は流路だった時代の形態をまだ保持していると考えられる(図1).また,伊藤沼,菱沼,トイ沼においては,等深線の間隔が湖沼の下流側で広くなっている.水深については水面の高さが人為的に制御されているため自然状態ではないものの,最深部の水深は伊藤沼で3.3 m,菱沼で7.5 m,月沼で2.2 m,トイ沼で2.5 m,ピラ沼で4.0 mであった. 各湖沼の湖底はほぼすべて細粒シルト~粘土からなっている.ただし,伊藤沼では水深の小さい,滑走斜面側の一部の地点で砂がみられた.各湖沼の柱状試料も最下部(湖底下30~40 cm程度)まで泥であった.したがって,近年は細粒物質の堆積が進んでいると推定される.時間を置いてから再び測深や底質調査をおこない,今回の調査と比較検討することで,湖盆形態や底質の変化を把握できるだろう.
抄録全体を表示
-
中村 純
セッションID: S0701
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ミツバチは,数千から最大6万匹ほどの社会集団を形成するが,社会性昆虫を扱う分野では,この社会単位を「コロニー」という.コロニーは1匹の女王蜂と,繁殖期には全体の10%ほどの雄蜂,そして残りはすべて働き蜂で構成される.コロニーの営みは,さながら多数の細胞で構成される動物一個体の営みに似ており,このため「超個体」とも呼ばれる.ちなみに,マルハナバチやスズメバチとはちがい,年間を通じて単独になるフェーズを持たないので,現存のミツバチは,およそ500万年前からコロニーという単位を崩したことがないことになる.コロニーの大部分を占める働き蜂は,女王蜂と同じ雌で,いずれも受精卵から生まれる(ミツバチの性決定においては,受精卵が雌,未受精卵が雄となる).働き蜂の母親に当たる女王蜂は,2~3年の一生の始めに10~16匹程度の雄蜂と交尾して精子を得て,これを体内に蓄えて,その後,一生の間,働き蜂や自分の後継となる女王蜂になる受精卵を産むたびに少量ずつこの精子を使い続ける.女王蜂の寿命は,通常2~3年であるが,実際には精子を使い切れば寿命となる.冬期には,コロニーとしての活動レベルも下がるので,6か月程度まで働き蜂の寿命は延長するが,年間の大半では短く,これを女王蜂が一日に産む1000個ほどにもなる卵によって補っている.つまり,ミツバチのコロニーは新陳代謝の高い状態を維持して檻,働き蜂を次々と更新して,若返りを図っている.働き蜂が3万匹ほどのコロニーでは,一日に1000匹死んで1000匹生まれることでコロニーの状態は安定的に維持できる.女王蜂が,巣の外で多数の雄蜂と交尾をすることで,生まれてくる働き蜂は,異父姉妹の集合となる.その結果,働き蜂はコロニーの中での遺伝的多様性を確保し,これが,外界の刺激に対して,一律に動くのを回避して,刺激の種類や程度に応じた最適な調節を実現している.一般的には血縁選択,つまりは母娘や姉妹の協力関係が社会進化の推進力とされるが,完成されたミツバチの社会は,血縁よりは遺伝的多様度に基づく,コロニー活動のための多機能性を優先している.遺伝的多様度を働き蜂の横軸方向の広がりとすると,縦軸方向は,春や秋にはわずか30日ほどしかない個々の働き蜂が持つ時間となる.ミツバチは日齢に伴う生理変化による分業によって,女王蜂に一任する産卵以外の,育児,食糧の加工と貯蔵,採餌などのすべての活動を分担している.巣の外で,害敵などに遭遇する外勤活動(主として採餌)は,このため一生の最後の分担となっている.ミツバチのコロニーは,年間で120 kgの花蜜と20 kgの花粉を花に頼る.これを集めるために,ダンス言語を用いるなど,昆虫としては非常に高度に発達した採餌戦略を持つ.また,ハナバチ類では最も高い定花性を示し,連続的に同じ花を訪れ,これが植物の側から見れば受粉の効率を高める結果となる.大量の資源を植物に頼る代償として,ミツバチは植物の繁殖を助けていることになる.このような高度な社会が維持できるのは,一方では,個々の働き蜂の高い能力に大いに依存しており,また,私たちからは想像しにくいが,これといった命令系統を当てにしていない社会構造と,外界の資源環境との明確な融合によっている.本シンポジウムのテーマは「飼育」である.ミツバチは,確かに法的には家畜に分類されているが,コロニーとして高度に自立していて,同時に資源環境とは切り離せない生物であり,実は字義通りの「飼育」は困難を極める.人間の作業としての飼育は,実際には,人間が与えるストレスを,飼育に伴う保護で補っている状態を指す.その点で,生産養蜂など,ミツバチとの共存的な関係を維持するためには,私たちもミツバチが利用する環境を考えることから始めなければならないのかも知れない.
抄録全体を表示
-
奈良間 千之, 風晴 彩雅, 山本 美菜子, 浮田 甚郎, 池田 菜穂, 田殿 武雄
セッションID: P015
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1 はじめに
調査地域である中央アジアの天山山脈やインド北西部のラダーク山脈(インド・ヒマラヤ西部)には,小規模な氷河湖が多数分布する.これまでの我々の調査結果によると,天山山脈北部地域に分布する781の氷河湖のうち約80%が1980年代以降に出現した新しい氷河湖であった.天山山脈では,1963年に多くの犠牲者がでた氷河湖決壊洪水(GLOF)をはじめ,多数のGLOFが1950~1970年代に起きた.最近では1998~2012年に再び犠牲者をともなうGLOFが1998年7月にギッサール・アライ地域(5万m3,犠牲者多数),2002年8月にパミール(10万m3,犠牲者24人),天山山脈北部地域(45万m3,犠牲者3人)の3回生じている.一方,ブータン・ヒマラヤにおいては,2000~2010年に急速に拡大した氷河湖は全体のわずか1~3%であった.東ヒマラヤでは1994年以降犠牲者をともなうGLOFは生じておらず,氷河湖の脅威は以前よりも減少している.東ヒマラヤではGLOFの脅威が減少する一方,天山山脈では1980年代以降に出現・発達した次世代の氷河湖が2000年以降再びGLOFを起こしはじめているのである.もう一つの対象地域であるインド北西部のラダーク山脈(インド・ヒマラヤ西部)では,天山山脈と同様に小規模な氷河湖が多数分布する.2010年,2011年,2012年と立て続けにGLOFが生じ,その特徴は両地域で多くの類似点を持つ.このような状況を鑑み,本研究では,小規模氷河湖分布地域である二つの山岳地域を対象に,氷河湖の現状分析と氷河湖決壊洪水の被害状況とその推定をおこない,氷河災害軽減に向けての対策を提案することを目的とする.
2 方法
氷河災害の軽減に向けて,本発表では以下の2点について報告する.(1)発生誘因である小規模氷河湖の基礎的な知識の獲得,(2)過去の洪水履歴からの災害実績図.天山山脈とインド・ヒマラヤ西部のラダーク山脈では,世界的にも報告例の少ない短命氷河湖が複数確認されている.短命氷河湖とは,1年~数か月の短期間で出現・決壊する氷河湖を指す.天山山脈のテスケイ山脈では2008年7月にわずか2か月半で氷河湖が出現・決壊して,45万m3の水を流出し,3人の犠牲者をだした短命氷河湖のGLOFが生じた.2012年7月には,同地域のキルギス山脈で1年前に出現した氷河湖(6万m3)が決壊し,首都ビシュケクを含む上流の村々の住民は突然の洪水に混乱した.インド北西部のラダーク山脈では2011年に出現した氷河湖が2012年7月に決壊し2つの橋を流出した.この短命氷河湖の現状を把握するため,空中写真,Corona,Landsat TM/ETM+など複数の衛星データを用いてモニタリングをおこなった.
3 結果と考察(1)氷河の現状と小規模氷河湖の基礎的な知識の獲得
キルギス山脈において,ALOS AVNIR-2/PRISM画像を用いて氷河湖分布を調べたところ,229の氷河湖(0.001㎞2以上)の氷河湖を確認した.その中でも比較的大きな氷河湖は山脈西側の北斜面に集中している.衛星画像を用いた面積の変動を調べた結果,短命・繰り返し型と変動型(拡大・縮小)の二つのタイプが存在していた.短命・繰り返し型の氷河湖タイプが3割近くを占めていることがわかった.さらに,過去の氷河湖決壊洪水の記録をみると,短命氷河湖タイプの出水が多いことが明らかになった.詳細は学会において報告する.
抄録全体を表示
-
岡田 真介, 今泉 俊文, 寺地 将史, 楮原 京子, 越後 智雄, 戸田 茂, 松原 由和, 三輪 敦志, 池田 安隆, 宮内 崇裕
セッションID: P004
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
東北地方太平洋沖地震の発生に伴って,東北地方を中心とする地殻応力場は劇的に変化し,内陸地域でも地震が多発するようになった.地震調査研究推進本部は,午伏寺断層・阿寺断層帯・立川断層帯・三浦半島断層群と共に双葉断層の地震発生確率が高まったとして,早急な調査が必要であると評価している.本調査の対象地域は,双葉断層と長町-利府断層に挟まれた仙台平野南部であり,これまでの調査では,活断層は認定されていない地域である.
本研究では,まず仙台平野南部の空中写真および1 m DEM および 2 m DEMから作成される立体地形図において,阿武隈山地北部と仙台平野を限る地形境界から東に約2 kmに位置する旧河道の自然堤防を南北方向切る活断層が示唆された.そこで,仙台平野南部における地下構造を明らかにするために,2013年1~2月にかけて浅層反射法地震探査を実施した (図).探査測線は,宮城県亘理郡亘理町竹ノ花から逢隈神宮寺を経て,亘理大橋西詰付近に至る東西約5.3 kmである.発震点・受信点間隔は共に10 mとし,震源にはEnviro vibを用いた.さらに2013年6~7月には,反射法地震探査で得られた地下構造のイメージングを検証するために,反射法地震探査測線を含むように200 m間隔を標準として,LaCoste & Romberg社製D型重力計を用い相対重力測定を実施した.得られた重力値からブーゲ重力異常値を算出し,2次元タルワニ法を使って密度構造解析を行った.
これらの物理探査の結果から,仙台平野南部の地下には,伏在活断層が存在し,地下では先第三系の基盤を大きく変形させている.さらにその上位に堆積する中新統から更新統の地質も変位させていると解釈できる.阿武隈川と名取川の間の愛島丘陵の東麓の撓曲崖や広瀬川以北の仙台平野下に推定されている伏在断層(苦竹断層)との関係については,今後検討・精査が必要である.
本調査では,阿部春建設株式会社,亘理町役場,宮城県土木事務所の方々に多くのご協力を頂きました.また東北大学大学院理学研究科の修士1年,同大学理学部4年の諸君にも探査に協力いただいた.産総研の高橋美江さんには重力探査におけるGPS解析を行っていただいた.ここに記し感謝します.
抄録全体を表示
-
都市空間をめぐる実践と表象
小川 杏子
セッションID: 504
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
【はじめに】 オリンピック招致との関連し日本においても報道があったように、トルコでは現在「開発」をめぐって様々なデモが起きている。これは「開発」への抵抗の場であると同時に現政権(AKP:公正発展党)の政策への反対の場ともなっている。本発表で取り上げる「不法居住住宅(ゲジェコンドゥ)」もその1つの事例である。ゲジェコンドゥはトルコ語で「一夜建て」を意味する、いわゆる「不法居住住宅」である。トルコ共和国では、第二次世界大戦以降、都市化にともない大都市を中心に「ゲジェコンドゥ」が多くみられるようになった。本発表においては、首都アンカラを事例に、「ゲジェコンドゥ」がいかに構築されてきたのか、アンカラという都市空間の持つ意味を踏まえたうえで明らかにすることを目的とする。
【「ゲジェコンドゥ」をめぐる都市政策の変遷と表象】 トルコ共和国の首都アンカラは、1923年に建国されて以降西欧化/近代化した空間を目指して、都市計画が進められてきた。モニュメントや公園、住宅というものを通じて「モダン」な空間が形成されてきたのである。第二次世界大戦後になると、冷戦構造の「対共最前線」としての重要性を見いだされたトルコは、アメリカの莫大な資金援助のもと、世界経済への参入をしていく。その過程の中で特に大都市を中心に現れてきたのが「ゲジェコンドゥ」であった。 1970年代までは規制を受けつつも住宅政策欠如の代替物として容認の政策もとられてきたが、それは1980年代に入りネオ・リベラリズム的な都市政策を取る政府の政策により、「開発」の対象へと変化してきている。そしてそれはゲジェコンドゥの人々へのまなざしへも大きな影響を与えている。1950年代においては「近代的」な都市と地方の二項対立的図式によって、都市に現れた「田舎の“他者”」としてゲジェコンドゥの人々は描かれてきた。しかしながら、ネオ・リベラリズム的まなざしが入ってくることにより、次第にネガティヴなイメージ(「脅迫的な“他者”」など)がそこに付与されていくのである。 このように、「ゲジェコンドゥ」はその時代ごとのトルコの経済・社会・政治状況の文脈において創り上げられたものである。そして、この権力側の実践・表象が彼らの生活に様々な制約を与えているのである。
【「ゲジェコンドゥ」をめぐる現状】 現在アンカラにあるゲジェコンドゥは2015年には全てなくなるとも言われている。発表者がフィールドとする首都アンカラのDikmen Vadisi(Dikmen Valley)においても、1990年代以降公園、高層住宅等の建設を進める都市政策が進められている。そしてこのDikmen Vadisiでは2006年以降、組織化された住民運動が行われており、行政の「開発」に対して抵抗が行われている。住民運動については、今後機会を改めて報告する。また、今後は現在進行形で進む社会・政治状況を注視しながら、彼らの運動が制約を受けた「空間」を変える可能性について考察する。
抄録全体を表示