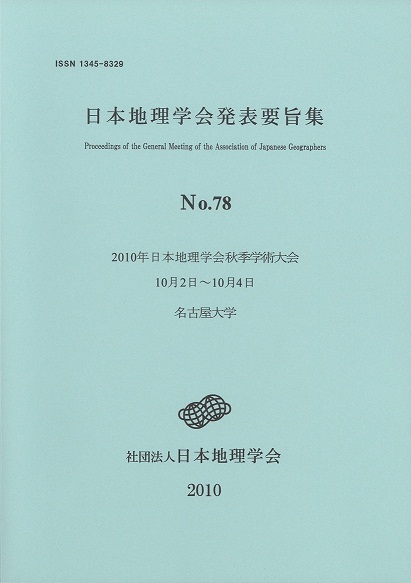-
自然条件との関連に着目して
太田 慧, 杉本 興運
セッションID: P063
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.研究背景と目的
本研究は,日本全国に立地する展望タワーの立地特性を自然条件との関連から明らかにしたものである.ヨーロッパにおける展望タワーの歴史は,19世紀のエッフェル塔の登場が大きな転換点となり,以後エッフェル塔を模した塔建築は世界各地で開催された博覧会のモニュメントとして建設され,その一部は現在でも観光施設として残っている(川村,2013).さらに,展望タワーは19世紀以降ヨーロッパの海岸リゾートにおいて多数建設され,ビーチ全体を見渡せるモニュメントとして観光客を非日常的な眺望で楽しませた(Urry,2002).また,19世紀のドイツでは,愛国心を鼓舞するために大自然の景色を見渡せる山頂に多数の展望タワーが建設された(川村,2013).このように,ヨーロッパにおける展望タワーは,博覧会会場,海岸リゾート,および自然を見渡せる山頂に立地していた.現在においては,展望タワーをはじめとした塔状建築は世界中の都市の内外において建設され,多数の展望タワーが世界各地に立地するようになった.日本においても,19世紀以降東京や大阪などの大都市において博覧会のモニュメントとして展望タワーが建設され,第2次世界大戦以降は日本全国に様々な展望タワーが建設され「タワー大国」となった(鈴木,2011).
以上のような展望タワー研究においては,展望タワーの歴史を明らかにすることでその成立背景について明らかにされているが,観光施設として展望タワーの立地特性を検証したものではなかった.そこで本研究では,日本における展望タワーがどのような自然条件下に立地し,それらがどのような立地パターンを示すのかを明らかにすることをことで,今後の展望タワー研究の基礎的史料とする.本研究は定量的データとGISを用いて,展望タワーの立地特性の包括的な把握と類型化を行う.
2.研究方法
本研究では,展望タワーに関する資料を基に,全国の展望タワーの分布図を作成した.さらに,ヨーロッパにおける展望タワーの立地傾向を考慮し,展望タワーが立地する環境として都市の内外,水域との近接性,および展望タワー周辺の地形を分析項目とした.なお,各分析項目については,国土数値情報より提供されている海岸線,河川,湖沼,都市地域,および標高データを用いた.
3.考察
以上の研究の結果,日本における展望タワーに関して以下の傾向が認められた.展望タワーの立地環境については,分析対象とした展望タワーの257棟のうち,160棟が都市域に立地していることが明らかになった.これは,展望タワーの62%が市街化区域やその他の都市域に立地していることを意味し,大都市中心部への展望タワーの立地傾向が示された.
また,水域との近接性については,海岸線,河川,および湖沼の3種類の水域ごとに異なる傾向がみられた.海岸線については,展望タワー257棟のうち,74棟が海岸線から500m以内に立地していた.一方,河川および湖沼との近接性については,海岸線のような偏在はみられずに分散して立地していた.
最後に,展望タワーが立地する地形の分析を試みた.展望タワーが立地する地盤の標高では,展望タワー257棟のうち92棟が標高10m以下に立地していた一方で,63棟は標高200m以上に立地しており,展望タワーが平地に多く立地する一方で,一部は山地や丘陵にも立地する傾向があることが明らかになった.さらに,展望タワー周辺の地形を把握するために,展望タワー立地する地盤の標高と展望タワー周辺平均標高との差(比高)を求めた.その結果,比高が10m以下の平地に立地している展望タワーが166棟認められた.一方,比高が30m以上の展望タワーは65棟にのぼり,山頂あるいは断崖にも展望タワー立地する傾向が明らかになった.
抄録全体を表示
-
沖津 進
セッションID: 514
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
南米ボリビアのアルティプラーノにおいて,潜在的森林限界に着目しつつ,土地の感想条件に対応した生態地理景観の違いと成因を検討した.首都ラパス附近の潜在的森林限界はおよそ4000メートルで,生態地理景観はこの上下で異なっていた.森林限界以下では生態地理景観は土地の乾湿によって異なっていた.湿潤地では農耕地が卓越し,牧草地は少なく,未利用地はわずかであった.放牧対象の家畜はウシが主で,ヒツジがそれに続き,リャマはまれであった.湿潤地の資源(水分,牧草の量と質)は豊富であった.乾燥地では牧草地が卓越し,未利用地が続き,耕作地は少なかった.家畜はヒツジが主で牛が続いたが,リャマもしばしばあらわれた.資源は湿潤地に比べるとが減少した.潜在的森林限界以上ではそれ以下と比べて生態地理景観が全く異なっていた.土地の乾湿の違いは明瞭ではなくなった.農耕地は分布せず,牧草地と未利用地がほぼ同じ割合で見られた.家畜はリャマが主体でわずかにヒツジが現れ,ウシは分布していなかった.資源は極めて少なかった.このように,アルティプラーノでは,潜在的森林限界が生態地理景観の違いをもたらしていた.それ以下では,土地の乾湿に応じて,豊富な資源量に対応した土地利用形態が見られた.それ以上では薄く少ない資源を広く利用する形で,リャマの放牧に特化した土地利用が見られた.
抄録全体を表示
-
井田 仁康
セッションID: S0309
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.国際地理オリンピックでの日本の成績
第10回となる国際地理オリンピックが、2013年に京都で開催された。日本チームは、800人近くの予選参加者を勝ち抜いた4人の選手が参加した。結果は、銀メダル1つ、銅メダル1つと2つのメダルを獲得した。2つのメダルを獲得したのは、2008年の第7回からの国際大会の参加から、初めてのことである。32の地域・国が参加したが、チームとしての団体成績も、今までは下位だったものから中位へと上昇した。国際地理オリンピックの試験は、マルチメディア試験、記述式試験、フィールドワーク試験の3つからなる。試験はいずれも英語での出題、解答である。日本の生徒の特徴は、選択式のマルチメディア試験では比較的いい成績を残すが、フィールドワーク試験で高い得点がとれない。配点は、マルチメディア試験が20%、フィールドワークが40%であることから、フィールドワーク試験の点の低さは、総合点に大きな影響をおよぼす。しかし、京都大会では、日本の生徒はフィールドワーク試験も健闘をみせ、メダルの獲得にいたった。
2.国際地理オリンピックからみる日本の地理教育の課題
国際地理オリンピックの日本チームの成績から明らかなように、日本の地理教育の課題の一つは、地理の醍醐味ともいえ、国際的にも重要視されているフィールドワークが、中学の社会科地理学習、高校での地理歴史科地理学習においてもあまり実施されていないということである。学習指導要領には野外調査をすることが明記されてはいるが、実施率は低いと推測される。地理の面白さ、有用性、そして世界の中での地理教育を高めていくためには、フィールドワークの実施が一つの鍵となる。国際地理オリンピックの国内大会においても、2013年度から第3次試験まで設け、1次試験のマルチメディア、2次試験の記述を突破した上位約10名が3次試験のフィール-ドワークに挑戦することになっている。国際地理オリンピックの国内大会でも、地理ではフィールドワークが重要であることを示すことになる。 また、国内大会でも2割は英語での出題、解答としている。すなわち、英語でのコミュニケーションの重要性を示している。国際大会に参加した生徒たちは、英語での出題、解答に難儀を感じているようだが、日本の高校生の英語レベルで十分に対応できる。英語を使うこと、それ自体に自信を持たせてあげることが肝要であろう。
3.地理オリンピックからみた国際化への具体策
国際地理オリンピックでは単なる知識を問う問題は少ない。地理的な知識に基づいてどのように考えるか、すなわち地理思考力が問われる。したがって、地理教育で国際化を進めるには、フィールドワーク、地理的思考力を高める教育をし、英語や地図などをコミュニケーションツールとして、世界の人たちと対峙できる地理的能力を習得することであろう。
抄録全体を表示
-
清水 長正, 藤森 美佐枝, 石井 正樹, 山川 信之, 池田 明彦, 柿下 愛美
セッションID: 612
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
北八ヶ岳・麦草峠近傍の地獄谷火口底(標高2108 m)における、風穴の現象に因る氷塊の発達と、初夏前後に出現する一時的な火口湖の推移について、氷塊が越年する年としない年、火口湖が出現する年としない年があることを述べた(清水ほか,2012,地学雑誌)。その後も氷塊と火口湖の観測を継続中で、2009年以降のそれらの推移を報告する。2009年~2013年の間では、火口湖が長期に出現した年の秋季には氷塊が融解し、火口湖が短期か出現しない年は氷塊が融解せず越年するという周期性が認められる。このことは火口湖が長期に出現すると氷塊の融解が促進されることを示唆している。いっぽう、氷塊が越年した翌年には火口湖が出現するという周期性も認められる。氷塊の発達のほか、不透水層となる火口底の凍土が夏季まで存続し、雨水・融雪水を湛えて火口湖が長期に出現することが推定される。
抄録全体を表示
-
飯島 慈裕, 朴 昊澤, フョードロフ アレクサンダー
セッションID: P018
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1. はじめに
20世紀後半以降の温暖化に伴い、寒冷圏陸域の永久凍土地温も同調して長期的に上昇傾向にある。その傾向は気候帯によって地域性があり、北東ユーラシアでは、北極沿岸のツンドラ帯から、カラマツが広がる北方林、山岳域、さらに南部のステップまで、景観の多様性に応じて地下の凍土環境変化が異なる。最近の気候変化に応じた永久凍土変化は、“表層付近の凍土層の融解に伴う活動層の深化”、が重要なプロセスになる。すなわち、熱的環境の変化とともに、活動層内に貯留される土壌水分量の変化が、植生の蒸発散や炭素収支の変化をもたらして気候や水文の諸過程にフィードバックする。すなわち、永久凍土の融解や温暖化は単に気候変化の指標ではなく、寒冷圏陸域の相互作用のサイクルに不可分な現象となる。このような活動層深化に伴う熱・水環境変化過程の理解には、気候帯や景観ごとの観測とそれに基づく凍土過程の数値モデル化によって、現状の診断や将来予測が可能になる。
本研究では、東シベリアでの過去の長期観測データを精査し、景観や気候帯の違いによる凍土表層の地温変化の地域性を明らかにするとともに、凍土環境(活動層変化)の評価に向けた陸面モデル解析の適用によるに結果について報告する。
2. データならびに方法
本研究では、All-Russian Research Institute of Hydrometeoro- logical Information-World Data Centre (RHIMI-WDC) が提供している、東シベリア(北緯50度以北、東経80度以東)の49地点の1930~2010年の気温、1977~2008年の1.6mと3.2m深の地温観測データを用いた。 凍土過程を含む陸面モデル(CHANGE:Park et al. 2013)によって、北方林の陸面状態を入れた1901~2009年 のシミュレーション結果を用いた。モデル入力気象データはWater and Global Change (WATCH)のWATCH Forcing Data 20th Centuryを用いている。
3. 結果
北極域では、最近の温暖化の以前に20世紀中盤(1930~40年代)の温暖化が知られている。地域ごとの気温偏差を1935-40年と、205~09年の2時期で示すと、まず20世紀中盤の温暖期では、北極海沿岸のツンドラ地帯に共通して東部+0.6~西部+1.1℃の強い温暖偏差が現れていた。一方で、中部の北方林地域や南部山岳域のシグナルは弱い。これは、20世紀中盤の温暖期が北極高緯度地域でのみ卓越していたという傾向(Johannessen et al., 2004)と一致する。それに対して、最近では、北東ユーラシア全体が顕著な温暖偏差となった。全体が+0.7℃以上の偏差であり、レナ川中流域からツンドラ地帯にわたる広域で強い偏差を示している。
続いて、レナ川中流域の地温観測データと地温と土壌水分のモデル計算結果の時系列を比較した。地温から、20世紀中盤の温暖期の影響はなく、観測・モデルとも期間を通じて緩やかに上昇する傾向にあった。10年程度の周期的な温度上昇、下降がそれぞれ認められたが、1980年代以前はその位相は合っていない。しかしそれ以降の変化はほぼ同調しており、特に直近の2000年以降に最高値がともに現れていた。活動層内土壌水分量の計算結果によれば、最近5年は長期的に見ても極大期に相当しており、気候温暖化に加えて、降水量増加による土壌の熱的性質変化の影響によって地温が顕著に上昇した観測事実(Iijima et al. 2010)と一致する。
抄録全体を表示
-
ケイ トエ ライン, 成子 春山, マウン マウン アイ
セッションID: 619
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
イラワジ川下流デルタ、ニャンドン地点においてオールコアボーリングを行い、10cmごとに堆積物を採取し粒度分析、EC,PH他の分析を行ったところ、完新世に河川地形を形成をする時期があったことをしめすことができた。
抄録全体を表示
-
ケイ トエ ライン, 成子 春山, マウン マウン アエ
セッションID: P023
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ミヤンマー・ラインタヤー地区は近年、ヤンゴン市の拡大に伴い、土地利用変化が顕著である。土地利用変化に伴う地下水の変化を空間的にみると偏差があることがわかった。
抄録全体を表示
-
清水 昌人
セッションID: 802
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本研究では非大都市圏における人口の社会減少について、コーホート別、地域ブロック別の特徴を検討する。
抄録全体を表示
-
大丸 裕武, 村上 亘, 黒川 潮
セッションID: 616
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
山口県防府地域で2009年に発生した表層崩壊について,GISを用いて植生や過去のはげ山荒廃との関係を解析した.2009年の崩壊は過去のはげ山の縁辺に集中していた.この原因として,ハゲ山から流出した土砂が谷頭部などの凹地に厚く堆積し,2009年の崩壊物質となったことが推定された.現地調査においても,防府地域の谷頭部には厚い砂質堆積物が見られ,中に含まれる炭片の放射性炭素年代から12世紀~15世紀頃に堆積したことが推定された.この時代には,西日本の花崗岩山地でハゲ山荒廃が進行したことが知られており,この地域では過去の山地荒廃が現在の崩壊形態に大きな影響を与えていると考えられる.
抄録全体を表示
-
谷 謙二
セッションID: 702
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに
近年、Web地図サービスが質・量ともに向上し、さまざまな地図情報が公開されるようになった。これには、タイルマップという標準化された地図画像形式でWebサーバ上に地図画像ファイルを置くことで、Google Maps APIやOpenLayers等を用いてWeb上で簡単に閲覧システムを構築できるようになったことが公開地図情報の増加に寄与している。筆者は、2005年から旧版地形図を閲覧するためのWindows上で動作するソフト、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ」を開発し、公開しているが(谷 2009,2011)、2013年9月にWebサイト時系列地形図閲覧サイト「今昔マップ on the web」(http://ktgis.net/kjmapw/)を公開し、Webブラウザ上で閲覧できるようにした。ここでは、システムの機能と開発過程および利用状況について報告する。
2.システムと機能および開発過程
本サイトでは、ユーザーがWebサイトのファイルにアクセスするとJavaScriptが読み込まれ、Google Maps API v3を使用してWebサーバ上の地形図画像ファイルを読み込んでいく。実行されるプログラムはブラウザ上で動作し、サーバ側にはファイルが置かれているだけでシンプルな構成となっている。図1は閲覧画面であり、左側に収録された過去の地形図画像、右側にはGoogleマップが表示される2画面構成で、位置を特定しやすくするほか、変化もわかりやすい。また、標高に応じた色分けもオーバーレイしている。さらに、街歩き等でスマートフォン等の画面の小さい携帯情報端末でも使用できるよう、ブラウザのサイズに応じてレイアウトが変更されるようにし、現在地を中心に移動軌跡を表示できるようにした。 地形図画像ファイルはWindowsデスクトップ版のファイルを再利用し、フリーソフト「MapTiler」1.0 Beta2を使ってタイルマップ形式に分割した。ただしこれは画像ファイルを1つずつしか変換できないため、重複部分を1つの画像にまとめるツールなどはVB2010で自作した。8地域に関してズームレベル8~16のデータセットを作成し、120万の画像ファイルをサーバにアップロードした。画像ファイルはGoogle Maps APIを用いて表示され、そのための処理をJavaScriptで自作した。8月に作成を開始し、9月15日に公開した。その後も標高を表示する等の改良を行った。
3.利用状況
本サイトの情報はTwitter等のSNSを通じて拡散され、最初の半月では1日平均4,400件と大量のアクセスがあったが、それ以降は500~1500アクセス/日で落ち着いている。従来のインストール作業の必要なデスクトップ版に比べ、簡単に閲覧できるWeb版の方が多くのユーザーの獲得という点ではより有効である。過去の地形図は地域の歴史を知るだけでなく、防災や住宅購入の下調べ等様々な用途に役立つので、さらに普及をはかっていきたい。
文 献
谷 謙二 2009.時系列地形図閲覧ソフト『今昔マップ2』(首都圏編・中京圏編・京阪神圏編)の開発 .GIS-理論と応用:17(2),1-10.
谷 謙二 2011.時系列地形図閲覧ソフト『今昔マップ2』への東日本大震災被災地域データセットの追加について.埼玉大学教育学部地理学研究報告:31,36-42.
抄録全体を表示
-
八木 令子, 吉村 光敏, 小田島 高之
セッションID: 626
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1 はじめに
近年、すぐれた景観(景勝地)を地域の潜在的な価値として評価しようとする動き(例えばジオパークの構成要素、観光振興の目玉に位置づけるなど)がさかんである。しかし従来の景観の捉え方は主観的、情緒的で、何がどうすぐれているのか科学的根拠に乏しい。一方、景観を構成している地形、地質、植生、人間活動の痕跡など個々の要素の最新のデータを把握し、その学術的重要性について詳細に論じても、それが実際に目に見えていなければ景観の価値を伝えることにはならない。景勝地の自然の捉え方として、まず現在目の前に見えている現象を正確に把握し、それらを基に地域の成り立ちや全体の景観の意味を示すことが重要と考え、その事例として千葉県北東部の屏風ヶ浦海食崖で行っている調査を紹介する。
2 調査地域と使用したデータ、分類の方針
屏風ヶ浦は下総台地を削る海食崖で、銚子市名洗町から旭市刑部岬まで、雄大なスケールの崖が約10km連続する。ここには波食による海食崖の後退で上流や下流を切られた谷(風隙、懸谷)や、新しい崩壊跡などが分布しており、消波堤の設置で侵食量が減少しているとはいえ、地形は現在も変化し続けている。なお屏風ヶ浦は、平成24年度に認定された「銚子ジオパーク」のジオサイトのひとつに位置づけられている。
この海食崖に沿って、約500m間隔で近接撮影した航空斜め写真を使い、崖上の地表面、崖面、崖下について、写真上で見えるもの(地形、地質、植生、人工物など)を判読し、図化した。その方針としては、①統一した基準で空間的にくまなく分類する②いろいろな規模の地形が混在するが、できる限り細かく分類③地層(鍵層など)のつながりを重視④地形(面)と地形を作る地層をセットで考える などである。また垂直空中写真の実体視、崖下(消波堤の上)や崖上からの目視及び測量など、現地調査のデータも利用した。
3 屏風ヶ浦海食崖の景観を構成する要素
屏風ヶ浦西方に位置する磯見川河口から銚子市三崎町にかけて、崖がどのような地形、地質あるいは人工物などから構成されているかを、写真と説明図で示す(レジメ図1)。
4 景観の見せ方―展望地点の設定
景観は眺める場所(展望地点)があって初めて成り立つもので、どこで、何を、どう見せるかが重要である。また景観はふつう遠景として捉えられることが多いが、地域の成り立ちを示すためには、中~近景も把握することが必要である。図1の展望地点から見える景観を、遠景、中景、近景などに分けて以下のように説明する。
遠景(大地形)(図1の範囲外)
銚子半島(愛宕山と段丘面):銚子の成り立ち
中景(中~小地形)
海食崖と消波堤、懸谷状の谷:波食
台地地形面(下総上位面など)と台地を作る地層:地形面の形成
近景(微地形):変化する地形
香取層新期崩壊
新しい島
海食崖型の滝
自然の海岸線(ノッチなど)
崖錐 など
抄録全体を表示
-
森脇 広, 永迫 俊郎
セッションID: P012
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
南九州の鹿児島湾奥は,姶良カルデラによって構成されており,活発な火山活動が生じている地域である.この中にあり,桜島の1.2km北東方に位置する新島(燃島)は,桜島火山の安永噴火(西暦1779-1782年)の一連の火山活動によって,海底から隆起した特異な島である(小林,2009).この島(周囲1.5km)は,貝化石を豊富に含む堆積物が陸上で観察でき,最終氷期最盛期以降の鹿児島湾の古環境変化の知見がもっともよく得られることから,火山学的な関心だけでなく,古生物学的,環境変遷史的視点からも注目されてきた(鹿間,1955;平田,1964;奥野ほか,1998;亀山ほか,2005).最近では,地球化学的,微化石的分析による古環境解析もなされている(Kameyama, et al., 2008; Yamanaka et al., 2010), 報告者はこれまで南九州の後期更新世末以降における種々の古環境記録の統合化を進めるために,テフラ編年を基にして南九州の陸上,周辺海域の古環境・文化の変化をグローバルな環境変化と高精度で対比・編年すること試みてきた(Moriwaki et al., 2010).鹿児島湾の古環境変化をこのような高精度対比・編年に位置づけるためには,新島の堆積物の高精度編年を進める必要がある.これまで,新島の堆積物の編年は主に
14C年代測定によってなされ,それは最終氷期最盛期以降の形成であるとされている(奥野ほか,1998;亀山ほか,2005;Yamanaka et al., 2010など).この堆積物の中にはテフラが見いだされているが(奥野ほか,1998など),それらの同定は十分ではない.また,最終融氷期前半の年代の知見はまだ少ない.ここでは新島で得られている鹿児島湾の古環境変化に高精度・高確度の年代軸を入れ,この変化を南九州やグローバルな高精度環境変化史に組み込むことを目指して,新島の堆積物のテフラの同定を行い,
また新しく
14C 年代資料を追加し,その意義を検討する.
テフラ:これまで,海成堆積物中に介在する未同定のテフラにS-AP,S-BPと呼ばれる2枚の降下軽石がある(奥野ほか,2005).このテフラは,厚い水中火砕流堆積物-燃島シラス(鹿間,1955)とか新島軽石(Kano et al., 1996),州崎軽石(亀山ほか,2005)と呼ばれている-の上に載るシルト堆積物(燃島シルト,亀山ほか,2005)の中に介在する.下位のS-APは層厚20cmで,この上位2.4mにあるS-BPは層厚10cmである.今回は,これらの軽石の火山ガラスの化学組成を求めて,標式地のテフラとの対比を行った.分析には鹿児島大学自然科学教育研究支援センター機器分析施設の波長分散型電子プローブマイクロアナライザーを使用した. その結果,S-AP,S-BPの主成分のwt%はそれぞれSiO
2 73.08,74.61,Al
2O
3 14.65,13.80,TiO
2 0.47,0.43,FeO 2.46,2.20,MnO 0.09,0.09,MgO 0.55,0.45,CaO 2.48,2.03, Na
2O 3.36,3.42,K
2O 2.88,2.97が得られた.この値は桜島火山由来のテフラの値の範囲内にある.詳細に見ると,S-APとS-BPとはその組成に差異があり,S-APの組成は桜島-高峠3(Sz-Tk3,10,600 cal BP, Moriwaki, 2010)S-BPのそれは桜島-上場(Sz-Ub,9,000 cal BP, Moriwaki, 2010)に類似することから,S-APはSz-Tk3, S-BPはS-Ubに同定される.
14C年代:
14C年代試料は炭化木片で,燃島シラス(州崎軽石)の上位2.2mに堆積する厚さ90cmの軽石層中から採取された.その年代は12973~12732 cal BP (PLD-25401)である.その中央値12,900cal BPはこれまでこの試料の層準付近で得られている年代(約17,700 cal BP)やその上位の年代(Nakayama, 2010)とあまり整合しない.今後の検討課題である. 今回のテフラ同定は,新島で知られる鹿児島湾奥の古環境変化の編年をより高精度なものにし,さらにこれまで求められてきた周辺の沖積低地の変遷,南九州の文化編年との高精度対比を可能とする.
抄録全体を表示
-
横山 秀司
セッションID: 827
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
福岡県には江戸時代に成立した豊前の上野焼、筑前の高取焼・小石原焼などの焼き物産地があり、今日に継承されている。この時代の窯場立地は、陶石・陶土、燃料の存在などの自然的条件、藩の政策などによって決定されている。本研究は、上野焼、高取焼、小石原焼における窯場立地の変遷を自然的・歴史的に考察したものである。
抄録全体を表示
-
フンク カロリン
セッションID: 309
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
観光者が様々な観光形態を求めることになり、「新しい観光」と言われる現象を生み出している。その中でアート・ツーリズムが今後の経済活動に重要な役割を果たすとされている創造的階層の旅行形態として(竹田・陳2012:78)、または地域住民の積極的な関わりを可能とする地域活性化手段として(Klien 2010: 519)期待されている。 現在日本で最もアート・ツーリズムの取り組みとして注目を浴びているのは香川県直島町とその周辺で開かれる瀬戸内国際芸術祭である。そこで本研究は直島におけるアート・ツーリズムに注目し、観光者と観光産業関係者の特徴と彼らが抱く直島に対する考えを調べる。また、訪れている観光者は、普段どの程度アートに関心を持っているのか、一般観光者層と異なるのか、アート・ツーリズムは観光産業にどのような効果をもたらしたのか明らかにする。 2.研究対象と方法 直島町は1917年に三菱鉱業(現在の三菱マテリアル)の精錬所を誘致し、鉱業の島として繁栄してきたが、銅市場の変化も影響し、精錬場の労働者数とともに直島の人口も1970年代から減少しはじめた。1970年から教育文化施設を島の中心部に集め、「文化ゾーン」を作り出した。1985年、当時の町長と当時の福武書店(現在ベネッセ・コーポレーション)社長の合意に基づいて、島の南部エリアを中心に総合的な観光開発が始まった。直島国際キャンプ場、ホテルと美術館を合体したベネッセハウス、本村地区で展開された家プロジェクト、地中美術館、犬島アートプロジェクトなど、アートを用いて25年をかけた文化・リゾートエリアが直島に誕生し、プロジェクトはその周辺の島にも広がった。その結果、島は現在、北部の産業エリア、中心部の生活・教育エリア、南部の文化・リゾートエリアに別れている。 現地調査は2012年11月24-25日に観光者、観光産業施設、住民という3つのグループを対象にアンケートを実施した。回答者数は観光者255人、観光産業施設40ヶ所、住民34人であったが、この報告では観光者と観光産業のみ取り上げる。 3.調査結果 アンケート調査で把握した限り、直島を訪れる観光者は旅行全体や普段の生活でもアートに強い関心を持つ人、アートとともに自然を楽しむ人、訪れた相手とゆっくり島を歩き回りたい人など様々であり、性別や年齢層による差もみられる。したがって他の観光地とは全く異なる客層を引きつけているというよりは、客層が拡大し、多様化しているといえよう。 観光産業については地中美術館の開館とそれに伴う観光者数の増加が影響し、2004年以降に島外からの若い人々が移住し、観光産業、特に宿泊施設に取り組む傾向が強まった。しかし、観光者向けのサービス、特に外国人旅行者に対する情報提供などはまだ限られている。外国人の増加に対してもそれほど積極的ではない観光産業従事者が多く、国際観光地としての成長はこれからの課題である。施設管理、サービス、値段がともに高水準であるベネッセの施設に比べると、その他の観光産業は小規模で、個人的で、施設の水準があまり高くなく、そのギャップは大きい。また、彼等はアートに強い関心を持つ、または積極的にアートプロジェクトに関わるようなことがあまりなく、「アート」に対する思いよりも、「島」へのこだわりや、自立して事業を行いたい志向が強いようにみえる。観光産業の成長はアート・ツーリズムの魅力の効果というよりも、アート・ツーリズムを通じて観光地として成功した効果によるところが強いといえる。 Klien, S. (2010): Contemporary art and regional revitalisation: selected artworks in the Echigo-Tsumari Art Triennial 2000–6. Japan Forum 22/3-4, 513–543 竹田茂生,陳那森 (2012) :観光アートの現状と展望. 関西国際大学紀要, 13, 77-90
抄録全体を表示
-
地理的側面を中心にして
岩本 廣美
セッションID: 713
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本報告は,1947年に発行された社会科読本『社会への旅』(全3冊,各A5判,計199ページ)の内容のあらましおよび作成の背景を明らかにすることを目的としている.『社会への旅』は,奈良県内の主として小学校高学年児童用の読本として作成された冊子である.全国的にはこれまでほとんど知られてこなかったが,地理的方法・内容に関する記述がふんだんに含まれていることや作成者グループの指導者的立場にいたと考えられる人物は,地理学を専門とする堀井甚一郎であったことから,戦後の社会科における地理教育の展開を把握するうえでは,基礎資料のひとつになると考えられるものである.堀井(1902年生)は,東京高等師範学校出身で,田中啓爾の教え子のひとりである.『社会への旅』発行当時,堀井は奈良師範学校教授であった.
抄録全体を表示
-
大村東彼薬剤師会会員薬局に対するアンケート結果から
中村 努
セッションID: 526
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ.はじめに 公平性が求められる日本の医療システムにおいて,医療サービスのアクセシビリティの地域格差を是正する可能性をもつ取組みを検討することは地理学における重要な研究課題の一つである。近年,医療サービスの供給において,地域のニーズに合った医療供給体制を構築するため,ICTの活用を前提とした多職種による役割分担と連携が進んでいる。しかし,実際には地域的に均等にICTが普及しているわけではなく,利用の有無や利用の程度には地域的偏在が認められる。そこで,本発表では,地域医療連携システムの先進事例として知られる長崎県のあじさいネットを事例に,大村東彼薬剤師会の会員薬局のシステム利用状況を明らかにするとともに,システムの普及において地域的偏在が生ずる要因を分析する。
調査の実施にあたって,大村東彼薬剤師会の協力を得て,全会員薬局に対して調査票を郵送し,封筒またはファクスにて回収した。回答期間は2013年8月26日から9月6日までとした。回答率は81.4%(48/59薬局)であった。
Ⅱ.あじさいネットの概要 あじさいネットワークは2004 年10 月に運用を開始し,長崎県内の主要な医療関係機関への普及を実現した地域医療連携システムである。参加形態は情報公開施設と情報閲覧施設の2種類に分かれる。前者は自施設の電子カルテをあじさいネットワークと接続して診療情報を公開する医療施設である。後者は公開された他の施設の診療情報を閲覧する医療施設である。
2014年1月現在,長崎県内の22施設が情報公開施設として,214施設が情報閲覧施設として,あじさいネットに参加している。医療機関が大部分を占めているが,その他の施設としては,37薬局が情報閲覧施設として参加している。
薬局にとっては,情報閲覧施設としてあじさいネットに参加することで,情報公開施設内に蓄積されている電子カルテデータのうち,医薬品同士の飲み合わせ,がん告知の有無,抗がん剤などの副作用,処方意図などを知ることで,適切な服薬指導につなげられるメリットがある。
Ⅲ.大村東彼薬剤師会会員薬局のシステム利用状況
回答のあった48薬局のうち,8薬局があじさいネットに参加していた。あじさいネット参加薬局の在庫品目数は多い傾向にある(図)。参加薬局は,検査情報や処方意図の閲覧を通じた適切な服薬指導および薬歴管理に効果を見出していた。
あじさいネットに参加していない薬局に対しても,利点,コスト,セキュリティ,操作性の4点から,あじさいネットをイメージで5段階評価してもらった結果,薬局の多くがあじさいネットの入会金や利用料を高いと認識していた。不参加薬局もシステムの有用性を認めていたが,現状において情報公開施設の受診患者の処方箋枚数が少ないこともあり,費用対効果が低いとの判断から参加を見合わせていることが分かった。
一方,今後,参加を検討する意思のある不参加薬局が半数以上存在していた。このことから,あじさいネットの利用実績を提示したり,事前に効果を予測したりして,費用対効果を薬局に具体的にイメージできるようにすることが,あじさいネットの普及に向けた課題になっている。 地域医療連携システムはアクセシビリティの地域格差を是正する手段として,職種や地域によらず利用可能になっているものの,コストの利用者負担が依然として大きい。そのため,システムの費用対効果に対する認識の差が,新たな利用機会の格差を生じさせる可能性がある。
抄録全体を表示
-
阿部 智恵子, 若林 芳樹
セッションID: 803
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
地理学における保育サービスの研究は、主として保育資源の空間的配分や保育ニーズの地域的多様性の面から研究が進められてきた。それらの研究で対象になったのは、主として認可保育所である。しかし、子育て支援は働く母親を主たる対象にした認可保育所だけで充足されるわけではない。政府の子育て支援策でも、近年では全ての家庭を対象に地域のニーズに応じた多様な支援が進められている。その一つが全国に配置された子育て支援センターである。本研究は、従来の研究ではほとんど注目されることがなかった地方都市の子育て支援センターを対象にして、そこでのサービス供給と利用にみられる地域的特徴と課題を明らかにすることを目的とする。
研究対象地域のかほく市は、石川県の中央部に位置し、2004年に河北郡のうち北部の3町(高松町、七塚町、宇ノ気町)が対等合併してできた人口34,659人(2010年国勢調査)の新しい市である。全国的にみて北陸地方は、女性の就業率が高く出生率も全国平均を上回ることから、比較的子育てに恵まれた環境にあるといえるが、かほく市も例外ではない。じっさい、かほく市の認可保育所待機児童数は長年ゼロが続いており、年少人口比率も24.1%と高い。また、3世代同居世帯が18.8%を占めることから、親族からの育児支援も受けやすいと考えられる。
本研究は、質的・量的研究方法を併用した混合研究法を用いた。市内の子育てに関する情報は、かほく市役所での聞き取りと同市のWebページなどから収集した。子育て支援センターの利用実態については、2013年9月に、市内の3カ所のセンターを利用する母親を対象とした質問紙調査を実施し、80名から回答を得た。回答者のうち7名に対しては聞き取り調査を実施した。また、センターの職員7名(全員が女性)への聞き取り調査を通して、支援する側からみた利用実態と課題について検討した。
子育て支援センターは、厚労省の地域子育て支援拠点事業の一環として設置されたもので、育児相談や子育てサークルの支援などを主たる任務としている。市内には公共施設の一部を使って3カ所のセンターが設置され、それぞれ複数の職員が配置されている。認可保育所については、合併後に新たに保育所整備計画が策定され、統廃合が進められた結果、現在10ヵ所ある認可保育所は、2015年には9ヶ所になる予定である。市の方針として、合併前の旧3町の融和と一体化に努めており、地域的バランスに配慮したまちづくりが進められてきた。こうした方針は、ゾーニングによる保育所配置計画や、旧町単位での子育て支援センターの設置にも反映されている。他の自治体では公設民営が多い中、かほく市の認可保育所や子育て支援センターはすべて公設公営という点に特徴がある。
子育て支援センターを利用する母親の年齢は20~30代で、利用頻度は週3~4回と月1~2回が大部分を占め、複数のセンターを利用する人もいる。利用する理由の上位は、閉じこもり予防、親子の友達づくり、ストレス解消であった。当該施設を選んだ理由は、家が近い、雰囲気、スタッフの順に多く、9割以上の回答者がセンターのサービスに満足している。結婚や出産を機に退職した母親の割合は約半数にのぼるが、再就職や復職をめざしている人も少なくない。自由回答で挙げられた要望には、日曜日のセンターの開所、職場復帰後の病時保育、ベビーマッサージなど乳幼児でも参加できる行事、園庭の設置などであった。聞き取り調査からは、専業主婦は子どもの世話に専念できるとはいえ、地域の人の目や世の中から取り残されることへの不安がセンターの利用につながっていることも明らかになった。6.支援する側からみた子育て支援の課題子育て支援センターの職員は、親子の居場所、特に母親がリラックスできるような関わりに配慮しており、子どもの成長や発達を身近に感じられることが仕事のやりがいになっている。子育て情報の提供や育児相談にも丁寧に対応し、それらが利用者の満足度の高さにつながっていると考えられる。また、市外からの利用者も受け入れており、近隣の市町のほか、実家に帰省中の母親が利用することもあるという。一方、職員の大半は保育士の経験があるため、保育所との違いからくる自分の立ち位置や、親子との距離感に戸惑いを覚えていることがわかった。そこにはセンターの職員に資格の厳格な定めがなく、職務の専門性が不明確であることも影響している可能性がある。施設のハード面でも、別の公共施設を転用したセンターでは、設備とサービスが適合していないところがあるという。また、育児サークルの支援を行っているものの、親同士の人間関係の煩わしさから、サークルが拡大しにくい実態が示唆された。
抄録全体を表示
-
深見 聡, 大久保 守
セッションID: 316
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
観光研究の場面において、地域住民が自地域の観光に主体的に関わるという観光のあり方に関する議論の高まりがみられる。観光の構成要素を考えると、観光対象となる地域に暮らす住民が支えるコミュニティの存在は、観光の持続的な展開を図る上で不可欠である。そのなかで、ジオパークはまさしくこの状況に合致する仕組みとして注目される。その際、日本のジオパークの多くが過疎地域に分布していることは特筆され、その中でも、より条件不利地域とされる小規模島嶼での認定がみられる点が特徴的である。世界ジオパークに認定された隠岐や、日本ジオパークに認定されている伊豆大島、天草御所浦、おおいた姫島は、いずれも過疎化が著しい小規模島嶼である。これらの島々では、地域ならではの自然資源や人文資源を「大地の遺産」と位置づけ、地域の活性化につなげていくというジオツーリズムに取り組むべく、ジオパークの導入を図ってきた経緯があり、認定後は知名度の向上に関して一定の成果がみられる。一方で小規模島嶼においては、その地理的特性から固有の課題も指摘されてきた。とりわけ、離島振興策として多額の公費を投じ、港湾・道路といったインフラ整備をはじめ、中央の大手資本などによるリゾート開発が進められた事例も多い。それにもかかわらず、その多くで当初期待された経済的な効果などを含む条件不利の克服に繋がったかと言われれば疑問符をつけざるを得ない。むしろ、公共事業に依存した短・中期的な地元の雇用創出という性格が色濃く、地域資源を活かした持続的な観光の取り組みに昇華した事例は決して多いとは言えない実情を直視しなければならない。 以上のような問題意識に立って、本研究は、新しい観光形態としてのジオツーリズムに注目し、特に小規模島嶼に焦点を絞ってジオパークの仕組みを導入することの可能性について検討を加えることを目的におこなう。
研究の目的を達するために、日本ジオパークの認定を目指している地域(日本ジオパークネットワーク〔JGN〕の準会員)の中で、2013年9月現在唯一、小規模島嶼から構成されている三島村ジオパーク構想を取り上げる。本構想は、鹿児島県三島村の有人三島(黒島・薩摩硫黄島・竹島)と海底を含む鬼界カルデラを主なエリアとして、特に薩摩硫黄島を中心に具体化の動きがみられる。 研究方法は、(1)三島村ジオパーク構想について概観した後に、(2)2013年9月6~8日,12月21日に三島村役場及び薩摩硫黄島住民への聞き取り調査をおこない、(3)その両者の意識をとおして、小規模島嶼におけるジオパーク構想の推進と課題について検討を加える、という手順で進めた。
その結果、小規模島嶼でジオパーク構想を展開していくときに、行政と地域住民の連携はもちろん、多様な主体の連携という理想を追求する以前に、高齢化・過疎化、狭いコミュニティという特性を踏まえた丁寧に導入過程における合意形の蓄積がなされる必要性が浮き彫りになった。 この点に関して、以下のような整理が可能であろう。行政・地域住民のいずれもジオパークの仕組みを理解した上での、三島村への導入については、理論上は高い可能性が見出せる。このことは、日本国内にすでに複数の小規模島嶼においてジオパークの認定地が誕生しており、認定の審査段階において、小規模島嶼という地理的条件が不利に働くことはないと思われ、むしろ、ジオパークやジオツーリズムの位置づけは定義の明確化と実質化を常に意識しつつ、現場への導入を図る必要がある。さらに両者の定義からすれば、小規模島嶼では空間的完結性の高さから、ゲートウェイとしての有用性も期待できる。 一方、課題も存在する。それらは、(1)小規模島嶼であるがゆえに、もはや行政や地域住民だけではそれらの仕組みを支えることが人的にも物的にも困難な点、(2)かつて中央資本によるリゾート整備がなさるといった外部依存の開発が頓挫した過去や、役場が三島村外の鹿児島市に置かれているため住民との距離感が払拭しがたい状況が存在するなどの理由から、観光の持続可能性を希求する議論が住民主体でおこなわれる機会に乏しかった点、の2つに集約できる。これらの克服を少なくとも試みる取り組みを始めることが、ジオパーク構想推進の最大の意義と言えよう。特に(2)に関しては、ジオパーク構想の推進段階でジオパークの仕組みを知るというきっかけが行政主導であったとしても問題ではない。むしろ重要なのは、知った後の実際にジオツーリズムを展開する担い手が住民主導でなければ、過去の開発の失敗と同じ道を繰り返しかねない。
これまで見てきたように、ジオパーク構想の推進にあたっては、特に小規模島嶼の場合、理論上の可能性は見出されても、その前提として、地域住民の理解がなければ容易ではないことが確認された。
抄録全体を表示
-
-2013年ボホール地震断層の緊急調査を例に-
中田 高, 井上 公, Cahulogan M., Rivera D. J. , Lim R. , Pogay C.
セッションID: 637
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本報告では,2013 年10月15日にフィリピン・ボホール島で発生したM7.2(PHIVOLCS)の地震に伴って出現した地震断層を,UAVとSfM(Structure from Motion)ソフトを用いて解析した例を報告し,この手法の地形調査・活断層研究への活用の可能性を検討する.
抄録全体を表示
-
大貫 靖浩
セッションID: S0503
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
演者は現在まで、さまざまな地形・地質・気候条件下における森林土壌を観察する機会を得てきた。森林土壌が斜面のどの位置でどのくらいの厚さを有し、どのような物理的性質(例えば容積重、孔隙率、レキ量)を持つかについては、森林土壌学の分野では系統だった研究は行われてきていないが、微地形分類を切り口にすると明瞭な区分が可能であることがわかってきた。本発表では微地形分類に基づく森林土壌の物理特性に関する研究成果について、北関東と沖縄で行った実例を紹介したい。
調査地は茨城県城里町の桂試験地、および沖縄県名護市の南明治山試験地である。両試験地ともにいわゆる「低山帯」に位置する小流域で、桂試験地は中古生層の頁岩・チャート等の上に関東ローム層が堆積し、乾性~湿性の褐色森林土が分布している。これに対し南明治山試験地は、第三紀層の砂岩・泥岩等が基盤となり、一部でレスが堆積し、赤色土・黄色土・表層グライ系赤黄色土が分布している。
桂試験地(2.3ha)では、682地点を測点とした地形測量によって精密地形図を作成した後、571地点で土研式簡易貫入試験を実施し、10地点で土壌断面調査を行った。桂試験地においては斜面中腹を限る形で明瞭な遷急線が確認でき、遷急線の上側には頂部斜面・痩せ尾根頂部斜面・上部谷壁斜面・上部谷壁凸斜面・上部谷壁凹斜面が、下側には谷頭斜面・谷頭急斜面・谷頭凹地・下部谷壁斜面・下部谷壁凹斜面・麓部斜面・小段丘面・谷底面が分布する。土層厚は痩せ尾根頂部斜面・上部谷壁凸斜面を除く遷急線上側の各ユニットと、谷頭斜面・谷頭凹地で厚いことがわかった。
土壌の物理特性は遷急線を境に明瞭に異なり、遷急線より上方の斜面では上部谷壁凸斜面を除き容積重が小さく、全孔隙率が高く、レキ量が非常に少ないのに対し、遷急線下方の斜面では容積重が大きく、全孔隙率が低く、レキ量が比較的多いことが明らかになった。保水機能に寄与する有効孔隙率は、遷急線より上方の頂部斜面で特に高い値を示すのに対し、遷急線下方の斜面では低い値を示し、レキ量の多寡が有効孔隙率に影響を及ぼしていると考えられた。
南明治山試験地(1.0ha)では、130地点を測点とした地形測量によって精密地形図を作成した後、99地点で土研式簡易貫入試験を実施し、9地点で土壌断面調査を行った。南明治山試験地においては、明瞭な遷急線は上部谷壁斜面および谷頭凹地と下部谷壁斜面の境界に確認でき、遷急線の上側には頂部平坦面・頂部斜面・上部谷壁斜面・谷頭凹地が、下側には下部谷壁斜面および谷底面が分布する。土層厚は頂部平坦面および谷頭凹地で厚い。 土壌の物理特性は微地形および土壌型によって明瞭に異なり、頂部平坦面に分布する赤色土は容積重が大きく、全孔隙率が小さいが、飽和透水係数は比較的大きい。頂部平坦面・頂部斜面に分布する表層グライ系赤黄色土は、容積重がA層でも1.0Mgm
-3を超え、全孔隙率・飽和透水係数ともに小さい。上部谷壁斜面・谷頭凹地に主に分布する黄色土は、赤色土・表層グライ系赤黄色土と比較して特にB層の容積重が小さく、全孔隙率・飽和透水係数が大きかった。土壌侵食危険度の指標となる粘土比と分散率は、赤色土・表層グライ系赤黄色土で高く、黄色土で低かった。
抄録全体を表示
-
村山 祐司
セッションID: S0301
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
欧米では,国際共同研究,大学院プログラム,人事・学生交流,ジャーナルの編集,書籍の出版をはじめ様々な面において,国際化が進行している.国際会議・ワークショップ・セミナーなども頻繁に開催されている.世界各国から多くの地理学者を集め,情報交換が日常的に行われるようになった.欧米の地理学者は,アフリカやアジアなど発展途上国との学術交流にも積極的である.国を越えた連携が加速しており,国際化の波は勢いを増している. このような状況を踏まえ,世界のなかで,あるいはアジアのなかで,日本の地理学がそのプレゼンスを示し,学術的ステイタスを高めていくには,今後どのような戦略で臨み,どんな具体的施策が必要であろうか.このシンポジウムを通じて,国際化を加速させるうえでの課題や方策,さらにはあるべき将来像などについて,議論を深めたい.
抄録全体を表示
-
白坂 蕃, 稲垣 勉, 大橋 健一
セッションID: 510
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
熱帯アジアには「hill stations」とよばれる高原避暑地がある。これは植民地時代のヨーロッパ人のアジア進出によって形成されたものである。
本稿では、hill stationsの一つであるマレーシアのCameron Highlandsをとりあげる。 Cameron Highlandsはいわゆるマレー半島の中央山脈に位置し、標高1,000-1500mに集落が展開している。 こんにち、Cameron Highlandsは、リゾートとして機能だけではなく、西マレーシアではもっとも重要な温帯蔬菜と花卉の栽培地域になっている。 Cameron Highlandsは1926年にhill stationsとしての開発がはじまったが、すぐに農業試験場。気象観測所が開かれた。1940年頃には数件のホテル、20をこえるバンガロー(大型の別荘)、それにゴルフ場があった。 第二次世界大戦後、マレーシアの経済発展により1980年代からはリゾートとして国民化され、西マレーシアでは重要な観光地になっている。
一方、hill stationsとしての開発の当初から、バンガローに雇われていた華僑によって、中国から種子が持ち込まれて蔬菜栽培もはじまった。 こんにち、この高原では30種を越える種類の温帯蔬菜を栽培されているが、ハクサイ、キャベツ、トマトが三大蔬菜である。それはマレーシアのどの民族もそれらを消費するからである。しかし、それらの種子の多くは日本をはじめ、韓国・台湾・アメリカなどから輸入されている。
現在、Cameron Highlandsで生産される蔬菜の80%はクアラ=ルンプルをはじめ西マレーシアの各都市に移出されている。またその20%はシンガポールに輸出される。
Cameron Highlandsの蔬菜栽培や花卉栽培農家では、1992年から外国人労働力の雇用が可能になった。2013年3月現在、約13,000の外国人労働者が農業に従事している。外国人労働者なしに、この高原の農業は維持できなくなっている。
抄録全体を表示
-
松本 太, 中村 圭三, 濱田 浩美, 谷地 隆, 駒井 武, 大岡 健三, 松尾 宏, 谷口 智雅, 戸田 真夏
セッションID: P053
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ネパール南部テライ低地においては、地下水のヒ素汚染が深刻な問題になっている。そこで、本研究グループでは、ナワルパラシ郡パラシにおいて、ヒ素汚染の実態把握やその対策に関する研究を行っている。それらの基礎資料とするため、気候調査を開始した。その一環として、屋内の温熱環境を調査している。その成果は、水収支や水利用、生活実態の評価にも有効と考えられる。また、疾病予防や気候特性に適応した住まい方や環境デザインの基礎資料となりうる。今回は、異なる建築構造の住居内で行なった温熱環境調査について、現段階での結果を報告する。
抄録全体を表示
-
高橋 日出男, 清水 昭吾, 大和 広明, 瀬戸 芳一, 横山 仁
セッションID: 213
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
◆はじめに
都市気温分布には,最も高温な都心(peak)と田園・郊外域との間に,気温の水平傾度の大きい気温急変域(cliff)の存在が想定されている(たとえば,Oke 1978; 1987)。スプロール状に都市化が進行した日本の都市では,気温急変域は不明瞭ともされるが,Yamashita(1996)は鉄道を用いた移動観測の事例により,東京都区部やその周辺における気温急変域の存在を指摘している。また,山添・一ノ瀬(1994)は,自治体の大気汚染常時監視測定局(常監局)の資料により,弱風晴天日夜間の都区部を中心とした気温分布の考察を行い,明確ではないものの気温急変域に言及している。 本研究では,都心と周辺部との気温差が一般に大きい冬季の夜間を対象として,複数の観測網を併用した稠密気温観測資料に基づき,都区部とその周辺における気温急変域の発現位置と時間変化を明らかにすることを目的とする。解析にあたり,都心と都区部外側との気温差が大きい晴天弱風夜間の事例を抽出したが,その際に気温差の大小と気象条件との関係についても考察を行った。
◆資料と対象期間
本研究で用いた気温資料では,広域METROS(三上ほか 2011)は百葉箱,気象庁アメダスは強制通風式シェルターが観測に用いられており,常監局については両者が混在している。ただし,Brandsma and van der Meulen(2008)やAoshima et al.(2010)などによる各種シェルターを用いた比較観測結果から,日射のない夜間については,百葉箱と強制通風式シェルターによる観測値に,解析に支障のある差異はないと判断し,あえて複数の観測網による気温資料を併用した。対象期間は,欠測を含むが広域METROSの資料が使用できた2006/2007年から2009/2010年の冬季(11月から2月)とした。気象条件(夜間平均の雲量・風速・水蒸気圧,前日中の全天日射量など)は東京(大手町)の観測値を用いて集計した(風速計の移設も考慮)。また,アメダス4地点(府中,さいたま,船橋,海老名)と東京(大手町)との気温差の平均値を,都心と都区部外側との気温差(TD:以下,気温差という)とした。
◆都心と都区部外側との気温差について
日の出前の06時における気温差と気象条件との関係として,雲量の大小は風速の強弱にあまり関わりなく気温差の大小に強く関係するが,風速の強弱は雲量が小さい場合に気温差の大小と強く関係していた。また,気温差を被説明変数とした重回帰式と雲量や風速の日々の変動幅(標準偏差)などから,気温差の大小に対する影響の主従関係としては雲量が主,風速が従と考えられた。晴天弱風の夜間(夜間平均の雲量2以下,風速3m/s以下:73事例)における時刻ごとの平均の気温差は,日の入り前後に急増する。ただし,その後は日の出までほぼ一定の気温差を示すとした山添・一ノ瀬(1994)に対し,気温差は緩やかに増大を続け,日の出前(06時)に最大となる(図1)。また,同様の晴天弱風条件であっても,06時の気温差が大きい場合(4℃以上:37事例)の平均では,夜半以降も気温差が顕著に増大を続けるが,気温差が小さい場合(4℃未満:36事例)の平均では,夜半過ぎから気温差は漸減する。
◆気温分布(気温急変域)について
06時の気温差が大きい晴天弱風夜間について,欠測をできるだけ含まない多数地点を多数事例において扱えるよう考慮し,124地点(アメダス:4地点,常監局:61地点,広域METROS:59地点)が使用できる2冬季(2006/2007年と2007/2008年)の25事例を対象とした。なお,各事例の毎正時における気温観測値から,クリギング法によって約1km間隔の格子点値を求め,水平気温傾度(-∇
T)などの計算や合成図等の作成を行った。 都区部における高温の中心は,夜間を通して中央区南部付近にある。都区部には明瞭な気温急変域(図2左)が多重構造をなして認められる(図2右)。気温急変域は日の入り前後の数時間で現れて,日の出前にかけてしだいに明瞭となるが,位置は変化しない。日の入り前後の気温低下量分布には,低下量の小さい都心部と大きい周辺部との間に,気温急変域に対応した気温低下量の急変域が認められる。その後の気温低下量も都心部で小さく周辺部で大きいが,顕著な急変域は認められず比較的なだらかな分布をしている。日の入り前後と夜半頃以降とでは,気温低下のプロセスが異なる可能性が示唆される。
抄録全体を表示
-
中田 高, 渡辺 満久
セッションID: P002
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
演者らは,これまでに,南海トラフや日本海溝周辺に分布する長大な活断層の位置・形状を明らかにし,海底活断層の位置と歴史地震の震源域が良く対応することを示してきた.ところが,従来のアスペリティモデル(Lay and Kanamori,1980 )を重視する多くの地震研究者は,このような海底活断層の位置・形状の重要性を理解してない.陸域では活断層情報をもとに地震の長期予測が行われているにもかかわらず,発生源となる活断層を直接観察できないためか,変動地形学的に認定された海底活断層や変位地形は長期予測に十分に生かされているとは言い難い.海底地形データ(変動地形)と地下の断層の状況は異なると考える研究者は少なくない.しかしながら,海底の変動地形は海底活断層による累積的断層変位の具体的な物証であり,モデル設定において無視できる情報であるとは考えられない.
抄録全体を表示
-
中澤 高志, 神谷 浩夫, 由井 義通, 丹羽 孝仁, 鍬塚 賢太郎, 中川 聡史
セッションID: 805
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに 現在、日本人の国際移動は第三段階にあるといえる。第一段階は、戦前から1970年ごろまでの「日系人」としての移住であり、経済的・人口学的プッシュ要因を背景に、政策的関与の下で行われた恒久的移動である。第二段階は1980年代以降に日本企業の多国籍企業化に伴って駐在員が増加した段階である。駐在員の派遣は企業組織の論理に起因しており、人的資源の最適な配置や従業員のキャリア形成などを主な目的とする循環移動である。現在に至る第三段階とは、1990年代半ば以降に自らの意志で海外就職を行う若者が増加してきたことを指す。こうした若者の移動は、必ずしも経済的な達成を第一の目的としておらず、自己実現の一手段という側面を持つ。報告者らは、2006年より、シンガポール、上海、バンコクなどの諸都市において、自分の意志で海外に移住し働いている日本人に対する調査を行ってきた。その結果、彼/彼女たちが海外就職を決意したきっかけは個別性が強い一方で、日本人の国際移動が第三段階を迎えた背景には、国内の若年労働市場の悪化や、日系企業の現地法人における駐在員から現地採用への切り替え、人材ビジネスの確立といった、共通の構造的要因にも目を向けるべきことが認識された。また、目的地となる都市ごとに移動者の属性や就業形態が異なっており、それを把握することも課題となっている。本報告では、シンガポールでの調査に基づくす既発表論文や、上海での調査に基づく学会報告を意識しながら、バンコクで働く日本人の特性について検討する。2.統計にみるバンコクで働く日本人の特徴2012年10月1日現在、バンコクに在留する日本人は、都市別では世界第4位である。海外在留邦人数統計によれば、バンコクの在留邦人の属性はシンガポールとは対照的である。すなわち、永住者が少なく、より男性に偏っており、同居家族として来ている人が少ない。上海とシンガポールとの対照性はさらに大きい。アジア通貨危機以降、タイに派遣される駐在員数は頭打ちであるが、在留邦人数は増加を続けている。大手企業の進出が一服した今日、タイに進出する日系企業の規模は小規模化しており、『海外進出企業要覧』から漏れている企業が少なくないと思われる。バンコクでは、日系企業や現地在留の日本人を対象とする「日本市場」の規模が大きいため、それを当て込んで日本人が起業した企業も数多く存在し、現地採用の日本人に対する新たな需要が生み出されている。当日は、報告者らが実施してきたインタビュー調査に基づき、バンコクで働く日本人の存立形態を、当該地域の「日本市場」の存在と関連付けて分析する。
抄録全体を表示
-
伊藤 千尋
セッションID: 515
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
自然資源に依存して暮らす人びとが多いアフリカにおいて、資源の減少は生活に直結する深刻な問題である。特に、政治・経済システムが不安定な地域では、人びとの資源へのアクセスや利用の仕方は、マクロ・ミクロレベルでの様々なイベントに左右される。そのため、持続的な資源利用の枠組みを構築していくためには、自然環境だけではなく、社会の動態を注視していくことが重要となる。 本研究では、ジンバブウェ・カリバ湖の漁業資源に関して、国家レベルでの政治・経済変動と、ローカルレベルでの人びとの応答との関係に注目する。ジンバブウェでは、独立以降、現政権が白人-黒人間の経済格差の是正を目指してきた。2000年の土地改革に見られるように一部強行的に、経済の「現地化」を進めてきた。この流れの中で、カリバ湖の漁業においても白人事業者から黒人事業者への漁業権の再分配が行われた。本研究では、この再分配のプロセスを、漁業に関わる人びとの生活やアクター間の関係性の変化に注目して明らかにし、その結果として資源利用にどのような変化が起こってきたのかを考察する。
調査はジンバブウェ共和国マショナランドウェスト州に位置する都市カリバにて、2013年6-8月、11-12月に行った。調査地はカリバ湖の沿岸に位置している。カリバ湖では、カペンタ(
Limnothrissa miodon)と呼ばれるニシン科の小魚が主要な商業漁業資源であり、現地の人びとの重要なタンパク源になっている。本研究では、カペンタ産業を対象として関連事業者への聞き取り調査を行った。また、漁業ライセンスや違法行為を取り仕切るジンバブウェ国立公園・野生動物保護庁における聞き取り調査と資料収集を行った。
カペンタの商業漁業は1970年代半ばから本格化した。カペンタ漁は、漁船などをはじめとする初期費用が高いため、独立以降も1980年代前半ごろまでは事業主体のほとんどが白人であった。政府は、経済機会を黒人層にも広げようと協同組合の結成を奨励し、1980年代後半に黒人事業主らは組合という形で参入し始めた。しかし、資本力に勝る白人企業が漁船数を多く持つという構図は、1990年代に入っても変化しなかった。 1990年代後半から、カペンタ産業でも「現地化」の機運が高まっていた。2000年以降、白人農家の土地を強制的に収容するという土地改革の動きが高まるなかで、漁業ライセンスを白人事業者から剥奪し、黒人側に分配するという再分配が実行された。 再分配により、既存の協同組合や、個人起業家、退役軍人や役人などが新たに漁業ライセンスを与えられた。しかし再配分の恩恵を受けた多くの人びとは、漁船を作る資金力が不足していたため、ライセンスを一時的に他者にリースすることよって資金を蓄えるという措置が取られるようになった。 ライセンスのリースが可能になったことで、従来よりも参入が容易になり、利害関係の異なる多様なアクターが乱立するようになった。アクターの多様化は、組織力の低下、禁止・違法行為の頻発、それにともなう漁獲量の低下、といった弊害を引き起こし、さらに参入・退出が頻繁に起こるという悪循環を生みだしていた。そのため、現在のカリバ湖の漁業資源利用は、政策の変化やそれに呼応する人びとの生計戦略、アクター間の関係性の変化といった様々なレベルのイベントの連鎖のもとで成り立っていると考えられる。
抄録全体を表示
-
福井 幸太郎, 飯田 肇
セッションID: 609
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
飛騨山脈,立山東面の内蔵助(くらのすけ)雪渓には,積雪の下に厚さ30mに達する日本最古(1500~1700 y BP)の氷体が存在する.この氷体には複数の礫層がみられ,下流方向にスラストアップする構造を示すことから少なくとも過去には氷河として流動していたと考えられている.しかし,現在,流動しているか否か不明で,現存氷河とはいえなかった.2011年9月~2013年9月にかけて二周波GPSを使って2年越しの氷体の流動観測を行った.その結果,751日間で10,31 cmと誤差以上の有意な流動が観測された(図1a).年間の流動速度は4,14cmと氷河としては非常に小さいものの,現在でも流動していることが判明したため,内蔵助雪渓も現存氷河であると考えられる.剱岳西面にある池ノ谷右俣雪渓で,2012年9月にアイスレーダー観測を行い,厚さ40 m以上,長さ700 mに達する氷体の存在を確認した.2012,2013年秋に行った氷体の流動観測の結果,秋の30,42日間に11~22 cmの流動が観測された(図1b, 1c).流動速度が一定だと仮定して年間の流動速度を求めると1.4~1.9 mになる.この流動速度は,三ノ窓,小窓氷河のそれ(2~4 m/年)につぐ速さであり,池ノ谷右俣雪渓も現存氷河であると考えられる. なお,発表では2013年秋に実施した剱岳三ノ窓氷河と立山御前沢氷河でのボーリングの結果についても簡単に紹介する予定である.
抄録全体を表示
-
菅澤 雄大, 伊東 真佑
セッションID: P033
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
2013年10月11日に発生した台風26号は,10月15日の夜から10月16日の明け方にかけて関東地方沿岸に最接近した.この台風26号は10年に1度の規模の大型台風と言われ,伊豆大島では大規模な表層崩壊と土石流が発生し,36人が死亡,3人が行方不明となる甚大な被害をもたらした(「朝日新聞」2013年12月30日朝刊).首都圏でも強風や大雨で交通網が乱れ,通勤・通学に支障が出た. 台風26号は,関東地方の東の太平洋上を通過したため,太平洋に面した平野部や海上において主に被害をもたらした.その一方で,関東地方や中部地方の山岳地域での土砂災害の報告は少なかった.近年,これらの山岳地域には,いわゆる「登山ブーム」によって多くの登山客が訪れている.今回の台風では登山客を巻き込む土砂災害は発生しなかった.しかし,強風や大雨の影響を受けやすい山稜部の登山道では倒木や小規模な崩壊が起こり,登山客の利用を妨げる障害が起こった可能性は十分にあり得る.このような被害は小規模であったとしても放置されることによって,登山道の管理を困難にするだけでなく登山者の事故を引き起こす可能性もあり,決して看過してはならないものと考える. そこで今回は,南アルプス北部,鳳凰三山の薬師ヶ岳(標高2780 m)に至る登山道において,台風26号が最接近した10月16日の2日後の10月18日に台風による倒木や登山道の崩壊の状況を調査し,山小屋の小屋人の聞き取り調査から登山道の整備活動についても知ることができたので報告する.薬師ヶ岳は南アルプス北部の鳳凰三山の一角で,山梨県南アルプス市と韮崎市の市境に位置している.多くの登山者は,甲府駅から山梨交通のバスを利用して,夜叉神峠登山口(標高1375 m)からこの山に登る.この登山コースは東京からのアクセスがよく,登山口から山頂までの標高差も小さい.また,岩場やガレ場などの危険箇所も少ないコースであることから,登山客の年齢構成も幅が広く,子供から年配者まで多くの登山者が訪れている.今回は,夜叉神峠登山口から薬師ヶ岳山頂までの登山道を調査地域に選定した. まず,気象状況を明らかにするため,台風26号が最接近した10月16日の前後2日間の降水量と風向・風速のデータを甲府気象台と山梨県・長野県のAMeDAS(計7ヶ所)から収集した.現地調査は,台風通過2日後の10月18日に行い,登山道沿いに見られた倒木や登山道の崩壊の発生位置をGPS(GARMIN社製Oregon 550TC)を用いて測量した.また,この登山道沿いに立地する薬師ヶ岳小屋(標高2711 m)と南御室小屋(標高2429 m)の小屋人から,台風接近時の小屋周辺の状況や登山道の整備活動に関する聞き取りを実施した.調査結果は以下のようにまとめられる. ① 調査地域に一番近い韮崎の気象データを見ると,降水量は10/15の22時から増え始め,10/16の6時には0.0 mmとなった.また,10/16の1時から2時に時間雨量の最高値(8.5 mm)を観測した.風は,10/16日の2時から強くなり,7時~8時に最大平均風速(15.6 m/s)を観測した. ② 現地調査の結果,登山道沿いにおいて倒木は18ヶ所,登山道の崩壊は9ヶ所存在することが明らかになった. ③ 倒木は,夜叉神峠登山口~夜叉神峠小屋(標高1375~1750 m)のカラマツ植林地,辻山(標高2584 m)周辺のシラビソ林で多かった. ④ カラマツ・シラビソの倒木には胸高直径が30 cm以上の樹木(年輪計測の結果,樹齢100年以上)が多かった.倒木の状態には,幹折れと根返りが認められた. ⑤ 調査地域北部の南御室小屋から薬師ヶ岳山頂付近までの登山道沿いに小規模な崩壊が多く見られた. ⑥ 辻山(標高2584 m)周辺で発生した倒木は,調査を行った10/18(台風最接近日の2日後)には短く切られ,登山道の通行を妨げない場所に移されていた.これは,南御室小屋の小屋人が独自に行った活動であった.また,小屋人は,地元の登山者の知らせで倒木の存在を知ったとのことである. ⑦ 聞き取り調査から辻山周辺は強風が吹き抜け,倒木が発生しやすい場所である一方,南御室小屋から薬師ヶ岳山頂まではこれまでも倒木が少なかったことが明らかになった.
抄録全体を表示
-
Field analysis of the local residents in a gentrifying neighbourhood in Shanghai
超 章
セッションID: S0603
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
In the context of urban regeneration, the conflict between corporate city and urban villages poses a crisis of authenticity. In Zukin’s research of New York City, she regards ‘a city is authentic if it can create the experience of origins’ (Zukin, 2010:3). Reviewing many cities in the world, gentrification process has been associated with ‘authenticity’ while reproducing local spaces both physically and socially. The case studied in this research is an old neighbourhood in inner Shanghai which is preserved and gentrified owing to the local authenticity of Shikumen architecture. Informed by Bourdieu’s field theory (1986, 1993), this research tentatively applies it in urban studies by developing the field analysis of this neighbourhood. Based on the field work between 2008 and 2011, this paper reveals the dilemma of authenticity at the neighbourhood level, and how gentrification as an uneven process, leads to the social exclusion and inequality among the local residents. Wacquant (2008:198) suggests the need to go beyond the diagnosis ‘gentrification of gentrification research’, and to recharge gentrification studies by a sturdier analytical framework for capturing ‘the (de)formation of postindustrial proletariat’. The development of field analysis in this case study is therefore, on the one hand, an echo of Wacquant’s call to systematically probe into the social relations in gentrification, and on the other, to explore the potential of Bourdieu’s field theory in urban studies (Savage 2010). The case, Tianzifang (abbreviated as ‘TZF’), is an old inner-city neighbourhood of industrial real estates and alleyway tenements, known as ‘Shikumen’(‘stone-gate house’) in the local context. In the end of the 1990s, artists started to settle in the vacant factories, making it an ‘art street’ which was later designated as a ‘creative industry cluster’ by the municipal government. Over the past decades, regeneration expanded from the industrial properties to the adjacent run-down Shikumen dwellings. The place gradually transformed to a well-known cultural and tourist destination themed on Shikumen heritage, and to a mixed neighbourhood and a space of consumption. Primarily using in-depth interview and visualisation for collecting data, the field analysis of TZF is focused on two groups – the local people who are still living in the neighbourhood, and those who have moved out by a rent gap thus becoming landlords. First, tensions and conflicts among the mixed neighbourhood are exposed. These are various forms of encroachment upon the local residential life from other space users, including shops, restaurants and tourists. These tensions develop into appeals and conflicts from the local residents for claiming their space from the commercial re-zoning. Secondly, this paper brings the discussion about the landlords, the economic profits and other benefits they have gained. Their particular identity – as previous long-term neighbours of the remaining residents, and landlords of boutiques, cafes and restaurants, brings them into alliance for safeguarding their vested rent gap. They formed a volunteering group to mediate the conflicts of the mixed neighbourhood and meanwhile adopting other strategies. Thirdly, I will summarise the distinct positions, strategies and struggles of the two groups as well as the forces in the field transformation of TZF. From a comprehensive analysis of the various space users, the remaining residents became the most vulnerable group in the field and were socially excluded from TZF though physically in space and perceived as a sign of ‘authenticity’, which marks the disruption of the original long-term established neighbourhood. Finally, the policy implications will be pulled out in terms of governing the mixed neighbourhood.
抄録全体を表示
-
龍崎 孝
セッションID: 107
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
2011年3月11日に発生した東日本大震災によって宮城県は142漁港全てが被災するなど多大な被害を受けた. 宮城県は水産業復興に向け、集約・効率化を図る施策を選択し、機能集約が図られる漁港は60港に絞られた. さらに県は水産業復興特区構想を打ち出し、2011年12月に国の特区法施行を経た上で2013年8月に石巻市桃浦が復興特区に認定された. 特区はこれまで漁協が優先順位一位で付与されてきた特定区画漁業権を、民間が資本参加した経営体を漁協と同列の一位で審査し、漁業権を付与する政策で、付与された経営体は漁協に参加せずに漁業を営むことができる. 水産業の復興にあえて「格差」を持ち込んだのである. 宮城県水産業復興特区には漁業文化、漁業経済の視点から賛否両論があるが、政策導入により漁業集落コミュニティがどのような影響を受け、変化し、その再生と持続につながりうるのかを本考察は明らかにしようとするものである. 漁獲量が戦後のピークの三分の一まで落ち込んでいるなど水産業を取り巻く状況は厳しい. 原因のひとつは漁協の漁獲量管理がずさんなためと指摘されている. 水産業復興特区は漁業権を保有し組合員たる漁民の「管理主体」としての役割を漁協から奪い、漁業権を一経営体に付与する政策で、県漁協の理解を得ないまま2013年4月に石巻市桃浦の特区が認定された. 石巻市桃浦は津波でカキ養殖施設が壊滅的な状況にあり、集落存続の危機にあった. 桃浦の漁民の大半が2011年秋に特区構想に応じることを決め、仙台市の水産会社と共同出資の「桃浦かき生産者合同会社」(以下桃浦LLC)が桃浦の養殖漁業者15人により発足した. 桃浦LLCは被災前の年間売上1億9400万円を2016年度には3億円に伸ばすことを目標にし①沿岸養殖漁業における六次産業化②持続的な地域産業形成によるコミュニティの再構築―を目指している. 宮城県は2012年2月に発表した「富県宮城の復興計画」の中で特区構想の特徴として(1)漁業権の行使料などの経費が不要(2)新たな販売経路が構築しやすい―などと説明している. これは漁協が独占している共販制度から離脱して加工販売の自由を確保し、六次産業化を容易に進めることを狙いとしており、これは漁民が漁協の管理下を離れることを意味する. 村井嘉浩県知事は震災直後の2011年5月10日に首相官邸で開かれた東日本大震災復興構想会議で水産業復興特区を提案した. 宮城県漁協は反対を表明したが、知事は5月29日の同会議で漁協を中心とする現在の水産業の在り方を批判的に説明し、同時に特区構想の必要性を主張、6月11日には原案となる復興特区法の全容を会議で提示し、6月25日に発表された「復興提言」の中に盛り込まれた. その間に宮城県漁協は反対署名などを提出したが、県は一切顧みることはなかった. 知事の動きなどから特区構想導入は、震災からの復興に寄与することは副次的な目的で主眼は漁協排除のきっかけを作ることではなかったか、と考察する. 水産業復興特区は、漁業コミュニティにどのような変化をもたらすのか. 視点の一つとして新自由主義的な政策を展開した英国・サッチャー政権下で行われた炭鉱闘争とその帰結を考察する. 英国の炭鉱産業は、労働者の流動性が少なく、地域のコミュニティと密接不可分にあった. その特性は日本の漁業集落と似ている. 1984年の英国炭鉱ストは、生産性の高いデューカリズ地区の炭鉱群がストに参加しなかったことなどから次第にスト離れが続いて崩壊し、その帰結として炭鉱は民営化された. 漁業権を得て漁協から離脱した桃浦の存在は、宮城県水産業における「デューカリズ」となる可能性を持つ. 県漁協は特区構想の導入によって、漁業紛争の解決にあたる調整者としての機能が失われる. 当事者能力が奪われる中で、漁業集落というコミュニティを束ねてきた漁協の地位は揺らぎ、漁協コミュニティの「分断」と「融解」が始まると考えられる. 一方桃浦では二つの事象が起きている. 一つは仮設住宅などで避難生活を送ってきた住民たちが桃浦に隣接する高台に移住する計画が進みつつあること、また桃浦LLCに参加せずに、従来通りの漁協組合員として桃浦でかきの養殖に取り組む漁民1名が存在することだ. 漁業集落コミュニティでは「生活の場」と「生業(なりわい)の場」が一体であることが常態であったが、桃浦では高台における「集落コミュニティ」と浜における「漁労コミュニティ」のふたつに「分離」することになり、その「融合」を今後どう図るかという視点が求められる.
抄録全体を表示
-
南極を通してのESD
久保田 充
セッションID: 712
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
@font-face { font-family: "MS 明朝"; }@font-face { font-family: "MS ゴシック"; }@font-face { font-family: "Century"; }@font-face { font-family: "Cambria Math"; }@font-face { font-family: "@MS ゴシック"; }@font-face { font-family: "@MS 明朝"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0mm 0mm 0.0001pt; text-align: justify; font-size: 12pt; font-family: Century; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; font-family: Century; }div.WordSection1 { page: WordSection1; } 1.はじめに 2002年12月の国連総会において、2005年から2014年までの10年間を「国連持続可能な開発のための教育の10年」とすることが決議された。「持続可能な開発」とは、将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、現代の世代のニーズを満たすような社会づくりのことを意味する(ユネスコ,2005)。 そして、平成20年3月告示の中学校学習指導要領、平成21年3月告示の高等学校学習指導要領において社会科系教科で、「持続可能な社会の実現を目指す」(以下、持続可能な開発のための教育を「ESD」と略す)という視点が明示された。つまり、ESDの視点を取り入れた学習指導がよりいっそう求められるようになったといってよい。本報告では、2012年12月、2013年1月に高校「現代社会」の授業内に実施したアンケート結果を示し、南極を取り上げたESDの可能性について考察する。 2.高校生の「日本の南極観測事業」に対する意識 昨年度、高校1年生の「現代社会」の授業で、日本の「南極観測事業」についてのアンケートをおこなった。「財政難で十分な予算が確保できないため、南極観測船『しらせ』に搭載する大型ヘリコプターの運用が滞っている」という新聞記事を配り、「現在の日本の国家財政を考えた上で、もしあなたが首相だったら、南極観測事業の予算を増額するか、しないか」を理由も含めて回答してもらった。回答者数145名、予算を増額する58名(40%)、増額しない87名(60%)であった。 増額しないと回答した生徒の理由をみると、「国家財政が厳しいから」、「東日本大震災への復興予算が必要だから」、といった必要性はわかるが止むなくという意見もあったが、一方で、「日本の南極観測事業が何をしているかわからない」「今まで日本が南極観測事業をしていることも知らなかった」という意見もみられた。 3.「出前授業」 つぎの授業で、元南極観測隊員の方に「出前授業」をおこなっていただいた。内容は自身の両極地域における観測経験についての話と地球温暖化についてである。授業後のアンケートで、1)南極に行ってみたいか、2)印象に残った内容、3)感想、を回答してもらった。回答者151名、南極に行ってみたい66名(約44%)、行きたくない85名(約56%)であった。感想をみると、地球温暖化について興味や関心が深まった、意識が変わったという意見が多かった。また、実際に体験した方の話を聞き、南極や北極の自然や環境に興味をもったという意見もあった。 4.ESDと南極 南極大陸は、地球上で唯一の「国境もなければ軍事基地もない大陸」であり、「人類の理想を実現した地域」である。それを可能にしたのが南極条約であり、80年代の南極における資源開発の波にも待ったをかけた。90年代には環境保護に関する南極条約議定書も発効し、より明確に環境保全に対する努力が求められるようになった。このような特質を有する南極は、学習指導要領で求められているESDの視点にたった学習指導の題材として最適な地域の一つであるといえよう。とくに、高等学校「地理B」の「(3)現代世界の地誌的考察」で南極の探検史、南極条約、南極からみた地球環境問題などを取り扱うことは、ESDの視点からも大変意義が大きいと考える。これは、「地理」という科目だからこそできる切り口ではないだろうか。その中で、近年研究機関でも活発になっているアウトリーチ活動の1つである「出前授業」を活用することは、生徒たちの興味・関心を高めるだけでなく、日本の南極観測事業を社会的に認知してもらう上でも大切であると考える。
抄録全体を表示
-
藤本 潔, 宮城 豊彦, 西城 潔, 竹内 裕希子
セッションID: S0501
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
地形学辞典によると、「微地形」とは「5万分の1~2.5万分の1の地形図には表現されないような地表面の微細な凹凸」と定義されている。実際には、例えば平野上では、自然堤防、後背湿地、旧河道、浜堤列など、丘陵地では、谷頭凹地、頂部斜面、上部谷壁斜面、下部谷壁斜面などが微地形単位と認識されており、貝塚(1998)で分類されたように、空間スケールとしては10
1mオーダー、時間スケールとしては10
3~10
1年オーダーで形成された地形を「微地形」として捉えることが一般的であろう。地表付近での様々な自然環境(例えば、植生、土壌、水環境、微気候など)は「微地形」と密接な関わりをもつ。その自然環境に左右され、あるいは利用してきたのが人間である。そのため、「微地形」を分類し、その分布や形成プロセスを理解すること、さらにはこれらを踏まえた上で「微地形」と人間活動の関わりを考察することは、地理学の重要な研究テーマのひとつとなってきた。しかし、例えば丘陵地における大規模開発は「微地形」の消失とそれに伴う生物多様性の喪失を招き、平野上での「微地形」を無視した人間活動の無秩序な拡大は、災害の多発の一因ともなってきた。その一方で、現在の大学での地理学教育において、「微地形」を捉えるための基礎となる「微地形分類」の手法やその応用について果たしてどの程度の教育がなされているのであろうか?本シンポジウムでは、このような背景を受け、微地形を認識して行動することの重要性を再確認するとともに、微地形スケールで環境を捉えようとする視点や微地形分類の技術を教育・普及させるための方策と研究の方向性について、隣接分野や人間行動への応用を意識しつつ議論することを目的とする。本シンポジウムは、1.微地形と植生・土壌、2.微地形と災害、3.微地形と人間活動の3部構成で進行する。第1部では、微地形とそれに関わる自然環境について、まず微地形と植生の関係を議論し、次に両者を繋ぐ土壌環境について、特に土壌物理の視点から考察する。また、森林限界付近の微地形形成プロセスについても議論する。第2部では、斜面災害と微地形、考古遺跡からみた氾濫原の微地形と災害を議論するとともに、災害時の人間行動と微地形の関係についても考察する。第3部では、微地形と人間活動の関係について、里山および半乾燥地域の土地利用の視点から議論するとともに、人間活動における微地形認識について人文地理学的視点からも考察する。土地分類基本調査の「5万分の1地形分類図」や「治水地形分類図」は、空中写真判読による地形分類を基礎として作成された地図である。前者は旧国土庁(1974年までは経済企画庁、2001年からは国交省国土情報課)の管轄の下、「国土の開発、保全及び利用」といった広範な用途のために各都道府県が作成したものである。ただし、縮尺が5万分の1のため、平野部を除くと必ずしも微地形単位での地形分類とはなっていない。後者は国土地理院が主要河川の主として平野部を対象に作成したものである。縮尺が2.5万分の1のため、前者より詳細な情報を判読できる。また、近年の自然災害の多発と土地の安全性への関心の高まりを受け、国交省国土情報課では分散した災害履歴情報の集約と提供を目的に「土地履歴調査」を開始し、その中で前述の「地形分類図」の改定版とも言える「自然地形分類図」を整備しつつある。一方で、治水地形分類図の更新作業も進行している。このように、微地形分類は、近年特に、防災の場においてその重要性が増しつつある。「微地形」は生物多様性保全や地球環境保全においても重要な切り口となり得る。植生分布は微地形と密接な関係があり(菊池 2001)、人はその植生を利用して生活してきた。地理学の強みは様々な事象を空間的に体系化して捉えることができる点にある。これに加え、微地形と植生を繋ぐメカニズムについて、例えば生理生態学や土壌学などの隣接諸科学の視点や分析手法を取り入れることで、生物多様性保全や生物資源の持続的利用、さらには地球環境保全上重要な炭素固定機能評価などにも貢献し得る新たな研究展開を切り開くことも可能となろう。本シンポジウムが「微地形」の重要性の再確認と、新たな研究展開のきっかけとなることを期待したい。
抄録全体を表示
-
植草 昭教
セッションID: 822
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
千葉市美浜区に形成された幕張新都心は、1970年代後半から東京湾を埋め立て、造成した土地に整備された都市である。1989年、国際会議場とイベントホールからなる幕張メッセがオープンしたところから幕張新都心の歴史は始まった。現在では、幕張新都心の建設は完了に近づき、幕張新都市の空間をどのように利用していくかの段階に移行してきている。今後も魅力ある都市であり続けるために、どのように維持、管理され、そして利用されて行くのかなど、幕張新都心が形成、利用されていく中で、幕張新都心の機能と景観に関して見てみることにする。
幕張新都心は、「職・住・学・遊」が融合した未来型の国際都市を目指して展開している。JR京葉線海浜幕張駅を中心とし、ホテル、シネマコンプレックス、アウトレットモール、スーパーマーケットなどがある「タウンセンター」、幕張メッセとビジネスのエリアである「業務研究地区」、教育機関や研究機関が集まる「文教地区」、幕張ベイタウンなどの「住宅地区」、野球場(QVCマリンフィールド)などがある「公園緑地地区」イオンモール幕張新都心が開業した「拡大地区」、この6つの地区から構成されている。計画面積522.2ヘクタール、計画人口 就業人口約15万人 居住人口約3万6千人。街づくりの特徴は、先進的な都市システムの導入や環境デザインマニュアルによる都市環境の整備と、調和のとれた街づくりである。
埋立地に整備された幕張新都心は、2011年3月11日に発生した東日本大震災の液状化現象によって、景観などに配慮して整備された街並みが損壊してしまった。しかし約1年6か月後には復旧した。復旧に当たっては、幕張新都心は景観に配慮されて建設されているため、元通りに復旧させた。2012年10月1日幕張新都市は、千葉市の景観形成推進地区の第一号として指定(2013年4月1日施行)された。景観形成推進地区は、地域の特性を活かし、先導的景観形成を図る必要がある特定の地区と位置づけられる景観形成推進地区に指定されると、その区域に建設される建築物は、すべて届け出の対象となる。
幕張新都市は、「職・住・学・遊」の複合機能の集積む進み、就業者、就学者、居住者及び幕張新都心への来訪者を合わせ日々約14万7千人の人々が活動する街となっている。テレビショピングを行っているQVCが、QVCスクエアビル前の歩行者デッキに3Dアート(トリックアート)を期間限定で描いたことが、行き交う人々の話題となり、2013年度千葉市都市文化賞まちづくり部門の優秀賞を受賞している。このパフォーマンスは、遊び心のあるアート空間を演出した。また、幕張新都心を観光地として活用しようとの考えもある。成田空港に近く、ホテルがあり、幕張メッセでイベントも開催されている。2013年12月には、拡大地区にイオンモール幕張新都心が開業し、ショッピングが出来ることなど、幕張新都心の空間に国内外の観光客を呼び込もうとする。この他に、幕張新都心は、多くのテレビや映画、CMの撮影地として登場する。引き続き、マスメディアに取り上げられるような、都市の姿を表現し続けることが求められる。
幕張新都心は、建設から25年が経過し、都市の姿が完成に近づき、様々な都市機能も有してきている。また空間は景観に配慮され、デザイン性の高い建築物が建ち並ぶ。幕張新都心が、成熟段階へと移行する時期になり、今後も魅力ある都市であり続けるためには、良好な都市環境、景観形成の継続が必要であり、加えて幕張新都心の都市文化とも言えるような、都市空間を創出していくことが必要であろう。
抄録全体を表示
-
長谷川 裕彦, 山縣 耕太郎
セッションID: 603
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ボリビアアンデス,チャルキニ峰(5392m)西カールに分布する小氷期堆石内で実施した表層地質調査の結果について報告する。現地調査の結果から,調査地域内の表層地質は,氷河表面ティル・氷河底ティル・融氷流水堆積物の3群に大区分される。
抄録全体を表示
-
小坂 英輝, 三輪 敦志, 今泉 俊文, 稲垣 秀輝, 橋本 修一, 楮原 京子, 佐々木 亮道
セッションID: 631
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
大年寺山断層は長町-利府断層のバックスラストで仙台市街地を横切って明瞭な断層崖を形成している.筆者らは,防災上重要な活断層の位置・形態および古地震情報を得るために,工事に伴い出現した大年寺山断層の断層露頭とその周辺の断層地形の観察を行った.断層露頭の断層は,5-6万年前に形成された上町段丘の砂礫層がローム層の上に衝上するF1断層とF2断層の2条の逆断層である.F1断層は,その変位を復元することで,砂礫層堆積後に少なくとも2回活動していると推定される.単位変位量はF1断層の上下変位量(1.6 m)と活動履歴から約0.8mと見積もられる.上町段丘面上の撓曲崖の比高(5-6 m)は,両断層を合わせた変位量より大きいため,両断層以外に断層の存在が推定される.これらの結果から,大年寺山断層は,断層崖の中で複数に分岐し,地表付近まで段差を生じる断層である.仮に同断層が活動すれば,横断する構造物に深刻な損壊が生じ,関連する災害も懸念される.このため,ライフライン構造物の配置計画,設計・施工に際しては,その種類や重要度に応じた十分な検討が必要になるものと考えられる.
抄録全体を表示
-
手代木 功基, 内田 諭, 真常 仁志, 田中 樹
セッションID: 516
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
はじめにギョウギシバ(
Cynodon dactylon)は,寒帯を除く世界の広範な地域に分布するイネ科多年生植物で,日本においても広く生育する種である.ギョウギシバは飼料作物や芝生にも活用されるとともに,砂漠化が進む地域において緑化を目的に導入されることもある.一方で,耕作地においては雑草とみなされ,各地で問題とされて駆除の対象となってきた.
ナミビア共和国の北中部では,農牧民オヴァンボが天水に依存した農業を行っている.この地域において,近年ギョウギシバが耕作地に侵入しているのが報告されている.しかしながら,特に天水に依存した耕作を行う乾燥地において,ギョウギシバがどのように分布し,農業にどういった影響を与えているのかといった実態は明らかになっていない.
そこで本研究では,特にギョウギシバの耕作地内における分布を明らかにすることを通して,地域の主食作物であるトウジンビエ栽培との関係を検討する.
方法調査地はナミビア共和国北中部,オシコト州のO村である.O村はエトーシャ・パンの北縁に位置し,傾斜が少ない平坦な地形を呈する.年間の降水量は400mm程度で年較差が大きい.村内には70世帯が散村形態で暮らしている.彼らは家畜を飼養するとともに,トウジンビエやモロコシ,豆類などを混作している.
現地調査は2013年4~5月,及び9月~11月に実施した.O村の全世帯を対象に聞き取り調査を実施し,農耕の現状やギョウギシバの影響を把握した.また,耕作地におけるギョウギシバの分布をGPSを用いて測定した.さらに衛星画像(WorldView2: 2011年8月16日および2011年9月15日撮影)の解析を行って各世帯の敷地面積等を算出し,それらをもとに分布の特徴を把握した.
結果と考察ギョウギシバはO村の70世帯中,44世帯の耕作地に分布していた.耕作地内にギョウギシバが存在すると,その場所ではトウジンビエや他の野菜類などは生育が悪くなると人々は話していた.そのため,人々はギョウギシバが生育する場所では耕起を行っていなかった.また,ギョウギシバが存在している場所をトラクターで耕起すると,地下茎が散乱し,それにともなってギョウギシバの分布が拡大しているといった問題も発生していた.さらに,年々耕作地においてギョウギシバの分布が拡大し,土地の半分以上がギョウギシバによって占められている事例もみられた.
ギョウギシバは耕作地の地理的な位置関係によって分布に偏りがみられ,特に村の西側と東側に分布していた.村の中央部に位置する世帯においては,分布が少なく,ギョウギシバの分布は微地形に影響されていると考えられる.耕作地内のミクロな分布も世帯によって異なっており,特にトラクターで耕起する世帯においては,地下茎の拡散によると思われるモザイク状の分布が確認された.
これに対し人々は様々な対策を講じていたが,ギョウギシバは一旦生育すると完全に駆除することが困難であり,有効な対応策を見いだせていなかった.今後は分布の原因等についてさらに調査を行い,具体的な抑制や駆除の方策を考えていく必要がある.
抄録全体を表示
-
阿子島 功, 門叶 冬樹, 加藤 和浩
セッションID: 903
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ペルー南部の海岸沙漠であるナスカ盆地の古気候変化の指標として、盆地周辺のカタツムリ遺骸の年代と高度、現世のカタツムリの生息環境を検討してきた。先行研究はMachtle,B.
et al.(2006)によるナスカ盆地北方パルパ地区の2点の報告がある。阿子島(2011)は2点,阿子島ほか(2012a,b)は13点、本報告で14点を追加して計31点の年代―高度関係から古環境を論ずる。
現世のカタツムリの下限高度は約1300m付近であるが、ナスカ盆地西南部の高度750mに約1万年前の遺骸を発見し、ナスカ地区で完新世初期に相対的湿潤期があったことを確認した。
[問題点の所在] 1.ナスカ文化(BC200—AD700年)の盛衰の原因として古環境変化が予想されてきたが直接的な証拠はない。盆地の中には高度300~500m前後の台地とこれに数100~数10m刻みこんだ谷底面がある。ナスカ文化を支えたのは谷底面のリバー・オアシスと呼ばれる耕地であり、耕地を涵養する水は高度4,000mのアンデス山脈西斜面からもたらされた。よって高度4,000m~500mの間の斜面における乾燥帯上限の変動、植生や降水量の復元が課題となる。
2. Machtle
et al. (2006),Eitel and Machtle(2008),Machtle and Eitel(2013)は、ナスカ盆地の北約20kmのパルパ地区の山地斜面の風成細砂層とその下部に含まれる陸成巻貝2点の年代(1.1万年前および現世)と高度を記載し、湿潤期に植被のために風成層が固定されたと考えた。さらに遺跡の分布、段丘堆積層中の洪水堆積期などの材料を加えて、次のような古環境変化を想定した;完新世前中期からBC4,000年までは湿潤,ナスカ期(BC200~AD800)には乾燥化がすすんで文化が滅んだ。AD1100年から1400年(後期中間期)は相対的湿潤期,インカ期および17-19世紀は乾燥化した。
再検討の結果“陸生巻貝から示唆される環境”とは、先行研究で想定された草原ではなく、サボテンが点在する岩屑斜面である。風成砂層があるとカタツムリは生息しにくい。むしろ完新世前期以降の乾燥化が風成層の供給を増加させた可能性がある(阿子島2011、阿子島ほか2012a,b)。
〔想定される古気候変化〕31点のカタツムリの年代―高度関係から;約1万年前は現在よりも湿潤、ナスカ期は不明。約1000年前以降の後期期中間期は現在よりやや湿潤もしくは同程度である。湿潤であっても天水のみにたよる耕作では不十分で(天水を一時貯留する耕作は現在も一部試みられているが)主要な耕作法とはならない(阿子島2010)。
文献 1) Machtle,B.
et al.(2006)Z. Geomorph 142,pp.47-62 2)Eitel,B.and Machtle, B.(2008)New Technologies for Archeology,Springer, pp.17-38 3) Machtle and Eitel(2013)Catena 103,pp.62-73 4) 阿子島 (2010)季刊地理学,62, pp.222-244 5) 阿子島(2011)日本地理学会春季大会予稿集 6) 阿子島ほか(2012a)日本地理学会春季大会 7) 同(2012b)東北地理学会春季大会
抄録全体を表示
-
黒田 圭介, 黒木 貴一, 磯 望, 宗 建郎, 後藤 健介
セッションID: P022
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
Ⅰ.はじめに 地理情報システム(GIS)の普及により,デジタル化した空中写真を人工衛星データと同じ取り扱いで最尤法により半自動的に分類項目ごとに分類し,土地被覆分類図を作成することは容易になってきた。この空中写真に人工衛星データの近赤外域の波長帯データ画像をGISで合成した画像を用いて最尤法分類すると,高解像度で誤分類の少ない分類図が作成できる(例えば黒田ほか,2013)
1)。しかし,数ある人工衛星データのどれを合成するのが適当か検討した研究は少ない。地理学的な解析がパソコン上で行われることが多くなった今日において,デジタル化空中写真の利活用方法について検討することは有意義であると考えられる。そこで本研究では,空中写真に合成する人工衛星データ選択への一助となるよう,空中写真と人工衛星データの組み合わせの検討を行い,分類精度評価を行った。本研究では,LANDSAT/MSS,LANDSAT/ETM,ASTER/VNIR,ALOS/AVNIR-2の近赤外域データを空中写真に合成し,それぞれについて分類精度の計算を行った。
Ⅱ.研究方法 解析に用いたGISソフトは,ArcView9.2である。最尤法分類は,ArcView9.2のエクステンション,Spatial Analysisの「最尤法分類」で行った。分類精度は,最尤法分類に使用しなかったポリゴン形式の教師データを重ねあわせ,その教師データ内の分類結果面積をGISで抽出することで評価した。本研究で精度評価に使用した人工衛星データは以下の通りである。なお,研究対象地域としたのは,熊本市白川流域,宮崎県大淀川流域,大分県大分川流域,そして福岡県福岡市東部である。 1)LANDSAT/MSSについては,1978年観測の白川流域を対象とし,近赤外域相当のBAND7を1975年撮影の空中写真に合成した。2)LANDSAT/ETMについては,2004年観測の大淀川流域を対象とし,近赤外域相当のBAND4を2005年撮影の空中写真に合成した。3) ASTER/VNIRについては,2007年観測の大分川流域を対象とし,近赤外域相当のBAND3を2007年撮影の空中写真に合成した。4) ALOS/AVNIR-2については,2008年観測の白川を対象とし,近赤外域相当のBAND4を2007年撮影の空中写真に合成した。
Ⅲ.分類精度 表1に,平均分類精度を,図1に土地被覆分類図の例として,福岡市東部の土地被覆分類図を示す。分類項目は,水域,市街地(宅地や道路),草地(水田含む),裸地(畑含む),樹林地である。ただし,白川はこれに竹林が加わり,福岡市東部は竹林が加わり,市街地については住宅地と道路,樹林地は針葉樹林と広葉樹林に分けて分類した。 白川を見てみると,LANDSAT/MSSを合成したものは11.1%,ALOS/AVNIR-2では5.3%,大淀川では,LANDSAT/ETMを合成したものは+14.2%,大分川では,ASTER/VNIRを合成したものは+7.4%,福岡市東部ではLANDSAT/ETMを合成したものでは+5%の精度向上が見られた。また,福岡市東部の土地被覆分類図を見てみると(図1),草地が水域に誤分類される例が多く見られたが,LANDSAT/ETMを合成することにより,その誤分類がほぼ解消された。白川,大淀川,大分川においても,水域の誤分類が多く解消された。水域は可視域より波長の長い近赤外域では反射率がほぼ0になるため,教師データとして取得した地点の水域の画素クラスの分布パターンが他の分類項目のそれと明瞭に異なる。よって,人工衛星データをコンポジットした空中写真で最尤法分類を行うことにより,水域の他の分類項目への誤分類が少なくなると考えられる。LANDSATは解像度が高くない(MSSは解像度83m,ETMは同33m)が,ALOS/AVNIR-2(同10m),ASTE/VNIR(同15m)と比べて遜色のなく精度向上に寄与している。LANDSATは多くのデータが無償で入手できるため,今後利活用が期待できる。
参考文献:1) 黒田圭介ほか(2013):ALOS近赤外域(BAND4)画像合成空中写真を用いた土地被覆分類-2012年九州北部豪雨による白川浸水範囲を例に.2013年秋季学術大会日本地理学会発表要旨集,84,p129.
抄録全体を表示
-
3次元景観データとの統合アプローチ
杉本 興運
セッションID: P048
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
GISを応用した観光レクリエーション空間の合理的な計画•管理技法における主要題目として, 景観資源の評価や魅力度推定(visual resource assessment and modeling)の研究が発展してきた(Chhetri and Arrowsmith, 2008).近年では空間管理におけるより有効性の高いアプローチとして,来訪者の現実空間(景観)に対する印象評価を景観の物理的変数と統合し,算出される場所ごとの魅力度をGISによって可視化するという方法が行われるようになった(Chhetri and Arrowsmith, 2008).こうした研究は主に自然観光地等におけるマクロスケールでの評価を想定しており,小領域あるいは複雑な空間設計を有した観光レクレーション空間の評価には適さない.これに対し,Sugimoto(2013)は,来訪者の関心生起地点(写真撮影地点)を空間情報として取得し,分析することで,ミクロスケールでの詳細な空間評価を可能にした.また,関心対象への視線の集積を,対象地域を覆うグリッドメッシュ間の関心生起数の流動データとして表現し,発地の関心発生数と着地の関心吸収数およびグリッド間距離を説明変数として空間的相互作用モデルを適用することで,視距離が関心生起に与える影響を定量的に分析した.しかし,要因分析が主体であったため,モデル精度の検証に関しては不十分であり,関心生起からみた空間の魅力度推定モデルとしての適用可能性に関しては言及されていない.本研究では,この関心生起の流動予測モデルのさらなる精緻化と予測分布の空間的可視化を行う.この過程において,対象地の3次元データを新たに活用し,物理的な景観特性に関する数値情報を関心生起の分析と組み合わせることで,人間の心理的側面と対象地景観の物理的側面とを統合した空間評価のさらなる可能性を提示する.
研究対象地は都立日比谷公園である.庭園•公園は都市の重要な人文観光資源として位置づけられており,当該公園は国の観光資源評価ランクで高く評価されている.日比谷公園とその周辺の物理的な景観特性を把握するために,2m間隔の3次元データ(DSMとDTM)と建物や水系のポリゴンデータを使用し,3次元データを樹木,建物,水系の景観要素ごとに分離し,それぞれを立体的に重ね合わせて基本的な景観構造を解析した.そこで得られたデータを,杉本(2013)の研究で検討した,関心生起の流動パターンを予測するためのポアソン/負の二項重力モデルに新たな説明変数として組み込み,係数値を最尤法によって推定した.また,説明変数の組み合わせから複数のモデルを構築し,適合度や実測値と予測値の誤差を比較した.最後に,得られた関心生起の流動分布を,GoogleEarthあるいはArcGISで作成した2次元や3次元の景観モデルの上で可視化し,平面と立体の側面から対象地景観と観光者の関心生起との関係を調べた.
分析の結果,グリッド間距離,関心発生数,関心吸収数だけを説明変数としたモデルでも予測精度は比較高かった.しかし,見晴らしの良い丘や池の周囲といった,局地的なスポット特性の影響で関心生起を上手く予測できない箇所があった.そこで,特定の景観要素の存在を明示的に変数に取り入れたモデルを構築した結果,予測モデルの精度向上がみられた.さらに,利便性を考慮し,2つ目のモデルから算出に手間のかかる関心吸収数を除外したモデルを構築した結果,予測精度は前2つに比べて下がったが,比較的有用性の高い状態を維持していた.
Chhetri, P, and Arrowsmith, C. 2008. GIS-based modelling of recreational potential of nature-based tourist destinations.
Tourism Geographies, 10, 233–257.
Sugimoto, K. 2013. Quantitative measurement of visitors’ reactions to the settings in urban parks: Spatial and temporal analysis of photographs.
Landscape and Urban Planning, 110: 59-63.
杉本興運. 2013. 関心線の空間情報取得と関心生起条件の空間的相互作用モデルによる分析. CSIS DAYS 2013 全国共同利用研究発表会研究アブストラクト集, 49.
抄録全体を表示
-
青野 靖之, 村上 なつき
セッションID: 209
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
極端な暖冬後と厳冬後に見られた日本におけるソメイヨシノの開花状況を比較し、気温を用いた解析を通して両者の特徴を検討した。2007年(極端な暖冬後)のいわゆる桜前線(開花初日の等開花季節線)は、温暖な九州で南下し、また西日本で比較的緩慢に移動していた。2013年(厳冬後)は、西日本の標高の低い地域で、過去数十年中最も早く、なおかつほぼ一斉に開花した。ただし4月に気温が低めに推移したことから東北地方での桜前線の移動は緩慢となった。両年の開花までに必要となった気温の指数の積算値を地点ごとに求めて比較した。東北地方では両年に差が見られなかったが、暖かい地方ほど暖冬後の方が厳冬後よりも開花までに多くの積算値を必要としていた。この現象は、暖かい地方ほど自発休眠覚醒の早晩の年次間差が、ソメイヨシノの開花時期を左右する要因となっていることを示唆している。
抄録全体を表示
-
淡野 寧彦
セッションID: P064
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに
いずみや(丸ずし)は,愛媛県に根付く郷土食の1つであり,アジやサワラ,イワシなどの魚とオカラを主原料とする。大きさや形状は,握り寿司とほぼ同じであり(写真参照),1個あたりの価格は50~100円ほどである。このようにいずみや(丸ずし)は,大きさ・価格等の面でも,手軽に食べることのできる食品であり,多くの人々に受け入れられやすいものである。また栄養面でも,良質なタンパク質や食物繊維を豊富に摂取することができる。本研究では,愛媛県におけるいずみや(丸ずし)の生産・販売実態の解明と,消費者の認知・消費度合の把握から,いずみやの食文化が空間的にどのように受容されているのかを明らかにすることを目的とする。これにより,地域の食文化の一形態を明らかにできるとともに,第1次産業等の地域産業との関連性についても分析できることが見込まれる。
2.いずみや(丸ずし)の認知度
愛媛県の郷土食を取り上げた既存の文献等によると,新居浜市近辺では「いずみや」の名称が,県南部の南予地方では「丸ずし」の名称が,それぞれ用いられる(土井中,2004)。また農山漁村文化協会編(2006)によれば,宇和島市の丸ずしは,1760年代に四国遍路を巡る旅人によって伝えられたとされ,地域で水揚げされるイワシなどが食材に用いられた。一方,松山市近辺では,祝事の際にいずみやが供されたとされる。県内の各市町に設置される食生活改善推進協議会が公表する情報では,松山市および新居浜市がいずみやの,宇和島市が丸ずしの,それぞれレシピをHP上で公開している。また,大洲市および内子町の「食育推進計画」において,郷土食の1つとしていずれも丸ずしが挙げられていた。 また,愛媛県内の大学生約500名に対していずみや(丸ずし)の認知調査を行った結果,愛媛県出身者245名のうち,46名(18.8%)がいずみや(丸ずし)を知っていたが,食べる機会や頻度はごく限られていた。
3.愛媛県におけるいずみや(丸ずし)の生産・販売状況
現在のいずみや(丸ずし)の生産・消費形態を把握するために,食品スーパーや惣菜店,飲食店などを訪れ,その販売有無,販売時の名称,価格,大きさや形状,製造者(企業)などを調査した。さらに製造者(企業)に対して聞き取り調査を行い,いずみやの製法,生産の歴史,年間生産数および売上,原料調達の方法,出荷先などに関する情報を得た。これらについては,発表当日に詳細を述べる。
4.いずみや(丸ずし)の地域資源化に向けて
いずみや(丸ずし)は,現在も愛媛県においてある程度受容されていることが明らかとなったが,若年層になるほど消費は少なくなる傾向にある。本研究では,今後,いずみや(丸ずし)の定着・存在状況を把握するだけにとどまらず,文化的,経済的,そして栄養学的視点から,いずみやの地域資源としての重要性および活用可能性を検討することを目標としている。そのために,医学分野の研究者(管理栄養士資格および博士(医学))と連携した学際研究として発展させる予定である。
【参考文献】
土井中 照 2004.『愛媛たべものの秘密』アトラス出版.
農山漁村文化協会編 2006.『伝承写真館 日本の食文化10 四国』農山漁村文化協会.
抄録全体を表示
-
その概要と保存・修復
長谷川 均, 後藤 智哉, 東郷 正美, マホムッド アル カァリオティ
セッションID: 639
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
ヨルダンにおいて、放置された1950年代初頭に撮影された大量の空中写真を見出した。この写真を保存と修復し利用と活用した。ヨルダン川流域ではイスラエル、ヨルダン川西岸地域、ヨルダンともに開発が進み灌漑による一大農作物生産地と化し大規模な地形改変が進行している。現在の空中写真ではオリジナルな地形を捉えることは不可能な状況である。従って1940から50年代の空中写真を使った地形判読,景観の復元は非常に価値が高い.また、プレート境界に位置するにもかかわらず、均質的な変動地形の把握は行われていないので、本研究によって防災科学や防災施策に対する多大な貢献が期待できる。
抄録全体を表示
-
長谷川 均, 磯谷 達宏, 小野 勇
セッションID: P034
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
GPS制御で飛行する自律型UAVを用いれば,任意の時刻に,同一飛行ルートで繰り返し高解像空中写真を取得できる.この点において,環境計測や反復調査を必要とする分野でUAVを使用する大きなメリットがある.本研究では,UAVを使い高度50~100mで撮影したサンゴ礁浅海域,マングローブ湿地,河川敷の植生,断層トレンチサイトの空中写真,フルHD動画などの近接リモートセンシング画像を得た.自律型UAVを使った空中写真は次のような利点を持つ.撮影計画時に地理座標を入力できるので,同一地点の反復飛行(反復調査)が可能である.地理座標付きの超高解像写真の取得が可能で,長期モニタリングに最適である.搭載機器の交換で,近赤外画像,フルHD動画,レーダー画像(小型化が必須)の取得が可能である.曇天時に撮影すれば水面からのハレーションなどの無い写真が得られる。また、一定の光量下での写真を得ることができる.
抄録全体を表示
-
ZUSに秘する権力のスキーム
能代 透
セッションID: 502
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
I はじめに
本研究はフランスのZUS(都市優先対策地区)空間の政策を批判的に論じるものである。 フランスの都市郊外での移民系若者と治安部隊との衝突とが「フランスのZUS政策」と深くかかわっている。 その底流に、ムスリム移民と向き合う「ポストコロニアリズム」と国民不可分性(単一性)を憲法に掲げる「共和制国民国家」と、それを揺るがせ多文化主義を促す「EU統合」の動きがあり、その狭間で「トリレンマ(矛盾)」を抱えるフランス共和国のリアリティを都市空間の側面から研究した。
II フランス郊外(バンリュー)
郊外(バンリュー)はその特徴により言葉以上に特別の意味をもつ。 かつての城壁都市の周辺地帯に位置しており、フランス特有の経緯による都市構造を形成している。第二次大戦後の復興期の労働者用に1950年代後半から、グラン・アンサンブル計画で郊外に低家賃社会住宅(HLM)の高層住宅団地(通称シテ)群が均衡都市郊外に政策で大量建設された。しかし、交通網、商店街、企業誘致などの街づくりが伴わなかったため都心部(旧城壁内)から隔離され、シテは低所得者層が集住するようになった。 さらに1980年代から脱工業化で、工場閉鎖、大量失業者、産業空洞化が始まり、次第にマグレブ系労働移民者階級が集住する空間となり、年を経て多様性を失い、ホスト社会の差別とセグリゲーションを受けるマグレブ移民二世が集住し、イスラム教義に基づくコングリゲーション(防衛・互助・文化維持・抵抗)が進行し、ジハード(ムスリムの防衛戦)に向かうマグマが増殖する空間となった。 ヨーロッパ最大のムスリム居住国である現在のフランスにおいて、それは「共和制理念とイスラム教義」の観念の対立となり、都市の「危険な均衡」をもたらせている。
III 監視・防諜の装置としてのZUS
1995年、アルジェリア系「武装イスラム集団」が関与したとされる爆弾テロが、リヨンやパリで続発していた。 フランスに「同化」していたはずの移民二世が、この組織に加わっていたことが分かり、フランス社会に大きな衝撃を与えた。 マグレブ移民が集住する「郊外」は、イスラム過激派の温床とされ、フランス政府は1996年に都市再活性化協定法で国家権力が自治体との契約統治を超えて、各都市で直接介入できる特定区(ZUS)を郊外(バンリュー)のシテを重点的に指定した。ZUSは表向きには貧困地区対策であるが、監視・防諜装置として誕生し機能した。 そのことは入手したにフランス諜報研究センター(CF2R)の2005年9月付報告書で明らかにされた。
1) それによると、「フランス国内の630カ所の郊外地区(ZUS)の180万人の住民が、移民としての出自の文化や社会と強く結び付き、イスラム過激派が郊外の若者たちの組織化が進み、フランス社会に分裂の危機をもたらす危険性が高まっている」との報告がフランスの防諜機関である中央情報局(RG)から内務省に上がっていた。 これはZUSをムスリムの監視と防諜の装置としていた「証拠」である。 2005年10月、パリ郊外のクリシー・ス・ボアの団地で移民系少年と警官に衝突事件が発生した。 その後にボスケ地区のモスクで抗議集会中のムスリムたちに治安部隊が催涙弾を打ち込んだため、衝突が一気に拡大した。 彼らの精神と結束の拠り所であるモスクへの攻撃を彼らが許すことはなく、権力の治安部隊との衝突がフランス全土に広がった。
IV おわりに
現在のフランスは、約500万人のムスリムが暮らしているが、彼らの「外に見える行為」を実践するイスラム信仰は、フランス共和国の世俗主義の観念になじまない。 移民二世・三世の重層的な空間への帰属意識がアイデンティティの不安定化を招き、フランスで生まれた移民子孫たちが差別を受ける中でイスラムに覚醒していく。 政府がその実態を把握しようとしてもフランスの国民不可分性の理念から一部集団への表立った調査ができず、中央情報局による防諜活動を必要とした。取り上げたZUSは日本でも差別・貧困・荒廃の社会問題として注目されることが多く研究も多いが、本研究ではそのZUSに関する政策・制度をフランス均衡都市の地理学的構造に着目して研究した。
注
1) Centre Francais de Recherche sur le Renseignment、Eric Denécé
LE DÉVELOPPEMENT DE L’ISALAM FONDAMENTALISTE EN FRANCE, ASPECT SÉCURITAIRES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX Rapport de recherché No.1 Septembre 2005, P7-9 「LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L’ISLAM RADICAL DANS LES BANLIEUES FRANCAISES、
抄録全体を表示
-
渡邊 達也, 松岡 憲知
セッションID: 607
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに 北極ツンドラ地帯の地表面には大小様々な模様で縁取られる構造土が広く分布しており,土質表層土からなる平坦面では主に不淘汰円形土(マッドボイル,ハンモック)と不淘汰多角形土がみられる.マッドボイルとハンモックはいずれも不等凍上や塊状変位,凍結圧などが成因として挙げられており,同じ成因から異なる形状が形作られるとも考えられている.一方,不淘汰多角形土は小型(径1 m以下)が乾燥クラック起源,大型(径5 m以上)が凍結クラック起源という見解でほぼ一致しているが,中型(径1~5 m)の成因に関しては十分な見解が示されていない.北極圏スピッツベルゲン島中央部のアドベントダーレン地域では,旧扇状地という狭い範囲内にマッドボイル,ハンモック,複合型構造土(中型多角形土の中心部にマッドボイルを伴う),氷楔(大型)多角形土の4種の異なる不淘汰構造土が分布している.本研究では,それぞれの構造土の地盤・環境条件や表層土の変位特性の比較をもとに,同じ気候条件下で異なる形態の構造土が生じる原因について考察した.
2. 地盤・環境条件の比較 調査地に選定した旧扇状地の約700 m四方の範囲内に4種類の構造土が分布する.マッドボイルは調査区域の上流部~中流部に,複合型構造土は中央部に分布する.空中写真判読と地形測量に基づくと,マッドボイル分布域は旧河道,複合型構造土分布域は砂州の範囲に対応する.マッドボイル分布域は粘土質シルトの沖積堆積物からなる.一方,複合型構造土分布域では,中心のマッドボイル部分は沖積堆積物,縁辺の中型多角形土部分は砂質シルトの風成レスで構成されており,粒土組成のコントラストが大きい.ハンモックは低湿地帯に分布しており,土壌水分が高く,積雪深も厚い.湿潤な条件を反映して,表層は腐植土で覆われる.氷楔多角形土は扇状地末端部に分布しており,レスの供給源となる主流の網状河川に近いため風成レスが厚く堆積する.また,局所的な地形,風速の違いにより積雪深が非常に薄いため,他の構造土分布域よりも冬季地温が低く,凍結クラックが起こりやすい条件下にある.このように場の条件の違いによって,表層土の粒土組成,土壌水分,積雪深が異なるため,結果として多様な構造土が狭い範囲に分布している.
3.表層土の変位特性
マッドボイルでは,植生を欠く中央部と植生で覆われた縁辺部間で明瞭な差別凍上がみられた.最大凍上量はマッドボイルの中心部で10~15 cm,縁辺部でせいぜい5 cm程度である.一方,ハンモックでの最大凍上量は約11 cmに達したものの,マウンド部分と周囲の凹地部分とで差別凍上はみられなかった.しかし,融解期にマウンド部分が凹地部分よりもゆっくりと沈下する動きがみられたことから,マウンド内部の根系の抵抗力により不等沈下がマウンド形状の維持に寄与していることが推察される.マウンド内部が腐植土で充填されていること,マウンド上に植生が密に繁茂することから,植生分布の不均一性がハンモック形成の一因と考えられる.
中型多角形土を縁取る地表クラックの水平変位を観測した結果,クラック幅は凍結進行期に縮小し,融解期に拡大する季節周期性の変形パターンが認められた.自動インターバルカメラにより取得した画像データでは,マッドボイル中心部での差別凍上・沈下に対応するように縁辺部の地表クラックが収縮・拡大する動きが捉えられた.これらの結果から,調査地に分布する複合型構造土は,マッドボイルの差別凍上による体積膨張収縮の繰り返しにより,縁辺部へ水平方向の圧縮・収縮が繰り返され,不規則な地表クラックを伴う中型多角形土の形態が形作られたものと考えられる.
液性・塑性限界試験を行った結果,中型多角形土を伴わないマッドボイル分布域では,マッドボイル縁辺部の表層土は沖積起源のため粘土含有量がやや高く塑性を示した.一方,複合型構造土分布域では,中型多角形土部分の表層土はレス起源のため粘土含有量が低く非塑性を示した.このような土質の違いが,構造土の形態に違いを生じさせているものと考えられる.
融解期の体積収縮により不淘汰多角形土を縁取る地表クラックが拡大するという考えは,20世紀前半に提案されていたが,検証不足から支持されてこなかった.本研究では,地盤条件次第でこのプロセスが起こりうることが示された.
抄録全体を表示
-
森田 匡俊, 小林 哲郎, 小池 則満
セッションID: 121
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
本研究では,集団での津波避難行動に関するGPSを用いた調査分析手法の提案を行い,津波からのより良い避難行動を考えるための一助となることを目的とする.具体的には,小学生のクラス単位での避難行動を対象とし,クラスの先頭と最後尾をGPSによって計測,さらに同時刻の先頭と最後尾を結ぶ線オブジェクトを時系列に沿って作成することで,クラス単位という集団での避難行動を検討する指標として用いることを試みる.
抄録全体を表示
-
川久保 篤志
セッションID: 404
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
1.はじめに
人口減少社会に突入したといわれる現在、グローバル化の進展に伴う国内産業の空洞化や財政赤字の深刻化によって、山間地域では製造業の立地や公共事業などが目に見えて減少し、1990年代後半には大都市圏との格差が一層拡大するようになった。そのような中、農山村地域では地域資源の持続的活用による地域振興事業が盛んに行われるようになり、6次産業化や農商工連携が地域存続の切り札として期待されるようになった。本発表で取り上げる鳥取県大山町でも、広域合併を機に農林水産業と観光業を柱とした地域振興計画「大山恵みの里計画」が立案され、両者が有機的に結合して相乗効果を上げることが目指された。そこで本発表では、上記計画が本格化して5年を経た現在、どのような成果と課題があるのか若干の考察を行う。
2.大山町の地域特性と食と観光を柱とした地域振興
1)地域概要大山町は、鳥取県西部に位置する人口約1.7万人の町で、2005年に西伯郡内の3町(大山町・名和町・中山町)が合併して誕生した。町域は中国地方最高峰の大山(1,729m)の北斜面に広がり、山岳地域は登山やスキー客を集める一大観光地となっている。また、山麓地域では約30年の歳月をかけた国営パイロット事業(385ha)が実施され、梨・ネギ・ブロッコリーの集団産地が形成されてきた。
2)山麓地域における「食」関連事業の展開 上記計画で「食」関連事業を担っているのは第3セクターの「大山恵みの里公社」である。この公社は、町内の1次産品・特産品・加工品の販売強化と雇用創出をめざし、①「大山」ブランド産品の開発と認証、②ネット通販などマーケティングの支援、③創業・新規参入の支援など人材育成、④販売拠点ともなる総合交流拠点の管理運営、の4事業を展開している。これらの事業の中で先行し、かつ最も実績が上がっているのが④に該当する「道の駅」の運営で、創業以来2000万円以上の収益を出している。しかし、他の3事業については未だ成果が乏しく、公社全体では赤字経営が続いている。
3)山岳地域における観光業の振興 山岳地域における観光業の中心はスキー場経営である。しかし、スキー場の集客は1990年代末以降は激減し、宿泊施設をはじめとする商業やサービス業の衰退が目立ってきた。そこで、大山観光局では夏期も含めた周年的な集客を増加させようと、近年、様々なイベントや周遊プランを提示すると同時に2013年秋には温泉施設を開業した。また、2011年以降は積雪にも恵まれ、客層の変化に対応したスキー場の取り組みもあり、スキー客は回復基調にある。しかし、これらの動きは必ずしも滞在時間の長さには結びついておらず、地元の「食」を観光資源として活かす試みも少ないのが現状である。
抄録全体を表示
-
倉茂 好匡, 中野 利昭
セッションID: P014
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
滋賀県彦根市の琵琶湖岸では南西向きの沿岸流が卓越しており,湖岸には浜堤が発達している.このため,琵琶湖に流入する小河川の河口は閉塞しやすく,河口部では湛水することが多い.北川もそのような小河川のひとつである.また,江戸時代から続く古い集落の多くはこの浜堤上に位置している.大藪は浜堤上に位置する集落のひとつである.そして,大藪集落のすぐ北側を流れる北川では,浜堤を横切る河口部に人工的な蛇行流路が作られている.ところが,滋賀県や彦根市の公的機関にはこの人工流路工事記録が残されていない.航空写真判読および地元住民への聞き取り調査の結果,この人工流路は1981年よりかつての流路を掘削したものであることが判明した.地元住民は,この工事をおこなうよう彦根市に陳情し,年度末予算を融通していただいて工事を進行させたとのことである.このころ大藪の住民は,特に夏季に北川河口部に湛水する水の悪臭に悩まされていた.なぜなら,大藪集落の南側に1970年代後半から建設されたニュータウンの生活雑排水が未処理のまま北川に流れ込んでいたからである.そのため,流路面積を小さくするべく流路を掘削した.その際,すこしでも景観を良くすべく,蛇行流路にし,護岸を松材で覆うなどの工夫をした.なお,大藪周辺では2003年までに下水道網が完備され,現在はこのような悪臭は発生していない.現在の北川河口部には1982年以降に堆積した泥質の堆積物が存在している.そして,2003年以前に堆積した堆積物は水質悪化条件下で,またそれ以降の堆積物は水質の改善した環境下で堆積したはずである.すなわち,この堆積物内には水質変化の履歴が残っていると考えられる.本研究では,北川河口部で堆積物柱状試料を採取し,ここから年代復元のための指標(可能なら年層となる指標)を探すとともに,堆積物中に残留している化学物質を分析することで,水質変化履歴を復元することを目的とする. 北川河口域で堆積物の柱状試料を採取した.堆積物はほとんどがシルト以下の物質で占められているが,ところどころの層準に粗砂から細礫に相当する粒径のものが挟まれている.ところが,河口域より上流では北川はコンクリート3面張であり,周囲に粗砂~細礫の供給源となるものは見当たらない.一方,河口を閉塞している堆積物は粗砂~細礫で構成されている.以上より,柱状試料中の粗砂~細礫は,台風等で風波の激しいときに河口閉塞部より逆流してきたものと判断した.また,表層より深さ23 cmまでには,枯葉の茎等の集積している層を19層確認できた.これらは,秋の落葉期に枯葉が河床に堆積し,その葉身の大部分は夏季に水生昆虫等による捕食等で分解・攪乱され,その結果として葉脈や葉柄部分のみが残留したものと考えている.すなわち,この茎の集積層は年層として利用できる可能性が高い.現在,堆積物試料中に残存している化学物質分析から水質変化履歴を復元する試みを行っている.その第1歩として堆積物中に含まれる全リンの分析を行った.その結果,堆積物下部から上部に向けて,堆積物中全リン濃度が増加する傾向が見られた.一方,彦根市が1980年代から北川河口域で行った河川水質データを見ると,北川流域で下水道網が建設された1990年代後半より河川水中全リン濃度が激減した.すなわち,堆積物中の全リン濃度の変化傾向は河川水中の全リン濃度変化傾向と調和的ではない.堆積物中全リン濃度から過去の水質変化を推定するには,堆積物に吸着したリンの堆積後の動態を解明する必要がある.
抄録全体を表示
-
―函館市・J-バス運行を事例に―
上野山 隆一, 山田 圭寿
セッションID: S0803
発行日: 2014年
公開日: 2014/03/31
会議録・要旨集
フリー
函館市陣川地区は,函館駅,五稜郭地区などを中心とする市街地北端の丘陵地に位置する市街化調整地域である.陣川地区のなかでも,陣川あさひ町会が組織される地域は,周囲を原野,山林などに囲まれた,とくに孤立した集落であるが,人口は約3,000人を擁する.この地域はバブル期,都市計画のいわゆる白地地域だった頃に開発が進んだが,その後,線引きの変更によって市街化調整区域になったため,周辺地域や近隣の市街地から孤立した集落となった.現在,当該地域では“既存宅地50戸連担”の枠組みによって,造成,建造が可能である.このため地域内には,行政施設や学校,病院,金融機関などは存在せず,商業施設として大手チェーン系のコンビニエンスストアが1店存在するのみである.このため,地域内で生活するうえで,運転免許および自家用車の保有は必須であり,また丘陵地に位置し,冬期間は積雪の影響により,自転車の利用には困難を伴う.一方で地域内の世代構成は,周辺地域に比べ大きな偏りがなく,若年層から高齢者まで,万遍なく分布する.この地域における既存の公共交通サービスは,函館バスによって運行される6‐2系統(函館バスセンター~函館駅前~五稜郭~上陣川)のみである.この路線は1996年,地域の強い要望によって開設された路線であるが,これ以前,公共交通は全く存在しなかった.市街地からこの地域に至る道路の整備が遅れており,バスが通行できる道路がなかったことも,路線開設に至らなかった背景にとしてあげられる.この路線は現在,通勤や高校生の通学を中心に利用されており,限られた便数ながらも,採算を確保できる水準が維持されている.路線バス開設と時期を同じくして,小中学生のためにスクールバスの運行も開始された.地域内に小中学校はなく,離れた市街地までの通学が必要であるが,距離上は行政のスクールバス運行基準に満たないため,当初は徒歩での通学を余儀なくされていた.しかし周囲を原野や山林で囲まれ,舗装はおろか,街頭も設置されていない箇所があり,安全上の懸念があったため,保護者による自家用車での送迎も日常的に行われていた.このなかで地域住民の発案,主導により,貸切バスを用いたスクールバスの運行が,1996年から行われてきた.一方で路線バスとスクールバスでは対応しきれない地域の需要が,少なからず生じてきた.函館市の市街地拡大や郊外化によって,いわゆる中心市街地は空洞化し,郊外に大型ショッピングセンターや病院が立地するようになった.路線バス(6-2系統)は,これらの地域を通らずに中心市街地や函館駅に向かう路線であり,日常生活のうえで十分とはいえない状態となった.地域住民の要望を受け,町会ではバス路線開設に向けたアンケート調査を実施し,これをもとに市長への陳情,町会および函館市,函館バスとの協議が進められ,2012年4月1日からJ-バスとして運行が開始された.当初は上陣川停留所を起点に,郊外の商業施設,病院などを廻り,上陣川に戻る循環ルートとした.車両は函館バスの一般路線バス車両1台を専用車として運用しているが,貸切バスとしての運行であり,車内での運賃収受は原則できない.このため事前に,利用券(歴月単位)か回数券(使用期限あり)を購入する必要がある.運行開始から,数か月単位で利用状況と路線・ダイヤを検討しており,2012年8月には循環ルートをやめ,大型商業施設に隣接する函館バス昭和営業所から,上陣川を往復するルートに改められた.利用の多くは,スクールバスからシフトさせた中学生であり,長期休暇中の利用の落ち込みが激しく,採算性の確保が課題となった.このため函館バス提供されたJ-バス専用車の広告枠を販売し,収入源とするほか,利用促進のための活動も活発化した.現在の運行体制は,これをもとにスクールバスを統合したかたちであり,スクールバスとして運行される一部の便のみに函館市から補助がされている. J-バスは町会が運営組織となり,行政,事業者との協働によって成り立っている.それぞれの組織が地域の公共交通サービスを確保するために“できること”からスタートしている.行政や事業者に頼り切らず,自主的に活動しようとする地域性もさることながら,三者が地域のために“何かする”という視点を強く持っており,かつ,担当者レベルでの意思疎通が極めて円滑であることも重要な要素といえるだろう.J-バスは2014年度,3年目の実証運行に入るため調整中である.
抄録全体を表示