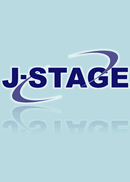-
久志本 成樹, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登, 石倉 宏恭 ...
2016 年30 巻3 号 p.
321-330
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
日本外傷学会将来計画委員会は,1)外傷急性期凝固異常の病態解明,2)病態把握に基づくhemostatic resuscitationの構築を目標とし,多施設共同後向き観察研究:Japanese Observational study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma(J-OCTET)を実施した.対象:2012年1〜12月に15施設へ入院した,年齢18歳以上,ISS≧16の外傷症例.他院紹介,妊娠中,肝硬変合併,来院時心停止,高エネルギー外力によらない脊髄損傷,熱傷は除外した.結果:796例のデータを収集し,年齢59歳(38-72),男性589例(74%),鈍的外傷790例,ISS 24(17-27),Ps 0.918(0.767-0.967),頭部外傷合併481例(60.4%)であった.治療・転帰をみると,24時間以内止血術93例(11.7%),IVR 110例(13.8%),受傷後3時間以内トラネキサム酸投与281例(35.3%),6時間以内輸血施行207例(26.0%),24時間以内RBC≧10単位125例(15.7%),6時間以内輸血施行例中24時間以内RBC≧10単位施行率58.5%,28日死亡117例(14.7%)であった.結語:本研究は外傷急性期凝固異常の解明と治療法構築に貢献するものと考える.
抄録全体を表示
-
早川 峰司, 前川 邦彦, 久志本 成樹, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登 ...
2016 年30 巻3 号 p.
331-340
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 外傷急性期におけるフィブリノゲン (fibrinogen, 以下Fbg) 低値は予後不良を示唆する. D–dimerは線溶亢進の指標であり外傷重症度を反映するが, 予後予測におけるFbgとの関係は明らかにされていない. 今回, 搬入時のD–dimer高値がFbg値に関係なく予後不良を示唆する可能性を検証した. 方法 : Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) データベースを用いて, 来院24時間以内における10単位以上の赤血球輸血, もしくは24時間以内の死亡を転帰不良と定義した. ROC曲線を用いて, 搬入時のFbg値とD–dimer値の転帰不良に対する閾値を求め, その閾値に基づいた群分けを行い比較した. 結果 : 転帰不良に対する閾値はFbg=190 mg/dLとD–dimer=38 mg/Lであった. この閾値に基づき, (1)D–dimer低値/Fbg高値, (2)D–dimer低値/Fbg低値, (3)D–dimer高値/Fbg高値, (4)D–dimer高値/Fbg低値の4群に分けた. (4)群の生存率は他の3群よりも有意に低値であった. (3)群の生存率は, (1)群および(2)群の生存率よりも有意に低値であった. 結語 : ISS16以上の成人重症外傷においては, 搬入時のD–dimer高値は, Fbg値に関係なく, 予後不良の予測因子である.
抄録全体を表示
-
村田 希吉, 大友 康裕, 久志本 成樹, 齋藤 大蔵, 金子 直之, 武田 宗和, 白石 淳, 遠藤 彰, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 佐 ...
2016 年30 巻3 号 p.
341-347
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
【目的】重症外傷患者における病院前輸液と生命予後, 大量輸血および凝固異常との関連について明らかにする. 【対象と方法】Japanese Observational Study of Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) で後方視的に収集したISS≧16の外傷796例について, 28日死亡, 大量輸血 (24時間Red Cell Concentrate : RCC10単位以上), 外傷性血液凝固障害 (Trauma–Associated Coagulopathy : TAC : PT–INR≥1.2と定義) の3つを評価項目として, 病院前輸液施行の有無の影響を検討するために多変量解析を行なった. さらに年齢 (65歳以上/未満), 性別, 重症頭部外傷合併の有無, 止血介入 (手術またはIVR) の有無により層別化解析した. 【結果】病院前輸液施行85例, 非施行711例であり, 両群間における年齢, 性別, 28日死亡, 大量輸血, 止血介入に有意差を認めなかった. 病院前輸液群ではISSが高く (中央値25 vs. 22, p=0.001), TACが高率であった (29.4% vs. 13.9%, p<0.001). 病院前輸液は28日死亡, 大量輸血の独立した規定因子ではなかった. TACの有無を従属変数とし, 年齢・性別・病院前輸液の有無・ISSを独立変数とするロジスティック回帰分析では, 病院前輸液 (オッズ比 (OR) 2.107, 95%CI 1.21–3.68, p=0.009) とISS (1点増加によるOR 1.08, 95%CI 1.06–1.10, p<0.001) は年齢とともに独立したリスク因子であった. 層別解析では, 65歳未満 (OR 3.24, 95%CI 1.60–6.55), 頭部外傷合併 (OR 3.04, 95%CI 1.44–6.42), 止血介入例 (OR 3.99, 95%CI 1.40–11.4) において, 病院前輸液は独立したTACのリスク因子であった. 【結語】ISS≧16の外傷患者に対する病院前輸液は, 28日死亡および大量輸血との関連は明らかではないが, TAC発症の独立したリスク因子である. 特に65歳未満, 頭部外傷合併, 止血介入を要する症例に対する病院前輸液は, TAC発症のリスクとなる可能性がある.
抄録全体を表示
-
仲村 佳彦, 石倉 宏恭, 久志本 成樹, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文 ...
2016 年30 巻3 号 p.
348-355
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
【目的】鈍的重症外傷患者において凝固・線溶系マーカーがmassive transfusion (以下MT) (24時間以内における10単位以上の赤血球輸血) の予測因子になり得るか否かを検討した. 【方法】Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) データベースの鈍的外傷患者をMTとnon–MT群に分類し, 目的変数をMTの有無, 説明変数を年齢, 性別, 搬入時バイタルサイン, Glasgow Coma Scale, ヘモグロビン値, 血小板数, 乳酸値, PT–INR, D–ダイマー値, フィブリノーゲン (Fbg) 値として, ステップワイズロジステッィク回帰分析を行い, MT予測因子を抽出した. さらに, 抽出した項目について, receiver operating characteristic (ROC) 解析を行い, Youden indexにてoptimal cut–off値を算出した. 【結果】心拍数 (per 10 bpm) [Odds ratio (OR), 1.72 ; 95%信頼区間1.47–2.05] , 体温 [0.70 ; 0.53–0.94] , Fbg (per 10 mg/dL) [0.89 ; 0.84–0.94] がMTの独立予測因子であった. ROC曲線下面積は, 心拍数 : 0.81, 体温 : 0.60, Fbg : 0.75であった. Optimal cut–off値は心拍数96 bpm (感度73.7%, 特異度76.6%), 体温36.3°C (感度66.7%, 特異度48.7%), Fbg 190 mg/dL (感度61.4%, 特異度80.2%) であった. 【結語】鈍的重症外傷におけるMTの必要性に関して, Fbg値は心拍数, 体温に比較し, 特異度の高い予測因子となる可能性がある.
抄録全体を表示
-
早川 峰司, 前川 邦彦, 久志本 成樹, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登 ...
2016 年30 巻3 号 p.
356-364
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 頭部外傷では播種性血管内凝固症候群 (以下DIC) を合併することが多く, DIC合併症例では予後不良である. 頭部単独外傷におけるDICと組織低灌流の関係を検討した. 方法 : Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) データベースとして, 18歳以上のinjury severity score≧16の外傷患者を後ろ向きに収集した. そのデータベースから, 頭部単独外傷患者 (TBI) (頭部abbreviated injury score (AIS) ≧4かつ頭部以外のAIS<2) と非頭部外傷患者 (non–TBI) (頭部以外のAIS≧3かつ頭部AIS<2) の患者を抽出し比較した. 結果 : 160人のTBI患者, 186人のnon–TBI患者が対象となった. TBI群では搬入時の全身性組織低灌流の指標としての乳酸値と凝固線溶系検査や血小板数, DICスコアに相関を認めなかったが, non–TBI群では, 搬入時の乳酸値と凝固系検査に相関を認めた. Non–TBI群におけるロジスティック回帰分析では, 乳酸値はDICの独立した予測因子であったが, TBI群ではその関係性は認めなかった. 結語 : 頭部単独外傷におけるDICは, 頭部外傷非合併患者とは異なり, 全身性組織低灌流と関係なく発症することが考えられる.
抄録全体を表示
-
渋沢 崇行, 佐々木 淳一, 仲村 佳彦, 石倉 宏恭, 植嶋 利文, 小倉 裕司, 加藤 宏, 金子 直之, 齋藤 大蔵, 武田 宗和, ...
2016 年30 巻3 号 p.
365-369
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
【目的】超高齢者の重症外傷における臨床的特徴および受傷後急性期の凝固線溶動態を明らかにすること. 【対象と方法】Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) に登録された2012年1〜12月に入院した796例を対象とし, 超高齢群 (≧85歳) と非超高齢群 (<85歳) の2群において, 各種属性データおよび凝固線溶動態の指標を比較検討した. 【結果】抗凝固薬/抗血小板薬内服率は超高齢者群の方が有意に高率であった (6.9% vs 20.0%, p<0.01). また, 超高齢者の24時間以内死亡および院内死亡リスクのオッズ比はそれぞれ5.53, 4.83 (ともにp<0.001) であった. PT–INRは超高齢者で延長する傾向を認めたが, 有意差は認めなかった. 急性期DICスコアについては, 両群間で差を認めなかった. 【結語】超高齢者では, 抗凝固薬/抗血小板薬内服率が高く, また, 凝固異常に陥りやすい可能性がある. ISS 16以上の重症外傷では, 85歳以上の高齢であることは, 独立して予後不良を予測するものと考えられる.
抄録全体を表示
-
工藤 大介, 久志本 成樹, 白石 淳, 大友 康裕, 齋藤 大蔵, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, ...
2016 年30 巻3 号 p.
370-375
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
【目的】頭部外傷非合併重症外傷例では, 抗凝固・抗血小板薬 (薬剤) 内服が, 止血的介入のリスクであるかを検討すること. 【方法】Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) データベースに収集されたInjury Severity Score (ISS) ≧16の外傷のうち, 頭部外傷合併例を除く312例を対象とした. 24時間以内の新鮮凍結血漿10単位以上投与または止血的介入施行による複合アウトカムを主要評価項目として, 薬剤内服による影響を検討した. 【結果】内服群は20例 (6.4%) であり, 両群間の生存期間に差はなかった. 上記複合アウトカムに対する年齢, 性別, ISS, 薬剤内服の有無を説明変数としたロジスティック回帰分析では, 薬剤内服は独立した止血的介入の予測因子であった (オッズ比3.16, 95%信頼区間1.08–9.10, P<0.05). 【結論】頭部外傷を合併しない重症外傷患者における抗血栓薬内服は, 止血的介入の増加と関連する可能性がある.
抄録全体を表示
-
久志本 成樹, 工藤 大介, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登 ...
2016 年30 巻3 号 p.
376-384
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 大量出血を伴う外傷治療には早期の輸血戦略が重要である. 重症外傷における6時間以内輸血施行例の早期抽出と, 転帰改善につながる治療戦略を明らかにすることを目的とした. 方法 : Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma, J–OCTETデータベースにより, 6時間以内輸血の有無による比較, 6時間以内輸血施行生存例と死亡例の比較を行った. 結果 : 6時間以内輸血施行207例中121例, 58.5%が24時間以内に10単位以上の輸血を要した. 腹部AIS≧3による予測特異度は95.4%であり, 心拍数≧90/分 and/or乳酸値≧2.5 mmol/Lの陰性的中率は90%以上であった. ロジスティク回帰分析では, 6時間以内のFFP/RBC比≧1が独立した転帰規定因子であった (オッズ比 : 0.285, P=.016). 傾向スコア逆数重み付けを用いたCox比例ハザード解析では, 6時間以内FFP/RBC比≧1が転帰に影響した (ハザード比 0.51, P<.001). 結論 : 急性期に輸血を要する重症外傷では, 6時間以内のFFP/RBC比≧1が転帰を改善する. 6時間以内輸血症例の60%は大量輸血を要し, "RBCとFFP10単位ずつ" にて開始することは転帰の改善につながる可能性がある.
抄録全体を表示
-
萩原 章嘉, 久志本 成樹, 加藤 宏, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登, 石倉 宏恭, 早川 峰司, ...
2016 年30 巻3 号 p.
385-396
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 救急治療室入室後の新鮮凍結血漿 (fresh frozen plasma, 以下FFP) および濃厚赤血球 (packed red blood cell, 以下RBC) の輸血量から, 患者の予後を改善させる適切なFFPとRBC輸血量の比を決定し, 早期から投与することによりの予後を改善できるかを検討することを目的とした. 方法 : Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) データベースから, 24時間以内にRBC輸血を行った207例を対象とした. 退院時転帰をアウトカムとして, 6時間以内に投与したFFP/RBC比を独立変数としたROC解析からカットオフ値を算出し, FFP/RBC比により2群に群分けした. 病院転帰を主要評価項目として, propensity score (PS) による調整に基づき, 6時間以内のFFP/RBC比による2群間における生存期間の比較を行った. 結果 : 207例中201例 (97%) が鈍的外傷患者であった. ROC解析によるAUCは0.56であり, 感度・特異度曲線から最大の感度 (0.59), 特異度 (0.67) を示すFFP/RBC比は1.0であった. 患者全体をFFP/RBC比≧1.0, FFP/RBC比<1.0の2群に分け, PS matchingとinverse probability of treatment weighting (IPTW) 法により解析した. 未調整Hazard ratioは0.44, 選択したすべての項目により調整したハザード比0.32, ハザード比によるHazard ratio 0.38, IPTW法 0.41であり, 6時間以内のFFP/RBC比≧1投与例では有意に生存率が高かった. 結語 : ISS≧16かつ24時間以内に赤血球輸血を要する外傷では, 6時間以内にFFP/RBC比≧1の輸血が行われた患者の死亡ハザード比は約0.4であり, 死亡リスクは約60%減少した. 97%が鈍的外傷である患者群においても, 輸血を必要とする重症外傷患者の転帰を改善するためには, 6時間以内にFFP/RBC比≧1となる輸血を行うことが必要である.
抄録全体を表示
-
白石 淳, 久志本 成樹, 大友 康裕, 齋藤 大蔵, 村田 希吉, 早川 峰司, 植嶋 利文, 金子 直之, 萩原 章嘉, 佐々木 淳一, ...
2016 年30 巻3 号 p.
397-404
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
背景 : トラネキサム酸投与が外傷患者の死亡率を低下させることがランダム化試験で示されたが, 多くの批判もなされている. 本研究では, 日本の実際の外傷診療における受傷後3時間以内のトラネキサム酸の投与が, 生死および輸血量に及ぼす効果を検証した. 対象と方法 : Japanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (以下J–OCTET) 研究で収集された全外傷患者を対象とし, 傾向スコアマッチ法を用いてトラネキサム酸投与例と非投与例の背景因子を調整した2群を抽出した. 28日死亡率と輸血量を群間比較した. 結果 : J–OCTETに登録された796例のうち, 受傷後3時間以内のトラネキサム酸投与群と非投与群のそれぞれ242例をマッチさせた. トラネキサム酸投与は28日死亡率を減少させたが (12.7% versus 20.6%, 平均差–7.9%, 95%信頼区間 [–14.2%, –1.6%]), 24時間赤血球平均輸血量 (4.2単位 versus 3.8単位, 平均差 +0.4, 95%信頼区間 [–1.1, +2.1]) と24時間新鮮凍結血漿平均輸血量 (4.3単位 versus 3.4単位, 平均差 +0.9, 95%信頼区間 [–0.7, +2.6]) には差がなかった. 結論 : 我が国で行われている重症外傷診療においても, CRASH–2試験により示された受傷後3時間以内のトラネキサム酸投与により, 死亡率減少効果が期待できることが示された.
抄録全体を表示
-
植嶋 利文, 白石 淳, 久志本 成樹, 早川 峰司, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 森村 尚登, ...
2016 年30 巻3 号 p.
405-411
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 頭部単独外傷に対するトラネキサム酸 (以下TXA) の生命予後に対する効果を検討すること. 対象と方法 : 多重代入法を用いてJapanese Observational Study for Coagulation and Thrombolysis in Early Trauma (J–OCTET) Studyデータベースの欠測値を補完した101個のデータセットを作成した. 頭頸部AIS4以上の頭部外傷で他部位AIS1以下の230例を抽出した. 3時間以内のTXAの使用の有無を従属変数, 来院時に得られたデータを独立変数とした傾向スコアマッチングを行い, TXA使用群と非使用群間の生存期間を比較した. 結果 : TXA使用群において有意な生存期間の改善が認められた (P=0.033). サブグループ解析において, 初期D–dimer値40μg/ml以上の群においてTXA使用による生存改善が有意であった. 結語 : 頭部単独外傷において, 3時間以内のTXA投与は有意な生存期間の改善を期待できる. 最も効果が高いのは線溶亢進が生じている群と推察された.
抄録全体を表示
-
前川 邦彦, 早川 峰司, 久志本 成樹, 萩原 章嘉, 齋藤 大蔵, 佐々木 淳一, 小倉 裕司, 松岡 哲也, 植嶋 利文, 森村 尚登 ...
2016 年30 巻3 号 p.
412-418
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
目的 : 外傷患者の死亡率低下のための急性期における輸血目標は明らかではない. 至適輸血目標レベルを明らかにするために, 重症外傷患者の受傷24時間後のヘモグロビン (Hb), 血小板数 (Plt), フィブリノゲン (Fbg) 値と病院死亡との関係を検討した. 方法 : J–OCTETデータベースから受傷24時間以上生存した外傷患者を抽出し, 病院死亡を予測する24時間後のHb, Plt, Fbgのカットオフ値をロジスティック回帰分析で同定し, ブートストラップ法で内部検証を行った. 結果 : 対象患者722例, 年齢57才 (中央値), ISS 22 (中央値), 病院死亡率は6.5%であった. 病院死亡を予測する最適なモデルは, Hb<10.0g/dL (c統計量0.77, 95%信頼区間0.69–0.85), Plt<10.0×10
4/μL (0.80, 0.72–0.87), Fbg<200mg/dL (0.82, 0.72–0.92) であった. ブートストラップ法で調整されたc統計量との差はそれぞれ0.03, 0.03, 0.01であった. 結論 : 24時間以内の急性期死亡例を除く重症外傷患者では, 受傷24時間後のHb<10.0g/dL, Plt<10.0×10
4/μL, Fbg<200mg/dLは病院死亡と関連した.
抄録全体を表示
-
遠藤 彰, 白石 淳, 久志本 成樹, 大友 康裕, 齋藤 大蔵, 早川 峰司, 小倉 裕司, 村田 希吉, 萩原 章嘉, 佐々木 淳一, ...
2016 年30 巻3 号 p.
419-423
発行日: 2016/07/20
公開日: 2016/07/20
ジャーナル
フリー
背景と目的 : 「外傷死の三徴」はダメージコントロールを行う根拠のひとつとして長らく使用されてきた. その従来基準 (PT–INR>1.5, pH<7.2, 体温<35°C) を検証するとともに, 治療方針決定に有用な新たな基準を構築した. 対象と方法 : 15施設に2012年の1年間に搬送されたISS≧16の患者を後方視的に検討した. 結果 : 計796例を解析した. 従来基準を1項目以上満たしたときの死亡予測感度は36%, 特異度88%であり, 3項目では感度4%, 特異度100%であった. 凝固・線溶異常, アシドーシス, 低体温の三徴の枠組内で各種項目の転帰予測精度・閾値・影響力を検討し, FDP>90μg/mlを大項目, BE<–3mEq/Lと体温<36°Cを小項目とする新基準を構築した. 新基準は大項目単独または小項目を同時に満たしたときに感度83%, 特異度67%で転帰を予測した. 結論 : 従来基準はダメージコントロール治療の指針として不適当と考えられた. 新基準は方針決定の客観的根拠となり得る.
抄録全体を表示