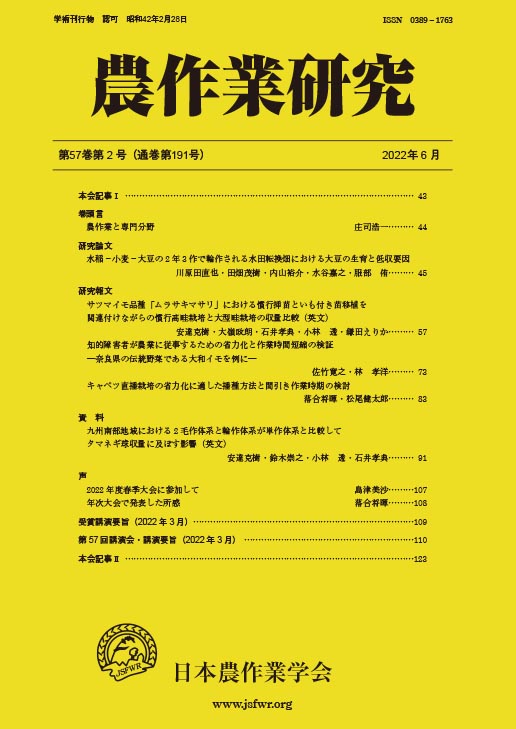
- 4 号 p. 201-
- 3 号 p. 145-
- 2 号 p. 45-
- 1 号 p. 3-
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
川原田 直也, 田畑 茂樹, 内山 裕介, 水谷 嘉之, 服部 侑2022 年57 巻2 号 p. 45-55
発行日: 2022/06/20
公開日: 2022/12/20
ジャーナル フリー水稲-小麦-大豆の2年3作で輪作される水田転換畑において大豆の収量向上を目的として,生産者が管理する30ほ場の大豆の収量と生育に関連する草型,収量構成要素,被害粒,およびほ場に関連する排水性,土壌物理性,土壌化学性との関係を調査・解析した.まず,生育に関連する項目との関係を解析した結果,株数が十分確保された条件下では,分枝数,一株総莢数,一莢内粒数が多く,百粒重が重いほ場において増収する傾向があった.また,収量とカメムシ類による被害粒率(吸汁害粒率)との間には有意な負の相関関係が認められることから,一株総莢数を収量につなげるためには,カメムシ類の適期防除が必要であると考えられた.次にほ場に関連する項目との関係を解析した結果,収量は地下水位,作土層の滞水時間,作土下層の飽和透水係数と有意な相関関係が認められた.このことから,ほ場に関連する低収要因を改善し,収量を向上させるためには,①地下水位が地表面から40 cm以内に上昇する日数を減少させること,②まとまった降雨時に作土層が滞水する時間を減少させること,③作土下層の土壌物理性を改善し,透水性を高めることが必要であると考えられた.また,地下水位が地表面から40 cm以内に上昇する日数と作土層の滞水時間の間にも正の相関関係が認められることから,地下水位を低下させることにより,降雨時に作土層が滞水する時間を短縮できる可能性があるものと考えられた.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (716K)
-
安達 克樹, 大嶺 政朗, 石井 孝典, 小林 透, 鎌田 えりか2022 年57 巻2 号 p. 57-71
発行日: 2022/06/20
公開日: 2022/12/20
ジャーナル フリー1畦に2条植えする大型畦栽培の収量性を慣行高畦栽培と比較して評価するために,慣行挿苗といも付き苗移植の2つの植付け方法によるサツマイモ品種「ムラサキマサリ」を用いた圃場試験を実施した.大型畦の形状は,2008年は,大型畦1(畦高さ35 cm,畦幅180 cm,畦裾幅120 cm,畦肩幅90 cm,通路幅60 cm)と大型畦2(畦高さ35 cm,畦幅160 cm,畦裾幅100 cm,畦肩幅70 cm,通路幅60 cm)であり,2009年は,大型畦3(畦高さ35 cm,畦幅160 cm,畦裾幅110 cm,畦肩幅80 cm,通路幅50 cm)とした.2008年では,大型畦1と大型畦2栽培は,いも収量において慣行高畦栽培に優ってはいなかった.2009年では,畦型と植付け方法の2つの要因に栽植密度の要因(2.222,1.852,1.500株m-2)を加えて,収量性について試験した.最も低いいも収量は大型畦3×慣行挿苗×1.852株m-2区で得られた.畦型と植付け方法の間の2要因交互作用に関係して,最も低いいも収量は大型畦3×慣行挿苗区で得られ,大型畦3の条件では,いも付き苗移植区のいも収量が慣行挿苗区と比べて有意に高かった.これらの結果は,大型畦3栽培では,いも付き苗移植方法は適しているだろうが,慣行挿苗方法は適していないことを示唆した.本研究で得られた結果はサツマイモ栽培における将来の畦型研究のために有用であろう.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2372K) -
-奈良県の伝統野菜である大和イモを例に-佐竹 寛之, 林 孝洋2022 年57 巻2 号 p. 73-81
発行日: 2022/06/20
公開日: 2022/12/20
ジャーナル フリー知的障害者が就農する時の課題として,任せられる仕事が限られていることや,生産効率が低下することなどが挙げられる.そこで本研究では,素工程分解(1動作もしくはその動作の繰り返しだけで行える工程まで分解すること)とポリエステル繊維培地,フェルトポットを組み合わせるとともに,デッドスペースを生かして栽培を行うことで,知的障害のある生徒が自立的に栽培した上で作業時間の短縮が可能か検証した.方法は,特別支援学校高等部の5名を対象に,県内で担い手不足が懸念されている大和イモの栽培を行った.調査は(1)生徒の作業様態の記述,(2)各工程における作業時間の比較,(3)栽培法の違いによる収穫物の比較,の3つを行った.その結果,大和イモの「芽かき」工程に関しては,一部支援者の補助が必要であるが,それ以外の全ての工程を生徒が自立的に実施することができた.作業時間は灌水を除く全工程合計で慣行法476分,繊維培地法313分と163分短縮した.収穫物の生鮮重量の比較では,慣行法より繊維培地法の方が0.1%水準で有意に重かった.一方,「外形」は慣行法の方が0.1%水準で有意に「球形」に近かった.以上のように,素工程と補助具,立地を生かしたフェルトポットでの栽培を通して,知的障害のある生徒が自立的に作業時間を短縮して作業できることが示された.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1705K) -
落合 将暉, 松尾 健太郎2022 年57 巻2 号 p. 83-89
発行日: 2022/06/20
公開日: 2022/12/20
ジャーナル フリーキャベツ直播栽培における間引き作業の省力化を志向し,播種方法と間引き作業時期の違いが間引き作業時間およびキャベツの生育に及ぼす影響を調査した.具体的には,2粒の種子が1か所に播種される慣行の直播栽培(慣行区)に対し,その種子間隔を10 cmで播種する手法(幅広区)を検討し,それぞれについて2葉期と6葉期に間引きを行った.その結果,間引き作業時間は慣行区で4.7–4.9 s/株,幅広区で2.0–3.1 s/株となり,種子間隔が広いと間引き作業時間が短縮することが分かった.また,種子間隔10 cmでは,6葉期に間引きする方が2葉期に間引きする場合に比べ,間引き作業時間を1.1 s/株短縮できることが分かった.キャベツの生育について,投影葉面積と結球重は間引き作業時期の違いによる有意な影響を受けなかったが,慣行区よりも幅広区の方が生育は良好な傾向を示した.以上のことから,種子間隔を10 cmに設定し6葉期に間引きを行う手法が間引き作業の省力化に適していることが明らかになった.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (647K)
-
安達 克樹, 鈴木 崇之, 小林 透, 石井 孝典2022 年57 巻2 号 p. 91-106
発行日: 2022/06/20
公開日: 2022/12/20
ジャーナル フリーソルガム―タマネギ2毛作体系とサツマイモ―タマネギ―ソルガム―タマネギ輪作体系におけるタマネギ収量を,タマネギ単作体系と比較して評価するために,九州南部地域における3年間の圃場試験を4回(2毛作体系2回と輪作体系2回)実施した.この研究により,4回の圃場試験の全てにおいて,1作目のタマネギ球収量は2毛作区および輪作区において単作区よりも約20%高いことが示された.しかしながら,それぞれの作付体系をタマネギ2作目そして3作目へと継続すると,単作体系に比べて2毛作体系および輪作体系による球収量を高める効果は消失した.このタマネギ2作目および3作目において増収効果が消失する理由は明らかではなかった.従って,南九州地域における2毛作体系と輪作体系がタマネギの生育と収量に及ぼす影響を明らかにするためには,菌根菌感染率および土壌養分状態の経時的な調査を伴う更なる試験が求められる.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1147K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|