巻号一覧
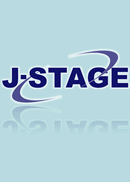
21 巻 (1996)
- 4 号 p. 169-
- 3 号 p. 111-
- 2 号 p. 69-
- 1 号 p. 1-
21 巻, 3 号
選択された号の論文の6件中1~6を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
近藤 昭二, 松尾 清, 野口 昌彦, 古川 博, 平林 伸一1996 年 21 巻 3 号 p. 111-117
発行日: 1996/07/31
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーvelo-cardio-facia1症候群が,常染色体22q11部分欠失により,生じることがわかってきた.本邦ではvelo-cardio-facial症候群と,先天性鼻咽腔閉鎖不全,粘膜下口蓋裂とは,別の疾患概念でとらえられているが,臨床上の分類は困難である.これらの疾患の関連について調査する目的で,先天性鼻咽腔閉鎖不全,粘膜下口蓋裂症例における22q11部分欠失症の頻度とその症候を検討した.治療後の患者については鼻咽腔閉鎖,構音獲得の状態についても調査した.
対象は,先天性鼻咽腔閉鎖不全,粘膜下口蓋裂の8例で,velo-cardio-facial症候群に伴う他の症候(心奇形,顔貌の異常,学習障害)は症例の選択にあたり考慮せず,他の染色体異常が明確なものは対象から除外した.FISH法による染色体検査で8例中4例に22q11に欠失が認められた.陽性例の4例中,velo-cardio-facial症候群様の顔貌と軽度の学習障害は全例に認められたが,心奇形が認められた症例は1例のみであった.術後の3例では,鼻咽腔閉鎖が完全もしくは軽度の鼻漏出でもあるに関わらず,構音獲得は不良であり,学習障害が構音獲得を不良にする一因と考えられた.
以上より,先天性鼻咽腔閉鎖不全,粘膜下口蓋裂症例中には相当数のvelo-cardio-facial症候群が含まれていることが推察された.また,鼻咽腔閉鎖不全を主徴とするvelo-cardio-facial症候群では心奇形を伴うことはむしろ少ないと考えられた.顔貌や学習障害は見落しやすく,先天性鼻咽腔閉鎖不全,粘膜下口蓋裂を示す症例に対しては,疾患概念を明確にし,治療方針を決定するために染色体検査は必須である.velo-cardiofacial症候群と診断された場合には,関連各科による集学的な診断と治療が必要であり,特に神経科の果たす役割が大きいと考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4240K) -
佐藤 耕一, 和田 健, 舘村 卓, 芝 良祐1996 年 21 巻 3 号 p. 118-125
発行日: 1996/07/31
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー本研究は,健常者と口蓋裂術後患者について,鼻咽腔閉鎖機能に関係する形質的要素のうち軟口蓋長と鼻咽腔深度について幼児期から思春期まで横断的資料にもとついて検討したものである.研究対象は健常者82名(健常者群)と片側性完全唇顎口蓋裂術後患者80名(口蓋裂群)であり,年齢により4つの発育段階(stage1:4歳時, stage 2:8歳時, stage 3:12歳時, stage 4:17歳時)に区分した.安静時に撮影した側面頭部X線規格写真上で,軟口蓋長と鼻咽腔深度およびその比率(Adequate ratio)について独自に作製したプログラムを用いてパーソナルコンピューターにより分析を行った.その結果は以下の通りであった.
1.軟口蓋長は,全発育段階を通じて健常者群では漸次増加の傾向を示したが,口蓋裂群では著変を示さなかった.
2.鼻咽腔深度は,健常者群では4歳時から12歳時まで増加を示し,口蓋裂群では4歳時から8歳時および12歳時から17歳時にかけて増加を示した.
3,Adequate ratioは,健常者群では4歳時から17歳時に至るまで安定した比率を維持した.口蓋裂群では17歳時に健常者群より小さい比率を示した.
以上の結果,口蓋裂術後患者では口蓋裂手術後の幼児期に鼻咽腔閉鎖が達成されていると評価されても,思春期に至る頃では形態的には鼻咽腔閉鎖不全を惹起する形質的素因が内在することが示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1074K) -
小野 和宏, 大橋 靖, 高木 律男, 永田 昌毅, 飯田 明彦, 今井 信行, 神成 庸二, 早津 誠1996 年 21 巻 3 号 p. 126-141
発行日: 1996/07/31
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー二段階口蓋形成手術法では,軟口蓋閉鎖後に残存する硬口蓋の破裂が縮小することを経験する.しかし,これについて経時的に詳細な追求はなされておらず,どの様な経過で硬口蓋の破裂が変化し,どこまで小さくなるのか,またどうして縮小するのかについては明らかではない.そこで,硬口蓋閉鎖まで終了した二段階口蓋形成手術例53症例を対象に,軟口蓋閉鎖時の1歳6か月から硬口蓋閉鎖時の6歳まで経年的に採取した上顎歯槽模型を用いて,硬口蓋に残存する破裂の変化を縦断的に分析した.得られた結果は以下のとおりである.
1.破裂幅径は4歳まで経年的に減少し,その後は硬口蓋閉鎖まで有意な変化はみられなかった.
2.前方部破裂幅径は,片側顎口蓋裂では約85%の減少率であったが,両側顎口蓋裂では約45%とわずかであった.一方,後方部破裂幅径は裂型により差はなく,いずれも約半分に減少した.
3.片側顎口蓋裂2例では,破裂の著しい縮小により,硬口蓋部破裂のみかけ上の閉鎖が認められた.
4.歯槽弓幅径が減少しないことから,破裂幅径の減少はsegment破裂縁の正中側への成長によると考えられた.
5.硬口蓋部破裂の縮小に鼻中隔の関与はみられなかった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1510K) -
朴 修三, 時岡 一幸, 加藤 光剛, 北野 市子, 仁田 直嗣1996 年 21 巻 3 号 p. 142-149
発行日: 1996/07/31
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー1977年4月より1996年3,月の19年問に静岡県立こども病院の口蓋裂診療班を受診した粘膜下口蓋裂は154例である.そのうち手術を行った症例は67例,手術を行っていない症例は87例である.未手術症例のうち,精神発達に著しい遅れのある28例や経過観察期間の短い症例などを除外し,初回言語評価後2年以上経過観察できている22症例に検討を加え,以下の結果を得た.
初回言語評価は初診時年齢が4歳未満では4歳前後,4歳以降では初診時の言語評価とし,最終言語評価時年齢は外来で言語評価した最も新しい年齢とした.
1)初回と最終の言語評価時の間に鼻咽腔閉鎖機能が悪化した症例が3例,改善した症例が5例,残りの14例で変化がなかった.
2)初回言語評価時に構音障害がみられたのは5例で,全例に構音訓練を行い,最終言語評価時には2例に減少し,経過観察期間中に新たに構音障害が出現した症例はなかった.
3)乳児期にミルクの鼻漏出や哺乳困難などの症状があった症例は5例で,全例生後1年以内に症状は消失していた.乳児期のエピソードの有無と初回および最終言語評価時の鼻咽腔閉鎖機能には明らかな関連はみられなかった.
4)セファログラム検査で軟口蓋の厚さは3~5歳群で未手術症例が手術症例より有意に厚く,咽頭腔の深さと軟口蓋長の比が1.0以下を示した症例は手術症例に有意に多くみられた.
5)安静時の鼻咽腔閉鎖面形態は切痕型を示す症例が多くみられたが,有意のある傾向はみられず,鼻咽腔閉鎖機能との関連もみられなかった.
6)鼻咽腔閉鎖運動パターンでは手術症例と宋手術症例の問に差はなく,閉鎖運動パターンと鼻咽腔閉鎖機能にも関連はみられなかった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1319K) -
浜口 裕弘, 古郷 幹彦, 飯田 征二, 竹村 日登美, 石井 庄一郎, 田中 晋, 安井 康順, 松矢 篤三1996 年 21 巻 3 号 p. 150-155
発行日: 1996年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー口蓋形成術は口蓋帆挙筋のmuscle slingの形成と鼻咽腔形態の形成,push back法による鼻咽膣の狭小化を目的としているため同手術施行直後は気道抵抗が大きくなり,経鼻呼吸が困難になる症例は多々存在する.しかし腫脹消退後も継続して気道閉塞を起こす症例はほとんどないと考えられている.
今回,われわれは口蓋形成術後に閉塞型睡眠時無呼吸症候群(Obstructive Sleep Apnea Syndrome:OSAS)を認めた症例を経験した.患児は生下時より口蓋裂を認めたため1歳2か月時に本院にて口蓋形成術を施行した.3歳3か月時に下気道炎から気道閉塞をきたし,6日間の挿管による人工換気が必要となった.ポリソムノグラフィー所見より患児の睡眠動態を観察したところ,閉鎖型の無呼吸発作が認められた.apnea indexはユ5.5だった.
OSASの診断の下に,持続的陽圧呼吸装置(nasal CPAP system)を装着させて睡眠させたところ,いびきは消失し,呼吸流量の停止も認めなくなった.apnea indexが15.5から3.1と改善した.
現在,患児は本装置を装着して良眠を得ている.今後,成長発育を待って治療を行うまでの補助的手段としては本装置は有用であると考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7608K) -
術後早期にみられた経過不良症例に関する検討福田 雅幸, 幸地 省子, 高橋 哲, 永井 宏和, 高野 裕史, 松井 桂子, 越後 成志1996 年 21 巻 3 号 p. 156-163
発行日: 1996/07/31
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー1991年1月から1993年12月までの3年間に,顎裂への新鮮自家腸骨海綿骨細片移植術を施行した174例,196顎裂のうち,術後早期にみられた経過不良症例12例,13顎裂について,その原因と対策について検討した.
1.経過不良症例は12例,13顎裂で,裂型別内訳は,片側口唇顎裂が1例,片側口唇口蓋裂が8例,両側口唇口蓋裂が3例(2例は片側のみ不良)であった.
2直接的な原因は,歯周組織,鼻腔,創し開部からの感染であった.
3.間接的には,骨移植時年齢,裂型,顎裂の大きさの因子が関与していた.
4.174例中,8歳から10歳までの犬歯未萌出症例は69例,39.7%であったが,この中に経過不良症例は認められなかった.
5.対策としては,術前に感染源を除去しておくこと,骨移植時期を遵守することが肝要であると思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9141K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|