巻号一覧
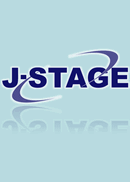
28 巻 (2003)
- 3 号 p. 203-
- 1 号 p. 1-
28 巻, 3 号
選択された号の論文の9件中1~9を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
布田 花子, 森田 修一, 山田 秀樹, 竹山 雅規, 花田 晃治, 齊藤 力, 高木 律男2003 年 28 巻 3 号 p. 203-211
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーこれまで一般の顎変形症患者に関しては,上顎骨LeFortI型骨切り術に伴い鼻部の形態が変化することは報告されているが,唇顎口蓋裂患者に関する報告は少ない。今回我々は,片側性唇顎口蓋裂患者において上顎骨LeFortI型骨切り術を施行した症例の,術前後における鼻部の形態変化について検討した。研究対象は,新潟大学歯学部附属病院にて外科的矯正治療が行われた片側性唇顎口蓋裂患者のうち,上顎骨LeFortI型骨切り術が施行された13名(男性4名,女性9名)である。また,対照群として唇顎口蓋裂を有さない顎変形症患者(骨格性下顎前突症)のうち上下顎移動術が施行され,上顎骨を前方もしくは前下方に移動した19名(すべて女性)との比較を行った。資料として,手術直前と術後6か月以上経過時に撮影された側面頭部X線規格写真および正貌顔面写真を用いて検討した。
結果として,1.唇顎口蓋裂群の術前における上顎骨(A点)の水平的位置は,対照群に比べて後方位にあり,上顎骨の劣成長が強い傾向を示していた。2.唇顎口蓋裂群の術前における鼻部形態は,鼻背角(∠1),鼻尖角(∠3)が小さく,鼻底角(∠2)は大きい値を示した。これは,鼻背の前方への突出傾向が弱く,鼻の上向き傾向も弱いことを示す。また,対照群に比べて鼻尖部は鋭角な形態を示していた。3.唇顎口蓋裂群の上顎骨の移動量に対する鼻下点(Sn)の変化量は,対照群よりも大きい値を示した。4.術前における唇顎口蓋裂群の鼻翼幅径は対照群に比べて拡いが,術後の変化量は小さかった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3782K) -
塚田 東香, 石川 博之, 高田 賢二, 高木 洋美, 飯田 順一郎2003 年 28 巻 3 号 p. 212-219
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー片側性唇顎口蓋裂の矯正治療において,初診時には上下顎の成長をコントロールすることによって顎関係の改善が期待できると判断された患者においても,治療の経過の中で外科的矯正治療に移行せざるをえない症例がある。本研究はこのような症例の顎顔面の成長変化の特徴を明らかにすることを目的とした。片側性唇顎口蓋裂男子患者を研究対象として,最終的に機能的咬合の確立のため外科的咬合改善術の適用が決定されたもの6名を外科群,矯正単独で治療したもの16名を非外科群とし,初診時より経年的に撮影された側面頭部X線規格写真を用いて顎顔面の成長変化を検討したところ,以下のような結果が得られた。
1.外科群では,上下顎の成長変化として矯正治療途中までは上下顎関係の前後的不調和の改善がのぞめたか,または悪化を防止できたが,思春期最大成長前後に下顎の前方成長により顎関係の不調和の増悪が認められた。
2,顎顔面各部の成長変化量より,外科群は非外科群と比較して上顎の前方成長量に明らかな差異は認められなかったが,下顎の前方成長量および骨体部の成長がより大きな値を示し,また下顎の前方回転(反時計回りの回転)の傾向が認められた。よって顎整形力について,外科群では下顎の前方成長の抑制効果が得られていないと考えられた。
3.外科群と非外科群の初診時顎顔面形態を比較したところ,両群を区別できる明らかな差異は認められなかった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1137K) -
Enkhtuvshin GERELTZUL, 馬場 祥行, 大山 紀美栄2003 年 28 巻 3 号 p. 220-228
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー目的:本研究の目的は,口唇口蓋裂患者における犬歯の萌出に対して,二次骨移植がいかに関与しているかに関し,萌出前の犬歯と裂隙の位置関係に着目して検討することである℃資料ならびに方法:犬歯の萌出前に骨移植術を行った21名(22歯;骨移植群),骨移植術を行わなかった16名(17歯;非移植群),および非裂側の犬歯(31歯;対照群)を含む合計37名の口唇口蓋裂患者の犬歯(70歯)の萌出について検討した。資料として,犬歯の萌出前と萌出後に撮影したオルソパントモグラムを用い,裂側の犬歯については,萌出前に裂隙に近接しているもの(groupI)と離れているもの(groupII)の2群に分けた。犬歯の歯軸と左右眼窩下点を通る直線のなす角を犬歯角とし,また,萌出後の歯槽骨の高さを評価し,検討した。結果:1.骨移植群と非移植群の問には萌出前の犬歯角に有意差を認めなかったが,骨移植群(p<0.05)および非骨移植群(p<0.01)と比べ対照群は有意に大きな値を示した。2.犬歯角の萌出前後の変化については,移植群では有意差を認めなかったが,非移植群(p<0.01)および対照群(p<0.0001)においては,萌出後に有意に大きな値を示した。3.萌出前後の犬歯角の変化について,骨移植群と非移植群で比較すると,groupIにおいては,骨移植群において有意に小さな値を示したが(p<0.05)が,groupIIにおいては2群間に有意差を認めなかった。4.萌出後の犬歯を支える歯槽骨の高さに関しては,groupIとgroupIIのいずれにおいても,骨移植群と非移植群の問に有意の差を認めなかった。結論:これらの結果より,裂隙に近接する犬歯(groupI)は,骨移植を行った症例では萌出前の歯軸傾斜を変えずに萌出するが,骨移植を行なわない場合は皮質骨の存在により,より垂直的に萌出する傾向が認められた。一方,顎裂から離れている犬歯(groupII)においては,骨移植の有無による萌出方向の変化の違いを認めなかった抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1180K) -
馬場 祥行, Eduardo Yugo SUZUKI, 北原 裕, 辻 美千子, 原田 清, 石井 正俊, 大山 紀美栄2003 年 28 巻 3 号 p. 229-237
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー目的:REDシステムによる骨延長法を適用した口唇口蓋裂患者における,上顎の骨延長術による変化,および術後経過観察期の変化について検討した。対象および方法:対象は,東京医科歯科大学歯学部附属病院においてREDシステムによる骨延長法を適用し,術後6ケ月以上経過した口唇口蓋裂患者8例で,適用時の平均年令は13歳3ケ月である。骨延長術直前,延長器の撤去時,および骨切り術後6ケ月以上経過時の側面頭部X線規格写真を用い,骨延長術中および経過観察期における上顎の変化について検討した℃結果:1.術中の水平方向における前方への変化はy最小4.Omm,最大14.5mmで,平均は9.4mmであった。また,経過観察期の変化はすべて前方移動に対する後戻りを示し,平均は一2.Ommで移動量の21.7%であった。術中および経過観察期の変化には有意の負の相関が認められた。2.術中の垂直方向の変化は,上方への変化を示したものが1症例,下方への変化を示したものが6症例,変化を認めないものが1症例で,平均は一2.9mmであった。また,経過観察期には,上方への変化を示したものが2症例,下方への変化を示したものが5症例,変化を認めないものが1症例であった。術中および経過観察期の変化には有意の負の相関が認められたが,術中の変化に対して7経過観察期に逆方向への変化を示したものは3症例のみであった。3.口蓋平面傾斜角の術中の変化は,時計回りおよび反時計回りの回転を示したものがともに4症例ずつで,平均は1.1。であった。一方,術中および経過観察期の変化には有意の負の相関が認められた。結論:成長期の症例を含む口唇口蓋裂患者の上顎骨にREDシステムを用いた骨延長法を適用し,平均9.4mmの大きな前方移動が達成され,本法の有用性が認められた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4255K) -
藤本 昌紀, 山本 一彦, 川上 正良, 梶原 淳久, 森崎 歩, 村上 和宏, 舘林 茂, 桐田 忠昭2003 年 28 巻 3 号 p. 238-249
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー奈良県立医科大学口腔外科開設後20年間に当科を受診した口唇裂口蓋裂患者332例について臨床統計的検討を行い,以下の結果を得た。1.症例は男性181例,女性151例で,男女比は1.2:1であった。2.裂型別分類では,唇裂66例(19.9%),唇顎裂が34例(10.2%)唇顎口蓋裂が127例(38.3%),口蓋裂69例(20.8%),粘膜下口蓋裂26例(7.8%),口蓋垂裂13例(唇裂および唇顎裂4例を含む)であった。3.破裂部の側性では,唇裂,唇顎裂,唇顎口蓋裂,歯槽裂患者228例のうち,片側性が178例(78.1%),両側性が49例(21.5%),正中が1例(0.4%)であった。片側性の左右比では,左側が111例(62.4%),右側が67例(37.6%)で,左右比は1.7:1であった。4.家系内の発現についての検索がなされていたのは281例であり,このうち18例(6.4%)に家系内発現があった。5.他部位合併先天性形態異常は41例(12.3%)にみられ,部位別では心臓が最も多く14例(4.2%)にみられた。6.手術は215例に施行した。このうち一次症例では227例中171例(75.3%),二次症例では105例中44例(41.9%)であった。術式は口唇形成術が127例,口蓋形成術が101例,顎裂部二次的骨移植術が26例,外鼻形成術が22例であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1635K) -
結城 美穂, 河田 俊嗣, 谷本 幸太郎, 宮本 義洋, 丹根 一夫2003 年 28 巻 3 号 p. 250-260
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー近年,口唇口蓋裂患者の顎裂部への自家腸骨海綿骨細片移植が積極的に行われ,良好な治療成績が得られている。今回,比較的軽度な顎裂を有する患者において,自家腸骨の移植なく骨再生誘導(GBR)法単独治療によって顎裂部の形態を改善し,良好な治療結果を得たのでその概要について報告する。症例は初診時年齢9歳6ケ月の女子で,上顎前歯の捻転を主訴として来院した。両側口唇裂および左側顎裂を有し,生後3ケ月時に両側口唇形成術を受けていた。上顎歯列の狭窄は認められず,上顎両側中切歯および右側側切歯が90。捻転を呈し,X線写真上ではe上顎右側犬歯,側切歯間と左側中切歯唇側に1委小過剰歯が,上顎左側中切歯,側切歯間に1mm程度の顎裂が確認された。上顎左側側切歯の萌出に合わせて,顎裂部に吸収性乳酸/グリコール酸共重合体バリアメンブレンを用いたGBR法を適用した。全身麻酔下で,上顎左側中切歯唇側の過剰歯を抜去し,周囲歯槽骨を一層切削することにより出血を促した。その後鼻腔底を縫合し,メンブレンを基底面に置き,裂隙部をメンブレンで覆うようにメンブレンと歯肉とを縫合した。足背より採血.した静脈血をメンブレン内に約10cc注入して歯槽堤の形態を修正し,予め剥離した歯肉弁を縫合して手術を完了した。術後3週間でマルチブラケット装置を装着し,上顎左側中切歯の捻転改善および上顎側切歯の唇側移動を行った。術後3ケ月のX線写真上で,顎裂相当部に海綿骨の良好な形成が認められ,同部位への歯の移動が可能となった。このことから,小さな顎裂に対してはGBR法による骨再生が有用な手法となり得ることが明らかとなり,臨床応用の展開が期待される。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (17791K) -
松本 尚之, 農端 俊博, 飯田 拓二, 大矢 卓志, 辻 準之助, 川本 達雄2003 年 28 巻 3 号 p. 261-270
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー初診時年齢6歳11ヵ月の上顎歯槽突起裂および口蓋裂を伴う正中上唇裂に起因する骨格性下顎前突症の患者を,長期にわたり治療,管理する機会を得た。患者は上顎の劣成長と上顎前歯の舌側傾斜を示していた。また,上顎歯列弓の狭窄が認められた。第0段階の治療として,7歳0ヵ月時に拡大装置による歯列弓の拡大を行い,また,chincapによる成長のコントロールを行った。第二段階の治療として,9歳11ヵ月時に舌側弧線装置による前歯部の被蓋の改善を行い0また,上顎骨の前方成長の促進を期待して,上顎前方牽引装置を着用した。そして第三段階の治療として,11歳9ヵ月時にマルチブラケットシステムを用いた治療を非抜歯にて行い,上下歯列の咬合の緊密化を図った。その後,咬合の安定が得られたことを確認し,成長発育の終了したと考えられる16歳10ヵ月時に動的治療を終了し,保定を行った。23ヵ月の保定期間中も咬合の安定は得られていた。治療結果より,今回経験した上顎歯槽突起裂および口蓋裂を伴う正中上唇裂の場合,長期間顎外固定装置を使用することにより,効果的な下顎骨の成長コントロールができ,骨格のバランスを保持できることがわかった。しかしながら,上顎前歯の移動に関しては,容易に離開が生ずることに留意する必要があることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (15554K) -
古崎 幸恵, 吉増 秀實, 佐藤 豊, 宮崎 秀隆, 松本 亨, 岡田 尚子, 天笠 光雄2003 年 28 巻 3 号 p. 271-276
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーLarsen症候群は先天性多発性関節脱臼と前額突出,扁平な鼻橋,眼間開離などの顔貌を特徴とする稀な疾患で,30-50%に口蓋裂を伴うとされる。本症候群は他にも多数の症状を有するため,口蓋裂を伴った患者の場合,口蓋形成手術の時期の決定や術前術後管理には十分な検討と配慮が必要である。今回われわれは,口蓋裂を伴ったLarsen症候群患児について治療する機会を得たので報告する。患児は生後1か月の女児で,口蓋裂の治療を目的として当科に紹介された。患児は生下時より頸椎亜脱臼,脊椎側轡,両側股関節脱臼,両側内反足,喉頭気管軟化症,漏斗胸などがあり,Larsen症候群の診断を受けた。また,呼吸困難のため出生直後より人工呼吸器を装着していた。軟口蓋裂を認めたが,哺乳において鼻漏出はみられなかったためHotz床は使用せず,まずは他科での治療に専念し全身状態が落ち着いてから当科で治療を行う方針となった。8歳時に当科を再受診した際,気管切開が施行され,気管カニューレが留置されていた。しかしカニューレ端を閉鎖することで発語可能であったため,鼻咽腔閉鎖不全に起因する構音障害の改善を目的として口蓋形成手術を行うこととした。8歳5か月時にFurlow法による口蓋形成が施行された。術前術後の管理においては,1)肺合併症,2)生活環境の変化に対する心理状態,3)歩行機能,4)コミュニケーションなどに配慮した。術後1年の経過は良好で,構音障害は改善しつつある。今回のように重篤な合併奇形や疾患を有する場合,治療時期の決定や術前術後の管理には十分な配慮が必要であり,他科との連携も重要であることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7293K) -
藤原 百合, 相野田 紀子2003 年 28 巻 3 号 p. 277-279
発行日: 2003/10/30
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー
- |<
- <
- 1
- >
- >|