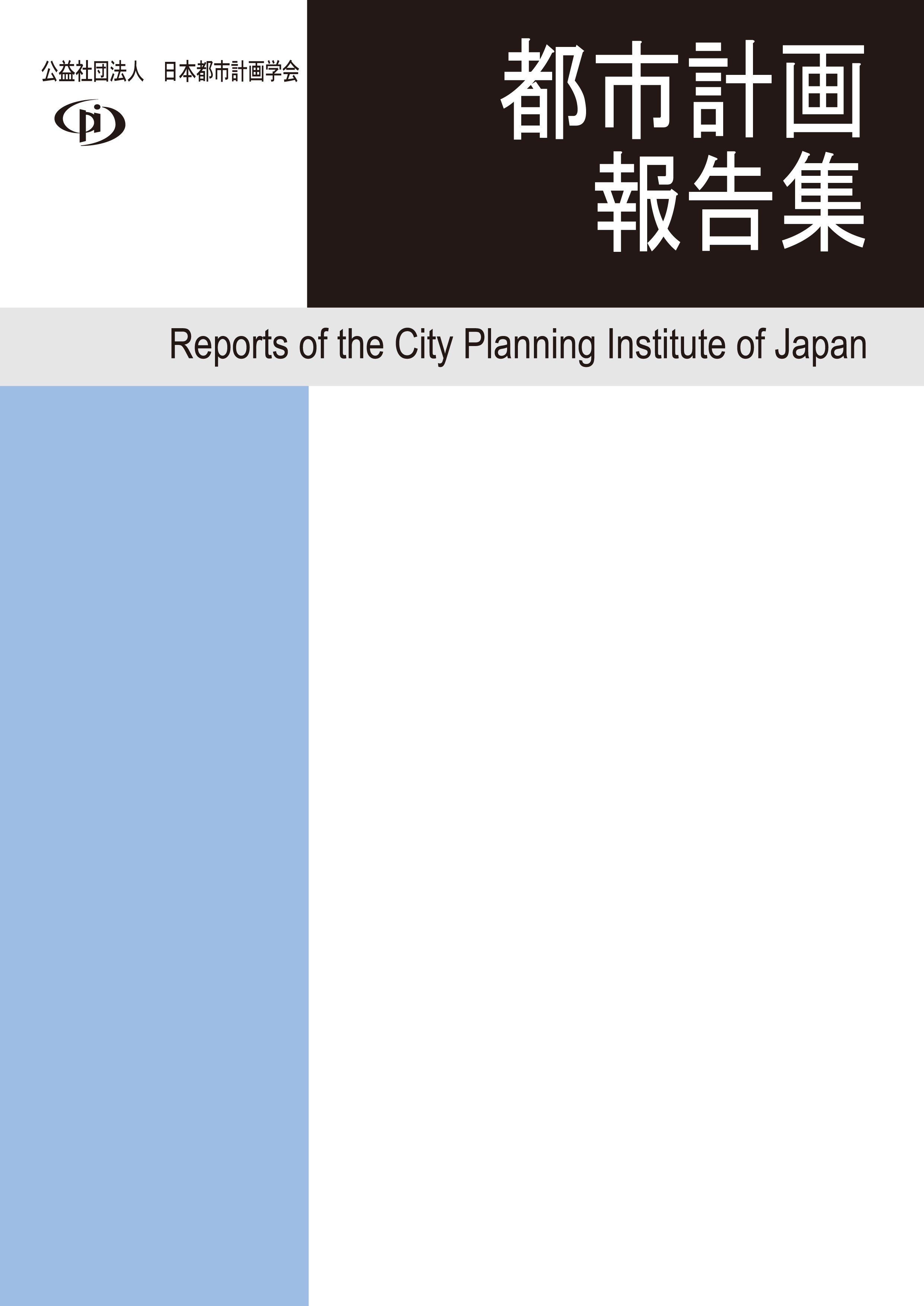
- 4 号 p. 259-
- 3 号 p. 228-
- 2 号 p. 106-
- 1 号 p. 1-
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
人口変化に対する柔軟な対応策として東 達志, 御手洗 陽, 小松﨑 諒子, 谷口 守原稿種別: 研究論文
2019 年18 巻3 号 p. 228-233
発行日: 2019/12/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書 フリー近年,自動運転車に商業や医療といった都市機能を搭載したADVUS(Automated Driving Vehicles with Utility Services)の開発が進んでいる.ADVUSは,無人で柔軟に都市機能を供給できることから,導入することで生活利便性の向上が期待される.しかし,ADVUSを導入する地域特性を考慮しなければ,結果的に既存の固定施設と競合し,施設を撤退させることが懸念される.そこで本研究は,「都市の人口変化時に生じる都市機能不足に対応する」という目的でADVUSを導入することを提案し,上記に該当する地域を全国の市区町村を対象に抽出した.その結果,人口減少地域では,特定の中山間部に位置する市区町村や人口減少率が特に高い市区町村が抽出された.また,人口増加地域では,大都市近郊のベッドタウンや新たなインフラ開発が行われた市区町村が抽出された.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1557K) -
“医療MaaS”の実現を見据えた基礎的検討相馬 佑成, 笹林 徹, 谷口 守原稿種別: 研究論文
2019 年18 巻3 号 p. 234-239
発行日: 2019/12/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書 フリー日本では人口減少・高齢化が進んでおり,医療分野に対する需要が高まっていくことが想定される.そういった中,患者の通院に対して,負担を軽減させるサービスの提供として,医療MaaSの検討がなされている.そこで本研究では,医療MaaSの実現を考える上で必要となる現状の通院行動分析を行った.結果として,(1)公共交通機関の整備水準によって,通院に利用される交通手段が変化するが,乗用車の運転割合が年齢階層に関わらず高い; (2)通院行動の発生には都市特性,集中には医療施設の充実度が影響を及ぼす; (3)高齢者ほど,自宅周辺の医療施設に通院する傾向があること,などが明らかになった.
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1931K) -
旅館業法の簡易宿所を中心にオウ チョウキ, 吉田 友彦原稿種別: 研究論文
2019 年18 巻3 号 p. 240-245
発行日: 2019/12/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書 フリー近年都市開発による京町家の滅失が進行している。その一方、京町家を宿泊施設に改築した例も見られる。本研究の目的は、京町家まちづくり調査でも対象とされてきた京都市の都心4区(上京区・中京区・下京区・東山区)の京町家型の簡易宿所を対象として、京町家型簡易宿所の所有者の実態把握を通じて、京町家の保存と活用への影響を考察することを目的とする。旅館業法許可施設一覧を基に、登記事項証明書の調査を通じて、京都市4区京町家型簡易宿所の所有者の実態を明らかにした。また、京町家型簡易宿所近年の流通量が増加は京町家の活用促進を示すものと捉えられる。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1773K) -
高齢者・障害者・子育て世帯居住安定化推進事業の事例調査から廣瀬 雄一, 小泉 秀樹, 大月 敏雄原稿種別: 研究論文
2019 年18 巻3 号 p. 246-253
発行日: 2019/12/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書 フリー本稿では、国交省の補助事業である⾼齢者・障害者・⼦育て世帯居住安定化推進事業の⾼齢者を対象にした事例を対象とした。研究の視点として、低廉性の確保、地域との接点をもてるコミュニティづくり、重度化対応のためのケア確保の3点を据え、住み慣れた地域内で住み続けるために、⾼齢者向け住宅に必要な建築計画の知⾒を次の通り提⽰した。低廉性の確保においては、中古不動産の活⽤であり、中でも今後統廃合で余剰が出ることが予想される⼩学校をはじめとする地域に散在する公的空間ストックを活かして、より利⽤しやすい価格の住宅整備に繋げることである。コミュニティづくりにおいては、空間構成では空間構成の多様性や、居住者どうしの接点が⽣まれる動線計画、住宅内外から利⽤可能な併設施設などが挙げられた。いずれにしても⼊居者に繋がりの選択肢を数多く⽤意することで、要介護状態でも⾃⽴時に近い社会性の維持や構築が可能になると考える。ケア確保を物理的な近接性も踏まえて検討した。重度化しても住宅内に限らず、隣地や近接地に訪問してくれる事業所の⽴地があることで、外部確保という形も含めてケア確保できていることが重要である。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1250K) -
「みんなの畑プロジェクト」の初めの2年間の経過と効果内野 絢香, 加藤 浩司原稿種別: 研究論文
2019 年18 巻3 号 p. 254-258
発行日: 2019/12/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書 フリー「旧八女郡役所」は八女福島伝建地区に位置し、明治期に建設された大規模な木造建物である。ここでは、郡役所の外部空間で行っている「みんなの庭づくりプロジェクト」開始からの2年間の取り組みについて報告し、この効果について検討する。結果として、園芸部という郡役所と関わりをもつサークル活動をつくりだすことができた。これに加え、誰でも参加しやすく、近所の人との接点も活動を通じてもつことができた。今後の調査として、園芸部での活動が住民同士のつながりの場になっていることや、園芸部から新しい活動がうまれることで新たな効果がみられるなどの可能性について必要であることが分かった。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1956K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|