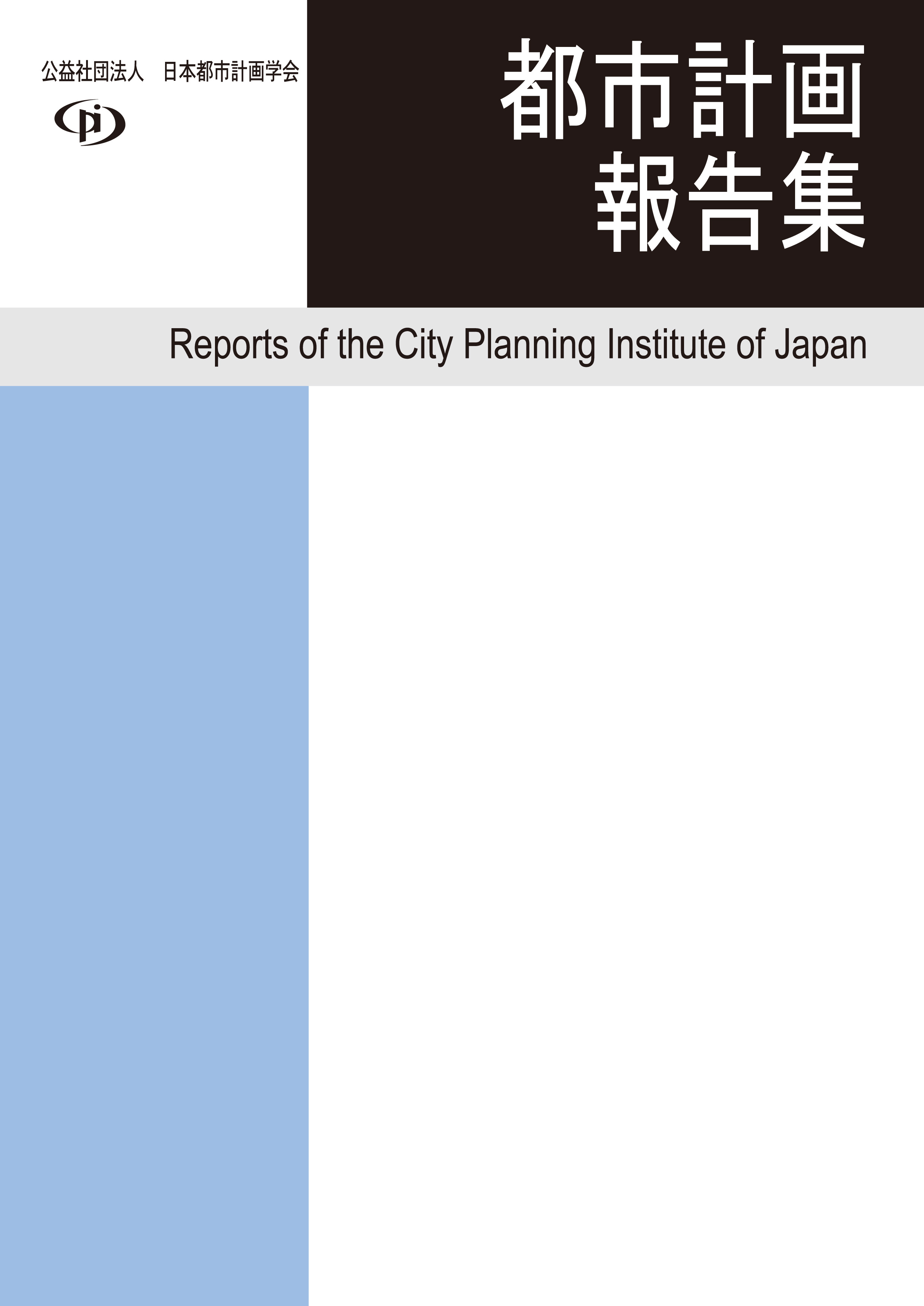-
永田 優河, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
341-347
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、歴史的風致維持向上計画を策定した市町村のこれまでの取組の実態を計画内容の変更に着目して分析し、歴史的風致維持向上計画の中長期的な運用における課題を明らかにすることを目的とするものである。本研究を通じて、(1)第1期計画ではハード整備が推進され、第2期計画では後継者・人材の確保・育成を中心としたソフト事業の展開が課題となっていること、(2)今後はこうした市町村の需要の変化に対応した支援策の改善が求められていることが明らかになった。以上を踏まえ、今後、歴史まちづくりを進める上では、後継者・人材の確保・育成をはじめとするソフト施策にかかわる支援策の充実が必要であること指摘する。
抄録全体を表示
-
福島県57市町村を対象とする事例研究
三浦 智啓, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
348-355
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、福島県内の公共施設等総合管理計画策定済み市町村を対象に、公共施設等総合管理計画策定後の地方公共団体における公共施設マネジメントの現状と課題を明らかにすることを目的とするものである。本研究では、(1)施設の方針のみを定めた個別施設計画を策定する市町村が多く存在すること、(2)施設保全に重きが置かれ、再配置事業の実施や実施予定がない市町村が多く存在することを明らかにしている。以上を踏まえ、今後の人口減少社会を見据えながら、公共施設等総合管理計画体系を、都市計画等との連携と住民との協働を前提として、公共施設の量的な削減と立地にかかわる計画的な再配置による質的な維持・向上を図る計画体系とするための制度的な条件を整備することが必要であると指摘する。
抄録全体を表示
-
浅川 杏珠, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
356-361
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
相馬野馬追は、福島県相馬市と南相馬市を中心に毎年夏に行われる伝統的な祭礼である。本研究は、相馬野馬追がどのように変化を遂げ、何百年もの間絶えず続けられてきたのかを明らかにすることを目的としている。研究の結果、相馬野馬追は徐々に発展していき17世紀末で一種の完成を迎えたこと、何度か消滅の危機に瀕するものの、その度に形を大きく変えることで対応し、消滅を免れていたこと、特に明治時代に大きな形態変化を経たため現在の相馬野馬追は江戸時代のものとは内容が異なることが明らかになった。
抄録全体を表示
-
関西圏の政令指定都市を事例として
岡本 瑞生, 太田 尚孝
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
362-365
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
私たちは、政令指定都市を事例にバリアフリー基本構想制度が果たす機能を調査した。本研究の目的は、バリアフリー基本構想が果たす機能を明らかにすることと、重点整備地区の設定方法の提案を行うことである。本研究は、政令指定都市のバリアフリー基本構想の文献調査を行い、担当部署や計画体系の違いを明らかにした。次に、関西圏の政令指定都市のバリアフリー基本構想に焦点を当て、自治体の担当者へヒアリング調査を実施した。調査結果に基づき、バリアフリー基本構想制度がもつ機能を明らかにし、政令指定都市における重点整備地区の設定方法について提案した。本研究は、バリアフリー基本構想の重要性を明らかにし、今後の政令指定都市における重点整備地区の設定方法を示唆するものである。
抄録全体を表示
-
藤澤 忍, 村上 修一
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
366-370
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
都市では快適な空間を求めて再開発が行われているが、道に草木が生えていることなど、場所の歴史である「場の固有性」への配慮が欠けている。しかし、場所とは日常生活の中で形成される風景や空間であることから、その更新には、景観に配慮し場所の固有性を重視した手法が必要である。そのため本研究では、クリストファー・アレキサンダーのパターン・ランゲージを批判的に検証した上で、自らを被験者として,多くの空間を記録し、場所を学び、即興で更新する方法を試行した。その試行結果にもとづき、空間経験を深めながら明らかに出来た場所の固有性を尊重する更新の手法とその共有伝達の方法について考究した。
抄録全体を表示
-
東京都の保健所・保健センターを対象とした洪水・高潮による浸水想定
坂巻 哲, 土肥 博, 大島 一夫, 阿南 朱音
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
371-374
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
国土交通省が国土数値情報で公表する荒川,利根川および高潮の浸水想定区域図を用いて,保健所施設(東京都の保健所・保健センターの計160施設)を対象に,河川の氾濫・決壊および高潮の浸水想定による災害リスク分析を行った.その結果,想定最大規模の洪水で浸水が想定されている保健所施設は,荒川で41施設(全体の25.6%),利根川で18施設(全体の11.3%)であった.想定し得る最大規模の高潮で浸水が想定されている保健所施設は,46施設(全体の28.8%)であった.こうした保健所施設では,浸水リスクの低い場所への施設移転やバックアップオフィスの設置など代替機能の対策,止水板の設置などのハード面での浸水対策が必要と考えられる.また,ソフト面での取り組みとして,保健所施設の在勤者が迅速に避難できるよう防災行動を時系列的に整理するタイムライン(防災行動計画)の策定が必要と考えられる.
抄録全体を表示
-
「都市経営論」発展の背景とその特性について
今津 海, 大西 春樹
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
375-378
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
今日、様々な分野において「都市経営論」が注目を集めている。しかしながら、「都市経営論」に関する学問的位置付けやその意義については、未だ不明瞭な点も多い。今日における「都市経営論」の学問的位置付けや意義を検討するにあたり、その端緒として、本稿では、「都市経営論」発展の経緯や先行研究などを概観しながら、「都市経営論」が有する特性などについて整理した。結果として、今日における「都市経営論」の学問的位置付けなどを検討する上では、市民福祉の向上や官民連携、学際性や目的志向型アプローチの必要性といった観点が重要であることを指摘した。
抄録全体を表示
-
三角ダイアグラムを用いた地域分類を踏まえて
平原 幸輝
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
379-380
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
日本社会ではサービス経済化が進み、産業構造の高度化が進んできた。一方で、こうした変化は、個別の産業が集中している地域においても生じているのか否か、本研究では調べた。本研究では、三角ダイアグラムに基づき、日本の市区町村を、産業構造の状況に応じて分類した。その結果、1980年代から2010年代にかけて、9割程度の自治体でサービス経済化が進み、半数程度では産業構造の高度化が実現した。社会地図からは、産業構造の高度化が実現した地域は首都圏の都心部に限られるような地域間格差が生じていることが確認された。
抄録全体を表示
-
東京圏を対象とした分析を踏まえて
平原 幸輝
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
381-382
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
日本では、高度経済成長期には製造業従事者の多い地域に人口が集中していたのに対し、低成長期には第三次産業従事者の多い地域に人口が集中していた。本研究では、地域における産業構造の状況と、若年層の人口流入の関連性を明らかにするために、東京圏の市区町村を分析単位として、相関分析を行った。その結果、金融・保険・不動産業従事者が多い地域ほど、若年層の人口流入が多いことが示された。また、サービス業従事者が多いほど人口流入は多く、製造業従事者が多い地域ほど人口流入は少なくなっていることが確認された。
抄録全体を表示
-
都市計画協力団体と協同した広島市の導入事例から
黒瀬 比呂志
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
383-385
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿は、2020年に制度を導入した広島市の事例を紹介しながら、地方自治体における生産緑地制度の導入に必要な観点を都市行政の立場から考察したものである。まず、本市の都市農業の現状と相続問題を確認した後、生産緑地に必要な要件及び農業協同組合との関係を整理し、最後に「農」と共生したまちづくりに関する今後の方向性について論じる構成としている。
抄録全体を表示
-
白 林, 卯月 盛夫
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
386-390
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
この研究報告は、携帯電話のGPS位置データを用いて、来場者人流の統計分析する方法とシステムツールの紹介記事である。開発システムツールには、来場者の統計と地理位置を表示するため、MySQLデータベースとQGIS地理情報システムが実装された。これら2つのシステムを連携させることで、来場者の滞在状況や移動状況を地理的に視覚化することができた。これにより建築および都市計画におけるGPSビッグデータテクノロジーの適用性を確認することができた。
抄録全体を表示
-
中 麻衣, 宮地 茉莉, 岡 絵理子
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
391-394
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、日本の「道の駅」が地域性をどのようにして意匠計画にとり入れられているか明らかにすることを目的としている。 まず、月刊誌「新建築」の17作品から地域性を表す語句を抽出し、9項目に分類した。 これらの項目を使用して、国土交通省が選定、認定した145のモデル「道の駅」・重点「道の駅」を分類した。 その結果、それらの半分は、意匠計画に関する地域性の記述がなかった。 つまり、モデル「道の駅」・重点「道の駅」は建物として地域性を取り入れることは重要視されていない。 そのほか、41の「道の駅」は「モチーフ」を使って地域性をとり入れていた。 モチーフは「道の駅」の意匠計画で地域性を表現する手段である。 地域性は分類した9項目をはじめ、さまざまな形で表現することができる。
抄録全体を表示
-
村上 雄哉, 宮地 茉莉, 岡 絵理子
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
395-398
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
2018年に尼崎城天守が再建され、市に寄贈された。 本研究の目的は、再建された天守を人々がどのように認識しているかを調査し、再建の意義を探ることである。 2021年12月、天守閣の来訪者を対象にアンケート調査を実施し、154票の回答を得た。 その結果,天守閣は来訪者に歴史的な展示やイベントを提供しており、観光スポットとして認識されていることが分かる。 観光客が地域の歴史に関心を持つ機会になり、それが市の観光施策に寄与することができる。 再建された天守は都市のイメージを向上させ,歴史的な都市計画を推進した。
抄録全体を表示
-
奈良県吉野郡吉野町上市を事例として
石井 茜, 室﨑 千重, 近藤 民代, 齋藤 真奈夢, 前田 充紀, 西田 極
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
399-404
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年増加する多拠点生活者を地域で受け入れるためには住民からの理解が必要である。本研究では、多拠点生活者が住民に与える影響を捉えた上で、多拠点生活者と住民の出会いを促す要素と仕組みを明らかにすることを目的とする。本研究から、多拠点生活者との出会いにより住民に非日常的な機会がもたらされ、地域の魅力を実感する効果があることがわかった。多拠点生活者と出会う機会は「サービス内容」と「20名以下規模のイベント」の2種類があり、住民参加を促す周知方法は、機会の種類・開催場所への住民意識により異なる。さらに、多拠点生活者と住民が出会う機会を増やすためには、住民から信頼される「地域仲介人」の協力を得ることが重要である。
抄録全体を表示
-
土器川において公園として利用される霞堤3例の現地踏査報告
村上 修一
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
405-408
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
堤防が不連続である霞堤は,堤防のすき間をとおしてまちと川との近しい関係を創出すると予想される。既報において国内48水系296箇所のうち公園緑地としての利用が確認された38箇所について,堤防のすき間によるまちから川に対する可視性や接近容易性の検証が,この仮説を実証するための課題として残されている。本稿は,38箇所のうち土器川の3箇所を踏査した結果の報告である。踏査の結果,以下のことが判明した。1)まちから川に対する可視性や接近容易性を低下させる要素として,かさ上げされた地盤,樹林,建物や施設,立入の規制された土地が存在する。2)霞堤であることが利用者にとって認識可能な空間的特徴を公園緑地が有する。
抄録全体を表示
-
西坂 涼
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
409-414
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿は、国土交通省による都市公園の評価事業を分析して、評価指標と公園機能の関係を明らかにした。評価指標と機能の対応を分析すると、国土交通省が示す7つの機能のうち、景観機能に関する評価指標が明示されていないこと、観光や活力の機能は、関連する事業の有無などが評価指標となっており、実際の都市公園の観光や活力の状況が測られていないことなどがわかった。費用対効果分析等の従来の定量的評価に加え、景観・観光・活力など人間の利用に基づく機能の発揮を評価する指標の開発が求められる。
抄録全体を表示
-
定額住み放題サービス利用者を対象として
前田 充紀, 近藤 民代, 室﨑 千重, 西田 極, 石井 茜, 齋藤 真奈夢
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
415-422
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、定額済放題サービスを利用した多拠点生活における居住動態パターンとライフスタイルを模索していくプロセスが、どのように新たなライフスタイルへの志向を形成しているのかを明らかにする。①移動がある場所へ訪れるための手段でなく、環境を変化させる目的になっている。②その場限りでありながら生活の情報交換を通じて多様な価値観にふれる関わり「流動的共生員」を求めている。③居住動態パターンは、生活に対する要求の影響を受け、そのパターンの違いにより志向も変化する。このライフスタイルは、従来の定住および地縁コミュニティで暮らす志向を持った人と異なり、自由に住む場所を移動し、働き、人と関わりたい志向を持った人のための生活である。
抄録全体を表示
-
川崎市麻生区を対象として
髙木 真育, 室田 昌子
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
423-426
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、東京30km圏域の近郊にある川崎市麻生区を対象に、居住者の住宅に対しての清掃管理意識と定住意向や今後の住まいの希望を把握した。それぞれ住宅形態別の居住者の清掃管理意識の実態や定住意向、住み替え、地域継承のためのあり方を把握し、清掃管理負担と住み替えの関係性分析した。
抄録全体を表示
-
ガントゥムル ノミン-エレデネ, 円山 琢也
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
427-429
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
モンゴル・ウランバートル市では,自動車依存の削減を目的にBRTの導入が検討されていた.ここで,多くの居住者はBRTを詳しくは知らないと考えられるため,BRTの利用意向調査では,適切な調査票の設計が重要となる.本研究では,BRTの説明方法が利用意向に変化を与えるかどうかを検証する.具体的に,(1) 文章と写真,(2) 文章とイラスト,(3) 文章のみ,の3種類の調査票を利用したWebアンケートを実施した.ウランバートル市民79人の回答が得られ,それらは3種類の調査票にランダムに割り当てられた.結果,(2)文章とイラストの調査票が最も利用意向が高いことが分かった.この結果は,BRTの表現法がアンケート調査で重要であることを示唆する.
抄録全体を表示
-
港北ニュータウン地域を対象に
田中 さくら, 室田 昌子
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
430-433
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、緑地協定の一人協定が締結され、一定年数の経過した成熟化した住宅地について、その現在の環境特性が地価に対して影響を与えているのか、またどのように影響するのかを把握分析する。緑化の状態として、朴らの一人協定では沿道部の緑化効果が認められるとの指摘をもとに、沿道部を重視し、その地価への効果をヘドニック法を用いて検討した。その結果、緑視率や緑地協定区域の面積は有効な説明変数となることを確認した。
抄録全体を表示
-
佐倉 弘祐, 磯部 聖太, 鈴木 悠
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
434-437
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、場所、立地、人の特性に着目して、コミュニティガーデンの空間デザインを分析した。研究対象地は、2021年12月の6日間で訪問した9箇所とした。研究方法は、主に、現地調査とヒアリング調査である。場所の特性については、どのような場所であっても、その場所の欠点以上に利点が多い場合には、CGになり得ることが明らかになった。立地の特性については、地域の歴史や風土、住環境が、空間デザインの決定要因になっていることが明らかになった。人の特性については、初期メンバーが全体のレイアウトやコンセプトを構築しており、それ以外の部分に関しては、組織や参加者の変化に応じて緩やかに変えていく事例が多いことを明らかにした。
抄録全体を表示
-
福岡県を事例として
須山 涼乃, 片山 健介
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
438-442
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
全国的に都市の「スポンジ化」が課題となる中、民間事業者のアイデアを活用した低未利用な公的不動産の利活用が求められている。本研究は、公民連携による公的不動産の利活用を促進するための事業の実態と課題を明らかにし、今後の取り組みにおいて必要とされる方策について考察することを目的とした。まず、全都道府県のホームページを分析したところ、民間の利活用提案を随時受け付けるためのページがあるのは7道県であった。次に、福岡県を取りあげてケーススタディを行った。福岡県では、街なかを対象に県と各市町村の所有物件を掲載したデータベースを構築し、民間事業者が情報を得やすい工夫がみられた。一方で、実際の利活用では、都市計画部局だけでなく企業誘致部局との連携が課題であった。
抄録全体を表示
-
民間の空き家ビジネスに着目して
森山 彩夏, 片山 健介
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
443-447
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
全国各地で空き家問題が深刻化する中、民間による空き家ビジネスが増加している。本研究では、民間のマッチングサイトに着目して、空き家ビジネスの実態を明らかにし、空き家のマッチング促進に向けた官民連携の可能性について考察することを目的とした。まず、新聞記事検索により抽出したマッチングサイトの特徴を分析したところ、対象エリア、業務範囲、行政との連携の有無などに多様性がみられた。また、官民連携を行っているマッチングサイトのケーススタディから、官民連携によって、自治体の空き家バンクと民間の空き家マッチングサイトの課題を相互に補完することができ、空き家問題の改善と地域活性化につながる可能性が期待される。
抄録全体を表示
-
近藤 紀章, 松本 邦彦, 石原 凌河, 笹尾 和宏, 竹岡 寛文, 中野 優
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
448-455
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本論では、文献から「散歩」に関する研究の拡がりを明らかにするために、都市空間や都市デザインとの関係性の観点から95編の文献を整理した。散歩の定義や目的として、実社会の要請に応えるために「都市活動」が定着した時期が転換期といえる。また、研究の拡がりとしては、人を対象とした研究は蓄積されているものの、空間や文献を対象とした研究、時系列比較や国際比較の研究の蓄積が少ない。目的を持って歩くことが実際の都市空間に適用されることで、「いかに人を(より)歩かせるか」という計画の視点が組み込まれている。しかし、「人はなぜ無目的に歩くのか」という原論が求められた初期の方が、自由で大胆な発想が、散見された傾向がある。
抄録全体を表示
-
上越地区の調査結果と県全域の分析
那須野 拓磨, 岡崎 篤行
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
456-459
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
日本酒の年間消費料や清酒製造場数は減少傾向にあり、酒蔵の持つ地域的特徴の損失を引き起こす可能性がある。一方近年、酒蔵建築を観光事業として活用する動きが見られ、地域の活性化につながっている。そこで、日本の酒蔵の残存状況や酒蔵建築の実際の活用状況を明らかにするために、網羅的な調査を行う必要がある。既往研究では、新潟県の下越、佐渡、中越地区の調査をしており、本研究では上越地区の調査と既往研究の結果を含む新潟県全体のまとめを行う。
抄録全体を表示
-
近畿・山陰地方日本海沿岸を対象として
宮澤 崇史, 岡崎 篤行
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
460-463
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
日本では近世の町の歴史や文化を知るための研究が行われている。しかし、城下町に比べて港町の研究は少ない。日本海沿岸において近世初期に城下町の外港として建設された港町の一群があることは広く周知されていない。本研究の目的は、日本海沿岸に位置する近世港町の成立経緯と都市形態を明らかにすることである。分析の結果、港側の町構造は合理的に計画され、一方、陸側は無秩序な傾向であった。
抄録全体を表示
-
植野 惟真, 岡崎 篤行
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
464-467
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
花街は日本の伝統文化の多くの側面を受け継いでいる。かつて、支援は旦那とよばれる経済界の顧客により行われていた。しかし、近年では、支援する主体や、支援内容が変化している。本研究は、全国の花街における支援を行う組織の運営及び活動実態を明らかにすることを目的としている。結論として、支援を行う組織は、全国に61箇所ある花街のうちの37箇所にあった。また、各花街においては、初めに商工会議所による直接支援(芸妓の技能・備品・生計、花柳界組織の運営)が、次いで間接支援(営業機会、広報)を行う組織が設立されるという流れがみられた。
抄録全体を表示
-
インターネット地図機能を用いた基礎的広域調査
丸山 想世可, 岡崎 篤行
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
468-469
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
伝統的な民家の形式である町家の棟向きは、それらが建てられている地域の特徴を表す重要な要素である。近年町屋の数は減少傾向にあるが、町屋の棟向きは局所的に変化することがわかっているため、それらを把握するためには広域的・網羅的な調査が必要である。本研究では栃木県全域を調査対象としている。また、町屋の棟向きの分布に加え、町屋の残存概況と細部意匠などの外観特性についても調査を行った。県内では、複合型及び竪屋優勢の集落が多く見られ、京都型町屋は確認できなかった。町屋の密度が高い上位10集落のうち6集落が文献に記載がなかった。外観特性として石張りの外壁を持つ町屋や両側戸袋などが確認できた。
抄録全体を表示
-
インターネット地図機能を用いた基礎的広域調査
国峯 泰己, 岡崎 篤行
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
470-471
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
町屋の屋根の棟向きは、街並みを形成する重要な要素である。近年、町屋が減少しているため、基礎調査が急務である。また、局所的に屋根の棟の向きが変わることがあるため、集落単位で全国的な調査が必要である。本研究は、茨城県を対象とし、各集落の主要地区における町屋の残存状況についても調査する。古地図、国絵図などの史料をもとに、インターネット地図機能を用いて簡易的かつ広域的に調査をする。その結果、36集落で517棟の町屋が見られた。屋根の棟の向きは茨城県全体で似た傾向があることが分かった。また、「店蔵」を持つ町屋や、2階の窓の両端に戸袋を設けている町屋が多く見られた。
抄録全体を表示
-
近藤 紀章, 柏尾 珠紀, 中野 桂
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
472-477
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、移動販売の一部であり、小さな経済活動でもある「行商」に着目し、文献調査を通じて、行商が構築する社会経済圏を再解釈するための基礎研究を行うことを目的としている。 その結果、以下のことが明らかとなった。研究テーマとしての行商が衰退する過程で、流通研究や移動販売の研究に統合、包摂された。 次に、行商は生活を支える移動販売という「補完型」であった。小さな経済活動の意味や内容が変化するなかで、「補完型」を母胎として、社会問題の解決に対応する「救済型」と、新しい活動形態を積極的に生み出す「価値創造型」が生み出された。
抄録全体を表示
-
高齢者を中心とした地域コミュニティ再生の視点から
新保 奈穂美
原稿種別: 研究論文
2022 年20 巻4 号 p.
478-481
発行日: 2022/03/03
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
都市の農には、高齢化社会で重要となる健康増進やコミュニティ形成など、さまざまな機能がある。日本では街区公園と呼ばれる最小タイプの公園が、身近で通いやすいコミュニティガーデンを設置できる場となり得る。しかし、都市公園での野菜や果物の栽培・収穫に向けては、一般に公益性の観点から不適切な行為とみなされることが障害となっている。本報告では、この問題を克服するために、富山市が街区公園を活用した自治体コミュニティガーデン事業を開始した経緯を紹介する。その主な成果は以下の通りである。1)自治体は、コミュニティガーデンが都市住民、特に高齢者にとって有益であり、現在の街区公園のニーズを満たすのに有効であることを担当省庁に納得させることができた。2) コミュニティガーデンの主導権は、公的なプロセスを通じて、地域住民で構成される公園愛護会に委ねられていた。
抄録全体を表示