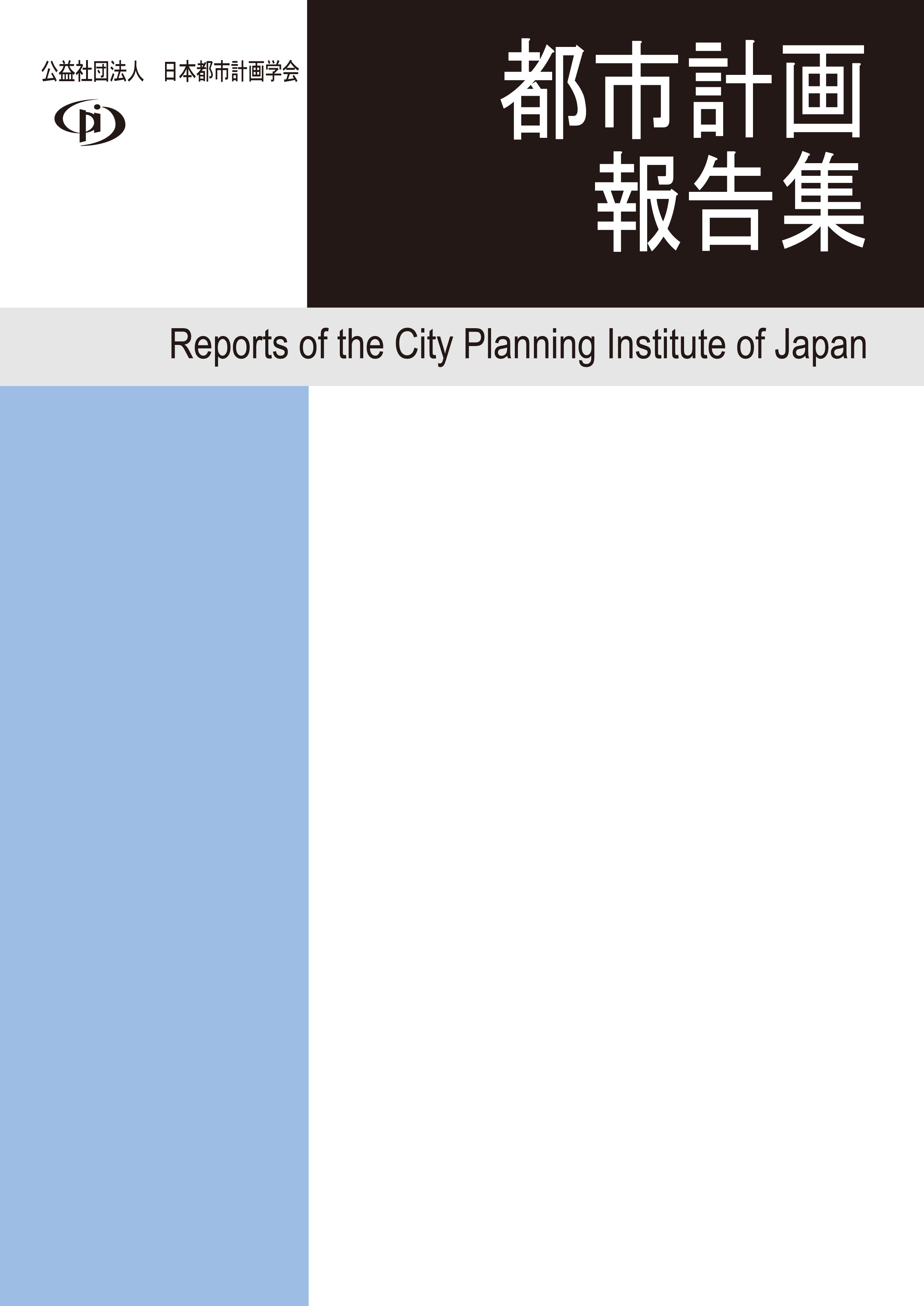-
地域子育て支援の多様性と包摂に向けて
濱野 裕華, 轟 慎一
2023 年22 巻3 号 p.
406-412
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
こども家庭庁設置法とこども基本法をめぐる政策過程について,唱導連合フレームワークを用いて分析した.旧民主党時代には,幼保一元化政策として新省創設が議論され見送られた.このたび政策課題として設定されたのは,いわゆる族議員から距離のある若手議員らの働きかけによるものだった.専門家らとともに政策志向学習が進められ,政府の基本方針の大枠が固められた.与野党双方に存在する唱導連合で,組織体制と基本理念の2本立てによる法改正への調整が進められた.そして,子ども政策を充実させるための新たな組織体制の必要性という信条のもと,こども家庭庁設置法が閣法として,こども基本法が議員立法として,それぞれ成立した.
抄録全体を表示
-
物流事業者による生活支援サービス拠点の展開事例
金 洪稷
原稿種別: その他
2023 年22 巻3 号 p.
413-419
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本レポートでは、物流事業者による生活支援サービスの事例として、ヤマト運輸株式会社の取り組みを紹介する。この取り組みには、居住地域を広くカバーできる物流拠点に併設してコミュニティ・生活支援サービスの提供拠点を設置できること、物流業界で地域巡回を行うドライバーの経験を活用する機会を提供できること、そして物流事業者としての経験を活かした新たな形態のサービス拠点を構築できる可能性があることなど、いくつかの利点がある。しかし、物流事業者によるコミュニティ・生活支援サービスの提供拠点の展開が住宅地をどれほど効果的にカバーし、住民が安心できる生活環境の構築に寄与できるかは不確かなままである。上記のような拠点展開の影響を明らかにする研究は、特に高齢化社会における住民の生活の質の観点から、効果的・効率的なコミュニティ形成を議論する際、必要不可欠な基礎資料として貢献することが期待される。
抄録全体を表示
-
但野 悟司, 川﨑 興太
2023 年22 巻3 号 p.
420-427
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、復興支援員を数多く設置してきたとともに、近年では最も多く設置している福島県を対象として、復興支援員の実態と課題を明らかにするものである。本研究を通じ、復興支援員の活動は被災者や被災地の復興に貢献できていると認識されていること、原子力災害からの復興の課題として挙げられた移住者や交流・関係人口の増大やコミュニティの維持・再生等は復興支援員制度を活用して解消しうると認識されていること、すべての自治体が任期終了後も復興支援員に復興に携わってほしいと考えていることなどが明らかとなった。本研究の今後の検討課題として、任期終了後の支援を組み込む等の制度面の改善をすること、全国の避難者を対象として生活再建状況を調査・検証し、被災者の生活再建状況に即した避難者支援策の見直しが必要であることを指摘した。
抄録全体を表示
-
横田 宗輝, 川﨑 興太
2023 年22 巻3 号 p.
428-435
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、原発避難12市町村における移住政策の実態と今後の課題を明らかにすることを目的とするものである。原発避難12市町村を対象として実施したアンケート調査と、川内村を対象として実施した詳細分析に基づき、原発避難12市町村では、若者世代を主たるターゲットとして、まちづくり会社などと連携しながら、「子育てに関する施策」、「仕事に関する施策」、「住まいに関する施策」、「移住促進のための人材受入支援に関する施策」を中心とした移住施策を展開していること、一部の自治体は、福島再生加速化交付金を活用した移住・定住促進事業に対して改善を求めていること、多くの市町村は、住宅や雇用をはじめとして、移住の促進に向けた課題が山積していることなどが明らかになった。以上を踏まえ、住宅や雇用等の問題の解決に向けた福島再生加速化交付金や移住・定住促進事業などの制度の改善と、それらの制度を運用する組織体制の改善が必要であることを指摘した。
抄録全体を表示
-
明見 駿, 松本 邦彦, 澤木 昌典
2023 年22 巻3 号 p.
436-443
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、広域的な視点からの効率的な図書館配置に向けた条件を明らかにすることを目的とした。この施設配置分析では、公平に提供されるべき図書館サービスの評価指標値を設定した。さらに、複数の市町が連携して策定している立地適正化計画と、近隣市町の図書館へのアクセス利便性を考慮して4つの施設配置シナリオを作成した。その結果、効率的な図書館配置を実現するためには、都市機能誘区域への図書館移転が有効であることが明らかになった。そのため、市町村は、公共交通機関へのアクセスが便利な都市機能誘導区域内に図書館を移転した場合、他の市町村の図書館へのアクセシビリティが向上することを考慮した図書館配置計画を策定することが求められる。
抄録全体を表示
-
和歌山県田辺市鳥ノ巣半島集落の持続可能性に関する課題
黄 琬惠, 小林 広英, 吉積 巳貴
2023 年22 巻3 号 p.
444-449
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
鳥ノ巣半島は、2015年9月に吉野熊野国立公園の拡張地域に指定され、今後景観保全の整備やまちづくりが進められることが期待されている。本調査の目的は、鳥巣地区の土地利用の過去と現状を把握し、土地利用の変化と人間の暮らしとの関連性を明らかにし、地主の年齢、世帯人口、後継者等を探ることである。鳥巣村が持続可能な発展に向けて直面するであろう地主の高齢化や農業の衰退による土地利用や生物多様性の喪失などの課題を取り上げた。公園指定されたとはいえ、農村地域の過疎化による農地山林の管理者不足の背景の中に、食料生産と生物多様性の維持を兼ねた里山ランドスケープの持続に危機が潜んでいて、やがて保全価値の高いエリアにも影響が及ぼす。国立公園内集落の持続性を実現するには,自然公園法の保護規制に加え,集落住民の生物多様性への理解を深め,共同的な保全活動の協働を求める必要がある。
抄録全体を表示
-
COVID-19流行を経た34年間にわたる追跡から
松場 拓海, 石橋 澄子, 谷口 守
2023 年22 巻3 号 p.
450-455
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
高密な都市ほど自動車CO2排出量が少ないという関係性に基づき、脱炭素型まちづくりが推進されている。しかし、自動車CO2排出量を削減するためには、その経年変化を追跡する必要がある。そこで本研究では、COVID-19流行による交通行動変化を踏まえた自動車CO2排出量の長期的変遷を明らかにすることで、市街化区域人口密度が自動車CO2排出量の変化に与える影響を検証する。本研究では、全国都市交通特性調査を用いることで、1987年から2021年の34年間にわたる自動車CO2排出量の長期的変遷を追跡した。その結果、2015年までの全体的な増加傾向から転じて、2015年から2021年にかけては、COVID-19などの影響により自動車CO2排出量は全体的に転じたことが明らかとなった。さらに、自動車CO2排出量の変化要因としては、都市構造などの他の要因の存在が示唆された。
抄録全体を表示
-
持続可能な世界に向けたまちづくりの再資源化の研究2
土肥 真人, 木村 直紀
2023 年22 巻3 号 p.
456-461
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿の目的は、社会的価値観の変化に対応した新たな価値をまちづくりに見出すことである。(シリーズ第2稿)本調査では、石巻において、まちづくりの実践者にインタビューを行い、一般的には明確にされていない価値観を抽出した。調査の結果、石巻市のインタビュー対象者が行っている、「住む」ことを追求する活動には、既存のまちづくりが持つ価値観に加え、7つの新たな価値観が内包されていることが確認された。移住希望者を支援する手段として空き家を活用し、その結果として、地域の自然や社会と関わりながら暮らす価値を発見した。この事は、災害で大きく変化したまちで、人々がどう住んでいくのかという、復興まちづくりの在り方に関わる問題を提起している。
抄録全体を表示
-
宇於﨑 勝也, 泉山 塁威
2023 年22 巻3 号 p.
462-467
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
改正文化財保護法の施行に伴い、重要伝統的建造物群保存地区では「保存活用計画」を定めることとなった。今後は保存計画に活用方策を含めて申請を行う必要がある。本研究は、重要伝統的建造物群保存地区の現状と保存活用の実態をふまえて、今後の保存・活用の方向性を明らかにしている。今後の方向性として移住促進をひとつの方策として見出している。
抄録全体を表示
-
飯田 晶子, 山崎 嵩拓, 樋野 公宏, 横張 真
2023 年22 巻3 号 p.
468-473
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、COVID-19パンデミック蔓延下に、誰が都市緑地を利用し、それが都市住民の健康と幸福にどのように関連したかを明らかにすることを目的とする。東京都在住の成人4,126人の横断データを用いて、二項ロジスティック回帰分析を行った。その結果、都市緑地を利用した人は利用しなかった人に比べ、主観的ウェルビーイングと身体活動量が向上していた。また同時に、利用者の属性によって利用する都市緑地の種類が異なっていたこと、及び都市緑地の種類によって主観的ウェルビーイングと身体活動量との関係の度合いが異なっていたことが分かった。様々な人々が都市緑地にアクセスできるよう、多様な都市緑地が混在する住環境づくりが重要である。
抄録全体を表示
-
栗山 尚子, 大庭 哲治, 石原 凌河, 大島 洋一, 岡 絵理子, 辻川 ひとみ, 松本 友惟, 宮部 浩幸, 森田 恭平
2023 年22 巻3 号 p.
474-478
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
ニュージーランドのカンタベリー地震は、クライストチャーチ市の中心部に大きな被害を及ぼした。クライストチャーチ市役所へのヒアリング調査、市中心部の復興計画の文献調査、現地調査を通して、本稿では、復興計画の内容を概括し、地震後12年を経過した2023年9月時点の計画の実現状況を報告する。市の中心部を集中して復興させるため、FrameとCore、17の重点プロジェクトが設定され、Frameの外周にある複数の大型拠点づくりと、Frame内は低層な建築物を中心としたコンパクトな都市づくりが進められている。復興計画の実現をサポートするデザインガイドによって、きめ細やかな公共空間のデザインがなされ、歩行者が滞留・回遊しやすい空間が実現されている。
抄録全体を表示
-
神戸市灘中央市場における防災空地の地域活動による利用に着目して
藤井 速人, 嘉名 光市, 高木 悠里
2023 年22 巻3 号 p.
479-486
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本事例報告では、神戸市の灘中央市場に焦点を当て、対象地の歴史的変遷、防災空地整備に至る過程と現在までの市場としての経過を明らかにする。次に、防災空地の地域活動による利用実態を、団体、内容、場所の観点から明らかにする。その上で、対象地域の団体・個人の防災空地への関わりや防災空地設置に対する意識を明らかにする。以上より、対象地における防災空地のまちづくりにおける防災的、地域活動的役割を明らかにし、今後の課題について考察する。
抄録全体を表示
-
滋賀県彦根市の都市近郊農村を事例として
萩原 和
2023 年22 巻3 号 p.
487-493
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本報告は、既存のノーコード機械学習ソフトを用い、簡易的な景観評価手法の構築について検討したものである。具体的には都市近郊農村を対象とし、アクションカメラ(GoPro)で取得された映像から画像データを抽出した上で、ノーコード機械学習ソフトによる画像分類および物体検出を試行した。その結果、十分な判定率で、伝統的な既存集落内の民家と、宅地分譲による住宅との差異を識別することができた。その一方で、画像のアングルなどの条件が異なる場合、誤判定が生じることもあった。ただし、この場合も物体検出によるポイント可視化によって、どの景観要素が誤判定に影響したかを推し量ることができた。本報告の結びでは、一連の課題解決に不可欠な観点を要約整理するとともに今後の展望を示した。
抄録全体を表示
-
持続可能都市とランドスケープアーバニズムに向けて
丸山 泰誠, 轟 慎一
2023 年22 巻3 号 p.
494-500
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、駅周辺でまちなかに賑わいを創出するために「居心地が良く歩きたくなる」空間づくりを促進し、ウォーカブルなまちを形成することが重要である。滋賀県の駅周辺でも様々な活動が行われている一方で、自然災害が頻発化・激甚化し、防災・減災への対応が必要である。そこで本研究では全国でも流域治水の先進事例として知られている滋賀県のJR駅周辺地域を対象に、水害リスクと地理地形的条件を踏まえた駅周辺評価の検討を行い、コンパクトなまちづくり実現に向けた分析考察を目的とする。滋賀県北部24駅の駅周辺1km圏の施設立地分析を行うとともに、駅周辺徒歩圏で市街化が可能なエリアを把握し、北部4市の地理地形的特徴と課題点を明らかにした。
抄録全体を表示
-
しがのふるさと応援隊事業を通して
佐藤 彩香, 堀 拓樹, 上田 隼也, 吉積 巳貴
2023 年22 巻3 号 p.
501-504
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究はは、2022年に滋賀県で行われた「しがのふるさと応援隊」事業を事例に、行政の農村体験事業が参加者の地域への関心の変化や関係人口創出の可能性について調査した。アンケート調査とインタビュー調査を通じて、参加者の地域への印象が向上し、消費行動や将来の地域活動への参加意欲が高まることが明らかになった。また、行政主体の事業から地域主体の事業へ移行していくことの必要性が明らかになった。
抄録全体を表示
-
人流データを活用した地区比較
上杉 昌也
2023 年22 巻3 号 p.
505-508
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では,三大都市圏および地方中枢都市圏の商業業務地区における滞在者の居住地特性に焦点を当て,社会経済的な側面からその多様性と変化を検証した.本研究の知見として,まず,携帯電話の位置情報を用いた人流データを分析することで,各商業業務地区における滞在者の居住地ランクの多様性を評価することができた.他都市圏と比べて東京の特殊性が明らかになったが,都市圏共通の傾向として,商業業務地区が多様な職種や業種が混在することで一定の多様性が確保されていることが示唆され,これにより都市の社会的相互作用の場を提供している可能性がある.
抄録全体を表示
-
溝口 萌, 竹中 彩, 泉山 塁威, 宇於﨑 勝也
2023 年22 巻3 号 p.
509-512
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、都市再生整備計画から公共空間活用における公共空間の活用状況を把握し複数の公共空間活用の傾向及び中心市街地における分布を明らかにすることが目的である。複数の公共空間活用を行う地区を対象に「活用空間」と公共空間の分布を調査し、地方都市中心市街地における複数の公共空間活用の傾向及び分布を明らかにした。地方中枢都市で公共空間を複数活用する場合、地区内の公共空間の位置を考慮し、「活用空間」と公共空間が地区全体に行き渡るようにすることが有効と考えられる。
抄録全体を表示
-
下田市旧町内を対象として
染矢 嵩文, 森本 あんな, 飛田 龍佑, 福井 勇仁, 泉山 塁威, 宇於﨑 勝也
2023 年22 巻3 号 p.
513-517
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
地方都市では、自動車利用が難しい高齢者の生活が困難となる。そのため、安全に歩いて暮らせるウォーカブルシティの形成が求められる。地方都市においてウォーカブルシティ形成するには、戦略的な交通マネジメントにより、人のアクティビティを誘発する「プレイス機能」が高い、人中心のストリートのネットワーク構築が必要であると考えられる。そこで、本研究では、下田市を対象として、沿道の土地利用や景観要素、散策や滞留を促す要素をプレイス機能を図る指標とした人中心のストリートの抽出手法を提示し、沿道の土地利用及び景観要素から、プレイス機能の高いストリートの抽出を行う。加えて、散策や滞留を促す要素の集積状況との重なりにより、下田市におけるウォーカブルシティ形成に向けた地域特性を示す。
抄録全体を表示
-
大手町・丸の内・有楽町地区、名古屋駅地区、博多駅地区、天神地区を対象として
一之瀬 大雅, 小野寺 瑞穂, 泉山 塁威, 宇於﨑 勝也
2023 年22 巻3 号 p.
518-521
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究ではエリアビジョン策定後に、長期間エリアマネジメントを行う地域では、エリアビジョン実現に向けた推進体制の構築などが確立するという仮説のもと、 エリアビジョンに基づきエリアマネジメントを行う大都市都心部を対象として、各地区の「ビジョンマネジメント」の変遷を整理し、動向を明らかにすることを目的とする。 研究結果として、社会情勢の変動など伴い、柔軟にビジョン形成を行うことや関連マニュアルの策定を行うことで、エリアビジョンを詳細化や補完することが明確となった。 また、新たなエリアマネジメント団体の設立を行う場合があることが明らかとなった。
抄録全体を表示
-
持続可能な世界に向けたまちづくりの再資源化の研究3
土肥 真人, 木村 直紀
2023 年22 巻3 号 p.
522-528
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿の目的は、社会の価値観の変化に対応した新しい価値をまちづくりに見出すことである。(シリーズ第3稿)本研究では、岩手県住田町において、仮設住宅の受け入れ地域と連携した復興まちづくりの実践者へのインタビュー調査を行い、新たな価値の抽出と言語化を試みた結果、6つのまちづくりの新たな価値が同定された。住田町の仮設住宅では、流域や文化を共有する同郷意識や、仮設住宅の立地、規模、デザインが影響し、受け入れ地域と被災者の間に信頼関係が構築され、その上で、ボランティアや定常的な支援団体(邑サポート)の活動が行われた。困難な状況を抱える人々を共に支援することで、地域を豊かにする住田町の事例は、持続可能な地域のまちづくりと、グローバルな世界の課題解決の可能性を示している。
抄録全体を表示
-
東京都中央区日本橋浜町地区を事例として
江坂 巧, 倉田 晃輔, 泉山 塁威, 宇於﨑 勝也
2023 年22 巻3 号 p.
529-532
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、都心部の「イノベーション・ディストリクト」における物理的資産に着目し、機能的特徴及び形成過程の特徴を明らかにすることを目的とした。文献調査より整備建築物や周辺施設の用途・機能、整備事業の主体・期間・手法を整理た。結論では、民間不動産事業により形成される要素の偏りや機能の柔軟性、物理的資産の形成や面的な展開における特徴を明らかにした。
抄録全体を表示
-
松葉 明里, 小野 悠
2023 年22 巻3 号 p.
533-537
発行日: 2023/12/11
公開日: 2023/12/11
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、ため池の減少が起きている問題がある。ため池とは、河川が無い場所で農業を行う水を引くための池である。都市化による緑地、農地の減少、高齢化による農業従事者の減少から、放棄された耕作地やため池が増加してしまい、ため池の消失が起こっている。ため池は農業用としての水資源のみの使い方ではなく、親水空間や防災用、生物多様性にとって重要な場所になるため、放棄や減少してはならない存在である。水資源の重要性が問われている中で、ため池は近年注目されているところであり、国際的分野にもなっている。ため池を取り巻く都市の生態系は、自然と共生する社会や、持続可能な社会を実現するためにも保全すべきものである。本研究では、愛知県豊橋市のため池における生物多様性と、ため池周辺の立地環境を明らかにし、ため池の今後の保全や、ため池内の生物多様性について検討した。本研究を通じて、ため池の周辺環境がため池に生息する生物多様性に影響する可能性が示唆された。農業従事者が減少し、放棄されるため池が増加するなかで、生態系ネットワークに配慮したため池の保全・管理のあり方を考えていく必要がある。
抄録全体を表示