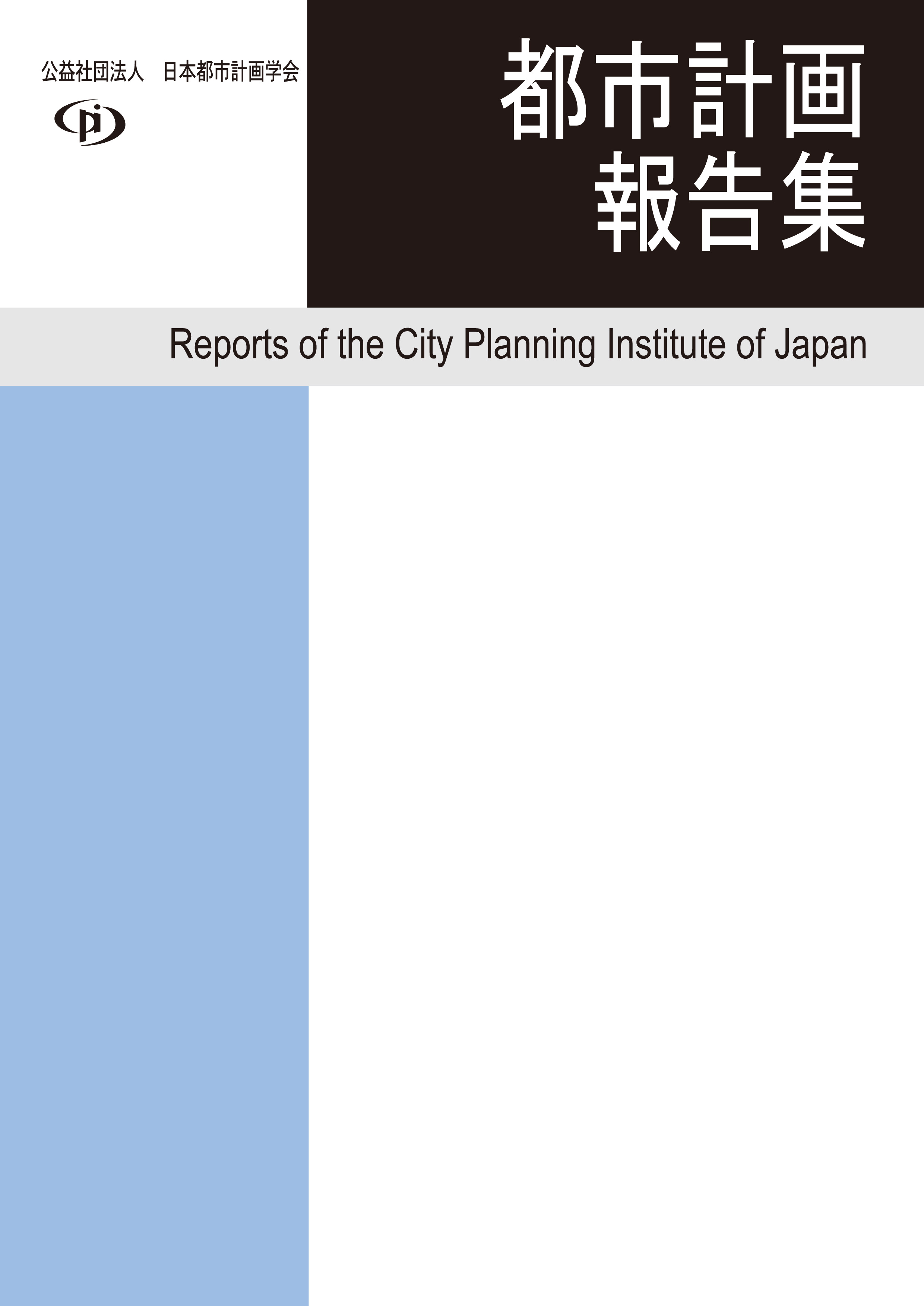-
菅 蒼太, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
1-7
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、原発事故が発生してからの10年間における農業復興事業の実績を整理するとともに、農業復興の現状と今後の課題を明らかにすることを目的とするものである。本研究を通じて、(1)事故後10年を迎えてもなお、福島県59市町村の農業被害は解消していないこと、(2)原子力被災12市町村の農業復興が特に進んでおらず、課題が山積みであること、(3)農業復興に向けた新たな取組が進められ、今後の推進が期待されていることなどが明らかになった。以上を踏まえ、市町村の実態に沿った支援をしていくこと、風評被害の払拭のための新たな取組が必要であることを指摘している。
抄録全体を表示
-
福島県内の立地適正化計画策定市町村を事例として
清水 遥翔, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
8-13
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、令和元年東日本台風によって最も大きな被害を受けた福島県内の立地適正化計画策定市町村における復旧・復興状況に関する分析をし、今後のまちづくりのあり方に関して基礎的な知見を得ることを目的としている。本研究を通じて、(1)河川の復旧等やソフト面での防災対策は多くの市町村で取り組まれていること、(2)市街地整備事業や建築規制等はほとんどの市町村で取り組まれていないこと、(3)すべての市町村で防災指針は検討中であることなどが明らかになった。以上を踏まえ、防災・減災に向けて都市の特性に応じた多様な解決策を行政と住民が協働で見つけ出していくことが重要だと考えられる。
抄録全体を表示
-
島根県松江市を事例にして
周藤 あゆみ, 諏訪 亜紀
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
14-21
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
高度成長期から約半世紀を経た2020年の現在でも,景観保全の促進よりも都市開発による経済性が優先される傾向が強い。特に「生活景」など日常の風景は忘れられがちであり,そこに住まう住民の景観保全への意識も必ずしも高くはないことが多い。このような状況下で景観の保全に取り組む人々が合意形成を図ることは可能なのか,そして可能ならばどのように行われているのであろうか。本稿では,現在全国各地で行われているまちづくりが展開されていった経緯に基づき,景観保全という1つの分野の視点を用いて,この側面から生活景保全における住民の合意形成プロセスを分析した。
抄録全体を表示
-
ボルチモア市グリークタウン(メリーランド州、アメリカ)の事例より
松本 奈何
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
22-26
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
世界各都市では移民や経済構造の変化によりダイバーシティ、多様性が急速に増している。都市計画・政策においては、多文化共生は重要な課題となっている。本稿では米国、メリーランド州ボルチモア市内で近年多様性を増してきているかつての移民街、ギリシャ街(グリークタウン)を事例として取り上げ、その変容しつつある多様性の状況を報告する。3年に及ぶフィールドワークの結果、各人種や民族、社会経済状況による住民グループの内部で多様性が進行していることが明らかになった。一方でグループとしての共通意識も依然として強いことがうかがえる。このようなグループ内の多様性と帰属意識は都市計画・政策にとって重要な示唆となりうることを提示した。
抄録全体を表示
-
金沢市、弘前市、福井市、尾道市、長門市、神山町の事例研究
服部 圭郎, 海道 清信, 藤井 康幸, 松行 美帆子, 吉田 友彦
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
27-34
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
全国的に人口縮小が進み、特に自然減の改善がみられない状況下では、自治体が人口減少を抑制するための有効な施策は社会減をいかに少なくするかということになる。本調査では、社会減を少なくすることに成功した6つの自治体(金沢市、弘前市、福井市、尾道市、長門市、神山町)を取り上げ、それらが成功した背景をその施策を推進した関係者を中心に取材調査した。これらの6つの事例はそれぞれ人口規模や社会経済環境、政策内容は異なるが、人口減少という地域の持続性を脅かす危機に対して、地域特性をうまく活かした社会減に着目した政策によって回避、もしくはそのダメージを緩和していることが見えてきた。
抄録全体を表示
-
全国の「こどものまち」の調査とミニいちかわのケーススタディより
鈴木 茜, 後藤 智香子, 新 雄太, 近藤 早映, 泉山 塁威, 吉村 有司, 小泉 秀樹
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
35-42
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、「こどものまち」における子どもの参画の実態を明らかにし、どのようにそれが実現されているのかを考察することを目的としている。「こどものまち」運営者の子どもの参画に向けた取り組みを理解するため、日本全国の「こどものまち」運営者へのアンケート調査を実施、及び働くことを通じた子どもの参画のプロセスを明らかにするため、ミニいちかわでの参与観察調査を実施した。「こどものまち」運営者は、子どもの参画を促進するため、事前準備への子どもの参加や大人の関与の制限等、様々な取り組みを行なっていた。また、子どもの参画のプロセスにおいては、1)子ども自身が目的意識や問題意識を持てること、2)子どもがその目的達成や問題解決に至るために必要な仕組みや方法を理解できていること、3)子どもがコミュニティに対する自分の行動の影響を実感できることの3点が重要であると理解できた。
抄録全体を表示
-
山本 晴菜, 中野 茂夫
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
43-47
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、我が国におけるまちづくりは開発中心の「つくる」時代から地域管理を中心に地区再生を目指す「育てる」時代に移行している。そこで、まちづくりはこれまでの行政主導ではなく地域主導で推進する取り組みが広がりつつある。なかでも重要視されているのが行政と民間事業者が連携してまちづくりを行う「官民連携まちづくり」だ。これを実行する主体として、平成19年に「都市再生推進法人(以下「推進法人」)制度」が創設され、まちづくりの新たな担い手として注目されている。しかし、推進法人制度初動期のエリマネの実態が明らかにされているのに対し、制度が普及しつつある現在の推進法人のエリマネの実態については未だ不明瞭な部分がある。そこで、活動内容と制度の利用実態から制度が普及しつつある現在の推進法人のエリマネの実態について明らかにする。
抄録全体を表示
-
福井 彩水, 田中 枝里子, 浅井 広巳, 中島 誠
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
48-49
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、本来誰もが楽しめる空間であるはずの都市公園では、禁止事項が増えて、子どもたちの遊びの自由度が低くなっている。禁止事項が増えた1つの要因に、公園内でのけがの発生を最小限に減らす目的がある。公園内で子どもがけがをすれば、その子どもや保護者からの苦情が公園管理者に寄せられる可能性があるためだ。しかし、既往研究によると、環境の中にある程度のリスクを残し子どもに経験させることで、子どもの危険予測・回避能力を育てることが分かっている。本稿では、大規模公園において実施したプレーパークの社会実験を通して、どの程度のリスクを含む遊びが子どもや保護者に受け入れられるのかについて考察し、ハザードの除去について、その妥当性を検証する。
抄録全体を表示
-
東京西郊の私鉄を対象として
吉田 泰寛, 吉川 徹
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
50-56
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、私鉄の駅前の広告物の色彩には沿線ごとに傾向があり、また開業年や乗降客数などの駅特性にも影響を受けるのではないかとの仮説を検証することを目的とした。このため、京王相模原線、東武東上線、小田急多摩線を対象として、色彩と駅特性の関係を、判別分析とクラスター分析によって検討した。結果として、沿線ではなく都心部からの距離によって、またターミナル駅より都心側か郊外部側かによって、色彩が大きく異なっていた。
抄録全体を表示
-
北川 拓, 吉川 徹, 讃岐 亮
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
57-59
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究の目的は、キャプション評価法に基づく手法を用いて、都市の植栽が歩行者の周囲の歩道の印象に与える影響を明らかにすることである。 分析結果は以下の通りである。 1)都市の植栽を整備された緑と未整備の緑の2つのグループに分類することが妥当であった。後者の状況下では、コメントがネガティブになる明確な傾向があった。2)ネガティブな印象を与える植栽は、最低限の選定しか行われていない、夜間に明るさが確保されていないなどの特徴があった。3)ポジティブな印象を与える植栽は、木漏れ日や夏場の涼しさなどを感じることができるなどの特徴があった。
抄録全体を表示
-
荒木 祐介, 佐久間 康富
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
60-65
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、指定都市と中核市の市庁舎前広場の管理運営実態と利用実態について明らかにした。管理運営実態については、以下の5点を明らかにした。第一に、市庁舎前広場は市民利用を広げる一つの手段である点。第二に、市庁舎前広場での営利活動の許可基準に関する点。第三に、市庁舎前広場の管理運営システムに関する点。第四に、市庁舎前広場の利用中止に伴う対応方法に関する点。第五に、市庁舎前広場におけるトラブルに対する対応方法に関する点。利用実態については、以下の3点について明らかにした。第一に、利用実態へもたらす営利活動の許可基準に関する点。第二に、利用団体が市庁舎前広場を利用する利点に関する点。第三に、市庁舎前広場の使いづらい点。
抄録全体を表示
-
国立市富士見台地域の三自治会を事例として
長 奈緒子, 近藤 早映, 後藤 智香子, 泉山 塁威, 新 雄太, 小泉 秀樹
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
66-72
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、自治会に参加することが高齢者の主観的幸福感に与える効果について評価することを目的とした。国立市富士見台地域の3つの自治会において、役職についている65歳以上の高齢者を対象としてアンケート調査及びインタビュー調査を行い、分析した。分析の結果、自治会活動参加と高齢者の主観的幸福感は関連していることが明らかになった。主観的幸福感と関連する自治会活動の要素としては包摂度、地域内での包摂度、自治会への積極性、役職、役割感、役職の経緯が抽出された。また、自治会に参加している高齢者は他者との関係性の中でもたらされる意義、自己の中で完結する意義、日常生活の変化によってもたらされる意義の3種類の参加意義を感じていることも明らかとなった。
抄録全体を表示
-
森谷 健太, 徳永 幸之
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
73-78
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では,世代間差異を考慮した公共交通における社会的便益評価手法として,富谷市の公共交通計画を事例に検討を行った。公共交通利用者を,通勤利用者を想定した時間抵抗重視グループ,高齢者を想定した移動抵抗重視グループに分けて評価を行った。その結果,それぞれの視点によって評価が異なること,それぞれの特徴に応じた課題の抽出を行うことができ,世代の違いを考慮して評価検討していくことの重要性を示すことができた。本評価手法では, Web上のフリーのGISシステムや汎用の表計算ソフトを用いて評価値を計測できるため,財政規模の小さな自治体での活用も期待される。
抄録全体を表示
-
後藤 耀摩, 佐久間 康富
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
79-84
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、ニュータウン周辺の施設変遷を明らかにするとともに、近隣センターの利用実態から近隣センターのあり方を明らかにする。施設変遷の調査の結果、スーパーが近隣センターから近隣センターの外、特にNT隣接500m圏に移動していることが明らかになった。また、近隣センターは高齢者向けの施設が増えるなど、周辺住民の属性の変容に合わせて変容していることが明らかになった。さらに、日常的に使う施設は近隣センターに残りやすい傾向があることが明らかになった。よって、身近な場所にあって使いやすいという利点を生かしたワークスペースやコミュニティの核となりうる可能性があると考える。
抄録全体を表示
-
東京都八王子市南大沢駅周辺を事例として
関塚 哲史, 岡村 祐
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
85-91
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
郊外都市では社会的課題や周辺機能の変化などの影響を受けやすいため、変化に柔軟で持続的なエリマネが必要である。今後のまちづくり方針の策定など動向が注目される八王子市南大沢では2003年からエリマネ活動を継続的に行っている。そこで、本研究では南大沢駅周辺におけるエリマネ活動の継続要因と今後の方向性を模索することを目的とする。継続要因は①外部団体との連携、②ペデストリアンデッキを使用できる環境、③会員内での目的の継承、④会員の持つ資源の活用、⑤地域連携を重視した企業の事務局への着任と引継ぎ業務の工夫、⑥中心人物の熱意が考えられ、今後の方向性は幅広いニーズに応えるための他団体との関係構築、財源確保に向けた収益活動、継続するための人材育成があげられた。
抄録全体を表示
-
港北ニュータウンを例に
竹内 智子
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
92-96
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
COVID-19感染拡大による二回目の緊急事態宣言期間を含む2020年12月~2021年2月、横浜市の港北ニュータウンの神社、街区公園、近隣公園2か所、緑道2か所の6か所において公園緑地の利用者の行動調査を行い、4,610名のデータから、以下の知見を得た。全体の53.6%が散歩やランニングなどの移動型利用をしており、これは大人や高齢者に多く見られた。神社や街区公園は、午前中利用者が少ないが高齢者や小学生以下の子どもが友人と過ごす場となっている。近隣公園のグラウンドは、スポーツや伝統行事など幅広い年代による集団型の利用が全体の20.2%を占めていた。自然豊かな近隣公園や緑道は、定常的な大人、高齢者の利用が多く、平日利用者の60%以上が一人で利用していた。
抄録全体を表示
-
豊橋駅前の「豊市」を事例として
鶴田 尚吾, 小野 悠
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
97-100
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
愛知県の東三河地域は、農業が盛んな地域であり、日本でも有数の農業地域である。本研究では、豊橋駅前にある「豊市」という店舗を事例に、利用者の「豊市の商品」「東三河の農業・食」「豊市の地域農業・食の発信力」に対する意識についてアンケート調査を実施しました。その結果、東三河の農と食に対して、「誇りに思う」「大切にしたい」などのポジティブな意識を持つ人が多いことがわかりました。一方で、豊市の商品から東三河の農と食についての知識を得た人は少数であり、豊市の発信力には改善の余地があることがわかりました。
抄録全体を表示
-
西村 怜, 小林 利夫, 西浦 定継
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
101-106
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では、交通(軌道系公共交通)と周辺土地利用との関係性について分析を行った。対象は、京王線(本線、相模原線)である。調布駅地下化工事期間を挟む期間を対象に、連担する16駅の利用者数、周辺人口、道路ネットワークのアクセス性評価、可住地面積データを用いて、駅ごとの特性値を算出した。交通と土地利用の関係性という視点で得られた結果をまとめると、1)駅周辺において徒歩によるアクセス性の高い地域での開発が進む駅では利用者数の増加がみられる、2)特定の地域ではその地域自身もしくは周囲の地域との関連性における何らかの要因によって、その地域の社会的属性が影響を受けるメカニズムが存在する、 3)駅から離れたところでの開発は利用者数の増加への寄与は低い、ことである。
抄録全体を表示
-
ヴッパータール大学リーツマン教授へのインタビューから
福地 健治, 卯月 盛夫, Anja Beniko Lorenz
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
107-112
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
ヴッパータール大学のディーネル教授によって考案された熟議民主主義の市民参加モデルであるプラーヌンクスツェレ(Planungszelle)は開発から半世紀を迎え、いまドイツで注目度が高まっている。その背景と現況を知り、さらに今後の展開を探るため、多くのプラーヌンクスツツェレの実施経験をもつヴッパータール大学の教授であり同大学の「民主主義と参加の研究所」の所長であるH.J.リーツマン教授にオンラインでのインタビュー調査を試みた。その結果、現在ドイツで行われている市民参加による都市問題の課題解決方法について多くの知見を得ることができた。
抄録全体を表示
-
国際協力機構の海外駐在員を対象としたアンケート調査報告
吉原 信一, 讃井 一将, 澤山 友佳, 高橋 光, 平林 由梨恵, 水上 貴裕, 室岡 直道, 森下 恵介, 森川 真樹, 志摩 憲寿
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
113-119
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本調査では、開発途上国を中心とした諸都市での変化を生活者の視点から把握するため、JICAの海外駐在員を対象としたアンケート調査を実施した。その結果、個人のライフスタイルや空間の利活用、都市政策に変化が見られたほか、脆弱な交通システムといった既往の都市課題においても密回避のための新たな視点の必要性や、これまで認識されてこなかった新たな課題も認められた。国際協力の観点からは、都市マスタープランの策定といった従来のアプローチの有効性が認められた一方で、多くの都市でニューノーマルの議論がなされていないことが明らかとなり、今後はコロナ禍で生じた変化の定着可能性や課題の分析を通し、適切な施策を講じていく必要がある。
抄録全体を表示
-
牟呂用水に立つ水上ビルを事例に
酒井 練, 小野 悠
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
120-123
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿の目的は、豊橋市中心部商店街における店舗構成とまちづくりに対する姿勢を、断面分析とアンケート調査により明らかにすることである。
抄録全体を表示
-
大山 祐加子, 薬袋 奈美子
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
124-130
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では東京都23 区を対象に、都市計画マスタープラン及び道路整備方針を用いて生活道路の道路分類の実態を確かめた。全ての区で道路整備を主目的として考えられており、統一的な道路分類が作成されていない区や地域も存在することが明らかとなった。道路分類の名称や配置間隔・道路幅員目安が区ごとに異なり、道路が密接に接続しあう23 区内という限られた中でも、細かな道路の分類方法や道路に求める機能に差がある。最も身近な公共空間である生活道路を、欧州のボンエルフのように滞留行為を許容する道路を設け多様な道路活用を促すためには、道路の機能・使い方に主眼を置き、特に「生活の場」としての利用を含めた道路の段階的分類を統一的に作成する必要がある。
抄録全体を表示
-
大西 暁生, 深井 智史
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
131-132
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
新型コロナウイルス(COVID-19)感染が流行したことによって、東京都の人口動態が変化したことが報道された。しかしながら、COVID-19の感染拡大と人口動態の要因である出生数、死亡数、転入者数、転出者数の関係は定かではない。そのため、本研究では、東京都を対象に、COVID-19の感染拡大と各人口動態の要因との関係を定量的に把握することを目的として基礎な分析を行った。
抄録全体を表示
-
東京都特別区で計画されている具体的防災施設について
石田 雅美, 薬袋 奈美子
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
133-138
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、様々な災害が発生しており、災害発生時には都市公園は避難地、防災拠点等となることによって都市の安全性を向上させる効果を有している。今後の災害においても公園が担う役割は多く、災害後に公園を活用するための整備を行うことが重要である。そこで本論文では、災害後の一時的避難生活時に公園を活用するためにどのような具体的な計画が立てられているのか、東京都特別区の地域防災計画・都市計画マスタープラン、緑の基本計画を対象に整理を行った。その結果、水関連施設は多くの区で公園に整備している一方で、非常用便所やエネルギー・照明関連施設、備蓄倉庫は機能に合わせて公園だけでなく他の防災関連施設と分担していることが明らかとなった。
抄録全体を表示
-
豊橋市に立地する3大学の学生に着目して
三井 寛子, 小野 悠
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
139-145
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
地方都市では近年都市部への人口流入が大きな問題となっており、今後も引き続き進んでいくと考えられる。そこで地方都市ではそれぞれこの状況を阻止すべく対策として、将来を担う学生の余暇活動や街に対する印象を調査し、それらをもとに中心市街地の活性化を試みることで、若年層の都市部への人口流入を食い止めることができるのではないかと考えた。豊橋市に立地する三大学の学生に焦点を当て、調査を行なったところ、余暇活動として外食をするという回答が多く、娯楽を目的とする学生が少ないことがわかった。また、まちの印象は日頃そのまちに親しんでいるかどうかが大きく関わり、まちを日常的に利用したり、長年居住している学生はまちの印象が良くなる傾向にあることがわかった。よって、日頃から必然的に豊橋駅周辺を利用するような環境を作ることが中心市街地活性化への一歩に繋がると考える。
抄録全体を表示
-
石井 儀光, 赤星 健太郎, 小坂 知義, 根元 一幸, 大矢 雅史, 本田 智比古, 小熊 早千香, 成田 佳絵, 吉武 哲信, 谷口 守 ...
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
146-153
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
人口減少社会を迎え,集約型都市構造の実現に向けた取り組みが進められている.都市構造の将来像を定める際の合意形成の重要性については論を待たず,このために,都市構造についての市民の理解を深めることは急務である.都市構造についてのコミュニケーションツールである「都市構造可視化」はその開発から15年の歴史を経て,全国の都市計画の現場への普及を実現した.一方,地理教育の現場でも15年にわたる取り組みの成果として,高校地理教育の義務化がなされることとなった.本稿では,それら2つの取り組みが歴史を経て融合することとなった経緯と成果,そして都市構造可視化の今後の展開について,その取り組みに尽力した関係者ら一同により論ずる.
抄録全体を表示
-
兵庫県神戸市の平野コープ農園の事例から
新保 奈穂美
原稿種別: 研究論文
2021 年20 巻1 号 p.
154-156
発行日: 2021/06/08
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
縮退都市では,都市の農が既存のコミュニティを活性化しうる.利用率の低い都市公園は,コミュニティガーデン(CG)を作るのに適した土地であろう.しかし,農園が公益性を持つかは疑問視されており,自治体は都市公園でのCG設置を躊躇しがちである.この問題について議論するため,本報告では,「平野コープ農園」の設立経緯を明らかにした.著者は,この設立経緯を把握するために,自治体の担当部署と民間企業にインタビューを行った.結果,この農園は現在,神戸市農政水産部の実験事業として存在しており,今後の展開を検討する必要があることがわかった.また,誰でも参加できる農園を作り,学びの機会を提供することが,コミュニティ形成に不可欠である可能性が示唆された.
抄録全体を表示