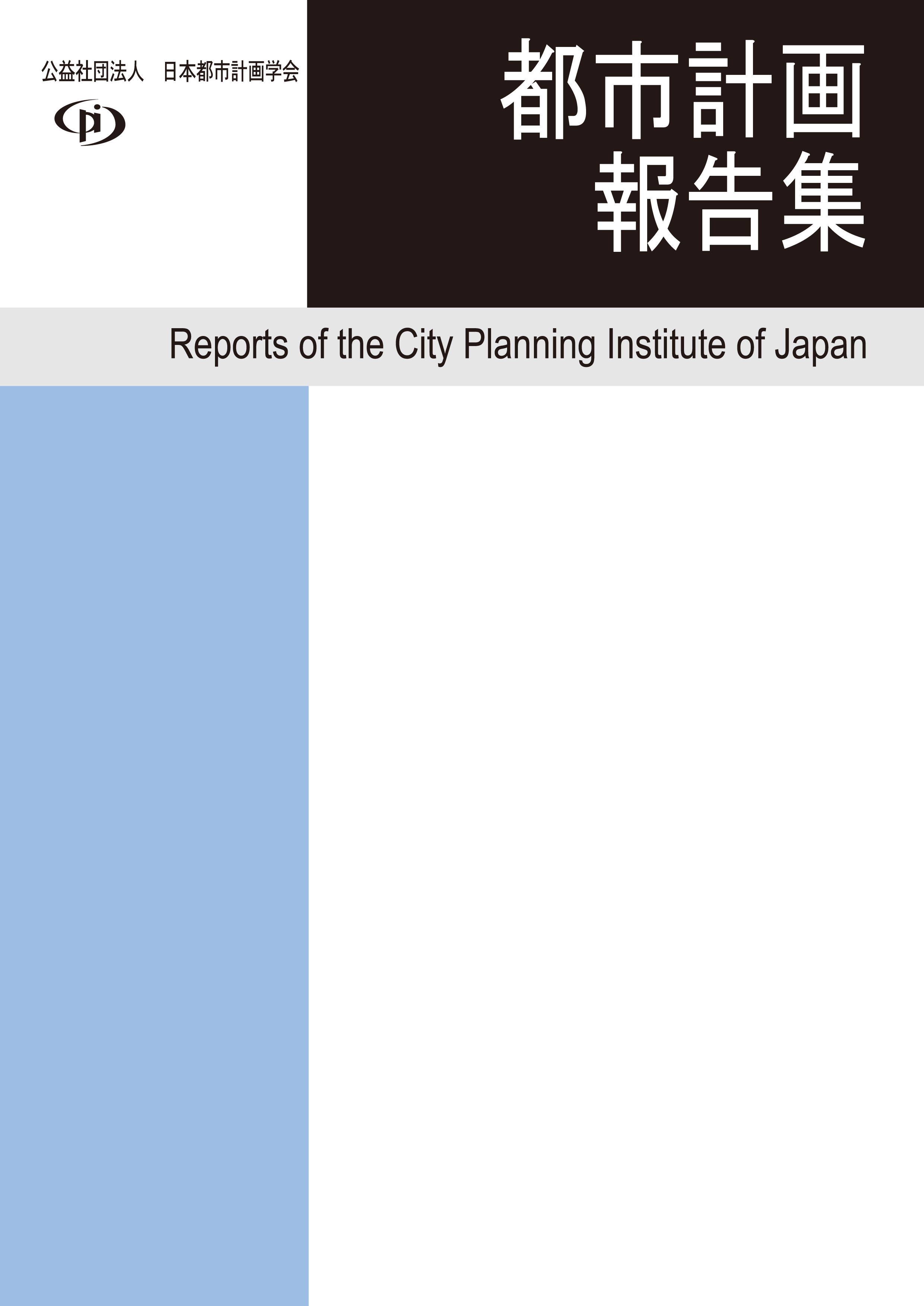
- 4 号 p. 102-
- 3 号 p. 81-
- 2 号 p. 56-
- 1 号 p. 1-
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
豊橋市を事例として馬 相烈, 大貝 彰原稿種別: 研究論文
2003 年2 巻3 号 p. 81-86
発行日: 2003/12/30
公開日: 2022/09/01
研究報告書・技術報告書 フリー本研究では、豊橋市の市街化調整区域における開発許可、建築許可、既存宅地の概要を把握すると共に、空間的な分布特徴を把握することが出来た。また、各開発行為における開発要因の抽出を試み、それらにより豊橋市の市街化調整区域における開発は駅、学校、集落、第2種大規模店舗等、概して交通や生活の利便性に関わる条件が主に影響していることがわかった。さらに、開発の多い地域は遠隔地道路沿い型、市街化区域周辺平均型、市街化区域近接型、駅近接道路沿い型、駅近接集落近接型、多開発型、低利便性型の7つのタイプに分類でき、各タイプにおける分布特徴や開発規模などを把握することが出来た。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1149K) -
山本 佳世子原稿種別: 研究論文
2003 年2 巻3 号 p. 87-90
発行日: 2003/12/30
公開日: 2022/09/01
研究報告書・技術報告書 フリー琵琶湖は近畿1,400万人の水源であり,自然史的、生態学的に貴重な湖である。このような琵琶湖の水質汚濁,富栄養化の進行を防止するために,1960 年代後半から主に主婦層を中心とした石けん運動が始まり,1979年には琵琶湖富栄養化防止条例(琵琶湖条例)が成立した。さらに現在までに多くの市民・住民団体が誕生し,環境保全を目的とした多様な活動が行われてきた。そして2001年には,湖国21世紀記念事業の一環として「水といのちの対話」をテーマに, 225の県民グループの環境活動が多彩に繰り広げられた。そこで本研究は,琵琶湖をめぐる近年の市民・住民活動の現状について概観したうえで,流域単位での環境パートナーシップ活動について代表的な活動事例を取り上げて展望することを目的とする。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (78K) -
平 修久原稿種別: 研究論文
2003 年2 巻3 号 p. 91-94
発行日: 2003/12/30
公開日: 2022/09/01
研究報告書・技術報告書 フリー人口減少に伴い、過去30年間において22市の人口集中地区(DID)が消滅し、直近の10年間で約4分の1の市のDIDが縮小した。コンパクト化を、全市に対するDIDの人口比が増加することと定義すると、DIDの人口・面積・人口密度の増減により5つのタイプに分類できる。1990年代にコンパクト化した75事例のうち、DIDの面積と人口が増加し、人口密度が減少するタイプが43事例である。この間、DID人口の純増加数が千人以上の市は4にすぎない。コンパクトシティの概念が注目を集めているが、実例は極めて限られている。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (228K) -
韓国ソウル特別市をケーススタディとして三輪 泰司, 上林 研二, 金 應周原稿種別: 研究論文
2003 年2 巻3 号 p. 95-101
発行日: 2003/12/30
公開日: 2022/09/01
研究報告書・技術報告書 フリー本研究では、街路歩行の安全は市民の生命に関わる人権の問題である認識により制定された、韓国ソウル市の「歩行条例」とその施行計画である「歩行環境基本計画」を考察する。「歩行条例」においては、条例制定の背景となった歩行環境改善のための市民運動とその条例制定が持つ意義を、「歩行環境基本計画」においては、内容分析による特徴と計画実施後の問題点並びに課題を明らかにする。さらに日本の当局や地方自治体が、歩行環境改善を進める際の法制度の必要性と実践方法などについても提案する。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (303K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|