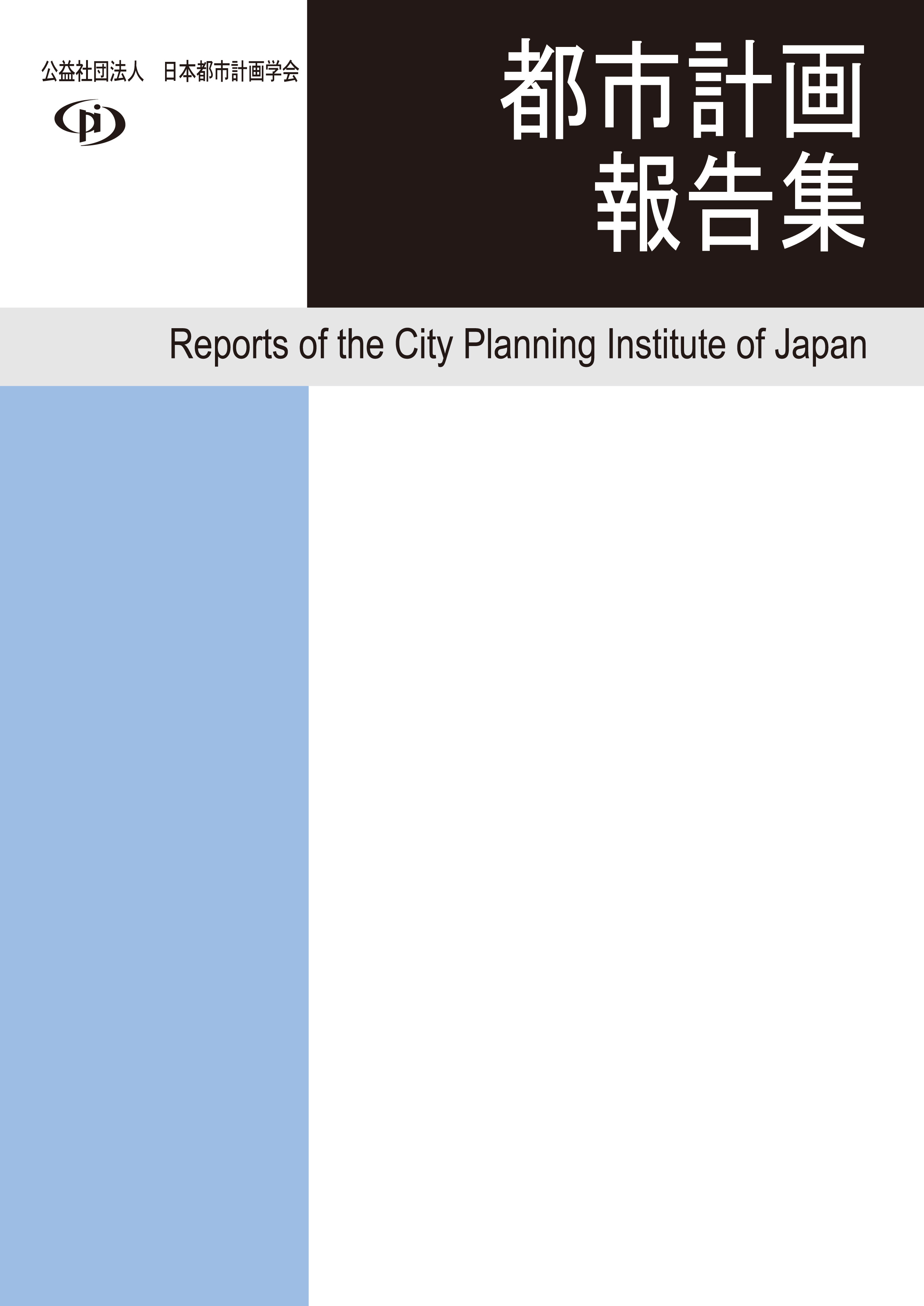
- 4 号 p. 122-
- 3 号 p. 94-
- 2 号 p. 28-
- 1 号 p. 1-
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
肥後 洋平, 山室 寛明, 谷口 守原稿種別: 研究論文
2013 年12 巻1 号 p. 1-6
発行日: 2013/06/10
公開日: 2022/07/01
研究報告書・技術報告書 フリーインターネットの普及・発展に伴い、買い物行動・サービス利用のサイバー空間への移行が進んでいる。それは結果的に実空間にも影響を及ぼすが、その全体像を的確に評価するには、過去からの推移を累積的に把握する必要がある。本稿では過去の想起に基づくレトロスペクティブ調査を実施することで、その影響特性を総計として明らかにした。調査の結果、書籍購入は既存中心市街地から移行が進んだのに対し、衣服購入ではむしろ郊外ショッピングセンターからの移行が多いことが示された。また、サービスの中でも銀行や保険等が、移行数の多い分野であることなどが明らかとなった。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1165K) -
嶋田 喜昭, 三村 泰広, 加藤 哲男, 呉 允杓, 本多 義明原稿種別: 研究論文
2013 年12 巻1 号 p. 7-12
発行日: 2013/06/10
公開日: 2022/07/01
研究報告書・技術報告書 フリー韓国・釜山市の南西に位置する巨済島は、韓国内では済州島に次ぐ2番目に大きな島である。この巨済島と付属島嶼から成る巨済市は、人口が約23万人で、造船業を主な産業として経済的にも豊かな市である。従来、巨済島から釜山市への道路アクセスは、島の西側の統営市から入るルートしかなく、約3時間を要していたが、2010年12月に巨加大橋が開通し、釜山~巨済間は50分程度に縮まった。本稿では、韓国の長大橋事業の事例として、著者らの現地調査を踏まえ、巨加大橋建設に至る経緯や開発計画、また巨加大橋開通が交通や産業等に及ぼした影響、そして、今後の開発プロジェクトの動向や方針について報告するものである。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1319K) -
UR八潮団地を事例として樋野 公宏, 原 文雄原稿種別: 研究論文
2013 年12 巻1 号 p. 13-16
発行日: 2013/06/10
公開日: 2022/07/01
研究報告書・技術報告書 フリー身近な商店の減少、本格的高齢社会の到来は、日常的な買い物に支障がある「買い物弱者」を生み出している。この問題の深刻度は地域特性によって異なるが、高度成長期に整備された団地では問題が顕在化しやすいと考えられる。そこで本研究では、急激な高齢化、商業施設の撤退を経験した八潮団地(埼玉県八潮市)を対象に、買い物弱者問題の現状と構造、対策について考察した。65歳以上の団地居住者78名を対象とするアンケート調査結果の分析から、加齢に伴い自家用車や自転車から徒歩やバスに交通手段が移行すると、日々の買い物に不便を感じるようになり、買い物の頻度が減るという構造が見出した。買い物環境の悪さが高齢者の食生活や健康に影響していることが懸念される。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1166K) -
道路整備に対する国民意識の変化富田 雄一, 鈴木 健嗣, 出口 忠義, 渡井 恭周, 大橋 昭宏原稿種別: 研究論文
2013 年12 巻1 号 p. 17-22
発行日: 2013/06/10
公開日: 2022/07/01
研究報告書・技術報告書 フリー我々は2008年11月に,国民が道路の状況や将来の道路整備についてどのように考えているのかを把握するためにWEBアンケート調査を実施している。その調査から5年が経過した今,社会情勢が大きく変化する中、公共事業や道路整備に対する国民意識がどのように変化しているのかを探るためにアンケート調査を実施したものである。アンケート調査はWEBアンケート手法を用いて全国に約2,000票を各県に人口按分して実施した。調査結果より公共事業に対する国民意識は高まっており、道路整備に対しても依然と改善要望を持っている。改善要望の内容は渋滞対策や交通安全対策など道路を利用する中で日常的に感じる問題点に集中した。一方で少数意見ではあるが防災対策や維持管理に対する意識も高まっていることが分かった。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (867K) -
大手町・丸の内・有楽町地区の附置義務駐車場整備の特例に関する地域ルール川﨑 美幸原稿種別: 研究論文
2013 年12 巻1 号 p. 23-27
発行日: 2013/06/10
公開日: 2022/07/01
研究報告書・技術報告書 フリー本稿では、大手町・丸の内・有楽町(大丸有)地区の附置義務駐車場整備の特例に関する地域ルールの策定経緯とその後の運用状況について考察する。まず、大丸有地区特性と地域ルールの必要性を説明し、次に協議会組織と駐車場附置義務緩和の考え方を説明する。当地域ルールは、実績として、駐車施設の設置台数を4,720台(附置義務台数)から3,080台(地域ルール適用台数)に軽減できている。また、路上に駐車されている貨物車のために、民間施設内においての荷さばき駐車施設の整備台数を129台(条例基準)から299台(地域ルール適用台数)に増やすことができている。現状においては、住民、専門家、設計者、行政が建築計画を事前協議し、審査・決定するという日本では珍しい住民参加の事例だと考える。
抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1052K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|