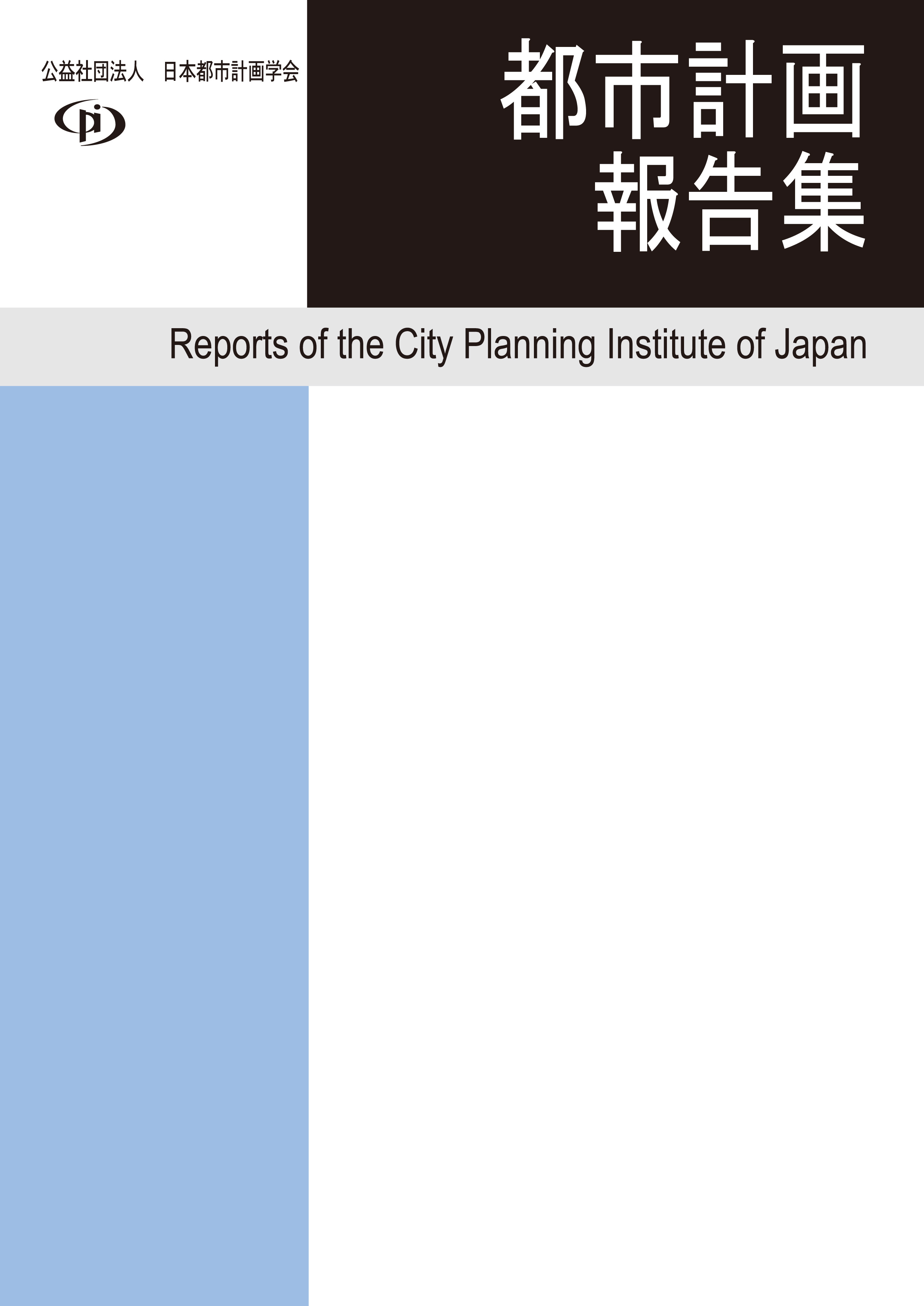-
田中 太加良, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
259-266
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究の目的は、東日本大震災及び原発事故後の福島県内における再エネの推進状況と課題を明らかにすることである。この研究により、(1)福島県内市町村のほぼすべてが、再エネを推進していること、(2)再エネ設備の導入は自然環境を破壊し、景観の破壊や騒音問題といった問題を引き起こす可能性があること、そして(3)再エネは地域活性化の手段となりうることが明らかとなった。これらの結果に基づき、さらなる再エネの推進のためには、予算と人材の確保だけでなく、同時に地域の問題に対する対策を講じる必要があること、また、国、県、市町村、事業者、研究機関の連携が重要であることを指摘する。
抄録全体を表示
-
福島県の復興公営住宅・勿来酒井団地の入居者を対象とする事例研究
高野 樹, 菅 蒼太, 皆川 健瑠, 清水 遥翔, 川邊 浩也, 川﨑 興太
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
267-273
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究の目的は、「仮の町」を実現した唯一の事例である双葉町の「仮の町(町外拠点)」を構成する要素の一つとして整備された勿来酒井団地の入居者を対象として、生活実態とコミュニティの維持・形成状況を明らかにすることである。この研究により、介護・福祉、医療については高く評価されているが、公共交通については特に評価されていないことが分かった。また、福島県によるコミュニティ支援策は一定程度評価されているが、帰還を考える人はとても少なく、交友関係は狭まり、孤独感を感じている人もいることが分かった。これらの結果に基づき、帰還する人に対する支援だけでなく、仮の町で生活する人に対する支援も必要であることを指摘している。
抄録全体を表示
-
東京都北区田端地区の事例分析を中心として
大木 寧子, 真鍋 陸太郎, 村山 顕人
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
274-279
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、木造密集市街地の解消による低家賃住宅の減少の実態を明らかにし、それに伴う住宅政策上の課題と居住支援の方策を模索することを目的とする。前半は、東京都における住宅政策の変遷や住環境整備の手法を整理し、民営借家の位置づけを明らかにするとともに、木造密集市街地解消によるインパクトを検証した。その後、区画整理事業を実施した田端地区において、事業前後における民営借家の変化を追った。後半では、地域内における居住支援の方策である従前居住者用住宅整備について、整備手法毎のメリットや課題を整理し、実施拡大にむけた課題を整理した。これらの結果をもとに、地域における居住支援の基本的方向を整理し、具体化に向けた課題を明らかにした。
抄録全体を表示
-
平原 幸輝
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
280-281
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
都市計画の実施にあたり地域の特性を把握し、その特性に応じた都市計画を遂行することが求められている。本研究では2015年の『国勢調査』と2018年の『住宅・土地統計調査』データを用いて、日本全国の市区町村について、各自治体の産業・職業構造に基づいて地域分類を行った上で、各地域の社会経済指標の平均値からその特性を明らかにした。その結果、日本の市区町村は6つのクラスターに分類されることとなった。特に、「グレーカラー集中地域」と「第一次産業中心地域」においては高齢化が進み、所得水準が低下しており、福祉的なアプローチを踏まえた都市計画を実行していくことが重要であるということが示された。
抄録全体を表示
-
平原 幸輝
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
282-283
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
各地域における都市開発と住民の所得状況には関連性があり、総合的な都市計画の実施のためには地域の所得分布を把握することが重要である。本研究では、2018年の『住宅・土地統計調査』データを用いて、首都圏の各市区町村について、所得分布に基づく地域の類型化を行った上で、各地域における所得状況の特性を明らかにした。その結果、首都圏の都心部には高所得者が多い自治体が集中し、首都圏の外周部には低所得者が多い自治体が集中していることが明らかになった。加えて、高所得者と低所得者が共に多く存在し、社会的分極化が進んでいる自治体が多く存在することがわかった。この地域は経済的な格差が大きく、高所得者と低所得者向けのサービスを両立した都市計画の遂行が求められていると言える。
抄録全体を表示
-
兵庫県神戸市が実施する市民花壇を事例として
大江 万梨, 太田 尚孝
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
284-287
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年地域住民が主体となって行う緑化活動に関心が寄せられている。例えば、兵庫県神戸市では1962年に地域の環境美化とコミュニティづくりを目的に「市民花壇制度」が制定され、現在735団体が活動している。本研究では市民花壇制度を事例に活動者へヒアリング調査、アンケート調査等を実施し、現在の活動状況の把握と活動が継続的に成り立つ仕組みについて調査した。その結果、活動の継続には、活動者のやりがいである活動中に発生する活動者以外の人との会話が起こりやすいようにすること、活動者の高齢化や人手不足に対応すること、ストレスのない活動の実現に向けた工夫をすることが必要であると言え、その実現に向けた提案について述べた。
抄録全体を表示
-
中央ジャワ州スマラン市を事例として
吉田 友彦, ムスティカ ワルダニ, アルプラディティア マリク
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
288-291
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、インドネシア大都市圏の公共施設・サービスに関する政府統計を通じて、郊外地域の開発過程に関する問題を考察することを目的としている。小地域ごとの社会・人口データは、郡政府が発行する統計書で入手することができる。統計書は毎年発行され、本研究では2018年のデータを使用した。スマラン市は、東に隣接するデマック県に向けて都市拡大を続けている。スマラン市の東部には多くの戸建て住宅地が開発されており、郊外特有のインフラ不足の傾向が観察される。本研究では、バイクや自家用車利用者の少なさ、小学校の少なさ、イスラム寺院の少なさ、小売店の少なさなどの弱い傾向が郊外で観察された。にもかかわらず、郊外では、よく計画された開発もあればそうでない開発もあり、非計画的住宅地開発では基盤施設の整備が不十分である傾向が見られた。
抄録全体を表示
-
ドイツ ザクセン州諸都市を事例として
清水 陽子, 中山 徹
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
292-298
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿はStadtsumbau Ostの実績と効果について調べたものである。ザクセン州の7都市を比較し、その傾向を明らかにすることを目的とする。ザクセン州ではこれまでのような人口減少は落ち着きつつある。西側への流出はほぼ見られなくなり、移動の傾向は州内の大都市へとなっている。州内の大都市では既に人口は増加し、中規模都市も安定傾向にある。これまでの人口移動の傾向は、州内から州外の流出であったが、その後大都市へ人口が集中するようになり、近年は州内大都市周辺へと移行している。しかし、人口動態についてはドイツ国内での人口は減少傾向である。人口増加は他都市からの人口流入によるものである。 国だけでなくEUも含めた支援の充実は各自治体の活動を牽引し、推進力となっている。また、補助金を獲得ことで民間の投資への動機づけとなり、地域改善の加速させることにもつながっている。
抄録全体を表示
-
樋野 公宏, 雨宮 護, 讃井 知, マシュー カレンダー, イアン ブリットン, ローラ ナイト
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
299-302
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿では、2019年9月に実施した英国の警察関連ボランティア(Citizens in Policing、以下CiP)に関する調査結果を報告する。CiPは直接または間接的に警察活動を支援する約50万人のボランティア全般を指す用語である。CiPは警察活動に対して年間約100億円の価値をもたらし、その発展は社会関係資本の構築や警察とコミュニティとの関係構築にも寄与すると考えられている。警察関連ボランティアが重視される背景には、2007年からの世界金融危機後の緊縮財政による警察の人員削減と、地域参加と地域主義を重視する政権への転換があるとされる。日本でも警察に期待される役割が拡大するなか、英国を参考に警察とボランティアとの関係性を再検討することが有意義と考えて本調査を実施した。
抄録全体を表示
-
福岡県内の移動図書館車実施状況についての調査報告
加藤 浩司
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
303-306
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
「公共図書館が図書館を利用しにくい地域の住民に対して,何らかの移動手段を用いて図書館資料を運び,図書館員による図書館サービスを提供する」活動である「移動図書館」は,地方都市に暮らす人々,特に自動車社会の中で移動が容易でない人々の,地域での生活を支える大切なサービスの一つであると考えられるが,移動図書館への社会の注目や期待は高くない。本研究は,事例調査を重ねることで,人口減少時代の地方都市における移動図書館の有用性を明らかにすることを目的とする。第一報となる本稿では,県内の市町村での事例調査を行う前提として,福岡県内で移動図書館を実施する市町村を明らかにし,当該市町村での移動図書館の実施状況(ステーションの特徴等)について調査報告を行った。
抄録全体を表示
-
小野市を事例に
大塚 一穂, 太田 尚孝
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
307-310
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究の目的は、兵庫県の特別指定区域制度を事例として、市街化調整区域における開発制限の規制緩和が持続可能なまちづくりにつながっているかに着目し、現状の成果と課題を明らかにすることである。調査対象である小野市において新築がみられたことから、特別指定区域制度は市街化調整区域内の開発制限の規制緩和として機能していることが示された。一方で、特別指定区域制度は開発動向に影響を及ぼしているとは言えず、今後より深刻になると考えられる空き家問題への影響は特段みられないことから、市街化調整区域内の問題を解消する役割として十分に機能しているとは言い難い。
抄録全体を表示
-
西坂 涼
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
311-313
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本稿は、岩手・宮城県の沿岸地域における東日本大震災の27件の復興計画を対象に、計画に位置付けられた95の震災伝承事業を抽出した。これらは、施設整備、記録整備、教育・訓練、観光・交流、その他の5種類の事業に分類された。施設整備として最も多かった事業は、復興祈念公園等の整備だった。そこで文献調査により、復興計画に復興祈念公園等の整備を位置付けた12の市町村が、震災伝承を実現するための具体的手法を明らかにした。手法は、震災遺構の保存、高台の造成、碑・モニュメントの建設、展示施設の開設、海岸林の造成、ガイドツアーの実施、参加型管理運営の実施、メモリアルイベントの実施、湿地や池沼の造成の9つに分類された。
抄録全体を表示
-
西坂 涼
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
314-317
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
東日本大震災により被災した複数の自治体が、被災した建築物や構造物を、震災遺構として整備する方針である。震災遺構には一定の整備・計画手法はなく、各自治体は復興の状況に応じて多様な手法で保存や整備を進めてきた。手法の一つとして条例を用いた例が挙げられる。本稿は、震災遺構の保存、整備、活用のために条例を策定した岩手県田野畑村、宮古市、気仙沼市、宮城県東松島市、山元町、福島県富岡町における9つの条例等について、条例等の内容や整備目的、体系を整理、考察した。震災遺構を復興祈念公園等と一体的な施設として位置付ける事例や、「保存活用計画」を定めて管理しようとする事例等が確認された。
抄録全体を表示
-
若木 美穂, 土屋 一彬, 大黒 俊哉
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
318-321
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
都市の良好な景観形成に向けた緑地保全や緑化推進の重要性の認識が高まりから、一部の地方公共団体で緑視率の都市計画での活用が進んでいるが、これまで街路における周辺土地利用と緑視率の関係について総合的に明らかにした研究はみられない。本研究では、都市の街路を対象に、統一された計測方法かつ多様な用途がなされる都市空間での緑視率と周辺土地利用の関係を明らかにし、さらに緑視率の構成要素について詳細に検討を行った。その結果、東京都心における緑視率の向上には緑被率が影響しているが、緑視率の向上には緑被率を大幅に増やすことは有効ではないこと、樹木および植込要素を充実させることで緑視率を高められる可能性が示された。
抄録全体を表示
-
永田 健一郎, 土屋 一彬, 大黒 俊哉
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
322-324
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
自然環境にストレスからの回復を促進する回復的環境としての性格があることは指摘されているが、回復効果の観点から都市の中にどのような自然環境を整備するべきかは十分に明らかになっていない。本研究は、都市の自然環境のひとつである緑道の構造多様性や個人の自然環境への感情的つながりの強さと回復特性の関係性を把握することを目的とした。東京都区部にある構造が多様な緑道と多様でない緑道での現地歩行後の質問表回答を分析した結果、緑道内の構造が多様なほど回復特性を持つ環境であるという仮説が一定程度支持された。他方で、自然環境への感情的つながりの強さと回復特性の評価の間の相関はみられなかった。
抄録全体を表示
-
滋賀県大津市南小松の観光開発と景勝保全を実例として
成田 茉優, 落合 知帆
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
325-328
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
歴史を遡ると、日本では入会による自然資源の共同管理、地域資源の活用がなされていた。任意団体である南小松入会地管理会が保有する滋賀県大津市南小松の近江舞子浜も、かつては村中共有の入会地であり、一部が財産区となっていた経緯を持つ。本研究は、約120年に渡り引き継がれてきた南小松の地域組織による観光開発と景勝保全活動を実例とし、古文書等の文献調査、聞き取り調査、現地踏査から1)入会地の歴史的変遷、2)その実態把握から地域組織による入会地管理の機能とその変遷を明らかにした。目的に則った機能分化のための組織編成、公益的利益配分、知的資源の限定を管理運営の特徴として考察した。
抄録全体を表示
-
滋賀県大津市南小松を事例として
大澤 颯太郎, 落合 知帆
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
329-332
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
滋賀県では石材加工の技術が古くから発展し、近年では多くの地域で石造物や石工の生産活動の歴史を活用した地域づくりが行われている。一方で、石材産業が発達したにも関わらず十分な歴史研究がなされてこなかった地域もあり、本研究の対象地である滋賀県大津市南小松もその一つである。本研究では石工の生産活動との関係を中心に集落の特徴を把握することを目的として、該当地域における石工の生産活動の実態と石工の生産活動と集落の関係を明らかにした。調査の結果、戦前は、採石・加工・販売の三つの過程で生産活動が成り立っており、この一連の生産活動を読み解く上で重要な建物や土地が集落に残っている事が集落の特徴として確認された。
抄録全体を表示
-
ヴァーチャルパワープラントの事業スキームに着目して
古内 大志, 村木 美貴
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
333-336
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
東日本大震災により災害時のエネルギー供給の重要性が認識され、国は市街地における太陽光発電導入を推進している。しかし、エネルギー設備の導入は初期費用が高いため、ステークホルダーの参入意欲を高める普及施策が必要とされている。そこで本研究では、市街地における太陽光発電の普及施策について、ステークホルダーの参入意欲を高める事業スキームの有効性を明らかにすることを目的とする。本研究より、市街地における太陽光発電の普及に向けては、市街地の更新に応じたエネルギー設備の導入により、各ステークホルダーのメリットを生み出す事業スキームを講じることが重要と明らかになった。
抄録全体を表示
-
船崎 公介, 村木 美貴
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
337-340
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
近年、行政は地球温暖化を背景に都市におけるエネルギーの削減を推進している。行政は地球温暖化の対策のために都市におけるエネルギーの削減を推進している。そのため、将来の長期的な削減目標を見据え、市街地の更新に合わせた段階的な環境施策の導入が必要である。しかし、環境施策の導入には多額の費用がかかるため、事業性の確保が重要とされている。本研究の目的は、長期的な削減目標の達成に向けた環境施策の導入とその際の経済性を改善する制度の活用のあり方を明らかにすることである。本研究は、環境施策の導入による削減効果の検証と環境施策の導入に合わせたBusiness Improvement District制度の活用を検討する。その結果、施策の導入の経済性のために制度の活用は可能であり、その徴収金額にも妥当性が示された。
抄録全体を表示
-
中 朝哉, 村木 美貴
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
341-344
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
地球温暖化防止のためのCO₂削減に向けたエネルギー利用の転換や、震災等の緊急時における安定的なエネルギー供給を行える都市形成が求められている。そのため国は、平常時の省エネルギー化と緊急時におけるエネルギー供給に寄与する自立エネルギーネットワークの導入を促進している。また、近年では都心部において特に高度経済成長期に建設された庁舎が老朽化により相次いで建替え時期を迎えており、それを契機としたエネルギーネットワークの導入が期待される。しかし、事業に係る初期費用は莫大であることから、高い環境性・防災性を担保しつつも各関係主体の事業性に留意した事業計画の策定が求められる。本研究では、庁舎建て替えを契機としたエネルギーネットワーク構築における事業性を明らかにし、その導入可能性を示した。
抄録全体を表示
-
千葉県大網白里市大網地域市街化区域を対象として
柴 直也
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
345-348
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
現在我が国では、人口減少を背景に空き家の増加が問題となっており、住宅の管理悪化が予測される。本研究では、遠郊外地域における既成市街地内の住宅の管理状況の実態を把握し、周辺環境や立地状況から生ずるその差異を明らかにすることを目的とする。この研究から、旧市街地は地域単位での高齢化の進行が懸念され、管理不全住宅が集中して取り残されている現状です。今後、駅前と旧市街地で二極化が進み、市街地全体の衰退に繋がるのではないかと予測される。
抄録全体を表示
-
小林 利夫, 森合 圭祐, 西浦 定継
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
349-354
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
平成29年の生産緑地法改正により、生産緑地地区の面積要件「500㎡以上」は、各自治体の条例で「300㎡以上」に変更可能となった。また、複数農地が連坦し、合計面積が面積要件以上になれば指定可能となった。しかし、連坦距離は各自治体の裁量であったため、対応が苦慮されていた。前回、試行的に日野市と国分寺市を対象に、500㎡未満及び300㎡未満の生産緑地地区を連坦距離の計測・分析をおこなった。今回、残りの多摩地域の生産緑地地区について、連坦距離の計測を進め、北多摩、南多摩、西多摩のエリア別に分析した。その結果、500㎡未満は80mから85mで同程度であった。300㎡未満は37mから114mでエリアにより差異があることを確認した。
抄録全体を表示
-
世田谷区、杉並区を対象として
渡辺 美優, 小林 利夫, 西浦 定継
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
355-358
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、過去に開園反対運動が生じた保育園、反対運動なく開園した保育園から空間的要素の特徴を見つけ、新たな候補地での反対運動有無を推定できるようにすること、また、どのような物事が反対運動となるのか察知できるようにすることも目的としている。今回の研究成果として、1つ目は反対運動が生じた保育園の特徴である。2つ目は、用途地域である。反対運動が生じた保育園の地域は第一種低層住居専用地域のみであり、2 階建ての住宅が多く、商業施設や近隣に騒音となりうるような建物は建たない地域である。このことから迷惑施設として捉えられる保育園が第一種低層住居専用地域に開設することで反対運動につながったと考えられた。
抄録全体を表示
-
千葉県における取り組みを事例として
小川 剛志
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
359-362
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
我が国は「地方分権改革」により、国から地方公共団体、都道府県から市町村への権限が委譲された。特に、都市計画の分野においては、これまで「機関委任事務」として都道府県が持っていた都市計画の決定権限や許認可権が、市町村に移譲しされ「自治事務」となり、市町村が主体的に地域の実情に応じたまちづくりが行えるようになった。本報告は、地方分権化のまちづくりにおいて、都道府県は市町村に何を支援できるのか。都道府県の役割について、千葉県の取り組みを一事例として考えてみた。
抄録全体を表示
-
楠 拓也, 吉川 徹
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
363-368
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、かかりつけ医制度導入を踏まえた日本の医療体制の将来の変化を見据えて、療養病床、精神科病床の分布の傾向を把握することを目的とした。このため、日本全国の1次医療圏と2次医療圏を対象として、AICを選択基準とした変数増減法重回帰分析を行った。目的変数は人口1万人当たりの一般病床数、療養病床数、精神科病床数として、説明変数は地域特性を表す27指標から変数選択を行ったものを用いた。結果として、療養病床や精神科病床の分布は、高齢者人口割合が高い地域かつ人口と生産年齢人口が少ない地域に偏在している傾向があった。ただし、療養病床の廃止を伴う新たな地域医療施設の配置は、コンパクトシティ政策を考慮し、長期的計画を確立し慎重に行わなければならない。
抄録全体を表示
-
井坂 和広, 村木 美貴
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
369-372
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
環境・防災都市づくりの実現が求められており、都市部・郊外部の連携が重要とされている。一方、人口減少期を迎えコンパクトシティ実現と都市再生との一体的な都市づくりが求められている。そこで米国で地域間の連携した都市再生の取り組みである開発権移転制度に着目し、国内での開発権移転制度適用による都市再生と都市全体の環境・防災都市づくりの実現のあり方を明らかにした。本研究の結論として、開発権移転制度による都市再生が都市環境・防災性の向上に資すること、また事業性の観点から有効であることが明らかとなった。
抄録全体を表示
-
西村 怜, 西浦 定継, 小林 利夫, 上杉 健太, 谷治 宣衛
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
373-377
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
多摩都市モノレールは多摩地域の南北方向の公共交通網の充実を目的として1981年に計画され、2000年に上北台から多摩センター間が開通した。現在、多摩センター駅から町田方面と八王子方面への延伸が計画されている。町田方面の計画では町田市が人口の減少抑制効果と経済効果の予測を行ったが、駅周辺の土地利用といった延伸に伴う持続的な視点による影響について考慮されているとは言い難い。このことから、駅周辺の土地利用の変化と利用者数の増減との因果関係を重回帰分析で、および新しく設置される駅へどのような手段で移動するかをパーソントリップデータを用いて分析した。利用者数に関しては妥当な結果が得られなかったが、移動手段に関しては徒歩において有意のある結果が得られた。
抄録全体を表示
-
愛媛県松野町でのワークショップの経験から
土屋 泰樹, 藤田 尚樹, 青木 悠輔, 大室 春喜, 中井 検裕, 沼田 麻美子
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
378-382
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
まちへの関心を持つことはまちづくりやシビックプライドの形成にとって重要である。しかし、普段生活する中ではまちづくりへの関心を持つきっかけは生まれにくい。そこで愛媛県松野町において中高生へのまちへの関心を持つきっかけにすることを目的としたまちづくりワークショップを開催した。ワークショップを開催したことにより、まちへの関心を高めるためには、まちの調査をすること、実際に手を動かして考えること、世代間で交流することが重要であることが分かった。
抄録全体を表示
-
中江 拓二郎, 松本 邦彦, 澤木 昌典
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
383-387
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究は、道路協力団体制度を用いた道路空間活用に着目し、道路協力団体制度で指定された民間団体の属性と活用実態を把握し、活用した道路空間の特性、並びに現行制度の課題とその要因を明らかにすることを目的とした。道路協力団体へのアンケート調査及びヒアリング調査から以下のことが明らかとなった。本制度への申請事に、道路空間の維持管理活動を期待する団体が最も多く、地域の賑わい創出にも一定の期待が持たれていたことが分かった。また収益活動を行う際には歩行者や車の通行に影響の出ない形態であることが求められ、歩行者空間でイベント事業を実施する際には、道路使用許可の基準が明確にされていないこともあり警察協議に時間を要している。さらに、収益活動を実施する上での主な障壁として、道路管理者以外の地方自治体や警察等との協力関係を築きにくいことや活動空間が限定されること、また労力に見合った収益を上げることが出来ないことが明らかになった。
抄録全体を表示
-
千葉県柏市のケーススタディ
松嶋 宏晃, 寺田 徹, 柏原 沙織
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
388-393
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
本研究では,人口減少黎明期にある首都圏郊外住宅地を対象に,空閑地を未利用空閑地と菜園利用空閑地に分類し,1) 2011年時点の空閑地の近年の変化と,2) 2019年現在の空閑地の最新実態を明らかにすることを目的とした.主要な結果として,菜園利用空閑地は未利用空閑地と比べて,他の用途に転用されずに残存する傾向にあること,未利用空閑地の量が減少している一方,菜園利用空閑地の量は増加していること,最寄駅から離れた場所で樹林地・田畑が宅地造成され,新たに空閑地が発生している一方,一度住宅として利用された空閑地は,相対的に駅から近い場所に残存していることが明らかとなった.
抄録全体を表示
-
成長都市における農的空間の計画的保全手法に関する―報告
新保 奈穂美, 太田 尚孝
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
394-397
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
成長都市において、伝統的なクラインガルテンは都市開発の圧力によって危機に晒されている。ベルリン市はそうした需要に対応するため、2019年にクラインガルテン発展計画(KEP)を改訂した。本報告はKEPがいかに変わったかを報告することにより、人口増加都市においていかに農的空間を保全していくかについて示唆を得るものである。当初のKEPは主に既存のゾーニングシステムに着目してクラインガルテンの保全指針およびその仕組みについて述べた一方、新たなKEPでは統計的・空間的分析の結果を用いてクラインガルテンの重要性を客観的に示した。さらに、改訂された保全カテゴリーのシステムは、より明確にどのクラインガルテン施設が保全されるか、あるいは開発に供されるか示すものとなった。すなわち、KEPはよりデータに裏付けられた計画となり、開発の可能性も明示したものとなったといえる。
抄録全体を表示
-
滋賀県比良山系を事例として
落合 知帆
原稿種別: 研究論文
2020 年18 巻4 号 p.
398-401
発行日: 2020/03/05
公開日: 2022/06/08
研究報告書・技術報告書
フリー
災害に対する対応は、地域の地理や地質的な特性に加えて、自然と人間との関係が顕著に表れる。かつて先人の水害対策や知恵は集落内で引き継がれてきたが、近年その機会が減っている。そこで本研究の目的を、滋賀県大津市の比良山地に位置する3集落を対象とし、地域に残る防水・砂防施設の遺構と集落住民が行っていた対策を明らかにすることとした。文献調査に加えて、古文書調査や古地図の解読、聞き取り調査および実測調査を行った。その結果、集落の山側の地質や地理的特徴によって、水害および土砂災害の被害は異なり、またその対処方法も集落により異なっていた。このため、集落に残る遺構と地域に残る伝統知を保存、活用することで、目に見える形で水害に対する伝統的な知識を身につける仕組みを作って行く事が重要である。
抄録全体を表示