巻号一覧
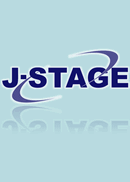
54 巻 (2008)
- 4 号 p. 432-
- 3 号 p. 282-
- 2 号 p. 110-
- 1 号 p. 2-
M33 巻 (1900)
- 336 号 p. 336_C1-
- 335 号 p. 335_C1-
- 334 号 p. 334_C1-
- 333 号 p. 333_C1-
- 332 号 p. 332_C1-
- 331 号 p. 331_C1-
- 330 号 p. 330_C1-
- 329 号 p. 329_C1-
- 328 号 p. 328_C1-
- 327 号 p. 327_C1-
- 326 号 p. 326_C1-
- 325 号 p. 325_C1-
- 324 号 p. 324_C1-
- 323 号 p. 323_C1-
- 322 号 p. 322_C1-
- 321 号 p. 321_C1-
- 320 号 p. 320_C1-
- 319 号 p. 297-
- 318 号 p. 249-
- 317 号 p. 201-
- 316 号 p. 155-
- 315 号 p. 105-
- 314 号 p. 57-
- 313 号 p. 1-
M32 巻 (1899)
- 312 号 p. 312_C1-
- 311 号 p. 311_C1-
- 310 号 p. 310_C1-
- 309 号 p. 309_C1-
- 308 号 p. 308_C1-
- 307 号 p. 307_C1-
- 306 号 p. 306_C1-
- 305 号 p. 305_C1-
- 304 号 p. 304_C1-
- 303 号 p. 303_C1-
- 302 号 p. 302_C1-
- 301 号 p. 301_C1-
- 300 号 p. 300_C1-
- 299 号 p. 299_C1-
- 298 号 p. 298_C1-
- 297 号 p. 297_C1-
- 296 号 p. 296_C1-
- 295 号 p. 295_C1-
- 294 号 p. 253-
- 293 号 p. 201-
- 292 号 p. 151-
- 291 号 p. 99-
- 290 号 p. 51-
- 289 号 p. 1-
M31 巻 (1898)
- 288 号 p. 288_C1-
- 287 号 p. 287_C1-
- 286 号 p. 286_C1-
- 285 号 p. 285_C1-
- 284 号 p. 284_C1-
- 283 号 p. 283_C1-
- 282 号 p. 282_C1-
- 281 号 p. 281_C1-
- 280 号 p. 280_C1-
- 279 号 p. 279_C1-
- 278 号 p. 278_C1-
- 277 号 p. 277_C1-
- 276 号 p. 276_C1-
- 275 号 p. 275_C1-
- 274 号 p. 274_C1-
- 273 号 p. 273_C1-
- 272 号 p. 272_C1-
- 271 号 p. 271_C1-
- 270 号 p. 267-
- 269 号 p. 211-
- 268 号 p. 161-
- 267 号 p. 107-
- 266 号 p. 53-
- 265 号 p. 1-
M30 巻 (1897)
- 264 号 p. 264_C1-
- 263 号 p. 263_C1-
- 262 号 p. 262_C1-
- 261 号 p. 261_C1-
- 260 号 p. 260_C1-
- 259 号 p. 259_C1-
- 258 号 p. 258_C1-
- 257 号 p. 257_C1-
- 256 号 p. 256_C1-
- 255 号 p. 255_C1-
- 254 号 p. 254_C1-
- 253 号 p. 253_C1-
- 252 号 p. 252_C1-
- 251 号 p. 251_C1-
- 250 号 p. 250_C1-
- 249 号 p. 249_C1-
- 248 号 p. 248_C1-
- 247 号 p. 247_C1-
- 246 号 p. 246_C1-
- 245 号 p. 201-
- 244 号 p. 165-
- 243 号 p. 109-
- 242 号 p. 61-
- 241 号 p. 1-
M29 巻 (1896)
- 240 号 p. 240_C1-
- 239 号 p. 239_C1-
- 238 号 p. 238_C1-
- 237 号 p. 237_C1-
- 236 号 p. 236_C1-
- 235 号 p. 235_C1-
- 234 号 p. 234_C1-
- 233 号 p. 233_C1-
- 232 号 p. 232_C1-
- 231 号 p. 231_C1-
- 230 号 p. 230_C1-
- 229 号 p. 229_C1-
- 228 号 p. 228_C1-
- 227 号 p. 227_C1-
- 226 号 p. 226_C1-
- 225 号 p. 225_C1-
- 224 号 p. 224_C1-
- 223 号 p. 223_C1-
- 222 号 p. 222_C1-
- 221 号 p. 211-
- 220 号 p. 157-
- 219 号 p. 109-
- 218 号 p. 59-
- 217 号 p. 1-
M28 巻 (1895)
- 216 号 p. 216_C1-
- 215 号 p. 215_C1-
- 214 号 p. 214_C1-
- 213 号 p. 213_C1-
- 212 号 p. 212_C1-
- 211 号 p. 211_C1-
- 210 号 p. 210_C1-
- 209 号 p. 209_C1-
- 208 号 p. 208_C1-
- 207 号 p. 207_C1-
- 206 号 p. 206_C1-
- 205 号 p. 205_C1-
- 204 号 p. 204_C1-
- 203 号 p. 203_C1-
- 202 号 p. 202_C1-
- 201 号 p. 201_C1-
- 200 号 p. 200_C1-
- 199 号 p. 199_C1-
- 198 号 p. 198_C1-
- 197 号 p. 197_C1-
- 196 号 p. 147-
- 195 号 p. 97-
- 194 号 p. 41-
- 193 号 p. 1-
M27 巻 (1894)
- 192 号 p. 192_C1-
- 191 号 p. 191_C1-
- 190 号 p. 190_C1-
- 189 号 p. 189_C1-
- 188 号 p. 188_C1-
- 187 号 p. 187_C1-
- 186 号 p. 186_C1-
- 185 号 p. 185_C1-
- 184 号 p. 184_C1-
- 183 号 p. 183_C1-
- 182 号 p. 182_C1-
- 181 号 p. 181_C1-
- 180 号 p. 180_C1-
- 179 号 p. 179_C1-
- 178 号 p. 178_C1-
- 177 号 p. 177_C1-
- 176 号 p. 176_C1-
- 175 号 p. 175_C1-
- 174 号 p. 174_C1-
- 173 号 p. 173_C1-
- 172 号 p. 155-
- 171 号 p. 105-
- 170 号 p. 53-
- 169 号 p. 1-
M26 巻 (1894)
- 168 号 p. 168_C1-
- 167 号 p. 167_C1-
- 166 号 p. 166_C1-
- 165 号 p. 165_C1-
- 164 号 p. 164_C1-
- 163 号 p. 163_C1-
- 162 号 p. 162_C1-
- 161 号 p. 161_C1-
- 160 号 p. 160_C1-
- 159 号 p. 159_C1-
- 158 号 p. 158_C1-
- 157 号 p. 157_C1-
- 156 号 p. 156_C1-
- 155 号 p. 155_C1-
- 154 号 p. 154_C1-
- 153 号 p. 153_C1-
- 152 号 p. 152_C1-
- 151 号 p. 151_C1-
- 150 号 p. 150_C1-
- 149 号 p. 149_C1-
- 148 号 p. 148_C1-
- 147 号 p. 103-
- 146 号 p. 51-
- 145 号 p. 1-
M25 巻 (1892)
- 144 号 p. 144_C1-
- 143 号 p. 143_C1-
- 142 号 p. 142_C1-
- 141 号 p. 1001-
- 140 号 p. 140_C1-
- 139 号 p. 139_C1-
- 138 号 p. 138_C1-
- 137 号 p. 137_C1-
- 136 号 p. 136_C1-
- 135 号 p. 135_C1-
- 134 号 p. 134_C1-
- 133 号 p. 133_C1-
- 132 号 p. 132_C1-
- 131 号 p. 131_C1-
- 130 号 p. 130_C1-
- 129 号 p. 129_C1-
- 128 号 p. 128_C1-
- 127 号 p. 127_C1-
- 126 号 p. 126_C1-
- 125 号 p. 125_C1-
- 124 号 p. 124_C1-
- 123 号 p. 101-
- 122 号 p. 51-
- 121 号 p. 1-
M24 巻 (1891)
- 120 号 p. 120_C1-
- 119 号 p. 119_C1-
- 118 号 p. 118_C1-
- 117 号 p. 117_C1-
- 116 号 p. 116_C1-
- 115 号 p. 115_C1-
- 114 号 p. 114_C1-
- 113 号 p. 113_C1-
- 112 号 p. 112_C1-
- 111 号 p. 111_C1-
- 110 号 p. 110_C1-
- 109 号 p. 109_C1-
- 108 号 p. 108_C1-
- 107 号 p. 107_C1-
- 106 号 p. 106_C1-
- 105 号 p. 105_C1-
- 104 号 p. 104_C1-
- 103 号 p. 103_C1-
- 102 号 p. 102_C1-
- 101 号 p. 101_C1-
- 100 号 p. 100_C1-
- 99 号 p. 89-
- 98 号 p. 47-
- 97 号 p. 2-
M23 巻 (1890)
- 96 号 p. 96_C1-
- 95 号 p. 95_C1-
- 94 号 p. 94_C1-
- 93 号 p. 93_C1-
- 92 号 p. 92_C1-
- 91 号 p. 91_C1-
- 90 号 p. 90_C1-
- 89 号 p. 89_C1-
- 88 号 p. 88_C1-
- 87 号 p. 87_C1-
- 86 号 p. 86_C1-
- 85 号 p. 85_C1-
- 84 号 p. 84_C1-
- 83 号 p. 83_C1-
- 82 号 p. 82_C1-
- 81 号 p. 81_C1-
- 80 号 p. 80_C1-
- 79 号 p. 79_C1-
- 78 号 p. 78_C1-
- 77 号 p. 77_C1-
- 76 号 p. 76_C1-
- 75 号 p. 75_C1-
- 74 号 p. 47-
- 73 号 p. 1-
M22 巻 (1889)
- 72 号 p. 72_C1-
- 71 号 p. 71_C1-
- 70 号 p. 70_C1-
- 69 号 p. 69_C1-
- 68 号 p. 68_C1-
- 67 号 p. 67_C1-
- 66 号 p. 66_C1-
- 65 号 p. 65_C1-
- 64 号 p. 64_C1-
- 63 号 p. 63_C1-
- 62 号 p. 62_C1-
- 61 号 p. 61_C1-
- 60 号 p. 60_C1-
- 59 号 p. 59_C1-
- 58 号 p. 58_C1-
- 57 号 p. 57_C1-
- 56 号 p. 56_C1-
- 55 号 p. 55_C1-
- 54 号 p. 54_C1-
- 53 号 p. 53_C1-
- 52 号 p. 52_C1-
- 51 号 p. 51_C1-
- 50 号 p. 49-
- 49 号 p. 1-
M21 巻 (1888)
- 48 号 p. 48_1-
- 47 号 p. 47_1-
- 46 号 p. 46_1-
- 45 号 p. 45_1-
- 44 号 p. 44_11-
- 43 号 p. 43_1-
- 42 号 p. 42_1-
- 41 号 p. 41_1-
- 40 号 p. 40_1-
- 39 号 p. 39_1-
- 38 号 p. 38_1-
- 37 号 p. 37_1-
- 36 号 p. 36_1-
- 35 号 p. 35_1-
- 34 号 p. 34_1-
- 33 号 p. 33_1-
- 32 号 p. 32_1-
- 31 号 p. 31_1-
- 30 号 p. 30_1-
- 29 号 p. 29_1-
- 28 号 p. 28_1-
- 27 号 p. 27_1-
- 26 号 p. 26_1-
- 25 号 p. 25_1-
M20 巻 (1887)
- 24 号 p. 24_1-
- 23 号 p. 23_1-
- 22 号 p. 22_1-
- 21 号 p. 21_1-
- 20 号 p. 20_1-
- 19 号 p. 19_1-
- 18 号 p. 18_1-
- 17 号 p. 17_1-
- 16 号 p. 16_1-
- 15 号 p. 15_1-
- 14 号 p. 14_1-
- 13 号 p. 13_1-
- 12 号 p. 12_2-
- 11 号 p. 11_13-
- 10 号 p. 10_12-
- 9 号 p. 9_11-
- 8 号 p. 8_11-
- 7 号 p. 7_11-
- 6 号 p. 6_10-
- 5 号 p. 5_11-
- 4 号 p. 4_10-
- 3 号 p. 3_10-
- 2 号 p. 2_10-
- 1 号 p. 1_15-
M19 巻 (1886)
- 39 号 p. 39_12-
- 38 号 p. 38_18-
- 37 号 p. 37_15-
- 36 号 p. 36_10-
- 35 号 p. 35_10-
- 34 号 p. 34_15-
- 33 号 p. 33_11-
- 32 号 p. 32_10-
- 31 号 p. 31_10-
- 30 号 p. 30_11-
- 29 号 p. 29_10-
- 28 号 p. 28_11-
- 27 号 p. 27_13-
- 26 号 p. 26_11-
- 25 号 p. 25_10-
- 24 号 p. 24_12-
- 23 号 p. 23_11-
- 22 号 p. 22_12-
- 21 号 p. 21_12-
- 20 号 p. 20_12-
- 19 号 p. 19_11-
- 18 号 p. 18_12-
54 巻, 2 号
選択された号の論文の23件中1~23を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
Contents
-
2008 年54 巻2 号 p. C5402_2
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (156K)
目次
-
2008 年54 巻2 号 p. C5402_1
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (147K)
特集 教授定年退職記念講演
-
--リンパ球機能分子と免疫調節--奥村 康2008 年54 巻2 号 p. 110-115
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー順天堂大学・免疫学教室でこの四半世紀行ってきた基礎免疫学の研究成果を要約する手段として, 以下の二つのトピックスを紹介する. 古くからT細胞の機能的亜群を分類する手段としてリンパ球表面の機能分子の研究を進めてきた. 特に, 数々の機能分子に対するモノクローナル抗体を作製し, それらの抗体を用いてin vivo, in vitroでの機能分子の働きを調べてきた. 中でもわれわれが同定で成功したB70に対する抗体と米国で同定されたB7に対する抗体を利用することによって臓器移植における永久寛容を導入することが出来, その結果が人の移植に応用されつつある進展を以下に述べる. また, もう一つのトピックスとして, 標的に細胞死を導入する分子群やそれらに対する抗体を駆使して, 今までほとんど不可能であった自然発癌における癌細胞にも, 免疫反応を惹起させることに成功し, in vivoにおいても私達の開発した抗体の投与で治療可能であることを示した. これは免疫増強に関連した抗体の組合せの投与によるもので, カクテル療法とも名付けている.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1254K) -
稲葉 裕2008 年54 巻2 号 p. 116-120
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー医学部を卒業して40年, 定年を迎えるにあたり, 自分の歩んで来た道を振り返り, 専門領域である疫学・衛生学の流れの中でどんな役割を果すことができたかを確かめることを試みた. 疫学では対象が感染症から慢性疾患へと大きく変わり, 方法論も記述疫学から分析疫学に移行し, コンピュータの発達とともに, 多変量解析が一般化してきた. 日本疫学会が設立され, 個人情報の保護への意識がたかまり, 倫理ガイドラインの策定と普及に時間をかけてきた. 衛生学では専門分野としてのアイデンテティの討議を中心に, 日本衛生学会, 衛生学・公衆衛生学教育協議会で責任ある役割を担当してきた. この分野でも倫理や行動規範が問題とされてきており, キリスト者としての立場からの発言・行動が問われていることを感じている.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (887K) -
河盛 隆造2008 年54 巻2 号 p. 121-132
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー健常人においても血糖値は食事や運動といった外乱に対応して, 絶えず変化している. 血糖値は全身でブドウ糖が処理された結果を示しているにすぎない. 血糖値は“糖のながれ”“インスリンのながれ”の結果である, と捉えてきた. 2型糖尿病の発症機序は一例一例で異なり, かつ各時点で病態は刻々と変動することから, 病態生理を的確に把握することが介入手段を決定する上で必須となろう. 糖尿病治療の目標は“血管不全”, その結果としての動脈硬化を防止することにある. 食後高血糖は動脈硬化の引き金であり, それは肝・糖取り込み率が低下した結果である, と捉え, その制御因子, ひいては血糖コントロール制御因子を体を一つのblackboxとして解明してきた. 2型糖尿病のnatural history, その背景を分子, 細胞レベルで捉えようと努力してきたが, 一応の成果があった, と満足している.おp発足以来, 代謝内分泌学講座で教育, 臨床, 研究をともに励んできた医局員一同に深謝したい.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2623K) -
鶴丸 昌彦2008 年54 巻2 号 p. 133-138
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー食道は生理機能は単純ではあるが, いったん病的状態になると意外に複雑怪奇で, 治療に難渋することが多い臓器である. 私の30余年にわたる食道外科医として歩んできた感想である. 大学卒後2年目から3年間, 会津若松市の竹田綜合病院にて研修したが, そこでの食道静脈瘤, 食道癌の経験が私の食道外科医としての契機となった. その後, 東大第2外科に入局したが, 研究は食道静脈瘤の副血行路について行った. 術中に門脈造影や縦隔の副血行路造影を行い, 形態学的に食道静脈瘤の成因に関する検討を行った. 副血行路としては左胃静脈系が関与したものが95%を占め, 短胃静脈系のみのものはわずか5%であった. 他の副血行路として脾腎静脈シャントや臍傍静脈, アランチウス静脈管なども確認した. 食道離断術では食道に入る副血行路の完全なる遮断が不可欠との結論を得た. その後, 虎の門病院消化器外科にて21年間, 秋山洋先生のもとで1344例の食道癌切除例を経験することができた. 当時の食道癌手術はいわゆる2領域郭清が行われていたが, 5生率は全国的には20%台で虎の門病院では35%であった. 1982年頃から再発の多かった上縦隔から頸部にかけてのリンパ節郭清の重要性が認識されるようになった. 私どもも3領域郭清の有効性を提唱して1984年からは定型手術とし, 手術手技の改良を経て現在に至っている. 1998年より順天堂大学に奉職する機会を与えられた. 以後10年余にわたり, 多くの患者さんに恵まれ, 最近の4年間は年間100例以上の食道切除再建を行うことができ, 全国でトップの栄誉を得ることも出来た. 925例の食道切除を行い, 手術成績も5生率が55.2%と良好な成績を収めることが出来た. 外科手術, とくに食道手術では固いきずなで結ばれたチームワークが大切であり, ともに働いた医局諸氏に感謝する. 順天堂大学は大変恵まれた環境であった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1484K) -
前原 忠行2008 年54 巻2 号 p. 139-144
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー脳を見る画像診断の進歩と現状と題して, 最新の3TMRI装置で見ることのできる脳構造についての一部を紹介する. 3T装置の特徴は, 従来の1.5T装置に比較して, より小さな構造がより明瞭に描出される事につきるが, この利点のほとんどは静磁場強度が高いことに依存している. 3T装置の利点をもたらす静磁場強度に依存する要素としては, 1. 高い信号雑音 (S/N) 比, 2. 磁化率効果の増強, 3. T1緩和時間の延長, 等が代表的で, ここでは各要素別にどのような効果があるのかを具体的な画像を呈示しつつ解説する.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3138K) -
梁井 皎2008 年54 巻2 号 p. 145-151
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー順天堂で過ごすこと22年, そのうち15年間を教授として過ごしてきた. その期間を今振り返り, 悔いを残すことなく定年退職を迎えることができた. 私の専門は形成外科学で記憶に残る仕事のひとつに, 舌下神経縦二分割移行による急性期顔面神経麻痺の治療がある. 順天堂における最後の10年間を病院の管理職を兼任し多くの問題にあたる機会に恵まれた. 動物実験室の空調トラブル, 医療安全対策, COE感染対策, 業務委託関連の根本的見直し, 医療情報センター関連, 副院長業務, 院長業務などである. 本稿では順天堂で過ごした22年間を振り返る.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2966K) -
林田 康男2008 年54 巻2 号 p. 152-157
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー1968年9月, インターン闘争の最中, 卒業し, 直ちに医師国家試験を受け, 12月に外科へ入局. その後39年間を順天堂大学で過ごした. この39年間の足跡を振り返ってみた. 外科入局後は手術と同時に内視鏡の開発, 改良等にも取り組み, 新しい診断技術の発見をも行うことができた. 外科教室に勤務しているかたわら, 医療保険の仕事も兼務となり医療保険指導医として保険全般にわたる仕事も行うことができた. また, 2001年には高齢者医療センター設立と同時に, 新しい発想のもと総合診療科構想が立ち上げられた. これに伴ない, 外科から総合診療科へ転出. 総合診療科ではプライマリーケア, 救急, 研修医の初期研修はもちろんのこと, 外科, 内科を問わず全科の診療にたずさわることを使命とし, 数多くの疾病に出合うことが得られた. まさに内視鏡による視る, 医療保険を覧る, 総合診にて診るという『ミル的』の39年間であった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3700K)
原著
-
ラクナ梗塞との比較古村 慎二, 尾崎 裕2008 年54 巻2 号 p. 158-165
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 画像解析ソフトウェアを用いた客観的評価法により, 多発性硬化症の脱髄斑辺縁部に認められる高信号帯hyperintense rimと周囲白質との信号差を検討する. また多発性硬化症とラクナ梗塞におけるhyperintense rimの出現頻度を比較検討する. 対象と方法: 2006年2月から2007年7月にMRI検査が施行され, T1強調像で結節状低信号を呈する多発性硬化症39症例239病変とラクナ梗塞34症例51病変を対象とした. MRI画像に標準化処理を施した後, 画像プロファイル解析機能を用いて脱髄斑の辺縁部と周囲白質それぞれの信号を測定した. 辺縁部白質信号比が1.05以上を呈する領域をhyperintense rimと定義した. 多発性硬化症群とラクナ梗塞群との間で, hyperintense rimの出現頻度および辺縁部白質信号比に統計学的な有意差があるか検討した. 結果: hyperintense rimと判定されたものは, 多発性硬化症群では39症例中21例 (53.8%), 239病変中81病変 (33.9%) で, ラクナ梗塞群では34症例中1例, 51病変中1病変のみであった. この2群間におけるhyperintense rimの出現頻度および辺縁部白質信号比には統計学的有意差が認められた (p<0.0001). 結論: 脱髄斑のT1強調像を定量的に解析することにより, 客観性をもってhyperintense rimの存在を評価できた. 多発性硬化症では, ラクナ梗塞と比較してhyperintense rimの出現頻度が有意に高く, 特徴的な画像所見の一つと考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2203K) -
王 美華, 片山 佳代子, 町田 和彦, 黒沢 美智子, 稲葉 裕2008 年54 巻2 号 p. 166-175
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 中国都市部高齢者のメタボリックシンドローム (MS) の実態と日常生活歩数との関連を明らかにすることを目的とした. 対象: 2004年3月の研究開始時点に中国天津市南開区にあるコミュニティ病院に登録された65歳以上の地域住民高齢者9,167人のうち, 200名が健診と質問票調査に参加した. 2005年2月に同じ健診を実施した. 質問票調査と2回の健診を受け, かつ1年間の平均歩数を測定できた90名を解析対象とした. 方法: 質問票調査と健診を受けた対象者全員 (200名) に万歩計を配布し, 1週のうち任意の3日間, 起床から就寝までの1日の歩数を1年間継続して記入するよう依頼した. この総歩数を記録日数で割った1年間の1日平均歩数を今回の日常生活歩数とした. MSの診断基準は中国のCDS (Chinese Diabetes Society 2004) に従い, 構成因子5因子中3因子以上該当する者をMSとした. 2004年と2005年の健診で2回ともMSと診断されなかった高齢者40名を非MS群とし, 2回あるいは1回MSと診断された50名をMS群とした. 解析には統計ソフトSPSS11.0Jを使用した. 結果: 対象90名は, 男性49名, 女性41名, 平均年齢 (±SD) 70.2 (±4.6) 歳, 年間の1日平均歩数 (以下歩数) (±SD) は5509 (±3480) であった. MS群 (歩数4811±2580) と非MS群 (歩数6380±4226) の歩数には有意な差が認められた (p=0.043). MS構成因子に全く該当しないグループの歩数は該当数1-4のグループより有意に多かった (p=0.004). また, 肥満群 (BMI≧25.0) の歩数は正常群 (BMI<25.0) より有意に少なく (p=0.004), 拡張期血圧 (DBP) ≧90mmHg群の歩数はDBP<90mmHg群より有意に少なかった (p=0.045). 歩数のカットポイントを各々5000歩, 6000歩, 7000歩, 8000歩として2カテゴリ化し, MS構成因子との関連を見たところ, 6000歩以上では肥満と, 8000歩では肥満および拡張期高血圧が有意な関連が認められた. 性, 年齢を調整した多重ロジスティック解析の結果, 歩数5000以上で肥満のリスク, 歩数8000以上で肥満と拡張期高血圧のリスクが有意に低かった. 結論: 中国高齢者で日常身体活動量の客観的指標である日常生活歩数はMSと関連があることが示された. 特に1日平均歩数5000以上で肥満, 8000歩以上で肥満と拡張期高血圧のリスクが低いことが示された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1671K) -
小林 裕幸, 内藤 久士2008 年54 巻2 号 p. 176-183
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 近年運動に対する筋細胞レベルでの適応現象として, 熱ショックタンパクHeat shock proteins (HSPs) の誘導が注目されている. 四肢の骨格筋では, 持久的トレーニングにより骨格筋HSP72が増加し, 加齢によりその応答性が低下することが報告されている. 横隔膜は, 呼吸筋として安静時に絶えず収縮と弛緩を繰り返し, 運動時には肺換気能力と深く関わるが, 持久的運動による横隔膜のHSP発現に関する応答は明らかではない. 本研究では持久的トレーニングおよび加齢がラット横隔膜のHSP72発現に及ぼす影響を検討した. 対象および方法: 若齢 (12週齢) および老齢 (100週齢) の雌F344ラットを若齢コントロール (非運動), 若齢トレーニング, 老齢コントロール (非運動) および老齢トレーニング (各n=6) の4群に分類した. トレーニング群には, トレッドミルによる持久的トレーニング (75-80%VO2max, 5日/週) を10週間実施した. トレーニング終了後, 横隔膜肋骨部を摘出しHSP72発現, ミオシン重鎖Myosin heavy chain (MHC) 組成およびクエン酸合成酵素Citrate synthase (CS) 活性を測定した. 結果: 横隔膜MHC組成は, 加齢によりTypeI線維の有意な増加 (p<0.05) ならびにType IId/x線維の有意な減少 (p<0.05) が見られたが, トレーニングによる変化は認めなかった. CS活性は, 若齢群においてのみトレーニンングによる有意な増加 (p<0.05) を認めた. 横隔膜HSP72のコントロール群の発現は, 若齢コントロール群 (100±16.4) と老齢コントロール群 (70.7±11.0) の間に有意な差を認めなかった. 一方, トレーニング群では, 若齢トレーニング群 (197.8±59.7) および老齢トレーニング群 (113.0±40.4) ともに, それぞれ同年齢のコントロール群と比べ, 有意な増加 (p<0.05) を認め, その増加率は, 若齢群: +98%, 老齢群: +60%と若齢群で高値であった. 結論: 持久的トレーニングは, ラット横隔膜のHSP72発現量を増大させるが, 加齢はその応答性を低下させた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1326K) -
馬 志雄, 金井 美紀, 高崎 芳成2008 年54 巻2 号 p. 184-191
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 今回われわれは, ステロイド剤を使用している膠原病患者でビスフォスフォネート製剤が使用できない症例に対し, 活性型ビタミンD3 (VitD) 製剤単独投与におけるステロイド性骨粗鬆症の治療効果を検討した. 対象: ステロイド剤を投与している膠原病患者51例で, ステロイド性骨粗犠症の治療の目的でVitD製剤を投与していない患者12名を対照群とし, 単独投与している患者39名 (男性4名, 女性35名) と比較検討した. 方法: VitD製剤の投与前, 投与後6ヵ月, 12ヵ月, 18ヵ月, 24ヵ月, 30ヵ月の時点でdualenergy X-ray absorptiometry (DXA) 法にて骨密度を測定し, VitD製剤の効果を検討した. 結果: 1) VitD群の骨密度は投与前より上昇した. 対照群では低下を示した. 2) 骨密度上昇例のステロイド剤投与量は低下例に比べ, より少ない傾向にあった. 3) 若年患者の骨密度が高く, 長期的にも上昇した. 高齢者の骨密度は低く, VitD製剤の投与にもかかわらず低下する傾向にあった. 結論: 膠原病患者のステロイド性骨粗鬆症にVitD製剤は単独で骨密度を増加した症例を認め, ビスフォスフォネート製剤を使えない症例に対して有用であると考えられた. しかし, 高齢者およびステロイド剤の大量投与患者では, 早急にビスフォスフォネート製剤の投与が重要と考える.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1122K) -
中高年と大学生を対象として堀越 あゆみ, 堀越 勝2008 年54 巻2 号 p. 192-199
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: ハーディネスは, ストレスが精神的健康に及ぼす影響の緩衝要因として海外で数多く研究されているが, 日本での研究は少なく, 日本語版の尺度の信頼性と妥当性は検証が不十分である. 本研究では, 中高年と大学生を対象に, 日本において最も有用と考えられる多田・濱野1) の15項目版ハーディネス尺度の構造, および精神的健康との関連を検討する. 対象: 関東圏に住む中高年向け会員制雑誌の50歳以上の購読者とその知人の合計750名と, 関東圏の大学に在籍する大学生164名であった. 方法: 多田・濱野の15項目版ハーディネス尺度により調査対象者のハーディネス特性を, 日本語版GHQ短縮版 (GHQ12) 2) により精神的健康を測定した. 結果: 因子分析の結果, 全ての世代および性別で, おおむね同様の3因子構造が確認された. 重回帰分析の結果, GHQ12に対してコントロールとコミットメントは負の影響を, チャレンジは正の影響を与えていた. 考察: 本調査で使用した15項目版ハーディネス尺度の信頼性と妥当性が確認された. コントロールとコミットメントは精神的健康を高め, チャレンジは阻害するという結果が示された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1179K) -
小柳 伊智朗, 濱田 千江子, 井尾 浩章, 故呂 勇樹, 稲葉 真範, 井沼 治朗, 金子 佳代, 富野 康日己2008 年54 巻2 号 p. 200-207
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー背景: 長期腹膜透析症例では, 表層を覆う中皮細胞の消失といちじるしい中皮下層の線維性肥厚, 毛細血管を含む細動静脈血管病変を中心とする組織学的変性を認め, これらの組織学的変化が透析機能低下による除水不全や細菌感染に対する防御機能低下の原因となっている. 腹膜透析の中止によって, これらの組織学的・機能的変化は改善するとの報告がある一方で, 中止後に腹膜線維化が進行し, 重大な合併症である被嚢性腹膜硬化症にいたるとする報告もみられる. hepatocyte growth factor (HGF) は, 組織修復関連因子であるとともに, 抗線維化作用を有する成長因子として知られている. 今回, われわれはクロールヘキシジンアルコールchlorhexidine gluconate (CG) を腹腔内に連続投与し作成した腹膜硬化マウスの組織修復過程を検索するとともに, この過程におけるHGFの関与を検討した. 方法: 55匹のBL/6雄マウスを2群に分け腹腔内に, 1) エタノールで溶解し, 生食で希釈した15%CG溶解液 (CG群), 2) 15%エタノール溶解液 (コントロール群) のそれぞれ0.5mlを隔日21日間注入した. 各群のマウスを投与終了時, 終了後7日, 21日, 35日目に屠殺した. 屠殺後直ちに前腹壁の腹膜を採取し, 腹膜組織のvimentin・HGF発現について免疫組織化学的に検索した. 結果: CG投与中止直後のいちじるしい血管新生を伴った間質の肥厚は, 35日後にはほぼ正常な腹膜組織に回復した. 腹膜肥厚や腹膜中皮下層への細胞浸潤は21日まではほとんど変化がなかったが, 31日では著明に改善した. 中皮下に多数のvimentin陽性細胞を認めた. 中止直後はvimentin陽性細胞が多数みられたが, 時間の経過とともに減少した. また, vimentin陽性細胞の一部にHGF陽性細胞を認め, その比率は21日目まで増加傾向を示した. 結語: CGによる腹膜障害の解除によって, 腹膜組織の修復機転が生じることが示された. この修復機転には, 間質に発現するHGFの組織修復誘導作用の関与が示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2669K) -
五十嵐 千代2008 年54 巻2 号 p. 208-213
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー職域保健において, 生活習慣病を予防するために, 肥満に対する保健指導を行うことが多い. 近年, 様々な生活習慣病につながるメタボリックシンドロームの概念から, 本来は腹部CT撮影による内臓脂肪面積を測定し, 保健指導につなげることが望ましいが, コスト, 検査時間, 被曝の問題などから, 職域の健康診断では困難である. 現在は, 職域での肥満をとらえる指標として, BMI (Body MassIndex) や体脂肪率, 臍ウエスト値 (以下腹囲) がある. 本研究では, 製造業の事務職と営業職590名を対象に, 上下肢での生体インピーダンス法による内臓脂肪測定機能付体脂肪計を用い, 内臓脂肪面積 (以下VFA推定値) を測定収, 生化学検査, 生活習慣病などとの関連について, 共分散構造分析などを用い, 検討を行った. その結果, BMIは非肥満でもVFA推定値が肥満である者が全体で5.6%, 腹囲は非肥満でもVFA推定値が肥満である者が男性で5.0%存在するなど, 〈かくれ肥満〉が存在していた. また, 生活習慣病リスクとして肥満度の関連が高いことがわかり, その肥満の指標として, VFA推定値の方がBMIや体脂肪率より関連が高く, 腹囲とほぼ変わらない高い関連性を示した. VFA推定値は, 隠れ肥満のスクリーニングなど, 的確に生活習慣病リスク者を把握できることや, 対象者への保健指導のアプローチとしてデジタルに示されることで, 対象者自らがボディーイメージしやすいことからも, 職域における健康管理において有用であるといえる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1009K) -
宮本 廣, 千葉 百子, 橋爪 真弘, 国井 修2008 年54 巻2 号 p. 214-221
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー目的: 中央アジアに位置するアラル海の大きさは徐々に減少し, もとの大きさの25%にまで縮小した. それは20世紀最大の環境破壊として知られている. この縮小に伴いアラル海の東側に生活している住民達は健康上の問題について苦情を訴えていた. われわれは2000年からこれに関連する疫学調査を行ってきた. この論文では調査地域に住む学齢期の子供達の呼吸機能障害と環境条件の関係に注目した.方法: 調査地域としてKyzylorda州のKazalinsk郡を選定し, 対照地域として調査地域からおよそ500km東の同じ州内のZanakorgan郡を選定した. 調査地域のKazalinsk郡はカザフスタン共和国でアラル海に最も近い郡である. 両地域から, 年齢6歳から15歳の被験者を住民登録台帳を使って無作為に各486人選んだ. 調査地域からは337人 (69.3%) が, 対照地域からは417人 (85.8%) がスパイロメーターによる呼吸機能試験を受けた. 環境試料の降下ばいじんと土壌は走査型電子顕微鏡, イオンクロマトグラフおよびガスクロマトグラフ質量分析計で分析した. 結果: 拘束性機能障害の発生率は対照地域より調査地域でより高かった. しかしながら, 閉塞性機能障害の発生率は両方の地域とも低かった. 粒径が10μm以下の微粒子 (以下, 浮遊粒子状物質 (SPM) という) の割合は調査地域のKazalinskで81.7%-97.7%であった. 対照地域のZanakorganは89.4%-97.4%であった. 調査地域において, 土壌試料では硫酸塩イオン, ナトリウムイオンと塩化物イオンが対照地域より高く, また残留農薬が検出された. これらの環境条件が子供達の呼吸機能障害に影響を与えている可能性が示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1744K)
抄録
-
2008 年54 巻2 号 p. 222-230
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (1954K) -
2008 年54 巻2 号 p. 231-242
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (2692K)
報告
-
-練馬病院開院から2年経過して-熊倉 誠一郎, 山口 敬介, 西原 紘子, 会沢 美由紀, 田邉 豊, 菊地 利浩2008 年54 巻2 号 p. 253-258
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリー順天堂大学医学部附属練馬病院は, 本学初の試みとなるすべての医療業務をペーパーレスで行う電子カルテシステムを導入し2005年7月1日に開院した. すべての医療業務がペーパーレスで行われる電子カルテシステムを構築するため, 電子カルテの導入とともに各部門システムも同時に立ち上げられ, すべて院内local area network (LAN) に接続された. 手術室内の麻酔記録も電子化され, LANにより電子カルテに接続されている. 会計データも同様に医事課に伝達される仕様となっており, 手術部門の稼働後, 約2年6ヵ月経過し, 日常業務にほぼ問題ない環境となっている. 病院全体をペーパーレス化する場合, 電子カルテの導入のみならず各部門サーバの導入が必要であり, それぞれを連携させるシステムの構築が必要となってくる. しかし当院では電子カルテと各部門サーバの連携が十分にとれていないため, 新規の職員情報や薬剤情報などに変更がある度に, 各部門で様々な変更作業が必要となっていることが問題点として上げられる. ペーパーレス化された手術部門の運営の為には電子カルテシステムをどのように構築するかが重要であり, 長期にわたる手術室の運営を安全・円滑に行うためもっとも重要だと考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1208K)
順天堂医学原著論文投稿ガイドライン
-
2008 年54 巻2 号 p. 278
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (252K)
順天堂医学投稿規程
-
2008 年54 巻2 号 p. 279
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (287K)
編集後記
-
木所 昭夫2008 年54 巻2 号 p. 280
発行日: 2008/06/30
公開日: 2014/11/12
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (243K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|