巻号一覧
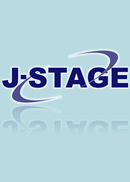
19 巻 (1968)
- 4 号 p. 487-
- 3 号 p. 341-
- 2 号 p. 131-
- 1 号 p. 1-
19 巻, 2 号
選択された号の論文の7件中1~7を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
根本 茂1968 年19 巻2 号 p. 131-230
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー自然風を対象とした現地測定は,多大な労力と経費を必要とし,なかなか充分な資料が得られないため,実用的な問題の解決にあたっては,風洞による模型実験に頼る部分が非常に多い。しかし,実験によって得た結果を自然風現象に適用する際の重要な根拠となる相似則に関しては,いろいろの提示があるにもかかわらず,まだ明確な結論が得られていない。
本研究では,定常状態で,比較的風の強い場合の近似的な相似則を取り扱った,対象とした範囲の最大は,水平方向約4km,垂直方向約1.5kmである。
まず相似の条件に関して仮説をたてた。すなわち,自然風と模型風の乱れの構造が相似であれぽ,両者の平均流のパターンの間にも相似が期待できると仮定し,ローカルな乱れの構造を特徴づける量として最小渦(Taylorの定義したいわゆる最小渦と異なり,慣性領域に属する最も小さい渦)の大きさ,速度を導入し,これにKolmogoroffの局部等方性乱流理論の第2仮説を適用し,対応する場所の最小渦の相似の条件から,(1)特別な場合として,(2)を求め,これを平均流のパターンの相似餌の条件とした。これらの条件は「分子根粘生の影響が無視できる低どの大きさの風速になると,それ以上の大きさの任意の風速で両者の平均流のパターンが相似になり,ある条件のもとでは,εM=εNの特別な場合が期待できる」ことを意味するものと理解される。これをもって相似則とし,その妥当性を実験ならびに理論的考察により検討した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (21486K) -
岡本 雅典, 魚津 博, 古川 武彦1968 年19 巻2 号 p. 231-241
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー温度,水蒸気に関し,地表面の値を用いないモデファイされた積分拡散係数を導入し,1966年千葉中央港埋立地で行なわれた野外観測(共同研究)の結果を用いてバルク法の検討を行なった。すなわち,傾度法によって求めたHおよびEと,バルク法によって求めたそれらとの比較を行ない,またモディファイされた積分拡散係数と安定度との関係を調べた。最後に,地表面の値を用いないで,HとEを評価する実験式を提案した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1160K) -
三宅 泰雄, 松葉 谷治, 西原 千鶴子1968 年19 巻2 号 p. 243-266
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー雲粒の18O含量は,閉鎖系における方が開放系におけるより大となる。また,平衡よりも非平衡条件下の方が大となる。
前線型の降水のときには,18O含量の時間的変化は開放系モデルを用いての計算にかなりよく一致する。雪をふらせる対流型のシャワーの18Oの変化は,開放型モデルで説明できる。
重い同位体を濃縮する効果は,落下雨滴と水蒸気の間の同位体交換の方が,蒸発よりも大である。落下雨滴と水蒸気の間の同位体交換反応の速度定数を計算した結果,フリードマン(1962)があたえた値の約半分になった、雨水中では計算値より小さい同位体交換量が観測された。
平衡の条件下での降水中のDと18O含量の関係は,近似的に座標原点を通る直線であらわされ,同位体の分離の小さいところでは,直線の傾斜は(αD-1)/(α18O-1)より小さい。直線からのかたよりはカイネティックな過程を考えて説明できる。直線の下へのずれはカイネティックな蒸発により,上方へのずれはカイネティックな条件での原料の供給か,同様の条件下で蒸発した水蒸気と雨滴間の同位体交換による。
Dと18O含量についてクレイグの与えた関係式の定数項は,原料になる水蒸気中の18O含量がD含量に比較して,平均1.2‰ だけ低いことに由来する。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3191K) -
三宅 泰雄, 葛城 幸雄, 杉村 行勇1968 年19 巻2 号 p. 267-276
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー東京における239Pu(期間:1958年3月~1966年末)と238Pu(期間:1959年~1966年)の積算降下量は各々0.92mCi/km2と34μCi/km2である。1959年から1966年末までの238Puと239Puの降下最の比は3.9%である。239Puと90Srの降下量の比は1.6%である。核実験にともなう239Puと238Puの全放出量は,239Puと90Srの比を1.6%と仮定すれば,各々約0.22MCiと<10kCiと推定される。1959年~1961年と1963年~1966年の期間の239Puの平均滞留時間は両者とも1.7年である。この値は90Srより求められた1.4年より若干長い。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1040K) -
奥田 穰1968 年19 巻2 号 p. 277-308
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー1951~60年の10年間について,気象官署137地点の資料を用い,日雨量≧50mm,≧100mm,≧150mm,≧200mm,以下100mmきざみで大雨日数を各月毎に取り出し,その地域特性と,特性を意味づける気象じょう乱について検討を加えた。結果を要約すると,次のとおりである。
(1)日雨量≧0.1mmの雨天日数から≧500mmの雨天日数までの階級別度数の分布は指数関数型となる。
(2)6~10月は一般に大雨度数が多いが,4月の度数の多いのも注目される。
(8)大雨日数の地域分布の特徴は,a)半島や島の東側の方が,その西側より多い。b)瀬戸内海,北海道のオホーツク海沿岸,中部地方内陸部の北部地方に著しく度数の少ない地域が現われ,特に顕著な地域は伊豆半島および紀伊半島の東側と,九州の内陸部および南東部である。
(4)(3)の地域分布の特徴は,顕著低気圧(台風を含む)の経路が東進ないし北東進するものが圧倒的に多いこと,それに伴う湿潤暖気の流入は,大気下層で南東成分をもって流入することから説明されるが,さらに,前線度数の多い地域に大雨日数の多いことも付け加えられる。瀬戸内海と中部地方内陸部の度数の少ないのは,地形の影響と考えられる。北海道,特にオホーツク海沿岸の度数の少ないのは,湿潤暖気の流入がこの地方にまで及ぶことが少ないためである。蒸気圧の平年値が13mb以下の地点では大雨日数も少ない。
(5)大雨日数の季節変化およびその年間総度数から,大雨の気候型として4個の典型に分類することが可能であり,各典型間には中間型が認められる。これらによる気候区分は,従来の気候区分にほぼ一致する。
(6)降水密度は,≧50mmおよび≧100mmの大雨日数の良い指標となる。
(7)大雨日数の多発域は季節変化しており,その変化は前線帯や,顕著低気圧,台風の発現度数,経路の季節変化によって説明される。関東地方北部や中部地方中央部の9月の多発域は雷雨によって説明される。
(8)平地と隣接する山岳部との大雨日数の比率は,≧100mmで1.4~1.6倍と山岳部が多くなり,この比率は両地点の年総降水量のそれにほぼ等しい。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5316K) -
高木 聖1968 年19 巻2 号 p. 309-322
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー1965年8月中旬より始まった松代地震は地下の岩しよう溜内の岩しようの活動によって起ったものであり,その岩しよう溜も3つ存在し,Fig.8に示したようになっている。これらの内,まず,松代岩しよう溜が活動を始め,その岩漿が地表への出口を求めて上昇して来たが,ついに地表に現われなかった。そのため,皆神山を下方から衝き上げ,南西に傾けてしまった。そうして,西条地区に東西の地割れを生じたものである。この活動の間に,隣接した若穂岩しよう溜も活動を始め,次に大峰岩しよう溜も活動したため,見かけは複雑な現象を呈したのである。これらの活動の原因は,岩しよう中に含まれる発熱原素(Th,U,Ra等)の熱エネルギーの蓄積によると考えられる。したがって,皆神山が沈下傾向を取るようになれば,活動は終末に近づいていると考えてよい。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1982K) -
広野 卓蔵, 末広 重二, 古田 美佐夫, 小出 馨1968 年19 巻2 号 p. 323-339
発行日: 1968/10/25
公開日: 2012/12/11
ジャーナル フリー本研究は本邦の地震予知に関する研究の一環として,高感度地震計の市街地における地震観測方法の改善を最終目的としている。このため,気象庁が現用している電磁式地震計と同一性能の地中地震計を開発し,これを主として地盤の雑微動の実態を解明する目的で観測井(深さ200m)の掘削過程における各種深度面(10,20,50,100,150,200m)に設置して,それぞれ地上との同時比較観測を行った。
本論文は観測資料の解析結果,また,地質調査資料について述べる。
おもな帰結;
(1) 高周波ノイズほど深さと共に減衰し,特に50mまでは著るしい。
(2)0.5cps以下の低周波ノイズはほとんど減衰しない。
(3) 周期1secの地震計による近地地震の観測を目的とする場合,50m程度の深さで著るしいSN比の改善が期待される。
(4) 重錘落下や自動車の通過によるノイズは50mより深くなると問題にならない。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3197K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|