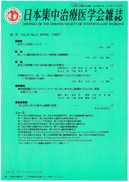巻号一覧
4 巻, 2 号
選択された号の論文の5件中1~5を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
中村 元行, 平盛 勝彦1997 年4 巻2 号 p. 97-104
発行日: 1997/04/01
公開日: 2009/03/27
ジャーナル フリー心臓由来のナトリウム利尿ペプチドは,腎排泄能,抗レニン-アルドステロン作用,血管弛緩作用を介して循環を調節する。その血中濃度は心不全の予後予測に役立つ。また,心不全などの新しい治療法に応用されつつある。内皮細胞で産生される一酸化窒素は血管弛緩のみならず平滑筋増殖や血小板凝集抑制作用をもつ。これらの産生低下は,虚血性心臓病の病因あるいは心不全の末梢循環調節異常を考えるうえで重要である。この物質は心筋内でも産生され,心機能低下や左室リモデリングの重要な因子と推定されている。血管内皮で作られるエンドセリンは血管収縮作用をもつ。心不全例でこの受容体をブロックすると血行動態が改善する。アドレノメデュリンは強力な血管弛緩作用などをもち,心不全状態で血中濃度が増加してこの病態に拮抗する可能性がある。心血管組織で合成・分泌される生理活性物質はオートクライン・パラクライン・ホルモンとして心臓血管系の機能や構造に影響を与えることが明らかとなってきた。また,これらの活性を調節することやその賦活度を測定することにより循環器疾患,特に心不全の治療と診断に新しい分野がもたらされてきた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1282K) -
加勢田 直人, 早崎 和也, 本田 喬, 堀内 賢二, 松山 公三郎, 生野 俊治, 牧 明1997 年4 巻2 号 p. 105-110
発行日: 1997/04/01
公開日: 2009/03/27
ジャーナル フリー急性心筋梗塞連続1135例のうち,75歳以上の高齢者と心原性ショック合併例に対する再灌流療法の治療成績を検討し,以下の結果を得た。(1)再灌流療法群(552例)の院内死亡率は,保存療法群(583例)より低率(11.4%vs19.7%,p<0.01)であったが,高齢者では両群の院内死亡率に差はなかった(23.1%vs29.4%)。(2)心原性ショック合併例においても再灌流療法群の院内死亡率は保存療法群より低率(51.6%vs82.0%,p<0.01)であったが,高齢者の院内死亡率は58.6%と高率であった。(3)両群の院内死亡例の死因および年齢分布に差はなく,再灌流療法群における院内死亡例の59%がポンプ失調死であり,また,51%が高齢者であった。以上から,再灌流療法による院内死亡率の減少は認められるものの,高齢者および心原性ショック合併例の予後は不良であり,短期予後の改善のために解決すべき最大の問題点と思われた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (793K) -
肝切除術での検討貝沼 関志, 山田 守正, 三宅 聰行1997 年4 巻2 号 p. 111-116
発行日: 1997/04/01
公開日: 2009/03/27
ジャーナル フリー13例の肝切除術中に,橈骨動脈と肝静脈から同時に得た血液中のアセト酢酸(AcAc)とβ-ヒドロキシ酪酸(β-OHB)の濃度および橈骨動脈血ケトン体比(AKBR)と肝静脈血ケトン体比(HKBR)の値の比較を行い,AKBRがHKBRをどのように反映するか調べた。採血は,肝切除前後には1時間間隔で行い,肝切除中は1分間以上肝静脈血酸素飽和度の値が安定したところで行った。検体数はそれぞれ80であった。結果は,回帰直線の上でAKBRが0.29より小さくなるとHKBRがAKBRより小さくなり,0.29より大きくなるとHKBRがAKBRより大きくなった。これは,手術操作に伴う肝静脈血と,上および下大静脈血の混合比の変化により,また末梢組織でのAcAcとβ-OHBのクリアランスおよび消失の時定数の違いにより,HKBRとAKBRにこのような解離が生じたものであろうと推測された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (808K) -
藤田 義人, 春原 啓一, 梶野 友世, 林 和敏, 中村 不二雄, 大林 利博, 勝屋 弘忠1997 年4 巻2 号 p. 117-123
発行日: 1997/04/01
公開日: 2009/03/27
ジャーナル フリーカテコラミンクリーゼによる急性左心不全にて発症し,体外式心肺補助(extracorporeal lung and heart assist; ECLHA)施行により救命しえた褐色細胞腫症例を経験した。36歳,男性,背部に激痛を訴えた後ショックとなった。心エコーで左室壁運動の著明な低下が認められ,心筋炎による急性左心不全を疑い人工呼吸下にカテコラミンおよび大動脈内バルーンパンピング(intra-aortic balloon pumping; IABP)で治療した。しかし循環維持は困難で,一時的なカテコラミンの増量に対し左室壁運動が改善されないことを受けECLHAを施行した。血行動態は安定し,左室壁運動が改善したところでECLHAを離脱したが,その後の循環動態はむしろ高心拍出となり降圧薬の投与を必要とした。腹部コンピューター断層撮影および血中,尿中カテコラミンより右副腎腫瘍(褐色細胞腫)と診断され,腫瘍摘出術を施行し,その後の経過は良好であったが,心電図に心筋障害と思われる異常所見を残した。われわれは,一時的なカテコラミン増量に対し左室壁運動が改善されないのを受け,さらなる薬物投与ではなく早期にECLHAを開始し良好に循環管理を施行しえた。このことは,ECLHAが褐色細胞腫のカテコラミンクリーゼのショック状態の循環維持に有用であるばかりでなく,さらなるカテコラミンによる心筋障害を予防しえたと考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1883K) -
将来計画委員会1997 年4 巻2 号 p. 125-170
発行日: 1997/04/01
公開日: 2009/03/27
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (5928K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|