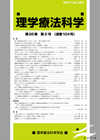-
─筋電図を用いて─
兵頭 甲子太郎, 丸山 仁司
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
183-187
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究の目的は,立位・膝立ち位にて2種類のリーチ動作を行わせ,肢位や施行方法の違いによる筋電図学的変化について検討していくことである。対象は整形外科的疾患の既住のない健常成人11名とし,立位・膝立ち位それぞれにて2つのパターンでの前方リーチ動作を行わせ,その時の大殿筋,大腿二頭筋,腹直筋,脊柱起立筋の筋活動とリーチ距離を測定した。実験の結果から,膝立ち位では立位と比べ大腿二頭筋の筋活動の割合の増加がみられた。また,リーチ動作を2つのパターンで行うことにより,筋活動に変化が表れたことから,臨床において特定の筋をより強調した形での動作が可能になるのではないかと考えている。
抄録全体を表示
-
─試合中の移動距離・移動スピードからみた生理学的特徴との関連性について─
宮森 隆行, 吉村 雅文, 綾部 誠也, 宮原 祐徹, 青葉 幸洋, 鈴木 茂雄
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
189-195
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では,大学サッカー選手25名を対象に体力測定を実施し,ポジション別での体力特性を解明するとともに,実際の試合中における移動距離・移動スピードを評価し,ポジション別での総移動距離に対する無酸素性および有酸素性エネルギー機構の動員比率を推定した。体力測定項目は,Vertical Jump,Sprint,Isokinetic muscle,YYIRT,OBLAであり,これらはポジション別での有意差は認めなかった。しかし,OBLAをもとに試合中の選手の移動距離・移動スピードの変動を評価したところ,ポジション別で要求される生理学的特徴が異なる可能性があることが示唆された。本研究結果におけるサッカーの専門的な体力評価は,実際の指導現場に反映させることにより,個々の選手の体力評価に基づく適切なポジション配置や,それぞれのチーム戦術におけるポジション別特徴を生かしたトレーニングメニューの考案などの一助となることが期待される。
抄録全体を表示
-
今井 祐子, 勝平 純司, 谷 浩明
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
197-202
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究は習得前後の者と熟練者をそれぞれ対象として,車いすキャスター上げ動作におけるヒトと車いすの合成重心,床反力作用点,合成床反力を赤外線カメラと床反力計を含む三次元動作分析装置で分析し,その運動力学的特長を明らかにすることを目的とした。計測の結果,車いすキャスター上げにはキャスターが最高点に達した後,バランス維持のために合成床反力後方成分を発生させ,ヒトと車いすの合成重心に対して床反力作用点を前方へ移動させることが必要と示唆された。
抄録全体を表示
-
藤野 英己, 上月 久治, 武田 功, 笹井 宣昌, 村上 慎一郎, 村田 伸, 石井 禎基, 松永 秀俊, 石原 昭彦, 梶谷 文彦
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
203-208
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
廃用性萎縮筋における毛細血管,及び血管増殖因子の変化をラット後肢懸垂モデルで検証した。2週間の後肢懸垂後のヒラメ筋は,正常筋に比較して,筋湿重量は61%,筋線維横断面積は47%に減少し,廃用性萎縮を示した。毛細血管・筋線維比も,廃用性萎縮筋では23%の減少を示した。骨格筋細胞における酸化的リン酸化反応を示すコハク酸脱水素酵素活性は,廃用性萎縮筋で低下し,骨格筋細胞の代謝活性が低下していることを示唆した。また,低酸素で誘導されるHIF1- αmRNAは廃用性萎縮筋では変化せず,血管増殖因子VEGF mRNAやVEGFタンパク質は有意に低下を示した。これらの結果から,廃用に伴う不活動は骨格筋細胞の酸化系酵素活性を低下させると共に,毛細血管の退行的なリモデリングを発生させ,血管増殖因子の減少が関与することを明確にした。
抄録全体を表示
-
朝山 信司
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
209-214
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
大腿骨頸部骨折の受傷者が手術後,歩行を再獲得する過程で,バランスに関わるどのような要素が歩行能力に関与するのかを検討するために,安静時重心動揺距離,受傷側下肢荷重率,Functional Reach Test,Timed Up & Go Testの結果を継時的に観察した。対象は片側に大腿骨頚部骨折を受傷し,手術加療とその後の理学療法を受けた高齢者8名であった。歩行開始後1週間おきに上記項目の測定を退院するまで実施した。その結果,対象者全員において入院期間を通して歩行速度が向上し,受傷側下肢荷重率とTUGの値に歩行開始後の1週間で急激な改善傾向が示唆された。受傷側下肢荷重率の向上は痛みの軽減と筋力の回復によるものと考えられ,同時期にTUGの値が向上したことから,その要素となっている複合的な諸動作や動的バランスには下肢の支持力が重要であることが示唆された。
抄録全体を表示
-
甲斐 義浩, 村田 伸, 竹井 和人, 志波 直人
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
215-218
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究は,肩関節周囲筋(三角筋中部線維・棘下筋・上腕二頭筋・広背筋)の最大随意収縮強度(100%MVC)を基準とし,50・25%MVCに漸減させることにより,表面筋電図周波数帯が各々の筋でどのような特性を示すのかについて検討した。分析の結果,上腕二頭筋および広背筋は,%MVCの漸減に伴い有意に周波数の低下を認めた。このことから,上腕二頭筋と広背筋は,収縮強度の低下に伴い,線維径の太いtype II線維の活動が減少し,周波数が低下したものと考えられた。一方,三角筋および棘下筋は,%MVCの漸減に伴い,有意に周波数の上昇を認めた。このことから,三角筋と棘下筋の周波数は,比較的低い収縮強度でピークに達し,収縮強度と運動単位の活動様式における特異性があることが推察された。
抄録全体を表示
-
日下 隆一, 原田 和宏, 金谷 さとみ, 浅川 康吉, 島田 裕之, 萩原 章由, 二瓶 健司, 佐藤 留美, 吉井 智晴, 加藤 めぐ美 ...
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
219-224
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
理学療法士による要介護高齢者の評価結果を分析した結果,「寝がえり」「起き上がり」「座位保時」「立ち上がり」「歩行」を一連の基本動作とした場合,基本動作の次元と要介護度および認知症とは関係性があり,これらは要介護高齢者の理学療法のポイントをより明確にするものであった。また,基本動作の自立に関しては,目的とする動作の下位に位置する動作の可否が重要であり,とりわけ「寝返りが可能な者」は「不可能な者」に比べて「起き上がり」の自立可能性が極めて高かったことは,「寝返り」動作の重要性を示すものであった。これらは,介護保険領域の理学療法提供にあたって考慮すべき視点と思われた。
抄録全体を表示
-
菅沼 一男, 丸山 仁司
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
225-228
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究は,健常人を対象とし広範囲侵害抑制調節(以下DNIC)が立位体前屈の指床間距離に及ぼす影響および効果持続時間について検討した。対象者は,健常者40名,平均年齢20.7歳を対照群とDNIC治療群に分けた。DINC治療の前後,および30分後の指床間距離を測定した。その結果,治療群において分散分析で有意差を認め多重比較(bonferroni)にて,すべての組み合わせにおいて有意差を認めた。DNICを実施することにより立位体前屈の指床間距離は大きくなり,30分後まで効果が存続した。しかし,DNIC実施30分後においてはDNIC実施時と比較して低下した。DNICの実施は指床間距離を増大させ,効果は減少傾向にあるものの少なくとも30分は効果が持続すると考えられた。
抄録全体を表示
-
柊 幸伸
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
229-234
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
立位姿勢で重心位置を最大限に移動する動作課題を与え,その時の足圧中心の移動軌跡を重心動揺計で計測した。この軌跡に囲まれる最大領域を重心移動域とした。同時に足形を方眼紙に転写し支持基底面積を計測した。本研究では,バランス制御能力評価のパラメータの1つとして,これらの比を用いる可能性を検討することを目的とした。被験者は青年男女20名(男性13名,女性7名)であった。検査台に方眼紙を敷いた重心動揺計の上で立位姿勢をとり,足形を転写した後,規定の動作を行った。支持基底面積は方眼紙上の足形の座標値より算出した。重心移動域は重心動揺計で計測した外周面積を採用した。立位姿勢は閉脚と開脚(10 cm)の2種類とした。結果,支持基底面積は閉脚時373.0±38.5 cm
2,開脚時602.9±54.2 cm
2,重心移動域は閉脚時105.7±18.2 cm
2,開脚時187.3±21.2 cm
2であった。支持基底面積に対する重心移動域の割合は閉脚時28.4±4.2%,開脚時31.3±4.3%であった。これらのパラメータはバランス制御能力評価のための指標として利用できる可能性を有していると考えた。
抄録全体を表示
-
村田 伸, 大田尾 浩, 有馬 幸史, 溝上 昭宏, 村田 潤, 弓岡 光徳, 武田 功
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
235-239
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究は,市販体重計を用いた下肢荷重力測定法の有用性とその限界について検討した。対象は片麻痺患者53名で歩行,立位保持,立ち上がり動作能力と,下肢荷重力の最大値を座位で左右別々に測定した。その結果,屋外歩行可能群と屋内歩行可能群,立位保持可能群と条件付き可能群における下肢荷重力には有意差が認められなかったが,その他の各動作では能力が高いほど下肢荷重力が有意に強かった。よって,本方法による下肢荷重力の値は,各動作の可否判定の指標となることが示唆された。ただし,歩行や立位保持動作に関しては,動作の可否判定の指標としては利用できるが,詳細な機能評価には適していない限界が示された。
抄録全体を表示
-
甲斐 義浩, 藤野 英己, 村田 伸, 竹井 和人, 村田 潤, 武田 功
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
241-244
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究は,健常成人37名を対象に,身体組成(骨格筋量・脂肪量)と上・下肢最大筋力および四肢周径を測定し,それぞれの測定値の関連性について検討した。分析の結果,男女ともに骨格筋量と上・下肢筋力との間に有意な正相関が認められた。また,上・下肢筋力は四肢周径との間にも正相関が認められたが,骨格筋量のそれと比べると低い相関であった。さらに,身体組成と四肢周径との間にも正相関が認められ,なかでも女性は脂肪量と極めて高い相関が認められた。今回の結果より,身体組成計が示す骨格筋量は上・下肢筋力を反映していることが示唆された。また,四肢周径の測定値は,筋力以外の骨格筋量や脂肪量に大きく影響を受けることが推察された。
抄録全体を表示
-
─東京都北西部における一施設での検討─
志村 圭太, 小林 修二, 佐藤 広之, 啓利 秀樹
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
245-248
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では,回復期リハビリテーション(以下リハ)病棟の導入効果を明らかにするため,開設前後における初発の脳血管障害患者316例(開設前群158例,開設後群158例)を対象に,基本属性,リハ実施時間,発症から入院までの期間(以下POA),Barthel Index(以下BI)の入院時,1,2,3ヶ月経過時の平均値と,各1ヶ月間の機能回復の伸びを示す ΔBIを比較した。基本属性は2群間で有意差を認めなかった。開設後群ではPOAが有意に短く(p<0.0001),リハ実施時間は有意に多く(p<0.0001),入院から最初の1ヶ月間の ΔBIが有意に増加した(p<0.05)。これらの結果から,回復期リハ病棟において発症早期に集中的リハを実施する効果は,入院から最初の1ヶ月間の ΔBIの増大に現れると考えられ,入院期間短縮につながる可能性が示唆された。
抄録全体を表示
-
吉澤 隆志, 太田 信夫, 藤沢 しげ子
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
249-253
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究の目的は,学習意欲が定期試験成績に及ぼす効果を調べるものである。対象は,当学院理学療法学科2年生,昼間コース学生41名および夜間コース学生40名とする。ここで,学習意欲要因としては,外発的動機づけ・内発的動機づけ・健康度(特に精神的健康度)・対人関係・学院への適応度の5つを挙げた。次に,これらの学習意欲が定期試験成績に及ぼす効果について調べた。結果としては,夜間コース学生において学院への適応度と定期試験成績との間に正の関係が見られた。よって,今後の学生指導としては,担任を中心として学生がクラスや学院に馴染めるような配慮を積極的に行っていく必要があると考える。加えて,授業方法の工夫も考慮していきたいと考える。
抄録全体を表示
-
金子 諒, 沢谷 洋平, 高橋 哲朗, 伝農 秀樹, 佐々木 誠
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
255-259
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
健常な学生28名を対象に,コントロール条件,閉脚坐位からの立ち上がりに対するPNF施行後の立ち上がり(閉脚PNF条件),開脚坐位からの立ち上がりに対するPNF施行後の立ち上がり(開脚PNF条件)の3条件で床反力を測定した。コントロール条件において,後方からの床反力を表すFxの正方向最大値は,開脚坐位よりも閉脚坐位からの立ち上がりで大きな値を示した。コントロール条件と比べてPNF条件の立ち上がりでは,垂直方向からの床反力を表すFzの最大値が高値であった。また,コントロール条件で閉脚と開脚坐位からの立ち上がりに有意差があったが,いずれの坐位においてもPNFを施行することによってその差を認めなくなった。PNF条件同士の比較では,閉脚PNF条件において開脚坐位からの立ち上がりと比較して閉脚坐位からの立ち上がりでFzの最大値が高値を示した。結果から,閉脚坐位と開脚坐位からの立ち上がりにはそれぞれ動作特性があること,いずれのPNFにおいても効果を認めること,PNFの効果は立ち上がりの動作特性により一部波及効果があること,PNFのより有効に作用する方法を用いた場合に一部動作特異性があることが示唆された。
抄録全体を表示
-
─fNIRSを用いて─
山田 実, 森岡 周, 杉村 修平
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
261-265
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
近年,運動制御過程に認知的な課題を組み入れるリハビリテーションが実施されるようになってきた。本研究の目的は,近赤外分光法(fNIRS)を用いて順序を対象とした弁別課題によって得られる脳賦活を検証することである。右利きの健常若年成人14名に対し,条件Aと条件Bの2条件において脳血流測定を行った。条件Aでは何も考えずに容器をつまみ,条件Bでは容器を5回つまみ,その中で一つだけ幅の異なる物を用意し,それが何番目であったかを実験終了後に聴取する課題であった。結果,条件Bでは運動前野,前頭連合野背外側部において有意な血流増加を認めた(p<0.05)。このことから,能動的な運動であるという条件は同じであっても,そこに弁別課題を組み込むことによって,一次的な記憶の保持や運動実行過程とそのフィードバック情報との比較を行うために前頭連合野や運動前野の機能が動員されたものと考えられた。
抄録全体を表示
-
浅川 育世, 臼田 滋, 佐藤 弘行
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
267-273
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
理学療法士がICFをどの程度認知し,活用しているかを明らかにすることを目的に,茨城県の理学療法士300名に対し,ICFの認知および利用に関する状況調査を郵送アンケート法にて実施した。その結果146通(48.7%)の有効回答が得られ,ICFに関しては殆どの回答者が認知しているものの活用されていない現状が明らかにされた。臨床場面と臨床実習場面とを比べると臨床実習場面での活用が多く,ICFが学生にとって有用であることが示唆された。一方,臨床場面ではICFを概念として使用していることはなされてきているが共通言語や調査・統計ツールとしての活用は不十分であり,今後改善の余地があることが示唆された。
抄録全体を表示
-
─入学後から2年間の追跡調査─
吉澤 隆志, 藤沢 しげ子
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
275-278
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究の目的は,内田クレペリン検査結果と留年・退学者との関係について調べることである。対象は,当学院理学療法学科学生87名(年齢24.6±6.2歳)である。結果としては,在学者と留年・退学者において,「性格・行動面の特徴」の1~3段階と4段階以上との学生間において有意に近い傾向(p<0.1)が認められた。よって,内田クレペリン検査の「性格・行動面の特徴」の結果が4段階以上と判定された学生に対しては,学業に専念できているかを常に注意して見守っていくことが必要であると考える。
抄録全体を表示
-
澤田 優子, 赤木 将男, 浜西 千秋, 朝田 滋貴, 森 成志, 丸尾 優子, 福田 寛二
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
279-283
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究の目的は,人工膝関節置換術における術後関節位置覚の経時的推移を明らかにし,膝関節位置覚の変化に影響を与える因子を抽出することである。人工膝関節置換術(以下TKA)を施行した患者30名を対象とした。術前後の位置覚を測定,得点化し,推移を明らかにした。その結果位置覚得点は3週で最も低下し,その後時間の経過に伴い改善することが分かった。術後3週での関節位置覚低下に関与する要因を検討するため,位置覚を高値群,中間群,低値群の3群に分けて関連要因を検討した。その結果,関節位置覚得点が低い群では,年齢が高い,日本整形外科学会膝関節スコアが低い,BMIが高い,術中・術後の出血量が多い,術時間が長い,皮切が大きい傾向が認められた。術前の日常生活活動性の維持,および改善が術後の膝関節位置覚の早期回復に重要と思われた。
抄録全体を表示
-
野中 紘士, 秋山 純一, 中嶋 正明
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
285-289
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
遠心性収縮による持久トレーニングが骨格筋の持久性改善に効果があるかを検討した。ICR雄マウスをコントロール群(CONT),上り走行群(求心性収縮,+16 °,UR),水平走行群(0°,LR),下り走行群(遠心性収縮,-16 °,DR)に分けた。走行運動は15 m/分で20分間とし,時間を10分/週で延長した。走行は6回/週で5週間行い,大腿四頭筋の解糖系酵素,酸化系酵素を測定した。解糖系酵素はCONT に比べ,UR,LRで上昇し,DRは変化しなかった。酸化系酵素はCONTに比べ,UR,LR,DRで上昇した。遠心性収縮による持久トレーニングは,嫌気的代謝に効果はないが,好気的代謝には効果があることが示唆された。
抄録全体を表示
-
─周術期呼吸リハビリテーションの関連─
澤田 優子, 原 聡, 廣畑 健, 南 憲司, 本田 憲胤, 西野 仁, 福田 寛二
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
291-295
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
術後在院日数を指標として呼吸リハの有用性を検討することを目的とした。リハ非実施群92名,リハ実施群87名の計179名を対象とした。平均年齢はリハ非実施群65.0±10.0歳,リハ実施群66.1±9.3歳であった。入院診療録より,性別,年齢,身体計測(体重,身長,BMI),術式,肺活量(%VC)および一秒率(FEV1.0%)などの肺機能,術中出血量,手術時間,在院日数を調査した。在院日数を短期,長期に2群し,性別,年齢などの基本属性,術式,術中所見などの手術データに加え,リハの有無との関連を検討した。一項目ずつの検定では,65歳未満,男性,出血量200 ml未満者,リハ実施群において在院日数が短いという結果が得られた。リハ実施においては,合併症の発生,在院日数延長に結びつくような状態を把握し,進めていくことが必要になる。
抄録全体を表示
-
高梨 晃, 烏野 大, 塩田 琴美, 藤原 孝之, 小沼 亮, 阿部 康次, 小駒 喜郎
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
297-300
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
2種類のアラーム無し(N1)とアラーム付き(NA1)の軟部組織硬度計を使用し,それぞれ異なる21人,22人の複数検査者(理学療法士および作業療法士)により,ポリウレタン素材のサンプル硬度を7回反復測定し,同一検査者内再現性と複数検査者間信頼性について検討した。結果N1,NA1の変動係数は,それぞれ2.9±1.3%,1.5±0.4%であり,級内相関係数(Intraclass correlation coefficients;以下ICC)はN1でICC(2・1)(2・7)=0.56,0.9,NA1ではICC(2・1)(2・7)=0.42,0.83であり,高い再現性と信頼性を示し,STSMは軟部組織硬度の定量的評価に有用である可能性が示された。
抄録全体を表示
-
明崎 禎輝, 山崎 裕司, 野村 卓生, 吉本 好延, 吉村 晋, 浜岡 克伺, 中田 裕士, 佐藤 厚
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
301-305
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では,階段昇降の自立獲得に必要な麻痺側下肢荷重率を検討した。対象は脳血管障害片麻痺患者110名である。これらの対象者に対して,年齢,体格指数,発症からの期間,非麻痺側下肢筋力,下肢ブルンストロームステージ,深部感覚障害の有無,非麻痺側・麻痺側下肢荷重率などを調査・測定した。2項ロジスティック回帰分析の結果,麻痺側下肢荷重率のみが階段昇降自立の有無に関係する有意な因子であった。さらに,階段昇降の自立獲得には麻痺側下肢荷重率のカットオフ値が84.0%において高い判別精度を示した。
抄録全体を表示
-
明崎 禎輝, 山崎 裕司, 松田 司直, 吉本 好延, 吉村 晋, 浜岡 克伺, 中田 裕士, 佐藤 厚
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
307-311
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では脳血管性認知症を呈した症例に視覚的プロンプト法を用いた杖歩行練習を実施し,杖歩行の手順獲得に対する有効性について検討した。研究デザインはシングルケースデザインを用いた。始めにジェスチャー・口頭指示期,次に歩行前と歩行中に杖歩行の手順を記載した紙を症例に提示する視覚的プロンプト期,最後に視覚的プロンプトを提示しない消去期を設けた。結果,ジェスチャー・口頭指示期では,ほとんどの歩行周期で手順の誤りを認めたが,視覚的プロンプト期では手順の誤りは0回に激減し,消去期でも0回を維持した。これらのことから,本症例において,視覚的プロンプト法は杖歩行の手順獲得に向けた有効な方法であることが示唆された。
抄録全体を表示
-
大平 雄一, 西田 宗幹, 大西 和弘, 植松 光俊
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
313-317
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では,自宅退院する入院患者の退院前後での身体活動量について比較検討することを目的とした。対象は自宅退院した回復期リハビリテーション病棟入院患者12名(男性3名,女性9名,平均年齢は72.1±9.3歳)とした。退院前3.2±1.0日と,退院後8.5±1.8日に24時間の身体活動量を携帯型身体活動量測定計アクティブトレーサーにて測定し,時間帯別の身体活動量についても比較した。また,主観的な活動感,疲労感や痛みの増減について調査した。その結果,身体活動量は自宅退院後有意に増加しており,特に19,20,21時帯の自宅での身体活動量が多かった。さらに,自宅退院後の疲労感や痛みの増加の訴えが多かった。このことより,スムーズな在宅生活への移行を図るためには入院中の身体活動量が不足しており,体力向上を目的とした理学療法プログラムや,病棟での身体活動量向上を図る介入が必要であることが示唆された。
抄録全体を表示
-
榊原 愛子
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
319-322
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
脳卒中発症後や整形外科疾患の術後早期の患者(17名)について,Berg Balance Scale(以下BBS),最大歩行速度,静止立位時の重心動揺を測定し,バランス能力を検討した。その結果,入院中に監視レベル以上の歩行が可能となった患者は,BBS合計得点が高得点で,転倒の危険がない程度の歩行能力を獲得した。しかし片足立ち,360度方向転換,タンデム立位,肩越しに後方を見る課題ではBBS得点が低く,バランスを崩しやすいことが明らかになった。さらに,健常高齢者に比べて,静止立位時は姿勢制御の微細さを示すパラメーターである単位面積軌跡長が有意に高値であり,歩行速度も有意に遅かった。以上のことから,健常高齢者と同様にバランスを保ち,歩行しているとは言えない。
抄録全体を表示
-
佐藤 香緒里, 吉尾 雅春, 宮本 重範, 乗安 整而
原稿種別: 原 著
2008 年 23 巻 2 号 p.
323-328
発行日: 2008年
公開日: 2008/06/11
ジャーナル
フリー
本研究では,股関節外旋筋群が股関節屈曲に及ぼす影響を検討することを目的とし2つの実験を行った。若年健常男女60名を対象とした股関節回旋角度の違いによる股関節屈曲角度の計測では,股関節内旋角度の増加に伴い股関節屈曲角度は有意に減少し(p<0.001),股関節外旋筋群の伸張が股関節屈曲を制限する因子として考えられた。新鮮遺体1体の両股関節後面各筋を切離するごとに股関節屈曲角度の計測と観察を行った結果,梨状筋と内閉鎖筋に著明な伸張が見られ,これらの切離後に股関節屈曲角度は顕著に増加した。梨状筋と内閉鎖筋は股関節外旋筋であることから,これらが股関節屈曲を制限している可能性があると考えられた。理学療法プログラムとして股関節屈曲可動域を拡大するときには,屈曲角度のみに注目せずに内旋角度にも注意を払う必要があると示唆された。
抄録全体を表示