巻号一覧
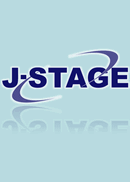
39 巻, 6 号
選択された号の論文の14件中1~14を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
榎本 卓朗, 中元 雅典, 竹内 裕一, 生駒 誓子1993 年39 巻6 号 p. 949-952
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー今回われわれは, 37歳女性の大動脈炎症候群に耳鳴, 難聴を合併した症例を経験した. 大動脈炎症候群などの自己免疫疾患に耳鳴, 難聴を伴う症例があることは今まで神崎らの報告などが認められる. われわれが経験した症例では, 大動脈炎症候群の部分症としての耳鳴, 難聴が疑われ, ステロイド剤の投与によりその症状は改善した. 耳鳴, 難聴を訴える症例に遭遇した場合, 自己免疫疾患によるものも考慮するべきと思われる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6803K) -
とくに再建手術を必要とする場合近藤 隆, 長谷川 泰久, 松浦 秀博1993 年39 巻6 号 p. 953-962
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー頭頚部領域悪性腫瘍にて再建手術を必要とした25例について前治療としての化学療法, 放射線治療, 最終目的である腫瘍切除に続く再建手術を可能にするための病名告知を含めたインフォームド・コンセント (IC) について検討した. 告知は段階的に施行し表現法に差はあつてもすべて悪性腫瘍であるという認識を本人が理解することのできるようにし, 告知後は医療スタッフ, 家族とともに協力して患者の身体的, 精神的苦悩の支えとなるべく努めた. 全例にICは成立し, 手術拒否例には遭遇しなかつた. ICに関してはいまだ確立した方式はなく, 個々の医師の判断, 患者, 家族の考えに基づいて行われているのが日本の現状であり, 諸外国とは異なるわが国独自のICが確立されるべきである. 併せて外来初診患者に病名, 検査結果の告知に関するアンケート調査を施行し, 現今の悪性腫瘍告知についての患者の意識の流れを検討した.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (21213K) -
守谷 啓司, 関谷 透, 沖中 芳彦, 大上 研二1993 年39 巻6 号 p. 963-966
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー74歳, 女性の硬口蓋小唾液腺由来の単形腺腫の一例を報告した.
本症例を含め, 本邦, 海外における小唾液腺単形腺腫症例を文献的に検討, 考察した.
小唾液腺単形腺腫は, 頻度的には口唇部とくに上口唇部に多く口蓋部は少なく, 径が 2cmを越えるものはほとんどないとされている. 本症例は硬口蓋小唾液腺由来で径が3 cm以上に及ぶまれなものであつた.
手術に際しては, 被膜のレベルで摘出し周囲粘膜はつけなくても再発はみられないとされているが, 長期観察を今後も続ける必要があるといえよう.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8743K) -
杉本 卓矢, 上村 卓也, 橋本 洋1993 年39 巻6 号 p. 967-975
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー九州大学医学部耳鼻咽喉科において1971年から1987年までの17年間に治療が行われた58例の上咽頭癌例について, 臨床病理学的に検討した. 全体の5年生存率は50%であつた. 初診時の症状では頸部腫瘤よりも鼻症状や耳症状が多かつた. 脳神経麻痺は第 V, VI, IX, X脳神経に多く見られた. 組織型による予後の差はなかつたが, 扁平上皮癌は非角化癌や未分化癌に比べ高年齢層に発生し, 性差も見られなかつた. 臨床病期では1期とII期を合計した群 (5生率: 78%) がIII期とIV期を合計した群 (5生率: 43%) よりも予後は良かつた. N分類は予後に相関したが, T分類は相関しなかつた. また未分化癌は分化型癌に比べ, 頸部リンパ節移転を来しやすい傾向にあつた. 治療に関しては, 放射線照射単独群とこれに化学療法, 手術を加えた群を比較したが, 両者には有意差は見られなかつた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (16194K) -
小川 晃弘, 西岡 慶子, 明海 国賢, 中川 文夫, 松浦 博夫, 立山 義郎, 山本 幸代, 中島 智子1993 年39 巻6 号 p. 976-981
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー頭頸部領域では比較的まれな鼻腔小細胞癌の1例を経験した. 診断に際し肺癌や食道癌など他部位からの転移との鑑別が問題となつたが, 剖検により鼻腔原発癌であることが確認された. また病理組織学的に光顕及びEGC染色により分泌顆粒の存在が疑われ, neuroendocrine carcicmaの一種である可能性が考えられたが最終的には電顕的検索により否定された.
また本症例は肝癌との重複症例であり, 経過中合併する肝硬変の悪化により死に至つた. 頭頸部癌と肝癌の重複症例及び肝重複癌の特殊性につき若干の考察を加えた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (12527K) -
佐藤 博久, 佃 守, 持松 いつみ, 湯山 誠一郎, 古川 滋, 高畑 喜延, 平田 佳代子, 澤木 修二, 古川 まどか, 久保田 彰1993 年39 巻6 号 p. 982-993
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー1979年1月から1988年12月の10年間に当教室で一次治療を行つた頭頸部悪性腫瘍 678例につき上皮性悪性腫瘍636例と非上皮性悪性腫瘍42例に分けて検討した.
(1) 上皮性悪性腫瘍 (頭頸部癌): 原発部位は喉頭が34.7%と最も多かつた. 症例数の年次別推移では中咽頭癌が増加傾向を, 鼻・副鼻腔癌は減少傾向を示した. 性比は4.0であつた. 年齢分布では男女とも60歳代がピークであつた. 臨床病期は喉頭癌を除いて大部分が進行癌の占める割合が高かつた. 頸部リンパ節転移は48.8%と高率であつた. 病理組織では扁平上皮癌が94.5%と大部分を占めていた.
(2) 非上皮性悪性腫瘍: 悪性リンパ腫が最も多く42例中35例であつた. その中では中咽頭が8例と最も多かつた. 悪性リンパ腫の性比は0.78であつた. 年齢分布は頭頸部癌と同じく60歳代にピークがみられ, 臨床病期もStageIVが最も多かつた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (18854K) -
被膜について谷垣内 由之, 浅井 忠雄, 森 朗子, 吉田 博一, 馬場 廣太郎1993 年39 巻6 号 p. 994-998
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー耳下腺腺房細胞癌の被膜と周囲耳下腺組織の形態について検討し, 次のような知見を得た.
1) 被膜および周囲組織の組織学的所見は, 多形腺腫に類似していたが, 顔面神経との関係は異なり, 本腫瘍では, 神経を被膜ごと腫瘍内に取り込んでいる像が認められた.
2) 本腫瘍は, 術前に確定診断されにくい. 全般所見からみると良性のように思われるが, 一部に悪性を疑わせる所見を認める例に注意が必要で, 術中腫瘍周囲に細血管が多く, 出血がやや多いと感じられる場合には, 本腫瘍の可能性も十分考慮に入れる必要があると思われた.
3) 転移はリンパ節に多いとされるが, 血管成分が多いことより, 血行転移にも注意する必要があると思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9891K) -
鳥原 康治, 山崎 正幸, 安達 裕一郎, 笠野 藤彦, 狩野 季代, 大迫 廣人1993 年39 巻6 号 p. 999-1003
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー宮崎医科大学耳鼻咽喉科で, 過去12年間で経験した挿管性肉芽腫16例について検討した.
男女比は, 4: 12と女性に多く, 6例が両側性であつた. 全症例で声帯突起部に肉芽腫の発生を認めた.
挿管の理由となつた14例の手術では, 肉芽腫の発生はとくに胸腔内手術に多い傾向があつた. 発症の誘因としては, 平均42.4時間にわたる挿管時間と, 2回以上の挿管操作を受けたことが関与するものと考えられた.
治療は, 原則的にラリンゴマイクロサージェリー下の切除とCO2レーザーによる蒸散およびステロイド剤の局注を行つているが, 現在のところ再発を認めていない.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8342K) -
成田 七美, 吉原 俊雄, 篠 昭男, 石井 哲夫1993 年39 巻6 号 p. 1004-1009
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー1987年より1992年5月までの約10年間に当科を受診し組織診断が可能であつた大唾液腺腫瘍112例について統計的観察を行つた. 耳下腺腫瘍100例, 顎下腺腫瘍12例でありこのうち耳下腺悪性腫瘍は16例 (16%), 顎下腺悪性腫瘍は1例 (8%) であつた. 耳下腺良性腫瘍ではpleomorphic adenomaが54例と最も多く上皮性良性腫瘍の69% を占め, 女性が72%であり平均年齢44歳であつた. 次いでmonomorphic adenomaが 24例だったがこのうち, adenolymphomaの95%が男性で, 平均年齢64歳であつた. 耳下腺悪性腫瘍はmucoepidermoid tumor・adenocarcimonaが多く, 男性に多く認めた. 顎下腺腫瘍はほとんどがpleomorphic adenomaで, 悪性の1例はaquamous cell car- cinomaであった. 自覚症状出現から受診までの期間は悪性腫瘍では良性腫瘍に比べ有意に短く, 腫瘍の大きさも悪性腫瘍に大きい傾向があつた. 疹痛・顔面神経麻痺も悪性腫瘍に特徴的な所見であつた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10798K) -
荻野 仁, 松永 亨1993 年39 巻6 号 p. 1010-1017
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー急性陰窩性扁桃炎に対する経口抗生剤・抗菌剤の統一効果判定基準の問題点を従来の比較試験成績より指摘し, 新しい統一効果判定基準の私案を報告した. すなわち, 新しい統一効果判定基準では, 評価項目および評価方法は咽頭痛, 膿苔, 発赤とし, 重症度を (+) か (-) の2段階で評価した. 臨床効果の判定は, 評価項目の状態により著効, 有効, やや有効, 無効の4段階で判定した. さらに, 評価項目のデーターの取り扱いについては観察日の症状に基づいてその前後の症状を決定し, 臨床効果を判定した. この判定基準により経時的に臨床効果と各薬剤の評価ができると考えられる.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (13601K) -
全国がん (成人病) センター頭頸部癌化学療法研究会・第2次研究報告井上 哲生, 内田 正興, 松浦 鎮, 佐竹 文介, 西尾 正道, 富樫 孝一, 竹生田 勝次, 武宮 三三, 谷川 譲, 小野 勇, 河辺 ...1993 年39 巻6 号 p. 1018-1025
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー全国のがん専門施設14施設の共同研究として頭頸部癌98例に対しCDDP+PEP+ MTX (PPM法), CDDP+PEP (PP法) の無作為比較試験を行い以下の結果を得た.
1. PPM法は46例中, CR2例, PR26例で奏効率61%, PP法は52例中, CR2例, PR10例で奏効率は23%であつた.
2. 初回再発別治療効果は, PPM法で初回治療例67%, 再発治療例50%, PP法でそれぞれ32%, 15%, 奏効率であつた.
3. 病期別治療効果では, PPM法ではIV期においても59%と高い奏効率が得られ有用性が認められた.
4. 副作用は, 白血球数が2000未満となつた症例がPPM法で36%, PP法で10%の症例に認められたが, 休薬期間中に回復した. その他, 重篤な副作用は認められなかつた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (12527K) -
全国がん (成人病) センター頭頸部癌化学療法研究会・第3次研究報告井上 哲生, 内田 正興, 松浦 鎮, 佐竹 文介, 西尾 正道, 富樫 孝一, 夜久 有滋, 竹生田 勝次, 小野 勇, 海老原 敏, 谷 ...1993 年39 巻6 号 p. 1026-1033
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー全国のがん専門施設16施設の共同研究として頭頸部癌98例に対しCDDP+PEP+ MTX (PPM法), CDDP+PEP+5FU (PPF法) の無作為比較試験を行い以下の結果を得た.
1. PPM法は44例中, CR3例, PR18例で奏効率48%, PPF法は54例中, CR2 例, PR25例で, 奏効率は50%であつた.
2. 病期別治療効果では, III期においてPPM法で90%, PPF法で63%の奏効率が得られPPM法で高い効果が認められた.
3. 初回再発別治療効果は, 初回治療例でPPM法54%, PPF法56%と高い奏効率を示したが, 再発治療例においては, それぞれ40%, 33%と低下した.
4. 副作用は, PPM法で白血球数が2000未満となつた症例が30%に認められたが, その他, 重篤な副作用は認められなかつた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10774K) -
安田 宏一1993 年39 巻6 号 p. 1035-1039
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー平衡機能検査8種 (自発眼振検査, 頭位眼振検査, 指示検査, 書字検査, 歩行検査, 足踏検査, 回転検査, 温度検査) について, その方法, 特徴, やり方のこつなどを論じた. それぞれの適した場面に応じて, これらの検査を選ぶのがよいが, 一般的には, 自発眼振検査と頭位眼振検査と足踏検査の3つを行い, 診断と経過の指標にするのがよい. この3つの検査を行うとすれば, 時間は5分程度しかからない. 温度検査は冷刺激よりも温刺激の方が, 患側を決定するのに誤りが少ない抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (317K) -
廣瀬 源二郎1993 年39 巻6 号 p. 1040-1043
発行日: 1993/11/20
公開日: 2013/05/10
ジャーナル フリー眼球運動の異常からみた脳卒中の病巣診断について論じた. 天幕上血管病変では前頭葉注視中枢 (area8) が含まれることが多く, 対側片麻痺と病巣を注視する共同偏視が特徴で, 天幕下病変では麻痺側への偏視をとる. しかし時にこれらの原則に従わない wrong side conjugate deviation (Fisher) が視床出血では高頻度にみられる. また視床後部出血では病側から対側へのsaccadichypometria, 病側へのdefective pursuit (OKNも障害), 病側のHorner徴候, 対側運動知覚障害, 対側感覚無視などの特徴的症候をとるSyndrome of posterior thalamic hemorrhage (Hirose) 力雪ある. 天幕下病変では垂直注視障害を含む背側中脳症候群, 腹側中脳症候群があり, 後者ではTo pof basilar syndromeがその代表である. MLF症候群, one and a half症候群, Wallenberg 症候群, skew deviationなどの眼球運動障害の把握が脳幹の解剖学的理解とともに重要である.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5272K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|