巻号一覧
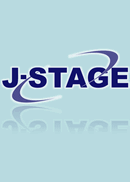
39 巻, 3 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
岡部 史郎1985 年39 巻3 号 p. 121-128
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (6701K) -
津村 健児, 山下 正幸, 渡辺 裕人, 稲葉 秀達1985 年39 巻3 号 p. 129-135
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー海水淡水化を目的とした熱拡散型積層蒸留装置を用いて太陽光により直接海水を蒸留し, 10セルの蒸留装置8台から得られた蒸留水合計の平均値W[l/m2・h] と集熱面温度TH[K] において, logWとlogTHは直線的関係にあることが実験的に確認された.
二つの任意の集熱面温度TH, およびTH'において, そのときの蒸留水収量W, およびW'は, Clausius-Clapeyronの式から誘導された第12式によって放熱面温度が一定なるときは, logWとlogTHが第13式によって直線的関係にあることが証明された.
一方, 蒸留水収量は集熱面温度と放熱面温度によって左右されることも第10式にて証明された. したがって集熱面温度が低く, 放熱面温度に接近しているときは,W→0故にlogW→-∞となり第13式に示される直線関係は不安定となる.
蒸留水収量はその対数値がlogTHだけでなく, 1/THに対しても直線的関係を示し, 蒸留装置への原水の供給量をコントロールするファクターに応用できるが, 後者の理論的解析は次の機会に述べる予定である.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4387K) -
新野 靖, 清水 典子, 西村 ひとみ, 尾方 昇1985 年39 巻3 号 p. 136-143
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー硝酸水銀滴定法 (ISO 2481), 電位差滴定法 (ISO 6227), および硝酸銀滴定法 (日本専売公社法) による食塩中の塩化物イオンの定量について, 操作, 精度, 所要時間, コストなどの面から比較検討した. 硝酸水銀滴定法は検液のpHとジフェニルカルバゾンの添加量によって影響された. 硝酸添加量は過剰になるとブランク値を増加させ, また色調の不安定を生ずるし, 不足すると定量値が低くなるから, 2N硝酸添加量0.5~1.0mlとし検液を約pH2にすると適当であった. ジフェニルカルバゾンの添加量によって終点の色調は変化するが, 定量の精度に影響しなかった. なお硝酸水銀滴定法の欠点は終点色調と終点判定用基準液の色調が一致せず, また終点の色調が不安定で分析者にしばしば不安感を与える点にある.
電位差滴定法は規定されている6種の電極の組合せでは相互に繰返し精度の差は認められなかったが, 正確さについては銀イオン選択電極とカロメル電極の組合せで比較的よい結果をえた. 滴定の繰返し精度は, 1: 電位差滴定法, 2: 硝酸銀滴定法, 3: 硝酸水銀滴定法の順に良好な結果をえた. しかし定量の全操作を通じての標準偏差はいずれもほぼ同一になった. これは希釈誤差が滴定誤差より大きいためと考えられる. 各方法の正確さは国際標準海水の基準値からの片寄りによって比較した. その結果硝酸銀滴定法が最も正確であり, 硝酸水銀滴定法はやや低い値を示し, 電位差滴定法はやや高い値を示した.
概略の分析所要時間は検液採取後で, 硝酸水銀滴定法25分, 電位差滴定法30分, 硝酸銀滴定法20分となった. 試薬コスト, 装置コスト, 人件費を試算したが人件費が試薬コストおよび装置コストより高いために試薬が高価な硝酸銀滴定法のほうが試薬の安い硝酸水銀滴定法よりむしろ全コストとしては安くなった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5284K) -
大矢 晴彦, 豊永 由布子, 島田 和彦, 根岸 洋一1985 年39 巻3 号 p. 144-151
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー電流密度を無限大としたときに観測さるべき選択透過係数 (T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=∞</USB>は, 式 (9) によって表される. 一方, 電流密度ゼロにおける選択透過係数 (T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=0</USB>を求めることができた. 実用的な電流密度において測定された選択透過係数T<USP>B</USP><USB>Na</USB>(i) を (T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=0</USB>と (T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=∞</USB>のできるだけ少ないパラメータで表現できる関数型を求めたところ, Co<USP>2+</USP>とFe<USP>3+</USP>については, 次式によって電流密度iの関数として表現できることがわかった.
T<USP>B</USP><USB>Na</USB>(i)=(T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=∞</USB>+ {(T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=0</USB>
-(T<USP>B</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=∞</USB>} e<USP>-βi</USP>(12)
ここのβの値はTable-7に示すよである. CMV膜については, Co<USP>2+</USP>, Fe<USP>3+</USP>ともに, ほぼ同一の値を示す. なお, キレート膜を用いたFe<USP>3+</USP>の場合には, 式 (12) による表現はT<USP>Fe3+</USP<USB>>Na</USB>の値が (T<USP>Fe3+</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=∞</USB>=1.36以下となるためできなかった. Fig.-4, 6中の実線およびFig.-7中のFeおよびCoに対する実線は式 (12) によって計算したものであり, 一致は良好である.
T<USP>Cr3+</USP><USB>Na</USB>については, ある程度の電流密度で, 値が (T<USP>Cr3+</USP><USB>Na</USB>)<USB>i=0</USB>の値の1/10近くまで減少してしまうために, 式 (12) による表現は不可能であった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4890K) -
鈴木 基之, 茅原 一之, 藤本 正彦, 八木 宏, 和田 明宏1985 年39 巻3 号 p. 152-163
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー海水からのウラン回収プロセスについて, ウラン生産コストの推算を行った. プロセスとして, 1次濃縮に粒径0.1mmのチタン酸 (飽和吸着量510μg-U/g-Ad, 10日間吸着量150μg-U/g-Ad) を充填した流動床を用いることとし, 吸着・洗浄・脱着・洗浄・再生において吸着剤の輸送はスラリー輸送を考えた. 脱着剤としては一例として炭酸アンモニウムを採用し, 脱着剤回収には, ストリッピング法を考えているが, 他の方法の場合はこの部分のみを簡単に修正できる. 後述のようにこの部分のコストに占める割合は小さい. 2次濃縮には, 強塩基性陰イオン交換樹脂を仮定しているが, これについても同様である. 高速増殖炉時代におけるウランの需要から1,000t-U/年の規模を想定し, 信号線図を用いる演算によりプロセス全体についての各成分の物質収支をまず決定し, その物質収支を満たす各装置の規模, さらにその各単位操作の運転費を, 詳細な化工計算により求めた. 結果として, 約16.0万円/kg-Uの総コストを最小値として得た. 全体コストのなかで, 吸着工程コストが8~9割を占め, そのうち固定費と変動費はほぼ半々で, 変動費ではポンプ動力費が大半を占めることがわかった.
今後さらに吸着工程については重点的な検討が必要であり, ポンプ動力削減のための海流や波力の直接利用等の検討が重要と思われる.
将来の高速増殖炉の実用化を仮定すれば, このウラン回収プラントは, エネルギーバランスは十分にとれ, エネルギー資源の乏しいわが国にとって, いくつかの1,000t-U/年規模のウラン回収プラントの建設は, わが国における全エネルギー消費をまかなえる可能性の高い方法で海水ウランは貴重な自給資源となろう.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7078K) -
和泉 健吉, 沢 俊雄, 山田 章1985 年39 巻3 号 p. 164-170
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー多段フラッシュ蒸発式海水淡水化装置において, 蒸発器の伝熱管に沈着するスラッジの生成機構について検討した. スラッジの主成分は有機物と鉄化合物であり, 前者は海水中の懸濁物後者は蒸発器缶体の腐食生成物と考えられる. そこで鉄化合物の酸化に伴う形態変化に関して基礎実験を進めるとともに, 実際の海水で長時間にわたる造水運転を行った100m3/dおよび2,000m3/dプラントで採取したスラッジの化学分析を実施し, 両者を比較検討した.
その結果, 腐食生成物の水酸化第一鉄Fe (OH) 2を溶存酸素により酸化したときの最終的な鉄化合物の形態は, 高温部で四三酸化鉄Fe304, 低温部でオキシ水酸化鉄γ-FeOOHとなり, 両者の温度領域は鉄濃度と溶存酸素濃度の比によって変化することがわかった. すなわち鉄濃度と溶存酸素濃度の比が小さな場合にはオキシ水酸化鉄の生成範囲が高温側に拡がり, 四三酸化鉄の生成はごく高温部に限定される.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4691K) -
乙津泊地における水質調査中原 東郎, 佐々木 英次, 神田 幸雄, 栂野 秀夫, 早野 市郎, 神谷 国男1985 年39 巻3 号 p. 171-174
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー別府湾内乙津泊地における水質調査の結果, 汚濁流入水は海水との比重差のために鉛直方向の混合が少ない状態で表層部を拡散すること, およびこの成層現象は夏期により明確に現れることがわかった. 底質のCOD, 硫化物量は上部の海水の汚濁度に関わりなくより汚濁の進んだ海域における値と同様であり, 汚濁物質が底質に蓄積することを示した. 一方, 夏期には底質中の硫酸塩還元細菌菌体数と底質中の硫化物量との間によい相関がみられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2244K) -
前田 昌調1985 年39 巻3 号 p. 175-181
発行日: 1985年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (4527K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|