巻号一覧
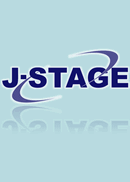
32 巻, 1 号
選択された号の論文の5件中1~5を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
杉田 静雄1978 年32 巻1 号 p. 3-33
発行日: 1978年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリースケール問題は「常に古く新しいテーマ」といわれる. 本研究は製塩と蒸留法海水淡水化におけるスケール生成と防止について基礎, 応用の両面から検討を行なったものである.生成については,
1) 海水の濃縮方法と海水中のスケール成分の挙動および付着スケールの組成の相互関係
2) 流下式塩田かん水を用いる製塩工程におけるNS三重複塩Aスケールの生成機構
3) イオン交換膜法かん水を用いる製塩工程における二ナトリウム-ペンタカルシウムサルフェイトスケールの生成機構
4) かん水中の硫酸カルシウムの転移における溶解, 析出速度
5) イオン交換膜法かん水の加熱におけるアルカリスケールの生成
6) イオン交換膜法かん水の加熱における縮合リン酸ナトリウムの分解の諸点を明らかにした.防止については,
1) アルカリおよび硫酸カルシウムスケールの生成におよぼす各種添加物の影響
2) アルカリおよび硫酸カルシウムスケールの生成におよぼす各種結晶種の影響
3) かん水予熱器のスケール防止のためのヘキサメタリン酸ナトリウム添加法の開発
4) 製塩工程のスケール防止のためのヘキサメタリン酸ナトリウム, 塩酸併用法の開発
5) 多段フラッシュ蒸発装置のスケール防止のための結晶種 [CaCO3+Mg (OH)2, CaSO4・anh], 消石灰併用法の開発について研究を行ない, 開発した方法については中間規模ないし現地試験で実証した.これらの方法のうち, 3) と4) の方法は塩田製塩法およびイオン交換膜法製塩工場に広く実用化された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (24711K) -
海水の脱気・脱炭酸 (第4報)杉野 邦雄, 小畑 健三郎1978 年32 巻1 号 p. 34-40
発行日: 1978年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリー検討した溶存酸素計はμg/l単位で指示するプロセス用計器であるが, 純水試料用に開発されている. この計器を海水試料に適用する目的で, 試作した微量溶存酸素試料調製装置に結合し, 0~60μg/lの試料濃度について初め純水, 次に海水で実験して下記の結果を得た.
1) 測定値は計算値に比例する.
2) 海水試料の測定値は純水試料の測定値より高い.
3) 試料水温は測定値に影響するが, 溶存酸素濃度の低いほうで影響は少ない.
結論として, 純水試料と同様に海水試料でも, この溶存酸素計を微量濃度測定に適用できることがわかった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4048K) -
塩の固結防止に関する研究 (第42報)増沢 力, 竹中 况三, 藤本 好恵, 鍵和田 賢一1978 年32 巻1 号 p. 41-52
発行日: 1978年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーイオン交換膜法による食塩の固結傾向と一貫パレチゼイション輸送導入による固結への影響とを検討するため, Z, W, P3製塩工場の食塩を, それぞれ生産地と中継地計6場所において, 3と6ヵ月間3パレット36段レンガ積みを対象に, 積付け試験を行ない, 次の結果を得た.
1) 積付け塩のマグネシウムは, ZとWがとくに少なくPは平均, 平均粒径はZとPが小さくWは平均であった. なお, 各工場とも日間, 年間の変動は相当に大きく, これらを小さくする必要があった.
2) 積付け試験結果をみると, Pは3と6ヵ月経過とも固結強さが1kg/cm2以下で問題ないが, ZとWは, 期間と場所により固結強さが2-5kg/cm2となり, 注意を要する.
3) すべての積付け場所の食塩の水分は, 保存中に増加した.
4) 固結強さは, マグネシウム量が少ないと, 乾燥吸湿などの気象条件が大きく影響するが, マグネシウムがある程度多いと, 気象条件に関係なく, 固結傾向を小さくすることができた.
5) 約3,700mmある食塩5k93パレット積付け塩袋は, 3カ月経過すると, 積付け時の高さに対して生産地で3.8%, 中継地で2.1%, 6カ月経過すると生産地で同じく4~5%, 中継地で2~3%沈下した. 塩の場合は, 3パレット積みでも倒壊のおそれはほとんどなかった.
6) 固結強さ1.3~3.5kg/cm2に固結した食塩5kgを, 1mの高さから水平に2回落下させると, 60%以上が砕塊した. それ以上落下させてもあまり効果が増加しなかった.
7) 一般に, イオン交換膜法による食塩の固結傾向は, 塩田法による食塩より小さいが, この原因は, 両者の液組成の差と, 前者が後者にくらべてバラツキ幅が小さくなり, マグネシウムが極端に少ないもの, 粒径が極端に小さいものがなくなったたためと推定された.
8) 一貫パレチゼイション輸送導入以前の食塩の固結強さは1.5kg/cm2以下であるが, この試験では, 0.3~4kg/cm2であった. 一貫パレチゼイション輸送導入以降の食塩の固結傾向は大きいようであるが, マグネシウムをあるレベル以上にコントロールすれば, 食塩の固結傾向を低くおさえることができた.
本研究を行なうにあたり, 種々ご協力をいただいた本社塩事業本部, 支部局塩事業部ならびに関係製塩工場の方々に厚く感謝する.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6493K) -
篠原 富男, 広井 功1978 年32 巻1 号 p. 53-57
発行日: 1978年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーガスクロマトグラフ法により食塩に添加された有機酸の定量法を検討した. リンゴ酸, クエン酸のそれぞれを含む食塩中に内部標準物質として酒石酸を加え, アセトンにごよる抽出を行ない, 抽出液の一部を分離し, 溶媒を乾固した後, 残留する3種類の有機酸を同時にN, O-ビス (トリメチルシリル) トリフロロアセトアミド (BSTFA) でトリメチルシリル化し, ガスクロマトグラフにかけた. ガスクロマトグラフの操作には, 2%OV-17/クロモソルブG (AW-DMCS){(60~80) メッシュ} を充填した分離管を使用し, 分離管温度100℃~230℃, 10℃/min昇温の条件下で行なった. この場合の保持時間, および検出率はそれぞれリンゴ酸については, 4.7min, 105%, クエン酸については, 9.1min, 106%であった.
酒石酸を内部標準として測定した場合, 食塩 (25g) に添加したリンゴ酸とクエン酸は, 0.02~0.08%の間で良好な直線関係を示した. この範囲内でのリンゴ酸の定量における再現精度は変動係数として1.2%クエン酸については2.2%であった. 食塩中に含有されるカルシウム, マグネシウム, 鉄, 銅, アルミニウムは, ほとんど妨害しなかった. 本法を用いて市販の “つけもの用塩” を分析した結果リンゴ酸0.05%, クエン酸0.04%の分析値が得られた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2841K) -
膜技術研究会 (昭和52年12月) での講演仲川 勤1978 年32 巻1 号 p. 58-66
発行日: 1978年
公開日: 2013/02/19
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (6956K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|