巻号一覧
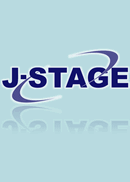
30 巻 (1992)
- 5 号 p. 867-
- 4 号 p. 707-
- 3 号 p. 517-
- 2 号 p. 333-
- 1 号 p. 1-
30 巻, 3 号
選択された号の論文の15件中1~15を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
細矢 由美子, 後藤 譲治1992 年30 巻3 号 p. 517-531
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー光重合型コンポジットレジンの経時的変色に及ぼす光照射時間の影響について観察した。
直径10mm,厚さ1mmのレジンディスクを3M社製Silux Plusを用い,厚さ1mmのガラス板を介して20秒,40秒及び120秒間光照射して作製した。試料を37℃の人工唾液中に浸漬し,硬化直後,1日,1カ月,3カ月,6カ月及び1年後の色調を背景色なしの場合と背景色が白色板の場合について高速分光光度計で測色した。
1)ΔE*ab値は,背景色の有無にかかわらず,120秒群ではほとんどのレジン色が硬化直後から6カ月もしくは1年後まで経時的増加を示した。20秒及び40秒群におけるΔE*ab値は,ほとんどのレジン色が硬化直後に対し1カ月後まで大きく増加した。
2)背景色なしの場合には,硬化直後に対する1年後のΔE*ab値は,L以外のすべてのレジン色が20秒及び120秒群と比較し,40秒群で高かった。背景色が白色板の場合には,硬化直後に対する1年後のΔE*ab値は,LとG以外のすべてのレジン色について,120秒群と比較し,20秒及び40秒群で高かった。
3)背景色なしの場合における120秒群のLとUO,40秒群のすべてのレジン色,20秒群のU,Y,L,UO,YO並びに背景色が白色板の場合における3群のすべてのレジン色について,1年後のΔE*ab値は2.5に近いか2.5以上であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2770K) -
乳歯列期に未治療の反対咬合者と比較して村上 照男, 松田 政登, 鈴木 陽, 横田 盛, 梶山 啓次郎, 玉利 和彦, 原田 保, 茂呂 直展1992 年30 巻3 号 p. 532-540
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー骨格性乳歯列反対咬合に著者らの考案した上顎前方牽引装置(MPBA)を適用し,その有効性及び若年者への効果を検討した。資料は骨格性の乳歯列反対咬合と診断され,上顎前方牽引が行われ,被蓋の改善を見た日本人女児11名の治療前後の側貌頭部X線規格写真22枚,及び乳歯列反対咬合で,その後,約2年半下顎永久前歯が萌出完了時まで反対咬合を呈していた日本人女児13名(対照群)の頭部X線規格写真,各個体3枚の計39枚である。その結果,
1)上顎ではA点,Ptm,未萌出上顎中切歯と乳歯列が前方へ有意に移動したが,口蓋平面の反時計回りへの回転とOr,PNSの前方移動には有意な変化は認められなかった。
2)下顎では後下方への有意な回転を示した。
3)B点の後方移動と上顎乳中切歯の唇側傾斜が被蓋改善に必要な動きの1/3ずつを占め,A点の前方移動と下顎乳中切歯の舌側移動が1/6ずつを占めていた。
これらのことから,本法は乳歯反対咬合者の上下顎及び歯列の成長に対し有意な変化を生じる手段であることが証明された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1935K) -
第2報 母乳と人工乳の比較宋 政文, 田村 康夫, 高柳 英司, 吉田 定宏1992 年30 巻3 号 p. 541-550
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー生後3カ月から7カ月の無歯期の乳児,乳房哺乳9名(以下母乳群)および人工乳哺乳8名(以下人工乳群)の計17名を対象に哺乳運動時の咀嚼筋活動を側頭筋前腹,咬筋,口輪筋および舌骨上筋群の4筋で比較検討し,以下の結果を得た。
1.咀嚼筋活動は両群とも主に口輪筋,舌骨上筋群が活動し,有意に側頭筋,咬筋よりも大きかった。
2.母乳群と人工乳群との比較では,各筋で両群に有意差は認められなかったが口輪筋,舌骨上筋群では母乳群が大きい活動を示す傾向がみられた。混合乳を使用している1例について母乳と人工乳の両者で比較検討すると,咬筋,口輪筋,舌骨上筋群の3筋で母乳時の方が有意に大きい筋活動を示していた。
3.哺乳行動についてみると母乳と人工乳の比較では総授乳時間には両群で差は認められなかったが休止時間,休止割合,休止回数では有意に母乳群が大きかった。
4.吸啜リズムで検討すると吸啜持続時間,吸啜サイクル,吸啜率とも両群で有意な差は認められなかった。
5.哺乳を前,中,後半と時間の経過で検討すると吸啜リズムには両群とも変化はみられなかった。しかし総筋活動量で検討すると母乳群は変化がみられなかったのに対し,人工乳群の筋活動量は低下する傾向がみられた。以上より,母乳群が人工乳群に比べより負担の大きい吸啜運動を行っていることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3851K) -
トータルエッチングとエナメルエッチングの比較検討副島 嘉男, 藤 英俊, 小笠原 靖, 久芳 陽一, 林田 宏紹, 本川 渉1992 年30 巻3 号 p. 551-567
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーコンポジットレジン充填において行われる酸処理法において,エナメルエッチング(EE)とトータルエッチング(TE)の歯髄への為害性の差異に関して,幼犬乳歯にClearfil-Posteriorを用い,術後3日から35日までの各期間において,病理組織学的に検索したところ,以下のような結果を得た。
1)窩底象牙質の厚径は種々のものがあったが,歯髄変化と窩底象牙質厚径との間には関連性はなく,厚径の厚薄に関係なく歯髄反応は類似した経過を示していた。
2)病理組織学的変化は,EEとTEの両群において大差はなく,両群ともに術後7日目までは炎症性変化が認められたものの,14日目以後では変化は消退し,修復反応の出現が認められた。
以上より,エッチングによる歯髄への刺激性は少なく,しかもエナメルエッチングとトータルエッチング間に差が認められなかった。また歯髄における炎症性反応も軽度のものが多く,みられた反応も早期に消退していた。なお形成された修復象牙質も緊密な構造をしているものが多かったことから,コンポジットレジン(Clearfil-Posterior)自体の刺激性も少ないと考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (21712K) -
第1報 適応児と不適応児の比較福田 理, 田中 泰司, 柳瀬 博, 黒須 一夫1992 年30 巻3 号 p. 568-574
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー歯科治療前後の小児の尿中カテコールアミンの測定により,適応児と不適応児の相違ならびに歯科治療時の行動と尿中カテコールアミンとの関連性について3~8歳の健康な小児13名を対象に検討し,以下の結果を得た。
1)アドレナリンでは,ほとんど全ての症例において,術前値に比べ術後値が増加する傾向を示した。
2)ドーパミンとノルアドレナリンでは,術前値と術後値の間に一定の傾向は認められなかった。
3)適応児では,アドレナリンが術前に対し術後,有意(p<0.05)に増加する傾向を示し,変化率ではドーパミン11.4%,ノルアドレナリン-0.5%,アドレナリン52.2%となっていた。
4)不適応児では,アドレナリン,ノルアドレナリンが術前に対し術後,有意(p<0.01,p<0.05)に増加する傾向を示し,変化率ではドーパミン0.8%,ノルアドレナリン16.9%,アドレナリン172.1%を示していた。
5)アドレナリンの変化率と歯科治療時の行動との間に高い正の相関(r=0.74,P<0.01)が認められた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1227K) -
第5報 上顎側切歯について土居 久美子, 関本 恒夫, 辻 裕子, 斉藤 文子, 大出 リエ子, 苅部 洋行, 高橋 美保子, 牧 志寿子, 坂井 正彦, 菊池 進1992 年30 巻3 号 p. 575-580
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー上顎永久側切歯の叢生状態に着目し,本研究では上顎永久側切歯の排列状態と上顎乳側切歯の排列状態,乳側切歯部歯槽部の大きさ,および乳側切歯の歯軸角との関連性について検討を加えた。
資料は日本歯科大学歯学部小児歯科学教室所蔵の経年資料のうち,歯列が正常な永久歯列に推移した26症例(正常咬合群)と乳歯列が永久歯列に推移した際に上顎両側の側切歯が口蓋側に萌出し逆被蓋となった7症例(逆被蓋咬合群)の経年歯列石膏模型(上顎)を使用した。
1.乳側切歯の排列状態は正常咬合群では乳側切歯が正常に排列しているA型46% ,近心部が舌側に捻転して排列しているE型40%,遠心が舌側に捻転しているD型8%,舌側に転位しているC型6%で,逆被蓋咬合群では,A型22%,C型14% ,E型64%を示し,正常咬合群と逆被咬合群では各型の出現頻度に差がみられた。
2.逆被蓋咬合群は正常咬合群に比べ,乳側切歯部の歯槽基底長径,歯槽基底高径において有意に小さく認められた。
3.逆被蓋咬合群は正常咬合群に比べ,乳側切歯の歯軸角度が小さい傾向がみられた。
以上のように,永久歯列において側切歯が逆被蓋となるような症例では乳歯列期においてすでに形態的な特微がみられ,特に乳側切歯部の歯槽部の大きさと乳側切歯の歯軸角度でその特徴は著明であった。
このことは咬合誘導を行っていく上で,乳歯列期における重要な情報源となると思われた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1355K) -
川田 寛子, 谷 博司, 中山 務, 栗原 洋一1992 年30 巻3 号 p. 581-589
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーコンピュータと直結した三次元測定機システムをもちいて下顎第二乳臼歯最大豊隆線および歯頚線を計測し,咬合面方向と咬合面水平方向より位置的関係を観察した結果,以下のことが認められた。
1)咬合面方向において最大豊隆線と歯頚線は,全体的に正の相関があることが認められた。とくに相関が高い部分は遠心部中央から遠心舌側隅角部にかけてであり,低い部分は近心舌側隅角部であった。
2)咬合面方向においては,最大豊隆線と歯頚線の相関が高く位置的に最も安定している部分は,遠心部中央から遠心舌側隅角部であった。
3)咬合面水平方向において最大豊隆線と歯頚線は,近心頬側隅角部付近から遠心頬側隅角部付近までの部分に正の相関があることが認められた。とくに相関が高い部分は遠心頬側咬頭頬側面であり,相関が低い部分は近心頬側隅角部および遠心頬側隅角部であった。
4)咬合面水平方向においては,最大豊隆線と歯頚線の相関が高く位置的に最も安定している部分は,遠心頬側咬頭頬側面から遠心頬側面溝付近にかけての部分であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1866K) -
牧 憲司, 高江洲 旭, 上田 秀朗, 加来 昭典, 児玉 昭資, 高峯 明彦, 山野 博文, 木村 光孝1992 年30 巻3 号 p. 590-597
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー近年,小児は硬い食品を嫌い,柔らかい食品を好み,食物摂取機能の劣化の傾向にあることが報告されている。我々臨床家においても小児の咬合異常,歯牙と顎骨のdiscrepancyの問題には頻繁に遭遇する。このような流れの中で小児の顎骨への物理的刺激量を知るために,今回我々は咬合力と咀嚼能力を知る目的で,九州歯科大学附属病院小児歯科外来を受診した3歳から5歳までの小児80名を対象に咬合力と咀嚼能力を測定し次のような結果を得た。
1.咬合力の平均値は男児において3歳14.00 kg,4歳15.64 kg,5歳21.33kg,女児においては3歳13.70kg,4歳15.21kg,5歳20.40kgであった。年齢とともに咬合力は増加傾向にあった。
2.咀嚼能力はATP穎粒剤を使用し,30回被験児に咀嚼させた後,分光光度計で測定した。平均値は男児において3歳0.096Abs,4歳0.113Abs,5歳0.127Abs,女児においては3歳0.092Abs,4歳0.111 Abs,5歳0.117Absであり,加齢とともに増加傾向であった。また,検量線を作製後(Y=0.726X)%に換算したところ,男児においては3歳は7.00%,4歳は8.20%, 5歳は8.47%であり,女児においては3歳は6.69%,4歳は8.05%, 5歳は8.49%であった。
3.咬合力と咀嚼能力の相関係数は全体では0.635であった(P<0.01)。年齢別の相関係数は,3歳児r=0.613,4歳児 r=0.332, 5歳児r=0.550であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1682K) -
木村 光孝, 牧 憲司, 田窪 二郎, 木村 京子, 秀島 治, 春岡 誠, 野沢 典央, 中島 龍市, 竹下 尚利, 渡辺 博, Raym ...1992 年30 巻3 号 p. 598-617
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー幼若犬の歯根未完成永久歯に50gと200gの荷重を加えて移動時における細胞の変化を透過電顕的に観察し,次のような結果を得た。
1.圧迫側の変化術後3日目では50g群,200g群ともに線維芽細胞と骨芽細胞は変性像がみられた。細胞内小器官のミトコンドリアに最も変化が認められ,細胞質内にはライゾーム様densebodyがみられた。骨細胞にも壊死がみられた。破骨細胞にはruffled border がみられ,その直下にもライゾーム様dense bodyがみられた。またマイクロファージ様細胞も認められた。
2週間では,変性像を呈する細胞は減少し,細胞レベルでの修復機転が起こっていた。
1カ月では細胞の修復が更に進み,硝子様変性像や破壊された細胞は3日,2週間と比較して減少していた。
2.牽引側の変化
術後3日,2週間においては線維芽細胞,骨芽細胞では細胞内小器官が発達し,特に粗面小胞体,ゴルジ装置の発達が著明で,細胞活性の高さが示唆された。骨細胞は歯槽骨の比較的表層にみられるものは骨芽細胞と形態が類似していたが,骨質の内部にみられるものは細胞内小器官の減少が著明であった。
術後1カ月に至ると線維芽細胞,骨芽細胞,セメント芽細胞は歯根の形成に伴って細胞内小器官の減少が認められた。
3.コラーゲン線維の変化
圧迫側,牽引側ともに周期性横紋にはほとんど変化はみられないが,牽引側でわずかに配列が疎であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (46598K) -
前田 隆秀, 荻原 清美, 栗原 洋一1992 年30 巻3 号 p. 618-623
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー著者らの教室では長年にわたり種々の系統の近交系マウスを用い,多因子性疾患である齲蝕の発症にhost側の感受性が遺伝することを明らかにしてきた。今回は異なった系統の近交系マウスを用い,齲蝕感受性の遺伝形式を確認すると共に主要組織適合抗原系(MHC)の関わりを検討した。
供試マウスとしてはMHCであるH-2のハプロタイプがkで,齲蝕抵抗性マウスであるAKR/JSlcマウスとH-2ハプロタイプがbで齲蝕感受性マウスであるC57BL/6NJclマウスを親系統とし,この2系統のマウスより得たF2マウス,ならびにN2マウスを用いた。実験方法としては21日齢より1週間streptomycin耐性としたStreptococcus mutansJC-2(serotype c)菌株を感染させ90日齢にて屠殺し,齲蝕スコアを算定し判別関数より蝕感受性マウスと齲蝕抵抗性マウスに分別した。その結果,次のような知見を得た。
1.親系統でH-2ハプロタイプがbであるC57BL/6NJcl マウスは,齲蝕感受性マウスであることを再確認した。
2.親系統でH-2ハプロタイプがkであるAKR/JSclマウスは,齲蝕抵抗性マウスであることを再確認した。
3.F2マウスは,齲蝕感受性マウスと齲蝕抵抗性マウスに分別でき,その匹数の割合はほぼ3:1になった。(X2=0.16 自由度=1 確率=0.68)
4.N2マウスは,齲蝕感受性マウスと齲蝕抵抗性マウスに分別でき,その匹数の割合は1:1になった。(X2=0.00 自由度=1 確率=1.00)以上の知見ならびに内藤,Kuriharaらの知見より,マウスの齲蝕発症には親系統の持つ遺伝形質,とくにH-2領域の遺伝子が大きく関与していることが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1260K) -
加納 能理子, 真柳 秀昭, 斉藤 徹, 神山 紀久男1992 年30 巻3 号 p. 624-633
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー萌出間もない第一大臼歯の齲蝕感受性は著しく高く,特にその好発部位である咬合面裂溝の封鎖による齲蝕予防法は従来より広く行われてきた。本研究は,東北大学歯学部附属病院小児歯科外来にて管理を行っている患者の第一大臼歯に光重合型シーラントを填塞した症例を長期にわたり観察し,シーラントの保持状況を調査することを目的としたもので,以下の知見を得た。
1)シーラントの咬合面での完全保持率は,12カ月時,上顎で約9割,下顎で10割を示したが,36カ月以上経過すると,上下顎とも保持率が6割となった。平滑面(頬側面溝,舌側面溝)の完全保持率は,12カ月時,上下顎ともに7割を示したが,36カ月以上経過すると3割となった。
2)窩溝別の保持率は,12カ月,36カ月時ともに,上下顎で,遠心小窩に比べて近心小窩で低い値を示した。
3)填塞時の齲蝕罹患の有無や程度と,保持率との間には関係は認められなかった。
4)咬合面では,12カ月以内で経過が良好な場合,上下顎ともに約6割の症例で36カ月以降の経過も良好であることが示唆された。平滑面では,その割合が,上下顎ともに3割と低い値を示した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9390K) -
吉位 尚, 寺延 治, 島田 桂吉, 浜田 充彦1992 年30 巻3 号 p. 634-639
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー患者は,8歳1カ月の男子で,オトガイ部を強打し,開口障害および下顎の左方への偏位が認められたが,X線的に明らかな骨折所見は認められなかった。そのため積極的な開口訓練を行い,機能的顎矯正装置,三連式チンキャップなどの矯正治療の手技を用いて顎偏位の修正を試みたところ,良好な改善が得られた。その概要を報告するとともに,小児期における顎関節障害に伴う顎の偏位に対する治療,特に矯正治療の果す役割について若干の考察を加えた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9048K) -
久芳 陽一, 塚本 末廣, 副島 嘉男, 本川 渉, 谷口 邦久1992 年30 巻3 号 p. 640-647
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー著者らは8歳女児で上顎右側中切歯の萌出遅延を主訴として来院した患児を経験した。口腔内X線写真により上顎前歯部の乳中切歯歯根の周囲に数片の不透過像を認めたので摘出術を施行した。処置は局所麻酔下で,上顎右側乳中切歯の抜歯を行い,同時に歯肉を剥離して歯槽骨の一部を削除しながら小硬固物を摘出した。これらの硬固物は一塊として摘出できず,大小不同の歯牙様硬固物4個からなっており,病理組織学的に歯牙腫と診断した。
歯牙腫は上顎右側乳中切歯歯根部に近接しており,しかも抜去された乳歯歯根には歯牙様硬組織の異常突起と歯根形成不全が存在し,歯牙腫との関連が疑われた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (10787K) -
茂呂 直展, 村上 照男, 安部 喜八郎, 近藤 嘉人1992 年30 巻3 号 p. 648-655
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーHallermann-streiff症候群と診断された9歳6カ月の男子を歯科的見地から,形態的,機能的に精査した結果,次のような所見を得た。
1)乳歯の矮小と晩期残存,多数の永久歯の先天性欠如。
2)咬合の不安定と開咬。
3)下顎の後下方への回転と下顎骨体部の短小。
4)両側の下顎頭の欠如と関節隆起の形成不全。
5)限界運動時の経路と収束の安定性の欠如。
6)タッピング運動時の収束とリズムの安定性の欠如,及び振幅,持続時間の不均衡とSilent Periodの不明瞭性。
7)咀嚼時は規則性,同期性のある筋活動を示し正常に近かった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (8716K) -
1992 年30 巻3 号 p. 657-692
発行日: 1992/06/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (20758K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|