巻号一覧
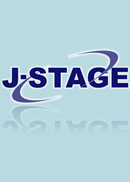
19 巻 (1981)
- 3 号 p. 431-
- 2 号 p. 247-
- 1 号 p. 1-
19 巻, 1 号
選択された号の論文の20件中1~20を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
岩瀬 泉1981 年19 巻1 号 p. 1-21
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー下顎4切歯が萌出完了した時期,整って配列する群(正常群)と,叢生を伴って配列する群(叢生群)で,歯冠の形態,乳歯列期の歯列形態,および成長による歯列弓変化がどの様に違うのかを比較検討し,さらにそれらが両群の配列状態の差とどの様にかかわり合うかを考察した.資料は男子14個体,女子15個体の連続歯列石膏模型を用いた.
その結果,歯冠の形態では,永久切歯の形態に差が認められ,叢生群では近遠心径に比べその唇舌径が小さい事が知られた.乳歯列期の歯列形態では,空隙の有無に差があり,とくに下顎前歯部ではその差が特徴的で正常群では隣接歯間に空隙があるにもかかわらず,叢生群では前歯は叢生状態にある事が知られた.さらに上下顎前方部長径,下顎前方部の広さに差が認められ,叢生群の方が長径は短く,広さは狭い事が知られた.歯列弓の成長変化では,幅径の変化に差は認められず,長径とくに前方部長径の変化に差が認められた.すなわち,上顎では正常群の変化が叢生群に比べ大きく,下顎では叢生群の減少傾向が強い事が知られたが,下顎での変化は中切歯萌出位置に関連すると解釈された.さらに両群の配列状態に差を生じさせるものを因子分析法によって考察したところ,叢生群では,下顎切歯の唇舌径は切歯の萌出位置と関係することにより,また乳歯列期の下顎前方部長径おおよび前方部の広さはその状態自体が重要な意味を持ち,正常群では乳前歯部の空隙量が重要な意味を持つ事が示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3884K) -
瀬尾 令士, 吉田 穣, 本川 渉, 平田 茂則, 新村 健三, 浜崎 三恵子, 谷口 邦久, 北村 勝也1981 年19 巻1 号 p. 22-37
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー本論文は軟化象牙質を特異的, 化学的に溶解すると言われているG K - 1 0 1 液を,(I) 切削された窩洞に, (II) 更に露髄して, (III) 根端に穿孔し露髄した根部歯髄に注入して,このGK-101液の歯髄に対する影響を病理組織学的に調べようとした論文である.本研究には幼雑犬23頭を用いた.この研究の結果,GK-101液は歯髄に与える直接の悪影響は少なく,しかも回復が早いことが判明した.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (16325K) -
-とくに重症齲蝕罹患児の治療後における血清免疫グロブリンの変動について-井上 雄温1981 年19 巻1 号 p. 38-50
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー乳歯重症齲蝕症を血清免疫学的に検索する目的で3歳5カ月から6歳11カ月までの小児で,歯髄感染歯あるいは根尖部に病変を有するが小児科的疾患のない乳歯重症齲蝕罹患児34名を対象に,歯科疾患の治療前と治療後の血清蛋白および血清免疫グロブリンの変動について検討し,さらに無齲蝕健康小児とも比較し次の結果を得た。
血清総蛋白量は治療前に比較し治療後に増減がみられず,Albuminは治療前に比較し治療後に有意の増加を示し,Globulinは治療前に比較し治療後にα2,γで有意の減少を示し, α1は増減はみられず, β は減少がみられたが有意の差は示さなかった
IgGは治療前に比較し治療後に有意の減少を示したが,治療後も無齲蝕健康小児群に比較し有意の高値を示したことから,乳歯重症齲蝕症および齲蝕経験との関連性が推察される。IgAおよびIgDは治療前に比較し治療後に増減を示さず,治療後も無齲蝕健康小児群に比較して有意の高値を示したことは,齲蝕経験との関連性も推察される。IgMは治療前に比較し治療後に増減を示さず,治療後も無齲蝕健康小児群に比較しやや高値を示したが有意の差はなかった。IgEは治療前に比較し治療後に減少を示したが有意の差はなく,治療前高値を示した3例中2例に治療後減少がみられたが,治療前も無齲蝕健康小児群に比較し有意の高値を示さなかったことから,今後さらに検索を深めることが必要である。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2339K) -
松原 清1981 年19 巻1 号 p. 51-70
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー上下顎第二乳臼歯咬合面における副溝の状態を形態学的にとらえる目的で,日本人小児(2歳6カ月-3歳6カ月)より採得した超硬石膏模型のうち,Dahlbergの上顎大臼歯咬頭表示法の4型に該当する上顎第二乳臼歯男女計152歯,またGregory-Hellmanの分類によるY5型に該当する下顎第二乳臼歯男女計146歯を用い,副溝の出現様式と頻度ならびに主溝への落ち込みについて性別を加え検討したところ次のような結果を得た。
上顎第二乳臼歯においては,paracone域で5種,metacone域で4種,protocone域で6種,hypocone域で3種の副溝を認め,その出現様式は基本型,分離型,接合型および2 種の副溝の結び合いがあった。また副溝が落ち込む主溝はI溝, II溝, III溝, IV溝, IV1溝,Fc,Faのいずれかであった。
下顎第二乳臼歯においては,protoconid域では4種,metaconid域で8種,hypoconid域で4種,entoconid域で5種,hypoconulid域で3種の副溝を認め,その出現様式は基本型, 類型, 接合型および2 種の副溝の結び合いがあった。また副溝が落ち込む主溝はI溝, II溝, III溝, IV溝, V溝, Fc1-Fc2のいずれかであった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3874K) -
小椋 正, 柴崎 貞二, 前田 隆秀, 蕪木 彰, 松本 好政, 深田 英朗1981 年19 巻1 号 p. 71-81
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーHistiocytosisXは,1953年,Lichtensteinにより,Eosinophilic granuloma ofbone,Hand-Schuller-Christian病,Letterer-Siwe病の3疾患を総称して,そのように呼ぶことを提唱して以来,この3つは同系統の疾患であると考える説が現在もっとも支持されている。これらの疾患についての報告は,本邦でも,皮フ科,小児科,内科等の領域から多数の報告がみられるが,歯科領域においても,歯牙の動揺,脱落及び歯肉の腫脹などを主訴として来院した症例の報告も少なくない。
今回,我々は,Letterer-Siwe病と診断された13歳2カ月の男児と,Hand-Schuller-Christian病と診断され,長期間経過観察した11歳6カ月の女児,2症例についての歯科的所見がいくつか得られた。
1)Letterer-Siwe病の上顎骨は極度に吸収していたが,下顎骨は上顎骨と比較して軽度であった。
2)Letterer-Siwe病もHand-Schuller-Christian病も,歯牙の動揺,脱落,歯肉炎などが著明に認められた。
3)Hand-Sehuller-Christian病の4歳9カ月時と,11歳6カ月時を比較すると,上下顎骨共に歯槽骨,及び骨体の吸収が進行していた。
4)4歳9カ月の頭蓋及び肋骨にあった骨の吸収,又は破壊像は11歳6カ月時には消失していた。
5)Letterer-Siwe,Hand-Schuller-Christian病共に,口腔内の異常は他の全身的異常と逆行し,口腔内の症状が先行して生ずるように思われた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (19902K) -
柴崎 貞二, 塩野 幸一, 吉元 辰二, 杉本 友夫, 小椋 正1981 年19 巻1 号 p. 82-94
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー乳歯列下顎前突の形態と機能との関連性を追求し,咀嚼筋の機能分析値を診断の一助とすべく,本研究を行なった。
被検児は,Hellmanの咬合発育段階IIAの幼児14名であり,SNAが80.0゜ 以上の症例を選択した。対照として,いわゆる正常咬合を有する同様な発育段階の幼児14名を用いた。
筋電図は,左右両側の側頭筋前部(TA)側頭筋後部(TP),および咬筋浅部(M)から記録した。これを測定して,最大振幅電位,_??_値および_??_値, さらに全体の百分率であるTA%,TP%,M%を算出した。これらのEMGの分析値を対照群と比較するとともに,セファロ分析値との相関性を検討した結果,以下の結論を得た。
1.下顎前突児群において,下顎の前後的位置を示すSNB,SNPの値は_??_値およびTP%と負の,TA%と正の相関がみられた。一方正常咬合児群においては,下顎前突児群のそれらとは全く逆の関係がみられた。
2.SNPと_??_値あるいはTP%との間における下顎前突児群と正常咬合児群の回帰直線の交点におけるSNPは77-8゜ であり,下顎前突症のSNPが,この値よりも大きな値をとれば,それだけ予後不良と考えられる。
.Mは下顎の前後的位置決定に働くのではなく,上下顎関係の適正な位置で最も強く働くと考えられる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2489K) -
-緊張性頸反射を応用した乳歯列咬合関係の検討-田村 康夫, 山口 和史, 吉田 定宏, 渡部 茂1981 年19 巻1 号 p. 95-105
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー18名の小児について,後屈時における緊張性頸反射時の咀嚼筋筋電図,模型分析,セファロ分析を行い,乳歯列期の咬合について検討した結果,次のような結論を得た。
1) 1 8 名中9 名について左右咀嚼筋の活動電位に差がみとめられ( G r o u p II) , 残り9 名については差がみとめられなかった(Group I)。筋群では側頭筋に筋緊張充進が出現しやすい傾向にあった。
2)活動電位の非均衡と,模型分析におけるover bite,over jet,乳犬歯関係,咬耗状態,歯列弓長径の相対的割合に高い相関がみられ,活動電位に非均衡のみられたGroup II,の咬合は深く,上下顎歯列弓長径の差も大きかった。
3)セファロ分析ではConvexity,A-Bplane,A-B differenceの上下顎歯槽の前後的差がみられ,また下顎骨におけるGn-Cd間,Cd-Go間の長さにおいても差がみられた。つまりGroup IIの下顎骨はGroup Iのそれよりも小さかった。
4)以上のことより,乳歯列期の望ましい咬合関係は,over biteは0.87±0.76mm,over jetは1.73±0.48mm,乳犬歯被蓋は1/2以下で,乳犬歯咬合は左右対称的であり,咬耗についても生理的範囲でみられる咬合が機能的にみて望ましい咬合関係であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6354K) -
広瀬 永康, 野原 義弘, 桑原 誠一, 馬場 弘, 朝倉 恒夫, 長岡 知之, 後藤 俊文1981 年19 巻1 号 p. 106-114
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー今回本学小児歯科に齲蝕治療を主訴として来院した10歳5カ月の男児にX線写真診査を行った結果,多数の過剰歯,永久歯の萌出遅延,鎖骨の一部欠如を認めたので本症を疑い,その他の必要な検査を行ってCleidocranial dysostosisと診断し,次のような所見を得た。
1)口腔内所見乳歯の晩期残存,永久歯の萌出遅延,狭く高い口蓋,前歯部での反対咬合を認めた。
2)X線所見両側鎖骨の一部欠如,頸椎の癒合不全,頭蓋縫合の開大,頭蓋冠の肥厚,筋突起の形態異常,下顎角の鈍化,過剰歯を認めた。
3)頭部X線規格写真および分析下顎骨体の前方へのRotationによると思われる前歯部反対咬合を認めた。
4)咀嚼筋(側頭筋,咬筋)機能診査所見一部の全身疾患のように筋機能に影響をおよぼしているような所見は認められなかったが,乳歯の多数歯喪失,永久歯の萌出遅延によると考えられる咀嚼筋のCo-ordinationpatternの乱れが観察され,それを改善するための小児義歯は効果が認められた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (17225K) -
前田 光宣, 堀口 浩, 棚瀬 精三1981 年19 巻1 号 p. 115-121
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー筆者らは上顎右側中切歯の脱落,同側々切歯の陥入による審美障害を主訴とし,受傷約40時間経過後,岐阜歯科大学病院小児歯科を受診した8歳7カ月の男児に再植,固定処置を施し,約1年3カ月経過観察を行ない,臨床的にみて一応の成功を収めた症例を経験したので報告する。
患児はプールで遊泳中,コンクリート縁に中切歯,側切歯を強打し,それぞれ脱落,陥入した。脱落歯は付着軟組織を除去後,抗生物質溶液中に20分間浸漬した後,Calvital®による根充を施し,これを通法により洗浄された歯槽窩に挿入し,整復した側切歯と共に固定した。
再植後,臨床的にもX線的にも予後良好であったが,術後約9カ月時,根尖および根尖周囲に透過像が認められるようになった。しかし,臨床的には骨植堅固であり,経過観察することに決定した。
顎骨の発育途上にある小児患者では,いずれは脱落の運命にあるとは言え,再植されなければ将来口腔内に様々な障害が考えられ,再植後数年間でも自分の歯牙として保持され機能を発揮することができれば,患者が抱く歯牙の喪失に対する心理的投影にも好影響が期待でき,目的の一部は達せられたと言えよう。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (13130K) -
高野 博子, 吉田 昊哲, 鈴木 千枝子, 町田 幸雄1981 年19 巻1 号 p. 122-127
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー乳歯人工歯排列の基準設定に関する研究の一環として今回乳歯側方歯すなわち,乳犬歯,第1乳臼歯および第2乳臼歯の唇・頬面の傾斜角度を測定した。
資料は,歯科口腔診査の結果正常咬合を有すると診断された3歳児の石膏模型109例である。
計測に先立ち,両側第2乳臼歯近心頬側咬頭頂および左側乳中切歯切端の3点を含む平面を咬合平面とし,咬合平面と模型基底面が平行となる規格模型を作製した。規格化された上下顎模型を歯列前方部より同一条件下で規格写真撮影を行った。次いで引伸し,焼付した印画紙上で唇・頬面外郭線の中央の1点を含む接線と咬合平面に平行な線,すなわち模型基底面が接する模型台前縁の線を記入し,これらが交わってできる角度を乳歯側方歯の唇・頬面の傾斜角度として計測した。
その結果,上顎における傾斜角度の平均値は70度前後でほぼ平行に近いことが判明した。これに対し下顎における傾斜角度の平均値は,乳犬歯で約70度で最も大きく,第1乳臼歯約55度,第2乳臼歯約49度と後方になるに従い移行的に傾斜角度が減少していく傾向が見られた。また傾斜角度には同顎同名歯牙間で有意の正の相関がみられ,左右対称性が強いことも示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3050K) -
荻田 修二, 山田 知博, 後藤 邦之, 村田 格一, 黒須 一夫1981 年19 巻1 号 p. 128-135
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー上下顎乳臼歯部の抜去乳歯,D:98歯,E:103歯,D:67歯,E:73歯,合計341歯を用いて咬合面の齲蝕初発部位およびその進行方向について検討を行なった。その結果;
1)上顎第1・2乳臼歯および下顎策1乳臼歯の咬合面における齲蝕初発部位は遠心小窩付近であった。下顎第2乳臼歯では近心小窩および舌側溝小窩付近であった。
2)齲蝕の進行は近遠心的に走向する溝より頬舌的に走向する溝の方が速く拡大していた。
3)齲蝕の進行方向は次の通りであった。
(1)上顎第1乳臼歯:遠心小窩付近に初発した齲蝕は遠心溝の頬側部,舌側部,中央溝の遠心部,遠心咬合縁溝と拡大し,同じ頃近心溝の頬側先端部にも齲蝕が発生していたが,比較的限局していた。
(2)上顎第2乳臼歯:遠心小窩付近に初発した齲蝕は遠心舌側溝の舌側部,頬側部の順に進み,同じ頃中央小窩,近心咬合縁溝小窩にも齲蝕が発生し,頬側溝,中央溝,近心咬合縁溝に沿って拡大していた。
(3)下顎第1乳臼歯:遠心小窩付近に初発した齲蝕は舌側溝,遠心咬合縁溝,頬側溝に沿って進み,近心小窩付近では限局していた。
(4) 下顎第2 乳臼歯: 近心小窩, 舌側溝小窩に初発した齲蝕は近心咬合縁溝, 舌側溝,遠心頬側溝,中央溝などに沿って咬合面全体に拡大していた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1583K) -
-在園期間が乳歯齲蝕罹患に及ぼす影響-小林 雅子, 真柳 秀昭, 神山 紀久男1981 年19 巻1 号 p. 136-144
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー仙台市北地区内保育園に通園していて,昭和52年3月,および53年3月にすでに卒園した小児228名(男児128名,女児100名)について,保育園の在園期間が乳歯の齲蝕罹患にどのような影響を与えるかを知ることを目的として,保育園在園年数によって,4群(5年連続在園群・4年連続在園群・3年連続在園群・2年連続在園群)に分け,齲蝕罹患状態を比較した。
その結果, 罹患者率では, 4 群間にあまり差がないのに対し, d e f 歯率では, 5 年連続在園群と他群との間に,どの時点においても,5年群の値が低く,常に7-10%の差が見られた。また,5年連続在園群と1年しか入園時期が違わない4年連続群は,歯率・歯面率で,5年群に近い値をとらず,3年・2年群と同じ高率の値を示した。一方,5年連続群に見られるdef歯率の減少は,上顎前歯部で特に著明であった。また,def歯面率においては,上顎臼歯部は上顎前歯部にやや似た傾向を示した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1650K) -
富沢 美恵子, 山崎 博史, 野田 忠, 小柴 宏明1981 年19 巻1 号 p. 145-149
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー歯の齲蝕などの口腔疾患を原発病巣として全身性疾患がひき起こされるということは,よく知られている。しかしながら,口腔疾患と全身性疾患の関係を証明することは困難であり,多くの報告では,口腔病巣の除去によって全身性疾患が改善されることにより因果関係を推測している。
今回,著者らは乳歯齲蝕によってひきおこされたと考えられる全身性紅斑の一例を経験したので報告する。
患児は,全身性紅斑に罹患した7歳10カ月の女児で,国立小児病院小児内科より歯性病巣感染の精査のため,同歯科を紹介された。既往歴から,全身の紅斑の出現した2回とも,直前より下顎右第1第2乳臼歯の歯痛と歯肉の腫脹を伴っていた。全身の管理を行ないながら,局所麻酔下にC3-C4の乳歯10本を抜歯したところ,紅斑は消失し,以後1年10カ月を経た現在まで再発もみられていない。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4135K) -
谷口 学, 泉谷 明, 落合 伸行, 大嶋 隆, 祖父江 鎮雄, 西村 英明1981 年19 巻1 号 p. 150-158
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーフッ化ジアンミン銀は,臨床実験および動物実験の結果より,齲蝕予防や齲蝕進行抑制効果を示すことが明らかにされている。しかし,この薬剤には,齲蝕部や未成熟永久歯を黒く着色させる欠点があり,より広い臨床応用を困難にさせている。
疫学的研究および動物実験の結果,モリブデンにも,抗齲蝕効果があると考えられている。したがって,我々は,フッ素とモリブデンを含有する新しい抗齲蝕剤(NH4) 2MoO2F4を開発した。今回, ラット実験齲蝕系をもちいて, (NH4) 2MoO2F4の抗齲蝕作用を, 市販のフッ化ジアンミン銀や酸性フッ素リン酸溶液(APF)と比較して,その効果を検討した。
動物には,齲蝕誘発性飼料2000を与え,Streptococcus mutans MT7038Rを感染させた。感染開始より4週間目に,上記フッ素剤と対照群として蒸留水を,ラットの下顎臼歯部に塗布した。塗布は,実験期間中1週間に1回計8回行った。実験動物はすべて感染後84日目に屠殺し,プラークスコアおよび齲蝕スコアを算出した。実験の結果,体重の増加においては感染群の間に統計学的に有意な差は認められなかった。(NH4) 2MoO2F4においては,フッ化ジアンミン銀と同様の齲蝕進行抑制効果が認められた。さらに,(NH4) 2MoO2F4は,フッ化ジアンミン銀のように,歯牙を黒く着色させる事がなかった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1652K) -
宮井 真理, 中野 博光, 足利 正光, 高橋 喜一, 下岡 正八1981 年19 巻1 号 p. 159-164
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー乳歯過剰歯の発現頻度は,永久歯過剰歯のそれより,非常に少ない。われわれは,永久歯列においても珍らしいといわれる犬歯形をとった両側性の乳歯過剰歯を,3歳5カ月の男児にみいだした。
過剰歯所見は,上顎両側の乳側切歯と第一乳臼歯の間に,乳犬歯が2本つつ,ともに歯列上に萌出している。X線所見では,各々の歯は独立し,歯根はほぼ完成し,正常乳犬歯の解剖学的形態を示している。その部位の後継永久歯の有無は不明である。
症例は,藤田の乳歯の過剰歯の判定規準にそしてさらに,歯冠の色沢,歯根の完成度,歯髄腔の大きさなどを参考にして,真性の乳歯過剰歯と判定した。
どちらの乳犬歯を過剰歯するかについてわれわれは,石膏模型分析の結果,前方の乳犬歯のみの歯冠巾径が-1SDより小さく,他の乳歯は全て(後方の乳犬歯も含めて)正常範囲内に入っていることより,前方の乳犬歯を過剰歯とした。
現在まだ,過剰歯の萌出機序はあきらかではないが,発生学的な隔世遺伝説と,歯胚の機械的分離説の2つがある。本症例では,形態及び大きさがともに正常形に近く,また犬歯部にあらわれたということより,歯牙原基の分裂説のほうをとりたい抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7492K) -
第1 報: 1 歳6 カ月児の口腔内状態と食習慣について井上 美津子, 臼田 祐子, 鳴島 和子, 向井 美恵, 鈴木 康生, 佐々 竜二1981 年19 巻1 号 p. 165-177
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー1歳6カ月児歯科健診において,保健指導をより効果的なものにするため,1歳6カ月児の口腔内状態と食習慣を中心とした生活習慣について調査を行ない,それらの関連について検討した。
対象は保健所を訪れた1歳6カ月児531名である。乳歯の萌出状態では第2乳臼歯以外のすべての乳歯が萌出している者が最も多く,1人平均萌出歯数は15.1歯であった。齲蝕罹患者率は15.1%,1人平均齲歯数は0.47歯で,上顎前歯部のみに齲蝕のある者が多かった。
カリオスタットによる齲蝕活動性は比較的活性の低い者が多く,齲蝕罹患と高度に相関を示した。歯垢の付着状態は萌出状態により差がみられたが,齲蝕罹患,齲蝕活動性とは関連が認められなかった。
歯みがき習慣に関しては,習慣化はまだ充分なされていなかったが,歯みがきの実行状況と歯垢付着状態との間には関連がみられた。
哺乳習慣の継続は46.7%にみられ,哺乳ビンの就寝時使用者が大半を占めていた。哺乳習慣の継続者は齲蝕罹患傾向が高かった。
間食摂取の規律性,回数,内容はともに齲蝕罹患,齲蝕活動性と関連がみられ,特に甘味食品を規律性なく摂取している者は高い齲館罹患傾向を示した。飲料摂取の規律性,回数と齲蝕罹患には明らかな関連はみられなかったが,甘味飲料の摂取頻度の多い者には齲蝕罹患が高かった。就寝前飲食習慣では飲料摂取者が多く,そのうち70%近くが哺乳習慣の継続者であった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3026K) -
第1報来院患者およびその治療内容について本間 まゆみ, 岡部 旭, 山下 登, 山下 篤子, 井上 美津子, 鈴木 康生, 佐々 竜二1981 年19 巻1 号 p. 178-187
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー小児患者の動態を把握するため,開院まもない本学小児歯科外来を訪ずれた患者の年齢主訴,治療内容などについて調査検討した。
対象は,昭和52年7月から昭和54年6月までの2年間に来院した患者で,総来院患者数1710名,(男児890名,女児820名)で,その内,心身に何らかの障害をもったもの,209名である。
来院患者の平均年齢は,4歳8カ月で,3歳児,4歳児,5歳児が圧倒的に多く,総来院患者数のほぼ半数近くを占めていた。これは,従来のこの種の報告結果と類似していた。
来院の主訴に関しては,齲蝕治療を希望するものが,著明に多くみられ,これは,小児の齲蝕が未だ蔓延している一担をのぞかせていた。しかし,齲蝕予防を主訴として来院した患者も少からずみられたことは,保護者の口腔衛生管理の意識が高まってきたことも感じられた。
また治療内容については,本学小児歯科外来診療システムにのった患者589名を対象に行い, 修復内容では, 既製乳歯金属冠, アマルガム充填が多く, とくに, II A 期およびII C期の小児に集中していた。歯髄処置内容では,断髄が圧倒的に多くみられ,中でもFC法の頻度が高かった抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (11223K) -
第1報抜去乳臼歯のX線写真による検討大西 雄三, 秋山 育也, 天野 秀昭, 鍋島 耕二, 長坂 信夫1981 年19 巻1 号 p. 188-193
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー乳臼歯隣接面の齲蝕診断に,咬翼法X線写真を用いることで,視診や触診よりも検出率が高いことはよく知られている。しかし,実際の齲蝕侵襲程度を正確に描写し得ないのではないかという疑問がある。そこで,とりあえず抜去乳臼歯を用いて視診による判定結果と,規格撮影したX線像との関係について,検討を行うとともに,いわゆる初期齲蝕群のものについては,未脱灰標本を作製し,X線像と実際の齲蝕侵襲像との関係について検討を行った。その結果,いわゆる初期齲蝕群については,視診による判定と,X線写真による判定は一致しないことが多く,診断の困難性がうかがわれた。また,X線写真でみられる透過像より,実際の齲蝕侵襲程度がまさっている傾向がみられた。一方,齲蝕が象牙質におよんでいる場合のX線写真では,比較的鮮明にその透過像を判定することができ,診断は容易であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5533K) -
峰松 小百合, 坂井 右子, 陳 璧真, 大西 雄三, 三浦 一生, 長坂 信夫1981 年19 巻1 号 p. 194-201
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーOdontodysplasiaは,McCa11ら(1947)により初めて記載された疾患で非対称性,局所性にあらわれ,エナメル質,象牙質の著しい形成不全と石灰化不全を主な特徴とする。X線像で特有な幻影状を呈することから,Rushton(1965)は,Ghost teethとも呼び,原因不明の特異な形成異常である。本症は稀な疾患で,約50例程度が記載されているにすぎず,本邦での報告はほとんどみない。今回,我々は,ABCにOdontodysplasiaを認める1歳11カ月の男児の症例に遭遇した。全身的に発育栄養状態に異常は認められず,手根骨の化骨状態も正常であった。_??_の萌出をみるが,BCは歯冠の一部しか萌出しておらず,ABC部歯肉にび慢性の発赤・腫脹・排膿を認めた。また,レントゲン写真より,ABCとその後継永久歯胚にOdontodysplasia特有のX線幻影像を認めた。病理組織所見では,エナメル質は薄く波状の凹凸を呈し,小柱の構造・配列は不規則であった。象牙質も薄く厚さも不規則で,そのほとんどが球間象牙質で占められ,冠部象牙質には多くのcleftが観察され,その一部は歯髄腔にまで達するものもあった。象牙細管の走向も不規則で,肥厚したpredentin内にはodontoblastや血管が陥入しているのが認められた。Cにおいては,歯髄は正常像を呈していたがodontoblastの配列はすうそであった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7970K) -
1981 年19 巻1 号 p. 203-241
発行日: 1981/04/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (8935K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|