巻号一覧
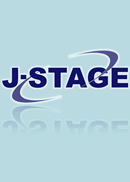
25 巻 (1987)
- 4 号 p. 773-
- 3 号 p. 501-
- 2 号 p. 273-
- 1 号 p. 1-
25 巻, 4 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
とくに既製乳歯金属冠とディスタルシューについての比較杉江 豊文, 山本 弘敏, 夏野 伸一, 加我 正行, 及川 清1987 年25 巻4 号 p. 773-778
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー小児歯科臨床で広く用いられている既製乳歯金属冠およびディスタルシューの組成金属であるNi,Co,Crの各イオンについて,その毒性を細胞培養法によって検討した.種々の濃度に調整した金属イオンを含んだ培養液中のヒト歯肉由来線維芽細胞の増殖および形態の変化を観察することにより次のようなことが明らかにされた。
1)Ni,Co,Crの各イオンは,その濃度を増すにつれ,ヒト歯肉由来の線維芽細胞の増殖を抑制し,細胞の形熊に影響を与えてやがて細胞死が生じる。
2)Ni,Co,Crの各イオンが線維芽細胞に障害を与える臨界濃度は,Niイオンについては12.5μg/mlと25.0μg/mlの間の値であり,Coイオンについては6.25μg/mlの前後の値, Cr イオンについては0.1μg/ml と0.5 μg/ml の間の値であると推定できた。従って各金属イオンの毒性の強さはCr>Co>Ni となる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (9867K) -
馬場 弘1987 年25 巻4 号 p. 779-801
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー本研究は小児における神経一筋の成長発育を検討する目的で,咀嚼筋反射の一つである咬筋 stretch reflex とそれに続くsilent period について観察した。さらに筋収縮力の変化に伴いSPがどのような影響を受けるかについても検討した。
被検者は咬合および顎機能に特に異常を認めなかった小児10名(CN群:平均6歳2カ月)と,同じく成人10名(AN群:平均21.1歳)および強く咬みしめると痛みを感じるなどの異和感を訴えた低咬合力成人5名(AS群:平均27.5歳)の計25名を用いた.下顎タップは, 1 ) 下顎安静時, 2 ) クレンチング時( 1 0 % , 5 0 % および最大クレンチング,ただし小児は10%を除く)および,3)バイティング(咬合力計咬合)時(5kg,10kg および最大咬合時)の条件下で一定の強さで行い,左右咬筋より双極表面電極で筋活動を導出した。
その結果,(1)La は3群とも安静時が長く,CN群とAN,AS群を比較した場合CN群の方が短い潜時を示す傾向が認められた。(2)クレンチング時,バイティング時とも筋活動量が増加するとSPDは有意に短縮した。この傾向はCN群とAN群で特に著しく,AS群では明瞭な短縮は認められなかった。(3)SPDにおける群間の比較では,CN群およびA S 群とA N 群でいずれの検査項目ともA N 群の方が短いS P D を示し, またC N群とAS群との比較では最大咬合時においてCN群の方が短いSPDを示していた。
以上の結果より,咀嚼筋の成長発育もSPDに影響を及ぼすことが強く示唆され,またSPDは筋活動量と強く関係することが明らかとなった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (11294K) -
蒲生 健司1987 年25 巻4 号 p. 802-821
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー本研究は学童期にみられる個々の不正咬合が増齢的にどの様な経過をとるのか側方歯萌出順序が咬合形成にどの様に関与しているのかなどについて検討することを目的として行ったものである。
調査資料は昭和55年度岐阜県各務原市立鵜沼第一小学校に入学した1年生の男子88名,女子72名,計160名であり6年生に進級した昭和60年度まで定期的に継続調査が可能であった男子6 4 名, 女子4 8 名, 計1 1 2 名である。調査はB j o r k らの方法に従い, 1) 歯牙年齢の経年別発現頻度および各永久歯の萌出率,2)各不正咬合の発現数と頻度並びに経年的推移,3)側方歯の萌出順序と各不正咬合発現との関連性を知る上で,側方歯の萌出順序を調査した。その結果,
1)増齢的に増加傾向にあった不正咬合は上顎前突,第1大臼歯遠心位咬合,過蓋咬合,Inversion,鋏状咬合および下顎臼歯部叢生であった。
2)増齢的に減少傾向が認められたものは下顎前突,開咬,大臼歯部交叉咬合および下顎切歯部叢生であった。
3)各不正咬合と側方歯萌出順序との関係では,上顎前突は4→3→5と3・4→5と4→3→5の萌出型が多く認められ,Inversionでは4→5→3と3→4→5の萌出型が多く,また過蓋咬合は4→3・5と4→3→5の萌出型に多く認められた。以上より上顎前突,Inversion,過蓋咬合の発現に側方歯の萌出順序が係りをもつことが示唆され,また今回の縦断的研究により,横断的研究だけでは得られなかった不正咬合の推移が伺えた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (6611K) -
第一報 各成熟段階の牛歯エナメル質粉末を用いて大土 努, 斉藤 隆裕, 楽木 正実, 祖父江 鎮雄1987 年25 巻4 号 p. 822-829
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーエナメル質の萌出後成熟を検討する前段階として,エナメル質の成熟過程全般を知る目的で牛歯エナメル質粉末を用い,代表的無機質成分(Ca・P・CO3・F)の変化とそれに伴う結晶性の変化および有機質成分の間の相互関係を検討した。その結果,
1)歯冠形成期には,エナメル質のCaおよびPの含有量は大きく増加し,それと対応してCO3,Fおよび有機質成分の含有量は大きく減少した。またハイドロキシアパタイトの結晶成長がa軸方向に認められたが,この段階ですでにc軸方向の結晶成長はほぼ完了していると思われた。
2)歯根形成期の初期でも,CaおよびPの含有量は増加するが,その増加量は歯冠形成期に比べて小さく, CO3 とF の含有量の減少本認められたくなった。しかしハイドロキシアパタイトのa軸方向の結晶成長と有機質成分の含有量の減少は,歯冠形成期と同様の割合で認められた。
3)歯根形成期の後半になると,各成分の含有量の変化やハイドロキシアパタイトの結晶成長はほとんど認められなくなった。
4)しかし萌出期には,もう一度CaとPの含有量の増加およびCO3と有機質成分の含有量の減少が,歯冠形成期に比べて程度は小さいが認められた。以上の研究結果は,萌出後成熟について多くの示唆を与えるものである。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (4218K) -
第3報 小児の人格的要因と歯科受診時の行動との相関性原田 桂子, 西野 瑞穂, 有田 憲司, 岡本 多恵, 中川 弘, 佐々木 保行, 鈴木 敏昭1987 年25 巻4 号 p. 830-839
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーわれわれは,歯科診療室における小児の行動を理解し,歯科診療時の協力性を向上させるために,幼小児の心理的しくみについての科学的実証的研究を続けている。
今回は,「幼児社会性発達検査」,「マッチングテスト」,「歯科診療意識調査」による小児の人格的要因と歯科診療時の行動観察による治療協力度との相関性について調査分析した。
対象児は3歳から7歳までの小児,男児22名,女児10名の計32名である。幼児社会性発達検査は対象児の母親に記入させ,マッチングテスト,歯科診療意識調査は小児一検査者という2者関係で行い,待合室から治療後退室までの小児の行動観察は鳴門教育大学修士課程の大学院生が行った。小児の歯科治療は卒後3年から6年の小児歯科医2名が行った。結果は次のとおりであった。
1 ) 幼児社会性発達検査では, 「運動・安全」および「集団行動」の2 領域で, 治療適応群が不適応群に比べ,社会性発達度が高い傾向を示した。
2 ) マッチングテストでは, 熟慮型, 衝動型という認知スタイルと, 治療適応性との間に関連性は認められなかった。
3 ) 歯科診療意識調査では, 受診動機, 健康意識については治療適応・不適応群に差はなかったが,適応群では治療に対する忍耐性が高かった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1766K) -
側貌頭部X線規格写真による作用効果を中心に荻原 和彦, 呉 英寛, 溝呂木 英二, 三枝松 広高1987 年25 巻4 号 p. 840-850
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー発育の旺盛な小児期にある患者に対し, アングルI I 級の症例に, バイオネーターを使用し,臨床的にほぼ満足すべき結果が得られた5症例について,治療前後の側貌写真,石膏模型,側貌頭部X線規格写真の資料を用いて,作用効果など臨床的検討を行った。結果は次のようであった。
1)初診時年齢5歳7カ月から11歳8カ月の男児3名,女児2名で,主訴は齲蝕歯の治療ならびに前歯部の歯列不正であった。装着時年齢は8歳6カ月から10歳10カ月で,ANB-diff.は5.43゜~8.56゜であった。
2)バイオネーターの作用によりoverjet,overbiteの著明な変化が生じ,前歯の被蓋関係の改善がなされた。同様に,第一大臼歯の咬合関係もアングルII級からI級へと改善された。
3)処置前,処置後の側貌頭部X線規格写真での比較では(特に第1症例・第2症例),それぞれの分析値が,1.S.D.内に納まる傾向にあり,歯系・骨格系にバランスよく作用していた。
前歯の被蓋の改善は,著明な上顎切歯の舌側傾斜によるものであった。
また下顎の位置変化についてみると,下方への移動が2例,前下方への移動が3例であった。
以上のことからバイオネーターは発育の旺盛な小児期に歯系・骨格系に優れた効果があるものと考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (15254K) -
小口 春久, 佐々木 洋, 小野 博志1987 年25 巻4 号 p. 851-862
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーEllis-van Creveld症候群は,軟骨形成不全,外胚葉形成不全,多指症と更には極めて高率に発症する先天性心疾患の4徴候を示す疾患である。
症例は初診時年齢が2歳9カ月の一卵性双生児の姉妹例である。姉は5カ月時において,呼吸困難を訴えて肺炎と診断され,また4歳2カ月時において,先天性心疾患に対する根治手術が施行された。第1子は不完全型心内膜床欠損症,第2子は単心房兼左大静脈遺残を合併していた。
口腔内所見としては,姉にのみ上顎の右側乳中切歯に先天性欠如が認められた。姉妹とも上下顎の口腔前庭溝が浅く,小帯は妹の上唇小帯を除いて全て消失していた。歯肉は厚く肥厚しており,小舌,狭高口蓋および2分口蓋垂が認められた。
頭部X線規格写真より,頭蓋底角度ならびに下顎角の著しい開大が認められ,各複合体では,特に下顎枝の劣成長が明らかであった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (18671K) -
西野 瑞穂, 有田 憲司, 田村 由紀1987 年25 巻4 号 p. 863-869
発行日: 1987/12/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーいわゆる「母親教室」を効果的に機能させるために, 保護者の歯科に関する理解度と,家庭での口腔衛生状況の実態,歯科受診の動機,どこまでの治療および口腔保健管理を希望しているかなどについて調査した。調査対象は,昭和52年10月から昭和61年12月までの10年間に,徳島大学歯学部附属病院小児歯科を受診した小児の保護者831名,および昭和58年3月から昭和61年12月までの3年9カ月間に行われた同科母親教室に参加した保護者531名である。
得られた結果は次のとおりである。
1 ) 過去1 0 年間の間で, 来院動機となった主訴については, 齲蝕が減少し, これにかわって歯列不正が増加傾向を示し,大学病院を選択した理由については,小児歯科専門だから受診したというものが増加していた。また治療内容については,齲蝕歯のみの治療を希望するものが減少し,予防管理まで定期的診査を希望するものが増加していた。
2)齲蝕の認識時期は,10年間ほぼ変化がなかった。
3)小児の歯磨状況について,低年齢児の0歳から2歳群,3歳から5歳群で歯を磨くものが増加した。
4)フッ素塗布経験のあるものが増加し,とくに0歳から2歳群,3歳から5歳群において,有意に増加していた。
5)何らかの齲蝕予防法について,知識のある保護者は有意に増加したが,いまだ知識を持たないと答えたものが約35%存在した。
6)保護者で習慣的に歯を磨くものは76.2%にとどまっていた。
7)小児の口膣衛生に関する講習,勉強を経験している保講者は約30%で,講習の場所は,多いものから順に保健所,大学病院,歯科医院であり,勉強は本,テレビによるものであった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (7348K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|