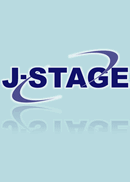-
第1報カナダ白人男子の縦断資料における正常咬合者と上顎前突不正咬合者の比較-側貌頭部X線規格写真における角度計測-
前田 隆秀, 岡本 和久, 栗原 洋一
1994 年32 巻4 号 p.
675-687
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
上顎前突咬合と正常咬合で頭蓋顎顔面の発育予測が可能か否かを知る目的で,白人男子で同一人の6,9,12,16歳時の経年資料を16歳時の口腔模型と側貌頭部X線規格写真からSNA85゜及びANB5゜を境界に,正常咬合群,上下顎前突群,上顎前突群,下顎後退群に分類,検討し以下の結果を得た.
1.SNA:6,9,12歳時で上下顎前突群,上顎前突群が正常咬合群,下顎後退群に比べ有意に大きかった.増齢変化では上顎前突群のみ有意に増加した.
2.ANB:6,9,12歳時で上顎前突群,下顎後退群が正常咬合群に比べ有意に大きかった.増齢変化では正常咬合群の6-9,9-12,6-16歳間,上顎前突群の6-9歳間が有意に減少した.
3.Convexity:6歳時より上顎前突群が正常咬合群に比べ有意に大きかった.
4.A-Bplane angele:6歳時より,上顎前突群が正常咬合群に比べ-sideに有意に大きかった.
5.SNP:6歳時より上下顎前突群が正常咬合群に比べ有意に大きかった.下顎後退群は最も小さく,また有意な増齢変化もなかった.
6.Mandibular plnae angle:6歳時より下顎後退群は正常咬合群より有意に大きかった.上顎前突群は増齢的に減少し,16歳時では下顎後退群より有意に小さかった.
7.GZN:下顎後退群は増齢的に大きくなり16歳時では正常咬合群より有意に大きく,下顎の後方位がみられた.
抄録全体を表示
-
第2報カナダ白人男子の縦断資料における正常咬合者と上顎前突不正咬合者の比較
前田 隆秀, 岡本 和久, 栗原 洋一
1994 年32 巻4 号 p.
688-702
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
第1報と同一資料を用い正常咬合群,上下顎前突群,上顎前突群,下顎後退群に分類した各群の頭蓋顎顔面の距離計測ならびに面積計測を行い,各群の頭蓋顎顔面の大きさの経年変化を検討したところ次のような結果を得た.
1.over jetにおいて,6歳時,16歳時の上顎前突群は正常咬合群より有意に大きかった.
2.over biteにおいて,6歳時で下顎後退群が正常咬合群より有意に大きかったが,増齢とともに正常咬合群と差が認められなくなった.上下顎前突群は6歳時から16歳時まで他の群より小さい傾向にあった.
3.PNS-ANSでは12歳時以降で上顎前突群で大きい傾向にあったが他の3群との間に有意な差は認められなかった.またその傾向は6歳時には全く認められなかった.
4.PNS-Aでは12,16歳時で上顎前突群が正常咬合群より5%の有意差をもって大きかった.しかし6,9歳時ではその傾向は認められなかった.
5.G-Meでは下顎後退群が他の群に比べ小さいという傾向はなく,4群間で有意差が認められなかった.
6.Ar-Gでは6歳時より下顎後退群が他の群より小さい傾向にあり正常咬合群とは9,12歳時に5%の有意差をもって小さかった.
7.上顎複合体部面積では上顎前突群が正常咬合群より大きいという傾向は全くなく,また全体面積に対する上顎複合体部の面積の占める割合も上顎前突群が大きいという傾向はなかった.
抄録全体を表示
-
第1報充填処置時の年齢群別の比較
山内 哲哉, 土屋 友幸, 横井 勝美, 渡辺 直彦, 黒須 一夫
1994 年32 巻4 号 p.
703-714
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
浸潤麻酔の有無が小児の顔面表情変化(瞼・眉・額の変化)に及ぼす影響を明らかにするために充填処置時の年齢群別の比較分析を行った.被験者は,3歳から6歳までの園児20名,6歳から10歳までの児童20名計40名である.調査方法は,浸潤麻酔下ならびに無麻酔下で乳臼歯部に窩洞形成後,成形充填を行い,その時の小児の顔面表情変化を浸潤麻酔の有無によって使用群(除痛群)40症例と不使用群(非除痛群)40症例に分類し,観察を行った.
その結果を要約すると,以下のようであった.
1.非除痛群:被験者全体では,額,瞼・眉の3部位ともに,タービン・エンジンの切削処置とバキューム・エアーの補助処置間で多くの有意差が認められ,切削処置で大きく補助処置で小さな顔面表情を表出していた.また,年齢群別の比較でも同様な結果が認められた.
2.除痛群:被験者全体では,切削処置の額と補助処置間において,年齢群では,園児・児童群とも眉のタービンとエアー間で有意差がみられたが,非除痛群に比べ処置間で有意差の認められる項目数は減少していた.
3.除痛群と非除痛群の比較:全体では,額・瞼・眉の3部位ともに,除痛群が非除痛群に比べ,低い得点を示し,顔面表情変化の抑制効果がみられた.園児と児童の比較においても,同様な傾向がみられたが,顔面表情変化の抑制効果は園児群で顕著であった.
4.浸潤麻酔と非除痛群の切削処置との比較:園児では,額・瞼・眉のほとんどの部位で,浸潤麻酔に比べ非除痛群の切削処置の顔面表情変化が高い得点を表出していた.園児では,額と眉で浸潤麻酔時の変化が,非除痛群の切削処置よりも大きくなっていた.
抄録全体を表示
-
緒方 哲朗, 中田 稔, 平沼 謙二
1994 年32 巻4 号 p.
715-721
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
小児歯科臨床の目標である「健全な永久歯列咬合」を育成するためには,齲蝕や歯列・咬合の異常を早期に発見し,これに対応しなければならない.そのためには,一般の人々とくに両親の口腔に対する関心の高さが重要となる.
今回,名古屋市と福岡市の中学生・高校生407名とその両親404名を対象に,歯列・咬合に関するアンケート調査を行った.その結果,次のことが明らかになった.
1)前歯部叢生と反対咬合に関しては,かなり正確に認識されている可能性がある.
2)半数以上の人が自分の歯列・咬合に対して無関心であった.しかし一方で,両親は自分の子供の歯列・咬合に対して健康観として強い関心を寄せていた.
3)全身の健康と関係するかという質問では,「虫歯」が最も多く,次いで「咬み合わせ」「歯並び」の順であった.
4)歯科用語の「歯槽膿漏」「矯正歯科」「歯周病」は8割以上の認知度があった.両親においては,「咬合」「反対咬合」「顎関節症」の認知度も高かった.
今後歯列・咬合に対する社会の認識を高めていくには,審美観としてだけでなく健康観としてアピールしていくことが有効であると思われる.
抄録全体を表示
-
X線入射角度による骨梁像の変化
宮本 雄一, 佐藤 直芳, 奥村 泰彦
1994 年32 巻4 号 p.
722-732
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
小児歯科臨床で撮影される咬翼法について基礎的実験を行った.歯およびフィルムに対して異なる入射X線角度で撮影された画像について,基準となる画像と比較し相関性を検討した.ヒト乾燥下顎骨大臼歯部とブタ乾燥下顎骨下顎角部骨梁を切り出し,アクリルレジンに包埋後ブロック状にカットし,X線写真撮影の試料とした.このブロックのX軸方向,Y軸方向の角度変化およびフィルム被写体間距離を変化できるシミュレータを作製し,X線写真撮影を行った.撮影された画像をコンピューターで解析し,以下の結果を得た.
1.被写体とフィルムの角度は一定で入射X線の角度が変化した場合,0゜のフィルムと比較すると95%以上の相関値を示し,同一画像と認識される角度は,ヒト乾燥下顎骨でX軸方向では-6゜-+4゜,Y軸方向では-4゜-+10゜,ブタ乾燥下顎骨でX軸方向では-10゜-+14゜,Y軸方向では-30゜-+30゜であった.
2.フィルムと入射X線を固定し被写体だけを角度変化した場合,0゜ のフィルムと比較すると95%以上の相関値を示し,同一画像と認識される角度は,ヒト乾燥下顎骨でX軸方向では-4゜-+6゜,Y軸方向では-3゜-+3゜,ブタ乾燥下顎骨でX軸方向では-12゜-+15゜,Y軸方向では-15゜-+15゜ であった.
3.被写体とフィルム問の距離変化について観察を行った場合,0-30mmまで95%以上の相関値を示した.4.咬翼法のX線入射角度の変化ならびに被写体からのフィルム間距離変化は,通常の咬翼法撮影において,規格的な撮影を行わなくても画像上で骨梁評価を行って問題はないと考えられた.
抄録全体を表示
-
及川 透, 白川 哲夫, 野崎 真也, 佐藤 直司, 小口 春久
1994 年32 巻4 号 p.
733-742
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
有病者,特に呼吸機能に障害のある患者の歯科治療には,呼吸状態を監視するための適切なモニターを使用することが望ましい.本研究では,有病者の意識下歯科治療時の呼吸モニターとしてカプノメーターの使用を試み,呼気終末炭酸ガス濃度(ETCO2),呼吸数,同時に動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定し,以下の結果を得た.
1.健康成人を対象とした測定では,SpO2とETCO2はともに分時呼吸量と相関しており,呼吸量減少時にSpO2は低下し,逆にETCO2は上昇した.
2.健常児において,歯科治療中のETCO2の変動係数は安静時に比べ大きくなったが,上昇傾向は認められず,SpO2は治療中も安定していた.
3.脳性麻痺患者では,浸潤麻酔時および歯科治療中にSpO2の低下傾向を認め,呼吸機能の予備力が低下していることが示唆されたが,ETCO2に明らかな上昇傾向は認められなかった.
4.Rett症侯群の小児および脳性麻痺患者の歯科治療中に惹起した無呼吸の際に,カプノメーターの呼吸曲線に早く変化が現れ,続いてETCO2,SpO2に変化が認められた.
5.有病者,特に呼吸機能の障害が疑われる患者の意識下での歯科治療の際には,カプノメーターによる呼吸のモニタリングは重要であり,パルスオキシメーターとの併用が望ましいと考えられた.
抄録全体を表示
-
進士 久明, 小嶺 隆一, 高見 由佳, 久保山 博子, 和田 浩利, 本川 渉
1994 年32 巻4 号 p.
743-750
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
乳歯列上にみられる生理的歯間空隙は永久歯列に交換する際有効に作用すると考えられているが,その存在によって,永久歯の正常排列が約束されるわけではない.歯間空隙量の多少は,そこに存在する歯の歯冠近遠心幅径に左右されるのではないかと考え,乳歯列上にみられる生理的歯間空隙の総和量によって乳歯列を6群に分け,空隙量と歯冠近遠心幅径および乳歯列周長との関係について調査を行った.
その結果,次の結論を得た.
1.歯冠近遠心幅径に,左右差は認められなかった.
2.歯冠近遠心幅径は,男児の方が女児より大きい傾向を示した.
3.歯間空隙量が増加するほど,歯冠近遠心幅径は小さくなる傾向が認められた.つまり,歯間空隙量は歯冠近遠心幅径に左右されることが示唆された.
4.下顎においては,歯間空隙量が増加する程,歯列周長も増加する傾向が認められた.
抄録全体を表示
-
香西 克之, 山木戸 隆子, 鈴木 淳司, 長坂 信夫
1994 年32 巻4 号 p.
751-755
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
歯口清掃の重要性は,近年ますます大きくなっているが歯口清掃器具の管理については,十分な指導がなされていないように思われる.今回我々は,歯口清掃器具の使用後の汚染を細菌学的に調査する目的で,本学小児歯科に来院した3-12歳までの45名の小児に対して,歯口清掃後の歯ブラシを任意に洗浄してもらい,その歯ブラシに残存している付着細菌数を測定し,以下の結果を得た.
1.洗浄後の付着細菌数は歯ブラシ1本当たり,最少で3.5×103コロニー,最多で3.7×106コロニー,平均4.8×105コロニーと非常に多くの付着細菌が検出された.
2.歯ブラシの洗浄方法によって付着細菌数は大きな差を生じたが,流水中での歯ブラシ洗浄が有意に少なかった.
3.さらに聞き取り調査も行った結果,家庭における歯口清掃器具の洗浄や管理には不十分な点が多く,これらについての指導の必要性が指摘された.
抄録全体を表示
-
一般集団における2度のアンケート調査-より-
中尾 さとみ, 森主 宜延, 奥 猛志, 豊島 正三郎, 小椋 正, 堀 準一
1994 年32 巻4 号 p.
756-768
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
鹿児島市内の中学校及び高等学校の生徒を対象に,2度にわたりアンケート調査を行い,顎関節症と生育歴との関係について検討した結果,以下の結論を得た.
1.2回の調査とも,偏咀嚼,かみしめ,頬杖,外傷の既往,家族内の顎関節症発症の有無の項目で,"あり"と答えた者が顎関節症群で有意に多く認められた.
2.かみごたえのある食品の摂取に関して,かみごたえがあると考え摂取していた食品の平均咀嚼筋活動量の評価では,顎関節症群と正常群の間に差はみられなかった.
3.回答として記載された食品の評価については,食品の種類が多く,また調理法の記載がない食品もみられたため,我々の評価法では,評価できない食品が半数以上みられた.
4.顎関節症と生育歴との関係について,これまでの報告と比較検討した結果,偏咀嚼,歯ぎしり,かみしめ,外傷の既往については,顎関節症の病因として示唆されるものと判断できた.
抄録全体を表示
-
伊出 和郎, 山口 武人, 内山 正, 平田 順一, 赤坂 守人
1994 年32 巻4 号 p.
769-777
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
1978年より1992年までに,日本大学歯科病院小児歯科を訪れた患者のうち,歯科健康管理アンケートに回答した,1946名を対象として,調査集計し,以下の結論を得た.
1.各習癖の男女合わせた発現頻度は,吸指癖,咬爪癖,口呼吸,咬唇癖の順に多かった.
2.近年の傾向を知るため,全対象者を中間で分け,1978-1985年を前半群,1986~1992年を後半群とした習癖の発現頻度を比較すると,吸指癖,口呼吸,咬爪癖は後半群の方が大きい傾向を示した.
3.習癖の期間は,吸指癖では3年以内の期間が多く,咬爪癖では1-2年の期間のものが最も多かった.
4.習癖の開始,終了時間は,吸指癖の開始時期は0歳代が最も多く,6歳以降に開始するものはいなかった.また終了時期は3歳が最も多かった.咬爪癖については開始時期は,3歳が最も多く,終了時期は4-6歳をピークに減少していた.
5.吸指癖と養育・生活習慣との関連については,母親の就業の有無との関連はほとんどなかった.祖父母の同居の有無との関連は,同居のあるものの方が吸指癖を経験しているものが少なかった.普段主に子供の世話をしている人が父親と祖父母の場合との関連では,祖父母の場合のほうが少ない傾向を示した.親の職業との関連は,自営業,公務員を職業とするものに比べ,会社員,教育研究機関を職業とするものの方が,吸指癖を経験しているものが多かった.単独子と中間子の吸指癖を持つ割合が,長子や末子に比べて高かった.
抄録全体を表示
-
柳田 憲一, 野中 和明, 渡辺 善久, 中田 稔
1994 年32 巻4 号 p.
778-784
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
ラット顎顔面頭蓋の大きさと形の成長過程における遺伝要因の関与の度合とその経時的変化の様子を解明する試みとして,顎顔面頭蓋形態を有限要素法を用いて大きさと形の2つのパラメーターで定量化した.即ち大きさの異なる2系統の親ラット間,そのF1児ラット間,親ラットとF1児ラット間で,それぞれに顎顔面頭蓋の大きさと形の類似性を10日齢より80日齢まで比較したところ,F1児ラット同志間,F1児ラットと雄親ラット間あるいはF1児ラットと雌親ラット間そして親ラット間の3グループに大別することができ,前者ほど類似性が高かった.このように遺伝的つながりのより強いラット同志の顎顔面頭蓋の大きさと形の類似性が,より高い傾向にあることが明らかとなった.このことは,顎顔面頭蓋の大きさと形の成長変化に遺伝要因が関与しており,また顎顔面頭蓋の大きさと形の定量法として,有限要素法が有用であることを示唆するものであった.
抄録全体を表示
-
細矢 由美子, 冨永 礼子, 後藤 譲治
1994 年32 巻4 号 p.
785-800
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
牛並びにヒト乳歯象牙質に対し,各種歯面処理材,プライマー,ボンディング材,ライナーを用いた場合のレジンの接着性について観察した.
使用した材料別に,1群(K-etchant,Clearfil Photo Bond),2群(CA agent,SAPrimer,Clearfil Photo Bond,Protect Liner),3群(10-3水溶液,Superbond Primer,Superbond D Liner),4群(Gluma2000-1,Gluma2000-2),5群(Scotchbond MultiPurpose Etchant, Scotchbond Multi Purpose Primer, Scotch bond Multi PurposeAdhesive)及び6群(AII-Etch,Primer A and B,Dentin/Enamel Bonding Resin)を設けた.コンポジットレジンは,4群のPekafill,5群のZ-100,6-A群のBisfil-M以外は,Clearfil Photo Anteriorを用いた.
1)歯面処理効果は,All-Etch=Gluma2000-1≧Scotchbond Multi Purpose Etchant=10-3水溶液>K-etchant>CA agentの順で高かったが,歯牙の個体差による影響が大きかった.
2)非サーマルサイクリング群並びにサーマルサイクリング群ともに,3群(10-3水溶液,Superbond Primer,Superbond D Liner,Clearfil Photo Anterior)と6-B群(All-Etch,Primer A and B,Dentin/Enamel Bonding Resin,Clearfil Photo Anterior)の接着強さは25MPa以上であり,両群で使用した材料は,乳歯象牙質に最も適していた.
抄録全体を表示
-
宮沢 裕夫, Yu-Faang Lin, 枝 早苗, 岩崎 浩, 上田 和樹, 中村 浩志, 外村 誠
1994 年32 巻4 号 p.
801-810
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
小児の歯周疾患の多くは生活に起因するといわれ,齲蝕と同様に日常生活との関連が深く,様々な要因が相互に絡み合いながら発症・進行し増悪するといわれている.本研究では単一の要因として捕らえにくいとされる小児期の歯肉炎と生活習慣を特徴付ける諸要因との関連を検討するための予備的研究として多変量解析の手法を応用し分析した.
1.食習慣と歯肉炎との関連では,小学生,中学生とも「歯科定期検診」(保護者,子ども)といった健康観の良否が罹患程度に寄与していた.また,食習慣では「甘味食品を好む」「間食を就寝時」「不規則に摂取」することの良否が歯肉炎罹患との関連が認められた.
2.各要因項目間の類似度関係をパターン化すると,罹患程度が高度なものは小学生では「間食が不規則」「就寝前の間食摂取」「固い食品を好まない」要因に加え,「刷掃の不良」が影響して増悪する傾向が認められた.
3.軽度なものでは「齲蝕」は存在するものの「刷掃回数」「間食の規則性」「甘味摂取」が良好なもののパターン化がみられた.
4.中学生では歯肉炎重度と食習慣との関連は認められず,中等度では「咀嚼時間」「甘味摂取不良」「歯科定期検診」といった健康感を示す項目の関与が認められた.
5.中学生の軽度な罹患では「甘味摂取」「間食の規則性」が良好であり,さらに保護者,児童・生徒ともに健康感を示す項目が良好な傾向が認められた.
抄録全体を表示
-
南 貴洋, 松本 道代, 田村 康治, 青野 亘, 藤原 卓, 大嶋 隆, 祖父江 鎭雄
1994 年32 巻4 号 p.
811-816
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
ウーロン茶特有のポリフェノールを含むウーロン茶抽出物(OTE)のStreptococcussobrinus 6715株感染SPFラットにおける齲蝕抑制効果を,その投与量および投与方法の差により比較検討した.粉末状ウーロン茶抽出物を飼料中に添加し,同時に飲料水中にも添加することにより,齲蝕の発生は濃度依存的に有意に抑制された.また,ウーロン茶抽出物を飼料中あるいは飲料水中に単独で添加した場合にも,有意の齲蝕抑制効果が認められた.さらに,市販のウーロン茶を飲料水のかわりにラットに投与した実験においても,齲蝕の発生は抑制された.これらの結果はウーロン茶抽出物がその投与形態に関係なく,齲蝕抑制効果を有することを示している.
抄録全体を表示
-
松下 繁, 堀川 容子, 田村 康夫, 吉田 定宏
1994 年32 巻4 号 p.
817-825
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
本研究は,吸啜時の口腔周囲筋活動を計測する際活動電位計測のための基礎的データを得る目的で,時間的経過により筋活動量,活動頻度,活動割合がどのように変化するかについて検討した.被検児は側頭筋,咬筋,口輪筋,舌骨上筋群の4筋から吸啜運動時の筋活動を最後まで記録できた母乳哺育児20名および哺乳瓶哺育児20名の計40名(平均週齢14.2週)を対象とした.
その結果,1)筋活動量は各筋とも個人差,時間経過による活動の低下,また4筋に有意な差が認められ,同様に4筋総筋活動量も時間経過による低下が認められた.母乳群と人工乳群との比較では咬筋,口輪筋,舌骨上筋群および総筋活動量で母乳群が大きい活動を示していた.2)総筋活動量に占める各筋の割合は,時間の経過でも変化がみられず,母乳群では側頭筋が約9.5%,咬筋が12%,口輪筋28%,舌骨上筋群50.5%を示し,人工乳群は側頭筋が11%,咬筋が11.5%を占め,口輪筋が27.5%,舌骨上筋群が49%を占めていた.3)活動電位出現率は母乳群,人工乳群とも口輪筋と舌骨上筋群がほとんど100%近い出現を示し最も高く,次いで咬筋で,側頭筋の出現が最も低かった.
以上の結果より,吸啜運動時には母乳群,人工乳群とも舌骨上筋群と口輪筋が主に活動し,活動量は時間の経過と共に低下するが活動割合は変化しないことが明らかとなった.
抄録全体を表示
-
箕輪 恵子, 村田 典子, 宮内 充子, 坂田 貴彦, 中島 一郎, 赤坂 守人
1994 年32 巻4 号 p.
826-831
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
食品の硬さが小児の咀嚼筋活動に及ぼす影響を検討した.被験者は顎口腔系の機能に異常を認めない,いわゆる個性正常咬合を有するHellmanの歯牙年齢IIA10名,IIIA10名,対照として永久歯列期成人10名とした.咀嚼試料は硬さのみ3段階に変化させたガムを用いた.筋電図は表面電極記録によりそれぞれの咀嚼運動時の左右側頭筋,咬筋から記録し,咀嚼筋活動量と咀嚼周期を求め,次の結果を得た.
咀嚼周期は,IIIA,成人において硬さ変化に対して影響されなかったが,IIAでのみ硬いほど延長した.咀嚼筋活動量はそれぞれの被験筋においてIIA,IIIA,成人の順で試料問の差が多く認められた.
成長する過程において,硬い食品を咀嚼するために咀嚼時間を延長させるのではなく筋収縮力を強めることによって,より機能的に円滑に咀嚼していくと考えられた.
抄録全体を表示
-
松本 敏秀, 井口 享, 落合 聡, 中田 稔
1994 年32 巻4 号 p.
832-837
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
小児歯科臨床での断髄処置において,乳歯および幼若永久歯とも可及的に歯根部歯髄を生活状態で保存するため,水酸化カルシウムを用いた生活断髄法が従来より広く用いられてきている.しかしながら,実際の小児歯科臨床の場においては水酸化カルシウムを使用する度に,滅菌した器具を用いての滅菌水との混和が必要であるなど,治療能率の点で問題がある.そこで我々は,水酸化カルシウムを基に,臨床で即時使用できる一剤型水酸化カルシウム製剤を試作した.今回は,それを用いた生活断髄後の庇蓋硬組織形成の有無を,動物実験により組織学的に確認した.
その結果,断髄処置1ヵ月後に象牙前質と細管構造を有する象牙質から成る庇蓋硬組織の形成を認めた.また,残存する歯髄組織においては炎症などの異常所見は見られなかった.以上により本剤を生活断髄剤として臨床に用いることが可能であることが示唆された.
抄録全体を表示
-
田中 美絵子, 尾崎 正雄, 馬場 篤子, 高田 圭介, 新村 健三, 本川 渉
1994 年32 巻4 号 p.
838-846
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
著者らは第3大臼歯の歯胚形成がどのような時期に行われ,また第1大臼歯の歯根形成状態と第3大臼歯の歯胚形成がどのような関係にあるのかを確認する目的で1978年から1990年の間に福岡歯科大学小児歯科で治療およびスクリーニングを目的として来院した2-15歳までの小児(847人)のパノラマX線写真1101枚(内男子533枚,女子568枚)を用いて調査を行った.収集されたパノラマX線写真は,Moorreesらの分類に基づき,下顎左右第1大臼歯と上下左右第3大臼歯を14段階に分類した.その結果下記のような興味ある知見を得た.
1.第1および第3大臼歯の歯胚の形成状態に男女差および左右差はなかった.
2.第3大臼歯の歯胚の形成は早いもので上顎で6歳時,下顎で5歳時より認められた.
3.第3大臼歯の歯胚発現時期は下顎第1大臼歯の歯根尖完成の時期とほぼ一致し,左右とも約76%の発現頻度に達することが判明した.
以上のように第3大臼歯の歯胚を確認する場合,下顎第1大臼歯の歯根の形成状態を指標とすることが有効であり,必要とされるX線被爆量の軽減に役立つものと考えられた.
抄録全体を表示
-
牧 憲司, 葛立 宏, 児玉 昭資, 古谷 充朗, 今村 隆子, 野沢 典央, 木村 光孝
1994 年32 巻4 号 p.
847-852
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
著者らは歯冠部硬組織の萌出後の成熟について検索するために九州歯科大学付属病院小児歯科外来を受診した6歳児,10歳児,13歳児の計42名を対象に下顎第一大臼歯の口内撮影法を行い,得られたデンタルフィルムから,photodensitometry法により歯冠部硬組織の石灰化度をAl当量に換算し次の結果を得た.
1)歯冠部硬組織の石灰化度の平均値は男児で6歳4.02±0.38mmAl,10歳4.92±0.51mmAl,13歳5.73±0.76mmAl,女児は6歳4.18±0.41mmAl,10歳5.08±0.49mmAl,13歳5.67±0.57mmAlであった.
2)男女間の歯冠部硬組織の石灰化度についてt検定を行ったところいずれの年齢でも有意差は認められなかった.年齢間についてt検定を行ったところ,6・10歳,6・13歳では後者が前者に対し有意に高値(p<0.01)であった.10・13歳間においても年齢の高い後者が前者に対し有意に高健(p<0.05)であった.
3)年齢と歯冠部硬組織の石灰化度の相関係数r=0.712であった.回帰直線式は,年齢をX軸にとり,歯冠部硬組織の石灰化度をY軸にとるとY=0.26X+2.55であった.
4)測定の再現性について基礎的検討事項として6歳インド人小児頭蓋骨を使用しi)焦点,被写体ならびにフィルムの位置づけによる歯冠部硬組織の石灰化度のばらつきii)エックス線照射線量の変化による歯冠部硬組織のばらつきについて変動係数を求めたところ,i)に関して3.04%,ii)に関しては3.25%と測定値のばらつきの少ないことが確認できた.
抄録全体を表示
-
奥 猛志
1994 年32 巻4 号 p.
853-871
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
顎関節症患者33名と対照者12名の左右顎関節部のFCRおよびMRI検査を行い,これらの画像検査結果から得られた定量評価により,顎関節内の状態と臨床症状との関連について検討し,以下の結論を得た.
1.開口障害の発症頻度は,IIIaグループおよびIIIbグループで有意に高かった.MRI所見により,IIIa群およびIIIb群の下顎頭ならびに関節円板の軌跡の領域が,正常群と比較して制限されていることが示された.
2.顎関節疼痛の発症頻度は,IIIa群およびIIIb群の顎関節で有意に高かった.MRI所見により,IIIa群およびIIIb群の顎関節では開口に伴う関節円板の物理的圧縮が確認された.
3.顎関節雑音の発症頻度は,II群の顎関節で最も高かった.
4.IIIaグループはIIIbグループに比較して,開口障害発症から来院までの期間が有意に長かった.FCR所見により,IIIa群はIIIb群に比較して下顎窩に対する下顎頭の上下的位置が有意に下方であることが示された.一方,MRI所見により,内外方転位の頻度が有意に低く,関節円板の前方への移動量の増大が確認された.
5.下顎窩に対する下顎頭の前後的位置は,全ての顎関節症群は正常群と比較して有意に後方に位置した.上下的位置は,II群およびIIIb群が正常群と比較して有意に上方に位置した.
抄録全体を表示
-
屋敷 徹, 朝隈 恭子, 赤坂 守人, 大森 郁朗, 吉田 定宏, 西野 瑞穂, 中田 稔, 小椋 正
1994 年32 巻4 号 p.
872-888
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
小児の顎口腔系の発達を筋電図学的にとらえるために日本大学,鶴見大学,朝日大学,徳島大学,九州大学および鹿児島大学の6大学歯学部小児歯科講座で分担して採取した筋電図を分析した.同時に採得した模型の計測を行い筋電図との関連を調査した.
ガム咀嚼と量大咬みしめの積分値から,咬合様式が成長に伴いTA主働からM主働へと変化していたことがわかった.また,ガム咀嚼の周波数分析からガム咀嚼時のパワースペクトラムは成長に伴い低域にシフトする傾向が認められた.最大咬みしめの周波数分析からは成長との関連はみいだされなかった.
また,疲労との関連では最大咬みしめの積分値から,TAは疲労しにくく,Mが疲労しやすいことがわかった.最大咬みしめの周波数分析から,MPFはTA,Mとも最大咬みしめの終了時にかけて低下していることがわかった.また,十分休憩をとって最大咬みしめを繰り返すと,2回目以降の開始時では疲労から回復しているようにみえるが,疲労しやすい状態になっていたことがわかった.
筋電図分析値といくつかの模型計測値の項目間で相関がみられたものがあったが,筋電図と模型の関係を説明するまでには至らなかった.
抄録全体を表示
-
野中 和明, 佐々木 康成, 松本 敏秀, 柳田 憲一, 渡辺 善久, 中田 稔
1994 年32 巻4 号 p.
889-896
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
Rieger's Syndromeは,虹彩前葉実質の形成不全,虹彩根部癒着および後部胎生環など眼科的症状を3大主徴としている.他にもさまざまな奇形を合併する常染色体優性遺伝疾患である.中胚葉組織の発育異常に起因しているため,歯や顎顔面の異常を生じることも多く,歯科学的にも注目すべき先天性疾患の1つである.今回我々が遭遇した初診時6歳の男児では,以下のような興味深い所見が認められた.
1)瞳孔異常と心房中隔欠損症
2)低身長傾向と骨年齢の遅れ
3)〓の矮小歯化傾向および〓の歯胚の石灰化遅延
4)上顎骨の劣成長および前歯部反対咬合.
抄録全体を表示
-
甲原 玄秋, 丹沢 秀樹, 佐藤 研一
1994 年32 巻4 号 p.
897-902
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
特発性血小板減少性紫斑病は急性型,慢性型,再帰型に分けられる.急性型は2歳から6歳の小児に多く性差はないとされる.本疾患は時に高度の歯肉出血を来す例がある.その際,適切で確実な局所止血が重要となる.
今回口腔内に多量の出血を伴った5歳女児が千葉県こども病院に受診した.初診時,上下顎の歯肉溝より持続する出血が認められた.臨床検査所見は白血球数7.7×103/μl,赤血球数392×104/μl,血小板数0.7×104/μl,プロトロンビン時間12.2sec,活性化部分トロンボプラスチン時間27.8sec,血小板結合免疫グロブリン265.6μg/cell,骨髄巨核球数94/μlであった.
臨床経過と検査所見に基づき特発性血小板減少性紫斑病の診断が得られた.
直ちに圧迫止血のためレジン製のスプリントを作成し,上下顎の歯列弓に装着した.それにより止血が得られた.同時に1日0.7g/kgの大量ガンマグロブリンを静脈内投与し,3日間継続した.4日後には血小板数は0.7×104/μlから5.1×104/μlへと上昇した.その時スプリントを除去したが,歯肉出血は認めなかった.1ヵ月後血小板数は26.5×104/μlに達し,その後減少しなかった.それゆえ急性特発性血小板減少性紫斑病の確定診断が得られた.
本症例では口腔内所見とガンマグロブリン療法が有効であり,血小板の補充を必要としなかった.
抄録全体を表示
-
福田 理, Raymond L. Braham, 黒須 一夫
1994 年32 巻4 号 p.
903-910
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
1990年5月から1992年8月までにカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)の日帰り全身麻酔手術施設であるSurgery Centerにおいて歯科治療を実施した小児歯科患者156名の特徴とその治療内容について調査検討し以下の結果を得た.
1.患者の種類及び年齢は健常群が156名中97名(62.2%)平均年齢3.3±1.2歳,全身疾患群22名(14.1%)平均年齢5.0±2.4歳,心身障害群37名(23.7%)平均年齢10.4±7.5歳であった.
2.全身疾患群の内訳は心疾患7名,血友病6名,他の血液疾患2名,白血病4名,その他3名であった.
3.一人平均処置歯数は健常群10.3歯,全身疾患群9.5歯,心身障害群7.6歯であった.
4.心身障害群では全顎の歯肉切除術(11例),縁下歯石除去(8例)を主目的に全身麻酔下歯科治療を実施した症例もみられたが,他の2群にはこのような症例は認められなかった.
5.麻酔時間は2時間以内の症例が77.5%で,その平均時間は健常群,全身疾患群がともに2.1時間,心身障害群が1.7時間であった.
6.術中1例に呼気ガス異常が認められたが,全症例の術後回復に問題はなく全身麻酔下歯科治療当日帰宅した.
抄録全体を表示
-
牛山 郁子, 長谷川 順子, 小杉 誠司, 野田 忠
1994 年32 巻4 号 p.
911-917
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
1979年9月-1994年3月までに,新潟大学歯学部小児歯科外来を乳歯の外傷で受診した308名520歯を対象として,乳歯外傷の実態調査を行った.また,後継永久歯の萌出をみた38名65歯を対象とし,後継永久歯に与える影響について調べた.
1)受傷時年齢は2歳が76名(24.7%),1歳が62名(20.1%)と1,2歳が多く,男女比は1.75:1を示した.
2)受傷部位は上顎乳中切歯が374歯(71.9%)を占め,2歯以内の受傷が多かった.受傷原因は転倒が多く,受傷から来院までの期間は受傷の翌日が最も多かった.
3)受傷状態は脱臼が182歯(35.0%),動揺160歯(30.7%),破折145歯(27.9%)であった.処置内容は経過観察が最も多く,ついで整復固定,抜歯の順であった.
4)後継永久歯に影響が現われたのは65歯中10歯であり,後継永久歯の影響の発現率は15.4%であった.
5)受傷状態別では,完全脱臼,陥入,挺出でやや高い影響の発現率を示した.受傷時年齢との関係では,低年齢時の受傷は歯冠形成に,年齢が高い場合は歯根形成や萌出に影響を与えるようである.
6)乳歯外傷は,受傷時年齢,受傷状態にかかわらず,後継永久歯へ交換するまでの長期間にわたる経過観察が重要である.
抄録全体を表示
-
長谷川 順子, 牛山 郁子, 小杉 誠司, 野田 忠
1994 年32 巻4 号 p.
918-925
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
1979年9月より1994年3月までの14年7ヵ月間に,永久歯に外傷を受けて新潟大学歯学部附属病院小児歯科を受診した,202症例,370歯についての外傷の実態調査を行い,以下のような結果を得た.
受傷時年齢は8歳が最も多く,次いで7歳,9歳の順であった.男女別では男児132例,女児70例で男児が女児のほぼ2倍であった.受傷部位は上顎中切歯が最も多く70%を占めた.1症例あたりの受傷歯数は8割以上が2歯以下であった.受傷原因は転倒が最も多く,以下,衝突,転落,交通事故,殴打の順であった.受傷状態は動揺が最も多く,次いで露髄を伴わない歯冠破折,露髄を伴う歯冠破折,完全脱臼の順であった.年齢別に受傷状態を見てみると,8歳以上では7歳以下に比べ破折の割合が増加していた.
また,32症例49歯には外傷の予後調査も行った.その結果,初診時の受傷状態が軽度に思える症例でも予後不良となる場合もあり,外傷歯の予後観察は少なくとも永久歯列完成時期まで数年以上の長期にわたって定期的に行う必要があると思われた.
抄録全体を表示
-
野中 和明, 井口 亨, 立川 義博, 佐々木 康成, 松本 敏秀, 渡辺 善久, 中田 稔
1994 年32 巻4 号 p.
926-933
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
Oculo-dento-digital syndromeは,小眼球症などの眼科異常,鼻翼の低形成による特異的な顔貌および合指症などの四肢異常を主症状とする先天性疾患のひとつである.胎生期における中胚葉性組織の発生異常を原因とする遺伝性疾患であり,その遺伝形式は常染色体優性遺伝が有力である.またその他にも歯や顎骨の形成異常を伴っているので,歯科学的にも注目すべき先天性疾患のひとつである.今回我々が遭遇した初診時年齢4歳の女児では,以下のような興味深い所見が認められた.
1)粗で短い頭髪
2)小眼球症と視力障害および癒合眼瞼分離形成術後
3)左右の手の第4 第5指の合指症分離形成術後
4)下顎骨関節頭および筋突起の形態異常
5)歯の形成不全と矮小化および歯髄腔狭窄化
6)歯槽骨部の異常な垂直的吸収7)〓の先天性欠如.
抄録全体を表示
-
森本 彰子, 太田 和子, 高江洲 旭, 赤嶺 秀紀, 古沢 ゆかり, 木村 光孝
1994 年32 巻4 号 p.
934-941
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
母子に出現した部分的無歯症の2症例を経験し次のような結論を得た.症例1として男子7歳11ヵ月は〓の部位に,症例2としてはその子供の母親32歳11ヵ月には〓の先天性歯牙欠損症が見られた.症例1の萌出歯牙においては,歯冠近遠心径は上顎乳犬歯,下顎乳犬歯,下顎第2乳臼歯が異常値を示したほかは,正常範囲内であった.症例1においては,上顎骨が劣成長のために今後下顎骨の成長に伴ってますます下顎が前方位になることが考えられ,チンキャップの装着および〓の正中離開の改善を開始し,予後の観察を行う予定である.また,症例2の場合歯槽堤は萎縮し発育不良であった.現在部分床義歯を装着している.
今回の症例では,祖母,母親その長男と3代にわたり系統的に,男女間の性差はなく部分的無歯症が起こっている.この結果より,成因は常染色体優性遺伝と考えられる.さらに,症例1では,父親にも先天性欠損が認められた.このことから,父親からの遺伝の関与が症状促進の一因子になったことが考えられる.しかし父親の方は系統的に調べることが不可能であり,確認できなかった.また症例2の場合は出産時,健康状態が不良であったことが確認されており,その症状をさらに促進する因子となったと思われた.
抄録全体を表示
-
岩崎 浩, 大須賀 直人, Yu-Faang Lin, 宮沢 裕夫, 安東 基善
1994 年32 巻4 号 p.
942-947
発行日: 1994/09/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル
フリー
萌出性腐骨(eruption sequestrum)は時として不快感あるいは咀嚼時の疼痛を伴うが,一般的には無症状に経過し,多くの場合自然脱落すると言われている.また,容易に摘出することが可能であるとされている.今回,萌出途上の下顎第1大臼歯にみられた萌出性腐骨の2症例を経験したので臨床的ならびに病理組織学的に検索した.
症例1は違和感を主訴としたものであり,症例2は無症状に経過し,リコール時に偶然発見されたもので,両症例とも硬組織小片が歯肉と線維性に結合していた.病理組織学的には,骨細胞は消失しており骨小腔は空虚で通常の腐骨の所見と同様であった.また腐骨表面には細菌叢の付着もみられ,硬組織小片周囲歯肉には軽度な炎症所見が観察され,小片周囲の清掃性の問題から周囲歯肉や顎骨部への炎症の波及も危惧された.
抄録全体を表示