巻号一覧
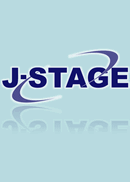
35 巻 (1997)
- 5 号 p. 773-
- 4 号 p. 563-
- 3 号 p. 393-
- 2 号 p. 195-
- 1 号 p. 1-
35 巻, 1 号
選択された号の論文の20件中1~20を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
木村 光孝1997 年35 巻1 号 p. 1-10
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー日本小児歯科学会は,全国29大学の小児歯科学教室における医事紛争の実態を把握することによって,日本小児歯科学会と各大学とによる小児歯科領域における歯科医時紛争の態勢作りの基礎資料を収集し,将来の医事紛争の防止を目的として,その実態を調査した.
実態調査は,平成元年1月から平成7年12月までの7年間を対象とし全国29大学の小児歯科臨床で起こった歯科医事紛争について,59件数が認められ,その実態を調査した.
全体調査では医事紛争のあった大学が29校中17校,なかった大学が12校であった.17校中,59件がその件数であった.
内容別の件数をみてみると医療不満が33件,医療過誤が12件,偶発事故が10件,不可抗力事故が4件で,医療不満を示す件が最も多かった.
個別調査では,平成6年が16件,平成7年が12件,平成5年が10件の順に多くを示した.
月別では6月が10件,11月が9件の順で,3月が最も少なく1件であった.
発生の時間帯をみてみると,圧倒的に午前中が多く38件,午後が16件,その他(不明を含めて)5件であった.
発生年齢をみてみると3歳が11件で最も多く,4歳8件,5歳8件の順であった.
性別では女子の方がやや上回っている.診療経験別では再診がほとんどである.
今後,医事紛争に対する概念として医療不満について詳細に調査する必要がある.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1400K) -
石川 雅章, 寺木 智子, 山田 恵理, 桔梗 知明, 舩山 研司1997 年35 巻1 号 p. 11-18
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー舌習癖を伴う歯槽性の開咬ないし開咬傾向と診断された混合歯列期の小児12名に,タングクリブを埋め込んだHawley型床装置(床装置群)および開咬治療用バイオネーター(バイオネーター群)を装着し,診査時および平均治療期間1年後の側貌頭部エックス線規格写真を標準値同年齢群と比較検討した.
両群とも診査時のオーバーバイト量は標準値群より有意に小さかったほか,床装置群ではプロスチオン-インフラデンターレ間距離が有意に長く,バイオネーター群ではS-N平面に対する上顎中切歯角が有意に大きかった.
装置撤去前後のオーバーバイト量は,床装置群で1.0mm-0.2mmの範囲に,バイオネーター群では1.5mm-0.2mmの範囲となった.床装置群では下顎下縁平面に対する下顎中切歯角が有意に小さくなり,上顎,中切歯歯軸は概して標準値に近づいていった.量的計測項目の変化量は,プロスチオン-インフラデンターレ間距離は有意でなくなったものの,この時期の標準値群変化量よりも多かった.バイオネーター群でも下顎中切歯舌側傾斜が観察された一方,上顎中切歯唇側傾斜は多少緩和され,A点の有意な移動とともに,付加した筋排除板の効果とも解釈できた.量的計測項目の変化量はこの時期の標準値変化量相当であった.
両群の過大であった下顎前歯の舌側傾斜を少なくするために,床装置ではタングクリブの設計を,バイオネーターでは調整法を改善することが必要と思われた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2528K) -
武田 郁子1997 年35 巻1 号 p. 20-29
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー本研究の目的は9-10歳における歯冠近遠心幅径および歯列弓の大きさや叢生ならびに顎顔面形態が歯の形成の早さとどのように関わっているか,また前歯反対被蓋者の下顎の歯の形成時期が前歯正常被蓋の者と比べて早いかどうかを調べることである.九州大学歯学部付属病院矯正科に来院した,初診時年齢が9歳0か月-10歳11か月の患者248名(男子94名,女子154名)を対象に歯列石膏模型,側方頭部エックス線規格写真,パノラマエックス線写真を用いて分析検討したところ,以下の結果を得た.
1.各歯の形成度は男子より女子,上顎より下顎の方が高い傾向にあった.特に側切歯において上下顎の差は顕著であった.
2.上顎では女子,下顎では男女とも歯列弓幅径が大きいことと歯の形成が遅いこととの間に有意な関係があった.また男子の下顎においては歯列弓長径が大きいことと歯の形成が遅いこととの間に有意な関係が認められた.
3.下顎前歯の叢生量と歯の形成度との間には明瞭な関係は見出せなかった.
4.急傾斜の下顎下縁平面,下顎後下方回転,大きな前顔面高,上顎切歯口蓋側傾斜,大きな前歯垂直被蓋などの顎顔面形態と歯の形成が早い傾向との間に有意な相関が認められた.これらの所見は女子より男子で顕著であった.
5.上下顎ともに顎骨の大きさと歯の形成度には有意な関係が認められなかった.
6.前歯水平被蓋が正か負で2群に分け,歯の形成度を比較したところ,両群の歯の形成度に有意差は認められなかった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (587K) -
-噴射切削法による形成窩洞の組織切片上の検討-後藤 譲治, 張 野, 今武 由美子, 山邊 陽出代1997 年35 巻1 号 p. 30-35
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー現在,歯科臨床において歯牙の切削には主として回転切削装置が用いられ,歯の切削時に加圧と振動,騒音と発熱さらに疼痛等を伴う.こうした不快事項が少ないとされるKinetic Energyの小児歯科領域への応用に関して,我々は一連の基礎的研究を行ってきた.今回は噴射切削装置によって形成された窩洞の詳細を知る目的で,組織切片上より窩洞形態等の検討を行った.成犬6頭の75歯に対して,噴射切削装置KCP-2001 J型を用いて5級窩洞を形成した.被験歯を脱灰後,パラフィン連続切片標本とし,ヘマトキシリン・エオジン複染色を施した.光学顕微鏡下に観察および写真撮影し,イメージスキャナーにより画像処理し,50例についてコンピューターにより窩洞の深さ,幅径等を計測した.
本研究の結果,以下の知見が得られた.
1.噴射切削装置による形成窩洞は基本的にはやや外開きのU字型であった.
2.噴射切削法により形成された窩洞の窩壁表面は比較的平滑であった.
3.噴射切削法では無注水であるにもかかわらず,窩洞周囲象牙質にはバーニング像は認められなかった.
4.噴射切削法において,点角,線角の明瞭な窩洞は形成困難であるが,他方,極めて細長い窩洞の形成が可能であるなど,噴射切削窩洞の特徴が判明した.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (287K) -
高井 経之, 小笠原 正, 野村 圭子, 奥田 寛之, 穂坂 一夫, 渡辺 達夫, 笠原 浩1997 年35 巻1 号 p. 36-40
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー小児が口腔内診査に対して適応できるようになる年齢を明らかにするために,1歳から5歳までの154名を対象に口腔内診査を行い,その時の外部行動と発達との関連を赤池情報量規準(Akaike's Information Criterion,以下AICと略す)を用いて解析した.
1.口腔内診査への適応・不適応と,発達年齢,暦年齢,日常生活動作(Activities of Daily living,以下ADLと略す)の自立度との間には強い関連性が認められた.
2.口腔内診査への適応性について最適な区分年齢は,暦年齢で2歳6か月,遠城寺式乳幼児分析的発達検査による発達年齢では2歳4.5か月から2歳10.5か月に分布していた.
3.暦年齢2歳6か月以上の小児は,口腔内診査に対してレディネスが備わっていることが明らかになった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (927K) -
-歯科医師と高校ラグビー選手との比較-松永 幸裕, 天川 三奈, 田中 光郎1997 年35 巻1 号 p. 41-46
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリースポーツ外傷に対する安全対策として,我々歯科医師が直接関与できるものに,顎顔面・口腔領域の防具が挙げられる.今回我々は,そのなかでも広く知られているマウスガードを作製する際,どのような点について注意が必要か,マウスフォームドタイプのものを用いて,使用感について比較・調査した.
高校ラグビー選手20名によって使用説明書通りに作製してもらったマウスガードと,同一人の石膏模型上で同じ材料を用いて歯科医師が作製したマウスガードについて,その適合度を計測し比較した.
側・口蓋側共に選手自らが作製したマウスガードよりも歯科医師が作製したマウスガードの頬方が有意差をもって適合が良いと思われる結果が得られた.しかしアンケート調査より作製したマウスガードに下顎の圧痕がないと,いかに歯科医師が適合良く作製したとしても,それだけでは満足感が得られず,むしろ使用感が悪くなる場合があるということが明らかになった.したがって適合状態に加えて,さらにマウスガードに対する要望事項としては,「呼吸のしやすさ」,「フィット感」,「脳震盪の予防」という順であった.また,「これから先マウスガードを使いたいと思いますか?」との問いには,「思う」とした者が17名に対して「思わない」とした者が0名,「わからない」とした者が1名であり,ほとんどの者が使う意志を示し,マウスガードの潜在的な需要を示唆していた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1440K) -
加我 正行, 橋本 正則, 辻口 鎮男, 高野 光彦, 小口 春久1997 年35 巻1 号 p. 47-52
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー光重合型コンポジットレジンの細胞毒性を調べるため,ヒト歯肉由来の線維芽細胞を用いて,細胞培養にて実験を行った.光照射時間を変えて硬化した市販のボンディング材と光重合型コンポジットレジン表面に線維芽細胞を直接播種し,1日目,3日目,6日目に倒立培養顕微鏡と光学顕微鏡にて細胞の形態変化を観察した.また,光学顕微鏡によりレジン表面上に生育した細胞の一定面積あたりの細胞数を算定して,細胞毒性を定量的に評価した.その結果,培養24時間後の観察では,ボンディング材とコンポジットレジン表面への線維芽細胞の付着は対照に比べてやや少なかったが,細胞の生育は確認された.Liner-Bond II®とAP-X®においては,光照射時間が長くなると細胞の増殖が認められたが,Z100®とMulti-PurPose®では光照射時間の影響は認められなかった.それらの表面の細胞数では,対照と同様に経時的な増加は1日目から3日目,6日目までみられなかった.しかし,硬化したボンディング材とコンポジットレジン表面で細胞が生育することから,培養細胞に対する硬化後のレジンの毒性は低いことが示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2797K) -
-定期管理受診状況の実態とその継続期間について-浜田 作光, 松原 聡, 杉村 和昭, 祝部 竜三, 内村 登1997 年35 巻1 号 p. 53-60
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー定期管理(診査)の改善点を探る目的で,神奈川歯科大学付属病院小児歯科外来に来院した患者について,定期管理の実態およびその継続状況を調査した.対象は1970年1月から1974年12月までの受診者のうち9歳以下を対象とし,そのほとんどが定期管理を受診しなくなった14年後まで調査した.
1)初診時の年齢構成は3歳をピークとして,2歳から5歳が全体の85.2%を占めた.平均年齢は4歳4か月であった.
2)定期管理の継続期間は平均3年4か月で,初診年に一度も定期管理に応じないものが241例(10.0%)認められた.
3)初診年齢別の継続期間は,0歳が5年6か月で最も長く,8歳および9歳が最も短く2年4か月であった.
4)期間別中止率は,初診時6歳以上で初年度から高いが,就学年齢前後による差はなかった.
5)地域別の来院患者構成は,当大学に近隣の地区で74.7%,遠方から25.3%が受診し,初年度定期管理来院率は,遠方で低下する傾向が認められた.
6)地域別の初診年齢による継続率は,低年齢では近隣が,年齢が高くなると遠方で高かった.地域別の初診年齢による継続率は,低年齢では近隣が,年齢が高くなると遠方で高かった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1880K) -
辻口 鎮男, 加我 正行, 堤 智紀, 小島 寛, 小口 春久1997 年35 巻1 号 p. 61-66
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー小窩裂溝填塞材として新しく開発された光硬化型グラスアイオノマーセメントを用いて,ヒト歯肉線維芽細胞に対する細胞毒性を寒天重層法にて調べた.
光硬化型グラスアイオノマーセメントの試料として,液,粉末単独のもの,および,練和したセメントを0,10,20,30,60秒間光照射したものを用いた.これらの試料をヒト歯肉線維芽細胞の上に寒天を介して間接的に置き,温度37℃,湿度100%,炭酸ガス濃度5%の条件下で24時間培養を行った.セメント材料の毒性成分が溶出することにより,培養細胞の死滅を示す発育阻止円が試料直下に発現し,この面積を計測して細胞毒性の程度を評価した.その結果,液成分は大きな細胞毒性を示したが,粉末は培養細胞の活性をまったく低下させなかった.また,光未照射の試料は大きな細胞毒性を示したが,光照射時間が長くなるにつれて細胞毒性は減少していき,30秒以上の光照射では細胞毒性をまったく示さなかった.これらのことから,本研究に用いられた光硬化型グラスアイオノマーセメントの硬化条件としては,細胞毒性の観点から30秒以上の光照射が必要であると考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2174K) -
大金 詩子, 尾上 博子, 藤居 弘通, 町田 幸雄1997 年35 巻1 号 p. 67-74
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー現在における幼若永久歯に対する歯冠修復法の応用状況を知る目的で,平成5年度に東京歯科大学千葉病院小児歯科臨床を訪れ,永久歯に歯冠修復処置を施した5歳4か月から19歳11か月までの患者758名の被処置永久歯1700歯を対象として調査した.
歯冠修復処置法は,前歯ではコンポジットレジン修復が最も多く,臼歯ではメタルインレー修復が最も多かった.
修復歯面数は,前歯,臼歯とも1歯面に対する修復が最も多かった.メタルインレー修復は2面に対し施されたものが最も多く,コンポジットレジン修復は,前歯,臼歯とも1面が最も多かった.グラスアイオノマーセメント修復および銀アマルガム修復はほとんどが1面に対するものであった.
窩洞形態は,メタルインレー修復では,上顎大臼歯はOL窩洞,下顎大臼歯はOB窩洞が最も多かった.コンポジットレジン修復では,前歯における窩洞形態はMを含む窩洞が大多数を占め,臼歯ではMあるいはBが多く,Oへの応用は皆無であった.
各歯冠修復法のそれぞれの窩洞形態は,何れもそれぞれの材料の長所短所を十分に考慮した応用状況であった.特にグラスアイオノマーセメント修復および銀アマルガム修復は,メタルインレー修復やコンポジットレジン修復に比べ低年齢児に対する応用が多かったが,これらは暫間的な修復手段として応用されたものと考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1530K) -
第2報臨床的有用性福田 理, 柳瀬 博, 小野 俊朗, 渡辺 直彦, 河合 利方, 磯貝 美佳, 佐藤 久美子, 鈴木 聡1997 年35 巻1 号 p. 75-82
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー笑気吸入鎮静法下の歯科治療時にマスク装着やガス吸入に抵抗し,歯科治療が極めて困難であった6歳から21歳の障害児21名を対象にミダゾラム0.2mg/kgを舌下投与し,笑気吸入鎮静法との併用下で歯科治療を実施し,その臨床的有用性について検討し,以下の結果を得た.
ミダゾラム舌下投与時に拒否的行動を示したものは,21名中4名(19.0%)で,投与5-10分後には鎮静効果が発現し始め,15-20分には全症例安定した鎮静度に達していた.歯科処置別有効率は,局所麻酔が65.0%と最も低く,開口・口腔診査が90.5%と最も高くなっていた.平均回復時間は116.3分で,投与直後から翌朝までの間に,臨床上問題となる不快事項の発現は,認められなかった.以上の総合評価である臨床的有用性は,76.2%に認められた.
21例中16例(76.2%)は,21秒以上舌下部にミダゾラムの貯留が可能で,20秒以下の貯留時間では5症例中2例(40.0%)に臨床的有用性が認められたのみであるのに対し,21秒以上の貯留時間では16例中14例(87.5%)に臨床的有用性が認められ,薬剤貯留時間と臨床効果の関連性が示唆された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2099K) -
-第3報心理的ストレス得点と性格特性との関連性について-簡 妙蓉, 石川 隆義, 長坂 信夫1997 年35 巻1 号 p. 83-88
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー小児歯科では,術者と母親とのコミュニケーションは重要であるが,診察室へ入室した母親は術者に何らかの心理的影響を与えていると考えられる.母親が術者に心理的ストレスをどのようにどの程度与えているかについての心理的ストレス反応尺度をアンケート形式で作成し,その有効性を認めた.そこで今回,心理的ストレス得点と広島大学歯学部小児歯科学講座に所属する歯科医師23名の性格特性がどのような関連性をもっているかについて検討を行い以下の結果を得た.
1.心理的ストレス得点における性別,歯科医師の年齢,歯科臨床経験,既婚か未婚かのすべての項目において有意差は認められなかった.
2.類型別出現頻度の検討では,D類の安定積極型が34.8%,C類の安定消極型が26.1%と情緒安定型は高率であった.続いてA類,B類,E類の順であった.
3.YG性格検査における12尺度のうち,情緒安定性を測定する4尺度(D:抑うつ性,C:回帰性,I:劣等感,N:神経質)全てと心理的ストレス得点との間で,5%レベルの危険率で有意な相関が認められた.社会適応性(O:主観性,Co:非協調性,Ag:攻撃性)や向性(G:一般的活動性,R:のんきさ,T:思考的外向性,A:支配性,S:社会的外向性)を測定する尺度においては,有意な相関が認められなかった.
以上のことより,小児歯科診療時に母親が術者に及ぼす心理的ストレスとYG性格検査による術者の性格特性との間において,情緒安定性を測定する尺度とは有意な相関は認められたが,社会適応性や向性を測定する尺度とは有意な相関は認められなかったことが示された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1372K) -
-第7報「幼児歯科診療協力性検査」の応用-原田 桂子, 有田 憲司, 西野 瑞穗1997 年35 巻1 号 p. 89-95
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー徳島大学歯学部附属病院小児歯科で臨床的有用性が確証された「幼児歯科診療協力性検査」を,開業歯科医院17か所を受診した3歳0か月から6歳10か月までの幼児82人および6歳8か月から12歳2か月までの学童88人に応用し,その有用性を検討した.
結果はつぎのとおりであった.
1.平均年齢5歳3か月の幼児の「幼児歯科診療協力性検査」による適応・不適応の判別予測と実際の診療後の適応性総合判定との一致した的中率は,74.4%であった.
2.平均年齢8歳11か月の学童における的中率は,86.4%であった.
3.本検査は,すべての開業歯科医院で容易に実施できた.
以上の結果から,「幼児歯科診療協力性検査」は開業歯科医院を受診する幼児および学童に対してきわめて有用であることが明らかであり,臨床的有用性が確証された.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1362K) -
大東 美穂, 園本 美恵, 木村 圭子, 三村 雅一, 嘉藤 幹夫, 大東 道治1997 年35 巻1 号 p. 96-110
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー歯の成長発育の実態を究明すべく,平成元年4月1日から平成6年3月31日までに大阪歯科大学附属病院小児歯科外来を訪れた2歳0か月-14歳11か月の小児のオルソパントモグラムを用いて調査した. 調査資料数は,男子5,700枚,女子5,500枚の合計11,200枚であった. そのうち実際に判定できた歯は,下顎第一小臼歯(男子右側5,158歯,左側5,164歯,女子右側4,975歯,左側4,977歯),下顎第二小臼歯(男子右側4,752歯,左側4,776歯,女子右側4,637歯,左側4,623歯),下顎第一大臼歯(男子右側5,204歯,左側5,185歯,女子右側5,027歯,左側5,024歯),下顎第二大臼歯(男子右側4,883歯,左側4,903歯,女子右側4,725歯,左側4,730歯)であった.
歯の成長発育の評価法としては,Moorreesらの分類法に準拠して分類した. すなわち,大臼歯では14段階,小臼歯では13段階に分類し,それぞれの石灰化の発育段階を0-14点までの数値におきかえて,資料の計測を行った. その結果,
1)各歯の発育段階において,女児のほうが,男児よりも歯の形成(石灰化)が早く,とくに形成中期において,その傾向の大きいことを認めた.
2)左右側の発育は,男児,女児ともに,その差異を認めなかった.
3)男女において第二小臼歯と第二大臼歯の石灰化状態は,近似していた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2990K) -
山口 理衣, 進士 久明, 河野 美佐, 久保山 博子, 石井 香, 山田 清夫, 鶴田 勝久, 久芳 陽一, 本川 渉1997 年35 巻1 号 p. 111-118
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー一般に過剰歯の好発部位は上顎正中部で,下顎前歯部には少ないといわれている.また,乳歯列に融合歯が存在すれば,その後継永久歯の先天性欠如の頻度は40-50%といわれている.今回著者らは,発生頻度の低い下顎前歯部過剰歯4症例に遭遇した.しかも,そのうち3症例において,その先行乳歯が融合歯である非常に稀と考えられる症例を報告する.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (5422K) -
船越 禧征, 千田 由紀子, 大道 士郎, 木村 圭子, 大東 道治1997 年35 巻1 号 p. 119-122
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー先天性心疾患児に抜歯を行う際の合併症として感染性心内膜炎がある.本症に罹患しやすい先天性心疾患は心室中隔欠損,動脈管開存症,ファロー四徴症および大動脈縮窄症で,後天性弁膜疾患では僧帽弁膜症,大動脈弁膜症などがある.また,ファロー四徴症や大動脈縮窄症,肺動脈閉鎖症,三尖弁閉鎖症などのように右→ 左シャントが存在する先天性心疾患では,菌血症が生じた場合,細菌が肺で除かれず,直接脳に達し脳膿瘍を合併する場合がある.今回,単心室,大動脈縮窄,僧帽弁狭窄,心房中隔欠損症を有する9歳7か月女児で抜歯を契機として脳膿瘍を併発したと考えられ,脳外科でドレナージの緊急手術,抗菌薬投与により治療し得た症例について報告した.本症例は先天性心疾患に加え,何らかの免疫機能の低下があり,抜歯を契機として口腔内の病巣から病原菌が右→ 左シャントを経由して脳内へ波及して脳膿瘍が生じたものと推測される.このことから,特にチアノーゼ性心疾患を有している患児においては口腔内病変が直接的に病巣感染をひきおこす可能性もあるので,観血的処置に際しては抗菌薬の予防投与などを行い,処置後も注意深い観察が必要である.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1600K) -
千田 由紀子, 船越 禧征, 田口 雅史, 大道 士郎, 木村 圭子, 大東 道治1997 年35 巻1 号 p. 123-127
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーStevens-Johnson症候群(以下S-J症候群)は1922年にStevensとJohnsonらが持続する発熱,多発性発疹,潰瘍性口内炎を伴う疾患として最初に報告した多型性浸出性紅斑の重症型である.今回,8歳7か月,男児のS-J症後群の1例を経験し,以下の所見が認められた.
1.口腔内所見として白濁,根の形成障害(短根歯),エナメル質減形成が認められた.これらの障害はS-J症候群が発症した時期が歯冠ならびに歯根形成開始期にほぼ一致し,そのため歯に障害がでたものと考えられる.また平滑舌もみられたが,これも本症が誘因になったものと考えられる.
2.上下顎両側中切歯と下顎右側側切歯に根の形成障害(短根歯)による歯牙の動揺がみられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3686K) -
大東 美穂, 人見 さよ子, 園本 美恵, 木村 圭子, 嘉藤 幹夫, 大東 道治, 竹花 一1997 年35 巻1 号 p. 128-132
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー外科的処置・歯内療法・歯冠修復から予防の重要性が認識され,そして,定期検診時や診査後,齲蝕予防法として,刷掃指導やフッ化物を用いている.そこで今回,American Dental Association承認の,人工甘味材を添加した1.23%フッ化物含有のムース状APF(リン酸酸性フッ化物)を平成6年1月10日から平成8年8年31日まで大阪歯科大学付属病院小児歯科外来,大阪府歯科医師会肢体不自由児センター,及び某一般歯科医院にて,患児(者)及び保護者の了承を得て塗布した.使用したフッ素ムースの甘味材の種類は5種類で,小児,障害児,障害者,成人において,各グループで各々50名を対象として反応を観察し,診療後アンケート調査も併せて行った.
その結果,
1)人工甘味材5種類(シナモンアップル味,ラズベリー味,バブルガム味,グレープ味,キャンディミント味)での嗜好比較は,小児,障害児,障害者で類似していた.また,年齢ならびに性別に差が認められた.
2)トレー法,綿球塗布法とハブラシ利用法ついて使用方法を比較,検討した結果ハブラシを利用し塗布する方法が使用しやすかった.
3)歯及び口腔粘膜に着色や刺激がなかった.
4)齲蝕予防や知覚過敏症に有効であった.
5)ムース状になっているため,少量で効果が得られた.
6)容器内で液状化する欠点があった.
7)小児,障害児,障害者において大変興味を示し,治療への導入が容易になった.また,歯科治療に対して非常に協力的になった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1609K) -
川島 成人, 土肥 順尚, 菊池 元宏, 中島 一郎, 松野 俊夫1997 年35 巻1 号 p. 133-139
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリー著者らは,術者との言語的コミュニケーションが取れないことから,術者の治療指示に従えず齲蝕治療に困難を生じた11歳7か月の女児に対して心理社会的背景の分析を行った.患児は不登校児で刺激に弱く,不安を感じると内向し閉じこもる傾向が見られ心理的脆弱さが考えられた.このため治療によって生じる過剰な不安や緊張を減少させる目的で,笑気吸入鎮静法を用いた.
今回著者らが用いた笑気吸入鎮静法は,行動療法の一法である系統的脱感作法を応用し,笑気ガス濃度と吸入時間を段階的に減少させた.また,同時に治療態度を積極的に評価して治療に対する自信を増加させた.その結果,治療9回目以降,治療に関する指示に従うことができるようになり,治療困難から通常下での歯科治療が可能となった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2318K) -
1997 年35 巻1 号 p. 140-182
発行日: 1997/03/25
公開日: 2013/01/18
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (14262K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|