巻号一覧
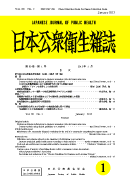
58 巻, 7 号
選択された号の論文の5件中1~5を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
原著
-
星 旦二, 高城 智圭, 坊迫 吉倫, 中山 直子, 楊 素雯, 栗盛 須雅子, 長谷川 卓志, 井上 直子, 山本 千紗子, 高橋 俊彦, ...2011 年 58 巻 7 号 p. 491-500
発行日: 2011年
公開日: 2014/06/06
ジャーナル フリー目的 本研究の目的は,都市在宅高齢者における健康三要因の 6 年間の経年変化とともに,相互の因果関係を明確にすることである。
方法 都市郊外在宅に居住する65歳以上高齢者を対象にして,2001年 9 月に実施した郵送自記式質問紙調査回答者13,195人(回収率80.2%)を基礎的データベースとした。3 年後の2004年 9 月と 6 年後の2007年 9 月に同様な追跡調査を実施した。分析対象者は2,375人である。健康三要因の因果関係は,交差遅れ効果モデルを応用し共分散構造分析によって分析した。
結果 身体的健康度の一つである BADL(Basic Activities of Daily Living)が全てできる割合は,91.0%から 6 年後には82.9%へと低下した。精神的健康度の一つである主観的健康感が,健康である割合は,85.4%から 6 年後には77.0%へと統計学的にみて有意に低下した。
健康三要因の因果関係は,“精神的要因”(“ ”は潜在変数を示す)が基盤となり,3 年後の“身体的要因”を直接に規定し,6 年後の“社会的要因”を間接的に規定するモデルの決定係数が,男性25%,女性19%であり,適合度指数はNFI=0.935, IFI=0.950, RMSEA=0.036と,高い適合度が得られた。
結論 高齢者の社会的健康は,6 年前の精神的健康が基盤となり,3 年前の身体的健康を経て間接的に規定される可能性が示唆された。研究成果を他の世代で明確にするとともに,外的妥当性を高めることが研究課題である。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (657K) -
金子 典代, 大森 佐知子, 辻 宏幸, 鬼塚 哲郎, 市川 誠一2011 年 58 巻 7 号 p. 501-514
発行日: 2011年
公開日: 2014/06/06
ジャーナル フリー目的 大阪市内の商業施設を利用するゲイ•バイセクシュアル男性における相手別のコンドーム使用のステージの分布を明らかにすること,ステージと予防への態度や規範等の要因との関連を明らかにすることである。
方法 NGO である MASH 大阪が予防啓発を行っている商業施設の協力を得て質問紙を用いた断面調査を実施した。1,340部の質問紙を配布し郵送により601件の有効回答を得た。対象者のコンドーム使用状況,性行為の相手の種類別に,無関心期群,関心期群,準備期群,行動期群,維持期群に分類し分布を明らかにした。さらに関心期群と準備期,行動期と維持期はそれぞれ 1 つの群にまとめ,無関心期群,関心•準備期群,行動•維持期群の 3 群に分類し,群間での各要因との関連の検討を行った。さらにコンドーム使用のステージを従属変数,関連要因を独立変数とし,多重ロジスティック回帰モデルを用いた解析を行った。
結果 全有効回答数601件(回収率44.9%)のうち男性と性経験を有する546人のデータを分析対象とした。対象者のコンドーム使用のステージ分類を行ったところ,特定相手とのコンドーム使用のステージは無関心期が最も多く,その場限りの相手とは維持期が最も多かった。MASH 大阪の予防啓発資材の受け取り率は,全ステージ群において 7 割を超えていた。相手がコンドームなしでの性交を望んだ際の使用の困難感,交際期間の長さに起因するコンドーム使用の困難感,薬物やアルコール使用時のコンドーム使用の困難感,状況に左右されないコンドーム使用への自信がコンドーム使用のステージに関連していた。
結論 商業施設を利用するゲイ•バイセクシュアル男性のコンドーム使用のステージと関連要因が明らかとなった。今後は質問項目の信頼性や妥当性の検討を行い,同様の調査を経年的に実施することで予防啓発活動の評価に資するデータを得ることができる可能性がある。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (604K)
研究ノート
-
中島 正夫2011 年 58 巻 7 号 p. 515-525
発行日: 2011年
公開日: 2014/06/06
ジャーナル フリー目的 既存の資料に記載されている乳幼児体力手帳制度,妊産婦手帳制度,母子手帳制度,母子健康手帳制度の政策意図などを整理し,各手帳制度の公衆衛生行政上の意義について考察することである。
方法 厚生省関係通知,関連書籍,および妊産婦手帳制度等の企画立案に従事された瀬木三雄氏の著作物等により,各手帳制度の政策意図などを整理,検討する。
結果 (1)乳幼児体力手帳制度:根拠は国民体力法(1942年改正)。1945年度まで実施。乳幼児体力検査受診者に手帳を交付。保健医療従事者が記載した記録を当事者が携帯,その後の保健指導等に役立てた。(2)妊産婦手帳制度:根拠は妊産婦手帳規程(1942年)。妊娠した者が医師または助産婦の証明書を付して地方長官に届出(義務)をすることにより手帳を交付。保健医療従事者が記載した健診等の記録を当事者が携帯,その後の保健指導等に役立てた。一定の妊産保健情報を提供。妊産育児に必要な物資の配給手帳としても利用。(3)母子手帳制度:根拠は児童福祉法(1948年)。(2)を拡充し乳幼児まで対象。手帳交付手続き等は基本的に(2)と同様。乳幼児を対象とした一定の保健情報も追加。配給手帳としての運用は1953年 3 月まで。(4)母子健康手帳制度:根拠は母子保健法(1966年)。妊娠の届出は勧奨(医師等の証明書は不要)とされた。当事者による記録の記載が明確化,また様々な母子保健情報が追加された。
結論 各手帳制度の公衆衛生行政上の意義について次のとおり考える。(1)母子保健対象者の把握:乳幼児体力手帳制度以外すべて,(2)妊産婦を早期に義務として医療に結びつけること:妊産婦手帳制度,母子手帳制度,(3)保健医療従事者および当事者が記載した各種記録を当事者が携帯し,その後の的確な支援等に結びつけること:基本的にすべての手帳制度(当事者による記録の記載は母子健康手帳制度で明確化),(4)当事者•家族による妊産婦•乳幼児の健康管理を促すこと:①保健医療従事者が記載した各種記録を当事者が保持;すべての手帳制度,②母子保健情報の提供;乳幼児体力手帳制度以外すべて,③当事者による記録の記載;母子健康手帳制度で明確化,(5)配給手帳として母子栄養を維持すること:妊産婦手帳制度,母子手帳制度。
以上のことから,わが国の手帳制度は,戦時下において主に父権的制度として制定され,その後の社会情勢の変化や保健医療体制の整備などに伴い,当事者の自発的な健康管理を期待する制度へと成熟していったと考えられる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (649K) -
丹 佳子2011 年 58 巻 7 号 p. 526-538
発行日: 2011年
公開日: 2014/06/06
ジャーナル フリー目的 育児中の保護者にとって配布された印刷物は有効な情報源である。小児救急パンフレットを受け取った幼稚園児の保護者を対象に,保管率,評価,役に立った内容等を明らかにすることによって,パンフレットの効果的な配布方法,含むべき内容を検討した。
方法 対象は幼稚園児の保護者269人。幼稚園を通じてパンフレットを配布し,その 2 か月後にパンフレットの保管状況や形態•内容に対する評価について無記名の質問紙調査を行った。パンフレット(筆者が作成)は母子健康手帳サイズの A6 判,オールカラー20ページ,主な内容は日常的に出会う 6 つの症状(発熱•ひきつけ•嘔吐•下痢•咳•腹痛)についての受診基準,受診判断のための情報収集技術としてフィジカルアセスメント方法やホームケアの方法,知っておくと便利な「小児救急医療電話相談」等の電話番号や URL である。
結果 有効回収数は111枚(有効回収率41.3%)。回答者の年齢(平均値±標準偏差)は36.0±4.50歳で,このうち,パンフレットを保管していたのは74人(66.7%)であった。保護者の属性と保管の有無との関係をみたところ,パンフレット配布後の急病体験(P<0.05)で有意差が認められ,保管あり群の方がなし群と比較して急病体験者の割合が高かった。保管者のうち,パンフレットに目を通した人は67人(90.5%)で,そのうち,役に立ったページがあったと回答した人は51人(76.1%),今後も使用したいという人は63人(94.0%)であった。役に立った項目を症状(発熱•ひきつけ•嘔吐•下痢•咳•腹痛)とその他(よくある質問•記録•電話 URL リスト)別にたずねたところ,最も多かったのは,「電話 URL リスト」で28人(54.9%),次いで「発熱の受診判断」24人(47.1%),「よくある質問」21人(41.2%)と続いた。
結論 急病体験者はパンフレット保管率が有意に高かったことから,急病体験の多い月齢の子どもの保護者に配布すると保管してもらいやすく,使用頻度も高まるのではないかと考える。また,パンフレットの内容では「電話 URL リスト」が役に立った人が多かったことから,今後はパンフレットですべての情報提供をするというよりも,必要な情報を効果的に探す方法や,得た情報の使い方などをパンフレットに含むことで,より実用的な教材になると思われる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2911K)
資料
-
福永 一郎, 渡部 三郎, 内藤 桂子, 赤松 亜衣子, 渡部 健一郎, 櫃本 真聿2011 年 58 巻 7 号 p. 539-549
発行日: 2011年
公開日: 2014/06/06
ジャーナル フリー目的 精神障害者の住居確保に関する市区町村自治体の支援体制の実態を明らかにする。
方法 2008年 9 月,1,805市区町村の障害福祉所管課(精神障害者担当課)に対してアンケート用紙を送付し,返信のあった1,141通に対して集計,解析を実施した。調査内容は「精神障害者の住宅確保に関する支援」,「精神障害者への金銭援助」および「精神障害者の保健福祉に対する障害福祉所管課の認識」であった。回収率は63.2%であった。
結果 保証人がいない者に対応する制度がある自治体は7.0%,住宅確保の負担軽減の取り組みがある自治体は17.7%で,取り組みの内容は住宅に関する相談場所の設置が多かった。行政から不動産業者や賃貸者に対してアプローチを行っている自治体は5.0%であった。生活保護を受けている精神障害者に身体障害者に適用される特別基準額を支給している事例がある自治体は12.9%,家賃等の一部に充当する金銭補助を行うなど,住宅を確保するために金銭援助を行う制度がある自治体は2.5%であった。地域移行を希望する精神障害者の数や実際の地域移行の状況が把握されていない自治体は52.9%,精神障害者が居住する住宅のアメニティについて「単身者,一般市民住宅水準と同等程度のアメニティが望ましい」とした自治体が64.9%,地域住民に対して障害者に抱いているネガティブなイメージを適切なものに変えてゆくアプローチを行っている自治体は41.4%であった。精神障害者の住居確保についての施策方針は,48.6%の自治体が「地域内での集住」であり,「一般近隣住民の中で自立して暮らしていく」は28.9%の自治体にとどまった。行政内での障害福祉部門と他部門との連携の状況は,「保健福祉を越えて必要な部門との連携はとれている」とした自治体は25.5%であった。
結論 住居確保に対する市区町村自治体の取り組みは,全国的に見ると萌芽的な状態にある。各自治体において,系統的な住居確保政策の立案がなされることが望まれる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (583K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|