巻号一覧
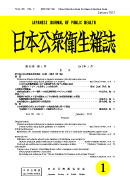
52 巻, 2 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
総説
-
宇津木 恵, 西條 泰明, 岸 玲子2005 年 52 巻 2 号 p. 115-127
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー初期の動脈硬化は,治療や生活習慣の改善により改善することが可能であるが,進行すると循環器疾患を発症し,致命的となるばかりでなく,重篤な後遺症を残す可能性がある。それゆえ,早期に動脈硬化を評価し予防に結びつけることが重要である。初期の段階である内皮/血管機能不全となる前に動脈硬化の兆候を把握するための,簡潔で,非侵襲的な手法の開発が望まれる。
脈波伝播速度(Pulse wave velocity:PWV)は,動脈の硬化度を測定する非侵襲的ならびに簡便な手法である。先行研究から PWV が動脈硬化程度の測定,ならびに予測因子として有用な指標となりうることが報告されてきた。しかしながら,PWV については一貫した結果が得られておらず,今後の PWV について検討の余地がある。
本稿は,以下の PWV に関して,3 点について過去の文献考察を行った。
1. 循環器疾患発症の予測因子としての PWV の価値
2. PWV と動脈硬化危険因子との関連
3. brachial-ankle PWV (baPWV)の研究の現状
その結果,血圧が,PWV と強い関連があるとする報告がほとんどであった。加えて,Body mass index (BMI),空腹時血糖,コレステロールも PWV と有意な関連があると多数の報告で認めていた。しかし,喫煙と PWV の間には関連があるとする報告はなかった。また,多くの報告から,PWV の上昇が疾患発症の予測指標となりうることが示された。しかしながら,近年開発されたより簡便な手法である baPWV を用いて予測因子との関連を報告したものはなかった。それゆえ,今後 baPWV を用いての検討が求められる。
以上より,PWV を用いることで,動脈硬化性疾患の予測が可能となり,一次予防・二次予防に結びつけることができると考えられる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (454K)
原著
-
柴田 亜希子, 高橋 達也, 大内 憲明, 深尾 彰2005 年 52 巻 2 号 p. 128-136
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 近年,日本では乳がん検診の方法の見直しが行われ,マンモグラフィによる検診の導入が進んできている。本研究では,1987年に老人保健法に組み入れられて以来山形県にて行われてきた視触診による乳がん検診を,地域がん登録を用いて精度と早期発見の効果の点で評価し,総括することを目的とした。
方法 (1)精度:対象は1997年 4 月から1998年12月までに山形県内 Y 検診施設実施の乳がん検診受診者,延べ51,700人で,山形県がん登録と照合して乳がん有病者を把握し,検診の感度,特異度,陽性反応適中度を求めた。偽陰性の定義は,検診で異常なしと判定された症例のうち,検診受診日から 1 年以内に乳がんと診断されたものとした。陽性反応的中度は要精密検査例を分母として求めた。
(2)生存率:1989年から1998年までの10年間に,山形県がん登録に乳がんとして登録された30歳以上の女性2,323人を対象とし,発見契機別(検診発見群と非検診発見群)の 2 群に分けて診断日からの予後の比較を行った。Kaplan-Meier 法を用いて生存率を推定し,2 群の生存時間分布の比較を log-rank 検定で行い,5 年目と9.8年目の生存率の点推定値の比較を z 検定で行った。また,閉経前後の年齢(49歳以下と50歳以上)で層化した検討も行った。
結果 (1)精度:感度46.6%,特異度97.3%,陽性反応適中度1.9%であった。
(2)生存率:log-rank 検定,生存率の点推定値(5 年,9.8年)の比較においては,検診発見群の方が非検診発見群よりも有意に高かった(P<0.001)。49歳以下と50歳以上で層化すると,生存率はどちらの年齢階級でも検診発見群の方が有意に高かったが,49歳以下では 2 群の差は,経年的に小さくなっていった。
結論 山形県において行われてきた視触診による乳がん検診は,検診を行うための条件のうち,早期発見による早期治療の効果が期待できるという必要条件は満たしていた。しかし,検査の精度の高さという条件は,日本の現行の他臓器のがん検診と比較した場合,十分であるとは言い難かった。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (439K) -
竹上 未紗, 笽島 茂, 山崎 新, 中山 健夫, 福原 俊一2005 年 52 巻 2 号 p. 137-145
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 地域住民における主観的な日中の眠気について The Epworth Sleepiness Scale (ESS) を用いて測定し,地域住民の ESS の分布を記述することである。また,日本における「日中の過度の眠気(excessive daytime sleepiness: EDS)」の有症割合を推定することである。
方法 北海道地方の人口約 1 万人のある自治体における20歳以上の全住民6,197人を対象とし,2000年10月から12月に自記式質問票を用いた悉皆調査を行った。日本語版 ESS を含んだ質問票は自治体の保健推進員の訪問により配布および回収された。解析対象は,ESS の 8 項目のうち 5 項目以上を回答したものとした。ESS の合計得点の平均値,標準偏差および性・年齢階級別分布は,分散分析により求めた。EDS の有症割合は,ESS の合計得点11点以上をカットオフ値として推定した。本調査の結果を2000年の性・年齢階級別日本人口を用いて標準化を行い,日本における EDS の有症割合を推計した。また,EDS に関連があるとされている諸要因についての検討を行った。
結果 調査票回収数は5,327人(86.0%)であり,解析対象者は4,412人(71.2%)であった。本研究の対象集団における ESS の平均値(±標準偏差)は5.18±3.75(男性5.25±3.89,女性5.12±3.75)であった。男性,女性ともに年齢階級別の ESS の平均値に差がみられた(P<0.001)。ESS を用いて推定された EDS の有症割合は,9.2%(男性9.6%,女性8.8%)であった。2000年の性・年齢階級別日本人口を援用して推計した EDS の有症割合は,9.3%(男性9.6%,女性9.2%)であった。また,EDS は年齢,6 時間未満の睡眠,鼾と関連があった(P=0.002, P=0.008, P<0.001)。
結論 地域住民を対象とした ESS の性・年齢階級別得点分布と日本における EDS 有症割合を推定した。これは,日本で初めて推定されたものであり,睡眠障害をきたす種々の疾患の診療,臨床疫学研究および公衆衛生施策に活用されることが期待される。また,ESS 得点による日中の眠気が年齢で違いがあることが明らかになった。これについては,生物医学,社会医学的な諸要因が関係していると考えられ,更なる研究が求められる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (396K) -
指田 百恵, 永田 智子, 村嶋 幸代, 春名 めぐみ2005 年 52 巻 2 号 p. 146-157
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 本研究は,らい予防法廃止以前に,ハンセン病療養所から社会復帰した経験をもち,現在は療養所で生活しているハンセン病回復者が,社会復帰時の生活をどのように認識しているのかについて明らかにすることを目的とした。
方法 現在,国立療養所 A 園に入所しており,ADL が比較的良好なハンセン病回復者で,社会復帰経験を有する者を対象とし,13人から面接への協力が得られた。半構造化面接で語られたインタビューデータを,「社会生活においてハンセン病が影響を及ぼしていた場面」に焦点を当ててカテゴリー化した。
結果および考察 社会復帰時の生活において,ハンセン病が影響を及ぼしていた場面のカテゴリーとして,「体調管理」,「再発不安・病気の不安」,「医療」,「社会生活の中でのハンセン病との関わり方」,「他者との関係性」,「仕事」の 6 つが抽出された。ハンセン病の影響の及ぼし方として,『(病気が)さわぐ〈再発する〉』と『(病気を)かくす』という 2 つの要素が抽出された。「さわぐ」は,病気に対する不安をもち,体調管理に気を使うという行動につながっていた。「かくす」は,社会生活の中でのハンセン病との関わり方や,他者との関係性に影響を及ぼしていた。また,医療には,「さわぐ」ことのないように通院や服薬を行うという側面と,他の病気で診察を受ける際にハンセン病が発覚しないよう「かくす」という側面の両方がみられた。同時に,「かくす」ために仕事で無理をすることが「さわぐ」につながっており,「さわぐ」と「かくす」の悪循環がみられた。対象者全員が,当時の経験を『良かった』と振り返っており,その理由は,困難を伴いながらも社会生活を続けられたという達成感や充実感であった。
結論 本研究の対象者は,社会復帰をした経験を「良かった」と振り返っていた。社会生活に大きく影響を与えた要因として,病気が「さわぐ」と病気を「かくす」の 2 つの要素が抽出され,ハンセン病のようなスティグマを伴う病を患った者が社会生活を営むには,これらにかかわる困難を軽減することが必要と考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (508K)
資料
-
佐藤 牧人, 森泉 茂樹, 桜山 豊夫, 小柳 博靖, 池田 和功, 川島 ひろ子, 岡田 尚久, 竹之内 直人, 田鎖 良樹, 佐々木 淳 ...2005 年 52 巻 2 号 p. 158-168
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 医療機関に対して立入検査に関するアンケート調査を行い,保健所と立入検査の現状および課題と今後のあり方について検討した。
方法 平成14年12月に全国の12保健所管内全ての276病院に郵送にて質問調査を行った。218病院から得た回答を分析した。
結果 1)立入検査の実施頻度については年 1 回が良いは 6 割で,4 割は隔年を希望していた。2)検査が「とても役立つ」とする意見は,「院内感染対策」,「医療事故防止対策」,「感染性廃棄物の取り扱い・管理」の項目で多かった。3)行政職員の専門知識が「充分である」とする意見は 6 割を超すが,不足とする意見も約 2 割あった。4)指導内容では「同一項目で検査年度や調査員によって異なる」など約 7 割の病院が不適切な点があると指摘した。5)今後助言・指導が必要と思われる分野として「他の医療機関で行われている良い取り組みについての情報」,「医療事故防止対策」,「院内感染対策」が挙げられた。6)検査が「負担とは思わない」が 6 割強だが,「やや負担である」も 4 割弱みられた。7)今後のあるべき姿として「法令に基づく項目の検査・指導のみでなく,院内感染対策や医療事故防止対策など幅広く助言した方がよい」の考え方が大多数であった。8)保健所に対して,医療機関との連携協力の強化,地域医療のニーズに応じたネットワーク作り,国や地域の有用な情報の発信,国・県・市民とのパイプ役などの機能を期待する自由意見がみられた。
結論 立入検査に関して保健所職員の資質向上や検査手法の標準化などの課題が指摘されているが,今回初めて医療機関側の意見が明らかにされ,その課題がより一層明らかとなった。立入検査は国民の健康と安全を守る公衆衛生上の重要な業務であり,自治事務として院内感染防止や医療安全対策普及など目的を一層明確にして取り組み,質の向上を図る必要がある。そのため国や自治体主管部局の積極的な関与のもと,共通の判断・指導基準の作成や全国的な情報交換と研修を行い,かつ保健所は医療機関との日常的な連携のもと,不要な負担を減らす配慮や,行政職員としての意識向上と専門知識の研鑽など普段の努力が望まれる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (635K) -
濱野 強, 宮本 有紀, 伊藤 弘人2005 年 52 巻 2 号 p. 169-175
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 精神科入院医療の急性期化の進展を明らかにすることを目的として,診療報酬上の精神科包括病棟の取得動向について全国調査を実施した。
方法 調査対象は,社会保険事務局(47局)と都道府県庁(47庁)である。前者には診療報酬上の精神科救急病棟,精神科急性期治療病棟,児童・思春期精神科入院医療管理加算病棟(以下,3 つの病棟を「精神科急性期・救急病棟」とする),精神療養病棟を有する病院を,後者には老人性痴呆疾患治療病棟,重度痴呆患者入院治療料病棟(以下,両病棟を「老人性痴呆疾患治療病棟」とする),老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院を列挙し,調査内容について記入することを依頼した(回収率100%)。調査内容は,診療報酬上の精神科包括病棟の届出を行っている医療機関名,病床数,算定開始年月日および辞退年月日である。在院日数に制限がある精神科急性期・救急病棟,老人性痴呆疾患治療病棟を「急性期型病棟」,在院日数に制限がない精神療養病棟,老人性痴呆疾患療養病棟を「長期療養型病棟」に分類し,各病棟の病床数(2003年 9 月現在)ならびに病床増加数について分析を行った。
結果 1) 精神科急性期・救急病棟は6,752床であり,毎月81.7床ずつ増加していた。老人性痴呆疾患治療病棟は11,761床であり,毎月102.5床ずつ増加していた。ただし,各病棟は都道府県ごとで整備状況に地域差がみられた。
2) 精神療養病棟は76,155床であり,2001年 6 月以前は毎月779.1床ずつ,同月以降は毎月286.4床ずつ増加していた。老人性痴呆疾患療養病棟は17,289床であり,毎月211.8床ずつ増加していた。
3) 急性期型病棟の病床増加数は長期療養型病棟に比べて少ないことが示された。
結論 診療報酬上では,急性期型病棟の病床は毎月増加していることが明らかとなった。今後は,都道府県による整備状況の差や長期療養型病棟の増加とのバランスを考慮した上で,急性期型病棟を整備していく必要がある。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (356K) -
岩佐 一, 鈴木 隆雄, 吉田 祐子, 吉田 英世, 金 憲経, 古田 丈人, 杉浦 美穂2005 年 52 巻 2 号 p. 176-185
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 高齢者が自らの記憶力低下について自覚することを記憶愁訴(memory complaint)と呼ぶ。本研究は,都市部に居住する高齢者を対象として実施した断面調査の結果を用いて,記憶愁訴の出現頻度,高齢者が抱える記憶愁訴の主症状の分類,記憶愁訴の関連要因の探索について検討することを目的とした。
方法 都市部に在宅する70歳から84歳の高齢者838人(男性453人,女性385人,平均年齢76.2歳)のデータを用いて分析を行った。記憶愁訴は,現在の日常生活において記憶に関する事柄で困った経験の頻度を評定させた。さらに,記憶愁訴の具体的内容について自由回答を求めた。その他,うつ傾向,認知機能低下(MMSE 総得点24点未満で定義した),聴覚・視覚機能障害,高次生活機能,健康度自己評価,年齢,性別,教育年数等を測定・聴取した。
結果 記憶愁訴の出現頻度は,「ときどきある」もしくは「しょっちゅうある」と回答した者が,男性では,26.8%,女性では,31.6%であった。
記憶愁訴の主症状について分類したところ,「人名を忘れる」が全体の約 1/4,「物品をどこに置いたか(しまったか)忘れる」が約 1/5,「物品をどこかに置き忘れてくる」が約15%を占めた。また,展望的記憶(prospective memory)に関する愁訴が全体の約 1/4 を占めた。
記憶愁訴に関連する要因の探索を多重ロジスティック回帰分析により男女別に行ったところ,男性では,健康度自己評価,認知機能低下において,女性では,聴覚機能障害,健康度自己評価において,それぞれ他の要因とは独立して,記憶愁訴と有意な関連が認められた。
考察 地域在宅高齢者における記憶愁訴は,聴覚機能障害,健康度自己評価等,認知機能以外の要因からも影響を受け生起することが示唆された。また,記憶愁訴と認知機能低下の関連は,男性においてのみ認められたことから,記憶愁訴は認知機能低下の有用かつ簡便な指標として男性において機能する可能性が示唆された。この点について明らかにするためには,今後縦断的調査を実施し,予測的妥当性(predictive validity)について検討を行う必要がある。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (386K) -
松田 明子, 九里 美和子2005 年 52 巻 2 号 p. 186-194
発行日: 2005年
公開日: 2014/08/06
ジャーナル フリー目的 訪問看護ステーションにおける訪問看護師によるリハビリテーションの役割を検討することを目的に,訪問看護師と理学療法士によるリハビリテーション利用者の介護サービスの提供状況および身体的状態を比較した。
方法 滋賀県済生会訪問看護ステーションを利用している者254人に対して訪問看護師(保健師を含む)および理学療法士が面接調査を行った。この調査をもとに訪問看護師によるリハビリテーション利用者(以下訪問看護群)と理学療法士によるリハビリテーション利用者(以下訪問リハ群)を選び出し,2 群間で利用者の性,年齢による 1 対 1 のマッチングを行い36ペアを作成した。調査項目は,性,年齢,主疾患,痴呆性老人の日常生活自立度判定基準,介護サービスの提供状況および身体的状態などであった。身体的状態の調査は日常生活動作能力(ADL; Barthel Index),手段的動作能力(IADL),意識状態(GCS)とした。分析方法は,χ2 検定および t 検定を用いた。
結果 利用者の痴呆ランクIII以上の者の割合は訪問看護群が訪問リハ群に比べて有意に多かった。訪問診療サービス利用者の割合は,訪問看護群が訪問リハ群に比べて有意に多かった。身体的状態では,訪問看護群の ADL 評価点および GCS 総合点は訪問リハ群に比べて有意に低かった。また,男性において,訪問看護群の IADL は訪問リハ群に比べて有意に低かった。
結論 訪問看護師によるリハビリテーション利用者は,理学療法士によるリハビリテーションの利用者に比べて身体的状態が低いことが明らかとなった。訪問看護師は理学療法士と同行訪問の機会をつくり,利用者の身体的状態を評価していくことが重要であると考える。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (432K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|