巻号一覧
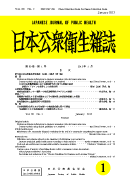
53 巻, 6 号
選択された号の論文の7件中1~7を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
論壇
-
田中 英夫2006 年 53 巻 6 号 p. 391-397
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリーがん患者の予後情報を有する地域がん登録資料は,当該地域のがんの医療水準の評価・モニタリング,生存率較差の分析,がん有病者数の推計に,必須の情報インフラとなる。また,届出医療機関に地域がん登録室が精度の高い予後情報を提供することにより,各病院が正確ながん患者の生存率を算出し,患者が診療方針を自己決定することを間接的に支援することができる。しかしながら,登録がん患者の予後調査を実施しているところは,登録事業実施34道府県のうち18府県に止まっており,その中で,届出医療機関に予後情報を提供するための利用規定が用意されていることころは,8 府県に限られている(平成17年時点)。
地域がん登録室が行う予後調査方法は,人口動態死亡票の目的外使用(統計法15条 2 項)と,住民基本台帳法に基く住民票照会または台帳の閲覧がある。人口動態死亡票の目的外使用は,その承認申請手続きや登録がん患者との照合作業に,実務面で相当の負担が生じている。また,住民票閲覧に関しては,本人の同意を得ることが困難であることから,この方法は今後法的に不安定な状況になる可能性が否定できない。
登録されたがん患者の予後情報を活用し,これを当該地域のがん対策や患者の自己決定に役立てられる体制を整えるためには,地域がん登録事業法の制定と,その中での予後調査に関する法的位置付けを明確にした上で,関連する法律との調整を図る必要がある。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (335K)
総説
-
吉益 光一, 山下 洋, 清原 千香子, 宮下 和久2006 年 53 巻 6 号 p. 398-410
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー児童の注意欠陥多動性障(attention-deficit/hyperactivity disorder; ADHD)は,年齢あるいは発達に不釣合いな注意力および/または衝動性,多動性を特徴とする行動の障害で,社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されているが,詳しい発症機序は不明である。近年学習障害および高機能自閉症とともに文部科学省による特別支援教育の対象に選ばれるなど,日本でも社会的関心が高まっている。しかしながら疫学的視点からみると統一された疾病概念や診断基準が長く確立されなかったため,有病率やその性比などの数値も過去の研究では一致していない。日本に比べて精神疾患の診断・統計マニュアルなどの客観性に秀でた操作的診断基準が臨床現場で普及している欧米においても同様である。近年欧米を中心とする疫学研究によって,ADHD は遺伝・環境要因による多因子疾患であることが明らかになりつつある。環境要因では主に妊娠中毒症や出産時の頭部外傷などの周産期障害が重視されてきたが,近年では妊娠中の母親の喫煙や飲酒など,胎生期における中毒性物質への曝露や家庭の社会経済的状況が注目されている。一方遺伝要因では両親の精神疾患の既往や,ドーパミン関連遺伝子多型との関連性が指摘されている。しかし,これら環境および遺伝要因と ADHD との関連性についての研究は日本をはじめ非欧米圏では全く行われておらず,要因間の交互作用の検証も含めて今後の研究結果が待たれている。
一方,臨床場面においては,子どもの注意や行動の制御機能とそれに関わる成育環境の発達経過に沿った変容を踏まえて,治療の開始時期やその際に標的となる問題を的確に捉える必要がある。とくに行為障害や反抗挑戦性障害などの併存障害は重要な要因であり,包括的視点を要する問題である。したがって ADHD の治療についても,前述の環境的・遺伝的な病因論を踏まえ,医療,教育,司法,行政なども含有した多次元モデルに基づく包括的治療プログラムの重要性が唱えられており,その有効性について今後の実証的な検証が求められている。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (459K)
原著
-
那須 郁夫, 斎藤 安彦2006 年 53 巻 6 号 p. 411-423
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー目的 日本全国の65歳以上の高齢者を対象とした大規模パネル聞き取り調査(「健康と生活に関する調査」日本大学総合学術情報センター研究プロジェクト)を,1999年から 2 年ごとに 3 回実施した。この縦断調査の個票データを用いて,高齢者の咀嚼能力別にみた健康状態別余命を男女に分けて推計した。
方法 本研究は,第 1 回から第 3 回調査に至る間における「健康」—「不健康」—「死亡」の状態間移動確率をもとに,多相生命表の手法による健康状態別余命の推計を行った点に特徴がある。ここで「不健康」な状態とは,質問した ADL 関連 7 項目と IADL 関連 7 項目のうち 1 項目以上に「非常に難しい」または「できない」と回答した場合とした。
都合 3 回の回答者と,この間の死亡者の合計4,323人の資料を計算に用いた。第 1 回調査時点(ベースライン)の咀嚼可能食品群による咀嚼能力に従い,男女別に,歯応えのある食品咀嚼可能群(A 群)と,普通または軟らかい食品咀嚼可能群(B 群)の 2 群に分けた。
結果 65歳における平均余命は,A 群で19.3/23.2(男/女以下同じ)年,B 群で16.7/21.1年,同歳の健康余命は,A 群16.8/18.6年,B 群13.6/16.3年,不健康余命は,それぞれ2.4/4.6年,3.1/4.8年であり,AB 群間で統計学的に有意差があったのは,健康余命のみであった。
ベースラインの健康状態が「健康」の場合,A 群では65歳時の平均余命は19.5/23.2年,健康余命は17.1/18.7年,不健康余命は2.4/4.5年,B 群ではそれぞれ17.0/21.1年,14.1/16.4年,2.9/4.7年であった。一方ベースライン時に「不健康」の場合,A 群の65歳平均余命10.8/22.1年,健康余命6.2/15.4年,不健康余命4.6/6.7年,B 群ではそれぞれ10.0/19.5年,4.0/12.1年,5.9/7.3年であった。ベースラインが「健康」の健康余命においては,AB 群間で統計学的に有意差があった。
結論 以上,高齢者において十分な咀嚼能力を維持・回復しておくことは,平均余命の保持もさることながら,むしろ健康余命の延長に強く関連することが示唆された。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (458K)
資料
-
片山 佳代子, 坂口 早苗, 坂口 武洋2006 年 53 巻 6 号 p. 424-431
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー目的 近親者との死別,とりわけ配偶者との死別経験はその後,遺族に身体的・精神的にも大きく影響を与えるライフイベントとして知られている。
死別体験者のセルフヘルプグループが悲嘆プロセスの適応や生活の再構成などの悲嘆緩和の手助けとなることは,近年広く知られるようになった。しかし,遺族がこうしたセルフヘルプグループと出会い,実際にメンバーとして参加することは容易なことではない。本研究は情報化が進む社会的背景を踏まえ,現在増えつつあるインターネット上で活動するセルフヘルプグループ(electronic support group)に焦点をあて,死別体験者のセルフヘルプグループの実態を調査したので報告する。
方法 配偶者と死別し,インターネット上で活動しているセルフヘルプグループに参加している人たちを対象に,喪失体験時期,入会方法,主観的悲嘆緩和効果などについて質問した。一定期間専用のホームページを開設して質問紙を掲載し,各自直接アクセスする形で無記名の自記式にて回答を依頼した。また,アンケートに回答した者の中から 4 人を対象に自由記述式調査を依頼した。
結果 調査対象者数は132人(男性39人;29.5%,女性93人;70.5%)であり,年齢構成は20歳代5.3%,30歳代48.5%,40歳代35.6%,50歳代6.1%,60歳以上4.5%であった。喪失体験時期は,1 年未満13.6%,1~3 年未満28.8%,3~5 年未満30.3%,5 年以上27.3%であった。図式投影法によると,約70%の者は夫婦との関係について親密型(密着・同化)を選択した。 インターネットセルフヘルプグループへの入会方法は,インターネットの検索が58.3%,紹介が25.8%,偶然にサイトに辿り着いた者が9.1%であった。セルフヘルプグループに参加することによる主観的悲嘆緩和効果については,約80%の者が認めていた。
個別の自由記述式質問紙調査の結果からは,死別間もない時期であっても,時間・場所の制約を受けずにインターネットセルフヘルプグループへ参加でき,心の支えになったことがわかった。
結論 インターネットセルフヘルプグループは遺族にとっては,死別間もない時期から容易に参加することのできるセルフヘルプグループであり,悲嘆緩和の第一歩である悲しみのわかちあいや相互援助効果から約 8 割の者が主観的悲嘆緩和効果を認めていることが判明した。今後は必要としている者が必要なセルフヘルプグループに辿りつけるようなインターネット上のセルフヘルプグループの情報整理が求められる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (417K) -
渋谷 雄平, 井上 明, 河上 靖登2006 年 53 巻 6 号 p. 432-436
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー目的 フィブリノゲン製剤納入先医療機関名の公表に伴い,神戸市では相談窓口の設置に加えて C 型肝炎ウイルス(以下 HCV)の無料検査(年齢制限及び HIV 同時検査なし)を実施した。それらの分析結果より今後の C 型肝炎対策についての一考察を加えた。
対象と方法 平成16年12月,保健所,各区役所保健福祉部など市内12箇所に相談窓口を設置するとともに,「平成 6 年以前に,公表医療機関で出産や手術等の際に出血のためフィブリノゲン製剤を使用された可能性がある神戸市民で,その後 C 型肝炎検査を一度も受けられていない人」を対象として,平成17年 3 月末まで HCV 検査を実施した。HCV 抗体を測定し,陽性の場合は HCV-RNA にてウイルスの有無を確認した。
結果 (相談件数・内容について)3,717件の「相談」があり,女性3,145件(84.6%),男性572件(15.4%)と女性が圧倒的に多かった。相談内容の主なものは,「肝炎検査について(検査場所,費用等)」,「過去に出産・手術をしたが大丈夫か」等であり,国の中間集計と同じ結果がみられた。
(C 型肝炎検査について)1,372人が検査を受け,女性1,165人(84.9%),男性207人(15.1%)と,「相談」と同様に女性が 8 割以上を占めた。HCV 抗体陽性は32人(陽性率:2.3%)で,その内 HCV-RNA 陽性者は13人(陽性率:0.95%)であった。持続陽性者は60歳代で 7 人と最も多かったが,30歳代でも男性 1 人を認めた。平成13年の非加熱血液製剤の使用医療機関公表時の実績(HCV 抗体陽性率:8.2%)と比較すると,今回の抗体陽性率は有意に低かった(P<0.01)。HCV-RNA 陽性率を節目検診(平成15年度)と比較してみると,女性では低く(0.60%),逆に男性では高い傾向がみられた(2.90%)。特に69歳以下の男性では有意に高く(P<0.05),節目外検診における HCV-RNA 陽性率にほぼ匹敵していた。
結論 「相談」・「検査」共に女性が多かったことが特徴的であったが,フィブリノゲン製剤は過去に外科的手術だけでなく,出産時にも頻繁に使用された経緯があるためと推察された。この公表を契機として肝炎対策を一層推進するために実施された今回の措置は,大規模な節目外検診として有益であった。今後も年齢に拘らず,C 型肝炎の感染リスクのより高い者を対象として,積極的に検査の普及啓発を展開していくことが適切な対応と思われる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (300K) -
大熊 和行, 松村 義晴, 福田 美和, 中山 治2006 年 53 巻 6 号 p. 437-447
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー目的 健康余命の定義や推計方法に関する研究は数多く報告されているが,いずれの方法も算定基礎となるデータの収集・調査に多くの時間と労力を要する。そこで,①経年推移が比較的容易に把握できること,②市町村・保健所管内等の地域間比較が容易にできること,③基礎データが全国一律に入手しやすいことを考慮し,三重県における介護保険データを用いた健康余命の算定方法について検討した。
方法 介護保険法により全国的にほぼ一律の判定が行われている要介護認定者数(要支援者数+要介護者数)の被保険者数に対する割合(要介護認定率)を障害有病率とし,平均余命は Chiang 法により,健康余命は Sullivan 法により算定した。算定にあたっては,Microsoft Excel 関数を用いた演算表を作成した。また,あらかじめ,1995年および2000年の三重県内69市町村の平均寿命を Chiang 法により算定し,同年の市区町村別生命表と比較検討した。
結果 Chiang 法による平均寿命から市区町村別生命表による平均寿命を差し引き,これを市区町村別生命表による平均寿命で除して得られるパーセント値(「較差」)の絶対値が 5%未満となる市町村人口は,男女とも10,000人以上であれば十分であることが明らかとなった。また,健康余命算定に必要な基礎資料が揃った2001年~2003年における県全体での40歳平均余命は,男はいずれの年も40.1歳で変わらなかったが,女は2001年46.1歳,2002年46.2歳,2003年46.4歳とわずかではあるが延伸していた。一方,40歳健康余命は,男は38.1歳から37.7歳に,女は41.6歳から40.9歳に年々短くなる結果となり,現時点で得られる介護保険データでは,十数パーセントの誤差を含むものと考えられた。
結論 Sullivan 法の基礎データは,「生命表」と「性・年齢階級別の障害有病率」である。生命表は Chiang 法により作成し,障害有病率は介護保険法に基づく要介護認定率を用いることにより,Microsoft Excel 関数を用いた演算表で容易に健康余命を算定することができた。しかしながら,その算定条件は,男女それぞれの人口が10,000人以上の規模に限定されることに留意する必要がある。また,介護保険法が施行され 5 年以上が経過し,制度自体は定着したと考えられるが,現時点で得られる介護保険データでは,要介護認定が安定していないことによる誤差が大きく,経年比較は特に問題があると考えられた。2005年 4 月に改正介護保険法が施行され,予防重視型の制度に転換されたが,同制度の定着状況をみつつ,誤差の小さい算定方法に改善することが今後の研究課題である。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (335K) -
冨田 直明2006 年 53 巻 6 号 p. 448-456
発行日: 2006年
公開日: 2014/07/08
ジャーナル フリー目的 愛媛県東部地域(以下東予地域)に発生した成人麻疹流行を分析し,保健所における今後の感染症対策のあり方を検討した。
方法 東予地域では,2002年10月~2003年 7 月の間に成人麻疹(18歳以上の麻疹)および麻疹(17歳以下の麻疹)の流行が発生したが,流行期間中,感染症発生動向調査だけでは把握が困難と判断されたので愛媛県医師会の協力により全数把握調査を行った。また麻疹を診察した医師に患者病状調査票による情報提供を依頼した。さらに成人麻疹多発の原因究明を目的に患者の検体のウィルス検査および遺伝子解析を行った。
成績 2002年10月~2003年 7 月の間に,麻疹200人,成人麻疹112人,計312人の麻疹患者が報告され,県全体に占める割合は麻疹89.7%,成人麻疹94.1%,全体で91.2%であり東予地域に限定した流行であった。さらに週毎の発生数の推移から成人麻疹発生から麻疹が流行した事例であった。患者疫学調査の結果,ワクチン接種歴無しの割合は麻疹84.1%,成人麻疹59.3%,全体で73.7%であり,接種歴有りの割合は麻疹11.4%,成人麻疹21.9%,全体で15.8%であった。そしてウィルス遺伝子型は全例で中国や韓国の流行株である H1 型であり,H1 型を原因とした成人麻疹の流行としては国内初の事例であった。また東予地域での小児科定点の麻疹患者報告数は全数把握の32.0%であり,基幹定点の成人麻疹患者報告数は全数把握の11.6%に止まった。
結論 東予地域では患者発生の極めて少ない状況が数年来続いたので,ワクチン未接種でも感染を免れた成人や小児(とくに年長児)および,ワクチン既接種者でも不顕感染による追加免疫がないために免疫力の低下した者(二次性ワクチン効果不全)が混在したことで成人麻疹の流行が発生したと考えられた。今回の結果より,乳幼児のワクチン接種率の向上と追加接種による学童や若年者への対策が必要である。また麻疹のように感染力が強く局地的に流行する感染症の場合,通常の定点報告では流行を見逃し対応が遅れる可能性が高いため,患者発生状況の的確な把握には,定点数の拡充および地元医師会を中心にした医療機関と保健所の平素からの積極的な情報交換が必要と考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (557K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|