巻号一覧
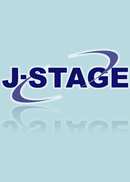
30 巻, 10 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
松原 弘明, 森 泰清, 正木 浩哉, 岩坂 壽二1998 年30 巻10 号 p. 611-616
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (3118K) -
冠動脈造影所見とamiodarone, PTCAによる影響楊 志成, 茅野 眞男, 村田 八寿子, 布施 淳, 西村 文朗, 名越 秀樹, 金 公宅, 前田 文昭, 松本 貢一, 葉山 泰史1998 年30 巻10 号 p. 617-624
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー心筋梗塞症亜急性期から慢性期に発症した再発性心室頻拍の冠動脈造影の特微,amiodarone,PTCAによる影響につき検討した.対象は発症より1週間以内の心筋梗塞症連続185例のうち,心室頻拍を合併した7例(3.8%)である.7例全例で,左室機能低下,多枝病変を認めた.I群3例は持続性単形性心室頻拍(SVT)で,平均左室駆出率(EF)34%である.亜急性期の造影で前下行枝(LAD)は完全閉塞し,2例でPTCAを施行した.PTCA施行1年~6カ月後再狭窄と再発はなく,EFは18→34%,38→47%に改善した.II群4例は心室細動(Vf)で,平均EF31%である。亜急性期の造影でLADは自然再灌流していた.PTCAが再狭窄までの再発予防に有効であった.I群の梗塞血管は完全閉塞し,PTCAによる虚血の改善,左室機能の改善が広汎な梗塞巣の安定したsubstrateを修飾し,SVTに有効であった.II群の梗塞血管は不完全閉塞し,PTCAにより梗塞巣,残存心筋の持続性虚血が改善し,Vfに有効であった.両群ともにamiodaroneが有効であった.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1916K) -
相澤 義房1998 年30 巻10 号 p. 625-626
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (468K) -
高田 佳史, 笹目 敦子, 田中 信大, 黒須 富士夫, 武田 和大, 高沢 謙二, 小林 恭彦, 清見 定道, 伊吹山 千晴1998 年30 巻10 号 p. 627-632
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー症例は45歳,女性.平成8年8月16日に心窩部痛を自覚し近医受診.心電図上V1,V2誘導にてQS波,V1~4誘導にてST上昇を認めた.急性前壁中隔心筋梗塞を疑われ,当院に入院となった.入院時の冠動脈造影では有意狭窄を認めず,左室造影では前壁の壁運動は著明に低下し,心尖部は奇異性壁運動を呈した.CK最高値は752U/lであり,99mTctetrofosmin心筋シンチグラムでは灌流欠損を認めなかったが,巨大陰性T波の回復には3カ月を要した.第25病日に施行した左室造影では壁運動異常を認めなかった.同時に測定した左前下行枝の冠血流予備能は著明に低下していた.
本例は広範なstunned myocardiumを伴った急性心筋梗塞の1例と考えられた.左室壁運動が著明に改善した時点において冠血流予備能の低下が観察されたことは,虚血再灌流後の冠血管機能障害の遷延,いわゆるvascular stunningに関連した現象として興味深く,若干の考察を加えて報告した.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2752K) -
江本 因, 野村 周三, 手島 保, 柳瀬 治, 徳安 良紀, 桜田 春水, 本宮 武司, 古川 仁, 前村 大成, 清水 浩一, 後藤 一 ...1998 年30 巻10 号 p. 633-639
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー症例は70歳の男性.3年来の狭心症歴がある.1994年8月30日,嘔吐を伴う前胸部圧迫感が約30分持続したが放置.10月初旬にも30分程持続する前胸部圧迫感を数回経験した.10月19日深夜,胸部圧迫感に続き呼吸困難が出現し徐々に増悪.近医にて心電図から急性下壁心筋梗塞を疑われ,発症約7時間後の10月20日早朝,当科に入院.
Killip III度の心不全を呈し,第4肋間胸骨左縁を中心にLevine 3度の全収縮期雑音を聴取した.冠動脈造影ではRCA#1:90%,LAD#6:90%,#9:99%,LCX#13:100%の重症3枝病変であった.左心室造影では下壁はakineticで,ここから右室に向かうシャントを認めた。左右シャント率は45.4%,心エコーでは心室中隔後基部に欠損を認め,蛇行した痩孔が中隔内を走り,カラードプラーで左右シャント血流を認めた.急性下壁心筋梗塞で生じた複雑型心室中隔解離が偽性仮性心室中隔瘤に発展し,慢性期に右室へ穿破することにより心室中隔穿孔を生じ急性心不全に至ったものと推定された.特異な形態およびメカニズムによる心室中隔穿孔について,文献的考察を含め報告する.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3296K) -
細川 忍, 日浅 芳一, 原田 慎史, 高橋 健文, 加藤 聡, 岸 宏一, 谷本 雅人, 大谷 龍治1998 年30 巻10 号 p. 641-646
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー主要冠動脈3枝に高度の冠攣縮を認め,気管支喘息発作が狭心症の発作に先行し,冠攣縮の誘因および致死的な1要因となった1例を報告する.症例は61歳,女性.主訴は前胸部痛である.56歳時より気管支喘息にて加療中であった.長時間胸部症状が続いたため急性心筋梗塞症を疑い,緊急冠動脈造影を施行した.左右冠動脈に著明な冠攣縮を認め,硝酸薬の大量冠動脈注入で改善した.十分な薬物療法を施行し,発作がコントロールできたので一時退院した.しかしその後,喘息発作が先行する狭心症発作を頻回に生じ,2回入退院を繰り返した.その際,前壁誘導,下壁誘導,高位側壁誘導に異時的にST上昇が心電図上記録された.以後も外来にて加療を続けたが自宅にて急死した.本例では喘息発作が冠攣縮性狭心症の致死的な1要因と考えられた.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2827K) -
遠山 治彦, 金澤 嘉夫, 松岡 正純, 稲村 昌和, 藤末 浩美, 段 房美1998 年30 巻10 号 p. 647-652
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー症例は60歳,男性.風邪症状にひき続き,食欲低下,ふらつきが出現し受診した.収縮期血圧は50mmHg,脈拍は102回/分であった.血液検査では,GOT,GPT,LDH,CPKの上昇を認め,心電図では,四肢誘導での低電位と,胸部誘導V1からV6でのST上昇を認めた.心臓超音波検査では,左室の壁運動のび漫性の低下,心嚢液の貯留を認め,左室心尖部には血栓を疑うエコー像を認めた.入院時,肺動脈楔入圧22mmHg,心係数1.69l/分/m2とForrester IV群であったが,利尿薬とドブタミンにて改善した.ペア血清ではインフルエンザAの抗体価の有意な上昇を認めており,このウイルスによる心筋炎と考えられた.
左室内血栓については,充実性の壁在血栓から,一部,低エコー領域(central echo lucency)を伴った血栓となり,完全に嚢胞状(cystic)の血栓となった後,可動性に富んだ充実性の血栓となり入院後11日目に消失した.血栓の継続的形態変化をとらえることができたという点で非常にまれな症例と考えられた.
また,心筋炎に合併した左室内血栓の報告も今まで内外で6例にすぎないが,この点でもまれな症例と考えられたため文献的考察を加え報告した.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2384K) -
良永 宇由, 宮原 嘉之, 波多 史朗, 内藤 達二, 園田 康男, 谷岡 芳人, 河野 茂1998 年30 巻10 号 p. 653-657
発行日: 1998/10/15
公開日: 2013/05/24
ジャーナル フリー原発性心臓腫瘍は極めてまれな疾患で,20-30%を悪性腫瘍が占める.最も頻度が多いのは血管肉腫であるが,典型的所見に乏しく,病期が進行してから発見されることが多いため,診断確定後の予後は不良である.今回,我々は,結果的には,早期の段階から2年間にわたり冠動脈造影にて自然経過が追えた心臓原発血管肉腫の症例を経験したので報告する.
症例は55歳,女性.主訴は胸痛で,狭心症を疑い冠動脈造影を行った.右冠動脈中枢部近傍にわずかな造影剤の濃染像を認めたが,心タンポナーデをきたした3カ月後には,腫瘤の存在は明らかにならず経過観察とされた.その後18カ月間の無症状の時期を経て2年後にショック状態となり,再入院した時には右冠動脈の濃染部は閉塞しており,胸部CT・MRI・心エコーにより右房~右室にかけて腫瘤を認め,その後の剖検にて初めて血管肉腫の診断に至った.本症例はこの経過から,初回の冠動脈造影の時点で既に腫瘍は存在したと考えられる.
血管肉腫の診断には,MRI,CT,心エコーなどの非侵襲的な検査が有力とされるが,心電図変化がなければ冠動脈造影は行われないこともある.しかし,本症例は初回入院時には冠動脈造影でしか診断の手掛かりを得ることができなかったという事実より,胸痛主訴の患者では腫瘍も鑑別に加えて造影所見を検討すべきと思われた.また,2年間にわたり自然経過が追えたことはまれと思われたため報告する.抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (3031K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|