巻号一覧
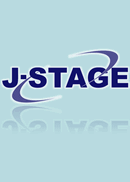
バーチャルイシュー
バーチャルイシュー
44 巻, 7 号
選択された号の論文の7件中1~7を表示しています
- |<
- <
- 1
- >
- >|
-
新島 端夫1991 年44 巻7 号 p. 705-717
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリーArbekacin (ABK) は, 梅澤浜夫らが, 細菌の抗生物質に対する不活性化機構の研究から合成した新しいアミノ配糖体系抗生物質である1)。本剤は1980年から筋注による基礎的, 臨床的検討が明治製菓により開始され, 1983年の第31回日本化学療法学会西日本支部総会, 新薬シンポジウムでの成績が討論された2)。その後, 点滴静注による臨床的検討が行われ, 更に, メチシリン・セフェム耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) 感染症に対して, 追加検討が行われた。ABKは開発当初から他のアミノ配糖体系抗生物質との交差耐性がなく, ブドウ球菌に対して強い抗菌力を示すことが注目されていたが, 臨床試験の中でもブドウ球菌感染症に対して優れた効果が認められた。特に本剤はMRSAの産生する各種不活性化酵素に安定で優れた抗菌力を示すことから臨床での治療効果が期待され, MRSA感染症の臨床試験でこのことが確認された。本剤は日本国内で初めてMRSAに対する適応 (敗血症, 肺炎) が認められた薬剤である。今回, 本剤のMRSAに対する基礎的, 臨床的成績につき, その概略を述べる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1336K) -
Fleroxacin 2 週間投与の有用性と休薬後の再発について荒川 創一, 高木 伸介, 松本 修, 守殿 貞夫, 仙石 淳, 羽間 稔, 山崎 浩, 濱見 学, 岡本 恭行, 田中 浩之, 伊藤 登, ...1991 年44 巻7 号 p. 718-731
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリーカテーテル非留置の複雑性尿路感染症の外来患者102例を対象に, 経口抗菌薬の至適投与期間を検討する目的で, 新規キノロン系合成抗菌剤であるFleroxacin (FLRX) を原則として14日間経口投与し, 5~7日目と14日目の効果を比較検討すると共に, 休薬後の再発の有無についても検討した。
FLRXは1日1回300mg投与とし, 臨床効果の判定はUTI薬効評価基準 (第3版) に準拠して行つた。その結果, 以下の成績を得た。
1. 総合臨床効果は5~7日目86%, 14日目84%の有効率であつた。5~7日目と14日目を比べると, 14日目で細菌尿については菌交代が増加するが, 膿尿については正常化が増加した。
2. 細菌学的効果は5~7日目91%, 14日目89%の除菌率であつた。3.主治医による臨床効果は, 5~7日目86%, 14日目88%の有効率であった。
4.副作用は9.1%にみられたが, 消化器症状が主であり, 5日目以降の発現はなかった.臨床検査値の異常変動は2.3%にみられたが, いずれも軽度且つ一過性であった。
5.膿尿と細菌尿を指標とした再発判定1では, 「再発なし」が休薬後1週目63%, 2週目54%, 3週目61%, 4~6週目81%であり, 「再発あり」はそれぞれ4%, 4%, 6%, 5%であり, 「再発疑い」はそれぞれ33%, 42%, 33%, 14%であった.「再発疑い」と判定されたものについては, 全般的に膿尿悪化例は少なく, 細菌尿だけ悪化という状態であった。
6.細菌尿だけを指標とした再発判定2では, 休薬後4~6週目に「治癒」と判定されたもの67%, 「再発」とされたもの33%で, 出現菌からみると再燃よりも再感染が多かった.
以上の成績から, カテーテル非留置の複雑性尿路感染症ではFLRXの14日間投与により十分な除菌, 臨床効果が得られるが, その効果は7日目前後ですでに明確となつていた。更に, 14日間の投与終了後菌陰性化の得られたもののうち, 1力月を経過した時点で30%程度の症例で103CFU/ml以上の細菌尿が再出現したが, 膿尿を伴うものはごく一部であり, 真の再発は全般に少なかった。又, 14日間投与によつて5日間投与に比べ副作用が増加することはなく, 本剤の安全性は高いものと考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1537K) -
田中 輝和, 田中 恭子, 入野 昭三1991 年44 巻7 号 p. 732-735
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリーSulbactam/Cefoperazone (SBT/CPZ) と生体防御能との関連をマクロファージを用いて検索した。Cefoperazone (CPZ) 存在下では, マクロファージの殺菌能に対し増強効果は認められなかつたが, Sub-MICsのSBT/CPZ存在下では, Escherichia coliに対するマクロファージの殺菌能に増強が認められた。SBT/CPZはCPZの広域抗菌スペクトル, SBTのβ-Lactamase不活化作用に加え, 生体防御能との協同作用により, その治療面における有効性が期待できる。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (377K) -
森本 健, 木下 博明, 中谷 守一, 酒井 克治, 上田 隆美, 藤本 幹夫, 大野 耕一, 森本 譲, 大森 国雄1991 年44 巻7 号 p. 736-747
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリー1988年3月から1990年6月までに大阪市立大学医学部第2外科及びその関連施設で取り扱つた外科的感染症23例にCefepimeを使用すると共に総胆管結石術後あるいはPercutaneous transhepatic cholangiodrainage中の5例における本剤の胆汁移行を検索し, 以下の結果を得た。
1.本剤1gを30分間点滴静注された5例の血漿中濃度は点滴静注終了時で59.9~118μg/mlのピークレベルとなり, 6時間後では6.4~29.0μg/mlにまで低下したのに対し, 胆汁中濃度は点滴静注開始後1~5時間で7.1~28.2μg/mlのピークレベルに達し, 5~6時間の分画では3.7~12.3μg/mlのレベルを維持していた。
2.本剤の臨床効果判定は評価可能22例では著効12例, 有効5例, やや有効1例, 無効4例で, 有効率は77.3%であつた。
3.細菌学的効果は16例で評価され, 消失10例, 減少3例, 不変3例であり, 消失率は62.5%, 分離菌別に細菌学的効果をみると, 分離菌31株中, 消失23株, 不変8株で, 消失率74.2%であつた。
4.今回検討された症例中, 治療開始時, Escherichia coliの検出された5例ではそのMICは0.05μg/ml以下, Pseudomonas aeruginosaを認めた2例ではMICは1.56μg/ml以下で, 本剤の有効性が期待された。黄色ブドウ球菌は3例に検出され, 1例はMethicillin-resistant Staphylococcus aureusで除菌されなかつた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (1189K) -
岩井 直一, 中村 はるひ, 宮津 光伸, 渡辺 祐美, 種田 陽一1991 年44 巻7 号 p. 748-769
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリー新しい注射用Cephem系抗生物質のCefpirome (HR 810, CPR) について, 小児科領域における基礎的, 臨床的検討を行った。
1.小児2例 (5歳, 7歳) に本剤20mg/kgをOne shot静注で投与した際の血漿中濃度と尿中排泄について検討した。
血漿中濃度の平均は静注後1/2時間44.7μg/ml, 1時間28.5μg/ml, 2時間10.5μg/ml, 4時間4.6μg/ml, 6時間1.5μg/mlであり, 半減期は平均1.57時間であつた。又, 尿中濃度の平均は静注後0~2時間1,785μg/ml, 2~4時間545μg/ml, 4~6時間198μg/mlであり, 6時間までの尿中回収率は平均52.0%であった。なお, これらの成績は, 成人領域の成績と比較すると, 尿中回収率が若干低い傾向にあつた以外はほとんど変わらないと考えられた。
2.本剤で治療した化膿性髄膜炎3例における髄液中濃度について検討した。1回44.4mg/kgを1日4回投与したNeisseria meningitidisによる症例では, 投与1時間後の髄液中濃度は115~23.1μg/ml, 5時間後では0.94μg/mlであった。又, 1回49.0mg/kgを1日6回投与したSrreptococcns pnenmoniaeによる症例の投与1時間後の濃度は1.01~4.23μg/mlであり, 更に1回52.2mg/kgを1日6回投与したS. pnenmoniaeによる症例では投与1時間後では16.8~37.1μg/ml, 3時間及び4時間後ではそれぞれ3.60, 11.3μg/mlであつた。この成績は, Cefotaxime, Ceftriaxoneなどに比較して決して遜色がなく, しかも小児期の本症の主要原因菌であるEschfrichia coli, Streptococcns agalacriae, S. pnenmoniae, Haemophilus influenzaeのMIC90値を十分凌駕し得ると考えられた。
3.小児期の各種感染症62例に本剤を投与し, その際の臨床効果, 細菌学的4果, 副作用について検討した。
臨床4果の判定対象となった化膿性髄膜炎3例, 急性化膿性中耳炎1例, 急性化膿性扁桃腺炎2例, 急性気管支炎1例, 急性肺炎49例, 狸紅熱1例, 急性化膿性骨髄炎1例, 急性腸炎1例, 急性尿路感染症2例の計61例に対する臨床効果は, 著効38例, 有効22例, やや有効1例であり, 著効と有効と含めた有効率は98.4%と極めて高く, 又, 有効以上の症例における著効率についても63.3%と非常に優れていた。一方, 原因菌と推定されたStaphytococcns anrens 1株, Streptococcns pyogenes 4株, S, agalactiae 1株, S. pnenmoniae lO株, N. meningiridis 1株, E. coli 2株, Serraria liqnefaciens 1株, H. inflnenzae 18株に対する細菌学的効果については, S.liqnefaciensが存続, H. inenzaeの1株が減少であった以外はすべて消失し, 菌消失率は94.7%と極めて高いものであった。これらの成績については, 今回の検討症例の原因菌の分布にもよろうとは思うが, 小児期感染症で問題となる細菌に対し本剤がほぼ平均して優れた抗菌力を有する点が反映された結果であろうと考えられた。
副作用としては下痢が1例, 下痢と発疹との合併が1例に認められただけで, 重篤なものはなかった。いずれも軽度で, 投与中止の必要はなく, 又, 止痢剤などの投与を行わずとも自然に改善された。又, 投与前後の推移でみた臨床検査値異常についてはGOT上昇が3例, GPTの1二昇が1例, 血小板増多が5例, 好酸球増多が1例, GOT上昇並びに血小板増多が1例, GOT上昇, GPT上昇並びに好酸球増多が1例, GOT上昇, GPT上昇並びに血小板増多が1例, 血小板減少並びに好酸球増多が1例に認められたが, いずれも軽度のものであり, しかも再検査ができた11例においては一部を除き正常化が確認された。これらは, 既存のCephem系抗生物質に比べ種類, 頻度とも大きく変わるものではなく, 本剤の小児における安全性を示すものと考えられた。
以上の成績から, 本剤は小児期感染症においても有効性, 安全性共に優れた, 有用性の高い薬剤であると考えられた。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2496K) -
池本 秀雄, 渡辺 一功, 森 健, 林 康之, 小栗 豊子, 近藤 宇史, 松宮 英視, 上田 京子, 斎藤 玲, 寺井 継男, 丹野 恭 ...1991 年44 巻7 号 p. 770-798
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリー我々は1981年以来全国各地の病院・研究施設と共同で呼吸器感染症分離菌を収集し, 分離菌の各種抗菌・抗生剤に対する感受性, 患者背景と分離菌などを経年的に調査してきた1~7)。今回は, 1988年度の調査結果を報告する。
1988年10月~1989年9月の間に全国18施設において, 呼吸器感染症患者439例の主として喀出喀痰から分離され, 起炎菌と推定された細菌は554株であった。このうち, staphylococcus aureus 68株, strgppococcus pneumoniae 102株, Haemophilus influenzae 120株, Pseudomonas aeruginosa 86株, Branhamella catarrhalis 65株, Klebstella pneumoniae 18株などに対する各種抗菌・抗生剤のMICを測定し, 薬剤感受性を調査した。
主要菌株の抗菌・抗生剤に対する感受性は, 各薬剤とも前年とほぼ同様の成績を示した。但し, S. aureusではMethici11inのMICが12.5μg/ml以上の株 (Methicillin-resistant S. aureus) が38.2%を占め, 前年の18.2%に比べ耐性菌の発現頻度が大きく上昇した。
又, 患者背景と感染症と起炎菌の推移等についても検討した。
患者背景については, 年齢別の分布では高年齢層の感染症が多く, 60歳以上が57.2%を占めた。疾患別の頻度では, 細菌性肺炎, 慢性気管支炎がそれぞれ32.1%, 31.4%と多く, 以下気管支拡張症, 気管支喘息の順であった。
疾患別の起炎菌の頻度についてみると, 細菌性肺炎ではS. aureus22.5%, S. pneumoniae 15.4%, 慢性気管支炎ではS. pneumoniae25.7%, H. influenzae24.1%, 気管支拡張症ではH. influenzae32.5%, P. aeruginosa23.8%, 気管支喘息ではH. influenzae31.4%, S. pneumoniae, B. catarrhalis20.0%が上位を占めた。
抗生剤の投与の有無日数ごとにみた分離菌についてみると, 投与前に分離され投与後減少した菌はS. pneumoniae, H. influenzae, B. caparrhalisである。一方, S. aureus, P. aeruginosaでは逆に投与後に頻度が上昇した。又, 投与期間が15日間以上の例ではP. aeruginosaの頻度が急増した。抄録全体を表示PDF形式でダウンロード (2619K) -
1991 年44 巻7 号 p. 799-801
発行日: 1991/07/25
公開日: 2013/05/17
ジャーナル フリーPDF形式でダウンロード (410K)
- |<
- <
- 1
- >
- >|